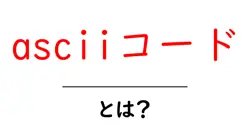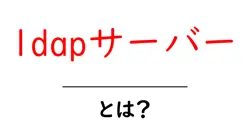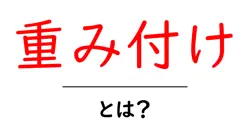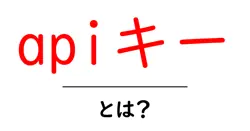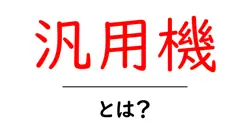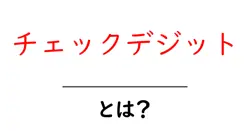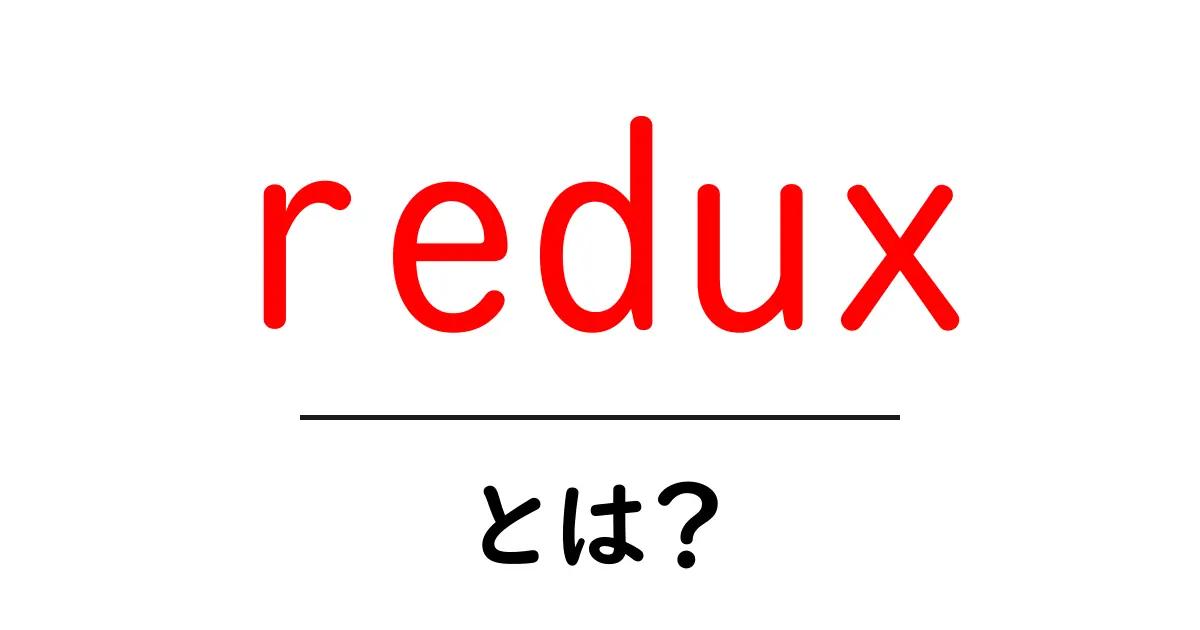

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
redux・とは?
Reduxは、JavaScript のアプリケーションで状態を一元管理するためのライブラリです。画面の表示に必要なデータが増えると、どこで・どのように変更されるのかを追いにくくなりますが、Reduxはその流れを整理してくれます。 Reduxの基本は「現在の状態を1つの場所に集約すること」「状態を変えるときはアクションという通知を送ること」「状態の更新を純粋な関数で決めること」です。これらの考え方を覚えると、UIがどう動くかを予測しやすくなり、バグの原因を見つけやすくなります。
ポイントは3つです。1) 状態は1つのStoreに集約されること、2) 状態を動かすのはアクションという通知、3) 状態の更新はReducerという純粋関数で決まることです。
Reduxの基本概念
Storeはアプリの現在の状態を保管します。getState で状態を参照し、dispatch action で状態を更新します。subscribe を使えば状態が変わった時に画面を自動で更新させることができます。アクションは状態の変化を伝えるための情報であり、通常は type という種別を持ちます。payload は任意で、変更の詳しいデータを渡す場合に使われます。Reducerは現在の状態とアクションを受け取り、新しい状態を返す純粋関数です。副作用を持たず、同じ入力には同じ出力を返します。
なぜ Redux が役立つのか
大きなアプリでは複数の画面や機能が同じデータに依存します。Reduxを使うとデータの流れが一方向になり、どの操作がどの部分に影響するかを追いやすくなります。さらに、過去の状態を遡って検証するタイムトラベルデバッグや、状態をスナップショットとして保存する機能など、開発を支援する仕組みが多く用意されています。
実践的な使い方の流れ
1) Store を作る
2) Action を定義する
3) Reducer を作る
4) UI を Store に接続して、状態の変更を反映させる
この流れを守ると、アプリの構造が整理され、状態の変更箇所を見つけるのが楽になります。
簡単な例で理解を深める
初期状態として count が0のような状態を持つとします。次の3つのアクションを想定します。INCREMENT は count を1増やす、DECREMENT は count を1減らす、RESET は count を0に戻す。Reducer は現在の count と受け取ったアクションを見て新しい count を返します。例えば INCREMENT なら count を +1、DECREMENT なら -1、RESET なら 0 になります。最終的に新しい状態は { count: 新しい値 } となり、Store はそれを保持して UI に反映します。
実際のアプリではこの流れを複数の状態に対して繰り返し、段階的に複雑さを増やしていきます。ここで覚えておきたいのは、アクションは状態をどう変えるかを伝える通知であり、Reducerはその通知に従って新しい状態を作る純粋な計算機だという点です。
React と組み合わせる基本
React と一緒に使う場合、react-redux という連携ライブラリを使います。アプリ全体を Provider で包み、useSelector で状態を読み取り、useDispatch でアクションを送るのが基本の流れです。これにより、UI と状態管理の結びつきを簡潔に保てます。最近は Redux Toolkit という公式ツールセットを使うと、ストアの作成や reducers の定義がさらに楽になります。
Redux Toolkit の紹介
Redux Toolkit はボイラープレートを減らせる公式の推奨ツールです。configureStore でストアを作成し、createSlice で reducer とアクションをひとまとめに作るなど、初心者でも扱いやすい設計になっています。これを活用すると、学習の敷居が下がり、ビジネスロジックに集中しやすくなります。
学習のコツと注意点
Redux は万能薬ではありません。小規模なアプリや React のシンプルな状態管理には Context API など他の選択肢が適している場合もあります。学ぶ際は、まず小さな機能の状態管理から始め、アクションと Reducer の役割を体感するのがコツです。状態を直接変更しようとする間違いを避け、常に新しい状態を返す純粋関数で更新することを心がけましょう。
要点の振り返り
まとめ
redux は状態管理を一元化し、データの流れを明確にすることで大規模なアプリの開発を楽にします。初心者はまず基本概念を押さえ、React との連携を経験しながら、Redux Toolkit などの便利なツールを活用して段階的に学習を進めると良いでしょう。
reduxの関連サジェスト解説
- redux とは 音楽
- このキーワードを見たとき、redux とは 音楽 という検索意図が気になる人が多いかもしれません。結論から言うと、Redux は音楽とは直接関係のないウェブ開発の道具です。音楽の話題と結びつくことは少なく、公式のドキュメントもプログラミングの話題を中心にしています。ただし、初心者が混乱しないように、二つの解釈を分けて解説します。まずは基本の意味から説明します。Redux とは何か。Redux は JavaScript の状態管理ライブラリです。ウェブアプリの「今、どんなデータがどこにあるのか」をひとつの場所(ストア)に集約します。データの変更はアクションというシンプルなオブジェクトを通じて行われ、変更の実際の作業を行うのがリデューサーという関数です。すべてのデータの流れは一方向で、状態の変化を追いやすく、バグの原因を特定しやすいのが特徴です。React のような UI ライブラリと一緒に使われることが多く、学習初期にはストア、ディスパッチ、リデューサーなどの用語を覚えるのが最初のステップです。使い方のイメージ。基本のセットアップはストアを作る、アクションを定義する、リデューサーを用意する、ディスパッチでアクションを走らせるという流れです。たとえばカウンターの例では、INCREMENT というアクションを作り、状態を0から始めるリデューサーが INCREMENT を受け取ると state を1増やします。実際には React-Redux というつなぎのライブラリを使って UI とストアをつなげ、ボタンを押すと dispatch が呼ばれる、という形になります。ここまで理解できれば、Redux の「何をどこに置くか」「どう動くか」という基本感覚がつかめます。音楽関連の検索についての注意。redux とは 音楽 というキーワードは音楽と関係があるのかを確かめたいときに出てくる組み合わせです。しかし現実には Redux は音楽の用語としては一般的ではありません。検索の意図をはっきりさせるために、音楽と関連づける場合は redux 音楽 バンド名 や redux 音楽 ソフトウェア など、別のキーワードを追加して調べると良い結果が出やすいです。公式サイトや日本語の解説サイト、英語のリファレンス などを順に見ていくのがおすすめです。初心者は最初に Redux の基本を理解し、その後で音楽とどう結びつくのかを自分の興味で深掘りすると良いでしょう。
- redux toolkit とは
- redux toolkit とは、Redux の公式が推奨する標準的な書き方を集めたツールキットです。従来の Redux だけだと設定やコード量が多くなりがちですが、RTK はその煩わしさを減らし、初心者にも扱いやすく設計されています。主な目的は状態管理をシンプルにし、バグを減らすことです。Redux はアプリの状態を一つのストアで管理します。ストアへ状態を更新するにはアクションとリデューサを用意しますが、これだと連携が複雑になりがちです。Redux Toolkit はこの部分を自動化・整理してくれる機能を提供します。例えば createSlice は状態の一部を担当する小さな部品であるスライスを作るのに使います。スライスには初期状態、reducers そして一連のアクションが自動で作られます。これにより、コード量を抑えつつ、予測可能でデバッグしやすい構成を作れます。次に configureStore はストアの設定を楽にします。ミドルウェアの追加、デベロッパーツールの有効化などを一箇所で整え、設定ミスを減らします。さらに createAsyncThunk で非同期処理、たとえばデータの取得を扱いやすくします。RTK にはデータを効率よく取得・管理するための RTK Query も含まれており、サーバーからのデータ取得とキャッシュの仕組みを簡単に組み込めます。初学者の方にはまず小さな機能から RTK を使い始め、徐々にスライスや非同期処理、RTK Query の使い方を覚えるのがおすすめです。
- redux reducer とは
- Reduxの中での役割は、アプリの状態(state)をどう変えるかを決める“ルール”を提供することです。そのルールを実装するのが reducer です。Reducerは純粋関数です。前の状態と action を受け取り、次の状態を返します。純粋関数というのは、同じ入力を与えれば必ず同じ出力になること、そして副作用を起こさずに外部の状態を変えないことを意味します。Action はアプリで何が起きたかを伝える情報で、形は通常 { type: 'SOME_ACTION', payload: … } のようなオブジェクトです。Reducer は action.type を見て、状態をどう変えるかを決めます。基本的な書き方の例を見てみましょう。初期状態が { count: 0 } の reducer は次のようになります。function counterReducer(state = { count: 0 }, action) { switch(action.type) { case 'INCREMENT': return { ...state, count: state.count + 1 }; case 'DECREMENT': return { ...state, count: state.count - 1 }; case 'RESET': return { ...state, count: 0 }; default: return state; }}この reducer を使うと、store に action を送るたびに count が変化します。例えば dispatch({ type: 'INCREMENT' }) を実行すると count は 1 ずつ増えます。重要な点は、state を直接書き換えず、新しいオブジェクトを返すことです。これにより状態の履歴を追いやすく、デバッグもしやすくなります。複数のリデューサを組み合わせて大きな状態を作る場合は、combineReducers を使います。個々の reducer が自分の担当部分のみを更新するので、コードが整理され、拡張もしやすくなります。注意点として、Reducer は非同期処理や API への呼び出しなどの副作用を扱いません。副作用はミドルウェア(例: redux-thunk, redux-saga)で扱い、Reducer は純粋に状態変化の規칙だけを担当します。初心者は「Reducer は状態の変化の設計図」という考えを持ち、Action と Reducer の関係をまずは理解すると学習が進みます。
- redux thunk とは
- redux thunk とは Redux のミドルウェアの一つで、非同期処理を Redux の流れに組み込むための仕組みです。Redux では通常、アクションはオブジェクトで状態を変える指示を出しますが、非同期の処理はすぐには結果が出ず、オブジェクトだけでは対応しづらい場面が多いです。そこで redux-thunk を使うと、アクションクリエーターが関数を返せるようになり、その関数が dispatch と getState を受け取り、非同期の処理を自分で制御できます。例えば API を呼び出して結果を待ってから、成功用のアクションや失敗用のアクションを dispatch する、という流れを1つの関数内で実現できます。使い方は簡単で、redux-thunk をインストールして createStore や configureStore に適用するだけです。設定例として、import thunk from 'redux-thunk'; const store = createStore(rootReducer, applyMiddleware(thunk)); または Redux Toolkit なら特別な設定をしなくても動く場合が多いです。実際のコードでは、データを取得する関数が dispatch する複数のアクション(開始、成功、失敗)を順番に呼ぶことで、UI に読み込み中の表示やエラーメッセージを反映させることができます。初学者はまず「アクションは返さず関数を返す」この点を覚えると、非同期処理の流れがつかみやすいでしょう。
- redux saga とは
- redux saga とは、Reduxでの非同期処理を安全に管理するためのライブラリです。Redux では状態を一つの箱に入れて、アクションという信号で状態を変えます。しかしネットワーク通信やタイマー、外部サービスとのやり取りなどの非同期処理は、実行の順序やエラーハンドリングが難しくなりがちです。そこで redux-saga が役立ちます。redux-saga は generator 関数と呼ばれる特別な関数を使って、非同期の流れを“別の場所”に作っておき、アクションを待って動作させます。コードの流れを“観て待つ人”と“実際に動く人”に分けて考えると理解しやすいです。takeEvery はあるアクションを監視して発生したときに処理を走らせ、takeLatest は同じアクションが連続した場合、最後のものだけ処理します。call は外部処理を実行するための道具、put はストアへ新しいアクションを送る道具、select は現在のストアの状態を読み出します。ボタンを押してデータを読み込むケースを想像してみましょう。ユーザーが「読み込み」アクションを出すと、Saga がそれを受け取り、call で API を呼び出します。データが返ってきたら put で新しいデータをストアへ送ります。エラーが起きた場合は別のエラー用のアクションを dispatch して、UI にエラーメッセージを表示することもできます。redux-thunk との違いを理解しておくと選択の目安になります。Saga は複雑な非同期処理の流れを分離して、テストもしやすく、キャンセルやリトライ、データの同時処理などを比較的自然に扱えます。大規模なアプリや複数のリクエストが同時に動く場面で特に力を発揮します。初心者はまず rootSaga や基本的な worker saga を作るところから始め、少しずつ takeEvery や takeLatest、call などのエフェクトに慣れていくと良いです。
- redux store とは
- redux store とは、アプリの状態をまとめて管理する特別な入れ物です。Redux というライブラリを使うと、全ての状態を一つの場所に集めておくことができます。これを store と呼びます。store があると、どの画面でも同じデータが使われ、バグを減らしやすくなります。store には現在の state(状態)、state を取り出す getState、状態を変えるための action を渡す dispatch、状態の変化を知るための subscribe などの機能があります。 action は「何が起きたか」を伝える情報で、 reducers がそれを受け取って新しい state を作ります。例えば、ショッピングアプリで「カートに商品を追加」したいとき、 dispatch で addToCart という action を送ります。 reducers はその action を見て、カートの中身を新しい配列に置き換え、変更後の state を返します。これにより画面は新しい状態を表示します。現代の実装では、React などの UI と組み合わせて使うことが多く、react-redux という仕組みを使ってコンポーネントと store をつなぎます。さらに UX を簡単にするために Redux Toolkit の configureStore を使うのが主流になっています。ポイントとしては、state を直接書き換えずに新しい値を作ること、action は純粋なオブジェクトであること、複数の reducer をまとめて一つの store にする設計を理解することです。これらを守ると、デバッグや機能追加が楽になります。まとめとして、redux store とはアプリの“現在の状態”を集めておく箱であり、 action の発行と reducer の更新を通じて状態を安定して変化させる仕組みです。初心者ならまずは基本の使い方を理解し、徐々に Redux Toolkit の導入へ進むとよいでしょう。
- redux dispatch とは
- redux dispatch とは、Redux で状態を変える“指示”をストアに送る仕組みです。アクションと呼ばれる plain object を渡すことで、ストアは現在の状態を新しい状態へ更新します。まず基本を押さえましょう。アクションは type と必要に応じた payload を含む形で作成します。例として { type: 'INCREMENT', payload: 1 } のような単純なものがあります。これを store.dispatch(incrementAction) のように呼ぶと、リデューサーが受け取り新しい状態を返します。続いて動きを整理します。Action Creator という関数を使うと、同じ形のアクションを何度も作りやすくなります。例: const increment = (n) => ({ type: 'INCREMENT', payload: n }); これを store.dispatch(increment(2)) のように使います。非同期処理が絡む場合には redux-thunk などのミドルウェアが必要になる点も押さえておくと良いでしょう。thunk を使うと store.dispatch に関数を渡して、途中で別のアクションを連続して送ることができます。
- flux redux とは
- flux redux とは、Webアプリの状態(表示しているデータや設定など)を管理する仕組みのことです。まず Flux は Facebook が提案した設計パターンで、データの流れを一方向に限定する考え方です。Redux はその思想を受け継ぎ、さらに使いやすさと予測可能性を高めたライブラリとして多くの開発者に使われています。Flux のしくみは次のように考えるとわかりやすいです。アクションという“何かが起こった情報”をきっかけに、ディスパッチャという中心の役割がアクションを受け取り、複数のストアにその更新を伝えます。各ストアは自分の持つデータを更新し、ビュー(画面)はストアの状態を見て表示を変えます。これを一方向の流れと呼び、データの流れを追いやすくする特徴があります。一方、Redux は Flux の長所を活かしつつ、構成を簡単にしたライブラリです。Redux では基本的に「単一のストア」に全体の状態を集約します。アクションを受け取るのはストアで、状態の更新は純粋関数であるリデューサと呼ばれる関数が行います。UI は store の状態を購読し、状態が変わると再描画します。Redux には dispatch という関数でアクションをストアへ送る仕組みがあり、デバッグ時にはアクションの履歴を時系列でたどれる Time Travel などの機能が強みになります。Flux と Redux の大きな違いは、ストアの数と処理の流れ方です。Flux は複数のストアを使い分け、アクションはディスパッチャを通じて各ストアに伝わります。Redux は単一のストアと純粋関数のリデューサで状態を更新する点が特徴です。学習コストは人それぞれですが、Redux は公開されているドキュメントが豊富で、初心者にも入りやすいと言われます。なぜ使われるかというと、データの流れが明確になるため大規模なアプリでもバグを減らし、デバッグやテストが楽になるからです。
reduxの同意語
- リダックス
- Reduxの日本語読み・別名。JavaScriptの状態管理ライブラリの名称として広く使われる表記。
- 復活
- 以前の状態や機能をもう一度取り戻すこと。テック用語では、機能の再有効化を指す場合もある。
- 復元
- データや設定を元の状態に戻すこと。バックアップからの復元など、保存された状態を取り戻す意味で使われる。
- 復旧
- 障害後に正常な状態へ戻すこと。システムやサービスの安定化を表す場面で使われる。
- 再現
- 過去の現象・状態をもう一度現すこと。仕様の再現性やデモの再現性を説明するときに使われる。
- 再構築
- 壊れた・古くなったものを新しく作り直すこと。コードベースの再設計・新規実装を指す場面で用いられる。
- 回帰
- 元の状態へ戻る、または元の流れに戻ること。データの過去バージョンへ戻す意味合いで使われることもある。
- 蘇生
- 比喩的に、機能やサービスを生き返らせること。強めの表現として使われることがある。
- 再導入
- 以前使っていたものを再び導入すること。新旧を入れ替える場面で使われる。
- 再起動
- アプリやシステムを再起動して、状態をリフレッシュすること。更新後の安定化を示す場面で使われる。
reduxの対義語・反対語
- 原初
- redux の反対の概念として、最初の状態。元の姿・初期のままで“戻されていない”状態を指します。
- 初期状態
- 開始時点の状態。redux が“再び戻す”意味合いに対して、初期状態はその初めの形を意味します。
- 新規作成
- 新しく作られた状態。過去の状態へ回復するのではなく、これから新しく生み出された状態を指します。
- 最新状態
- 現在・最新の状態。redux が過去へ戻すイメージに対し、今ここにある最新の状態を示します。
- 旧式
- 古い仕様・設計。redux の復活・復元という意味と対照的に、昔のままの状態を指します。
- 廃止
- 機能の停止・撤廃。redux の“復元”と反対の方向性を表します。
- 消滅
- 存在しなくなること。復元して戻るという意味とは逆の概念です。
- 未復活
- まだ復活していない状態。redux で“戻る”こととは反対の状態を示します。
- 未再現
- 再現されていない、再現される予定がない状態。redux の復元とは逆の方向性。
- 破棄
- 廃棄・放棄された状態。redux の復元とは対照的に、対象を捨て去るイメージです。
reduxの共起語
- React
- Reduxと併用されるUIライブラリ。UIの状態をReduxと連携して管理するのに使われる。
- React-Redux
- ReactとReduxをつなぐ公式ライブラリ。Provider、connect、useSelector、useDispatchを提供。
- Redux Toolkit
- Reduxの公式ツールセット。設定を簡略化する configureStore、sliceの作成 createSlice、非同期処理のための createAsyncThunk などを提供。
- RTK
- Redux Toolkitの略称。
- store
- Reduxの中心となる状態の保管場所。アプリ全体の状態木を保持。
- state
- 現在のデータの状態。Reduxでは単一の state ツリーとして管理。
- reducer
- 現在の状態とアクションから新しい状態を返す純粋関数。
- action
- 状態変更を指示するオブジェクト。typeとpayloadを含むことが多い。
- actions
- 複数のアクションの集合、またはアクションオブジェクトを作るためのアクションクリエイター群。
- dispatch
- アクションをストアに送って処理を開始する関数。
- action creators
- アクションオブジェクトを生成する関数。
- middleware
- アクションがストアへ渡る前後で処理を追加できる拡張機能。
- thunk
- 非同期処理を扱えるミドルウェアの一種。
- redux-thunk
- thunkミドルウェアの正式名称。
- redux-saga
- 非同期処理をエフェクトとして扱うミドルウェア。
- saga
- redux-sagaの機能や概念。
- combineReducers
- 複数のリデューサを1つにまとめる関数。
- rootReducer
- アプリ全体のリデューサをまとめたもの。
- configureStore
- Redux Toolkitで推奨されるストア生成API。
- createSlice
- Redux Toolkitで状態とリデューサをひとまとめにする単位を作成する関数。
- createAsyncThunk
- 非同期処理を簡潔に定義するRTKの関数。
- createEntityAdapter
- エンティティ集合を扱うための補助ユーティリティ。
- Immer
- 不変性の扱いを楽にするライブラリ。Redux Toolkitはデフォルトで Immer を使う。
- selector
- ストアの状態の一部を取り出す関数。
- useSelector
- React-Reduxのフックで、ストアの状態を取得する。
- useDispatch
- React-Reduxのフックで、ディスパッチを取得する。
- connect
- 従来の高階コンポーネントで、状態とディスパッチをプロパティとして接続する。
- Provider
- React-Reduxの Provider。ストアをコンポーネントツリー全体に提供する。
- mapStateToProps
- connectと一緒に、ストアの状態をコンポーネントの props へ変換する関数。
- mapDispatchToProps
- connectと一緒に、ディスパッチをコンポーネントの props へ変換する関数。
- redux-persist
- ストアの状態を永続化してページ再読み込み後も復元する仕組み。
- redux-devtools-extension
- Redux DevToolsと連携してデバッグを容易にする拡張機能。
- DevTools
- DevToolsの略称。Reduxのデバッグ機能の総称。
- reselect
- メモ化されたセレクターを作るライブラリ。
- immutability
- 状態を直接変更せず、新しいオブジェクトを返して不変性を保つ設計。
- state management
- アプリの状態を管理する考え方・技術。
- unidirectional data flow
- データの流れが一方向で、予測可能な更新を促す設計原理。
- SSR
- サーバーサイドレンダリング。Reduxはサーバーとクライアントで状態を共有するのに使われる。
- hydration
- サーバーから受け取った初期状態でクライアントのストアを復元する処理。
- slice
- Redux Toolkitでリデューサ・アクションをひとまとめにした単位。
reduxの関連用語
- Store
- Reduxの根幹となるオブジェクト。アプリの全状態を一箇所で管理し、状態の取得・更新の入口になる。
- Action
- 状態の変化を伝える情報を含むオブジェクト。通常は type と payload を持つ。
- Reducer
- 現在の状態と渡された Action から新しい状態を計算して返す純粋関数。
- Dispatch
- Action をストアに送信して、Reducer を経由して状態を更新する操作。
- State
- Store に現在格納されているデータの集合。
- Action Creator
- Action オブジェクトを作成する関数。
- Action Type
- Action を識別するための文字列(例: 'ADD_TODO')。
- Middleware
- Dispatch と Reducer の間に介在し、非同期処理・ログ・エラーハンドリングなどを可能にする機能。
- applyMiddleware
- ミドルウェアをストアに組み込むための関数。
- Thunk
- 非同期処理を可能にするミドルウェア。関数を返すアクションを使えるようにする。
- Redux Thunk
- 公式の Thunk ミドルウェア。
- Saga
- 副作用を扱うミドルウェアの考え方。複雑な非同期処理をジェネレータで制御する。
- Redux-Saga
- Saga の実装。
- Redux Toolkit
- Redux を使いやすくする公式ツールセット。ボイラープレートを減らす。
- createSlice
- Redux Toolkit で状態とリデューサーを一つにまとめる『スライス』を定義する関数。
- createAsyncThunk
- 非同期処理を簡潔に扱える RTK のヘルパー。
- extraReducers
- createSlice で、他のアクションに対応するための reducers を追加するセクション。
- Slice
- 状態と reducers をひとまとめにした機能単位。
- Selector
- ストアの全体状態から、必要な値を取り出す関数。
- createSelector
- 再計算を memo 化するセレクターを作るための関数。
- Reselect
- セレクターをメモ化して、同じ入力で再計算を避けるライブラリ。
- Memoization
- 同じ入力が続くと前回の結果を再利用する最適化手法。
- Immutability
- 状態を直接変更せず、コピーを作って新しい状態を返す設計思想。
- Immer
- 不変性を保ちながら、可変的な書き方で状態を更新できるライブラリ。
- Immer.js
- Immer の実装ライブラリ。
- bindActionCreators
- アクションクリエイターをディスパッチと結びつけるヘルパー。
- mapStateToProps
- React コンポーネントへ、ストアの状態をどう渡すかを定義する関数。
- mapDispatchToProps
- React コンポーネントへ、ディスパッチをどう渡すかを定義する関数。
- connect
- React-Redux の高階コンポーネント。ストアと UI を結ぶ。
- Provider
- React アプリに Redux ストアを渡すためのコンポーネント。
- Redux DevTools
- 状態の変化と履歴を可視化するデバッグツール。時間旅行機能などがある。
- Redux Persist
- ストアの状態をローカルストレージなどに永続化するライブラリ。
- PersistGate
- 永続化されたデータの復元を待つための UI コンポーネント。
- combineReducers
- 複数の reducer をひとつの reducer に結合する関数。
- compose
- 複数の関数を順に適用するための関数。
- Store Enhancer
- ストアの機能を拡張する拡張機能のこと。
- Time-travel debugging
- 過去の状態に遡ってデバッグする機能。
- Hot Module Replacement
- 開発時にモジュールを差し替え、ページ再読み込みなしで更新する機能。
- Ducks pattern
- 機能別にファイルをまとめる Redux の組織パターン。
- Normalizr
- 関連データを正規化して扱うためのライブラリ。
- Normalized state
- 参照の一意性を保ち、データを正規化して管理する状態設計。
- Async actions
- 非同期処理を伴うアクション。
- Side effects
- 副作用。API 呼び出しなど、純粋関数以外の処理。
- Serializability
- 状態をシリアライズ可能な形に保つこと。
- Optimistic updates
- 実際の更新前に UI を先に反映し、後で結果を整合させる手法。
- RTK Query
- RTK に含まれるデータフェッチ・キャッシングの機能。
reduxのおすすめ参考サイト
- 今度こそ Redux を完全に理解する(初心者向け) #React - Qiita
- 【2024年11月最新】Reduxとは?特徴や使い方を丁寧に解説
- 【2024年11月最新】Reduxとは?特徴や使い方を丁寧に解説
- Reac初心者でも読めば必ずわかるReactのRedux講座