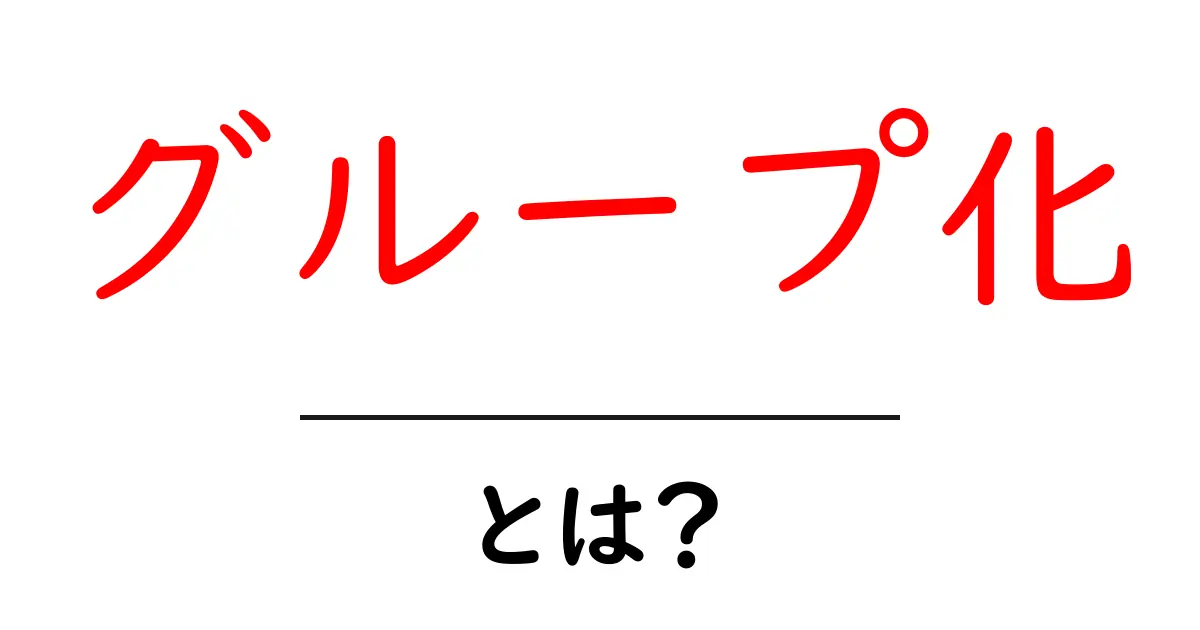

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
グループ化・とは?基本の意味と使い方
グループ化とは、関連する要素を集めてひとつのまとまりとして扱う作業のことです。日常のノート整理から、データ分析、ウェブサイトの構造設計、SEO対策まで、さまざまな場面で役立ちます。整理と分類を組み合わせることで、情報の重複を減らし、目的の情報へたどり着く時間を短くします。
グループ化の基本的な考え方
グループ化の基本は3つの要素です。第一に関連性。似た性質や目的を持つものを一緒にします。第二に階層。大きなグループの中に、さらに小さなグループを作ることがあります。第三に目的。なぜグルーピングを行うのか、検索のしやすさ、表示の分かりやすさ、分析の効率化などを意識します。
SEOの世界でのグループ化
SEOでは、キーワードやページを適切にグループ化することで、検索エンジンに伝えたい関連性を強く伝えることができます。例えば、同じテーマの記事をひとつのグループにまとめ、それらへの内部リンクを増やすと、検索エンジンは「このグループはこのテーマに関する情報がまとまっている」と判断します。結果として、ユーザーが検索する際に関連性の高いページが表示されやすくなります。
グループ化の実例
実生活の例としては、ノートのノートを「数学」「英語」「科学」といったグループに分けることです。データ分析では、顧客データを年齢層別、または地域別に分けて集計します。ウェブサイトでは、記事をトピック別にカテゴリ化し、訪問者が似た話題を一度に読めるようにします。
グループ化の具体的な方法
下の表は、グループ化の基本的な使い方を整理したものです。各分野で「意味」と「ポイント」をチェックしておくと、実務で役立ちます。
このように、グループ化は情報を整理して、探す手間を減らし、伝えたいメッセージを明確にするための基本的な技術です。練習のコツは、まず小さな範囲から始め、関連性がはっきりする基準を自分なりに作ることです。
グループ化の関連サジェスト解説
- エクセル グループ化 とは
- エクセルのグループ化とは、データの行や列をひとまとめにして、必要な時だけ表示を切り替えられる機能です。長い表の中身を整理するのに便利で、全体の見通しをよくします。グループ化は「行をグループ化」か「列をグループ化」を選んで適用します。グループ化した範囲には、左端や上部に折りたたみ用の記号が現れ、-をクリックするとそのグループが隠れ、+をクリックすると再表示されます。これにより、表を印刷するときに要点だけを出力したり、説明用の本文をすっきり表示したりできます。使い方の手順は基本的に次のとおりです。まずグループ化したい行または列を連続して選びます。次にデータタブを開き、グループ化をクリックします。表示が「行」なら行を、「列」なら列をグループ化します。画面左側に「-」「+」のアウトライン記号が現れます。- を押すとグループが折りたたまれ、+ で展開します。具体例として、月別売上データを例に挙げます。月ごとにグループ化すると四半期や年の推移を見やすくできます。部門別にデータが並んでいる場合は部門ごとにグループ化して比較を楽にします。注意点として、グループ化はデータを削るわけではなく表示を切り替える機能である点、並べ替えをしたあとにグループ化すると順番が変わることがある点、必要に応じて複数段階の階層を作ることもできる点を挙げます。解除方法はデータタブのグループ化からグループ解除を選ぶか、アウトラインをクリアします。これらの使い方を覚えれば、長い表の作業効率が大きく向上します。
- access グループ化 とは
- 「access グループ化 とは」って言葉は、複数の人に同じ権限をまとめて管理する考え方のことです。ITの世界では、だれが何をできるかを一人ずつ決めていくと手間も間違いも増えます。そこで、同じ役割や作業を担当する人を集めて“グループ”を作り、そのグループに対して権限を一括で設定します。これにより、新しく加わった人も同じグループであれば同じ権限を持ち、離職してもグループ名を消すだけで済むことが多くなります。具体例で考えてみましょう。学校の図書室の運用を例に取ると、先生用グループ、学生用グループ、図書委員用グループの3つに分け、それぞれが閲覧できるフォルダや編集できるファイルを決めます。先生グループにはすべての資料の閲覧と編集を許可、学生グループには閲覧のみ、図書委員グループには予約表の更新ができる権限を与える、という感じです。ウェブサービスやクラウドでも同じ考え方が使われます。個人ごとに権限を設定すると管理が大変ですが、部署や役割でグループを作ると、一括で同じ権限を与えられます。例えば「営業部」「人事部」などのグループを作り、それぞれのメンバーに同じフォルダへのアクセスを許可します。ただし注意点もあります。必要以上の権限を与えない“最小権限の原則”を守ること、グループ名と実際の役割が一致していること、誰がいつグループに参加・退会したかを定期的に見直すことです。初めて挑戦する人は、1) 目的に合うグループを決める、2) そのグループに必要な権限を決める、3) グループを作成してメンバーを追加する、4) 簡単なテストをして、実際にアクセスできるか確認する、という順序で進めると分かりやすいです。この考え方を覚えると、学校や職場、クラウドサービスなどで情報を安全に、効率よく共有できるようになります。
- スプレッドシート グループ化 とは
- スプレッドシート グループ化 とは、表の中の行や列をまとめて表示・非表示を切り替えられる機能のことです。データが細かく長くなると見にくくなるため、必要な部分だけを広げて確認できるようにします。グループ化はExcelでもGoogleスプレッドシートでも使え、目的は同じです。使い方の基本は、まずグループにしたい連続した行または列を選択します。次に、データメニューから「グループ化」または「アウトラインを作成」を選びます。表示される左端のマージンに小さな「+/-」のボタンが現れ、クリックで折りたたみ・展開ができます。活用のコツは次のとおりです。- 長いデータを整理して、トピック別に起動する。- グループ化した行を折りたたんだ状態で、合計や平均などの計算を目安にする場合は、別の列に集計式を置くと見やすいです。- 複数のグループを組み合わせることも可能で、必要に応じて階層構造を作れます。実例を挙げると、月別の売上データを地域ごとに並べた表では、地域ごとに行をグループ化しておくと、地域を展開して中身を確認したり、全体の傾向だけを見せたいときに折りたたみで表示を切り替えられます。なお、グループ化はデータそのものを結合するわけではなく、表示を整理する機能です。結合してしまうとデータの再分析が難しくなるため注意しましょう。手順の要点- Googleスプレッドシートの場合: グループ化したい連続した行を選択 → データメニューから「グループ化」を選択 → 左端のマージンに出る「-」ボタンで折りたたみ/展開。- Excelの場合: 同様に選択して「データ」タブ → 「グループ化」 → 行または列を指定して作成。- 非連続な行や列は同時にはグループ化できません。順番を揃え、適切にグループを分けることが大切です。この機能を知っておくと、報告用の表をすっきり見せたり、作業中のデータを効率的に整理したりできるようになります。
- パワポ グループ化 とは
- パワーポイント(以下パワポ)で資料を作ると、図形やテキストボックスが増えてきて個別に動かすと位置がずれてしまうことがあります。そんなとき役に立つのが“グループ化”です。パワポ グループ化 とは、複数のオブジェクトをひとつのまとまりとして扱える機能のことです。グループ化すると、ひとつのユニットとして移動、サイズ変更、回転ができ、整列や等間隔配置を崩さずに作業できます。これにより、図形の組み合わせを長く使えるプレゼン資料の作成が楽になります。操作手順はかんたんです。まずShiftキーを押しながらクリックするか、ドラッグで複数のオブジェクトを選択します。次に、リボンのホームタブの配置または整列メニューから「グループ化」を選び、さらに「グループ化」をクリックします。ショートカットはCtrl+Gです。グループ化された状態では、要素を「1つの塊」として移動・サイズ変更・回転ができます。個別の要素を編集したいときは、グループを選択した状態でCtrl+Shift+Gで「グループ解除」します。必要に応じて再度選択して「グループ化」することも可能です。日常の活用例として、ロゴ風のセット、図表の部品をまとめて扱う場合、見出しとサブタイトルをセットで整える場合などがあります。グループ化は配置の一貫性を保ちながら作業効率を上げ、資料の見栄えを整える基本テクニックのひとつです。注意点としては、グループ内の特定の要素だけ先に編集したい場合、一度グループを解除してから作業するか、ダブルクリックで個別要素を編集する方法があります。最後に、図形だけでなく画像や図表、テキストボックスなど同じプレース内の複数要素をまとめられる点を覚えておくと、複雑な資料でも美しく整理できます。
- パワークエリ グループ化 とは
- パワークエリ グループ化 とは、データの中の似た行をまとめて1つのまとまりにする機能のことです。たとえば日付ごと、商品ごと、地域ごとなど、共通の特徴を持つ行を“集めて”合計や平均を出す作業を簡単にします。Excelの通常の並べ替えやフィルターだけでは、同じ項目を何度も手作業で集計しなければならず手間がかかりますが、グループ化を使うとその手間を大幅に減らせます。Power Queryでは、まずデータを取り込み、グループ化したい列を基準に設定します。次に「グループ化」ボタンを押すと、集計方法を選ぶ画面が出ます。ここで「合計」「平均」「件数」などの集計を選べます。たとえば売上データを「商品名」ごとにグループ化して「売上金額の合計」を出すと、商品ごとの売上規模が一目でわかります。複数の集計を同時に作成することも可能で、1つの新しい列に「合計」、別の列に「件数」を作ることもできます。グループ化では、集計後のデータの形が大きく変わるため、元の表の列がすべて消えず、集計後の新しいテーブルとして表示されます。使い方のコツは、集計のキーとなる列をしっかり決めることと、集計の種類をケースごとに使い分けることです。中学生にも理解しやすいポイントとして、まずはごく少数の列で練習し、結果を元データと比べて正しく反映されているかを確認すると良いでしょう。
- クエリ グループ化 とは
- クエリ グループ化 とは、検索エンジンの視点から見て、似ている検索ワードを一つのグループにまとめて扱う考え方のことです。要は「同じ話題や似た意図を持つ質問をまとめて、ひとつの流れとして整理する」作業です。なぜこれが大切かというと、ユーザーの検索意図は微妙に違っても、根っこのテーマは共通していることが多く、そうした関連クエリを一緒に考えると、サイト全体の構成が分かりやすくなり、検索結果での評価も安定しやすくなるからです。例えば「ダイエット 方法」「ダイエット 効果」「ダイエット レシピ」は、すべてダイエットという大きなテーマにかかわります。これらを別々のページにばらまくよりも、同じグループとして整理し、内部リンクでつなぐことで、検索エンジンにも「このサイトはダイエットに関する情報を網羅している」という信号を伝えやすくなります。実際の進め方は次のようになります。まずキーワード調査で意味が近いクエリを集め、リストを作成します。次にグループの基準を決め、意図(情報収集、比較、購入)やトピックの共通点で分類します。続いてグループごとにコンテンツ設計をします。大きなグループには pillar ページ(総論)、細かな話題は cluster ページ(詳しい解説)を割り当て、内部リンクを整えます。こうすることで、同じグループ内のページ同士が関連づけられ、ユーザーが次に読み進む導線が自然になります。具体的な例として、旅行初心者向けのグループを考えてみましょう。グループAは「予算内で楽しむコツ」、グループBは「格安航空券の探し方」、グループCは「現地での交通手段の比較」などです。各グループに対応する記事を作成し、 pillar ページで全体の方針を示し、 cluster ページで詳しい情報(費用の目安、実践的な手順、注意点など)を分かりやすく解説します。ツールとしては Google キーワードプランナー、Google サーチコンソール、Ahrefs などを活用して、検索ボリュームや競争状況を確認します。ただし、扱う範囲が広すぎると煩雑になりやすいので、初めは大きなグループを作ってから徐々に細分化していくのがコツです。最後に運用のポイントとして、検索結果の変化を定期的にチェックし、分析結果をもとにグループの見直しを行います。ユーザーの検索意図は時とともに変わるため、グルーピングの基準自体も柔軟に調整することが大切です。これを習慣化すれば、SEOの基盤が安定し、長期的に検索トラフィックを増やすことにつながります。
- ワード グループ化 とは
- ワード グループ化 とは、複数のキーワードを意味が近いテーマごとにまとめる作業のことです。SEOの現場では、検索意図が似ている語句を同じグループに寄せて整理することで、記事のテーマを明確にしたり、内部リンクの設計を効率化したりします。たとえば「ワード グループ化 とは」「ワード グループ化 方法」「キーワード グルーピング」といった語を一つのグループにまとめ、別のグループには「SEO 基礎」「キーワード選定」「ロングテール戦略」などを置く、という形です。\n\nなぜこれが役立つのかというと、グループごとに最適なコンテンツを作りやすくなり、検索エンジンにも関連性の高い記事を連携させやすくなるからです。具体的には、以下のメリットがあります:\n・検索意図に沿った記事が作りやすい\n・キーワードの過密化(キーワード過不足)を減らせる\n・内部リンクの設計がスッキリする\n・新しい記事のアイデアが浮かびやすい\n\n実際の進め方はシンプルです。まずは全体のキーワードを洗い出し、次に意味が近い語をテーマ別にグループ化します。グループ名は分かりやすく短く、検索意図を示すものが望ましいです。次に各グループに対して狙うページタイプを決め、記事の長さや見出し構成を決めます。最後に定期的に見直して、検索トレンドの変化にも対応します。\n\n注意点としては、グルーピングに時間をかけすぎて実行を先延ばしにしないことと、グループごとの競合性を考慮して現実的な難易度を設定することです。実務ではExcelやGoogle Sheetsなどの表計理ツールを使い、キーワードを列に、グループを行にして整理すると見やすくなります。
- sql グループ化 とは
- sql グループ化 とは、データを似た値ごとにまとめて、各グループごとに集計を行う仕組みのことです。データベースの表には複数の行があり、同じ特徴を持つ列の値が並んでいます。グループ化を使うと、同じカテゴリの行を1つのグループにまとめ、そのグループ全体に対して集計を行えます。たとえば商品データをカテゴリで分け、各カテゴリの売上の合計を知りたいときに便利です。SQLの基本は選択する列を指定する SELECT、データの居場所を示す FROM です。GROUP BY を使うときは、集計関数とともにグループを作り、各グループごとに結果を出します。集計関数には COUNT、SUM、AVG、MIN、MAX などがあり、これらを使ってグループ内のデータをまとめます。GROUP BY の後には、通常、集計対象の列を指定します。これを忘れるとエラーや予期しない結果になることがあります。実際の例として、sales テーブルをカテゴリごとに分けて売上件数を数える場合は、 SELECT category, COUNT(*) AS total_sales FROM sales GROUP BY category; あるいはカテゴリごとの売上金額を知るには、 SELECT category, SUM(amount) AS total_amount FROM sales GROUP BY category; なお、SELECT に現れる列は GROUP BY で指定した列か、集計関数を使った列に限定される点に注意してください。非集計の列を表示したい場合はウィンドウ関数や別のクエリを検討します。
- ピボットテーブル グループ化とは
- ピボットテーブルは、データを集計して表としてまとめるExcelやGoogleスプレッドシートの機能です。その中の「グループ化」とは、細かいデータをまとまりごとに分けて、見やすく比較しやすくする操作です。例えば日付データを「日・月・年」で区切ってトレンドを見たり、金額を「0–1000・1000–5000・5000以上」のようにレンジ分けして分布を確認したりします。グループ化を使うと、膨大なデータでも合計、平均、件数といった集計を直感的に把握でき、報告資料の体裁も整います。実際の手順はシンプルです。まずピボットテーブルを作成し、分析したいデータ範囲を選択。次に、行または列に項目を配置します。右クリックやメニューから「グループ化」を選び、日付なら「日・月・年」、数値ならレンジ幅を設定します。グループ化の粒度を変えるだけで、見え方は大きく変わります。初めは日付のグループ化から試し、月次の推移や季節性を確認すると良いでしょう。正しく使えば、データの背後にある傾向を一目でつかめ、レポート作成の強力な味方になります。
グループ化の同意語
- グルーピング
- 同じ特徴を持つ要素をひとまとめにする作業。データ整理やUIの設計、分析で使われる日常的な表現です。
- グループ分け
- 基準を決めて要素を複数のグループに分けること。最も身近でわかりやすい言い換えです。
- 分類
- 性質・特徴に基づいて物事を分類してカテゴリを作る考え方。汎用性の高い基本語です。
- カテゴライズ
- 要素をカテゴリに割り当て、整理・分析の軸を作ること。
- カテゴリ化
- 要素をカテゴリへ属させ、整理のためのカテゴリ体系を作ること。
- カテゴリ分け
- カテゴリを作って要素を所属づけする作業の表現。
- 区分化
- 要素を基準で区分(区分)に分け、グループを作ること。細分化を含む場合も多い。
- 区分
- 性質・目的で別けて、異なるグループに分けること。
- セグメンテーション
- 市場やデータを似た特徴で分け、ターゲットグループを作る手法。
- クラスタリング
- データを似ているもの同士で自動的にグループ化する分析手法。
- クラスター化
- クラスタリングと同義。要素を類似度でクラスターにまとめること。
- 集約
- 複数の要素をまとめて1つのまとまりにすること。データ処理でよく使われる用語。
- 統合
- 別々の要素を統一して一つのまとまりにすること。互換性のある要素を結合するニュアンス。
- 組織化
- 要素を目的や機能で整理し、体系的に配置すること。構造化の意味合いを含む広い表現。
グループ化の対義語・反対語
- 分割
- グループを複数の部分に分けること。グループ化の反対の概念として使われる。
- 分離
- 要素同士を結びつけず、独立させる状態・処理。グループ内の結合を解くイメージ。
- 散在化
- 要素をばらばらに配置し、グループとしてまとまらない状態にすること。
- 分散
- データや要素をグループ化せず、広く散らすこと。まとまらず分散した状態を指す。
- 解体
- 既存のグループを崩して崩壊させること。
- 個別化
- 各要素を個別に扱うようにすること。グループ化の対極として捉えられる。
- 孤立化
- 他の要素との結びつきを断ち、孤立した状態にすること。
- 単独化
- 要素を単独の状態にすること。グループ化とは逆の状態。
- 非グループ化
- グループ化という状態を取らないこと。
- 非集約化
- 集約・統合を行わない状態。グループ化を避け、個別性を重視する動き。
- 非結合化
- 結合・結束を解除すること。
- 拡散
- 要素を広く分散させ、グループを作らず広く散らす状態。
グループ化の共起語
- クラスタリング
- データを特徴が似ている集団ごとに分ける手法。似たデータを同じグループに分類します。
- 分類
- データをあらかじめ決めたカテゴリに割り当て、整理する作業。初心者にはラベルづけのようなイメージです。
- カテゴリ化
- データをカテゴリ名で整理すること。大分類を作る基本的な整理方法です。
- 階層化
- グループを階層構造に整理すること。親子関係のあるグループを作ることを指します。
- タグ付け
- アイテムに関連性のあるキーワード(タグ)を付け、後でまとめやすくする方法です。
- カテゴリ
- データを分ける際の大分類名。カテゴリは分類の一形態です。
- フォルダ分け
- ファイルやデータ項目をフォルダで整理する感覚のグルーピングです。
- ピボットテーブル
- Excelなどでデータを基準別にまとめて集計表示する機能。データのグルーピングに使われます。
- 集計
- データを要約して合計、件数、平均などの指標を出す作業です。
- 集約
- 複数のデータをひとつの値にまとめる処理。集計と近い意味です。
- 条件
- グループ化の基準となる条件やフィールドのことです。
- GROUP BY
- SQLで列の値ごとにデータをグループ化して集計する句のことです。
- SQL
- データベースからデータを取得・操作するための言語です。
- データベース
- 大量のデータを整理・保存する場所。グルーピングはデータベース操作でよく使われます。
- データ分析
- データを解釈して意味のある洞察を得る作業です。グループ化は分析の基本技法です。
- データ整理
- データを使いやすい形に整える作業の総称です。
- データ前処理
- 分析前にデータを整える準備作業。欠損処理や型揃えなどを含みます。
- 並べ替え
- データの表示順序を整える操作です。グループ化とセットで使われることが多いです。
- 重複排除
- データの重複を取り除く、または重複を避けて整理する処理です。
- セグメンテーション
- 市場やデータを意味のあるセグメントに分けること。ターゲティングにも使われます。
- ビニング
- 連続データを区間に分けてグルーピングする方法です。
- ラベル付け
- データに意味あるラベルを付け、分類・検索を容易にします。
- 階層データ
- 階層構造を持つデータのことです。親子関係を表現します。
- アグリゲーション
- データを集約して総計や平均などの指標を作る処理です。
- データクレンジング
- データの誤りを修正・除去して整える作業です。
- グルーピング
- グループ化という語の別表現。
グループ化の関連用語
- グループ化
- データやアイテムを共通の特徴や条件でまとめること。分析・整理・検索の前提となる基本的な操作です。
- 分類
- 物事を同じ属性・性質で分け、グループを作る行為。カテゴリの設定を含みます。
- カテゴリ化
- 内容をカテゴリ(分類の枠組み)に振り分け、整理・検索性を高める作業です。
- セグメント化
- 対象を共通の特徴で小さな塊(セグメント)に分け、分析・ターゲティング・最適化に活用します。
- タグ付け
- アイテムに複数のタグを付け、横断的なグルーピングを可能にする方法です。
- 階層化
- グループを階層構造で整理し、親子関係を表現します。
- 階層構造
- グループをツリー状に並べ、上位と下位の関係を可視化する構造です。
- クラスタリング
- データを類似性の高いグループに自動的に分ける統計的手法。教師なし学習の代表的な技法です。
- クラスタ
- クラスタリングにより生まれる、それぞれのグループのこと。
- 階層型クラスタリング
- データを階層的な親子関係のグループに分ける手法です。
- 非階層型クラスタリング
- 事前に決めた数のグループにデータを割り当てる手法(例: K-means)。
- ピボットテーブル
- データを集計・グルーピングして要約する表。ExcelやGoogle Sheets でよく使われます。
- 集約
- グループごとに合計・平均・最大値・最小値などの統計量を計算して要約します。
- GROUP BY
- SQL でデータをグループ化し、各グループごとに集計を行う句です。
- 集約関数
- グループ化したデータを要約する関数の総称。例: SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN。
- パーティショニング
- データを複数の部分に分割して管理・分析を効率化する手法。大規模データの処理に有用です。
- バケット化(ビニング)
- 連続データを区間(バケット)ごとに分けてグルーピングする方法です。
- メタデータによるグルーピング
- 作成日時・著者・ファイルタイプなど、データに付された属性情報で整理する方法です。
- タグとカテゴリの使い分け
- タグは複数のグループを横断して付けられることが多いのに対し、カテゴリは整理の枠組みを提供します。
- セグメンテーション
- 市場・顧客などを類似の特性で分け、ターゲット戦略や分析を行う手法です。
- OLAPのロールアップとドリルダウン
- 多次元データを階層的に分析する手法。ロールアップは上位レベルへ、ドリルダウンは下位へ移動します。
- データマイニングのグルーピング
- 大量データから意味のあるグループを発見する応用技術の総称です。



















