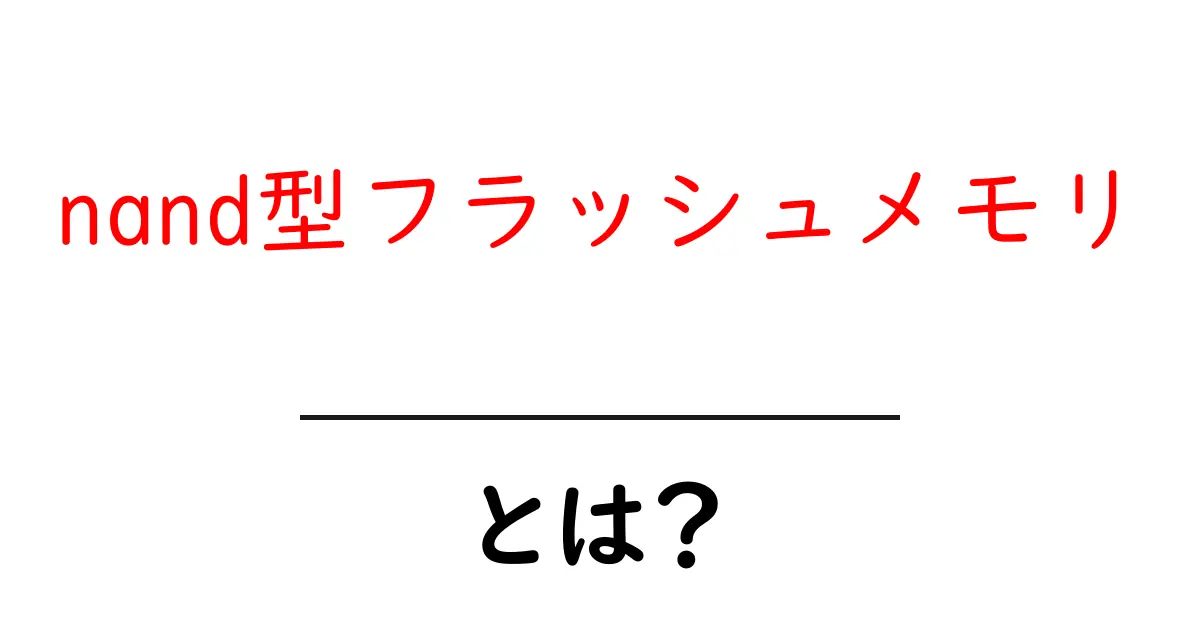

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
nand型フラッシュメモリ・とは?
このページでは、nand型フラッシュメモリ とは何かを、中学生にもわかる言葉で解説します。非揮発性の記憶装置で、電源を切ってもデータを保持できる特徴があります。スマホの内部ストレージやパソコンのSSD、USBメモリなど、私たちの身の回りの多くの機器に使われています。
nand型フラッシュメモリは、セルと呼ばれる小さな記憶の単位を直列に並べて、たくさんのセルを一つのブロックにまとめています。直列接続により、容量を高くすることができ、同じスペースでより多くのデータを格納できます。
読み出しはページ単位、書き換えや消去はブロック単位で行います。データを一部だけ修正するのではなく、ブロック全体を消して新しいデータを書き込むのが基本的な方法です。これがNAND型の特徴で、同じ大きさのチップでもNOR型より高密度・低コストを実現しますが、書き換えの粒度が大きい点に注意が必要です。
| 特徴 | NAND型 | NOR型 |
|---|---|---|
| セルのつながり | 直列に多くのセルを連結 | セルを独立してアクセスする構造 |
| 容量とコスト | 高密度・低コスト | 低密度・高コスト |
| 読み出し/書き換えの単位 | ページ/ブロック単位 | アドレス単位やセル単位の読み出しが中心 |
| 寿命・耐久性 | ブロック単位の劣化と書き換え回数の制限 | 個別アクセスは可能だがデータ容量は少なめ |
このような特性を踏まえて、実際の製品にはウェアレベリングやエラー訂正コード(ECC)といった工夫が組み込まれ、長い期間データを正しく保てるように設計されています。SSDでは高速性と大容量、USBメモリでは持ち運びやすさが重視されるため、用途に応じてNAND型フラッシュメモリの種類や回路設計、コントローラの性能が大きく影響します。
用途の例としては、スマホの内部ストレージ、ノートパソコン(関連記事:ノートパソコンの激安セール情報まとめ)のSSD、外付けのUSBメモリ、デジタルカメラの記憶媒体などが挙げられます。技術的な観点からは、容量・速度・耐久性・価格のバランスを見て選ぶのが基本で、初心者には“容量は大きいほど良い”“耐久性が高いモデルほど信頼性が高い”と覚えておくと良いでしょう。
要するに、NAND型フラッシュメモリは私たちの生活の中で最も身近な非揮発性記憶装置の一つであり、現代の多くの電子機器の「頭脳」として働く重要な部品です。正しく選んで使えば、データを長く安全に保てます。
nand型フラッシュメモリの同意語
- NAND型フラッシュメモリ
- 非揮発性のデータ記憶装置で、NAND型のセル構造を採用したフラッシュメモリ。主に長期保存や大容量データの保存に使われる
- NAND型フラッシュ
- NAND型のフラッシュメモリの略称。非揮発性でデータを長期間保存できる記憶装置。
- NANDフラッシュメモリ
- NAND型フラッシュメモリと同義の表現。NANDタイプのフラッシュメモリ。
- NANDフラッシュ
- NAND型フラッシュメモリの口語・略称表現。非揮発性のデータ記憶装置。
- NANDメモリ
- NAND型のメモリ全般の略称。NAND構造を用いる不揮発性メモリを指すことが多い。
- NAND型メモリ
- NAND型のセル構造を採用した不揮発性メモリの総称。データを電気的に長期間保持する。
- NAND型不揮発性メモリ
- 不揮発性メモリの中でもNAND型のアーキテクチャを指す名称。
- NAND系フラッシュメモリ
- NAND系統のフラッシュメモリ。NAND構造を用いるフラッシュメモリの別称として使われることがある。
- NAND型ストレージ
- ストレージ用途のNAND型フラッシュメモリを指す呼び方。容量の大きい記憶媒体のこと。
- NANDアーキテクチャのフラッシュメモリ
- NANDアーキテクチャを採用したフラッシュメモリの別称。
nand型フラッシュメモリの対義語・反対語
- NOR型フラッシュメモリ
- NAND型フラッシュメモリの対になる別タイプのフラッシュ。セル配置がNOR型で、特定アドレスのデータ読み出しが速いが、書き換えや消去は難しく容量単価も高い。主にコード格納やファームウェアの読み出し用途に適する。
- RAM(揮発性主記憶)
- 電源を切るとデータが失われる揮発性の主記憶。NAND型フラッシュは不揮発性であるのに対し、RAMは作業領域として使われ、データ保持の性質が真逆。
- DRAM
- RAMの一種で、容量が大きく高速だが揮発性。NAND型フラッシュとは用途・設計思想が異なり、主記憶として使われる。
- HDD(磁気ハードディスク)
- 磁気ディスクを用いた機械的ストレージ。データ保持は長期的だがアクセス速度はSSD/NANDより遅く、衝撃耐性も異なる。NAND型フラッシュとは媒体・構造が別の対照となる。
- 磁気テープ
- 長期アーカイブ向けの磁気テープ。大容量・低コストが魅力だがランダムアクセスが苦手で、NAND型フラッシュの即時アクセス性とは性格が異なる。
- 光ディスク(CD/DVD/BD)
- 光学媒体。読み出し速度が遅めで、再書き込みの可否や媒体ごとの仕様が仕様次第。NAND型フラッシュとは全く別の媒体としての対比になる。
- ROM(リードオンリーメモリ)
- 読み出し専用で書き換え不可の不揮発性メモリ。固定されたデータを格納する用途で、NAND型フラッシュの柔軟性とは異なる。
nand型フラッシュメモリの共起語
- 3D NAND
- NANDセルを垂直に積み重ねた3次元構造。2Dに比べて高密度・容量拡張がしやすい。
- セルタイプ
- SLC・MLC・TLC・QLCの4種類のセル構成で、1セルあたりのビット数が異なる。耐久性・容量・コストのバランスを決める要素。
- SLC
- セルあたり1ビットだけ記録する構成。耐久性・信頼性が高いが、同容量の場合は他のタイプより高価になる。
- MLC
- セルあたり2ビットを記録。容量と耐久性のバランスがよく、一般的なSSDで広く使われる。
- TLC
- セルあたり3ビットを記録。容量は大きいが耐久性が低下しやすく、書き込み速度の安定性にも影響することがある。
- QLC
- セルあたり4ビットを記録。容量最大化が可能だが耐久性・速度の点で他より不利になりやすい。
- ページサイズ
- 1ページあたりのデータ量。典型的には4KBまたは8KBなど。読み書きはページ単位、消去はブロック単位で行われる。
- ブロック
- 複数のページをまとめて消去できる最小の単位。消去操作はブロック単位で行われることが多い。
- 消去単位
- データを消去する最小単位。NANDは通常ブロック単位で消去する仕様が一般的。
- 書き込み
- 新しいデータをNANDのページへ記録する操作。多くの場合先に消去を行ってから書き込みを行う。
- 読み出し
- NANDからデータを取り出す操作。読み出しは速さと信頼性が重要。
- ECC
- エラー訂正コード。データ転送中の誤りを検出・訂正してデータの信頼性を保つ。
- ウェアレベリング
- 書き込みをブロック間で均等に分散させ、特定ブロックの劣化を抑える技術。寿命を延ばす要素。
- ガベージコレクション
- 無効になったページを整理して空きブロックを再利用可能にするSSD内部の整理作業。
- FTL
- フラッシュ翻訳層。論理アドレスを物理ページへ対応づけ、書き換えの管理と寿命対策を行うソフトウェア層。
- コントローラ
- NANDを制御する半導体チップ。エラー訂正、ウェアレベリング、マッピングなどを担当。
- DRAMキャッシュ
- NANDコントローラやNAND内に搭載されるDRAMキャッシュ。データの読み書きを高速化する役割。
- マルチプレーン
- 1つのNANDチップ内で複数のプレーンを同時に操作して並列処理を実現する機能。性能向上につながる。
- パラレル処理
- 複数のページを同時に処理することで読み書き速度を向上させる設計要素。
- バッドブロック
- 不良ブロックのこと。データの再配置(リマップ)により使用可能なブロックへ置換される。
- TBW
- Total Bytes Writtenの略。寿命の目安となる総書き込み容量の指標。
- DWPD
- Drive Writes Per Day。容量あたり1日あたりの耐久書き込み量を示す指標。
- P/E回数
- Program/Erase回数。セルを書き換える回数の上限の目安。
- 容量
- NANDの総容量。実使用容量はフォーマットやパリティ領域を含めて表現されることがある。
- 耐久性
- 長期間の書き込み耐性の総称。P/E・TBW・DWPDなどの指標で表される。
- データ保持
- 電源を供給しなくてもデータを保持できる期間。温度環境などの条件によって変化する。
- ONFI
- Open NAND Flash Interfaceの略。NANDとホスト間の規格化されたインターフェース。
- Toggle NAND
- 別のNANDインターフェース規格。ONFIと並ぶ主要な規格の一つ。
- NOR型フラッシュ
- 別種のフラッシュメモリ。読み出しはランダムアクセスが得意だが、NANDと比べて容量単価が高い傾向にある。
- マルチプレーン構造
- 1つのチップ内で複数のプレーンを同時に操作して性能を向上させる構造。
nand型フラッシュメモリの関連用語
- nand型フラッシュメモリ
- 非揮発性の半導体メモリの一種。電源を切ってもデータを保持し、主にSSD・USBメモリ・SDカードなどに使われ、読み書きはページ単位、消去はブロック単位で行います。
- NAND型フラッシュメモリ
- NAND型のフラッシュメモリで、データをページ/ブロック単位で読み書きし、ブロック単位で消去します。
- 2D NAND
- 平面的にセルを配置した従来タイプのNAND。コストは低いが密度にも限界があります。
- 3D NAND
- セルを垂直方向に積層して高密度化したNAND。容量増加・耐久性・省電力性の改善を実現します。
- 浮遊ゲート型セル
- セル内に電荷を蓄えてビットを表現するセル構造。従来のNANDで多く使われます。
- チャージトラップ型セル
- 絶縁体内部に電荷を蓄えるセル構造。3D NANDで普及しやすく、耐久性向上の効果があります。
- SLC (Single-Level Cell)
- セル1つにつき1ビットを格納。高速・高耐久だが容量・コストが限定的。
- MLC (Multi-Level Cell)
- セル1つにつき2ビットを格納。容量とコストのバランスが良いが耐久性は下がることが多い。
- TLC (Triple-Level Cell)
- セル1つにつき3ビットを格納。高密度だが耐久性・性能は抑えられがち。
- QLC (Quad-Level Cell)
- セル1つにつき4ビットを格納。容量は最大化するが耐久性・性能の制約が大きいことが多い。
- ページサイズ
- NANDの読み書きの基本単位。代表的には2KB〜4KB程度、製品世代で異なります。
- ブロックサイズ
- データを消去する最小単位。一般に64〜256ページ程度のブロックが多いです。
- FTL (フラッシュ翻訳層)
- 論理アドレスと実データ位置を対応づける層。ウェアレベリングやGCの前提となります。
- ウェアレベリング
- 書き換え回数をブロック間で均等に分散させ、特定のブロックの劣化を防ぐ機構。
- ガーベジコレクション
- 不要データを整理して空きページを確保する処理。GCがないと長期性能が低下します。
- ECC (エラー訂正コード)
- データの誤りを検出・訂正して信頼性を高める技術。BCH・LDPCが主流です。
- BCH
- 古典的なエラー訂正コードの一種。中程度のエラー訂正能力を提供します。
- LDPC
- Low-Density Parity-Check。高い訂正能力を持ち、大容量NANDで主流のECCです。
- BBM (Bad Block Management)
- 不良ブロックを検出・管理して使用対象外とする機構。
- 不良ブロックマネジメント
- BBMと同義で、不良ブロックの管理全般を指します。
- 書き込み増幅 (Write Amplification)
- 実際に書き込むデータ量より内部の書き込みが多くなる現象。GC・ウェアレベリング・TRIMの影響を受けます。
- P/E回数 / P/Eサイクル
- プログラム/消去の繰り返し回数の上限。セルの劣化指標として用いられます。
- データ保持時間
- データを保持できる期間。温度条件や世代によって異なります。
- 読み出しディストラブ (Read Disturb)
- 読み出し時に近接セルへ影響して誤りが生じる現象。
- 書き込みディストラブ (Program Disturb)
- 書き込み時に近接セルへ影響して誤りが生じる現象。
- 消去ディストラブ (Erase Disturb)
- 同一ブロックの消去操作が隣接セルへ影響する現象。
- ONFI (Open NAND Flash Interface)
- NANDチップとコントローラ間の通信規格を統一する標準。
- Toggleモード
- NANDの高速転送モードの一つ。通信効率を高めます。
- 3D NANDの層数 (Layer Count)
- 3D NANDのセル層の数。層が多いほど密度が高くなります(例: 96層、128層など)。
- オーバープロビジョニング (OP)
- 実使用容量以外に確保する予備領域。性能安定性と durability の向上に寄与します。
- TRIM
- OSから未使用ブロックをガベージコレクション対象として知らせる命令。長期性能維持に寄与します。
- ホストメモリバッファ (HMB)
- 一部SSDでホストPCのRAMをバッファとして使用する機能。
- Pseudo-SLCキャッシュ
- MLC/TLCデータを一時的にSLCモードで書き込み、性能と耐久性を向上させるキャッシュ機構。
- コントローラ
- NANDの動作を制御するハードウェア。読み書き・GC・ウェアレベリング・エラー訂正を統括します。
- ファームウェア
- コントローラの内部ソフトウェア。機能性・安定性・耐久性を大きく左右します。
- 実効容量と表示容量の差
- OSに表示される容量と実際に使用可能な容量の差。パリティやオーバーヘッド分が影響します。
- MTTF / MTBF
- 平均故障時間。信頼性の指標として使用され、環境条件で変動します。
nand型フラッシュメモリのおすすめ参考サイト
- NAND型フラッシュメモリとは | KIOXIA - Japan (日本語)
- NAND型フラッシュメモリ (なんどがたふらっしゅめもり) とは?
- SSDに使われている「NAND」とは?フラッシュメモリの基礎知識
- NAND型フラッシュメモリ (なんどがたふらっしゅめもり) とは?
- NAND型フラッシュメモリーとは 大容量化しやすく - 日本経済新聞
- フラッシュメモリとは?種類やSSD・HDDとの違いを解説 - NetApp



















