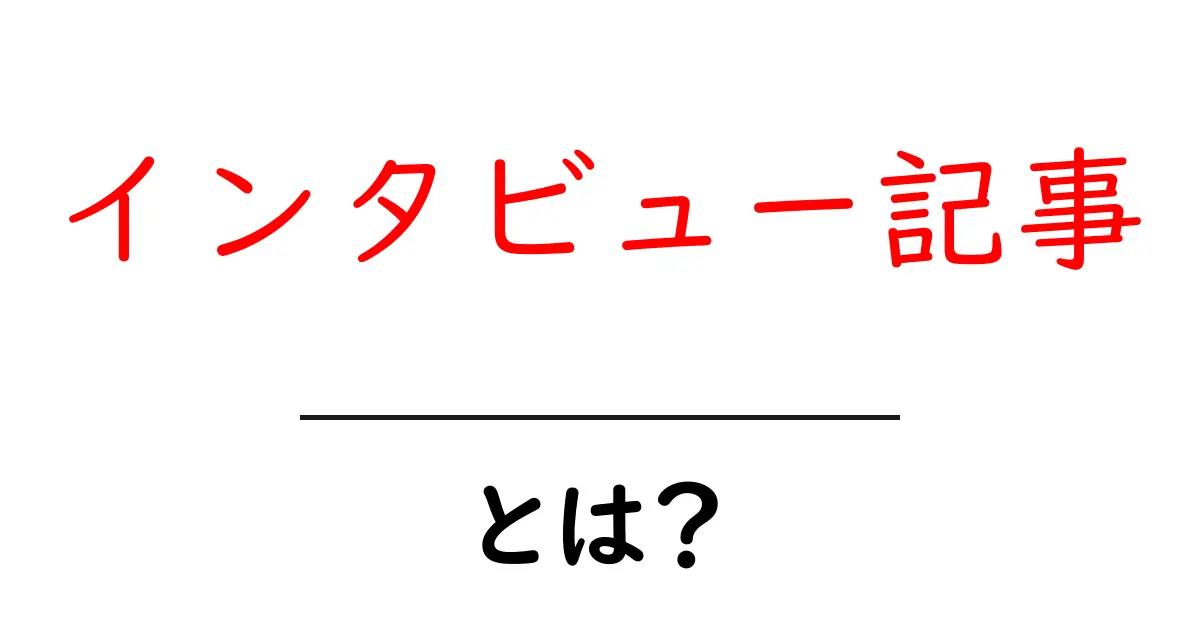

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
インタビュー記事とは何か
インタビュー記事とは、取材をもとに人の話を読者に伝える文章のことです。記者は話し手から情報を引き出し、要点を整理して読みやすい形にします。ニュース記事と比べると、話し手の言葉のニュアンスや考え方が生きてくるのが特徴です。
インタビュー記事を読むと、専門家の考え方や体験を直接知ることができます。読み手は人物の表情や言い回しから、その人がどんな状況で、どう感じたのかを想像しやすくなります。
基本の目的
目的は大きく三つあります。第一に情報を伝えること、第二に視点を広げること、第三に読者の共感を呼ぶことです。インタビュー記事は何かを教えるだけでなく、読者の心に残る言葉を選ぶことが大切です。
基本の構成
導入部分には話者の紹介とテーマの設定を置きます。次に質問と回答を中心に本文を展開します。最後に結論や意味、今後の展望を短くまとめます。
実例と注意点
実例として、企業の新製品を紹介するインタビュー記事では、製品の特徴だけでなく開発の背景や課題も取り上げます。注意点は、事実と意見を区別すること、誤解を招く引用を避けること、そして相手の言葉をそのまま伝えるのではなく要約して伝えることです。
インタビュー記事の同意語
- インタビュー記事
- 質問を軸に登場人物の発言を中心に構成した記事。取材した内容を整理して公開する、一般的な形のインタビュー形式の記事です。
- 対談記事
- 2名以上の登場人物が対話する形式で進行する記事。相互の意見交換を通じてテーマを掘り下げます。
- 対談形式の記事
- 対談の進行形式をとる記事。会話を中心に情報を伝えるタイプの文章です。
- 座談会記事
- 複数の登場人物が座談会のように話す内容を記事にしたもの。多角的な視点を示します。
- 取材記事
- 取材を実施して得た情報と発言をもとに書く記事。事実関係を重視して伝えます。
- 取材レポート
- 取材の要点を整理して報告する形式の記事。速報性より客観的な情報整理が中心です。
- インタビュー特集
- 特定のテーマや人物について深掘りする連載形式のインタビュー記事。
- Q&A記事
- 質問と回答の形式で構成された、要点が分かりやすい記事タイプ。
- 質問応答記事
- 質問と回答の流れで進む、読者の疑問に焦点を当てた記事。
- 人物インタビュー記事
- 特定の人物の考え方・経験・背景を深掘りする、人物中心の記事。
- インタビュー形式の記事
- 質問と回答を軸にした、インタビュー形式の標準的な記事構成。
インタビュー記事の対義語・反対語
- 解説記事
- 事実背景や仕組み、用語の意味などを分かりやすく説明する記事。質問形式のインタビューとは異なり、筆者の説明中心で構成されます。
- 論説記事
- 筆者の主張や結論を論理的に展開する意見記事。対話形式ではなく、論旨と根拠を明確に示すことを重視します。
- 社説
- 新聞社などの組織的な見解を公式に述べる記事。読者との対話よりも組織の立場・意見を伝える性質が強いです。
- コラム
- 著者の個人的な見解や経験を自由な文体で綴る連載記事。筆者の声が前面に出ることが多く、質問形式は少ないです。
- 批評記事
- 映画・本・音楽などを評価・分析する記事。著者の評価観点や批評視点を中心に展開します。
- 体験談
- 筆者自身の体験や体験談を語る記事。インタビュー形式を前提とせず、語り口が主役になります。
- エッセイ
- 個人的な感想・考えを自由に綴る文章。取材を前提とせず、思考の流れを重視します。
- プレスリリース
- 企業や団体が公式に発表する公的な文章。ニュース性はあるものの、取材を伴わない発表文が中心です。
- ガイド記事
- 特定の手順や使い方を分かりやすく解説する実務的記事。実践的な情報提供を目的とします。
- 総括記事
- テーマ全体を整理・要点をまとめる解説・総括型の記事。複数情報の統合が特徴です。
- 学術論考
- 研究的な分析・論考を展開する学術寄りの記事。専門的な視点で論理を積み上げます。
- 取材なし記事
- 取材を前提とせず、筆者の解説・体験・主張で構成される記事。対話性は抑えられています。
インタビュー記事の共起語
- 質問
- インタビューで使われる問いのリスト。読者が知りたい点を引き出すための設問設計と例を含む
- Q&A形式
- 質問と回答をそのまま並べる形式。読みやすさや引用の明確さを重視する際に用いられることが多い
- 対談
- 複数人が対話する形式のインタビュー記事。対比や相互作用を活かして深掘りする表現が特徴
- インタビュアー
- インタビューを実施する記者や司会者。質問設計・進行・相手の話を引き出す役割を担う
- インタビュー対象
- 話者・被インタビュー者。専門家・著名人・現場の当事者など、取材の中心となる人物
- 取材
- 現場で情報を集める取材作業。背景情報や事実確認の基礎を作る活動
- 取材ノート
- 現場でのメモや要点を整理したノート。後の記事構成の根拠となる情報を蓄積する
- 要点
- 記事で伝えたい核心ポイント。読者に伝えたい重要事項の要約
- 要約
- 長い回答や発言を要点だけに整理した短いまとめ
- 見出し
- 記事の核となる見出し。クリック率とSEOに影響する重要な要素
- 導入文
- リード文とも呼ばれる、読者を引き込む導入部の表現
- リード
- 導入部の別称。記事の要点や背景を簡潔に伝える最初の段落
- 構成
- 記事の段落やセクションの配置。論理的な流れと読みやすさを決定する設計
- 文字数
- 記事全体の文字量。読みやすさとSEOのバランスを取る指標
- 字数
- 文字数の別表現としての用語。文字数と同義で使われる場合がある
- 引用
- インタビュー内での発言をそのまま引用する表現。信頼性を高める要素
- 写真
- 記事を補足するビジュアル。人物像や現場の雰囲気を伝える役割
- キャプション
- 写真の説明文。文脈を補足し、読みやすさを補完
- 動画
- 記事と連動する動画コンテンツ。視覚・聴覚で情報を伝える補助素材
- ポッドキャスト
- 音声版の配信。移動中や作業中など、別の読み方を提供する要素
- OGP
- SNSでの記事表示を最適化するOpen Graphデータ。タイトル・画像・説明を設定
- メタデータ
- 検索エンジンに表示されるタイトル・説明・キーワードなどの情報
- SEO対策
- 検索エンジンでの可視性を高める実装とライティングの工夫全般
- 文字起こし
- 音声を文字に起こす作業。全文または要点の掲載により検索性を高める
- 公開日
- 記事の公開日。新鮮さや更新履歴と関連する重要情報
- 掲載日
- 公開日と同義で用いられることがある表現。媒体や記事の運用方針次第で使い分け
- 著者
- 記事を書いた人の名前・プロフィール。信頼性と著作権の観点にも関わる
- 編集部
- 編集方針や品質管理を担当する部門。監修や校正を行う役割
- 背景情報
- 話者の背景・文脈・実績など、理解を深めるための補足情報
- ストーリーテリング
- 物語性を持たせた伝え方。読者の興味を引き、伝えたいメッセージを効果的に伝える技法
- 信頼性
- 事実確認・出典の明示・整合性の確保を通じた記事の信頼度
- 客観性
- 複数の視点や事実に基づく公正な伝え方。偏りを避ける工夫
- 編集方針
- トーン・スタイル・目的・読者層を統一する運用方針
- 現場感
- 現場の雰囲気・緊張感・生々しい描写を伝える表現
インタビュー記事の関連用語
- インタビュー記事
- 特定の人物の言葉や体験を中心に、質問と回答を通して情報を伝える記事形式。導入・本文・結論の構成を取ることが多い。
- インタビュー
- 取材対象者と対話を通じて情報を引き出す手法。質問を準備して行う取材活動そのものを指すことが多い。
- 取材
- 情報源を現場で直接取材する行為。書き起こしや編集の前段となる。
- 書き起こし
- 録音した音声を文字に起こす作業。発言者の区分や語気もできるだけ正確に表記することが多い。
- 文字起こし
- 書き起こしと同義。口述を文字データへ転写する作業。
- 録音
- 取材時に音声を記録する作業。後の書き起こし・検証に必須。
- 音声品質
- 録音の音声の鮮明さ、ノイズ、話速など。読みやすさに直結する要素。
- 質問リスト
- 事前に用意する質問の一覧。取材の軸を決め、漏れを防ぐために作成する。
- 質問テンプレ
- 質問のひな型。ジャンル別に用意することで効率を上げる。
- 質問作成のコツ
- 具体的・明確・短い文で質問を設計し、回答を引き出しやすくする工夫。
- 導入文
- 記事の冒頭で要点を伝え、読者の関心を引く文。
- リード文
- 導入文と同義で、本文の要点を要約する文章。
- 本文構成
- インタビュー回答をどう展開するかの段落構成。読みやすさを意識する。
- 見出し
- 各セクションのタイトル。読者の興味を引き、SEOにも寄与する。
- 見出しの階層
- H1, H2, H3 などの見出しレベルの使い分け。情報の階層を示す。
- サブ見出し
- H2以下の補足タイトル。読みやすさとSEOを高める。
- リード
- 導入文の別呼称。要点を端的に伝える短文。
- 結論
- 記事の締めの要点や今後の展望をまとめる部分。
- 要約
- 記事全体の要点を短くまとめた段落または箇条書き。
- 引用
- インタビュー内の発言を引用符で示し、出典を明示する表現。
- 引用符
- 発言部分を引用符で囲う表記(例: 発言の一部を引用する際に用いる)。
- 出典
- 情報の出典を明記すること。信頼性の向上につながる。
- 著作権表示
- 画像や長文引用の著作権に関する表示。
- 著作権処理
- 引用・転載の範囲やクレジットの付け方を管理する。
- ファクトチェック
- 事実関係の検証。誤情報を避けるための工程。
- 事実確認
- 発言やデータの正確性を再確認する作業。
- 誤情報対策
- 誤情報の混入を防ぐためのガイドラインとチェックリスト。
- 編集方針
- 記事のトーン、目的、読者層に合わせた編集の指針。
- トーン
- 文章の雰囲気や話し方のスタイル。公正・親しみ・専門性などを決定する。
- 語り口調
- インタビューの語り口の具体的な表現スタイル。
- 語彙選定
- 専門用語の扱い方、読みやすさを意識した言葉の選定。
- 用語解説の併記
- 専門用語には簡易解説を併記する工夫。
- 表現の透明性
- 事実と解釈を明確に分け、過度な誇張を避ける表現。
- 構成案
- 記事の全体設計のひな形、アウトラインの前提となる案。
- アウトライン
- 記事の骨組み、見出しと段落の配置を決める設計図。
- リードと本文のつなぎ
- リード文と本文が自然につながるような設計。
- 事実関係のチェック
- 事実と意見を混同しないよう検証する作業。
- 出典の明示
- 参照した資料や人名・組織などを明記すること。
- プライバシー配慮
- 個人情報の扱いを慎重にする方針。
- 倫理審査・同意
- 取材の倫理的側面を確認し、同意を得るプロセス。
- 同意書・取材同意
- 取材・掲載の同意を文書で取得する手続き。
- インタビュアー
- 質問を投げかけ、回答を引き出す人。編集者・記者・ブロガーのこと。
- インタビュワー
- 表記揺れの別表現。どちらかを採用する。
- クリエイターインタビュー
- 作家・デザイナー・YouTuberなど創作者へのインタビュー。
- 企業インタビュー
- 企業の担当者へのインタビュー。事業戦略や社風などを掘り下げる。
- プロフェッショナルインタビュー
- 専門職の視点を深掘りするインタビュー。
- プロフィールインタビュー
- 人物の経歴・背景・価値観を掘り下げる形式。
- 対談
- 二者以上の対話形式で進むインタビュー記事。
- 対談記事
- 対談の内容を記事として編集したもの。
- 取材レポート
- 現場の状況・取材の過程をレポート形式で伝える記事。
- 事例インタビュー
- 特定の事例を通して体験談を伝える形式。
- Q&A形式
- 質問と回答を縦に並べる定番形式。
- 質問リストの公開
- 読者向けに質問リストを公開する工夫。
- SEO対策
- 検索エンジンでの露出を高めるための最適化。
- キーワード選定
- 狙いたい検索語を選ぶ作業。競合分析も含む。
- メタディスクリプション
- 検索結果に表示される要約文。魅力的に要点を伝える。
- タイトル最適化
- 魅力的でクリックされやすいタイトルを作る。
- 見出しタグの活用
- 見出しに適切なタグを使い、構造化する。
- URL構造
- SEOとユーザビリティの観点から適切なURLを設計。
- パーマリンク
- 記事の固定URL。簡潔で意味のある語で構成する。
- サマリー
- 記事全体の要点を短くまとめた要約。
- スニペット最適化
- 検索結果での表示を工夫する要約文・構造化データ。
- 画像・写真挿入
- 理解を深めるための写真・図版の活用。
- 画像クレジット
- 写真の出典・著作者を明記する。
- ビジュアル要素
- 図表・写真・キャプションで視覚情報を補う。
- レイアウト
- 読みやすさを高める段組・フォント・行間の設計。
- 読みやすさ
- 読者がスムーズに読めるよう文章を工夫する。
- 文字数・ボリューム感
- 適切な文字数・段落数・改行のバランスを取る。
- 引用の整合性
- 引用部分の表現と原文の意味を一致させる。
- 署名・著者情報
- 記事の著者名・所属を明記する。
- 公開日
- 記事を公開した日付。
- 更新日
- 記事を更新した日付。



















