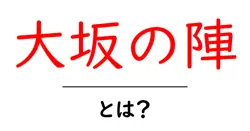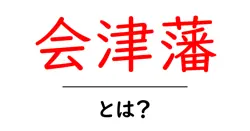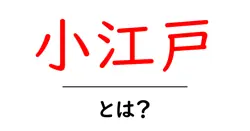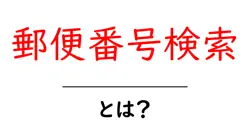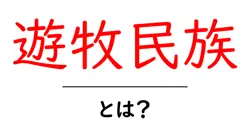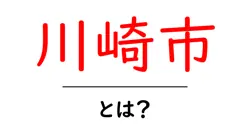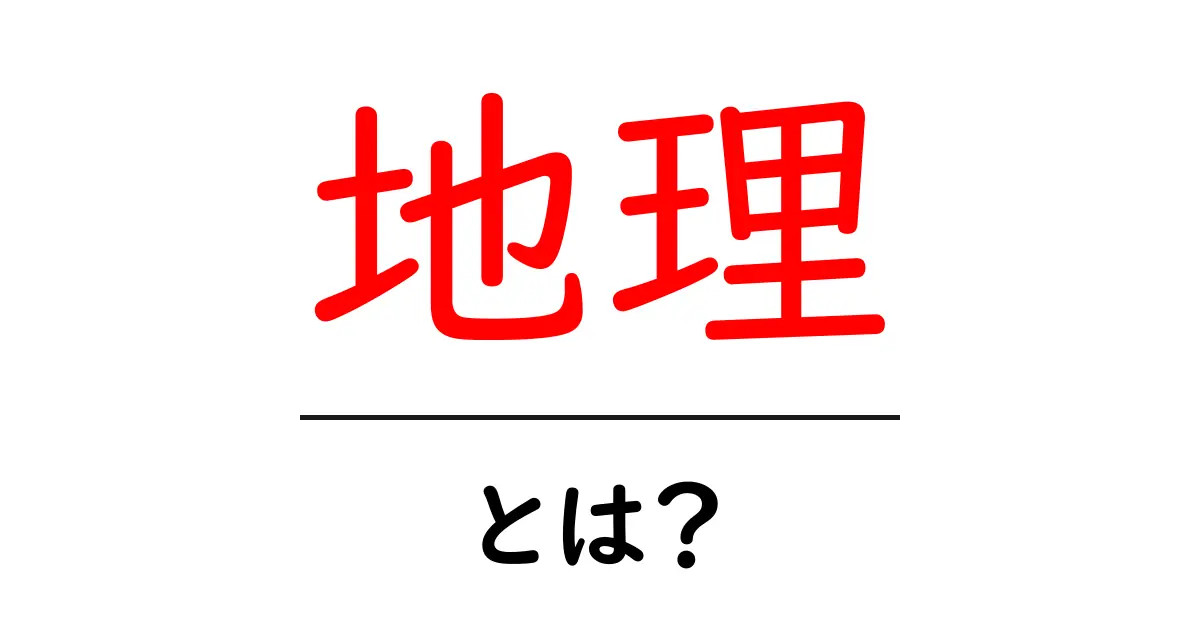

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
地理・とは?
地理とは、場所と人・自然の関係を研究する学問です。世界がどのようにつながっているのか、私たちの生活にどんな影響を与えるのかを、地図やデータを使って理解します。地理は単なる地図の読み方だけでなく、気候、地形、人口、経済、文化など、さまざまな要素がどう結びついているかを考える学問です。中学生くらいの年齢でも、日常の「今日はどのくらい暑いかな」「東京と大阪の違いは何だろう」といった身近な疑問から、地理の世界を楽しく学ぶことができます。
地理の大きな分野
地理には大きく分けて自然地理と人文地理があります。自然地理は山や川、気候、地形など地球の自然現象を研究します。人文地理は人口の動き、都市の成り立ち、文化や経済の地域差など人間社会の特徴を扱います。また、現代の地理では地理情報学(GIS)と呼ばれるデジタル地図の作り方・活用方法も重要です。GISを使えば、地図の上にデータを重ねて、地域の問題を分析できます。
地理用語の基礎
地理を学ぶときによく出てくる基本用語を、簡単に知っておきましょう。
- 緯度(Latitude)
- 地球上の位置を、赤道からの角度で表す基準。北緯と南緯に分かれます。
- 経度(Longitude)
- 地球を縦に区切る基準。本初子午線を0度として東西に測ります。
- 赤道
- 地球の中心を横切る想像上の線で、緯度0度を示します。
- 本初子午線
- 経度0度の基準線。イギリスのグリニッジを通ります。
- 北半球 / 南半球
- 赤道を境に分かれた地球の2つの半球。季節や気温の違いは半球によって異なります。
地理を学ぶと何が楽しくなるのか
地理を学ぶと、世界の成り立ちや地域の特徴を理解でき、旅行の計画やニュースの背景理解にも役立ちます。例えば、なぜある地域は夏に乾燥して冬に雨が多いのかを知ると、気候の違いが生活にどう影響するかを想像できます。人々がなぜ異なる習慣を持つのか、経済活動がどのように場所に影響を与えるのか、そうした疑問に対して地図とデータを使って答えを探すのが地理の楽しさです。
地理の学習ポイント
1. 地図を読み解く力:縮尺、方位、図例を理解して、現実世界の情報と地図上の情報を結びつけます。
2. データの活用:気温・降水量・人口などのデータを読み取り、グラフや表で比較します。
3. 地域のつながりを考える:地理は世界がどうつながっているかを示します。交通、貿易、環境問題など、地域間の関係性を考える視点を育てます。
簡単な表でおさらい
このように、地理は「場所と人・自然の関係を明らかにする科学」です。身近な疑問から世界の仕組みまで、地図とデータを使って解き明かすことができます。地理の学習を始めると、世界を新しい視点で見る力が身についていきます。
地理の関連サジェスト解説
- 塵 とは
- 塵 とは、私たちの周りに存在する小さな粒の総称で、日常語では“ほこり”や“ちり”と呼ばれます。漢字としては塵はほこりや汚れを意味し、音読みはジン、チン、訓読みはちりです。「塵も積もれば山となる」などのことわざに登場し、身近な語として覚えやすい言葉です。さらに「微塵(みじん)」という語もあり、非常に小さな粒を指します。みじんは日常会話でも耳にすることが多い表現です。使い方の例としては、掃除の場面で「塵を払う」「塵を取り除く」といった言い方をします。意味はほこりをなくすことです。文章や作文では、塵を比喩的に使って「穢れ」や「煩悩の象徴」とする場合もあり、文学的な表現として使われることがあります。また、仏教や哲学の文献では「六塵」という語が出てくることがありますが、これは感覚対象を意味する難しい語なので、日常の会話では出会う機会が少ない語です。まずは基本の読み方(ちり、ジン、チン)と意味を押さえること、そして身近な語としての使い方を覚えることから始めましょう。掃除の話題や文章を書く際には、塵という語がもつ“小さな粒の集合”というイメージを思い出すと、適切な表現を選ぶ助けになります。
- チリ とは
- チリ とはには主に2つの意味があります。1つは国のチリ、もう1つは唐辛子のことを指す言葉としてのチリです。この記事ではこの2つをやさしく説明します。国のチリについて:チリは南アメリカにある国です。地図で細長い形が特徴です。北にはペルー、東にはボリビアとアルゼンチン、南には広い海と南極近くまであります。首都はサンティアゴです。公用語はスペイン語、通貨はチリペソです。面積は日本より少し小さく、人口は約2000万人程度です。気候は場所によって大きく違います。北は乾燥しています。中央は温暖で雨が少ないです。南は寒さと風が強い地域が多いです。アンデス山脈が国の東側を走り、太平洋に面した長い海岸線があります。観光地としてはワインの産地、山の景色、海の景色、都会の文化施設などが人気です。経済は鉱山(特に銅)、漁業、農業が中心です。唐辛子のチリについて:チリは辛味の材料として世界中の料理に使われます。乾燥したもの、粉末状のチリパウダー、ペースト状のチリソースなどいろいろな形があります。料理にピリッとした辛さと香りを加え、味を引き締めます。辛さの強さは品種で違います。栄養面ではビタミンCが含まれているものもあり、適量を使えば体に良いとされています。チリは家庭菜園でも育てやすく、太陽の光と暖かい気候を好みます。このように、文脈で「チリ」が国の話か、唐辛子の話かを見分けることが大切です。学校の授業やニュース、料理のときには「チリ とは」というキーワードが意味を混同しないよう役立ちます。
- チリ とは 食べ物
- チリ とは 食べ物?と聞くと、たいていの人は「辛いもの」や「唐辛子」を思い浮かべます。実はチリは1つの果実の総称で、さまざまな品種を指します。英語では chili pepper、日本語では唐辛子やチリと呼ばれ、緑色のまだ熟していないものから、真っ赤に熟したものまで形も味も違います。チリは主に熱さ(辛さ)の成分であるカプサイシンを含みますが、品種によって辛さが大きく異なります。辛さは「スコヴィル値」という数値で表され、同じ長さのものでも品種によって数値が変わります。料理には新鮮なもの、乾燥したもの、粉末状のチリパウダー、ペースト状のソースなど、いろいろな形で使われます。新鮮なチリはサラダや炒め物、ピクルスに入れると風味が増します。乾燥チリは煮込み料理の香りづけや、カレー・スープのベースとして重宝します。粉末チリパウダーはカレーや煮物、ファヒータなどのごちそう作りに便利です。チリを使うと料理にピリッとした辛さと香りが加わり、体を温める効果があると言われていますが、子どもには辛すぎる場合もあるので、量を調整したり、甘い野菜と合わせて使うとよいです。取り扱いには注意点もあります。乾燥チリや粉末は目に入ると刺激が強いので手袋をすること、切るときは手をよく洗い、目をこすらないようにしましょう。食べ物としてのチリは、太陽がいっぱいの地域や中南米、アジアの料理で広く使われてきました。日本でもメキシコ料理やエスニック料理の店でよく見かけるようになり、家庭料理にも取り入れやすくなっています。栄養面では、ビタミンCが多いことや、カプサイシンには代謝を高めるといった話もありますが、食べ過ぎは体が熱くなりすぎることもあるので注意しましょう。初心者はまず辛さが控えめな品種から始め、徐々に辛さに慣らしていくのがおすすめです。
- チリ とは 車
- このページでは、キーワード「チリ とは 車」について、中学生にも分かるように解説します。まず「チリとは」について説明し、続いて「車とは」について説明します。最後に両方を組み合わせた検索意図に対応する読み方のコツを紹介します。チリとは何かチリは南アメリカにある国です。正式名称はチリ共和国で、首都はサンティアゴ。日本語で「チリ」と呼ばれ、スペイン語圏の国として長い海岸線と山が特徴です。地理的には長く細い形をしており、太平洋に面しています。公用語はスペイン語、通貨はペソです。観光地や歴史、自然が豊富で、地理や文化の話題としてもよく取り上げられます。車とは車は人を運ぶ乗り物の一つで、私たちの日常生活でよく使われます。エンジンや電動モーターで動き、タイヤ・ブレーキ・ハンドルなどの部品で走ります。車には乗用車、トラック、バス、電気自動車などさまざまなタイプがあります。安全のためには、運転免許・交通ルール・点検整備が大切です。チリ とは 車 の意味づけと使い方このキーワードは、チリと車という2つの語を同時に扱う場合に使われることがあります。初心者向けの解説記事では、まずチリの基本情報と車の基本情報を別々の段落で分けて説明し、読者がそれぞれを理解できるようにします。SEOのコツとしては、両方の語を自然に結びつける例文を用意し、見出しと本文で一貫性を保つことです。よくある質問- チリとは何ですか?- 車とは何ですか?- 「チリ とは 車」はどう使えばよいですか?この記事を読めば、チリの基本と車の基本を分かりやすく理解でき、検索者の意図に合わせた記事の作り方も学べます。
- ちり とは 建築
- ちりとは、もともと日本語で「ほこり・粉塵」を指す言葉です。建築の現場では、コンクリートの粉、木材の削りカス、石灰の微粒子など、さまざまなちりが発生します。これらのちりは空気中を漂い、作業員の健康に影響を与えるだけでなく、完成後の部屋の美観や内装の仕上がりにも影響します。そのため、建築現場ではちりを管理することがとても大事です。効果的な対策には、現場の水かけ作業(ウェット工法)や機械式の集塵機・排風機の活用、粉じんを吸い取るダストキャプチャ、清掃の頻度を高めること、養生シートで床や壁を保護するなどがあります。作業員はマスクやゴーグル、手袋などの保護具を正しく着用します。さらに、廃材や粉じんの適切な保管・処分も大切です。建築現場だけでなく、完成後の住まいにもちりは影響します。空気がきれいでないとアレルギーの原因になったり、家具の表面に粉がついたりすることがあります。建材を選ぶときは、粉じんの出にくい材料や仕上げ材を検討するのもひとつの方法です。
- 地利 とは
- 地利とは、地理的な条件によって得られる「利点」のことです。天気や地形、交通網、周囲の市場など、場所によって変わる有利さを指します。古くは「天時 地利 人和」という三要素の一つとして語られ、戦略やビジネスの判断材料として使われてきました。地理的な利点には、例えば港や川沿いのアクセスの良さ、商業都市への近さ、主要道路や鉄道の通過点になる立地、資源の近接、人口の多さ、観光地としての魅力などがあります。これらは製品を届けるコストを下げたり、取引先を増やしたり、広告の効果を高めたりします。初心者にポイントを分かりやすく言うと、地利は「どこにいるか」で決まる有利さです。ネット通販でも、配送の早さを競うには配送網が整っている場所が有利ですし、店舗ビジネスでは立地が客の流れを作ります。逆に、山奥の断面的な場所や交通が不便な地域は、他の利点(安い家賃など)で補う必要があります。地理的条件だけで勝つわけではありませんが、事業計画や受注戦略を考えるときに地利を一つの指標として使うと、無駄なコストを減らせます。最後に、現代ではデジタルの力で「地理的な不利」を補える事例も増えています。オンライン市場での配送網の整備や地域性を活かした商品展開など、地利を活かす創意工夫が重要です。
- 治理 とは
- 治理 とは、中国語の語で、社会や組織をどのように整え、運営していくかを指す広い意味の概念です。直訳では「統治」「治理する」という意味になりますが、日本語で同じ語を日常的に使うことは少なく、意味を説明する際には「統治(国や自治体が社会を治めること)」や「管理・規制・解決へ向けた運営」といった言い換えを使います。政治の場面では、政府が法や制度を作って人々の生活を安定させる“治理”が重要です。企業や自治体の場面でも、予算の配分、ルールの設定、トラブルの対応といった“治理”の機能が求められます。IT業界では「IT治理」という言葉もあり、情報技術の活用を通じて組織をどう統治・管理するかを指します。環境問題や都市計画の世界でも、清掃・衛生・資源の使い方を整える意味で“治理”が語られます。つまり治理とは「物事を正しく秩序立てて運営し、問題が起きたときには原因を探り、改善策を実行していく仕組みづくり」のことです。初心者には、まず“統治”と“管理”の両方の意味を押さえ、身の回りのニュースやニュース記事で出てくる例を想像して理解を深めるとよいでしょう。
- 散り とは
- 散り とは、動詞の「散る」の名詞形で、ものが散らばることや花びらが落ちる様子、風に乗って広がる現象を指す言葉です。日常会話では「葉が散る」「花が散る」といった表現を使いますが、文章や説明文では「散り」という名詞を使って現象そのものやその光景を主題にします。例えば桜の季節には「桜の散り際が美しい」という表現を耳にします。このときの“散り”は単なる落下の事象だけでなく、時の移ろい美しさのはかなさといった感情的なイメージも含んでいます。散りの使い方にはいくつかのポイントがあります。まず動詞 散る は「散る」「散らす」「散らばる」などの派生語を作る元の動作を表します。散るは対象が自然に落ちたり崩れたりする動作を意味します。対して 散り はその落ちる現象を名詞として取り上げ、文の主語や目的語として使われることが多いです。たとえば「花の散りを数える」「散りゆく景色を見て心が動く」のように、散り自体を話題にします。季節の風物詩としての散りには、桜だけでなく紅葉や木の葉の散り、花粉の散りなど、さまざまな場面があります。日常生活では庭木の葉の散りや雨風で落ちる花びらの散りを観察することが身近な例です。さらに他の言い方として「散り際」「散りぎわ」といった言葉も覚えておくと、より豊かな表現ができます。語源的には、散るは動作を表す動詞、散りはその動作の結果や様子を指す名詞として使います。語感としては硬すぎず、詩的な響きを持つことが多いので、作文・文章の雰囲気づくりにも役立ちます。最後に、似た言葉との違いにも触れておきます。散ると散らすは逆の動作を示し、散らばるは多くの小さなものが広く広がる様子、散乱は乱雑に散らばる状態を指します。使い分けを意識すれば、散り とは何かをより正しく伝えやすくなります。
- 知里 とは
- 知里 とは、どういう意味の言葉かを一言で答えると、主に日本語の人名として使われる名前の一部である、ということです。日常会話で出てくる一般的な語彙というより、個人を指す固有名詞としての扱いが多いのが特徴です。読み方と由来知里の読み方は字面だけを見るとちさとと読むのが自然ですが、名前として読む場合は人によって読み方が異なることがあります。一般的にはちさとと読むケースが多いです。漢字の意味は知が知ることや知識、里が故郷や街などを表し、組み合わせることで知恵と温かな場所のイメージを伝えやすくなります。使われ方最も多いのは女性の名前として使われるケースです。地名やブランド名、創作作品の登場人物名として使われることもあり、たとえば物語の登場人物名として検索されることもあります。検索時のポイント検索語として知里 とは だけでなく読み方や意味の派生表現も組み合わせて使うと情報が広がります。例として知里 とは 意味、知里 とは 読み方、知里 とは 地名 などがあります。またひらがな表記の ちさと とは なども試してみましょう。日常の例文例文1 彼女の名前は知里です。例文2 学校の掲示板に知里 とは 何かを調べる課題が出ました。SEOのコツ記事内で知里 とはという語を自然に使い、関連語として知里 名前、ちさと 読み方、知里 という名前 のような語を併記すると検索エンジンに理解されやすくなります。読み方のバリエーションを併記することも検索結果の幅を広げます。
地理の同意語
- 地理学
- 地理という学問・学科を指す語。地球表面の場所・空間の分布・自然と人文の相互作用を体系的に研究する分野。
- 地誌
- ある地域の地理・地形・自然環境・人文・歴史的特徴をまとめて扱う語。地理的描写や地域研究の基盤として用いられる。
- 地誌学
- 地誌を研究対象とする学問。地域の地理的特徴や人文・自然の歴史を総合的に理解する分野。
- 地域地理
- 地域ごとの地理要素(気候・地形・資源・人口など)を中心に研究する学問分野。
- 世界地理
- 世界規模の地理現象や地域間の分布・相互関係を扱う分野。
- 地域研究
- 特定の地域の地理・歴史・文化・経済などを総合的に研究する学問領域。地理と深く結びつくことが多い。
- 地理情報科学
- 地理データの収集・管理・分析・応用を扱う現代的な学問分野。GISやリモートセンシングを含む。
- 地図学
- 地図の作成・解釈・地図資料の研究を扱う分野。広義には地理学の補完要素として扱われることもある。
地理の対義語・反対語
- 天文学
- 地球の表面・地域ではなく、宇宙全体の天体や法則を扱う学問。地理が地球上の地形・場所の関係を研究するのに対し、天文学は宇宙を対象とします。
- 心理学
- 人の心・感情・認知・行動を研究する学問。地理が場所・空間の関係を扱うのに対し、心理学は内面的な心の働きを扱います。
- 抽象哲学
- 存在・認識・価値など、具体的な場所への言及を含まない抽象的問題を扱う哲学の分野。地理が現実の地理現象を扱うのに対して、抽象哲学は抽象概念を扱います。
- 抽象数学
- 数・形・構造の抽象的関係を研究する分野。地理が地球の場所を扱う現象の記述に着目するのに対して、抽象数学は現実の地理的事象と距離を離れた概念を扱います。
- 芸術
- 言語・表現・創作を通じて人間体験を伝える分野。地理が場所と空間の現象を分析するのに対して、芸術は感性や経験の表現を重視します。
- 内面的体験
- 自分の感情・意識・主観的体験など、外部の地理的現象とは別の内側の世界を重視する観点。地理の外部・外界の分析と対照的です。
地理の共起語
- 地理学
- 地球の表面の特徴や自然と人間の関係を体系的に研究する学問分野。
- 地理教育
- 学校教育における地理の授業設計や教材開発、学習の促進をめざす分野。
- 地図
- 地理情報を視覚化する図で、場所の位置関係や特徴を示すツール。
- 地形
- 山・谷・平野・河川など、地表の形状と配置を指す地理的要素。
- 気候
- 地域の長期的な天候パターン。地域差を理解する際の重要な要因。
- 天気
- 日々の天候状態。短期的な気象の現象を指す用語。
- 地域
- ある程度の広がりを持つ場所のまとまり。地理学の基本単位。
- 都市
- 人口が集中し、行政・経済の中心となる地域。地理的特徴と課題の対象。
- 人口
- 地域や国家に居住する人の総数と分布。地理分析の基本指標。
- 人口統計
- 人口の構成や推移を統計的に分析する学問・手法。
- 輸送
- 交通網や物流の構造。地理的分布と生活・経済に影響を与える要素。
- GIS
- 地理情報システムの略。空間データを管理・分析して地図を作成・可視化するツール。
- 空間データ
- 位置情報を含むデータ。地理分析の基礎となるデータ形式。
- 緯度経度
- 地球上の位置を表す座標系の基本。位置特定の基礎概念。
- 地域開発
- 地域の経済や社会の持続的発展を目指す計画・活動。
- 都市圏
- 大都市を中心とした広域の地域。人口・経済が集積する区域。
- 地理的分布
- 現象や生物が地理的にどこに分布しているかのパターン。
- 地理的要因
- 地形・気候・水資源・地質など、地域の特徴を決定づける要因。
- 地理認識
- 場所や現象を地理的な視点で捉える理解力。
- 地理概念
- 位置・距離・相関など、地理を理解するための基本的考え方。
- 地理情報
- 場所に関する情報の総称。地図・データ・報告などを含む。
- 地政学
- 政治と地理の関係を研究する学問。国家間の力学や資源の分布を分析する分野。
- 地名
- 場所を示す固有の名称。地理の基本要素。
- 地図作成
- 地図を設計・作成する作業。地図を作る技術・プロセスの総称。
地理の関連用語
- 地理
- 地球表面の場所・現象を空間的につなげて研究する学問。自然地理と人文地理に分かれる。
- 地図
- 地理情報を図として表現する平面図。縮尺・方位・凡例が基本要素。
- 地形
- 地球表面の起伏や形状の総称。山地・平野・盆地などを含む。
- 地形図
- 地形を表す地図で、等高線や等深線などを用いる。
- 地図記号
- 地図上に用いられる記号。道路・建物・自然地物などを表示する。
- 地球儀
- 地球を球体で再現した模型。地理の理解に役立つ。
- 緯度
- 北緯・南緯を示す角度で、赤道を0度とする。
- 経度
- 東経・西経を示す角度で、本初子午線を0度とする。
- 赤道
- 緯度0度の想像上の円。地球を縦に二分する南北の基準線。
- 本初子午線
- 経度0度の線。多くはグリニッジを基準とする。
- 極
- 北極・南極。地球の最北端・最南端。
- 気候
- 長期にわたる地域の天気の傾向。降水量・温度・風などのパターン。
- 気候区分
- 気候の分類体系。例: 熱帯・温帯・乾燥など。 Köppen など。
- 気象
- 日々の天気の状態。気温・降水・風・湿度など。
- 気象観測
- 温度、降水、風速などの気象データを測定・記録すること。
- 気圧
- 大気の圧力。天気の変化に関係する基本要素。
- 降水量
- 降水の総量。雨・雪・雹などの量を測定する。
- 温度
- 空気の寒さ・暖かさを表す指標(摂氏や華氏)。
- 風
- 大気の動き。風速と風向が含まれる。
- 風向・風速
- 風が吹く方向と速さ。風は気象の基本要素。
- 水循環
- 蒸発・凝結・降水・蒸散・地表流など、水が地球全体を循環するしくみ。
- 水系
- 河川・湖沼・湿地など、水の流れを構成するまとまり。
- 河川
- 川の流れ。水系の主たる水路。
- 湖
- 陸地に囲まれた大きな水の集まり。
- 海洋
- 地球上の広大な海の領域。海水と生物を含む。
- 海流
- 海水の大規模な流れ。気温・塩分の違いで生じる。
- 地理情報システム GIS
- 地理データを収集・管理・分析・可視化するソフトウェアと技術の総称。
- 地理情報
- 地理データと地理的な情報の総称。
- 地域研究
- 特定の地域を多角的に研究・分析する学問領域。
- 地域計画
- 地域の発展と土地利用を計画する活動。
- 地域資源
- 自然資源・文化資源・観光資源など、地域が持つ資源。
- 人口地理
- 人口の分布・移動・成長などを地理的視点で研究。
- 都市地理
- 都市の分布・構造・機能を地理的に分析する学問。
- 都市化
- 人口が都市へ集中していく現象。
- 産業地理
- 産業の分布や立地、輸送網との関係を研究。
- 経済地理
- 経済活動と地理的要因の関係を分析する分野。
- 交通地理
- 交通網の配置と地理との関係を研究。
- 観光地理
- 観光資源と地域の関係を地理的に考える分野。
- 環境地理
- 環境問題と地理的要因の関係を扱う分野。
- 自然地理
- 地球の自然現象(気候・地形・水など)を扱う分野。
- 人文地理
- 人間活動(文化・経済・社会)と地理の関係を扱う分野。
- 地誌
- 特定地域の自然・歴史・人間の特徴をまとめた記述・資料。
- 地理教育
- 地理を学ぶ授業・教材作り・学習指導。
- 地理用語
- 地理学で使われる専門語彙の総称。
- GIS技術
- GISの具体的な技術・分析手法・データ処理。
地理のおすすめ参考サイト
- 地理(チリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 12.8 地理って、どんなことを学ぶのか。役に立つ地理とは
- 地理学とはどんな学問?研究内容や学び方などを解説
- 12.8 地理って、どんなことを学ぶのか。役に立つ地理とは
- 地理の語源とは? 地理空間思考の概念、歴史、未来 - エネがえる