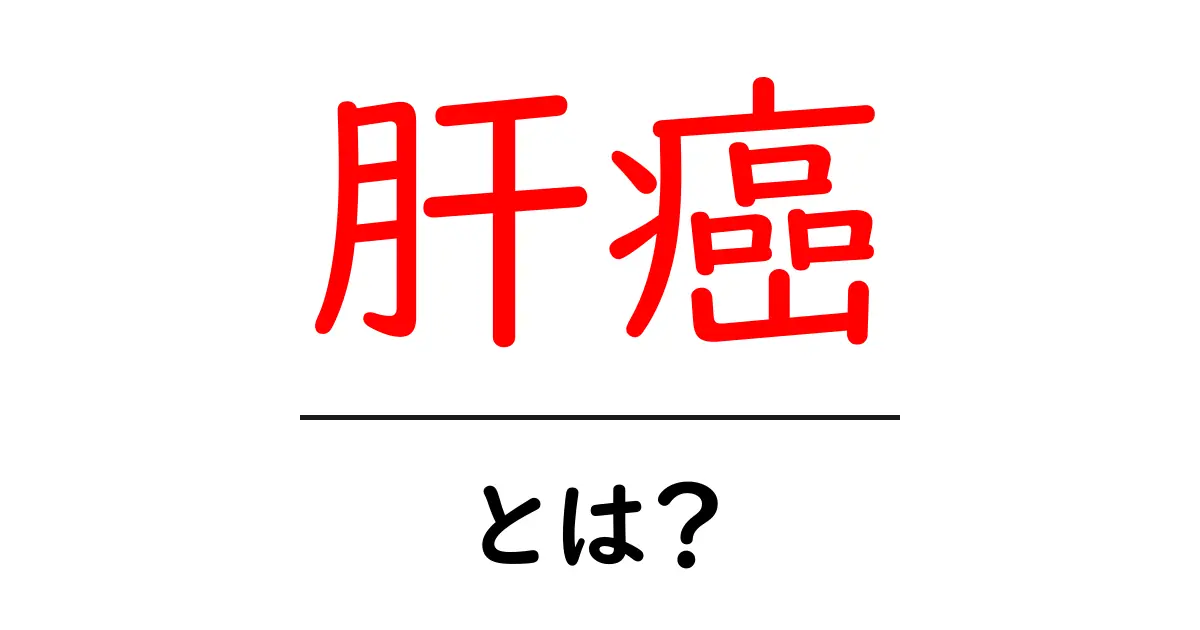

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
肝癌・とは?初心者向けガイド
このページでは「肝癌・とは?」をやさしく解説します。肝癌は肝臓のがんの総称で、成人に比較的多く見られる病気です。名前だけ聞くと難しく感じますが、基本は「肝臓の細胞が異変を起こして増える病気」です。
肝臓と肝癌の関係
肝臓は体の中で最大級の臓器のひとつで、消化の手伝い・解毒・栄養の蓄えなど多くの役割を果たします。肝癌はこの肝臓の細胞が悪性の腫瘍になる状態を指します。早期には自覚症状が少ないことが多く、気づかないうちに進むこともあります。
肝癌の原因
いくつかの要因が関係します。慢性肝炎ウイルス感染、肝硬変、長年の過度なアルコール摂取、肥満、糖尿病などが関連し得ます。これらが長く続くと肝細胞に傷が蓄積され、癌へと進むリスクが高まります。
主な症状
初期には自覚症状がはっきりしないことが多いですが、病気が進むと腹部の腫れ・体重減少・倦怠感・黄疸(目の白い部分が黄ぶくなる)などが現れることがあります。体調の変化を感じたら受診を考えましょう。
診断の流れ
診断は複数の検査を組み合わせて行います。まず血液検査で腫瘍マーカーの値を調べ、次に 超音波、CT、MRI などの画像検査で病変の位置や大きさを確認します。必要に応じて 生検 で細胞を取り、病理診断を行います。
治療の基本
治療法は病気の進行度・肝機能・全身状態により異なります。代表的な選択肢は以下のとおりです。
治療の選択は医師とよく相談し、生活の質や他の病気の有無を含めて決めます。
予防と生活のポイント
肝癌を完全に予防する方法はありませんが、リスクを減らす生活習慣はあります。慢性肝炎ウイルスの治療を受ける、過度なアルコールを控える、バランスの取れた食事と適度な運動、診察の継続が大切です。
受診のタイミングと注意点
体調の変化が少なくても、肝炎の既往や肝硬変がある人は医師の指示に従い定期検査を継続します。痛みがなくても腹部の腫れが続く、体重が急に減るなどの兆候があれば早めの受診が大切です。
検査の表:種類と目的
よくある質問
Q: 肝癌は遺伝しますか?
A: ほとんどの場合、遺伝ではなく生活習慣・感染症などが影響します。個別の家系については医師に相談してください。
結論
肝癌・とは何かを知ることは、早期発見と適切な治療につながります。症状が軽い場合でも定期的な検診が重要です。分からないことがあれば、専門の医師に相談することが最も大切です。
肝癌の同意語
- 肝臓がん
- 肝臓にできる悪性腫瘍の総称。肝細胞癌をはじめとする肝臓のがんを指す一般的な表現です。
- 肝がん
- 肝臓に発生する悪性腫瘍の総称。日常語としてよく使われ、肝細胞癌を含むことが多い表現です。
- 肝臓のがん
- 肝臓に生じた悪性腫瘍のことを指す総称的表現。肝細胞癌を代表とする病型を含む概念です。
- 肝細胞癌
- 肝臓の主な悪性腫瘍で、肝細胞由来の癌。肝臓がんの代表的病型で、英語では hepatocellular carcinoma(HCC)といいます。
- 肝細胞がん
- 肝臓の主な悪性腫瘍の病名。肝細胞癌と意味は同じく、表記揺れの一つです。
- 肝内胆管がん
- 肝臓の胆管から発生する悪性腫瘍。肝癌の一つの病型として扱われますが、肝細胞癌とは別の病型です。
- 肝臓悪性腫瘍
- 肝臓にできる悪性腫瘍の総称。肝癌を含む概念として用いられる場合があります。
肝癌の対義語・反対語
- 健康な肝臓
- 肝臓が健康で、病変や機能異常がない状態のこと。
- 正常な肝機能
- 肝臓の機能が正常に働いている状態を指す。
- 良性肝腫瘍
- 肝臓にできた腫瘍が悪性ではなく良性と判断される状態。
- 非悪性病変
- 肝臓の病変が悪性(癌性)ではないことを示す表現。
- 非癌性病変
- 肝臓の病変ががん性ではないこと。
- がんではない肝臓
- 肝臓の状態が肝癌ではないことを示す口語的表現。
- 悪性ではない肝腫瘍
- 肝臓腫瘍が悪性ではないことを指す表現。
- 肝腫瘍なし
- 肝臓に腫瘍がない状態。
- 肝臓病変なし
- 肝臓に病変が認められない状態。
肝癌の共起語
- 肝細胞がん
- 肝臓の細胞が悪性化してできる肝癌の代表的なタイプ。
- 肝がん
- 肝臓にできる悪性腫瘍の総称。肝細胞がんを指すことが多いですが、他の種類も含むことがあります。
- 肝腫瘍
- 肝臓にできる腫瘍の総称。悪性・良性を含みますが、文脈では肝癌を指すことが多いです。
- 肝硬変
- 慢性的な肝障害が進行して硬くなる状態。肝癌の発生リスクが高まります。
- 肝炎ウイルス B型
- B型肝炎ウイルス感染は肝臓の炎症を引き起こし、肝癌リスクを高めます。
- B型肝炎
- 肝炎ウイルスの一つで慢性化すると肝癌のリスク要因となります。
- 肝炎ウイルス C型
- C型肝炎ウイルス感染は慢性化すると肝硬変・肝癌の原因となります。
- C型肝炎
- C型肝炎ウイルス感染は肝癌リスクの要因です。
- アルコール性肝疾患
- 長期の過度な飲酒による肝臓の障害で、肝癌リスクを高めます。
- NAFLD
- 非アルコール性脂肪肝疾患。肥満などが背景で肝癌リスク要因になることがあります。
- 肝癌の診断
- 肝癌を特定するための検査と判断の過程を指します。
- AFP検査
- 血液中のアルファフェトプロテインの量を調べる検査。肝癌の腫瘍マーカーとして使われることがあります。
- PIVKA-II
- 肝癌の血液マーカーの一つ。診断や治療効果の評価に用いられることがあります。
- DCP
- PIVKA-IIの別名。肝癌の血液マーカーとして用いられることがあります。
- 画像検査
- 肝腫瘍の有無や性質を調べるための検査群です。
- 超音波検査
- 腹部の超音波で肝腫瘍を探したり血流を評価します。
- CT検査
- 造影CTなど、腫瘍の大きさ・位置・広がりを詳しく見る画像検査です。
- MRI検査
- 磁気共鳴画像法。腫瘍の性質を詳しく観察します。
- 造影CT
- 造影剤を用いて腫瘍の血流を評価するCT検査方法。
- 造影MRI
- 造影剤を用いたMRI。腫瘍の性質をより詳しく評価します。
- 手術 肝切除
- 病変を含む肝臓の一部を切除する治療法です。
- 肝移植
- 肝臓全体を取り替える治療法。適応を満たす場合に選択されます。
- アブレーション治療
- 局所的に腫瘍を焼灼して死滅させる治療法の総称です。
- ラジオ波焼灼療法
- RFAとも。高周波の熱で腫瘍を焼灼します。
- RFA
- 肝腫瘍の局所治療の一つです。
- 経動脈化学塞栓術
- 腫瘍の血流を止め薬剤を投与して縮小させる治療法です。
- TACE
- 肝腫瘍治療の代表的な局所療法。
- 放射線治療
- 放射線を使って腫瘍を縮小する治療です。
- 免疫療法
- 免疫系を活性化してがんを攻撃する治療法で、肝癌にも用いられます。
- ソラフェニブ
- 肝癌の第一選択肢として長く使われる分子標的薬です。
- レンバチニブ
- 他の分子標的薬。肝癌治療で用いられることがあります。
- アテゾリズマブ
- 免疫チェックポイント阻害剤。肝癌の治療にも使われることがあります。
- ビバシズマブ
- VEGFを抑える薬。免疫療法と組み合わせて使われることがあります。
- BCLCステージ
- 肝癌の重症度と治療方針を判断する国際的な分類です。
- Child-Pugh分類
- 肝機能の評価基準。治療選択や予後予測に使われます。
- 肝癌の再発
- 治療後に再び肝癌が出現する現象です。
- 早期発見
- 初期の段階で肝癌を見つけること。治療成績を大きく改善します。
- 予後
- 治療後の生存や回復の見通しを指す言葉です。
- 肝癌予防
- 生活習慣の改善やウイルス対策など、発生を減らす取り組みです。
- 臨床試験
- 新薬や新しい治療法の実験的試験です。
- 肝臓がん
- 肝臓にできる悪性腫瘍の別称。肝癌とほぼ同義で使われます。
肝癌の関連用語
- 肝癌
- 肝臓にできる悪性腫瘍の総称。主には肝細胞がんが多いが、肝内胆管がんなど原発性の別の肝がんも含まれる。
- 肝細胞がん
- 肝臓の主要な細胞から発生する最も多いタイプの原発性肝がん。慢性肝疾患の人に発生リスクが高い。
- 肝内胆管がん
- 肝臓の胆管にできる原発性のがん。肝細胞がんとは別の病態で、治療方針が異なることがある。
- 肝転移
- 他の部位のがんが肝臓へ転移して生じる病態。肝臓自体の原発性がんとは別物。
- 肝硬変
- 長期の炎症・損傷で肝臓組織が硬くなる病態。肝癌リスクを高める重要な要因。
- 慢性肝疾患
- 長く続く肝臓の病気全般。肝がんリスクの背景になることが多い。
- C型肝炎
- C型肝炎ウイルス感染による慢性肝炎。肝硬変・肝がんの原因になり得る。
- B型肝炎
- B型肝炎ウイルス感染。長期化すると肝がんリスクが高まる。ワクチンで予防可能。
- アルコール性肝疾患
- 過度のアルコール摂取による肝臓の炎症・脂肪変性・肝硬変。肝がんリスクと関係する。
- NAFLD / NASH
- 非アルコール性脂肪肝疾患。肥満・糖尿病と関連し、肝がんリスクの背景となることがある。
- 腫瘍マーカー AFP
- α-フェトプロテイン。肝細胞がんの存在を示唆する血液検査の一つ。診断補助に使われることがある。
- 腫瘍マーカー AFP-L3
- AFPの分画の一つで、肝がんリスク評価の補助材料として用いられることがある。
- 腫瘍マーカー PIVKA-II / DCP
- 肝細胞がんに関連して上昇することがある検査値。診断補助に使われることがある。
- 腹部超音波検査
- 肝臓の腫瘍を非侵襲的に発見する基本的な画像検査。スクリーニングに適することが多い。
- CT (Computed Tomography)
- 腫瘍の形や広がりを詳しく見るための断層撮影。造影剤を使うことが多い。
- MRI (Magnetic Resonance Imaging)
- 磁気を用いて肝臓を高精度に描く検査。腫瘍の性質判断にも有用。
- 肝生検
- 針を使って肝組織を採取し、病理で悪性・良性を確定する検査。治療方針に影響する。
- 黄疸
- 胆汁の流れが悪くなったときに皮膚や白目が黄色くなる症状。進行した肝疾患で現れやすい。
- 腹水
- 腹腔内に液体が過多となる状態。末期の肝硬変・肝癌でよくみられる。
- 手術的治療: 肝切除
- 腫瘍を切除して取り除く外科的治療。肝機能が許す範囲で検討される。
- 肝移植
- 病変が適切な条件を満たす場合、患者の肝臓を新しい肝臓へ置換する治療法。
- 局所治療: RFA(ラジオ波焼灼療法)
- 腫瘍を熱で焼き尽くす局所治療。小さな腫瘍に適用されることが多い。
- エタノール注入療法
- 腫瘍内にアルコールを注入して壊死させる治療法。局所治療の一つ。
- TACE (Transarterial Chemoembolization)
- 動脈から抗がん剤を投与し、腫瘍への血流を遮断して成長を抑える治療法。
- 肝動注化学療法
- 肝動脈を介して直接抗がん剤を投与する治療。局所効果を狙う。
- 免疫チェックポイント阻害薬
- 免疫系の働きを活性化してがん細胞を攻撃しやすくする薬剤。肝癌にも適用が進んでいる。
- ソラフェニブ
- 肝細胞がんの第一選択として使われる分子標的薬。血管新生を抑制して腫瘍成長を抑える。
- レンバチニブ
- 肝細胞がんなどに使われる別の分子標的薬。副作用に注意が必要。
- アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法
- 免疫療法と血管新生抑制療法の組み合わせ。適応により効果が期待される治療法。
- 放射線治療
- 外部から放射線を当てて腫瘍を縮小・局所制御を行う治療。状況に応じて用いられる。
- BCLC分類
- 肝癌の進行度を評価する国際的な分類。治療戦略を決める目安になる。
- TNM分類
- 腫瘍の広がりを示す国際的ながんの分類。病期を決定する基準の一つ。
- 定期検診・画像モニタリング
- 再発予防・早期発見のためのフォローアップ。患者ごとに検査間隔を決める。
- 予防接種
- B型肝炎ワクチンなど、肝がんリスクを下げる予防手段。
- 生活習慣改善
- 禁酒、適正体重、適度な運動など、肝臓の健康を保つ生活習慣の改善。
肝癌のおすすめ参考サイト
- 肝臓がんとは?原因、症状、治療法について解説
- 肝癌とは? | 肝悪性腫瘍 | 一般・患者さん - Boston Scientific
- 1.肝臓癌とは|肝癌 - 日本臨床外科学会
- 肝癌とは | 東京大学医学部附属病院消化器内科 肝臓がん治療チーム



















