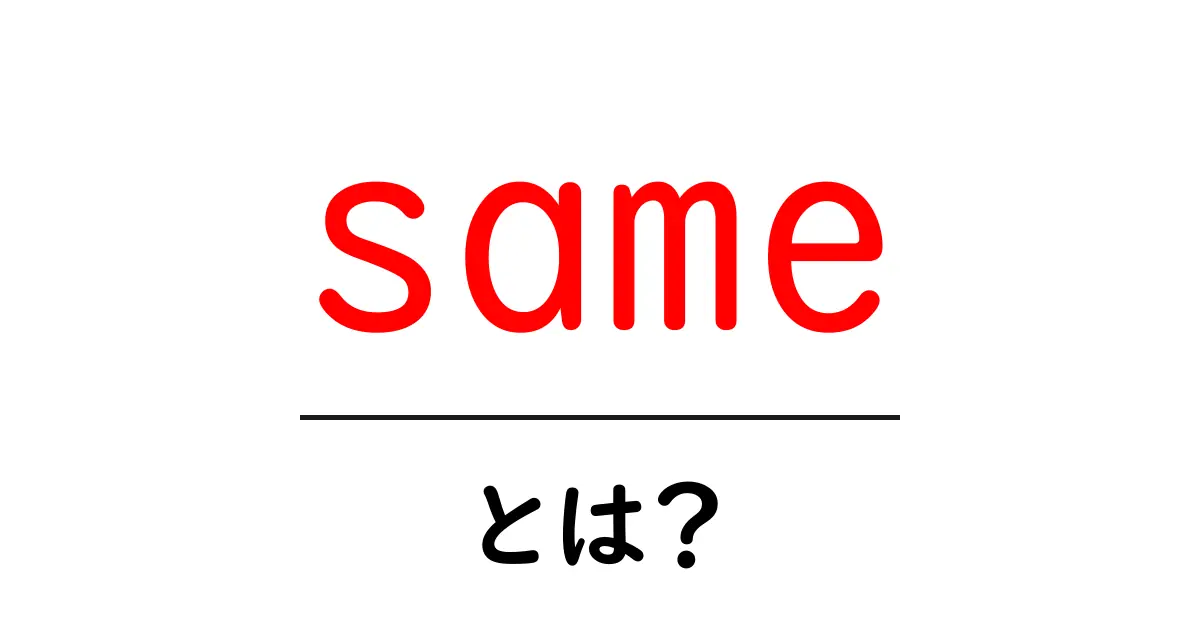

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
same・とは?基本の意味と使い方
英語の単語 same は日本語で「同じ」や「同様」を表す言葉です。一般には形容詞として使われ、名詞の前につけて「同じ〜」という意味を作ります。文の中ではしばしば「the same as 〜」の形で比較を表すほか、短い独立表現として使われることもあります。初心者の人はまず意味をしっかり押さえ、次に使い方のパターンを覚えると英語の表現力が広がります。
意味の基本:same は「違いがない」「別物ではない」という意味です。訳し方は文脈によって変わりますが、基本は日本語の「同じ」です。例を見てみましょう。例文を日本語に直して読んでみると、どの場面でどの意味になるかが分かります。
例: These two shirts are the same. = 「この二着は同じです。」
例: This color is the same as that one. =「この色はあの色と同じです。」
the same as は「〜と同じ」という意味の決まり表現です。文の中でほかの表現と混同しやすいので、例文を通じて慣れることが大切です。
例: The color of the sky and the sea is the same today. =「今日は空の色と海の色が同じです。」
the same は名詞の前につくと「同じもの」そのものを指します。独立して使うこともあり、複雑な名詞句を短くまとめるときに便利です。例: I'll take the same. =「私も同じものをください。」
日常会話での便利な表現として same here があります。これは「私も同じです」という意味で、同意を短く伝えるときに使います。例: A: I like this song. B: Same here. =「この曲が好き。私も同じです。」
使い方のポイントと注意点
同じという意味を強く出したいときは the same を使い、比較の文では the same as の形を使います。発音のポイントは /seɪm/ で、語尾をはっきり言うことです。same と similar、identical などの似た言葉は混同しやすいので、意味のニュアンスを覚えて使い分けましょう。
表現と意味を整理する表
まとめ:same は「同じ」や「同様」という基本的な意味から、比較を表す the same as や、独立表現の the same、同意を表す same here まで、幅広く使える英語の基本語です。初めは意味と使い方をセットで覚え、実際の会話や文章の中で何度も練習していくと、自然に使える表現が増えます。
使い方のコツ:日常の会話では短い表現から覚えていくと続けやすいです。例えば「私も同じです」は Same here だけで伝わる場面が多く、初心者にも扱いやすい表現です。英語を始めたばかりの人は、まず上で出てきた例文を声に出して練習してみましょう。
sameの関連サジェスト解説
- same とは 意味
- same とは 意味を知ると、英語で物事を「同じ」に言い換えるときに役立ちます。この記事では、same の基本的な意味と、名詞の前に置く使い方、比較表現の「the same as」へのつなぎ方、そして日常で使える例文を紹介します。まず、same の意味ですが、英語で『同じ』『等しい』を表します。日本語の「同じ」と同じ意味で、違いがないことを伝えるときに使います。使い方のコツ:1) 形容詞として使う場合: 名詞の前に置く。例: the same color, the same idea, the same shirt。2) the + same + 名詞の形もよく使われる。例: The two shirts are the same. We wear the same uniform.3) 比較を表すときは 'the same as' を使う。例: This color is the same as that color. It is the same as yesterday.4) 短い返答として 'Same here.' も使われる。5) 注意点: 'same' は完全に同じを意味します。似ている場合は 'similar' や 'like' を使います。例文:- The two bags are the same. = 2つのバッグは同じです。- This shirt is the same as that one. = このシャツはあのシャツと同じです。- We have the same homework as you. = あなたと同じ宿題です。- Same here. = こちらも同じです。使い分けのポイント:- the same は、2つ以上のものを「違いがない」と表現するときに使います。- the same as は、2つを比べて「同じであること」を明確に示す表現です。- similar は「似ている」程度で、完全に同じではない場合に使います。このように覚えておくと、日常会話や文章で、物事が違わないことを素早く伝えられるようになります。初心者のうちは、例文を声に出して練習するのがおすすめです。
- same here とは
- same here とは、前に言われたことと自分の気持ちが同じだと伝える英語の短い表現です。日常の会話やSNSの返信でよく使われ、私も同じ気持ちだという意味をすぐ伝えることができます。使い方の基本は、相手の発言を受けてすぐに同意を返す形です。例として I love this movie に対して Same here と返します。和訳は 私もだよ や 私も同感です などが自然です。 ただしニュアンスの違いにも注意。Me too との違いは使える場面と意味の範囲です。Me too は一般的に同意を示す万能な表現ですが、名詞が続く場合にも使える一方で、same here は直前の文全体の内容に対して同じ感情を共有するニュアンスが強く、よりカジュアルな場面で使われます。フォーマルな場面では I feel the same way などの表現を選ぶと良いでしょう。 使い方のコツとして、相手の感情を強く受け止めたいときには同意を強調して Same here と返すと自然です。メールや公式文書では使わず、友人との会話・チャット・SNSで活用しましょう。 中学生にも役立つポイントとして、同じ気持ちを短く伝えるこの表現は会話のテンポを生み出します。さまざまな場面の例文をいくつか覚えておくと、英語での受け答えがスムーズになります。
- 鮫 とは
- 鮫 とは、海に住む魚の仲間で、体の骨が軟骨でできている特徴をもつ生き物のグループです。日本語で『サメ』と呼ばれることも多いですが、漢字の『鮫』も使われます。サメは軟骨魚類に分類され、ヒラメやマグロなどの『硬い骨を持つ魚』とは異なります。体は細長く、歯が並ぶ口が前方にあり、ヒレで水を進ませながら泳ぎます。代表的な種類にはホオジロザメ、ジンベエザメ、サメの仲間でも性格が穏やかなものがあります。ジンベエザメは世界最大の魚であり、口を大きく開けて海の小さな生物をすくうように食べます。サメの体には鋭い歯が並んでおり、獲物を捕らえる時には歯を使います。ただし、ジンベエザメのように歯が小さく、主に口の中でプランクトンをこすように食べる種類もいます。成長の仕方は種によってさまざまで、繁殖方法も異なります。サメは嗅覚が発達しており、水中の匂いを強く感知し、血の匂いをたどって獲物の場所を見つけることがあります。また、体に並ぶ感覚器(ロレンツィーニの電気受容器)で海の微弱な電場を感じ取り、獲物の位置を推測します。視覚も発達しており、暗い水中でも動くものを見分けられます。サメは海の生態系で重要な役割を担い、海を健全に保つための自然なバランスを作っています。中には人へ危険な種類もいますが、海での遭遇は比較的稀で、安全に学習・観察するための知識が必要です。保護活動も盛んで、乱獲や生息地の破壊を防ぐ努力が続けられています。
- サメ とは
- サメ とは、海に住む魚の仲間で、サメ目に属する多様な生き物です。体の骨は硬い骨ではなく軟骨でできているため、軽くてしなる体が特徴です。内臓は体の中心を横切る鋭い歯と、長い尾びれを使って泳ぎ回ります。サメは基本的に海水を住処としますが、淡水域に現れる種類もいます。世界中の海に広く分布しており、体の大きさはミニサイズのスナギサメから巨大なホオジロザメまで様々です。生き方は肉食が多く、魚や海鳥、時にはクジラの仲間を捕食します。嗅覚が良く、匂いを頼りに獲物を探すことができます。聴覚、視覚、感覚器官も発達しており、エイっとかぶりつくタイミングを見極めます。歯は成長とともに絶えず生え替わり、欠けても新しい歯が生えてきます。泳ぐ力が強く、速い種は時速60キロ以上で水中を滑るように進むことができます。サメ とは怖い生き物だと思われがちですが、攻撃的な性格ばかりではなく、多くは人間に対して危険と感じさせる状況下でのみ反応します。自然の一部として、海の生態系を保つ働きもしています。絶滅の危機に瀕している種も多く、漁業や海洋汚染などが影響しています。私たちは持続可能な漁業や海を守る行動を通じて、サメ の未来を守ることが求められます。今回の記事では、サメ とは何かを基本から詳しく解説しました。
- さめ とは
- さめ とは、日本語でサメのことを指す言い方です。この記事では、さめ とはという言葉を出発点に、サメの基本を中学生にも分かるようにやさしく解説します。サメは海に生息する軟骨魚類で、骨の代わりに軟骨と呼ばれる柔らかい組織で体を支えています。エラを通して水中の酸素を取り込み、呼吸します。体は流線形で水の抵抗を減らし、速く泳ぐことができます。多くのサメは歯を並べた鋭い口を持ち、歯は使われるうちに欠けても新しい歯が生えてきます。種類は非常に多く、巨大なジンベエザメのように大きいものもいれば、小さなネズミザメ程度のものもいます。サメの多くは肉食ですが、雑食性の種類もいます。嗅覚、電気を感知する感覚器官、視覚を使って獲物を見つけ、狩りをします。サメは海の食物連鎖において重要な役割を果たしていますが、過剰な捕獲や生息地の破壊により種が減っているものもあります。そのため、私たちはサメについて正しい知識を持ち、海の生態系を守ることが大切です。日常生活で「さめ とは」という問いをきっかけに、サメの不安なイメージを払拭し、科学的な情報を学ぶことができます。とくに初めてサメの話を読む中学生にも分かるよう、専門用語はできるだけ平易な言い回しで説明しました。
- 冷め とは
- 今回は『冷め とは』について、温度の意味と感情の意味の2つの側面を分かりやすく解説します。まず物理的な意味から。冷めるとは水や食べ物の温度が温かい状態から低くなることを指します。熱いお茶が自然に冷めるとき、温度は下がり味わい方も変わります。次に感情の意味です。人の気持ちが冷めるとは、以前の興味や情熱が薄れて、熱意が減っていくことを指します。恋愛や友情、趣味の熱意でも使われます。使い方のコツとしては、動詞の形は冷める、形容詞として使う場合は冷めた、状態を表す場合は冷めていると変化させます。例文をいくつか見てみましょう。熱心だった趣味への気持ちが、長く続かないときに『気持ちが冷めた』と言えます。夏のイベントは混雑や暑さで、熱意が薄れて『冷めてしまう』こともあります。友だち同士の会話では、過度に熱く語るより『冷めた目で見る』ほうが場面を選ぶ場面もあります。日常の会話やSNSの投稿でも、冷めた表現を使うと状況を落ち着いて伝えやすくなります。最後に、温度と感情の意味を混同しないことが大切です。温度の話なら“冷える”“温かい”を使い、感情の話なら“冷める”と覚えておくと迷いません。
- team same とは
- team same とは、英語の語感をそのまま日本語で質問している検索語の一つです。team はチーム・団体を、same は同じ・同一を意味しますが、この二つを並べた team same には決まった意味があるわけではありません。多くの場合、ユーザーはこのフレーズの意味を知りたい、あるいは固有名詞やブランド名として使われているのかを調べようとしています。以下に初心者にも分かりやすく解説します。まず、意味の整理です。1) 単なる検索語としての解釈:この場合は team と same という二つの英単語の意味を同時に知りたい意図です。2) 固有名詞の可能性:プロジェクト名・サービス名・企業名などとして使われている場合もあり得ますが、一般的には広く知られていません。3) SEOやウェブ運用の観点:ページ作成者が team と same を関連づけたコンテンツをどう扱うか、キーワードの意図を崩さずに整理する工夫の話題として現れることがあります。理解を深めるコツとしては、まず辞書や辞典でそれぞれの意味を確認し、次に実際の検索結果を見てユーザーの意図を読み解くことです。例えば公式サイトやニュース記事、学校の教材といった信頼できる情報源を比べてみると、どの意味が適切かが見えてきます。さらにSEOの実務としては、以下の点を意識するとよいです。1) 2語の組み合わせとしての意味を説明する本文を用意する。2) 似た意味の語や関連語を併記して検索クエリの幅をカバーする。3) FAQ形式でよくある質問を想定して回答を用意する。これにより、読者は team same とは という質問に対して、統一感のある答えを得られます。例文をいくつか挙げると、例1 私たちのチームは同じ目標を持っています は team と same を別々の文脈で用いた自然な表現の一例です。例2 Team Same という名前のプロジェクトがあるのかもしれません は固有名詞としての使用を想定した表現です。実際の検索時には、上のように意味を分けて考え、適切なキーワードを選ぶことが大切です。もしこのフレーズで記事を書くなら、読者の疑問を先回りして解決する構成を心がけましょう。
- all the same とは
- この記事では、英語表現「all the same とは」について、意味と使い方を中学生にもわかる言い方で解説します。結論から言うと「all the same」は“どれを選んでも変わらない”や“それでも”という意味で使われる表現です。状況によってニュアンスが変わるので、使い分けを押さえましょう。意味の基本「all the same」は「全部同じ」という直訳ではなく、実際にはふたつの意味として使われます。1つは“結局はみんな同じだ、差がない”という意味。例: 'It doesn't matter which option you choose—it's all the same.'(どの選択肢を選んでも構わない。結局どれを選んでも同じだ。)もう1つは“それにもかかわらず”という意味で、文を始める“Nevertheless/Even so”のニュアンスとして使われます。例: 'The plan failed, but all the same, we tried again.'(計画は失敗した。それでも私たちは再度挑戦した。)使い方のコツ- 主語は人でも物でもOKで、文章の最後に置くと自然です。- 形式ばった場面では使いにくいので、友達との会話やブログのようなカジュアルな場面に向いています。- 「to me」「for me」など後ろに所有者をつけて“私にはどうでもいい”という意味にもできます。例: 'It’s all the same to me.'(私にはどうでもいい。)- 反対の意味の言い換えとして「different from each other」や「not a big difference」と覚えると混乱を避けられます。例文と訳- 'Which shirt should I wear? Red or blue? It's all the same.' → 「どっちのシャツにする?赤と青、どちらを選んでも同じだ。」- 'All the same to me.' → 「私にはどうでもいい。」- 'The result looks different, but all the same, we learned a lot.' → 「結果は違って見えるが、それでも私たちはたくさん学んだ。」最後に「all the same とは」を使い分ける練習として、身近な場面で3つの例文を作ってみましょう。
- write same とは
- write same とは、日本語に直すと「同じ文章を書くこと」または「同じ内容を繰り返して書くこと」という意味に近い表現です。SEOの世界では、同じ内容を複数のページに掲載してしまう状態を“重複コンテンツ”と呼ぶことがあり、時に write same と言われることがあります。なぜ問題なのかというと、検索エンジンはユーザーにとって最も役に立つページを選びたいからです。もしサイト内の多くのページが似た内容だと、どのページを表示すべきかがはっきりせず、結果としてすべてのページの順位が下がる可能性があります。初心者の方には、まず「自分の言葉で新しい情報を付け加える」ことを心がけるのが基本です。具体的には、製品ページなら仕様の違い、使い方のヒント、実際の利用シーンの例を増やす、記事なら同じテーマでも導入の角度を変える、事例を追加する、図やリストで情報を整理するなどの工夫をします。重複を避けるための実用的なコツとしては、まず各ページの目的をはっきりさせること、タイトルやリード文を変えること、既に存在する内容をそのまま転用せずに新しい角度で再構成することが挙げられます。必要に応じて canonical タグを使って“このページが主たる情報源です”と伝える方法や、古いページを noindex にする方法も知っておくと安心です。最後に覚えておきたいのは、読者にとって有益な価値を生み出すことを最優先にすることです。写し書きのような単純な繰り返しではなく、違いを生む工夫を重ねれば、読者にも検索エンジンにも喜ばれる文章になります。
sameの同意語
- identical
- 完全に同じ。形状・性質・状態が区別できないほど同一であること。
- alike
- 似ているが完全には同じではないことが多い。外見や特徴が似ている状態。
- equal
- 数量・価値・程度などが等しい。対等な関係や量を表す。
- matching
- お互いにぴったり合っている。色・柄・サイズ・特徴が一致している状態。
- uniform
- 全体が均一で変化がない。ばらつきがなく、同じ状態が続くこと。
- congruent
- 形・角・サイズが一致している。特に数学的・幾何学的な整合性を指す。
- indistinguishable
- 見分けがつかないほど同じ。差異を識別できない状態。
- equivalent
- 意味・価値・機能が同等で、代替可能な状態。
- analogous
- 類似しているが完全には同じではない。共通の特徴があることを示す。
- commensurate
- 相応する。大きさ・価値・程度が釣り合って同等とみなせる状態。
sameの対義語・反対語
- 違う
- 同じではない。二つ以上のものが一致せず、別の特徴を持つ状態を指す。例: 赤と青は違う。
- 異なる
- 同一ではない。性質・特徴・程度が異なることを示すニュアンス。似ていても等しくはない。
- 別の
- 同じではない別物・別種を指す表現。比較対象が異なる場合に使う。
- 別々
- 一緒にはならず、それぞれ独立している状態。複数のものが個別であることを示す。
- 相違
- 違い。二つの物事が異なる点を指す名詞。意見や特徴に差があるときに使う。
- 違い
- 差。二つのものの異なる点を表す名詞。比較の焦点となる。
- 異質
- 質や性質が異なること。別の種類・カテゴリに属することを表す。
- 対照的
- 二つの対象が正反対の特徴を持つこと。比較の文脈で用いられる表現。
- 別物
- 同じではなく、全く別の物を指す口語的表現。
- 多様
- さまざまで、均一でない状態。違いを含む広い範囲の差を示す。
sameの共起語
- the same
- 同じであることを強調する定冠詞付きの語句。比較・対照の場面で使われる最も基本的な共起表現です。
- same as
- 〜と同じであることを示す表現。比較対象を明示する定型句です。
- same-day
- 同日を意味する形容詞で、日付を強調する際に使われます。
- same-day delivery
- 注文日と同じ日に配送するサービスを表す用語。EC・小売で頻出。
- same-day service
- 同日対応のサービスを指す表現。業務・小売・公共機関で使われます。
- same time
- 同じ時刻・同時を表す表現。複数の出来事を同時に説明するときに使われます。
- same time zone
- 同じタイムゾーンを指す表現。国際業務・旅行の文脈で使われます。
- same place
- 同じ場所を指す表現。地図・案内・集合の文脈で使われます。
- same color
- 同じ色を指す表現。デザイン・ファッション・商品説明でよく使われます。
- same colour
- 同じ色(英国綴り colour の場合)を指す表現。
- same meaning
- 同じ意味を指す表現。辞書的・言語学的文脈で使われます。
- same idea
- 同じアイデア・意図を示す表現。ブレインストーミングや提案で使われます。
- same result
- 同じ結果を示す表現。比較・検証の論点として使われます。
- same outcome
- 同じ結末・成果を示す表現。研究・評価の文脈で使用。
- same purpose
- 同じ目的を示す表現。説明・提案の場面で使われます。
- same topic
- 同じ話題を指す表現。記事・会話の文脈で使われます。
- same issue
- 同じ問題・課題を示す表現。報告・相談でよく使われます。
- same problem
- 同様の問題を指す表現。技術サポートや研究討議で使われます。
- same condition
- 同じ条件・状況を示す表現。実験・比較・条件設定の文脈で使われます。
- same quality
- 同じ品質を指す表現。製品比較・品質管理で使われます。
- same price
- 同じ価格を示す表現。価格比較の文脈で頻出。
- same cost
- 同じ費用を指す表現。見積もり・予算の文脈で使われます。
- same size
- 同じサイズを指す表現。衣料・家具・建材などで使われます。
- same shape
- 同じ形を指す表現。デザイン・設計・製造で使われます。
- same weight
- 同じ重量を指す表現。梱包・物流・製品仕様で使われます。
- same length
- 同じ長さを指す表現。裁縫・建築・測定の場面で使われます。
- same height
- 同じ高さを指す表現。設計・建築・スポーツの文脈で使われます。
- same volume
- 同じ容量・体積を指す表現。パッケージ・科学の文脈で使われます。
- same origin policy
- ウェブブラウザのセキュリティ原則。別オリジンからのリソース制限を指します。
- same-origin policy
- 同一オリジンポリシー。ウェブセキュリティの基本概念です。
- same-sex
- 同性を表す接頭語として用いられる語。LGBT関連の文脈で使います。
- same-sex marriage
- 同性婚を指す法的・社会的用語。
- same-sex couple
- 同性カップルを指す表現。
- same spelling
- 綴りが同じであることを示す表現。辞書・言語学の文脈で使われます。
- same pronunciation
- 発音が同じであることを示す表現。語学学習などで用いられます。
- same term
- 同じ用語を指す表現。専門分野で用語の統一を話すときに使います。
- same word
- 同じ語を指す表現。語彙の一致を示す際に使われます。
- same phrase
- 同じフレーズを指す表現。翻訳・言語学・文章の統一で用いられます。
- sameness
- 同一性・類似性の概念。哲学・言語学・比較研究で使われます。
- same routine
- 同じ日課・習慣を指す表現。生活・ダイエット・ルーティンの話題で使われます。
- same pattern
- 同じパターンを指す表現。データ分析・教育・デザインで使われます。
- same process
- 同じプロセスを指す表現。業務改善・製造・ソフトウェア開発で使われます。
- same policy
- 同じ方針・規約を指す表現。組織内の運用・ルールで使われます。
- same channel
- 同じチャンネルを指す表現。マーケティング・配信・メディアの文脈で使われます。
- same language
- 同じ言語を指す表現。翻訳・言語比較・学習の文脈で使われます。
sameの関連用語
- 同じ
- 性質や状態が等しいこと。例:内容が同じ、サイズが同じ。
- 同一
- 同じ対象を指す固有性・同一性。別物と区別できるようにする概念。
- 同一性
- ある対象を他と区別するための独自の性質。識別性を保つ指標。
- 同等
- 価値・機能・量が等価で、比較可能な関係。
- 等しい
- 数値・量・属性が等しいこと。
- 一致
- データ・文字列・結果がぴったり合致している状態。
- 一致性
- 複数の要素が整合している性質。
- 完全一致
- 検索クエリと語句が完全に一致するマッチタイプ。
- 部分一致
- 検索クエリの一部が語句と一致するマッチタイプ。
- フレーズ一致
- 語句の連続が一致するマッチタイプ。
- 類義語
- 意味が近い別の語。
- 同義語
- 意味が同じ語。
- 類似語
- 意味が近い語。
- 類似性
- 2つの語や表現の意味的な近さの程度。
- 意味的類似性
- 意味が近いかを評価する指標。
- 同義語検索
- 検索時に同義語を含めて探す機能や技術。
- パラフレーズ
- 同じ意味を別の言い換えで表現すること。
- パラフレーズ検索
- パラフレーズを前提にした検索の意図を捉えること。
- セマンティック
- 意味論的・意味に基づく性質。
- セマンティック検索
- 語の意味を理解して関連性を判断する検索方式。
- 同義語置換
- 同義語に置き換えて言い換える技法。
- 置換表現
- 別表現に置換して同じ意味を伝える表現。
- バリエーション
- 表現のバリエーション、言い換えの幅。
- キーワードバリエーション
- キーワードの言い換え・派生形の集合。
- 重複コンテンツ
- 同じ内容がサイト内外の複数ページに現れる状態。
- 重複コンテンツ対策
- 重複を避け、正規URLへ誘導する対策。
- 正規URL
- 同じ内容を指す複数URLがある場合、正規と認識させるURL。
- canonicalタグ
- 正規URLを示すHTMLタグ(rel=canonical)。
- canonical化
- URLを正規化して一意化するプロセス。
- 正規化
- データを一貫した形式へ統一する処理。
- 一貫性
- 情報や表現の統一性・信頼性を保つ性質。



















