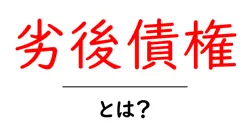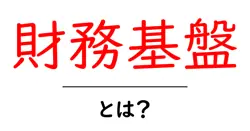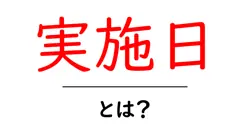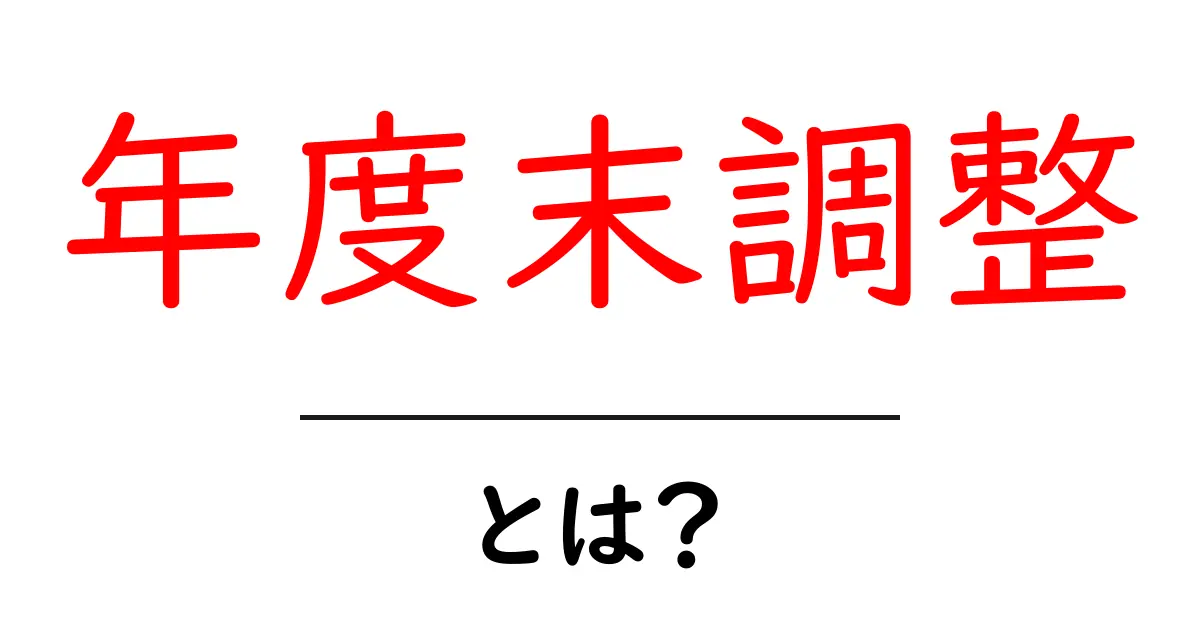

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
年度末調整とは?
年度末調整は、給与所得者の所得税を「正しく」計算し直すための制度です。会社が年末に行い、毎月源泉徴収していた税額と、1年間の収入・控除をもとに最終の税額を決定します。この時、皆さんが普段気にしている控除の適用が正しく反映されることが大切です。基本的には個人が自分で確定申告をする必要はありませんが、例外もあります。
年末調整を理解するうえで大切なポイントは次のとおりです。「誰が・いつ・何をするのか」「どんな書類が必要か」「どんな場合に確定申告が必要になるか」を押さえることです。
誰が、いつ、何をするのか
通常、勤務先の人事・経理部門が中心になって年末調整の作業を行います。対象は給与を受け取っている人で、正社員・契約社員・アルバイトなど雇用形態は問われません。タイミングは年末頃、12月前後に進められ、結果は新しい源泉徴収票として知らせられます。
必要な書類と準備
年末調整を正しく行うためには、いくつかの書類の提出が求められます。主なものは以下のとおりです。
年末調整が終わった後の流れ
年末調整が完了すると、会社は「源泉徴収票」を発行します。これには1年間の給与所得と所得税の額が記載され、年末に従業員へ配布されます。控除が多く適用されると税金が戻る場合があり、逆に控除が少ない場合には追加の納税が発生することもあります。
年末調整と確定申告の関係
原則として、給与所得のみで他の副収入が少なく、年末調整で完結します。しかし、次のケースでは確定申告が必要になることがあります。
・副業所得がある場合、複数の収入源がある場合
・医療費控除や住宅ローン控除を年末調整だけでは適用できない場合
まとめ
年度末調整は、給与所得者の税負担を正しく反映する重要な制度です。基本的な流れを知り、必要な書類を前もって準備することがポイントです。自分の状況に合わせて、年度末調整だけで済むか、確定申告が必要かを判断しましょう。
年度末調整の同意語
- 年末調整
- 給与所得者の所得税額を年末に最終確定させる手続き。控除の過不足を清算し、年末時点で税額を確定します。
- 年末税額調整
- 年末に行われる税額の最終調整のこと。年末調整とほぼ同義で使われる表現です。
- 年末の税額調整
- 年末時点での税額を最終的に調整する作業を指す表現。
- 所得税の年末調整
- 所得税の額を年末に確定するための調整作業の正式名称。
- 所得税の最終調整
- 所得税の最終的な額を決定する年末の調整作業の別称。
- 給与所得者の年末調整
- 給与所得者を対象とした年末調整の手続きという意味の表現。
- 源泉徴収の年末調整
- 源泉徴収された税額と実際の控除額を差し引いて最終的に清算する作業を指します。
- 年度末の税額調整
- 年度末に行われる税額の最終調整を指す表現。年末調整とほぼ同義で使われます。
- 年末税額の確定
- 年末時点で税額を確定させることを意味する表現。
年度末調整の対義語・反対語
- 確定申告
- 年度末調整の対義語として最も一般的。給与所得者が副収入がある場合や控除の適用が年末調整だけでは足りない場合に、本人が税額を自分で計算して税務署へ申告・納付する制度です。申告期間は通常、翌年の2月頃から3月頃です。
- 源泉徴収のみ
- 会社が年末調整を行わず、給与からの源泉徴収だけで税額を処理する状態。追加の控除申請や副収入の申告などを個人が別途行わない場合を指します。
- 自己申告
- 正式名称ではない表現ですが、個人が自分で税額を申告することを意味します。確定申告とほぼ同義として使われることがあります。
- 副業所得がある場合の申告
- 給与以外の所得(副業・不動産所得など)がある場合、確定申告が必要になるケース。年末調整だけでは完結せず、別途申告を行います。
- 個人による確定申告(自分で税額を確定して申告する形)
- 個人が自ら所得と控除を計算し、税務署へ申告して税額を確定させる手続き。年末調整と対になるイメージで使われます。
年度末調整の共起語
- 源泉徴収票
- 給与所得の総額や各種控除の情報が記載された給与の最終報告書で、年末調整の根拠データとして雇用主が作成・配布します。
- 給与所得者
- 年末調整の対象となる、給与を得る従業員のこと。アルバイト・パートも含まれます。
- 住宅ローン控除
- 住宅ローンを利用している場合に年末調整で適用される税額控除。支払額に応じて所得税が軽減されます。
- 配偶者控除
- 配偶者の所得が一定以下のケースに適用される所得控除。年末調整で反映されます。
- 配偶者特別控除
- 配偶者の所得が一定レンジ内の場合に適用される控除。年末調整で適用され得ます。
- 扶養控除
- 扶養している家族の人数・条件に応じて控除額が変わる。年末調整で適用されます。
- 社会保険料控除
- 支払った社会保険料の額を控除として認める制度。年末調整で自動的に反映されることが多いです。
- 生命保険料控除
- 支払った生命保険料を控除として認める制度。年末調整で適用されるケースがあります。
- 地震保険料控除
- 地震保険料を支払った場合に適用される控除。証明書が必要です。
- 保険料控除証明書
- 生命保険料・地震保険料の控除を受ける際に提出する証明書。年末調整で使われることが多いです。
- 医療費控除
- 一定額を超えた医療費に対する控除。確定申告で申請するのが一般的ですが、条件次第で年末調整で反映される場合もあります。
- 医療費控除の証明書
- 医療費控除を受ける際に必要となる領収書・レシート等の証拠書類。提出が求められることがあります。
- 控除証明書
- 各種控除を証明する書類の総称。年末調整で提出・活用されます。
- 確定申告
- 年末調整で対応できないケースや初年度の住宅ローン控除などで、別途税務申告として行う制度。
- 申告書類
- 年末調整・確定申告で必要となる各種提出書類の総称。
- 書類提出
- 年末調整に必要な証明書や申告書を雇用主へ提出する手続き。期限があります。
- 勤務先/会社
- 年末調整を実施する雇用主・勤務先。従業員の控除計算と源泉徴収票の作成を担当します。
- 年末調整の流れ
- 給与の確定、控除の適用、税額の調整、源泉徴収票の作成までの一連の手順。
- 期限
- 年末調整に関する提出書類の締切日。期限を過ぎると控除の適用が難しくなる場合があります。
- 住民税への影響
- 年末調整は主に所得税を計算する仕組みですが、その結果は住民税の算定にも間接的に影響します。
年度末調整の関連用語
- 年度末調整
- 給与所得者の年間の所得税の過不足を年末に調整する制度。会社が代行して実施し、過払い分は還付、徴収不足分は追加で徴収されます。
- 確定申告
- 個人の所得税を税務署へ申告する制度。年末調整で処理しきれない控除や所得がある場合に用い、通常は翌年の2月16日から3月15日頃に提出します。
- 源泉徴収票
- 給与所得者に対して年末に発行される書類で、年間の給与総額・控除額・源泉徴収税額などを記録しています。雇用主から受け取り、年末調整の根拠になります。
- 基礎控除
- 誰でも受けられる基本的な所得控除。現在の制度では一定の所得制限ありで控除額は38万円などと定められています。
- 配偶者控除
- 配偶者の所得が一定以下の場合に適用される所得控除。配偶者の収入状況により控除額が決まります。
- 配偶者特別控除
- 配偶者の所得が一定の範囲内にあるとき、段階的に控除される制度。配偶者の収入が増減すると控除額も変わります。
- 扶養控除
- 扶養する家族がいる場合に適用される所得控除。扶養親族の年齢や人数によって控除額が変わります。
- 扶養控除等申告書
- 年末調整時に提出する書類の一つ。扶養控除の適用を申告します。
- 社会保険料控除
- 支払った社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険など)を控除します。
- 生命保険料控除
- 支払った生命保険料を控除します。契約内容により控除額が決まります。
- 地震保険料控除
- 支払った地震保険料を控除します。
- 小規模企業共済等掛金控除
- 小規模企業共済等の掛金を支払っている場合に適用される控除です。
- 寄付金控除
- 認定NPO法人などへの寄付金を控除します。寄付金の額に応じて控除額が決まります。
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
- 住宅ローンを組んで住宅を取得した場合に適用される控除。初年度は原則確定申告が必要ですが、条件を満たすと年末調整で適用されるケースもあります。
- 医療費控除
- 1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される控除。通常は確定申告で申告しますが、年末調整で扱われるケースは限定的です。
- 雑損控除
- 災害などで生じた損失を控除します。
- 寄付金控除(住民税控除を含む)
- 寄付金のうち住民税にも影響する部分がある控除。所得税だけでなく住民税にも適用されます。
- 控除証明書
- 各種控除を受けるために必要な証明書。生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、寄付金控除証明書などがあります。
- 特別徴収
- 給与所得者の所得税を会社が給与から毎月天引きして納付する方式。年末調整はこの前提で行われることが多いです。
- 普通徴収
- 住民税を自分で納付する方式。特別徴収が適用できない場合に選択されます。
- 年末調整の提出書類
- 給与所得者の保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、控除証明書など、年末調整時に提出する書類の総称です。