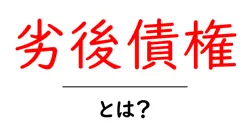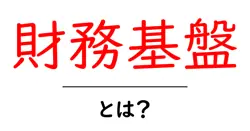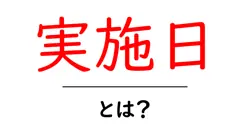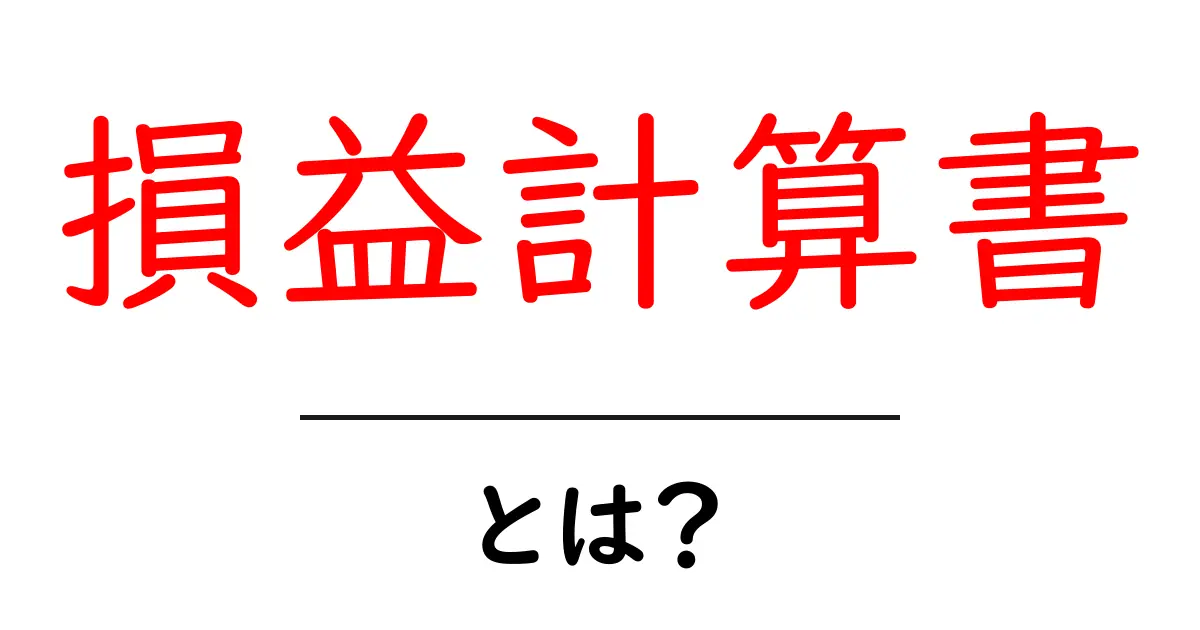

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
損益計算書・とは?
ビジネスの世界では、お金の出入りを整理するための基本的な書類がいくつかあります。その中のひとつが「損益計算書」です。日常生活では難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえるととてもシンプルです。
損益計算書は、一定の期間(通常は1年間)に「どれだけ売上があって、どれだけ費用がかかり、結局いくら利益が出たのか」を示す表です。企業だけでなく、学校の部活動の活動費の記録にも似た考え方を使います。以下のように、売上と費用を並べて最終的な利益を出します。
損益計算書の役割
役割の要点は3つです。1) 成果を客観的に示す、2) 将来の計画の判断材料にする、3) 他の人にお金の状況を伝える、という点です。特にビジネスでは、株主や銀行といった外部の人に「この会社は利益を出しているのか」を伝える大切な道具になります。
主な構成項目
損益計算書にはいくつかの項目が並びます。以下の表は、初心者にも分かりやすい基本的な構成です。
注釈として、実務では「営業利益」や「経常利益」など、用途が異なる複数の利益指標を用いて分析します。中学生にも分かる考え方のコツは、売上高から直接かかった費用を引いた「売上総利益」を理解することです。その上で、さらに費用を引いて最終的な利益がいくらかを考えると、企業の健康状態が見えやすくなります。
作成の流れ(简易版)
実務では、会計ソフトや帳簿を使って取引を1つずつ登録し、月次や年度末にみにまとめます。基本的な流れは以下のとおりです。
- 1) 売上を集計
- 販売した商品や提供したサービスの総額を記録します。
- 2) 原価を集計
- 商品を作るための直接的な費用を積み上げます。
- 3) 費用を集計
- 広告費・人件費・家賃など、事業を動かすための費用をまとめます。
- 4) 税引前・税金の計算
- 経営成績をもとに税金を見積もります。
- 5) 当期純利益を確定
- 最後に税金を差し引き、最終的な利益を出します。
このように、損益計算書は「売上と費用の差額を追いかける表」です。難しそうに聞こえますが、実は日常的な家計簿の考え方と似ています。家計簿では「収入 − 支出 = 残金」ですよね。損益計算書も同じ原理で、「収入(売上)」と「支出(費用)」を比べ、最後に何が残るかを見ます。
最後に、練習のコツを一つ紹介します。自分の「部活動費の損益計算書」を作ってみましょう。例えば、1年間の部費やイベント費を売上として、参加者数×費用、グッズ販売などを売上に含め、実際にかかった費用と照らし合わせてみると、損益計算書の作成感覚が身につきます。
損益計算書の関連サジェスト解説
- 損益計算書 とは わかりやすく
- この記事では、損益計算書 とは わかりやすくというキーワードの意味を、初心者でも理解できるように順を追って解説します。損益計算書とは、一定の期間における“お店や会社の儲け”を示すお金の帳票です。難しそうな用語は避け、売上高と原価、そして費用を整理して“どれくらい儲かったのか”を表します。大事なポイントは、売上高、売上原価、売上総利益、販管費、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益の順序です。売上高は商品やサービスの総売上、売上原価はその商品を作るための費用、売上総利益はこの差額です。販管費は広告費や人件費、家賃などの日々の費用をまとめたもの。営業利益は売上総利益から販管費を引いた額で、ここが事業の“本当の利益の力”を示します。次に、経常利益は営業外の収益と費用を含む最終的な利益で、税金の前の数字である税引前当期純利益は、この経常利益に加算・減算されたものです。最後に、税金を差し引いた後の当期純利益が“実際の儲け”として現れます。実用的な理解を深めるため、具体的な例を使います。売上高1000万円、売上原価600万円、売上総利益400万円、販管費320万円、営業利益80万円、営業外収益0万円、営業外費用0万円、経常利益80万円、税引前当期純利益80万円、法人税等20万円、当期純利益60万円という数値を仮に置いてみましょう。こうした数字の並びを追うだけで、どの段階でお金が増えるのか、どこにコストをかければ利益を伸ばせるのかが見えてきます。損益計算書は企業の健康状態を判断する道具であり、事業計画づくりや投資判断の基礎にも役立ちます。
- 損益計算書 租税公課 とは
- この記事では、損益計算書 租税公課 とは何かを、初心者でも分かる言葉で丁寧に解説します。まず、損益計算書は企業の利益がどう生まれたかを示す報告書です。売上から原価・費用を差し引いた結果が利益になります。この費用の中には、人件費や広告費だけでなく、税金に関する費用も含まれます。ここでいう租税公課とは、国や自治体に納める税金や公的料金のことを指す費用の総称です。日本の会計では、租税公課には法人税、住民税、事業税などが含まれることが多いですが、企業によっては法人税等を別の項目として表示することもあります。決算書における分類は企業の会計方針や会計基準によって異なります。例として期末に支払う税金を租税公課として計上するケースを挙げます。税金の支払いは現金の動きと連動しますが、損益計算書上は費用として認識され、期間の利益に影響します。会計ソフトを使うと、租税公課の内訳を別途表示する設定もあります。ポイントは、損益計算書の租税公課が税金の費用という性質を示す項目であり、企業の経営状態を判断する材料のひとつになるということです。
- 損益計算書 売上原価 とは
- この記事では、損益計算書の中の売上原価とは何かを、中学生にもわかるようにやさしく解説します。まず、売上原価とは、商品を作るために直接かかった費用のことです。材料費・仕入れ費・直接人件費などが該当します。売上原価は通常、期間内に売れた商品のコストを指し、これを売上高から引くことで、売上総利益が生まれます。売上原価が大きいと、売上総利益は小さくなり、会社の利益が減ります。逆に原価を抑える工夫や生産性の向上が進むと、利益が増えます。実務的な考え方では、売上原価は「期首在庫 + 当期仕入高 - 期末在庫高」という式で計算されます。製造業と小売業では、対象となる費用の内訳が少し違いますが、基本の考え方は同じです。材料費・直接労務費・仕入原価などが中心で、間接費は別に「販売費及び一般管理費」などとして計上します。また、売上原価率(売上原価 ÷ 売上高)を見れば、製品がどれだけ効率的に利益を生み出しているかが分かります。棚卸資産の変動や在庫管理の状況も、売上原価に影響を与える重要な要素です。初心者の方へ押さえてほしいポイントは3つです。1) 売上原価は「直接に商品づくり・仕入れにかかった費用」であること、2) 計算式と在庫の動きで日々変わること、3) 売上総利益と売上原価率を使って利益の状況を把握することです。これらを理解すれば、会計の基礎がぐっと身につき、日常のビジネス判断にも役立ちます。
- 損益計算書 支払利息 とは
- 損益計算書は、会社の1年間の“売上・費用・利益”の流れを示す大事な書類です。その中に支払利息という項目があります。支払利息とは、銀行や他の金融機関からお金を借りたときに、借りた金額に対して毎年支払うお金のこと。利息は現金で払うこともありますが、発生主義という会計ルールにより、実際に支払った時だけでなく、発生した時点でも費用として計上されます。この支払利息は、営業利益とは別の費用として表示され、税引前利益の計算にも影響します。多くの会社では支払利息を「営業外費用」や「財務費用」として表示しますが、表の名前は会社ごとに少し前後します。支払利息が大きいと、借入が多い、または金利が高い状態を表すことがあり、資金の調達状況を示す指標にもなります。簡単な例で考えましょう。売上高が1000、営業費用が700の場合、営業利益は300です。ここに支払利息が50あれば、税引前利益は250になります。税金を引くと最終的な純利益はこれより少なくなります。要するに、支払利息は会社の“お金を借りるコスト”です。読み方のコツとしては、営業利益と純利益の差をつくる要素の一つとして見て、借入の多さや金利動向を把握する手掛かりにするとよいでしょう。
- 損益計算書 車両費 とは
- この記事では、損益計算書に登場する車両費について、初心者の方にも分かりやすく解説します。車両費とは、会社が車を業務で使うことで発生する日常的な費用の総称です。具体的には燃料費、整備・修理費、タイヤ交換費、車検費用、任意保険料、駐車場代などが挙げられます。これらは通常、損益計算書の費用欄の車両費として一括して計上します。ただし減価償却費は車両の資産価値の減少を表す別の科目であり、車両費とは別に計上するのが一般的です。車両費を正しく管理するコツとしては、日次・月次で実際の走行距離と費用を記録すること、車両の使用目的を分類すること、税務上の扱いを確認することです。例えば、配送用の車と営業用の車を別々に集計することで、費用の透明性が高まり、実際の利益率を正しく把握できます。リース車を使っている場合はリース料が車両費に含まれることもありますが、多くの場合はリース料は別の科目で計上します。具体例として、月の燃料費が8,000円、保険料が3,000円、修理費が2,000円、駐車場代が1,000円なら合計14,000円が車両費の目安になります。会計ソフトや表計算で車両費をきちんと分けておくと、利益の計算や税務申告がスムーズになります。
- 損益計算書 販売費及び一般管理費 とは
- この記事では「損益計算書 販売費及び一般管理費 とは」という言葉を、初心者にもわかりやすく解説します。まず損益計算書について簡単におさらいします。損益計算書は、一定期間の会社の収入と支出をまとめた報告書で、売上高から原価を引いた売上総利益、その後にかかった費用を引いて最終的な利益を示します。販売費及び一般管理費、略して SG&A は、売上を得るために直接かかったコスト(販売費)と、日常の会社運営にかかる費用(一般管理費)をまとめた費用の大きな区分です。\n\n- 販売費には、販売員の給料、販売促進の広告費、配送費、販売に関わる旅費などが含まれます。\n- 一般管理費には、役員や事務スタッフの給与、オフィスの家賃、光熱費、通信費、備品費、減価償却費などが含まれます。\n\nこれらは原価計算のうちの別セクションで、売上原価(COGS)とは別に表示されます。売上原価は商品の仕入れや製造に直接かかった費用ですが、SG&A は商品を作るかどうかに直接連動しない、間接的な費用です。\n\n損益計算書の流れとしては、売上高から売上原価を差し引いて売上総利益を算出し、そこから SG&A を差し引いて営業利益を出します。場合によっては営業外の収益や費用、特別項目も含まれ、最終的な純利益に到達します。\n\nなぜ SG&A を知るのが大切かというと、企業の経営効率を測る指標になるからです。SG&A 比率(SG&A÷売上高)を見れば、規模の成長に対して費用がどのように増減しているかを把握できます。広告費が大きく増えると売上が追いつかない場合、利益が圧迫されることがあります。\n\n初心者向けのポイントとしては、まず SG&A とは何かを理解し、次に自分の関心のある企業の決算短信を見て、SG&A の内訳がどうなっているか、売上との関係を見てみることです。
- pl 損益計算書 とは
- pl 損益計算書 とは、一定の期間における会社の“お金の出入りの結果”をまとめた報告書です。売上高という収入から始まり、そこから売上原価を引いて売上総利益を出します。さらに販売費及び一般管理費といった経費を引くと営業利益が出ます。営業利益の次には、営業外収益・費用を加減して経常利益、特別な利益や費用を含めて税引前当期純利益が決まり、最後に法人税などを引いて当期純利益(最終的な利益)になります。PLは期間を区切って作るので、1か月・1四半期・1年など、会社のパフォーマンスを時系列で見やすく比較できます。PLの読み方のコツは、まず売上高と最終的な当期純利益の関係を確認すること。売上高が増えても費用が同じか増えると利益は伸びないことが多いからです。実際の例として、ある小さな会社の単純なPLを想像してみましょう。売上高が1000、売上原価が600、販売費及び一般管理費が300なら、売上総利益は400、営業利益は100、経常利益も同じく100、税引前純利益は90、当期純利益は60などとなり、数字の意味が見えてきます。PLは企業の“現状の強さ”を示す指標であり、投資家や経営者が次の一手を考える際の手がかりになります。
- 貸借対照表 損益計算書 とは
- このページでは、貸借対照表 損益計算書 とは何かを、初心者のあなたにも分かる言葉で丁寧に解説します。まず、貸借対照表とは、ある特定の時点における会社のお金と持っているものの総額を並べた表のことです。左側に資産、右側に負債と純資産が並び、資産の総額と負債+純資産の総額が必ず同じになるのが特徴です。資産には現金や預金、売掛金、在庫、車や机などの物も含まれます。一方、負債は借入金や未払いの費用、買掛金など、将来支払う義務のことです。純資産は、資産から負債を引いた“自分の資本”のような部分で、オーナーの出資や、これまでの黒字の蓄積が積み上がったものです。これを見れば、会社が今どのくらいお金を持っていて、どれくらい借りているかが一目でわかります。次に、損益計算書とは、一定の期間(例:1年や3か月)における“売上”から“費用”を引いて、どれだけ利益が出たかを示す表です。売上は商品やサービスを提供して得た代金、費用には材料費、人件費、家賃、光熱費、広告費などが含まれます。例えば、あるパン屋さんが1年間で売上が1000万円、材料費が300万円、家賃が100万円、人件費が250万円、光熱費が40万円、広告費が60万円だったとします。これらを合計すると費用は750万円となり、利益は250万円です。この利益は会社が自分で使えるお金の目安になり、次の投資や配分を決める指標になります。ただし、損益計算書の利益は必ず現金の動きと同じとは限りません。実際には売上が入金になるまで時間がかかったり、費用の支払いが後になることもあるため、現金の動きを知りたい場合はキャッシュフロー計算書も合わせて見る必要があります。このように、2つの表は別々のものですが、同じ会社の資金の“今”と“この期間の成果”を両方見せてくれる、非常に大切な道具です。
- 簿記 損益計算書 とは
- 簿記 損益計算書 とは、1年間に企業がどれくらい『儲かったか』を示す財務報告のひとつです。売上高から始まり、売上原価、売上総利益、販管費を経て営業利益、経常利益、税引前当期純利益、そして当期純利益へと進みます。売上高は商品やサービスの総収入、売上原価はその商品を作るのに直接かかった費用です。売上原価を引くと売上総利益が出ます。次に販管費を引くと営業利益が出ます。さらに営業外の収益・費用を加減して経常利益、特別な利益・損失があれば調整して税引前当期純利益を得ます。最後に法人税等を差し引いて当期純利益となります。例えば、ある会社が1年間で売上高1000万円、売上原価600万円、販管費250万円、営業外収益10万円、営業外費用5万円、特別利益0円、特別損失0円、法人税等40万円だったとします。これを計算すると、売上総利益は400万円、営業利益は150万円、経常利益は155万円、税引前当期純利益は155万円、法人税などを引いた当期純利益は115万円になります。このように、損益計算書は“実際にいくらお金が残るのか”を数値で示してくれ、事業の強みや改善点を見つける手助けをしてくれます。簿記では、実際の取引を借方と貸方の仕訳で記録します。例えば商品を売って現金を受け取るときは、借方現金、貸方売上高と記録します。仕入れて現金を払うと、借方仕入高、貸方現金など。これらの積み重ねが損益計算書の数値となります。この知識は決算の基礎であり、将来会計や財務を学ぶ出発点です。
損益計算書の同意語
- 損益表
- 企業の一定期間における売上高・費用・利益などをまとめた財務諸表。損益計算書と同義として使われることが多い表現です。
- 利益計算書
- 損益計算書とほぼ同義の表現。期間中の売上高から費用を差し引いた利益を示す財務情報を指します。
- P/L
- Profit and Loss の略称。英語表記で、期間の損益を示す財務資料として用いられます。
- PL
- P/L の別表記。略語として同じく損益を表す財務諸表を指します。
- 収益計算書
- 収益(売上)と費用の差額を計算して利益を示す表。公式文献では『損益計算書』の代替表現として使われることがあります。
損益計算書の対義語・反対語
- 貸借対照表
- 資産・負債・純資産の水準を特定の時点で示す財務諸表。損益計算書が期間内の成績(利益・損失)を示すのに対し、こちらは財政状態を把握する用途です。
- 収支計算書
- 一定期間の現金収入と現金支出をまとめた報告書。損益計算書が利益・損失を計算するのに対し、現金ベースの動きを把握します。
- キャッシュフロー計算書
- 現金の流入と流出を分類して示す報告書。発生主義ベースの損益計算書とは別の視点で現金の動きを明らかにします。
- 現金主義
- 現金の入出だけを記録する会計の考え方。発生主義(損益計算書の作成の基盤となる考え方)に対する現金ベースの対比です。
- 発生主義
- 売上や費用を発生した時点で認識する会計の考え方。現金主義の対になる概念で、損益計算書の作成基盤として一般的です。
- 予算対比表
- 実績と予算を対比して差異を示す報告書。損益計算書そのものの対義語ではないものの、実績と計画の対比を通じて異なる視点を提供します。
- 財務分析報告
- 財務データを分析して業績の要因や改善点を解説する報告書。損益計算書の直接的な対義語ではないが、業績解釈の別視点として対照的な情報を提供します。
損益計算書の共起語
- 売上高
- 商品の販売やサービス提供によって得られた総収益。損益計算書の最上段に表示される基本的な収益項目です。
- 売上原価
- 商品を作る・仕入れるなど、売上を生み出すために直接かかった原価。売上高から差し引かれ、売上総利益を算出します。
- 売上総利益
- 売上高から売上原価を差し引いた利益。粗利益とも呼ばれ、事業の本業の基本的な収益力を示します。
- 粗利益
- 売上総利益と同義。売上高から売上原価を差し引いた金額です。
- 販売費及び一般管理費
- 販売活動と事務・管理にかかる費用の総称。販管費とも略されます。
- 販管費
- 販管費の略。販売費及び一般管理費を指します。
- 営業利益
- 売上総利益から販管費を差し引いた利益。企業の本業の儲けを示す主要な指標です。
- 営業外収益
- 本業以外で得た収益。例: 受取配当金、為替差益、投資利益など。
- 営業外費用
- 本業以外で発生した費用。例: 支払利息、為替差損、投資損失など。
- 経常利益
- 営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を控除した利益。通常の経常的な収益力を示します。
- 税引前当期純利益
- 法人税等を控除する前の当期純利益。税負担の前の数値です。
- 法人税等
- 法人税・住民税・事業税など、課税所得に対して課される税金の総称。
- 税引後当期純利益
- 税金を控除した後の当期純利益。最終的な純利益です。
- 当期純利益
- 税引後の最終的な純利益。損益計算書の最終行に相当します。
- 純利益率
- 当期純利益を売上高で割った割合。企業の収益性を示す指標のひとつ。
- 売上総利益率
- 売上総利益を売上高で割った割合。粗利の水準を示します。
- 営業利益率
- 営業利益を売上高で割った割合。事業本来の収益性を示します。
- 前年同期比
- 前年度と比べてどれだけ増減したかを示す指標。成長性の比較に使われます。
- 年度比較
- 複数年度の売上や利益の比較を表す表現。財務分析の基本です。
- 連結決算
- 親会社と子会社を合算して作成する決算。P/Lも連結表示になることが多いです。
- 単体決算
- 連結決算とは別に、個別の会社単体で作成する決算のこと。
- 会計期間
- 損益計算書が対象とする期間。通常は1会計年度(12か月等)です。
- 財務諸表
- 企業の財政状態や業績を示す書類の総称。損益計算書はその一部です。
- 収益認識
- 収益をいつ・どの時点で計上するかを定める会計原則。IFRS・日本基準で定義されます。
- 原価
- 商品やサービスを提供するために直接かかった費用の総称。売上原価と関連します。
- 減価償却費
- 資産の価値を耐用年数にわたって費用として配分する費用。
- 人件費
- 従業員の給与・賞与・社会保険料など、労働に対する費用。
- 広告宣伝費
- 商品やサービスの販促活動にかかる費用。
- 研究開発費
- 新製品・新技術の研究・開発にかかる費用。
- 旅費交通費
- 出張時の交通費・宿泊費などの費用。
- 支払手数料
- 取引や決済に伴う手数料や仲介費用。
- 連結子会社
- 親会社が支配する子会社のこと。連結決算の対象になります。
- 日本基準
- 日本の会計基準(Japanese GAAP)のこと。
- IFRS
- 国際財務報告基準。世界的に広く用いられる財務表示基準です。
- 会計基準
- 財務諸表の作成方法を定める基準全般を指します。
損益計算書の関連用語
- 損益計算書
- 企業の一定期間の収益と費用をまとめ、最終的な当期純利益を示す財務諸表。
- 売上高
- 商品やサービスの販売によって得た総収入。売上のはじめの金額。
- 売上原価
- 売上を得るために直接かかった費用。材料費・労務費・製造間接費などを含む。
- 売上総利益
- 売上高から売上原価を差し引いた利益。営業活動の基本的な収益力指標。
- 売上総利益率
- 売上総利益を売上高で割った割合。粗利率とも呼ばれる。
- 販管費
- 販売費と一般管理費の総称。販促活動や事務運営にかかる費用。
- 販売費及び一般管理費
- 販促費・広告宣伝費・人件費・事務費など、日常的な管理・販売活動関連の費用。
- 営業利益
- 売上総利益から販管費を差し引いた利益。企業の本業による利益を示す指標。
- 営業利益率
- 営業利益を売上高で割った割合。営業活動の利益率を示す。
- 営業外収益
- 本業以外で得られる収益(例:受取利息・配当金・雑収入など)。
- 営業外費用
- 本業以外で発生する費用(例:支払利息・為替差損・雑費など)。
- 経常利益
- 営業利益+営業外収益−営業外費用。日常的な経常的利益を示す指標。
- 経常利益率
- 経常利益を売上高で割った割合。
- 特別利益
- 一時的で臨時的な利益(例:固定資産売却益)。
- 特別損失
- 一時的で臨時的な損失(例:固定資産売却損、事業整理損失)。
- 税引前当期純利益
- 税金を控除する前の利益。法人税等を差し引く前の最終的な利益。
- 法人税等
- 法人税・住民税・事業税など、税務上の負担に相当する費用。
- 当期純利益
- 税引後の最終的な利益。最も重要な企業の純粋な利益指標。
- 1株当たり当期純利益(EPS)
- 当期純利益を発行済株式数で割った1株あたりの利益指標。
- 減価償却費
- 固定資産の価値を耐用年数にわたって配分する費用。現金出動を伴わない費用。
- 減損損失
- 資産の回収可能価額が簿価を下回った際に計上する評価損。
- 研究開発費
- 新製品・新技術の開発にかかる費用。
- 広告宣伝費
- 商品やブランドの認知度向上を目的とした宣伝費用。
- 人件費
- 従業員の給与・賞与・社会保険料・福利厚生費などの人件費用。
- 旅費交通費
- 出張や業務上の交通費用。
- 水道光熱費
- 電気・水道・ガスなどの光熱費。
- 賃借料/リース料
- 賃貸物件や機械の使用料・リース料。
- 売上高からの控除項目(売上返品・割引・値引き)
- 販売時に控除される返品・割引・値引きを反映した正味売上高。
- 連結損益計算書
- 親会社と子会社をひとつに統合した財務諸表の損益計算書。
- 単体損益計算書(個別損益計算書)
- 親会社や特定の事業単位ごとの損益を示す損益計算書。
- 売上原価配賦/原価計算
- 売上原価をどのように配分し、原価計算を行うかの手法・方針。
損益計算書のおすすめ参考サイト
- 貸借対照表(バランスシート)とは?損益計算書との違いや読み方 - OBC
- 損益計算書とは?項目別の見方やチェックポイントを解説 - Freee
- 損益計算書(P/L)とは?各項目の見方をわかりやすく解説|mycard
- 損益計算書とは何か~初心者にもわかりやすく解説
- 損益計算書(P/L)の見方超入門:初心者でも30分で理解できる!
- 損益計算書(P/L)とは?項目の見方や作り方、分析のポイントを解説
- 損益計算書(P/L)の読み方とは?計算式や見るべきポイントも紹介
- 損益計算書(PL)とは?読み方や項目の見方を初心者向けに解説