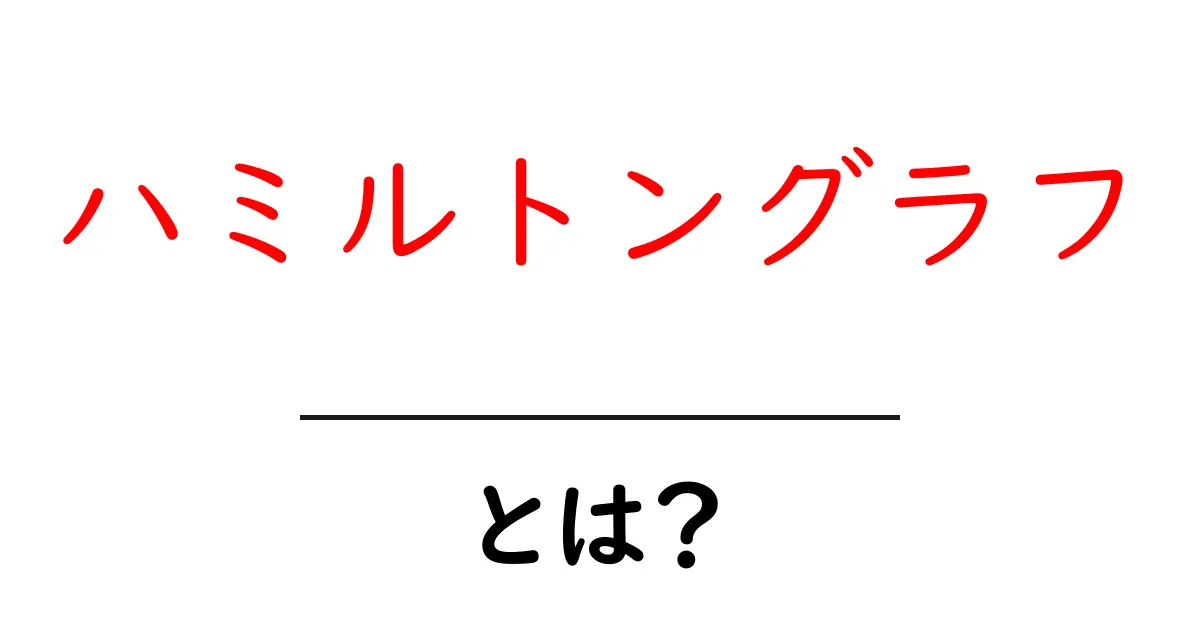

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
ハミルトングラフ・とは?
グラフ理論という数学の分野で使われる用語です。グラフとは点とそれを結ぶ辺の集まりのこと。ハミルトングラフとは すべての点を一度ずつ訪れる道や回路が存在するグラフのことを指します。
ここで覚えておきたい2つの用語を紹介します。ハミルトン路は すべての点をちょうど一度ずつ通る道、ハミルトン回路は始点に戻る 閉路ですべての点を訪問する道のことです。
次に具体的な例を見てみましょう。3つの点を使って作る三角形のグラフは ハミルトン回路を持ちます。なぜなら、3つの点を順番に訪れて最後に始点に戻せば、すべての点を一度ずつ通ることになるからです。
別の例として、一直線に並んだ4つの点だけを結んだグラフを考えると、ハミルトン路は存在しますが ハミルトン回路はありません。端の点に戻ることができないからです。
このように ハミルトングラフは「すべての点を訪問する道」をグラフが持つかどうかで決まります。実際にはグラフが大きくなると自約の判定が難しくなります。研究者は特定の条件のもとで ハミルトン回路があるかを調べるコツをいくつか提案していますが、一般にはすべてのグラフについて簡単に答えを出すのは難しい問題です。
まとめ
ハミルトングラフとは何かを、身近な例で理解することが第一歩です。点と辺の関係を追いかけながら、すべての点を訪問する道があるかを考える練習をしてみてください。難しさはありますが、基本を押さえれば、グラフ理論の世界がぐっと身近になります。
実生活の例として、迷路を解くときの考え方や、路線図を計画するときのヒントとして役立つことがあります。友達を順番に訪問する計画を立てるときにも ハミルトン思考の考え方を活かせます。
ハミルトングラフの同意語
- ハミルトン回路を持つグラフ
- グラフに、全ての頂点を1周して戻る閉路(ハミルトン回路)が存在する性質を指します。
- ハミルトン回路を含むグラフ
- グラフの中にハミルトン回路が存在することを意味します。
- ハミルトン性を持つグラフ
- グラフがハミルトン性(ハミルトン回路を持つ性質)を有することを指す表現です。
- ハミルトン性グラフ
- ハミルトン性を持つグラフを指す表現で、ハミルトングラフの別称として使われることがあります。
- ハミルトン性を有するグラフ
- 同義。ハミルトン性を有するグラフという意味です。
- ハミルトン性を満たすグラフ
- 同義。ハミルトン性を満たす、すなわちハミルトン回路を持つグラフを指します。
- 全頂点を巡るハミルトン閉路を含むグラフ
- グラフに、全ての頂点を巡回する閉路(ハミルトン閉路)が含まれることを表します。
ハミルトングラフの対義語・反対語
- 非ハミルトングラフ
- ハミルトン巡回を含まないグラフ。すべての頂点を一度ずつ訪れて元の頂点に戻る、ハミルトン巡回が存在しないことを意味します。
- ハミルトン巡回を含まないグラフ
- 同義表現。グラフにハミルトン巡回が存在しないことを示します。
- ハミルトン性を欠くグラフ
- ハミルトン性(全頂点を一周する巡回が存在する性質)を満たさない、すなわちハミルトン巡回を持たないグラフを指します。
- ハミルトン性を持たないグラフ
- ハミルトン巡回を含まない状態のグラフ。呼び方の一つ。
- 非ハミルトン性グラフ
- ハミルトン性を欠く性質を持つグラフ。ハミルトン巡回が存在しないことを意味します。
ハミルトングラフの共起語
- ハミルトン路
- グラフのすべての頂点をちょうど1度ずつ訪れて終点と出発点が異なる、いわゆる頂点の巡回路のこと。
- ハミルトン回路
- グラフの全頂点を1度ずつ訪れて元の頂点に戻る閉路のこと。ハミルトングラフの核心的な性質です。
- ハミルトン性
- グラフがハミルトン路またはハミルトン回路を含む性質のこと。グラフがハミルトン性を持つかどうかを問います。
- グラフ理論
- 頂点と辺からなる構造を扱う数学の分野。ハミルトングラフはこの分野の重要なトピックです。
- 頂点
- グラフの基本要素の点。辺をつなぐ対象で、英語では vertex(複数は vertices)。
- 辺
- グラフの基本要素の線。頂点同士を結ぶ接続部分で、英語では edge。
- 次数
- ある頂点に接続する辺の数のこと。ハミルトングラフの性質を判断する指標の一つです。
- 連結性
- グラフが1つのまとまりとして連結している性質のこと。ハミルトン性の議論にも関連します。
- 有向グラフ
- 辺に向きがついたグラフのこと。ハミルトン路・回路には有向版も存在します。
- NP完全
- ハミルトン路・ハミルトン回路問題が解くのが難しいとされる計算複雑性のクラス。現実的には近似解法が用いられます。
- 計算複雑性
- 問題を解くのに必要な計算量の難しさを示す概念。ハミルトン問題は一般に難解とされます。
- 巡回セールスマン問題
- すべての都市を一度ずつ訪れて元の出発点へ戻る最短経路を求める問題。ハミルトン回路の最適化版として広く知られています。
- サイクル
- 頂点を順につなぎ、最後に元の頂点へ戻る閉路のこと。ハミルトン回路は特定のサイクルの一種です。
- 閉路
- グラフ内で始点と終点が同じになる道のこと。ハミルトン回路は特別な閉路の一例です。
ハミルトングラフの関連用語
- ハミルトングラフ
- グラフ G が、すべての頂点を1度ずつ訪れるハミルトン回路を含む場合、そのグラフをハミルトングラフと呼ぶ。
- ハミルトン回路
- グラフの頂点をすべてちょうど1度だけ訪れて元の頂点に戻る閉路のこと。
- ハミルトン路
- グラフのすべての頂点をちょうど1度だけ通過する簡単な路のこと。始点と終点が異なることが多い。
- ハミルトン性
- グラフがハミルトン回路を持つ性質のこと。
- トレース可能グラフ
- ハミルトン路が存在する、つまりすべての頂点を一度通る道があるグラフのこと。
- ハミルトン連結グラフ
- 任意の2頂点を端点とするハミルトン路が存在するような、非常に強いハミルトン性を持つグラフ。
- パンシックグラフ
- グラフが長さ3からnまでのすべての長さのサイクルを含むようなグラフのこと。
- ハミルトン分解
- グラフの辺を互いに重ならないハミルトン回路に分解すること。条件が揃う正則グラフなどで成り立つことが多い。
- Diracの定理
- グラフの頂点数 n に対して最小次数 δ(G) ≥ n/2 を満たすと、そのグラフはハミルトンになるという十分条件。
- Oreの定理
- 非隣接頂点 u, v に対して deg(u) + deg(v) ≥ n が成り立つと、そのグラフはハミルトンになるという十分条件。
- Bondy-Chvátalの閉包定理
- 非隣接頂点の次数和が n 以上になるペアを辺として追加する閉包操作を繰り返すと得られる閉包グラフがハミルトンであるなら、元のグラフもハミルトンである、という関係。
- 閉包
- Bondy-Chvátal の閉包操作のこと。条件を満たす非隣接頂点間に辺を追加していく操作。
- 非ハミルトングラフ
- ハミルトン回路を持たないグラフのこと。
- ペーテルソン図形
- 有名な小さな非ハミルトン3正則グラフの例。ハミルトン性を持たないことが示されている。
- ハミルトン路問題
- グラフにハミルトン路が存在するかを判定する問題。NP完全であることが知られている。
- ハミルトン回路問題
- グラフにハミルトン回路が存在するかを判定する問題。NP完全であることが知られている。
- NP完全性
- ある問題が NP に属し、かつ他の NP 完全問題への多項式還元が可能であることを意味する、計算複雑性のクラス。
- Tutteの定理
- 4連結平面グラフは必ずハミルトンであるという重要な定理。



















