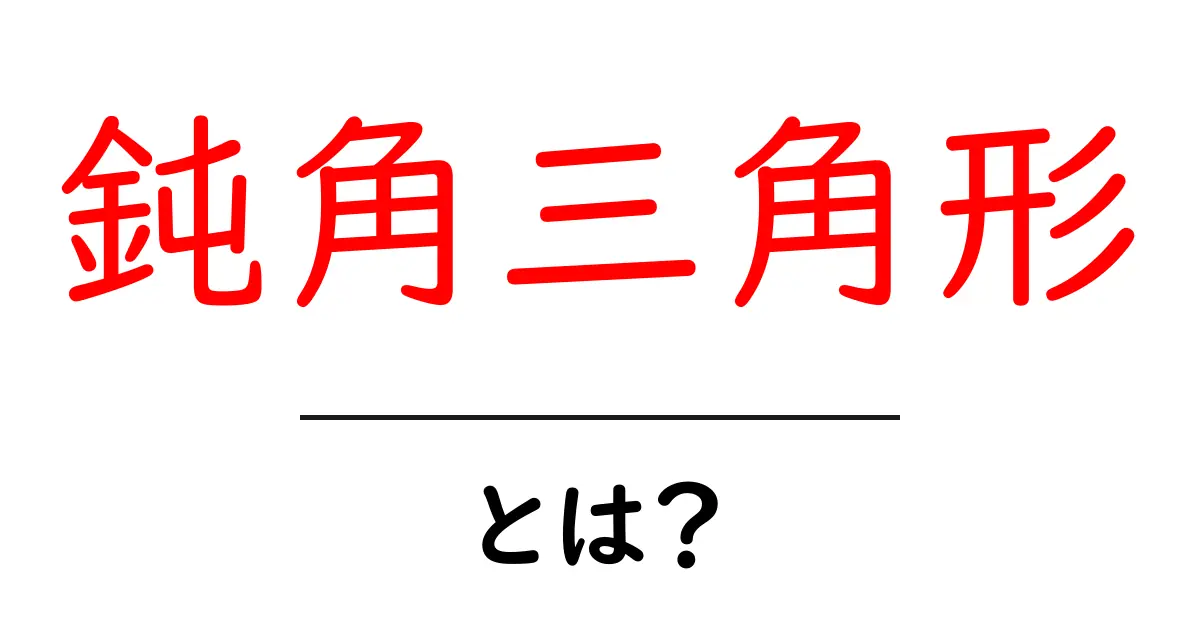

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
鈍角三角形・とは?
鈍角三角形とは一つの角が 90度を超える三角形のことです。
この三角形ではもう一つの角が 鋭角(90度未満)で、もう一つの角も 鋭角であることが多いです。三角形の内角の和は常に 180度なので鈍角の分だけ他の二角の和が調整されます。
基本の性質
長さの関係:鈍角を挟む辺は通常最も長い辺になります。つまり鈍角の対辺は三角形の中で最大の辺です。
角の大きさを決めるときは各角の和が 180度になることを思い出してください。鈍角があると他の二角の和は 90度未満になることが多いですが必ずしもそうとは限りません。
具体的な性質を表す表
例を見てみよう
例として角度が 120度・30度・30度の三角形を考えます。120度が鈍角であり、他の二つの角は合計 60度です。長さの関係としては 120度の対辺が最も長くなることが多いです。実際に図を描くときは底辺を取り高度を求めると面積を求めやすくなります。
直角三角形との違い
直角三角形にはちょうど 90度の角がありますが、鈍角三角形にはその角がなく代わりに 90度を超える角があります。
見分けるときのポイント
三つの角のうち どれか一つが 90度を超えるときに鈍角三角形と呼びます。図を描くときは一番大きな辺がどの角の対辺かを確かめるのも有効です。
まとめ
鈍角三角形とは ある角が 90度を超える三角形です。三角形の角の和は 180度で、長さの関係としては 鈍角の対辺が最も長いことが多いです。これらの性質を使えば図形の判断や問題の解法が進みます。
鈍角三角形の関連サジェスト解説
- 鋭角三角形 鈍角三角形 とは
- 鋭角三角形 鈍角三角形 とは、三角形の角の大きさで分類する基本的な考え方のひとつです。三角形には三つの角があり、それぞれの角の大きさを比べると、鋭角三角形と鈍角三角形のほかに直角三角形があります。ここでは鋭角三角形と鈍角三角形がどう違うのか、どう見分けるのか、実生活のイメージとともに学びます。\n\n鋭角三角形は、三つの角のすべてが90度より小さい三角形です。たとえば三角形の角度が50度・60度・70度なら、すべてが90度未満なので鋭角三角形です。内角の和は常に180度なので、50+60+70=180となります。鈍角三角形は、1つの角が90度を超え、残りの2つの角はそれぞれ90度未満のときに該当します。例えば120度・30度・30度なら、1つの角が大きく、それ以外は小さいため鈍角三角形です。直角三角形は90度の角を1つもつ三角形で、鋭角三角形と鈍角三角形のどちらにも該当しません。\n\n見分けるポイントとしては、角度の大きさを頭の中で想像する方法が分かりやすいです。もう一つのコツは、与えられた2つの角から3つ目の角を求め、全体が180度になることを確かめることです。たとえば、ある三角形の2つの角が45度と40度なら、3つ目は95度となり鈍角三角形であることがすぐ分かります。逆に、50度・60度が並ぶと、3つ目は70度となって鋭角三角形になります。\n\nこの知識は図形を勉強するときの基礎となります。文章問題や幾何の証明問題で角の関係を扱う際、鋭角・鈍角の区別が解法の手がかりになる場面が多いです。最後に覚えておくべき要点は「内角の和は180度」「鋭角三角形はすべての角が90度未満」「鈍角三角形は1つの角が90度を超える」という三点です。
鈍角三角形の同意語
- 鈍角三角形
- 一つの内角が90度を超える三角形。典型的に他の二つの角は鋭角で、合計は90度未満になる。
- 鈍角を持つ三角形
- 三角形の内角のうち、一つが鈍角(90度より大きい角)である三角形。
- 一つの角が鈍角である三角形
- その三角形には内角の中に鈍角が一つ存在するという説明表現。
- 一つの角が90度を超える三角形
- 内角の一つが90度を超える性質を表す表現。
- 90度を超える角を1つ含む三角形
- 1つの角が90度を超える角であることを示す別表現。
- 片方の角が90度を超える三角形
- 片方(1つ)の角が鈍角であることを示す言い換え表現。
- 鈍角を含む三角形
- 一つ以上の鈍角を含む三角形という意味の表現。
鈍角三角形の対義語・反対語
- 鋭角三角形
- すべての内角が90度未満の三角形。各角が鋭角で、典型的には全体的に角が小さい形です。
- 直角三角形
- 一つの内角がちょうど90度で、残りの二つの角はそれより小さい三角形。鈍角を持たない構成です。
- 非鈍角三角形
- 鈍角を含まない三角形。つまりすべての内角が90度以下で、鋭角と直角の組み合わせから成り立ちます。
- 正三角形
- 三辺がすべて等しく、各内角が60度の三角形。鈍角は存在せず、鋭角三角形の典型例のひとつです。
鈍角三角形の共起語
- 鈍角
- 鈍角とは、角の大きさが90度より大きい角のこと。三角形に一つだけ存在するのが普通です。
- 三角形
- 三角形は3つの辺と3つの角からなる平面図形です。鈍角三角形はこの中のひとつのタイプです。
- 鋭角
- 鋭角は角の大きさが90度未満の角のこと。鈍角三角形の他の2つの角は通常鋭角です。
- 直角
- 直角はちょうど90度の角のこと。直角三角形は別の三角形のタイプです。
- 内角の和
- 三角形の3つの内角の和は必ず180度です。
- 最長辺
- 鈍角がある三角形では、鈍角の対辺(反対側の辺)が三角形の中で最長の辺になります。
- 対辺
- ある角に対になる辺のこと。鈍角の対辺は最長になる性質があります。
- 余弦定理
- 余弦定理は、三角形の辺と角の関係を表す法則で、辺の長さと角の大きさを結びつけます。
- コサインの法則
- コサインの法則(余弦定理の別名)は、a^2+b^2−2ab cos C = c^2 のように三角形の辺と角を結びつけます。鈍角では cos C が負になります。
- ピタゴラスの定理
- 直角三角形で成り立つ関係ですが、鈍角三角形では長辺の二乗が他の二辺の二乗和より大きくなることがあります(c^2 > a^2 + b^2)。
- 外心
- 外心は三角形の外接円の中心で、鈍角三角形ではこの外心が三角形の外側に位置します。
- 外接円
- 三角形の頂点がすべて等距離になる円。鈍角三角形では外心が三角形の外側にあります。
- 高さ
- 三角形の高さ(底辺に対してから頂点を引いた垂線)は、鈍角の頂点から引くと辺の外側に落ちることがあります。
- 底辺
- 基準に使われる辺のこと。問題に応じて底辺を選び、そこから高さを求めます。
- 外角
- 三角形の各角の外側にできる角。内角の補角として180度になる性質を持ちます。
- 座標平面
- 座標平面上で頂点の座標を用いて鈍角三角形の性質を計算する場合に使います。
- 底辺と高さの公式
- 底辺と高さを用いた面積公式(Area = 底辺×高さ÷2)は、どの三角形にも適用できます。
鈍角三角形の関連用語
- 鈍角三角形
- 1つの内角が90度より大きい三角形。残りの2つの角の和は180°−その鈍角で、合計は180°です。鈍角の対辺は一般に最も長い辺となり、外心は三角形の外側に位置します。
- 鋭角三角形
- すべての内角が90度未満の三角形。
- 直角三角形
- 1つの内角がちょうど90°。この場合、斜辺と呼ばれる最も長い辺が対辺となります。ピタゴラスの定理 a^2 + b^2 = c^2 が成り立ちます。
- 最も長い辺
- 三角形の3辺のうち、最も長い辺のこと。鈍角三角形では必ず鈍角の対辺になることが多いです。
- 対辺
- 三角形で、ある角に対して反対側にある辺のこと。鈍角の対辺は通常最も長い辺になることが多いです。
- 斜辺
- 直角三角形において、直角の対辺。最も長い辺です。
- 外心
- 三角形の外接円の中心点。
- 外接円
- 三角形をすべての頂点が接する円。
- 内心
- 三角形の内接円の中心点。
- 内接円
- 三角形に内接する円。
- コサインの法則
- 任意の三角形で、辺の長さと対角の余弦の関係を表す法則。c^2 = a^2 + b^2 − 2ab cos C。C が鈍角のとき cos C は負となり、c^2 > a^2 + b^2 となることがある。
- サインの法則
- 任意の三角形で、辺の長さは対する角の正弦に比例する法則。a / sin A = b / sin B = c / sin C = 2R。
- ヘロンの公式
- 3辺 a, b, c から三角形の面積を求める公式。s = (a+b+c)/2、S = sqrt[s(s-a)(s-b)(s-c)]
- 内角の和
- 三角形の内部角の和は常に180°である。
- 辺の長さによる鈍角判定
- 最も長い辺を c とすると、c^2 > a^2 + b^2 なら対角は鈍角。c^2 = a^2 + b^2 なら直角、c^2 < a^2 + b^2 なら鋭角。
鈍角三角形のおすすめ参考サイト
- 三角形とはどんな図形?辺の長さ・角度の定理や種類を知ろう
- 鈍角三角形とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書
- 鈍角三角形とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書
- 【中2数学】鋭角・鈍角とはいったい何ものなのか?? | Qikeru



















