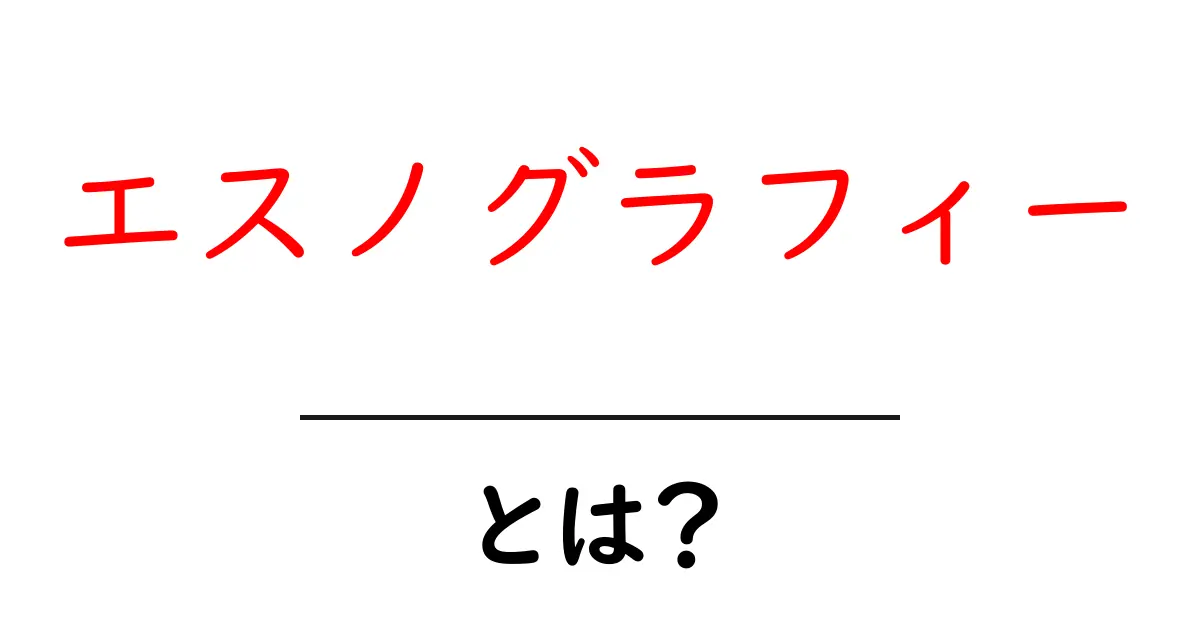

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
エスノグラフィー・とは?
エスノグラフィーとは人々の暮らしや文化をじかに観察して記録する研究の方法です。研究者は現場に出て、実際の生活の中に入り込み人々の言葉や行動を観察します。長い時間をかけて現場を理解することが大切で、数字だけではなく言葉の意味や感情も重視します。
どうやって行うのか
研究を始める前にはテーマを決め、研究の目的と質問を明確にします。次に現場を選び、許可を得て観察を始めます。観察には参加観察と非参加観察の2つのやり方があります。参加観察は研究者が現場の活動に参加して記録します。非参加観察は外から観察する方法です。
データの主な集め方として、ノートをとる、人々の会話を記録する、写真や動画を使うなどがあります。言葉だけでなく視覚的な情報も大切ですが個人のプライバシーに配慮します。
実践の例
例として地域の祭りを対象にするエスノグラフィーがあります。研究者は祭りの準備から開始し、道具の使い方、参加する人々の行動や言葉を記録します。時間の経過とともに、なぜその行動が生まれるのかを分析します。
倫理と注意
倫理はとても大切です。相手のプライバシーを尊重し、名前を仮名にする、同意を得る、データを安全に保管するなどの配慮が必要です。
データの分析と結論
集めた情報は整理して共通のテーマを見つけ出します。意味のあるパターンを見つけることで、現場で起きていることの理由が見えてきます。結論は現場の言葉で説明することが多く、数字だけでは伝わりにくいニュアンスも伝えられます。
エスノグラフィーと他の研究方法の違い
アンケート調査や実験と比較すると、エスノグラフィーは長期間現場を観察する点が特徴です。人の暮らしの複雑さや文化的背景を理解するのに向いています。
要点のまとめ
エスノグラフィーは現場での観察と対話を通して、人々の生活の意味を深く知る研究方法です。長期の現場経験と倫理的配慮が不可欠です。
よくある誤解を解く
エスノグラフィーは「ただの観察日記」ではありません。計画的な研究デザインと分析の枠組みが必要です。データの意味を探る作業であり、研究者の視点や背景が研究に影響を与えることもあります。
まとめ
エスノグラフィーは人と文化を深く理解するための強力なツールです。現場での長期観察、倫理的配慮、そして丁寧な分析が成功の鍵となります。
データの記録と分析のコツとして、現場ではまず事実を素直に記録し、後で意味づけを行います。引用の正確さ、匿名化、データの保管を徹底しましょう。
エスノグラフィーの同意語
- 民族誌
- エスノグラフィーの日本語表現のひとつ。日常生活や文化を対象とし、現場での観察・記述を中心に行う研究を指します。
- 民族誌学
- エスノグラフィーを学問として体系化した分野。人類学の一分野で、文化や社会の記述・分析を目的とします。
- 民族誌研究
- エスノグラフィー的な手法で行われる研究全般を指します。現地での観察・対話・資料の統合を通じて文化を解釈します。
- フィールドワーク
- 研究者が現場に赴き、自然な社会状況の中でデータを収集する方法。エスノグラフィーの基本的な実践形態。
- 現地調査
- 研究対象の場所で直接情報を収集する調査。観察・インタビュー・資料調査を組み合わせます。
- 参加観察法
- 研究者が対象社会の活動に参加しつつ観察する方法。最も典型的なエスノグラフィーの手法の一つ。
- 参加観察
- 現場の生活へ参加して観察する実践。手法名の短縮形として使われることが多い。
- 実地調査
- 現場での直接的なデータ収集を意味します。野外での観察・対話・記録が中心です。
- 文化人類学的調査
- 人類学の視点から文化を調べる調査。エスノグラフィーの方法論を含むことが多い。
- 現場研究
- 現場で行われる調査・研究全般を指す語。フィールドワークと同義または近義として用いられます。
エスノグラフィーの対義語・反対語
- 定量研究
- エスノグラフィーが質的・現場重視のアプローチであるのに対し、定量研究は数値データを大量に集めて統計的に分析し、一般化を狙う研究手法です。現場の細かな文脈理解より、傾向や相関を重視します。
- デスクリサーチ(デスクワーク調査)
- 現地へ赴かず、文献や既存データを分析して結論を導く研究。フィールドワークを伴わない点でエスノグラフィーの対極に位置します。
- 二次データ分析
- 新たな現場観察を行わず、既に存在するデータを再分析して結論を出す研究。現場体験・参与観察といったエスノグラフィーの特徴を避けます。
- 客観主義的研究(ポジティビズム)
- 主観的解釈を最小限にし、客観性と測定可能性を重視する学術姿勢。エスノグラフィーの主観的文脈理解と対照的です。
- 普遍主義的研究
- 特定の文化や文脈に依存せず、普遍的原理や法則の発見を目指す研究。エスノグラフィーの文脈依存性と対比されます。
- 仮説検証中心の研究
- 予め仮説を設定し、データを使って検証する研究デザイン。現場で文脈を深く理解するエスノグラフィーとは性質が異なります。
- 調査票・サーベイ中心の量的調査
- 質問紙やオンライン調査などを用い、統計的に分析して結果を一般化するアプローチ。現地の参与観察や深い文脈理解を重視するエスノグラフィーとは異なります。
- エティック視点の研究(外部者の視点で分析する研究)
- 外部・異文化の視点から比較・分析を行う研究。エスノグラフィーが内的文脈・文化理解を重視するのに対し、外部視点に偏る研究の対義です。
エスノグラフィーの共起語
- 参加観察
- 研究者が現場に入り込み、観察と交流を通じてデータを収集するエスノグラフィーの基本手法。
- フィールドワーク
- 長期間にわたり現場で暮らし・働き・交流しながらデータを集める実地調査。
- 民族誌
- 文化や社会の生活を詳しく描写する、エスノグラフィーの代表的成果物。
- 文化人類学
- エスノグラフィーの学問領域で、異文化・社会を理解・比較する分野。
- 人類学
- 人間とその文化・社会を研究する学問全体の総称。
- 質的研究
- 数値以外の言語・行動・文脈をもとに理解を深める研究形式。
- 研究方法
- データ収集・分析の設計と実践全般を指す概念。
- データ収集
- 観察・インタビュー・文献などを組み合わせて情報を集める作業。
- フィールドノート
- 現場での気づきや発見を記録する専門的ノート。
- 現場観察
- 現場で直接状況を観察する基本的な活動。
- インタビュー
- 参加者の言葉を深掘りする対話形式のデータ収集。
- 言語データ
- 会話・語り・テキストなど、言語に関する情報。
- コード化
- 収集したデータをテーマ別に分類・整理する作業。
- テーマ化
- データから主要な主題・パターンを抽出する作業。
- 三角測量
- 複数のデータ源・方法を組み合わせて証拠の信頼性を高める手法。
- 濃密な記述
- 現地の文脈・意味を詳細に描写して理解を深める表現。
- 信頼性
- 結果の安定性・再現性を高めるための検証・透明性の確保。
- 妥当性
- 観察結果が現象を適切に説明しているかを評価する観点。
- 倫理的配慮
- 調査に伴う倫理的な問題を事前に検討・配慮すること。
- 研究倫理
- 研究活動における倫理規範の遵守。
- 倫理審査
- 研究計画を審査機関に提出して承認を得る手続き。
- インフォームド・コンセント
- 参加者の自発的な同意を得る手続き。
- 現地化
- 対象をその文化・文脈に合わせて理解すること。
- 文脈化
- 現象を社会・歴史・文化の文脈の中で解釈すること。
- 共同体研究
- 地域社会と協働して進める研究アプローチ。
- 参加型研究
- 研究対象の人々と共に研究を推進するアプローチ。
- 民族誌的記述
- 調査対象の文化・社会を詳述する記述表現。
- 民族誌的報告
- 調査結果を民族誌の形式で報告する表現・形式。
- 現地語りデータ
- 現地の人々の語りをデータとして扱うこと。
- 現地サイト
- 調査の実施場所となる現場・現地の場所。
- データ分析
- 収集したデータを整理・解釈する分析プロセス。
- 理論的枠組み
- データ解釈を導く理論的な土台・前提。
- 文化相対主義
- 他文化を自文化の価値観で判断せず、文脈の中で理解する立場。
- リフレクシビティ
- 研究者自身の立場・影響を自覚し、分析に反映させる姿勢。
エスノグラフィーの関連用語
- エスノグラフィー
- 文化や社会の生活世界を理解するため、現地での長期滞在・観察・インタビュー・記録を組み合わせて記述する定性的研究手法。
- 民族誌
- エスノグラフィーの成果物。対象となる集団の習慣・信念・日常を詳しく描写した報告書や記述のこと。
- 参与観察
- 研究者が観察対象の場に参加し、活動に身を置きながらデータを収集する基本的な方法。
- フィールドワーク
- 現地の自然な場でデータを収集する調査活動。観察・インタビュー・資料収集を組み合わせる。
- 現地調査
- 現地での観察・インタビュー・資料収集を通じて data を得る調査手法。
- 文化人類学
- 人間の文化を比較・解釈する学問分野。エスノグラフィーはその主要な研究手法の一つ。
- 反省的実践
- 自分の立場・偏りが研究結果に影響することを自覚し、研究過程で透明にする姿勢。
- 研究倫理
- 被研究者の権利と尊厳を守るための原則。適切な同意、匿名化、データ保護などを含む。
- インフォームド・コンセント
- 研究参加に際して目的・方法・リスクを説明し、自由意思で同意を得るプロセス。
- フィールドノート
- 現地での出来事・発言・観察内容を時系列・文脈とともに記録するノート。
- 半構造化インタビュー
- 一定の枠組みを持ちながら、回答の自由度を高く保つ対話形式のインタビュー。
- アーカイブ・記録
- 現地の文書・写真・行政記録・日誌などを収集・整理する作業。
- データ分析
- 収集した定性的データを整理・分類・解釈して意味を引き出す作業。
- コーディング
- テキストデータを意味カテゴリに分類し、コードを付与する作業。
- テーマ化
- コード化したデータから主要なテーマを抽出して整理する過程。
- 三角測量
- 複数のデータ源・方法を組み合わせて検証し、結論の信頼性を高める手法。
- エスノグラフィックデータ
- 観察記録・インタビュー記録・録音・映像など、現地で得られたデータ群。
- 言語・談話データ
- 現地語の話し言葉・文書・談話の内容を分析対象とするデータ。
- 厚い記述
- 現地の生活世界の意味と文脈を、豊富な描写で表現する記述スタイル(Geertz に由来する概念)。
- 共同研究
- 研究者と対象コミュニティが協力して設計・実施・成果を共有する参加型の研究アプローチ。
- 匿名化・機密性
- 個人を特定できる情報を伏せ、データの取り扱いを厳格に管理すること。
- 倫理審査
- 研究計画が倫理基準を満たすかを審査する機関(例:倫理審査委員会)の承認を得る手続き。
- 解釈的人類学
- データの意味を解釈的に理解し、現地の意味世界を重視するアプローチ。
- 現場の情報公開と引用
- 現地語の引用や現場情報を適切に公開・引用する透明性と尊重の実践。
- 文化コンテキスト理解
- 習慣・信仰・制度などの背景となる文化的文脈を理解する力。
- 研究計画・設計
- 研究の目的・対象・方法・倫理対応を体系化した事前計画。
- 対象集団への還元
- 研究成果を参加者や地域に還元し、恩恵を共有することを重視する姿勢。
- 引用と倫理的取り扱い
- 現地語・個人名の引用時には同意と配慮をもって扱うこと。
- 研究成果の透明性
- 方法・データ・分析過程を他者が検証できるよう公開・明示する姿勢。
エスノグラフィーのおすすめ参考サイト
- エスノグラフィーとは?【意味をわかりやすく解説】具体例 - カオナビ
- エスノグラフィとは?定義や注目される背景、事例などを紹介
- エスノグラフィー (ethnography) とは? 調査の方法やメリット
- エスノグラフィーとは?活用ポイントや事例をご紹介
- エスノグラフィーとは|簡単解説 - QiQUMOコンテンツ
- エスノグラフィとは – 【公式】 - 定性調査 - アスマーク
- エスノグラフィーとは?意味やビジネスで活用するやり方を徹底解説



















