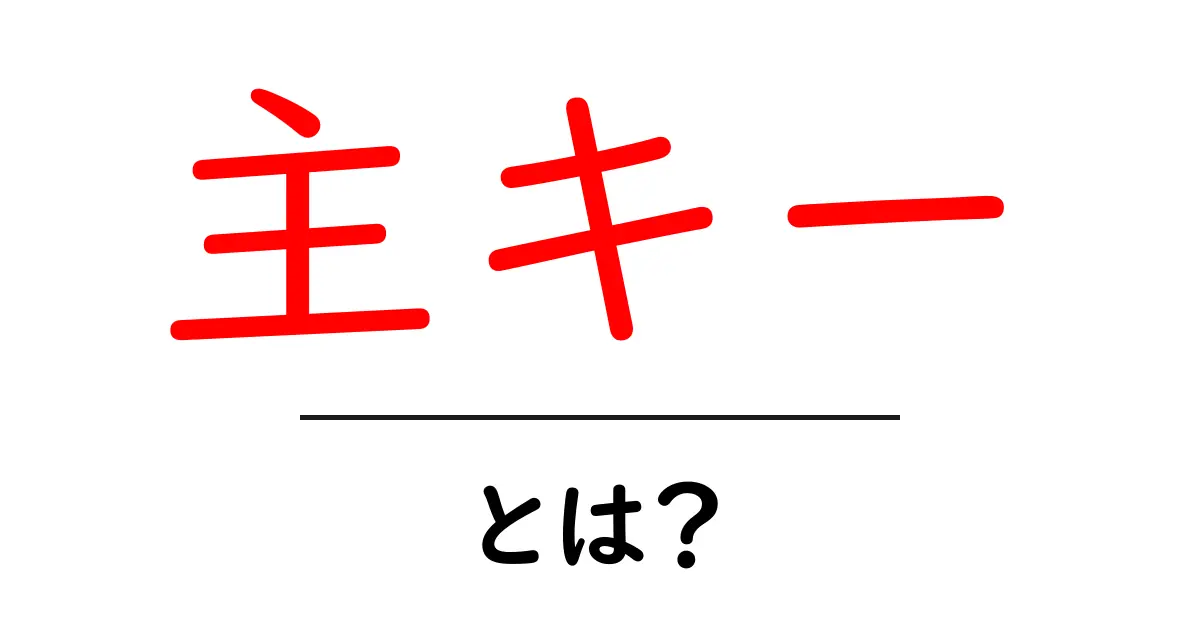

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
主キーとは? 基本の意味
主キーとは、データベースの表(テーブル)の中で、各行を一意に識別するための「鍵」のことです。ここでの「一意に識別」とは、同じ行が二つ現れないようにすることです。例えば、学校の生徒名簿を例に挙げると、生徒ごとに番号(ID)を付けると、それぞれの行が別々の値になります。これが主キーの役割です。
通常、主キーは1つの列で表されます。場合によっては、複数列を組み合わせて「複合主キー」を作ることもあります。
主キーの特徴
特徴1: 各行を一意に識別すること。
特徴2: NULL(不明な値)は許されないこと。
特徴3: 基本的にはテーブルごとに1つ用意しますが、用途によっては複数の候補キーの中から1つを主キーとすることがあります。
自然キーと代理キー
主キーには、自然キーと代理キーの考え方があります。自然キーは、自然に存在する識別子(例: 学生番号、社員番号など)です。代理キーはデータベース側で新しく作るIDで、必ずしも現実の情報と同じではありません。実務では安定性や長期的な運用を考え、代理キーを主キーとして使うことが多いです。
SQLでの基本的な使い方
以下は概念の説明のみです。実際の SQL では、CREATE TABLE のときに主キーを設定します。例として「id」という列を主キーとするStudentsテーブルを想定します。
例として、id 列を主キーに設定する場合、id は整数型(INT)で、他の列は name や birth_year などです。主キーを設定することで、同じ id の行は作られないようになります。
外部キーとの関係
主キーは、別の表とつながる「外部キー」として使われることが多いです。外部キーは、他の表の主キーを参照します。これにより、表と表の間の関係性を正しく保つことができます。
表の例と簡単な表
よくある誤解とポイント
「主キー=人の名前」などと考えがちですが、同じ名前の人は複数います。主キーとして名前を使うと重複や変更に弱くなるため避けるべきのケースが多いです。代わりに、id のような代理キーを主キーにすることが安全で一般的です。
まとめ
要するに、主キーとは表の各行を一意に識別する「鍵」です。値はユニークで NULL にはなりません。表同士の関係を作るために外部キーが使われ、実務では代理キーを主キーとする選択が多くあります。この記事を読んで、データベースの基本的な考え方がつかめるようになると良いでしょう。
主キーの関連サジェスト解説
- 主キー 外部キー とは
- データベースとは、情報を整理しておく箱のようなものです。学校の名簿や授業の履修情報を別々の表で管理しても、後で人を探したり、誰がどの授業を取っているか知りたくなることがあります。そんなときに役立つのが主キーと外部キーです。主キーとは、表の中で“その行を一意に特定するための番号”のようなものです。たとえば学生テーブルでは、各学生に一人ずつ割り当てられる student_id が主キーになります。主キーには“同じ値を使えない”(重複禁止)ことと“空っぽにしてはいけない”(NOT NULL)ことが求められます。一方、外部キーは“別の表の主キーを指す鍵”です。外部キーを使うと、2つ以上の表を結びつけて情報を関連づけることができます。例として、学生テーブルと履修テーブルを考えましょう。履修テーブルには student_id(外部キー)と class_id(外部キー)があります。これらは、それぞれStudents表の student_id と Classes表の class_idを参照します。こうして「この学生はこの授業を取っている」という関係をデータベース上に作るのです。外部キーは参照整合性を保つ役割もあり、参照している値が消えたり変わったりしないように守ってくれます。初心者には、2つの表をつなぐ“橋”のようなイメージで捉えると理解しやすいです。実際の SQL では、CREATE TABLE で主キーと外部キーを設定します。例として、学生テーブルと授業テーブル、履修テーブルを組み合わせると、データが重複せず、正しく結びついた状態を保つことができます。主キーと外部キーの考え方を知ることで、データを安全に整理・活用できるようになります。
- access 主キー とは
- access 主キー とは、データベースの表(テーブル)の中で“各行を一意に識別するための目印”となる列のことです。主キーとして使われる列は、同じテーブル内で値が絶対に重複しないように制約され、NULL(空の値)を含むこともできません。これにより、データの重複や混乱を防ぎ、別の表と正しくつながる基盤を作ります。たとえば Students という学生の表があり、StudentID という列を作るとします。StudentID が主キーになると、同じ StudentID を持つ学生は2人以上存在せず、他の表と結びつけるときの参照元として信頼できます。別の表には Enrollments という科目の履修表があり、ここで StudentID を外部キーとして参照させると、どの学生がどの科目を履修しているかを正確につなぐことができます。複数の列を組み合わせて主キーにする「複合主キー」も存在します。例えば、授業コードと学生IDの組み合わせを主キーにすることで、同じ科目を同じ学生が2回履修しても識別できるようになります。Access で主キーを設定する方法は主に2つです。1つ目はDesignビューで対象の列を選んでリボンの「Primary Key」ボタンをクリックする方法です。これにより、その列が主キーとして指定されます。複数列を主キーにしたい場合は、複数の列を選択してから同じボタンを押します。2つ目はSQLを使う方法で、ALTER TABLE 文や CREATE TABLE 文の中に PRIMARY KEY 制約を指定します。主キーを正しく設定する利点は、データの整合性を保ちつつ、他の表と安全に結合できることです。逆に、主キーを変更する際は関連する外部キーの参照にも影響が及ぶため、慎重に行う必要があります。初心者のうちは、まず単一列の主キーを作るところから始め、データの性質に応じて複合主キーの検討へと進めると良いでしょう。
- sql 主キー とは
- sql 主キー とは、リレーショナルデータベースのテーブルの中で、各行を一意に識別するための列または列の組み合わせのことです。この特徴があるおかげで、同じ行が2つ以上現れることを避けられ、データを正しく結びつけられます。主キーにはいくつかの大事な約束があります。まず、主キーの値は重複してはいけません。つまり、同じ値を持つ行を2つ作ることはできません。次に、主キーの値は空欄にしてはいけません。必ず何らかの値が入っている必要があります。さらに、主キーにはインデックスが自動的に作られることが多く、値を探すときにデータベースの検索が速くなります。1つのテーブルには原則として1つの主キーがありますが、複数の列を組み合わせて1つの主キーにする複合主キーもよく使われます。複合主キーは、複数の列の組み合わせが一意になる場合に適しています。主キーはテーブル同士をつなぐ手がかりにもなります。別のテーブルの列がこの主キーを参照することで、データの整合性を保ちながら関係を作れます。これを外部キーと呼びます。実務でよく見かける例として、students という表を考えます。id 列を主キーとし、name や age を他の列として持つとします。id は自動採番にしておくと、新しい生徒を追加するたびに自動で番号がふられ、重複や空欄を避けられます。具体的な SQL の例は次のとおりです。CREATE TABLE students ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), age INT );別の表として enrollments があり、student_id が students.id を参照します。複合主キーを使う例として、student_id と course_id の組み合わせを一意に定義する場合もあります。CREATE TABLE enrollments ( student_id INT, course_id INT, PRIMARY KEY (student_id, course_id), FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id) );
- テーブル 主キー とは
- テーブル 主キー とは、データベースの表(テーブル)でこの行を一意に決める目印のことです。テーブルには名前や年齢など多くの列が並びますが、主キーは各行を区別するための唯一の識別子になります。主キーには三つの大事な約束があります。第一に同じ値を二度使ってはいけないこと、第二に空欄にしてはならないこと、第三に同じテーブル内で重複してはいけないことです。例えば「学生」というテーブルを作るとき、id列を主キーにすると各学生に一つのidが割り当てられ、同じidを別の学生に使うことはできません。名前だけでは同姓同名の人がいて区別が難しい場合でも、idは必ず異なります。主キーがあると他のテーブルとつなぐときの道具、つまり参照の基準になります。別のテーブルからこの主キーを使って情報を引っ張ってくるときには外部キーという仕組みを使います。さらに実務では主キーを自動的に増える数字にしておくと便利です。要するに主キーはテーブルの正しい住所票の役割を果たし、データの重複を減らし、他の表とデータを確実に結びつけるための大切な仕組みです。
主キーの同意語
- プライマリキー
- テーブルの各行を一意に識別するための列または列の組み合わせ。NULLを許さず、テーブル内で値が重複しないように保証する制約。
- PK
- 英語表記の略称。プライマリキーと同じ意味で、テーブルの行を一意に識別するキー。
- Primary Key
- 英語表現。日本語では“プライマリキー”と同義。テーブルの行を一意に識別するためのキー。
主キーの対義語・反対語
- 代替キー
- 主キーとしては選択されていないが、ユニーク性を満たす別の候補キー。通常は主キーの代わりとして使われる可能性がある。
- 一意キー
- UNIQUE制約を満たすキー。テーブル内の値が重複しないことを保証するが、必ずしも主キーとして使われるわけではない。
- 候補キー
- テーブルの行を一意に識別する属性の集合で、将来主キーや代替キーとして採用される可能性がある。
- 外部キー
- 他のテーブルの主キーを参照するキー。自テーブル内の一意性を保証するためのものではなく、参照整合性を保つ役割。
- 自然キー
- ビジネスデータに基づく自然な識別子。 surrogateキーと対比されることが多い概念。
- 代理キー
- サロゲートキー。システムが自動的に生成する識別子で、ビジネス意味を持たず主キーとして用いられることが多い。
- 非主キー
- 主キー以外のキーの総称。テーブル内で主キー以外の属性をキーとして使う場合に該当。
- 複合キー
- 複数の属性を組み合わせて一意性を作り出すキー。単一属性の主キーではなく、複数属性の組み合わせを用いる場合に用いられる。
主キーの共起語
- 外部キー
- 別のテーブルの主キーを参照してテーブル間の関連を表し、参照整合性を保つためのキー。
- 候補キー
- テーブル内で一意に行を識別できる可能性のあるキーの候補。
- 代替キー
- 主キー以外の候補キー。実務では主キーとして選ばれないキー。
- 複合キー
- 複数の列を組み合わせて一意性を確保する主キー。
- 自動採番
- 新しい行に自動で連番などの値を割り当てる仕組み。主キーとして使われることが多い。
- サロゲートキー
- 自然キーを避けて人工的に作る主キー。安定性のために使われることが多い。
- 代理キー
- 自然キーの代わりに使う人工的なキー。
- 自然キー
- 現実のデータの属性をそのまま主キーとして使う考え方。変更や重複に注意。
- 一意制約
- 列の値が一意であることを保証する制約。主キーは自動的にこれを満たす。
- NOT NULL
- 列を空値にできない制約。主キーには通常適用される。
- インデックス
- 検索を速くするためのデータ構造。主キーにも自動で作成されることが多い。
- レコード
- テーブルの1行分のデータ。主キーで一意に識別される。
- テーブル
- データを格納する表。主キーで各行を一意に識別する。
- 正規化
- データの重複を減らし、整合性を高める設計思想。主キー設計も正規化の一部。
- 参照整合性
- 外部キーと主キーの関係でデータの整合性を保つルール。
- ER図
- Entity-Relationship図。エンティティの識別子として主キーが示される。
- PK
- 主キーを表す略語。設計資料でよく使われる。
主キーの関連用語
- 主キー
- テーブルの各行を一意に識別するための列(または列の組み合わせ)。NULLは許されず、他のテーブルから参照される場合の基準にもなる。
- 候補キー
- 主キーとして選べる可能性のある一意なキーの総称。複数存在することがあり、設計時に1つを主キーとして決定する。
- 代替キー
- 主キーとして選ばれなかった一意キー。主キーが使われなくなった場合の代替として機能することがある。
- サロゲートキー
- データの意味と直接関係しない、人工的に作られた主キー。例えば自動採番IDなど。
- 自然キー
- データ自体の意味に基づく一意キー。例: 社員番号、ISBNなど、意味を持つ値で識別するキー。
- 複合主キー
- 主キーを複数の列で構成するケース。例: (country_code, id) の組み合わせ。
- 外部キー
- 別のテーブルの主キーを参照する列。リレーションを作り、参照整合性を保つ。
- 外部キー制約
- 外部キーの値が参照先テーブルの主キーと一致することを強制するデータベースの制約。
- 一意性制約
- 列の値が全体で一意になることを保証する制約。NULLの扱いはDBMSによって異なる。
- UNIQUE制約
- 一意性を保証するための具体的な制約。いくつかのDBではUNIQUE KEYと呼ばれることもある。
- NOT NULL制約
- 列にNULLを入れられないようにする制約。主キーは自動的にNOT NULLが課される。
- 自動採番
- 新しい行に自動的に一意の値を割り当てる仕組み。MySQLのAUTO_INCREMENT、PostgreSQLのSERIAL、SQL ServerのIDENTITYなど。
- シーケンス
- 連番を生成する独立した仕組み。主キーや他の列の値を一意にする際に使われる。
- インデックス
- 検索を速くするデータ構造。主キーは通常インデックスを伴い、検索・結合が速くなる。
- クラスタ化インデックス
- データの物理的な並びとインデックスの並びを同じにするインデックス。主キーで作成されることが多い。
- 非クラスタ化インデックス
- データの物理的並びと別に作るインデックス。検索を速くするが更新コストが増える。
- 正規化
- データの重複を減らし、更新異常を防ぐ設計手法。主キーは正規化の核となる。
- 第一正規形(1NF)
- 各列の値が原子値であること。主キー設計の基本前提。
- 第二正規形(2NF)
- 1NFに加え、非キー属性が主キーの全ての候補キーに機能従属していること(部分従属の排除)。
- 第三正規形(3NF)
- 非キー属性間の推移的従属を排除。データの独立性を高める。
- 参照整合性
- 外部キーを介して参照元と参照先のデータの整合性を保つ性質。
- データベース設計
- 要件定義からER図作成、テーブル・列・キーの設計、正規化・インデックスの検討までの全体設計。
- リレーショナルデータベース
- テーブル間の関係性を前提とするデータベースの総称。主キーと外部キーが核となる。
- ER図
- エンティティ(実体)とリレーション(関係)を図示した設計図。
- テーブル
- データを格納する基本的な構造。列が属性、行がレコード。
- カラム/列
- テーブルの属性を表す列。主キーの一部になることもある。
- 行/レコード
- テーブルの1つのデータ行。主キーで一意に識別される。
主キーのおすすめ参考サイト
- 主キーとは - IBM
- 【SQL】プライマリーキーとは?ユニークキーとの違いなどを解説
- プライマリーキーとは?一意キー、外部キーとの違いも解説
- 主キーとは - IBM
- 【SQL】プライマリーキーとは?ユニークキーとの違いなどを解説
- プライマリーキーとは?一意キー、外部キーとの違いも解説
- 【SQL】主キーとは?選び方や設定方法をわかりやすく解説



















