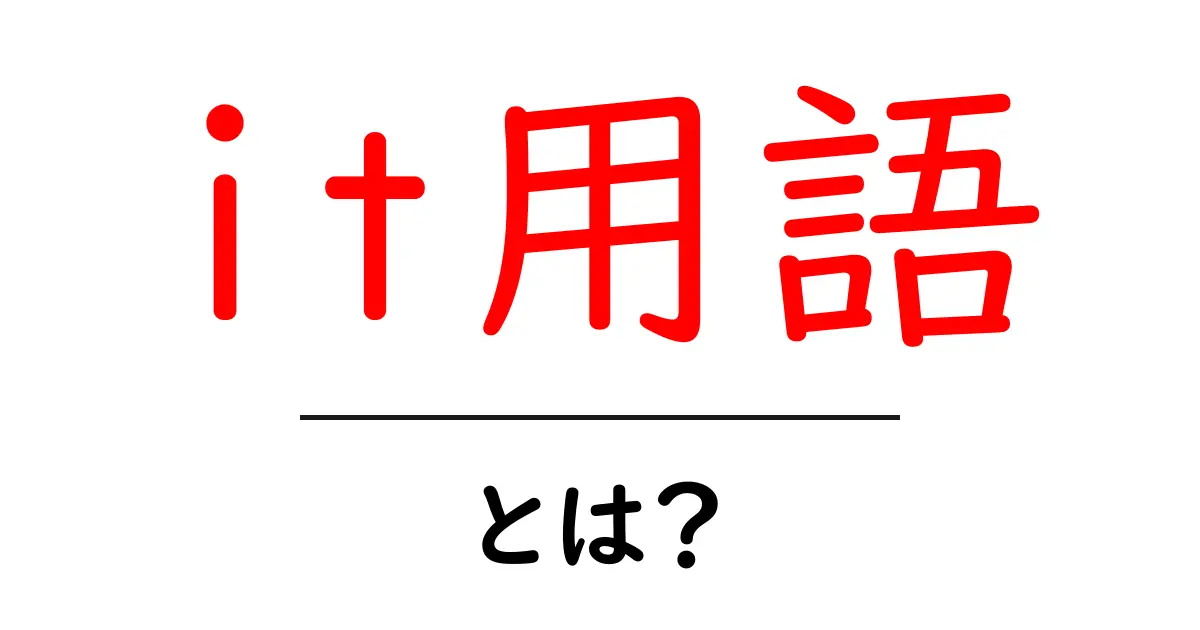

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
IT用語は情報技術の世界で使われる専門的な言葉です。パソコンやスマホ、インターネットを使うとき、耳にする言葉がたくさんあります。でも意味が分からないと、困る場面が出てきます。この記事では中学生にも分かるように、IT用語の基本をやさしく解説します。
IT用語・とは?基本の考え方
用語を覚えるコツは、まず意味をひとことにまとめること、そして実際の場面と結びつけることです。例えばURLはウェブページの住所、HTMLはページの骨格、CSSは見た目を整える部品、といった具合です。
代表的なIT用語の解説
URL とはウェブページの住所のことです。例として https://example.com のように表されます。URL を知っていると、どのページに移動するかが一目で分かります。
HTTP はウェブ上で情報をやり取りする基本的な仕組みです。HTTPS は HTTP に加えて通信を暗号化する安全版で、通信内容を第三者から守ります。
HTML はウェブページの骨格を作る言語です。見出しや段落、リンクなどの配置を指示します。
CSS は HTML の見た目を整える言語です。色、フォント、余白などを決め、ページを見やすくします。
クラウド はデータやアプリをネット上のサーバーで管理する考え方です。自分のPCに全部を保存せず、インターネット経由で利用します。
API はソフト同士が話をするための窓口です。天気アプリが気象データを別のサービスからもらうときなどに使われます。
学習のコツ
まずは用語を見つけたとき、意味を短く覚えることを心がけましょう。次に、実際の場面での使われ方を想像する練習をします。例えばニュースサイトを開くと URL が表示され、クリックすると HTML や CSS が組み合わさってページが表示されます。これを繰り返すと、用語と現実の動きが結びつき、覚えやすくなります。
最後に、身近なサイトを観察するのも効果的です。サイトの URL の長さ、表示している情報の仕組み、デザインの背景にはどんな用語が使われているかを注意深く見ると、自然と理解が深まります。
このように IT 用語は難しいと思われがちですが、基本を押さえれば日常のネット利用がずっと楽しく、安全になります。焦らず、一つひとつ覚えることが成長の秘訣です。
例えば授業や部活の資料作成で出会う用語をチェックリストとして作ると良いです。用語と意味を自分の言葉で再表現することが、理解の定着につながります。
新しい IT 用語に出会ったら、まず辞書的な意味を探し、次に自分の生活の中でどう使われているかを考えましょう。こうして少しずつ語彙を増やしていけば、将来の学習にも役立ちます。
it用語の関連サジェスト解説
- it用語 ou とは
- it用語 ou とは、英語の Organizational Unit の略で、ITの現場でよく使われる「組織用の入れ物」のような概念です。主に Active Directory というディレクトリサービスの世界で使われ、ユーザーアカウントやコンピュータ、さらには他の OU を中に入れることができます。重要なのは OU は実際の地理的な場所を表すものではなく、管理上のまとまりを作るための仮想的な入れ物だという点です。こうした仕組みにより、部門ごとや拠点ごとに整理がしやすくなり、特定のグループや端末に対する設定をまとめて適用したり、管理権限を特定の担当者だけに委任したりすることが可能になります。 OU を使うメリットは、組織の成長に合わせて木のような階層構造を作れる点と、ポリシーの適用範囲を細かく制御できる点です。例えば大企業なら部門ごとに OU を作り、部署ごとに異なるセキュリティ設定や使い方のルールを適用することができます。 さらに、GPO(グループポリシー)と呼ばれる設定ルールを OU にリンクすることで、その OU に属する全てのユーザーや端末に対して同じポリシーを適用できます。こうして管理の手間を減らしつつ、管理者は責任範囲を明確化できます。一方で OU とグループの役割を混同しないことも大切です。グループは主に権限を割り当てるための集合で、リソースへのアクセスを決定します。対して OU は組織の構造を表す入れ物であり、ポリシーの適用対象や管理者の委任先を決めるためのものです。覚えておくと良いポイントは、OU を設計する際には命名をわかりやすく、階層は過度に深くしすぎず、部署名や拠点名など現場で使われている呼称をそのまま使うこと、そして変更による影響範囲を必ず事前にテストすることです。適切な OU の設計は、IT運用の効率化とセキュリティ管理の両方に役立ちます。もし初めて OU を作る場合は、まず 3〜4 階層程度のシンプルな構成から始め、徐々に必要に応じて拡張していくと良いでしょう。
- st とは it用語
- st とは it用語 という問いには答え方が複数あります。実際には文脈によって意味が変わる略語です。ここでは中学生にも分かるように代表的な意味を3つ紹介します。1) Structured Text ST: 産業用のプログラミング言語である構造化テキストの略称です。PLCと呼ばれる機械制御の分野で使われ、複雑な条件分岐や計算を読みやすく書ける特徴があります。例としては最初は if then else の形で書かれることが多く、動かす装置の動作を指示するために使われます。2) System Test ST: ソフトウェアの全体を組み合わせて動作を確認する System Test の略です。単体の動作だけでなく、複数の部品が連携して問題なく動くかを確かめる段階で行います。UT や IT とは役割が異なり、現場の要件を満たしているかを検証します。3) Security Token ST: 認証やアクセス管理で使われるセキュリティ トークンのことを指す場合があります。アプリにログインする際の鍵のような役割で、パスワードだけでなく token 自体を用いて本人確認を行います。これにより安全にデータへアクセスできるようになります。4) ここまでの他の意味: 文脈によっては ST が Storage の略として使われることもありますが、IT の話題では少なくとも上の3つが代表的です。文書やコードの中で st の意味が不明な場合は、近くの説明欄や定義を確認しましょう。このように st は一つの意味に決まっているわけではなく、使われる場面で意味が変わる abbreviation です。
it用語の同意語
- 情報技術用語
- 情報技術分野で使われる専門用語の総称。ハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク・データ処理など、ITに関する語を広く含みます。
- ICT用語
- 情報通信技術(ICT)分野で使われる用語。情報技術と通信技術を横断する語彙を指します。
- テック用語
- テクノロジー分野の専門用語。ITだけでなくAI・クラウドなど最新技術を含むことが多い表現です。
- コンピュータ用語
- コンピュータの仕組み・操作・構成要素に関する語彙。CPU・メモリ・OS・ファイルなどが代表例です。
- IT関連語彙
- ITに関連する語彙の総称。IT用語とほぼ同義で使われることが多い表現です。
- 情報処理用語
- データの収集・処理・分析・出力といった情報処理に関する用語の総称です。
- デジタル用語
- デジタル技術やデジタル化に関する用語を指します。
- ソフトウェア用語
- ソフトウェアの開発・配布・運用に関する語彙。プログラミング用語を含むことも多いです。
- ハードウェア用語
- 機器の部品・仕組み・動作に関する語彙。CPU・メモリ・ストレージなどが含まれます。
- ネットワーク用語
- データ通信・ネットワークの構成・規約に関する語彙です。
- セキュリティ用語
- 情報を守る技術・対策に関する専門用語。暗号・認証・脅威などの語が該当します。
- データベース用語
- データの整理・保存・検索を行うデータベース技術の語彙です。
- クラウド用語
- クラウドコンピューティングに関する用語。SaaS/IaaS/PaaSなども含みます。
- プログラミング用語
- プログラミングの構文・概念・ツールに関する語彙。変数・関数・ループなどが代表例です。
- IT業界用語
- IT業界で頻繁に使われる業界用語。現場の略語や専門用語を含みます。
- IT語彙
- IT分野で用いられる語彙全般を指す、やわらかな表現です。
- 情報技術語彙
- 情報技術分野の語彙(語彙集)を指します。専門用語の集まりとして使われます。
- データ技術用語
- データの取り扱い・分析・保存に関する語彙。データベース・データ分析関連の語を含みます。
it用語の対義語・反対語
- 平文
- 暗号化されていないデータの状態。暗号化の対義語としてよく使われます。
- 暗号化
- データを読み取れないように変換する処理。平文の対義語として理解されます。
- 公開鍵
- 公開鍵暗号で用いられる鍵のこと。秘密鍵と対になる概念として扱われることが多いです。
- 秘密鍵
- 秘密に保管する鍵。公開鍵の対になる概念として使われます。
- クライアント
- サービスを利用する端末。対になるのはサーバーです。
- サーバー
- サービスを提供する端末/プログラム。対になるのはクライアントです。
- フロントエンド
- ユーザーが直接操作する部分。対になるのはバックエンドです。
- バックエンド
- データ処理やアプリのロジックを担う部分。対になるのはフロントエンドです。
- ソフトウェア
- 動作するプログラム全般。対になるのはハードウェアです。
- ハードウェア
- 物理的な機器。対になるのはソフトウェアです。
- オンプレミス
- 自社の設備内にIT環境を持つ状態。対になるのはクラウドです。
- クラウド
- クラウド上で提供されるIT環境。対になるのはオンプレミスです。
- オンライン
- ネットワークに接続された状態。対になるのはオフラインです。
- オフライン
- ネットワークに接続されていない状態。対になるのはオンラインです。
- バックアップ
- データの複製を作成する作業。対になるのはリストア/復元です。
- リストア
- バックアップからデータを復元する作業。バックアップの対語として使われます。
it用語の共起語
- ハードウェア
- IT機器や部品を指す、CPUやメモリ、ストレージなどの物理的要素。
- ソフトウェア
- 動作するプログラムやアプリケーション全般。
- ネットワーク
- 複数の端末を繋ぎ、データをやり取りする仕組み。
- クラウド
- インターネット経由で提供されるリソースやサービスのこと。
- データベース
- データを organized に保存・管理する仕組み。
- セキュリティ
- 情報を保護するための対策全般。
- バックアップ
- データを別の場所に複製しておくこと。
- アクセス権限
- 誰が何にアクセスできるかの許可設定。
- アカウント管理
- ユーザーアカウントの作成・削除・権限管理。
- プログラミング
- コンピュータに指示を与えるためのコードを書く作業。
- アルゴリズム
- 問題を解く手順のこと。
- API
- アプリ同士が機能を利用し合うための窓口。
- デバッグ
- プログラムの不具合を探して直す作業。
- テスト
- 機能が正しく動くかを検証する作業。
- バージョン管理
- コードの変更履歴を管理する仕組み。
- Git
- 代表的なバージョン管理ツール。
- CI/CD
- 継続的インテグレーション/デリバリーの自動化手法。
- 仮想化
- 実物の資源を仮想的に分割して使う技術。
- コンテナ
- アプリとその依存関係をパッケージ化して動作させる技術。
- Docker
- 代表的なコンテナ実装のひとつ。
- Kubernetes
- 複数のコンテナを自動配置・運用する管理ツール。
- アーキテクチャ
- システムの全体構成や設計の考え方。
- OS
- オペレーティングシステム、PCやサーバの土台となるソフト。
- CPU
- 処理を実行する中央演算処理装置。
- メモリ
- データを一時的に蓄える記憶領域。
- ストレージ
- データを長期的に保管する場所。
- ファイアウォール
- 不正な通信をブロックするセキュリティ機器。
- VPN
- 安全に遠隔地のネットワークへ接続する仕組み。
- SSL/TLS
- 通信を暗号化して安全にする技術。
- 暗号化
- データを読めない形に変える技術。
- 認証
- 本人確認の仕組み。
- 認可
- 権限を付与して利用を許す仕組み。
- MFA
- 多要素認証、複数の要素で本人確認。
- プロトコル
- 通信の約束事や規約。
- REST
- Web API の設計原則の一つ。
- RESTful
- REST の設計原則に沿った API。
- SQL
- データベースを操作する言語。
- NoSQL
- 非リレーショナルなデータベースの総称。
- HTML
- ウェブページの骨組みを作るマークアップ言語。
- CSS
- ウェブページの見た目を整える言語。
- JavaScript
- ウェブページに動きをつけるプログラミング言語。
- ウェブ開発
- ウェブサイトやWebアプリを作る作業。
- フロントエンド
- 利用者が直接触れる部分の開発領域。
- バックエンド
- サーバー側の処理やデータベース連携の開発領域。
- データ分析
- データを集めて意味を読み解く作業。
- BI
- 企業の意思決定を支える分析ツールと手法。
- AI/機械学習
- 人工知能とデータから学習して予測する技術。
- IoT
- モノがインターネットにつながる仕組み。
- アジャイル開発
- 柔軟に計画・開発を進める開発手法。
- ITIL
- ITサービスのベストプラクティスフレームワーク。
- SLA
- サービス水準を約束する契約条件。
- KPI
- 成果を測る指標。
- BCP
- 事業継続計画、障害時の対応計画。
- DR
- ディザスタリカバリ、復旧計画。
- アクセス制御
- 誰が何にアクセスできるかを管理するしくみ。
- ログ管理
- 活動記録を収集・保管して分析する作業。
- 監視
- システムの健全性を常にチェックすること。
- アラート
- 問題を知らせる通知。
- パッチ
- ソフトウェアの修正や更新プログラム。
- バグ
- 不具合のこと。
- オープンソース
- 誰でも利用・改変できるソフトウェアの考え方。
- ライセンス
- ソフトウェアの利用条件。
- APIキー
- API を利用するための鍵となる識別情報。
- OAuth
- 第三者アプリへの権限委譲の仕組み。
- SSO
- 一度の認証で複数サービスへログインする仕組み。
- RPA
- 事務作業を自動化するロボットソフト。
- DNS
- ドメイン名とIPアドレスを対応づける仕組み。
- DHCP
- ネットワーク機器へ自動的にIPを割り当てる仕組み。
- IPv4
- IPアドレスの4つの数値表現。
- IPv6
- 次世代のIPアドレス表現。
- CDN
- 世界中の利用者へ高速に配信する仕組み。
- WAF
- ウェブアプリを守る防御壁。
- ログ収集
- イベント情報を集める作業。
- 監査ログ
- 誰が何をしたかを記録するログ。
- PCI-DSS
- クレジットカード情報の処理基準。
- GDPR
- 個人データの取り扱いに関する規制。
it用語の関連用語
- IT用語
- IT分野で使われる用語の総称。情報技術、ソフトウェア開発、ネットワーク、データ管理などに関する言葉を指します。初心者向けに解説します。
- ハードウェア
- コンピュータを構成する物理的な部品のこと。CPU、メモリ、ストレージ、周辺機器などが含まれます。
- ソフトウェア
- コンピュータが動作するプログラムと、それを支えるデータの総称。OSやアプリケーションなどを含みます。
- オペレーティングシステム (OS)
- ハードウェアとアプリの仲介役となる基本ソフトウェア。資源管理や基本機能を提供します。
- アプリケーションソフトウェア
- ユーザーが日常的に使うソフトウェアのこと。表計算、メール、ブラウザなどが例です。
- データベース
- データを組織的に保存・検索するための仕組み。テーブル形式が一般的です。
- DBMS
- データベースを作成・運用するソフトウェア。例としてMySQL、PostgreSQL、Oracleなど。
- SQL
- データベースと対話するための標準的な問い合わせ言語。選択・挿入・更新・削除などを行います。
- NoSQL
- NoSQLは非関係データベースの総称。スキーマが柔軟で大規模データに向く場合が多いです。
- クラウド
- インターネット経由で提供される計算資源やサービスの総称。必要な時に利用できる利点があります。
- IaaS
- インフラをサービスとして提供するクラウド形態。仮想サーバーやストレージが中心です。
- PaaS
- アプリ開発用のプラットフォームを提供するクラウド形態。開発・デプロイを簡易化します。
- SaaS
- ソフトウェアをサービスとして提供する形態。利用者はブラウザ経由で使います。
- コンテナ
- アプリとその依存を一つの単位にまとめ、軽量に動かせる仮想化技術。
- Docker
- コンテナを作成・実行する代表的なツール。
- Kubernetes
- 複数のコンテナを自動で配置・管理するオーケストレーションツール。
- 仮想化
- 物理資源を仮想的に分割して複数の仮想環境として動かす技術。
- VM
- 仮想マシン。実機と同じ機能を持つ仮想的なPCです。
- マイクロサービス
- 大きなアプリを小さな独立サービスに分割して開発・運用する設計。
- モノリシック
- 全機能を一つの大きなアプリとして開発・運用する設計。
- API
- アプリ同士が連携する窓口となるインタフェース。
- REST
- Web APIの設計スタイルの一つ。HTTPを使いリソースを操作します。
- GraphQL
- 必要なデータだけを取得できるAPI設計の仕様。
- APIゲートウェイ
- 複数のAPIを統合して一つの入口として扱い、認証・ルーティングを行います。
- HTTP
- Web通信の基本プロトコル。
- HTTPS
- HTTP通信をTLS/SSLで暗号化した安全な通信。
- TLS/SSL
- 通信を暗号化し、データの改ざんや盗聴を防ぐ技術。
- DNS
- ドメイン名とIPアドレスの対応を管理する仕組み。
- IPアドレス
- ネットワーク上の端末を識別する番号。
- VPN
- 仮想プライベートネットワーク。安全なリモート接続を実現します。
- ファイアウォール
- 不正な通信を遮断するセキュリティ機能。
- IAM
- Identity and Access Managementの略。身元とアクセス権限を一元管理します。
- 認証
- 利用者が誰かを確認する手続き。
- 認可
- 認証済みの利用者に対し、アクセスできる資源や操作を制限すること。
- OAuth
- 第三者アプリに限定的なアクセスを許可する認可の標準。
- OpenID Connect
- OAuthを拡張して認証機能を提供する標準。
- SAML
- シングルサインオンの標準フォーマット。主に企業内で使われます。
- JWT
- JSON Web Token。ユーザー情報を安全に伝えるトークン。
- CI
- 継続的インテグレーション。コードを頻繁に統合して自動テストまで回します。
- CD
- 継続的デリバリー/デプロイ。変更を自動的に本番環境に反映できるようにします。
- CI/CD
- コードの変更を小さな単位で頻繁に統合・テスト・デプロイする自動化の流れ。
- DevOps
- 開発と運用の協力と文化。
- アジャイル
- 変更に迅速に対応する開発手法。短いスプリントで成果を出します。
- スクラム
- アジャイルの代表的な実践フレームワーク。
- デバッグ
- プログラムの不具合を探して修正する作業。
- テスト
- 機能が正しく動くかを検証する工程。
- QA
- 品質保証の略。テスト計画や品質管理を含みます。
- リファクタリング
- 機能を変えずにコードの内部設計を改善する作業。
- バージョン管理
- ソースコードの変更履歴を管理する仕組み。
- Git
- 分散型のバージョン管理システム。
- GitHub
- Gitのリポジトリをオンラインで管理するサービス。
- GitLab
- Gitのリポジトリをオンラインで管理する別サービス。
- リポジトリ
- ソースコードや資産を保管・管理する場所。
- ビルド
- ソースコードを実行可能な形に変換するプロセス。
- デプロイ
- アプリを本番環境へ配置して公開する作業。
- パイプライン
- ビルド・テスト・デプロイをつなぐ自動手順の流れ。
- コード品質
- 可読性・保守性・動作の信頼性など、コードの品質を指します。
- セキュリティ
- 情報を守るための一連の対策。
- サイバーセキュリティ
- インターネット上の脅威から資産を守る実践。
- GDPR
- EUの一般データ保護規則。
- 個人情報保護法
- 日本の個人情報保護に関する法律。
- PCI DSS
- クレジットカード決済のセキュリティ基準。
- SOC
- Security Operations Centerの略。セキュリティ監視の拠点。
- 監査ログ
- システムの操作やイベントを記録するログ。
- 監視
- システム状態を継続的に確認する活動。
- モニタリング
- 監視と同義。性能や可用性を追跡します。
- アラート
- 検知した異常を通知する機能。
- ログ
- システムのイベント履歴を記録するデータ。
- キャッシュ
- よく使うデータを近くの場所に一時保存して高速化する仕組み。
- メモリ
- データを一時的に保持する高速な記憶装置。
- CPU
- 中央処理装置。計算の頭脳。
- GPU
- グラフィックス処理装置。並列処理が得意。
- ストレージ
- データを長期間保存する場所。
- SSD
- ソリッドステートドライブ。高速なストレージ。
- HDD
- ハードディスクドライブ。容量重視のストレージ。
- RAID
- 複数ディスクで冗長性や性能を向上させる構成。
- バックアップ
- データを別の場所に複製して、喪失時に復元できるようにする作業。
- ディザスタリカバリ
- 大規模障害からの復旧計画。
- データセキュリティ
- データの機密性・完全性・可用性を守る対策。
- データ分析
- データを整理・加工して意味のある情報を得る作業。
- ビッグデータ
- 従来の処理手段では扱いづらい規模・多様性のデータ。
- 機械学習
- データから自動的にパターンを学習するAIの一分野。
- AI
- Artificial Intelligence。知能を模倣する技術。
- データウェアハウス
- 分析用に設計された大規模データの蓄積庫。
- データマイニング
- データから未知のパターンを見つけ出す技術。
- BI
- ビジネスインテリジェンス。データを使った意思決定支援。
- UI
- ユーザーが触れる画面の外観・操作性のこと。
- UX
- ユーザーの体験全体の満足度。
- UI/UX
- UIとUXを総称する言い方。
- HTML
- ウェブページの骨格を作るマークアップ言語。
- CSS
- ウェブページの見た目を整えるスタイルシート言語。
- JavaScript
- ウェブページに動きをつけるプログラミング言語。
- Python
- 読みやすく、用途が広い高水準プログラミング言語。
- Java
- 汎用的に使われる言語。大規模アプリに強い。
- C
- 低レベルから高レベルまで扱える言語。
- C++
- Cの拡張版で、高速・効率的なアプリ開発に使われる。
- Go
- シンプルで高速、サーバーサイドに向く言語。
- Rust
- 安全性と性能を両立するシステム言語。
- Swift
- AppleのiOS/macOS向け言語。
- Kotlin
- JVM上で動くモダンな言語。
- JSON
- データ交換に使われる軽量フォーマット。
- XML
- データのマークアップ言語。構造を表現します。
- YAML
- 設定ファイルなどに使われる、人間が読みやすいデータ表現形式。
- OpenAPI
- REST APIの仕様を標準化してドキュメント化する枠組み。
- Swagger
- OpenAPIを活用してAPIドキュメントを自動生成するツール群。
- 3層アーキテクチャ
- プレゼンテーション層・ビジネスロジック層・データアクセス層の3つの役割に分ける設計。
- ORM
- オブジェクトとデータベースの間のデータ変換を自動化するツール。
- デザインパターン
- よくある設計上の課題と解決方法の定型。
- アルゴリズム
- 問題を解くための手順の集合。
- データ構造
- データを効率的に扱うための組織化方法。
- 依存関係管理
- プロジェクトが依存するライブラリの管理。
- パッケージマネージャ
- 外部ライブラリの導入・更新を管理するツール。
- npm
- JavaScriptのパッケージマネージャ。
- pip
- Pythonのパッケージマネージャ。
- Maven
- Java向けビルド・依存関係管理ツール。
- 自動化
- 繰り返し作業を自動化して人手を減らすこと。
- TDD
- テスト駆動開発。テストを先に書く開発手法。
- BDD
- 挙動駆動開発。仕様を中心に開発する手法。
- E2Eテスト
- エンドツーエンドのテスト。システム全体の動作を検証します。
- 2FA
- 二要素認証。認証の安全性を高める手法。
- 多要素認証
- 2つ以上の認証要素を組み合わせて認証する方式。
- SSO
- シングルサインオン。一度の認証で複数サービスへアクセス可能。
- オープンソース
- 誰でも使える、改変可能なソフトウェアの考え方・実装。
- ライセンス
- ソフトウェアの利用・再配布の条件を定めた契約。
- ロードバランシング
- 複数のサーバへ負荷を分散して高い可用性を保つ仕組み。
- CDN
- コンテンツ配信ネットワーク。地理的に近いサーバから配信して高速化。



















