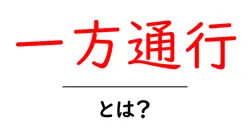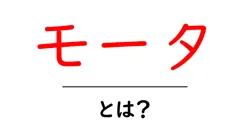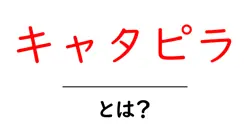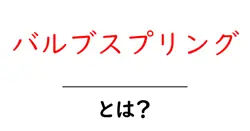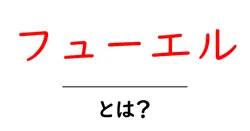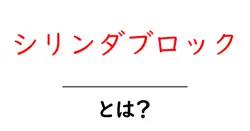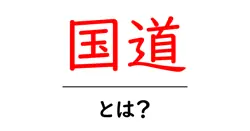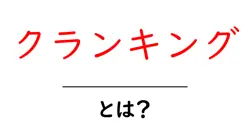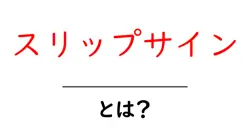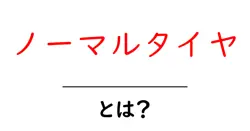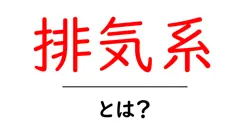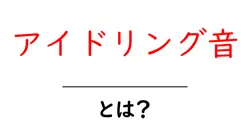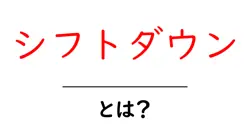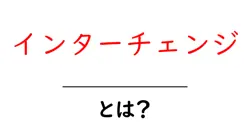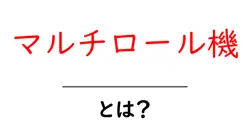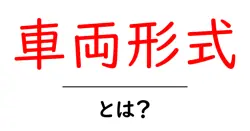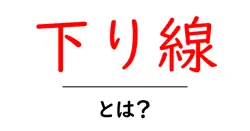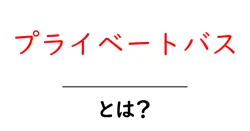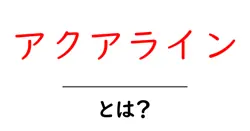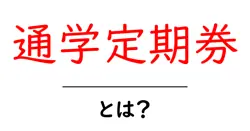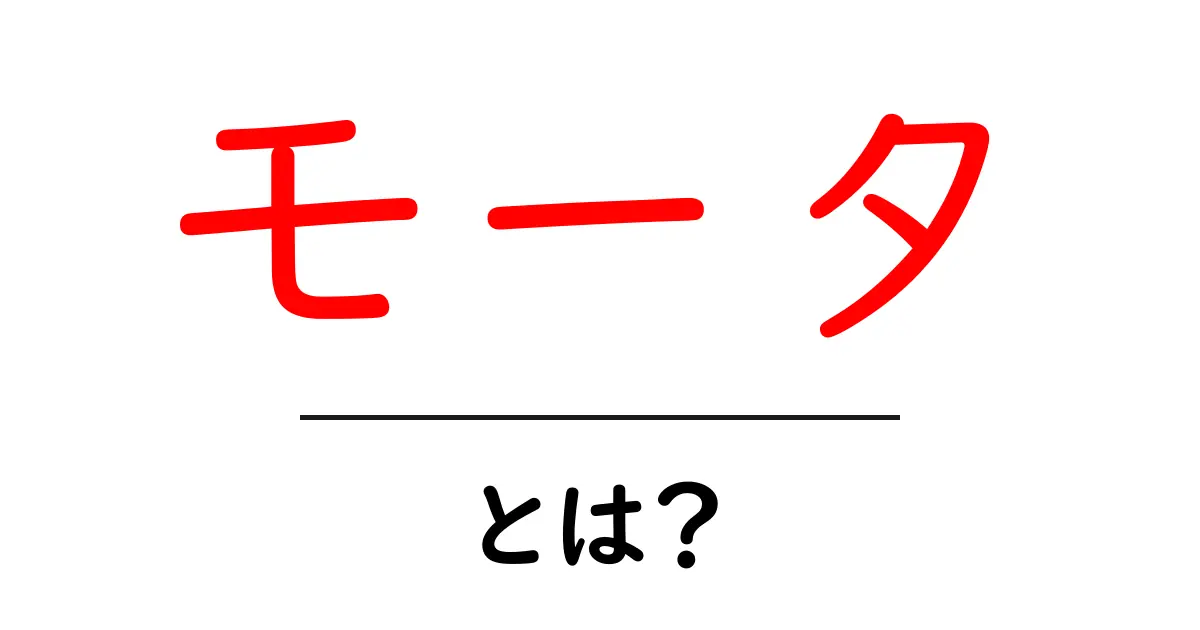

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
モータとは?
モータとは電気のエネルギーを回転運動に変える装置です。家庭の扇風機や掃除機(関連記事:アマゾンの【コードレス 掃除機】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)、デスクトップのファンなど、身の回りの多くの機械に使われています。この記事では、モータの意味を分かりやすく解説します。
モータとエンジンの違い
車のエンジンは化学エネルギーを機械的エネルギーに換える装置ですが、モータは電気エネルギーを直接回転運動へ変換します。つまり、燃料を燃焼させて動くエンジンと、電気を使って動くモータは「エネルギーの作り方」が異なるのです。
モータの基本的なしくみ
モータの中には「ステータ」と「ロータ」という回転する部品があります。外側の静止部分をステータ、回転する部分をロータと呼びます。コイルに電流を流すと、コイルの周りに磁場ができます。磁場と磁石の力が作用してロータが回転します。これがモータの基本的な動きです。さらに、どの電源をどう使うかで動き方が変わるのがモータの特徴です。
主な種類と特徴
以下の表は、身近でよく使われるモータの代表例と特徴をまとめたものです。
モータの選び方のポイント
モータを選ぶときは、用途、必要な回転数、必要なトルク、制御のしやすさ、効率とコストを考えます。小型で静かに動かしたいならBLDC、安価で単純な動作ならDCモータ、産業用の大きな出力にはACモータが適していることが多いです。
身近な注意点と未来
モータは発熱しやすい装置なので、連続運転や高負荷運転をする場合は適切な放熱対策が必要です。また、近年は電気自動車の普及やロボット技術の発展で、モータの効率化と制御技術の進化が進んでいます。今後も私たちの生活をより省エネで便利にする原動力として、さまざまな場面で活躍が続くでしょう。
モータの関連サジェスト解説
- モータ ドライバ とは
- モータ ドライバ とは、モーターを動かすための電流と電圧を適切に制御する電子部品です。マイコンやラズベリーパイのような小さな制御回路は、モーターを直接動かすと大量の電流が流れてしまい、回路が傷んだり動作が不安定になったりします。そこで使うのがモータ ドライバで、信号を受けてモーターに流す電流を調整し、回転の速さや向きを変えられるようにします。モータには大きく分けてDCモーター、ステッピングモーター、BLDC(ブラシレス)モーターがあります。DCモーターには単純な回転制御用のHブリッジ型ドライバ、ステッピングモーターには段階的に動かすためのステップと向きを指示する入力が必要です。BLDCモーターには回転を滑らかにするための位相制御が求められ、専用のBLDCドライバが使われます。選び方のポイントは、まずモーターの定格電流と必要な電圧を確認し、それを安全に制御できるドライバを選ぶことです。過電流や過熱を防ぐ保護機能、現在の流れを調整できる電流制限機能、そしてマイクロステップ機能(1/2や1/4ステップなど)などの性能があると扱いやすいです。接続のコツとしては、制御側と電源側を適切に分離し、必須の信号線(速度を決めるPWM、方向を決めるDir、ステップを進めるStepなど)を用意します。入門用のモータドライバキットには、Arduino などのボードと組み合わせた実例が多く、コードもサンプルがついています。実際の使い方のイメージとしては、Arduino でStep信号を出してドライバに伝え、モーターを少しずつ回す、という流れです。初めは低速・低電圧で試してみて、配線や機構部品の温度を観察します。モーターとドライバの加熱、配線の整理、配布電源の容量にも気をつけましょう。モータドライバはロボット、3Dプリンター、工作機械など幅広い分野で使われています。初心者には、まず入門用のキットを使い、動作原理と安全な取り扱いに慣れることをおすすめします。
- モータ 極数 とは
- モータ 極数 とは、モーターの磁極の数を指す用語です。一般的には、ステーターやローターに作られる磁極の総数をPと表し、2極、4極、6極などと呼びます。ACモーターでは周波数と極数の関係で回転速度が決まり、実際の定格回転数はn_s = 120 f / Pで計算します。たとえば50 Hzの電源を使う場合、2極のモータは理論上の同期回転数が3000 rpm、4極は1500 rpmになります。60 Hzならそれぞれ3600 rpmと1800 rpmです。ここでよく混同されがちなのが「極数」と「極対数(pole pairs)」です。Pが磁極の数で、Pole P = 2×pole pairs という関係があり、実際の回転速度を考えるときにはPole pairsを使う場面も多いです。極数が多いほど回転数は遅くなる傾向があり、低速でのトルク特性や始動性に影響します。そのためファンやポンプのように高速で回ることが大事な用途には2極または4極がよく使われ、ベルト式の機械や低速大トルクが必要な装置には多極のモータが選ばれることがあります。実際の機械を設計・選定する際には、仕様書に記載された極数や周波数、電圧、定格トルク・始動トルクを確認し、用途に合った極数を選ぶことが大切です。
- モータ ブラシ とは
- モータ ブラシ とは、DCモーターやブラシ付きの交流モーターで使われる部品です。正式には炭素ブラシと呼ばれ、固定された部分(定子など)と回転する部分(ローターのコマータ)を電気的に結ぶ役割を持ちます。モーターが動くと、電流はブラシを介してコマータに伝わり、磁場が生まれてローターを回します。ブラシは通常、円柱形の炭素片で、接触面が小さく設計されています。これをスプリングで押し付け、回転するコマータに沿って摩耗します。なぜブラシが必要かというと、固定部と回転部の間に電気の道を作るためです。ブラシが摩耗して短くなると、電流が十分に流れずモーターの出力が下がったり、回転が不安定になったりします。さらに接触時に火花(アーク)が生じて部品を傷めることもあります。これが長く使われるとブラシの摩耗が進み、交換時期のサインになります。材質は主に炭素系ですが、耐久性を高めた特殊な合金が使われることもあります。故障のサインには、異音、ギクシャクした動き、火花の増加、出力低下、モーターの停止などがあります。これらを放っておくとモーターのコマータや巻線が傷つく恐れがあります。点検や交換は、まず電源を切って安全を確保し、型番に合ったブラシを選ぶことが大切です。ブラシの長さや摩耗の程度、スプリングの力を確認します。慣れていない場合は専門家に依頼するのが安心です。適切に交換すれば、モーターは安定して長く使えるようになります。
- モータ d軸 q軸 とは
- モータ d軸 q軸 とは、モータの回転を正しく制御するための「仮想の座標軸」です。電動機には三相の回路があり、回転すると磁場も動きます。この複雑な動きをわかりやすく管理するために、回転と直交する二つの軸を導入します。d軸はローターの磁気の方向に沿う軸、q軸はd軸に直角に回転方向を基準とした軸です。つまり、d軸とq軸に沿って電流を分けて考えると、モータが生み出す磁束(磁力の量)とトルク(回す力)を別々に扱えるようになるのです。これを実現するのが「Park変換」という考え方で、三相の電流情報をabcからdqに変換します。dq表現では、idが磁束をつくる力を、iqがトルクを生む力を表します。実務ではダンピングや効率の向上のため、idとiqを適切に調整します。例えば、磁石を強くして磁束を増やしたいときはidを増やし、同時に過度な電流を抑えたいときはiqを制御します。これは場指向制御(FOC)と呼ばれる方法で、モータを滑らかに、効率良く回すのに欠かせません。日常の例えで言えば、d軸は車の直進のベースとなる力、q軸は曲がるときの方向制御の力と考えるとわかりやすいです。最後に、d軸とq軸の概念は、モータの種類(同期モータ、ブラシレスDCモータなど)に関係なく使われます。実際の設計や学習では、abcからdqへ、dqから回転角を追跡する変換の理解が基礎になります。
- モータ トルク とは
- モータ トルク とは、モーターが回転軸を回そうとするときに生まれる“回す力”のことです。力の大きさと、力を伝える軸の半径を掛け合わせた量を指し、単位はニュートン・メートル(N·m)です。身近な例で言うと、手で棒を回すときに感じる回しやすさがトルクの直感です。長さが長い棒や力を強く加えれば回す力は大きくなり、短い棒では難しくなります。モーターの場合も、ローターの端までの距離(半径)が大きいほど、同じ力でもより大きな回転力を生み出せることがあります。トルクは「初動の力」に強く結びつきます。車のエンジンや電動機能を持つ機械は、発進時に大きなトルクを出せる設計になっていることが多いです。発進トルクが大きいほど、車は信号待ちから動き出しやすく、階段のように急な坂道でも動かしやすくなります。一方で回転数が高くなると、同じトルクでも感じる力は小さくなることがあります。これを「トルクと回転数のトレードオフ」と呼ぶことがあります。モーターの出力は、トルクと回転数の組み合わせで決まります。出力はワット(W)という単位で表され、目安としては“出力 = トルク × 回転数(rad/s)”のような関係が成り立ちます。実務では、モーターのデータシートに「最大トルク」「定格トルク」「回転数域」「出力容量」などが載っています。初心者はまず、どの用途でどのくらいのトルクが必要かを考え、車両なら発進トルク、機械なら定格トルクを確認すると良いです。要するに、モータ トルク とは、モーターが回る力の“強さ”を示す指標であり、発進の力と密接に関係します。回転数と結びつくことで出力が決まるため、用途に合わせて適切なトルクと回転数の組み合わせを選ぶことが大切です。
- モータ 脱調 とは
- モータ 脱調 とは、モータの回転と電気的な指示がずれてしまう現象のことです。特にステッピングモータ(ステップモータ)や同期モータで使われる用語で、正確な位置決めや一定の回転を保つことが難しくなります。脱調には主に2つのタイプがあります。1つは「位置の脱調」で、設定した位置に到達しない、または途中で数え間違える状態。もう1つは「速度の脱調」で、速度を一定に保てず、動きがガクガクしたり遅れてしまう状態です。なぜ脱調が起こるのかの原因は、荷重が大きく変化する、モータが必要以上のトルクを出せない、電流設定が適切でない、機械の摩擦や緩み、配線のノイズなどです。特にステッピングモータでは、1ステップごとの励磁が遅れると、次のステップを見失い脱調します。回路側の問題として電源の電圧変動やケーブルの長さも影響します。脱調を防ぐにはいくつかの方法があります。まず適切なモータの選定とトルクの余裕を確保すること。次にドライバの設定を見直し、マイクロステップ化やフィードバックの導入でズレを減らします。荷重を急に変えないように設計すること、急加速を避けること、機械側の摩擦を減らすこと、ベアリングの状態を整えること、ケーブルの長さを短くすること、電源電圧を安定させることも有効です。実務で脱調を根本から防ぐには、エンコーダ付きのサーボモータや閉ループ制御を検討すると安心です。これにより回転数や位置を正確に追従でき、脱調が起こりにくくなります。初心者はまず、トルクと負荷のバランス、ドライバ設定、機械の整備を優先して学ぶと良いです。
- モータ フランジ とは
- モータ フランジ とは、モータの出力軸と他の部品をつなぐ平面の接合部のことです。フランジにはボルト穴が配置されており、ボルトでモータとギアボックスやポンプ、カップリングなどを固定します。これにより回転力を機械側へ伝え、軸の位置を正確に保つ役割を果たします。フランジは部品の取り付け方や機械の性格に合わせていくつかの形があります。主に鋳鉄、アルミ、ステンレスなどの材料が使われ、規格もISOやJIS、NEMAなどが存在します。サイズはモータの出力軸径や取付孔の数・ピッチ、穴径などで決まり、規格に合わせて選ぶことが大切です。フランジには平面フランジ、ボス付き、スプラインなどの形状があり、用途に応じて適切なタイプを選ぶ必要があります。選ぶときは、まず軸径と孔配置をチェックし、次にフランジの厚みや材質、耐荷重を確認します。現場の部品と規格を照合するのが最も確実です。取り付け時にはボルトを適正なトルクで締め、対称に締め付けることが重要です。初心者向けのポイントとしては、同じ規格の部品同士を組み合わせること、寸法を測ったうえでメーカーのデータシートで照合すること、締め具の長さを間違えないこと、そして作業中は機器を停止して安全を確保することです。
- モータ ステータ とは
- モータ ステータ とは、電動機の動かない部分を指す専門用語です。電動機は回転するローターと、それを囲んで固定されているステータから成り立っています。ステータは鉄の芯(コア)と、そこに巻かれた絶縁された銅線の巻線でできています。電気を流すと、巻線に磁場が生まれ、その磁場がローターと相互作用して回転を起こします。ステータが固定されているおかげで、モーターは安定して外部に力を伝えることができます。\n\nステータのコアは通常「ラミネーション」と呼ばれる薄い鉄板を何枚も積み重ねたもので作られ、これが渦電流という無駄な熱を減らす役割を担います。巻線の材質や巻き方、そしてコアの形は、モーターの効率や騒音、発熱に大きく影響します。直流モーターでも交流モーターでも、ステータの役割は基本的に同じで、磁場を作ってローターを動かす力を生み出すことです。\n\nモータ ステータ とはの説明を少し応用すると、例えば交流モータの場合、三相の巻線を使って回転磁場を作り出します。回転磁場がローターに作用して、ローターを継続的に回転させます。逆に、永久磁石式モーターのようにローター側に磁石があり、ステータの巻線だけで磁場を動かす設計もあります。\n\nステータの設計次第で、モーターは静かさ、効率、始動性などが変わります。新しくモーターを選ぶとき、ステータの性能は重要なポイントです。
- モータ 枠番 とは
- 「モータ 枠番 とは」とは、電動機の外装部分である枠(フレーム)の大きさを表す番号のことです。枠番は外形寸法やシャフト径、取付穴の間隔、ファンの位置など、実際の取り付けや部品の互換性に直結します。銘板やカタログには必ず枠番が記載されており、例として 63、80、90S、112M などの文字と数字の組み合わせで表されます。枠番だけでモータの出力を決めるわけではなく、同じ枠番でも定格出力や回転数は異なることがあります。実務では、機械の取り付けベースに合うかどうかを枠番で判断するのが基本です。枠番を正しく理解するためのポイントは次の通りです。1) 枠番は“外形のサイズ”を示す指標で、機械のベースや取付部品の選定に使われます。2) 例として 90S や 112M などの表示があり、文字と数字の組み合わせが規格を表します。3) 重要なのは枠番だけでなく定格出力、冷却方式、取り付け穴の間隔(ボルト穴配置)も同時に確認することです。4) 交換時には同じ枠番か、適合するアダプターや取付部品を用意する必要があります。これらを意識すると、部品選びや修理がスムーズになります。
モータの同意語
- モーター
- 電気で回転を生み出す機械。家庭用・産業用を問わず広く使われる最も一般的な表現です。
- 電動機
- 電力を機械的な回転へ変換する装置を指す正式名称。技術文書や仕様書でよく使われます。
- エンジン
- 通常は内部燃焼機関などの推進力を指す語。日常会話ではモーターの代わりに使われることもありますが、厳密には異なる場合があります。
- 回転機
- 回転して動力を生み出す機械の総称。モーターを含む広い意味で使われることがあります。
- 駆動機
- 物を動かすための動力機構を指す語。文脈によってはモーターの代わりに使われることがあります。
モータの対義語・反対語
- 手動
- モータを使わず、手の力で動かすこと。自動化・機械化の対義語として使われる。例: 手動ドア、手動運転。
- 人力
- 人の力で動かすこと。モータではなく人力で作動させる状態を指す。
- 非動力
- 動力を使用しない状態。モータなどの動力源に頼らない設計・運用を表す。
- 無動力
- 動力源がない、または動力が停止している状態。機械が動いていない状態を指す。
- 静止
- 機械・物体が動いていない状態。動力があっても現在は停止していることを意味する。
- モータレス
- モータを搭載していない状態。手動・非動力の対比で用いられることがある。
- 非モータ化
- 機械・装置からモータを取り除く、またはモータに依存しない状態にすること。
- 手動式
- 操作が手動で行われる設計・形式。自動・モータ式の対義語として使われる。
モータの共起語
- DCモーター
- 直流を動力源とするモーター。ブラシ付きとブラシレスの2系統があり、速度・トルクの制御が比較的容易です。
- ACモーター
- 交流を動力源とするモーター。代表的には誘導モーターと同期モーターがあり、産業用途で広く使われます。
- ブラシレスDCモーター
- ブラシがなく、摩耗が少なく高効率。回転数制御には電子制御とエンコーダが必要です。
- ブラシ付きDCモーター
- ブラシと整流子を用いる従来型。コストは低いがメンテ性・耐久性が劣る場合があります。
- ステッピングモーター
- 角度ごとに回転するモーターで、位置決めの分解能が高く、3DプリンタやCNCなどでよく使われます。
- サーボモーター
- 位置・速度・トルクを高精度に制御するモーター。サーボユニットと制御器を組み合わせて使います。
- 誘導モーター
- ACモーターの代表格。回転子が導体でできており、構造がシンプルで信頼性が高いです。
- 同期モーター
- 磁界と回転子を同期させて回るモーター。速度制御の精度が高い特徴があります。
- モータ制御
- モータを正しく駆動するための信号設計・回路・アルゴリズム全般。フィードバック制御や保護機能も含まれます。
- PWM
- パルス幅変調の略。平均電圧・電流を調整してモータの速度を滑らかに制御します。
- インバータ
- DCを可変周波数のACに変換する装置。ACモータの速度・トルクを調整するのに使われます。
- モータドライブ
- モータを駆動するための電源と制御を一体化した装置。産業機器で広く使われます。
- トルク
- モータが出せる回転力のこと。用途に応じて必要なトルクを選定します。
- 回転数
- モータの回転速度。一般にrpmで表されます。
- 効率
- 投入電力に対する機械的出力の割合。高効率は省エネ・発熱低減につながります。
- 電源
- モータを動かす電力源。直流・交流のいずれにも対応できるよう、電圧や電流仕様を揃えます。
- 負荷
- モータにかかる機械的な荷重の総称。負荷が大きいほど必要トルクや電流が増えます。
- 軸受/ベアリング
- 回転軸を支持する部品。潤滑と摩耗管理によって長寿命・滑らかな回転を保ちます。
- ギアボックス
- 出力トルクを増大させる減速機を内蔵または接続した装置。
- 減速機
- 出力軸の回転数を下げてトルクを増大させる機構。モータと組み合わせて使われます。
- 小型モータ
- スペースの制限がある用途向けの小型モータ。低速・低トルクの用途に適します。
- 大出力モータ
- 高出力が必要な設備向けの大容量モータ。発熱・冷却・機械的設計が重要です。
- 用途/アプリケーション
- 家電・産業機械・車載など、モータの実装先・使用目的を指します。
モータの関連用語
- モータ
- 電力を機械的回転運動に変換する装置。入力された電力を回転軸の運動に変換します。
- モーター
- モータの別表記。一般的には同義語として使われる言葉です。
- 直流モータ
- 直流電源で駆動するモータ。電圧を変えると回転数を調整できます。
- 直流ブラシ付きモータ
- ブラシと整流子を用いて回転させるDCモータ。高トルクを得やすいがメンテナンスが必要なことが多いです。
- ブラシレスDCモータ
- ブラシを使わない直流モータ。高効率・長寿命・低騒音が特徴です。
- 交流モータ
- 交流電源で動くモータの総称。家庭用・産業用の多くがこのタイプです。
- 誘導モータ
- 交流モータの一種で、回転磁界によってロータを回す装置。耐久性が高く普及しています。
- 同期モータ
- ロータが回転磁界と同期して回るモータ。高精度の速度制御に向きます。
- ステッピングモータ
- 位置決め用のモータ。一定の角度ステップで回転角度を細かく制御できます。
- サーボモータ
- 位置・速度を精密に制御するモータ。通常はフィードバック機構を備えています。
- 永久磁石モータ
- ロータに永久磁石を用いるモータ。高効率で小型化が可能です。
- ブラシレスモータ
- ブラシを使用しないモータ全般の総称。BLDCはその代表例です。
- モータドライバ
- モータへ電流を適切に供給・制御する回路・IC。
- モータコントローラ
- モータを動かすための制御装置やソフトウェア。
- PWM制御
- パルス幅変調で平均電圧を調整してモータの速度を制御する方法。
- インバータ
- 直流を交流に変換したり、周波数を変えてモータの速度を調整する装置。
- V/Hz制御
- V/F制御とも。誘導モータの速度を電圧と周波数で制御する基本手法。
- 起動トルク
- モータ起動時に必要とされる大きなトルクのこと。
- 定格電圧
- モータが安全に動作する設計電圧の範囲。
- 定格回転数
- 連続運転時の回転数の目安となる範囲(rpm)。
- 定格トルク
- 連続運転時に維持できる最大トルクの値。
- 最大トルク
- 短時間に出せる最大のトルク。
- トルク
- 回転を生み出す力のこと。
- 回転数
- 単位時間あたりの回転数。例: rpm。
- 速度制御
- モータの回転速度を安定させる制御方法。
- 効率
- 入力電力に対する機械出力の割合(高いほど無駄が少ない)。
- 効率等級
- IE規格で示される省エネ性能の等級(IE1/IE2/IE3 など)。
- 騒音
- モータ作動時に発生する音の大きさ。
- 振動
- モータ運転時に生じる機械的振動。
- 過負荷保護
- 過負荷時に停止・保護する安全機能。
- 過電流保護
- 過電流を検知して電流を遮断する機能。
- 過熱保護
- 温度が過度に上がった場合に動作を停止・保護する機能。
- 冷却方式
- モータを冷却する方法の総称。
- 空冷
- 空気を用いて冷却する方式。
- 水冷
- 液体を用いて冷却する方式。
- ファン付きモータ
- 内部ファンで冷却を補助するモータ。
- ベアリング
- ロータ軸を支持する回転機構の部品。
- シャフト
- モータの回転軸。
- ステータ
- 固定子。コイルが巻かれた部分。
- ロータ
- 回転子。ロータは回転運動の主体。
- エンコーダ
- ロータ位置を検出する光学または磁気センサ。
- ホールセンサ
- BLDCなどで角度・位置を検出する霍尔効果センサ。
- エンコーダ付きモータ
- エンコーダを搭載したモータ。フィードバック付きで高精度制御が可能。
- ギアボックス
- 減速機を内蔵してトルクを増やし回転数を下げる装置。
モータのおすすめ参考サイト
- モーターとは?種類や仕組み、役割や特徴などをわかりやすく解説
- 1-1 モータとは何か | ニデック株式会社 - Nidec
- モーターとは? 種類・特徴・用途を紹介 - ミネベアミツミ製品サイト
- モーターとは?種類や仕組み、役割や特徴などをわかりやすく解説
- モータとは? | エレクトロニクス豆知識 | ローム株式会社
- モーター(電動機)とは? モーターの種類と動作原理 - モーノポンプ
- 1-1 モータとは何か | ニデック株式会社 - Nidec
- モーターとは? 種類・特徴・用途を紹介 - ミネベアミツミ製品サイト
- モータとは? | サーボモータ | 製品・ソリューション - 安川電機
- 電動機とは - ASPINA
- モータとは | MISUMI(ミスミ)