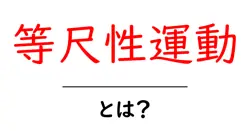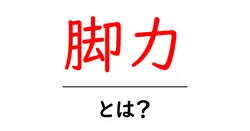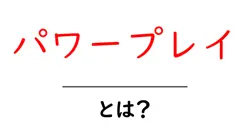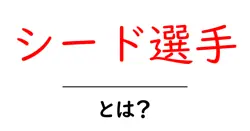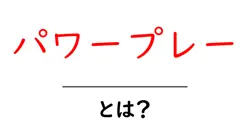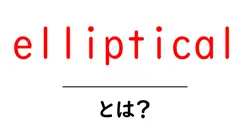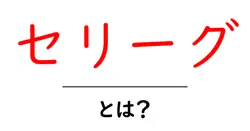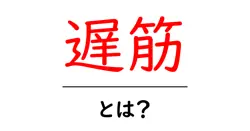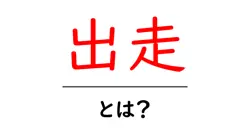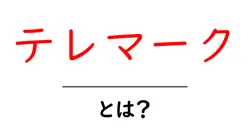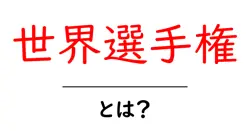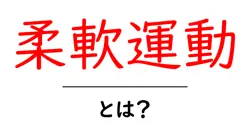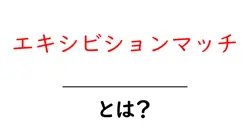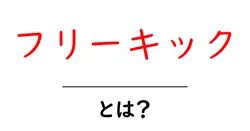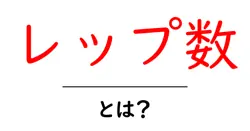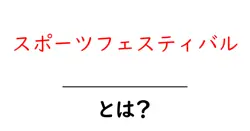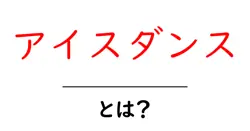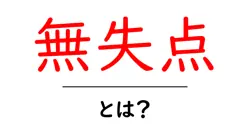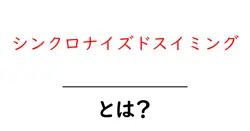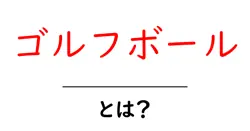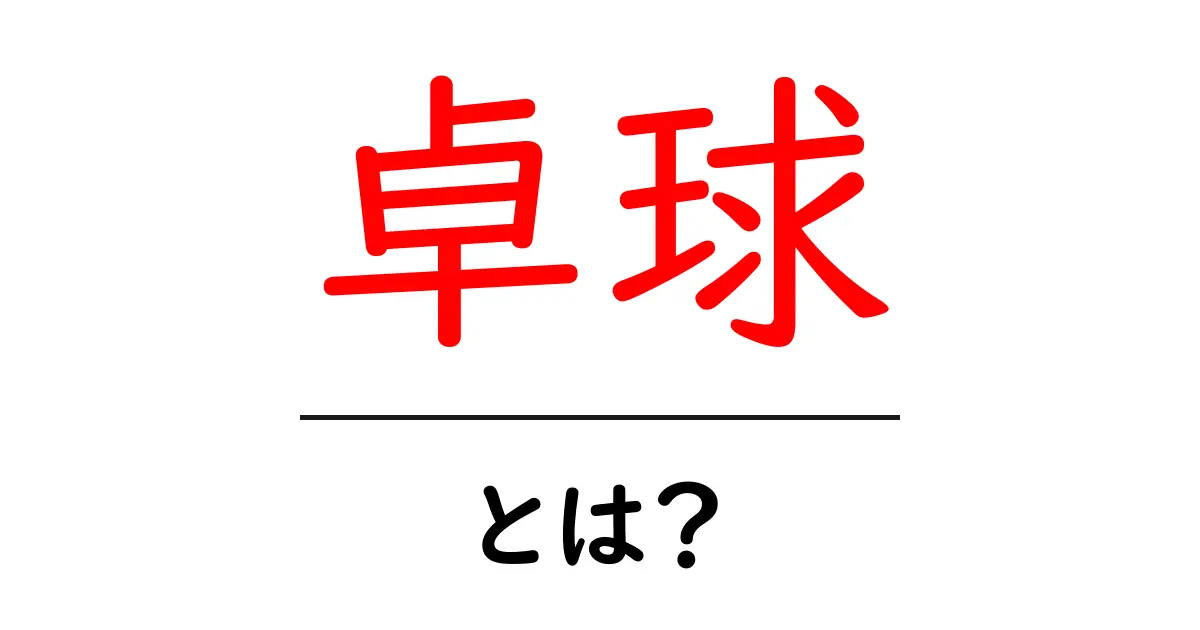

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
卓球・とは?初心者が知る基本と魅力をわかりやすく解説
卓球は小さなボールとラケットを使って行う室内のスポーツです。読み方はたっきゅうといい、世界中で親しまれています。このスポーツの魅力は手軽さと運動量のバランスにあり、練習の初期 단계から楽しみやすい特徴があります。家でも学校でも友達と気軽に遊べ、反射神経や集中力、体力を自然と養えます。
卓球の基本ルール
ルールの要点は次のとおりです。ゲームは11点先取で行われ、同点の場合は1点差以上のリードが必要です。サービスは基本的に2点ごとに交代します。ダブルスでは打つ順番が決まっており、ペアと協力して相手のコートへラリーを展開します。初めて触れる人は点数の数え方とラケットの振り方を覚えるだけで十分です。
用具とラバー
用具はシンプルですが、選び方でプレーの感触が大きく変わります。ラケットは自分の握りやすさと手の感覚を重視し、ラバーの粘着性や硬さを選びます。
基本の打ち方
フォアハンドは体の正面で振り抜く動きが基本です。肘を自然に曲げ、手首を使ってスイングの終わりで軽く下を向くようにします。初めはボールをコントロールすることを意識し、台の中央へ返す練習を繰り返します。
バックハンドは反対側の腕の動きを使って体の横からボールを返します。初心者は体の回転と腕の動きを同時に使う練習から始め、無理なくラケットを振れるようにしましょう。
練習のコツとメニュー
まずは正しい姿勢とグリップを安定させ、フォアハンドとバックハンドの基本動作を身につけます。反復練習が上達の鍵です。
初級の練習メニューの例です。1日目はフォアハンドの安定を、2日目はバックハンドを加え、3日目は両方をつなぐ練習、最後に壁打ちなどの簡単な対人練習を行います。
| 練習メニュー | 内容 |
|---|---|
| 初級 | フォアハンドとバックハンドの基本動作の安定化 |
| 実戦練習 | 友達とラリーを長く続ける練習 |
卓球の魅力と始め方
卓球は反射神経を鍛えつつ心肺機能も高めることができ、社交性も養えます。初めての人は近くのスポーツセンターや卓球場で安全に楽しむのがおすすめです。必要なのはラケット1枚と許容できるスペースだけです。
安全に楽しむコツとして、視線をボールに集中しつつ周囲への注意を忘れないこと、手首や肘の故障を避けるために無理をしないことを挙げられます。
卓球の関連サジェスト解説
- デフ 卓球 とは
- デフ 卓球 とは、聴覚に障がいのある人が楽しむ卓球のことです。デフは deaf の意味で、デフリンピックと呼ばれる国際大会も開かれています。デフ卓球は基本的には健常者と同じルールで行われ、ITTF の規定に沿って試合が進みます。しかし試合中の合図は音だけで伝わるわけではありません。審判の合図やレストタイムの指示は、手の動きや旗、そして選手同士の視覚的な合図で伝えられることが多く、プレーの流れを見逃さないことが大切です。デフ卓球の特徴として、コミュニケーションの工夫が挙げられます。コーチは遠くからも伝わるよう、声だけでなくジェスチャーや文字でサポートします。試合の準備には、色のコントラストがはっきりした用具選びや、耳が遠い人でも見やすいスピード感のあるプレーを身につけることが役立ちます。初めてデフ卓球に挑戦する人へのアドバイスとしては、まずは基本のフォームとボールのコントロールをゆっくり練習すること、近くの卓球クラブや学校の部活で経験者と一緒にプレーすることをおすすめします。誰でも楽しめる競技なので、友達と一緒に体を動かしながら練習すると続けやすいです。デフ卓球の魅力は、同じ境遇の仲間と支え合いながら成長できる点です。大会や練習会では、視覚的なサインの使い方を学ぶことで、相手の動きを読み取る力も高まります。聴覚に障がいがある人も、卓球を通じて友だちを作り、競技の喜びを味わえるスポーツです。
- wtt 卓球 とは
- wtt 卓球 とは、世界の卓球を動かす新しい仕組みを作ったブランドと組織のことです。WTTは World Table Tennis の略で、日本語で言うと“世界卓球”の意味になります。従来のITTF(国際卓球連盟)が主催していたプロ大会の仕組みを、商業的な活動も含めて一つのブランドとしてまとめ直したのがWTTです。これにより、プロ選手が出場する大会のスケジュールやランキングの仕組みが分かりやすくなり、ファンも楽しみやすくなりました。主な対象はトップ選手たちで、WTT World Tourには男女の大会が世界各地で開かれ、勝つと世界ランキングにポイントが入り、賞金も出ます。年間のツアーが組まれていて、賞金や放送、観戦の方法も整備されました。いわば、以前のITTFの大会を、ゲーム感覚で追いやすい世界の卓球のツアーとして整理した形です。初心者には、世界の大会スケジュールと、選手の成績がどう結びつくのかを知ると、試合の見どころが分かりやすくなります。WTTの目的は、スポーツとしての人気を高め、若い人にも見てもらえるようにすることです。公式サイトや公式SNS、配信で試合を観られる環境を整え、地域ごとの大会の活性化にも取り組んでいます。これから卓球を始めようとしている人は、wtt 卓球 とはを知るだけで、世界のトップ選手がどんな大会でどう競うのか、どうやって勝ち星を積み上げていくのかのイメージがつかむことができます。
- カデット 卓球 とは
- カデット 卓球 とは、主に中学生を中心とした15歳以下の選手を対象にした卓球の年齢カテゴリーです。日本の大会やITTFの階層では U15 に該当することが多く、地域のクラブや学校の部活で始める子が多いです。カデットの選手は、基礎技術の習得と試合経験を積み重ねることで、上の年齢カテゴリーへとステップアップします。競技は男女を問わず行われ、仲間と切磋琢磨する中で、技術だけでなくチームワークやフェアプレーの精神も育ちます。地域の大会では年齢が近い仲間と対戦することで、技術だけでなく体力や試合への適応力も高まります。ルールと道具の基本を押さえましょう。公式戦ではラリーを続けるごとに点数が入る 11 点制を採用することが多く、得点は2点差がつくまでゲームは続けられます(大会規定により多少異なる場合があります)。プレーに使う基本道具はラケット、ラバー、卓球ボール、専用コートなどです。ラケットは木製または合成材で、ラバーは表と裏で異なる粘着度やスピードの性質を選べます。試合中はサーブの順番、レシーブの受け方、相手への礼儀とスポーツマンシップを守ることが大切です。勝ち方のコツはルールの理解と状況判断。相手のリズムを崩すサーブやコントロールの練習が役立ちます。練習のコツとしては、まず基本のフォア打ちとバック打ちの正しいフォームを固めること。足の運び(フットワーク)を意識する練習、ボールのコントロールを磨く練習、サーブの種類を増やして相手の返球を読めるようにする練習が重要です。試合では緊張を落ち着かせる呼吸法や、負けを悔しがり過ぎず次に活かすメンタルの切り替えが役立ちます。クラブやコーチの指導のもと、徐々に難しい技へと挑戦していくと良いでしょう。また、練習日誌をつけて自分の長所と弱点を把握するのも効果的です。始め方はとてもシンプルです。地元の卓球クラブや学校の部活を探して見学・体験をしてみましょう。初心者には基本練習メニューと安全なウォームアップが用意されています。道具は初めはレンタルや安価なセットで十分です。上達には継続が大切なので、週に1〜2回の練習を定着させ、上の学年の選手やコーチのアドバイスを素直に取り入れると早く上達します。
- ドライブ 卓球 とは
- ドライブ 卓球 とは、卓球の基本的な打球のひとつです。ラケットを前に押し出すように短い距離で力を伝え、速い直線的な球を相手コートへ送るショットを指します。ループのように強い回転を狙うわけではなく、スピードとコントロールを重視します。試合の中盤やチャンスのリターンを崩すときに使われ、相手の守備の隙や回転の読みを崩すのにも役立ちます。打ち方の基本は、構えを安定させ、打点を身体の前方で作ることです。グリップは自分の癖に合ったものを選び、フォアハンドでもバックハンドでも、膝をしっかり曲げて体重を前方へ移動させます。ラケットの面はほぼ水平か、やや閉じ気味にして、ボールに対して平らか少し下向きの角度を作ります。打点はボールが胸の高さ前後、体の前で捉え、腕だけでなく体幹の回転と肘の動きを使って前方へ振り抜きます。フォロースルーは体の正面方向へ続け、力が抜けないように手首はリラックスさせます。練習のコツは、まずフォアハンドのドライブをリズムよく安定させることです。次にバックハンドのドライブにも挑戦し、位置取りと打点をそろえます。初めは台の近くで、壁打ちやパートナーとラリーを長く続ける練習が良いです。目標は、相手の返球を予測して最短の動きで打つことと、球が長くならないようにコントロールを意識することです。ドライブは、相手が激しく回転をかけてくる球に対しても、正面から力で返せる強力な武器になります。適切なフォームを身につけるには、コーチの見本を見たり、動画で自分の打ち方を確認したりするのも効果的です。焦らず、基本を反復練習して、徐々に速度と精度を高めていきましょう。
- ツッツキ 卓球 とは
- ツッツキ 卓球 とは、相手のボールを低い弾道で安定して返す基本的な技術です。強く打つのではなく、相手のリズムを崩すことを目的とします。ツッツキは初心者が最初に身につけるべき守備的なショットで、ラケットをやさしくボールの下をすくうように接触します。基本の姿勢は足を肩幅に開き、膝を少し曲げ、体の前で腕を自然に構えること。打点はボールが高さ的に台の高さより低い位置で、ネットすれすれの近距離で行います。打ち方のポイントは、手首を小さく動かし、肘を体の横に近づけて、ラケットを水平またはわずかに上向きに保つことです。力を入れすぎず、ボールに対して“押す”感覚で優しく触れるのがコツです。ツッツキを使う場面は、ラリーの初期や相手の短いボールを返すとき、小さな打点の取り合いになったときなど、相手にプレッシャーを与えつつ自分のペースを作る場面です。練習のコツとしては、最初はフォームの安定を優先し、力まずにボールが低く出る感覚を身につけること。次に、同じ場所から連続して短いツッツキを返すドリル、相手と向かい合って横方向の動きを加える練習、最後にゲーム形式で実戦感覚を養います。よくある失敗は、打点が高すぎてボールが浮く、手首を振りすぎてコントロールを失う、体の上半身だけで打ってしまう—この場合は体重移動とリズムを見直しましょう。始めは難しく感じますが、地道な反復練習で安定したツッツきが身につきます。できるだけリラックスして、相手の力に頼らず自分のリズムで返す練習を続けてください。ツッツキは卓球の土台になる技なので、これをマスターすると、フォアハンド・バックハンドの応用技術へ自然につながります。
- ホープス 卓球 とは
- ホープス 卓球 とはというキーワードは、卓球を学ぶときによく検索される言葉です。この記事では、中学生でも分かる自然な日本語で、どんな意味で使われるのかを解説します。まず、ホープスが何かを決定するには、文脈を確認することが大事です。ホープスはブランド名、チーム名、クラブ名、または特定のトレーニングプログラムの呼び名として使われることがあります。地域や学校によって意味が変わるため、公式情報を確認するのが確実です。次に、よくある使われ方の例を挙げます。例1: 子ども向けの卓球教室が「ホープス」という名前で開講されている。例2: あるメーカーが提供する入門用ラケットのシリーズ名として使われている。例3: 趣味の団体名として地域の卓球クラブが「ホープス」を名乗っている。こうした場合、意味は全部同じではなく、実際には「何を指しているのか」を特定する必要があります。確認のコツとしては、公式サイトやSNS、パンフレットの説明を読み、所在地・運営元をチェックすることです。さらに、検索結果の説明文や問い合わせ先が一致しているかを見れば、正しい意味に近づけます。最後に、初心者が知っておくべきポイントをまとめます。ホープスが団体名か商品名かで学習の進め方は変わりますが、どの場合も基本の基礎(正確な握り方、ストローク、サービスの基本)は共通して重要です。検索する時は、単に言葉の意味を知るだけでなく、その言葉が自分の興味のある文脈でどう使われているかを読み取る力を養いましょう。
- メディカルタイムアウト 卓球 とは
- メディカルタイムアウト 卓球 とは、試合中に体の不調やケガが発生した場合に、試合を一時停止して医療スタッフが介入するための短い休憩のことを指します。テーブルテニスでは、選手の安全と怪我の悪化を防ぐ目的でこの制度が設けられることがあります。例えば足首のねんざ、頭痛、脱水など、プレーの継続が難しいと判断されるケースです。この時、選手はコート上で治療を受けることを審判に申請します。審判が同意すると、試合は一時停止し、医療スタッフがコートに入り、治療や包帯、冷却などの処置を行います。時間の長さは大会規定で定められており、一般的には1回あたり約60秒前後とされることが多いですが、競技大会や大会規程により異なります。医療タイムアウトは治療目的であり、戦術的な休憩には使えません。審判は必要であれば、プレーの公平性を守るために時間を制限します。連続で複数回の医療タイムアウトを認めない大会も多いです。大会ごとにルールが異なるため、出場する大会の規程を必ず確認してください。
- 後藤杯 卓球 とは
- 後藤杯 卓球 とは、後藤杯という名の卓球大会のことです。名前の由来は創設者やスポンサーの姓が「後藤」であることが多く、その貢献を称える意味を持ちます。大会は地域の学校やクラブが主催することが多く、地域の選手や部活動の仲間が集まって技術を競い合います。年齢別や男女別の部門が用意され、シングルスだけでなくダブルスが行われることもあります。試合形式は大会ごとに異なりますが、一般的には予選を経て決勝トーナメントへ進む形が多く、11点制のゲームを複数取り、2点差以上で勝者が決まります。公式ルールに近い形で運用されることが多い一方で、地域のルールが加わることもあります。参加方法は公式サイトや学校・地域の掲示板で案内され、エントリー費が必要な場合があります。道具は自分のラケットとラバーで挑むのが基本ですが、会場でレンタルや販売をしている大会もあります。初めて参加する人には、基本姿勢やフォアハンドとバックハンドの練習、焦らず1点ずつ取るリズム作り、応援を受けながら楽しむ心構えが役立ちます。観戦する場合は、試合の流れやポイントの取り方を見て学ぶことができます。
- 新体連 卓球 とは
- 新体連 卓球 とは、一般には学校や地域のスポーツ組織で使われる表現ですが、具体的な意味は文脈によって異なる点に注意が必要です。略称のため、特定の団体名を指す場合もあれば、より広い意味で新体連系の卓球活動を指す場合もあります。多くは学校の部活動や地域のクラブ活動として行われ、仲間と一緒に楽しく練習することを目的としています。活動の内容は、基本的な打ち方の練習、ラケットの持ち方、フットワーク、サーブとリターンの練習、そして簡単な戦術の理解など、初級者にも理解しやすいものから始まります。練習は週に数回行われることが多く、校内戦や地域のミニ大会が開かれることもあります。公式戦のルールは通常の卓球と同じですが、審判の指示に従いマナーを守ることが大切です。参加方法は、学校の部活動として参加する方法、地域のスポーツクラブに加入する方法、または学校行事として行われる体験会に参加する方法など、さまざまです。必要な道具は、初心者ならレンタルや共有のラケット、卓球台、球、運動しやすい服装が基本です。道具選びのポイントとしては、握りやすさ、重量のバランス、グリップの感触が自分に合うかどうかを確かめることが挙げられます。初めての人は、まずはクラブの体験会や見学に参加して雰囲気をつかみ、コーチや部長に基本の姿勢や挨拶の仕方を教わると良いでしょう。短い練習から始めて、徐々に足の使い方やラケットの持ち方、ネットを越える感覚をつかむことが大切です。新体連 卓球 とは、こうした学校や地域の活動を通じて、体を動かす楽しさと協力する喜びを学ぶ機会でもあります。
卓球の同意語
- テーブルテニス
- 卓球の正式名称。国際的・公式で使用される表現で、規則や大会名にも使われる。
- ピンポン
- 日常会話や報道の中で使われる親しみやすい表現。競技を指すときも使われることがある。
- 卓球競技
- 卓球を競技として捉えた表現。公式説明や教育資料で見られる表現。
- 卓球種目
- 大会・競技紹介の中で、卓球を構成する“種目”の一つとして言及する表現。
- テーブル・テニス
- テーブルテニスと同義の表記。中黒入りの表現で使われることがある。
- テーブルテニス競技
- 卓球を競技として表す表現のひとつ。公式資料や解説で使われることがある。
卓球の対義語・反対語
- 室内スポーツ
- 卓球は主に室内で行われるスポーツの代表格。対義語としては、室内で行われない、または室内を前提としない競技を指す使い方ができます。
- 屋外スポーツ
- 卓球が室内競技であるのに対し、屋外で行われる競技を指す対義語。風や天候の影響を受けやすい点が特徴として挙げられます。
- 野球
- バットとボールを使う球技の代表格。用具・戦い方・競技環境が卓球と大きく異なるため、対義語として捉えられることが多いです。
- サッカー
- 足でボールを扱う世界的に広い競技。卓球とは競技の性質・用具・プレースタイルが異なる対照的な例として挙げられます。
- バレーボール
- ネットを挟んでボールを打ち合う球技。環境・ルール・戦術が卓球と大きく異なるため、対義語的な例として適しています。
- 水泳
- 水中で行う競技。球技ではなく体力・技術の面で異なる競技カテゴリである点が対比になります。
- 陸上競技
- 地上で走る・跳ぶ・投げる競技の総称。卓球と異なる競技種別として、対義語・対比として用いられることが多いです。
卓球の共起語
- ラケット
- 卓球を打つ道具。木材や合成材料で作られ、表面にはラバーが貼られている。
- ラバー
- ラケットの打球面を覆うゴム。回転とコントロールを生む重要な部分。
- ボール
- 直径40mmの軽い球。白またはオレンジ色で回転とスピードが特徴。
- 卓球台
- 競技用の平らな台。両サイドにアウトラインがあり、中央にはネットが張られる。
- ネット
- 卓球台の中央に張る網。打球が越える必要がある。
- サーブ
- 試合開始時の打ち出し球。回転・方向・スピードを変えて相手を崩す技術。
- フォアハンド
- 前方に振って打つ基本の打球。初心者にとって最初の技術のひとつ。
- バックハンド
- 後方に振って打つ基本の打球。利き手と反対側で打つことが多い。
- レシーブ
- 相手のサーブを受けて返球する技術。位置取りと反応がポイント。
- スマッシュ
- 速く強い打球。決定打として得点を狙う技術。
- ドライブ
- 回転をあまりかけず、速度とコントロールで攻める打球。
- ループ
- 強い回転をかける技。綺麗な打点とコントロールが求められる。
- 回転
- ボールの回転のこと。攻撃・守備の鍵になる要素。
- スピン
- 回転の英語表現。回転量と向きを指す用語として日常的に使われる。
- ブロック
- 相手の速い球をその場で受け止めて返す守備的技術。
- カット
- 回転を活かして守る技。低い軌道の返球が特徴。
- グリップ
- ラケットの握り方。フォア・バックの持ち方に影響する。
- フットワーク
- 足の動き。打点を作り、素早く位置を変える。
- 練習
- 上達のための日々のトレーニング全般。
- 試合
- 対戦形式の競技。勝敗を競う場。
- 大会
- 公式の競技イベント。全国・世界レベルの大会がある。
- ITTF
- 国際卓球連盟。ルール・ランキング・統括を行う国際機関。
- 日本卓球協会
- 日本国内の卓球競技を統括する団体。
- Tリーグ
- 日本のプロ卓球リーグ。
- テーブルテニス
- 卓球の別称。英語のTable Tennis の和名。
- オリンピック
- 卓球が正式種目として実施される国際大会。
- 世界選手権
- 世界規模の選手が競うトップレベルの大会。
- 公式戦
- 公式ルール下で行われる対戦形式の試合。
- スコア
- 得点の表示。1点ずつ加算され、セットやゲームの勝敗を決める。
- サーブ&レシーブ
- サーブを打つ側と受ける側の一連の攻守の流れ。
卓球の関連用語
- 卓球
- 室内で行われる競技。小さなラケットで球をネット越しに相手の台に返して得点を競うスポーツ。
- 卓球台
- 長さ2.74m、幅1.525m、高さ0.76mの平らな台。中央にネットが張られ、白いラインがあります。
- ネ ット
- 卓球台の中央に張られた網。高さ約15.25cm。
- ラケット
- 球を打つ道具。木製の板にゴムを貼って使う。
- ラバー
- ラケットの表面に張るゴム。スピンとコントロールの要。
- 表ソフト
- 表面が柔らかいゴム。回転をかけやすい。
- 粒高ラバー
- ゴム表面に粒(突起)があるラバー。相手の回転を崩しにくい打球が出やすい。
- ペンホルダー
- 握り方の一種。ペンのように握って打つラケットの持ち方。
- シェークハンド
- 握る形のラケット。最も一般的な握り方。
- フォアハンド
- 前方の手で打つ基本の打ち方。
- バックハンド
- 後方の手で打つ打ち方。
- サーブ
- 試合開始時に自分のコートから相手コートへ球を打つショット。
- サーブ回転
- サーブにかかる回転の種類。上回転、下回転、横回転など。
- リターン
- 相手のサーブを返球する動作。
- レシーブ
- サーブを受けて返すこと。地域によって呼び方が異なることも。
- トップスピン
- 球に強い上向き回転を掛ける打球。飛距離と速度を稼ぎやすい。
- バックハンドトップスピン
- バックハンドでトップスピンを掛ける打球。
- バックスピン
- 球が後方に回転する球。落下時に沈む傾向がある。
- サイドスピン
- 横方向の回転を掛けた球。横回転で相手の返球を崩すことがある。
- スピン
- 球の回転の総称。回転量と方向で球の挙動が大きく変わる。
- ループ
- 高さのある回転重視の攻撃打法。主にフォアハンドで使われることが多い。
- カット
- 相手の球の回転を読み、低く浅い弾道で返す防御的技術。
- プッシュ
- 低く短く回転をかけて返球する守備的技術。
- ロブ
- 高く大きく弧を描く打球。相手の前進を止めるのに有効。
- ブロック
- 相手の強打をラケットで受け止めて返す守備的技術。
- デュース
- 得点が10-10などのデュース状態。勝つには2点差が必要。
- 11点制
- 1ゲームの得点は11点先取で、2点差が必要。
- サービスエリア
- サーブを打つ際のサービス側の決められたエリア。
- サーブ交代
- サーブの回数を交代するルール。通常は2点ごと、デュース後は1点ごとに交代。
- ダブルス
- 2人1組で行う対戦形式。サービス・リターンの順序に特有のルールがある。
- シングルス
- 1対1の対戦形式。
- 団体戦
- 複数の選手がチームとして対戦する形式。全国大会などで採用される。
- ITTF
- International Table Tennis Federationの略。国際卓球連盟。公式ルールを管理。
- 日本卓球協会
- 日本国内の卓球競技を統括する組織。大会運営や普及活動を行う。
- 公認球
- ITTF公認の公式戦用ボール。直径40mm、重さ約2.7g、計測規格が定められている。
- 公認球の材質
- 現在はABS樹脂が主流。以前はセルロイド球が使われていたこともある。
- 台上戦術
- 台の近くでの打ち合いを重視する戦術。短い球やネット前の駆け引きが重要。