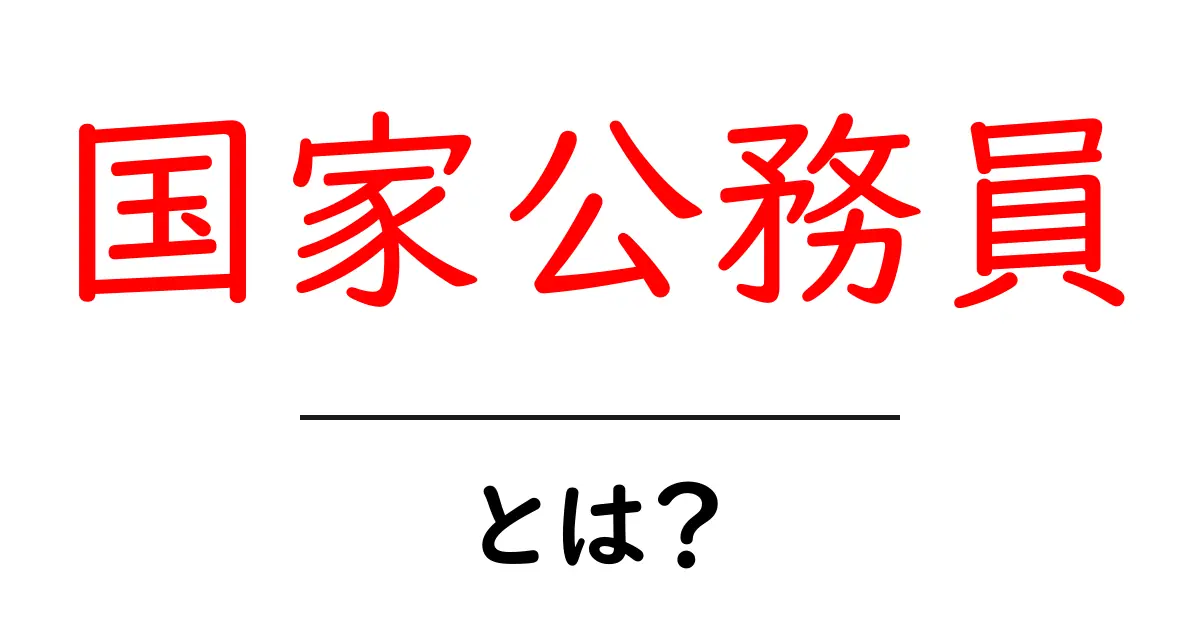

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
国家公務員とは何か
国家公務員とは国の行政機関で働く公務員のことです国の政策を実行し国民の生活を支える役割を担います。
国の機関には中央省庁や独立行政法人などがあります外交財政教育警察など幅広い分野を担当します。
地方公務員との違いは任用の主体と任用の仕組み給与制度などです。地方公務員は都道府県市区町村の自治体で働くのに対し国家公務員は国の機関で働きます。
主な職種と仕事内容
国家公務員の職種は多岐にわたり実際には数え切れないほどですのが代表的なものを挙げると次のようになります
外交官として外国との交渉や国際協力を行う人もいます
税務官として国の財政を支える人もいます
警察官公務員として治安の維持や防災に関わる仕事もあります
上の例のほかにも財務医療教育行政の部署で法令の作成や予算の配分など幅広い業務があります
国家公務員になるには
新しく国家公務員になる人は国家公務員採用試験を受けます。試験は種別があり I種 II種専門職などがあり自分の適性に合わせて受けます。
試験に合格したあとは研修を受けて配属先が決まります。初任給や福利厚生は国の水準に合わせて定められており安定した職場として知られています。
国家公務員は長い間安定して働くことができる反面責任も大きく時には残業や公務に伴う緊急対応が求められます
国と地方の違いと将来
国の公務員と地方の公務員は働く場所と役割が異なります。国は国内の法律や予算を作り実行する中心的な役割を担い地方は地域の生活を支える役割を担います
表で見る国家公務員と地方公務員の違い
| 項目 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| 定義 | 国の機関で働く公務員 | 都道府県市区町村の機関で働く公務員 |
| 採用 | 国家公務員採用試験など | 地方公務員採用試験など |
| 給与 | 国家公務員給与制度 | 地方公務員給与制度 |
まとめ
国家公務員は国の仕事を支える大切な役割を持つ職業です。国家公務員になるには試験と研修を経て配属先で経験を積みます。地方公務員と比べる場面もありますがどちらも国と地域を支える重要な存在です。
国家公務員の関連サジェスト解説
- 国家公務員 一般職 とは
- 国家公務員 一般職 とは、国家が直接雇う公務員のうち、特別な専門職や総合職ではない、一般的な事務作業を主に担当する職種のことです。国家公務員にはいくつかの分類があります。総合職は将来の幹部候補として育成されるキャリアパスで、一般職は日々の行政の現場を支える役割です。一般職には、窓口対応、文書作成、予算の取り扱い、データの管理、官庁内の庶務など、幅広い業務が含まれます。採用の道は年度ごとに異なりますが、大学卒業程度で応募できることが多く、試験科目は学力と適性を測るものです。配属先は省庁の本庁、出先機関、地方自治体と連携する部局などで、窓口対応やデータ管理、会議の準備といった実務を担います。職場は転勤がある場合も多く、勤務地は東京だけでなく全国の各官公庁に広がります。一般職は、安定した雇用と福利厚生、昇給・昇格の機会が整っており、長期的なキャリアを築きやすい点が魅力です。仕事の例として、窓口対応、文書作成、データ整理、予算の執行補助、統計調査のサポート、会議運営の補助などがあります。国の仕事は公正さと正確さが求められ、私たちの生活を支える政策の実行を支える重要な役割です。公務員としての働き方には、安定と責任感の両立、チームでの協力、時に大きな決定を行う場面がある点が特徴です。難しく聞こえますが、丁寧な研修と先輩のサポートがあり、初めてでも学びやすい環境が整っていることが多いです。総じて、国家公務員 一般職 とは、国家の組織の中で、日常の行政事務を担う一般的な職種で、大学卒業程度で受験できる採用試験を経て就職する、安定した公共の仕事です。
- 国家公務員 総合職 とは
- 国家公務員 総合職 とは、政府の中で最上位の採用区分のひとつです。国家公務員にはいくつかの区分がありますが、総合職は「政策を作り、国を動かす指揮をとる人になる道」です。一般職よりも将来の幹部候補として期待され、海外の活動や行政の現場を結ぶ橋渡しをすることが多いです。仕事の内容は多様で、予算の組み方を考えたり、他の省庁と協力して新しい制度を作ったりします。調査・分析、国際交渉、災害対応、教育・産業施策など、幅広いテーマを扱います。配属は最初のころは実務の基礎を学ぶ研修期間があり、以後は所属する省庁で現場の業務を経験します。将来は部局の課長クラスや政策決定の場でリーダーとして働く機会が増えます。採用と試験のしくみは、大学卒業程度の応募が中心です。総合職の採用試験では、筆記試験(日本語、一般教養、外国語など)、論文、適性検査、そして面接が行われます。受験勉強では、社会の出来事に関する知識、論理的な文章を書く練習、そして面接で自分の考えをしっかり伝える練習が必要です。試験は毎年行われ、競争も激しいのが特徴です。生活の面では、勤務地は全国に点在し、転勤があるのが普通です。安定した仕事ではありますが、責任の重さや長時間の勤務となることもあり得ます。やりがいとしては、国の未来を決める政策づくりに関われる点や、社会の困りごとの解決に直接関わる点が挙げられます。総合職を目指す人は、好奇心・粘り強さ・協調性が大切です。ニュースや制度の変化を日々追う習慣を持ち、文章力と説明力を磨くと良いでしょう。高校生・大学生のうちに、模擬対策や公務員試験の基礎を身につけておくと、総合職への道が開けます。
- 国家公務員 教養区分 とは
- 国家公務員とは、日本の中央政府の機関で働く職員のことです。国家公務員にはいくつかの職種区分があり、教養区分はその一つです。教養区分は、主に一般的な行政事務や政策の企画・調整を担当する職務を想定した区分です。具体的には、法令の運用を考えたり、予算の使い道を決めたり、いろいろな人と相談して新しい制度を作る仕事などがあります。教養区分の人は、幅広い知識と柔らかい思考、文章力が求められます。技術区分と違い、機械や専門の技術を直接扱う仕事よりも、組織全体を動かす役割を担うことが多いのです。この区分は、大学を卒業して一定の学力を持つ人が対象になることが多く、試験も「一般教養」や「総合的な判断力」を測る設問が中心になることがあります。年度や制度の改正で区分名が変わることもあるため、最新情報は公務員試験の公式サイトで確認してください。勉強のポイントとしては、広い教養を身につけることです。経済・社会・政治のニュースを日常的に読み、難しい文章を分かりやすく整理する練習をします。文章の要点を自分の言葉でまとめる練習や、図表を読み解く練習も役立ちます。また、英語や外国語の基礎があると選択肢が広がることもあります。作文力やプレゼンテーションの技能も評価につながることがあるので、日記風のメモをつける、友人や先生に説明する練習をするとよいでしょう。
- 国家公務員 特別職 とは
- 国家公務員とは、日本の国の仕事を行政として行う公務員のことです。国の政治を行う人たちは大きく分けて「一般職」と「特別職」に分かれます。特別職とは、一般の公務員の枠組みには必ずしも当てはまらず、任用の仕組みや任期、任務の性質が特別なポストを指します。多くの場合、政治的任用の色が強い役職や、国家の重要な機関のトップ級の役職がこの特別職に含まれることが多いです。具体的には、国務大臣や副大臣、政務官といった政治任用の職、そして司法・外交などの分野で高位の責任を担うポストが挙げられることがあります。これらの職は、任命権者が所属する機関によって任期が定められており、任期途中での交代や再任の可能性がある点が一般職とは異なります。また、特別職は公務の中でも国家の政策決定に深く関わることが多く、安定した身分の保証よりも、時には新しい方針を実行するための柔軟性が求められることもあります。公務員制度は複雑で時々改正されるため、最新の情報を公式の資料で確認することが大切です。
- 国家公務員 専門職 とは
- 国家公務員 専門職 とは、国家機関で働く公務員のうち、専門的な知識や資格を必要とする職種のことです。日本の公務員制度では、一般職と専門職という区分があり、専門職は法律・会計・医療・技術など、特定の分野で高度な専門性を求められます。専門職は日常の行政業務だけでなく、政策の立案・分析・実務の実行にも関わることが多く、専門性の高い業務を担います。採用の仕組みは分野ごとに異なり、国家公務員専門職採用試験や、大学の学位・資格を前提とした応募、あるいは実務経験を重視する選考などがあります。一般職の試験と比べて、専門分野に関する知識や資格を持っていることが前提となるケースが多いです。必要な学歴は大学卒以上が多く、資格試験の合格や実務経験が応募条件になる場合もあります。代表的な分野としては、法務・財務・会計・医療・薬剤・技術・環境・教育などが挙げられ、分野により必要な資格や免許も異なります。実際の職場は省庁の本庁だけでなく、独立行政法人や政策研究機関など多岐にわたり、政策の研究、監査、法令の整備、規制の設計、技術開発の支援など、国家の運営を支える役割を果たします。キャリアパスとしては、所属分野で経験を積んだ後、異動・昇進・配置換えを通じて専門性を深める道が描かれます。定年制や任期制の枠組みの中で、長く働く人もいれば、専門職としてのスキルを活かして他の公的機関へ移る人もいます。受験準備のコツは、募集要項を丁寧に読み、必要資格の取得を計画することです。関連する実務経験を積み、ニュースや学術的な動向に目を向けておくと面接での話題づくりに役立ちます。中学生にも理解しやすく言えば、専門職は「その分野のプロとして国の仕事をする人たち」です。このように、国家公務員 専門職 とは、特定の分野で専門性を活かして国家の仕事を支える職種群です。安定した雇用と専門性の両方を得たい人に適しており、学ぶ意欲と実務経験が重要なポイントです。
- 国家公務員 一種 とは
- 国家公務員 一種 とは、中央の省庁や独立行政法人などで働く高位の職を指す採用区分の一つです。主に総合職や高級専門職と呼ばれる職種が含まれ、政策の立案・企画・調整・国際業務など、組織の中核となる業務を任されることが多いです。I種を受ける人は大学卒業以上の学歴を持つことが多く、学力だけでなく論理的思考力や幅広い教養が求められます。選考は国家公務員採用試験の一部として実施され、筆記試験・適性検査・面接などが組み合わさります。難易度は高く、競争倍率も年度や職種により大きく変わります。 II種は一般職と呼ばれ、現場の行政事務や窓口業務を中心に担当します。I種とII種の大きな違いは、任務の規模・難易度・求められる専門性です。I種は政策づくりや組織運営といった中枢的な役割を担う機会が多く、キャリアの幅も広い傾向があります。受験を目指す人は、まず公式の募集要項を確認し、過去問や模試で実力を測るとよいでしょう。語彙力・読解力・計算力・時事問題への関心をバランスよく鍛えるほか、ニュースや公的な資料に触れる癖をつけると効果的です。合格後は研修・OJTを経て多様な部署で経験を積み、専門性を深めながら長期的なキャリアを築く道があります。
- 国家公務員 キャリア とは
- 国家公務員とは、日本の国の機関で働く人のことです。国家公務員の仕事は、国の法律をもとに、予算をつくったり、社会を支える制度をつくったりすることが中心です。そんな仕事を続ける道として「キャリア」という言葉がよく使われます。キャリアとは、将来どんな役割を担うかという“職務の道筋”のことを指します。国家公務員には、歴史的に「総合職」と「一般職」という二つの道があり、より戦略的な仕事を目指す人は総合職、窓口業務や事務を長く積む人は一般職という区分がありました。最近ではこの区分の呼び方や制度が変わってきましたが、基本的な意味は“役所の中で昇進していくためのキャリアをどう設計するか”です。入庁後は、基礎的な教育を受け、所属する部署で仕事を経験します。若い時は現場の経験を積み、徐々に企画を任されたり、課長クラスの仕事を手伝ったりします。キャリアを積む人は、国の政策づくりに携わる機会が増え、他の省庁への出向や海外勤務、部局間の人事ローテーションを通じて幅広い経験を得ることができます。安定した雇用と公的な責任を両立しつつ、社会の課題に対して長期間貢献できる点が魅力です。将来を見据えると、どの分野に関心があるか、どんな仕事で社会に役立ちたいかを考えながら学び、試験や評価の仕組みを理解しておくとよいでしょう。
- 国家公務員 指定職 とは
- 国家公務員とは、日本の国の仕事を担う公務員のことです。国家公務員にはいくつかの区分があり、その中の一つが指定職です。指定職とは、法令で“指定”された特定の職務・職種を指し、一般に知られている一般職とは採用の仕組みが異なる場合があります。要するに、難しい専門性を持つ仕事や重要な任務を任されるポストを、法令が指定して区別しているということです。具体的には、外交、検察、裁判所などの公的機関の中で、特定の任務を担う職が指定職として位置づけられることが多いです。しかし、すべてのケースが外交官や司法関連だけというわけではなく、研究者的な技術職や政策の企画・運用を担う職など、分野はさまざまです。指定職は一般の新規採用の試験とは別のルートで任用されることがあり、経験や専門性が重視される場合もあります。なぜこの区分があるのかというと、国家の重大な任務や高度な専門性を要する業務は、広く一般試験だけでは確保しにくく、適切な人材を適切なポストに配置するための制度として作られています。ポイントとしては、指定職は法令で定義され、区分として存在すること、採用ルートが一般職と異なる場合があること、専門性・経験が重視されることなどです。制度は自治体ごとに内容が違うこともあるので、最新情報は総務省や人事院の公式情報を確認するとよいでしょう。
- 薬剤師 国家公務員 とは
- 薬剤師 国家公務員 とは、薬剤師免許を持つ人が国の機関に雇われ、公務員として働く人たちのことです。国の薬事行政を支える立場で、薬の安全性を確保し、医薬品の品質管理・適正使用の推進、健康政策の立案などを担当します。勤務先は厚生労働省の薬務局・健康局や、独立行政法人の研究機関、国立病院機構、検査研究所など多岐にわたり、地域ごとの自治体勤務よりも国全体を見渡す仕事が中心です。具体的には新薬の審査や承認の制度運用、医薬品の監視・副作用情報の収集、災害時の医薬品対策、薬事行政の企画・立案、教育・啓発活動、場合によっては研究開発の現場にも関わります。薬剤師としての臨床経験を生かしつつ、公務員としての規則や手続き、組織運営の仕組みを学ぶことになります。国家公務員としての採用は、国家公務員採用試験を受けて合格することが多く、薬学部卒業と薬剤師免許の取得が条件になる場合があります。配属先は厚生労働省のほか、独立行政法人や公的研究機関など多岐に及ぶため、地域の枠を超えたキャリアを描くことができます。
国家公務員の同意語
- 公務員
- 国家公務員を含む、政府機関で公務を担う人の総称。広義には地方公務員も含まれますが、文脈で国家公務員を指す場合も多いです。
- 国家職員
- 国家公務員を指す言い換え表現で、国の機関で働く職員を意味します。
- 国の職員
- 国(政府)所属の公的機関で働く職員のこと。文脈次第で国家公務員を指すことがあります。
- 国家行政職
- 国家公務員のうち、行政を担当する職種を指す語。行政系の職員を広く表現します。
- 中央公務員
- 国の行政機関で働く職員のこと。国家公務員の総称として使われることがあります。
- 中央省庁職員
- 中央省庁に所属する国家公務員を指す表現。政府の中央部門で働く人を示します。
- 行政職員
- 公務員の分類の一つで、行政を担う職員を指します。国家公務員の中の一部を指す言い換えとして使われます。
- 政府職員
- 政府の機関で働く職員を指す表現。日常会話や報道で見かけることがあります。
- 国家機関職員
- 国の機関に所属して公務を行う職員を指す表現。国家公務員の同義語として使われることがあります。
国家公務員の対義語・反対語
- 地方公務員
- 地方自治体で公務を担う職員。国家公務員とは組織の所属先が異なる点が対になる概念として挙げられる。
- 民間企業の社員
- 企業に雇われ、民間部門で働く従業員。公的機関ではなく私企業に所属する点が対比される。
- 民間人
- 公務員として雇われていない一般の人。公務員ではない立場を示す広義の対義語。
- 自営業者
- 自分の事業を自ら運営する人。雇われる立場ではなく、個人事業主として活動する点が対義的。
- フリーランス
- 特定の企業に長期所属せず契約ベースで仕事を受ける働き方の人。公的機関の職員ではない点が対になる。
- 非公務員
- 公務員ではない人。公務員という身分以外の人を指す総称的な対義語。
- 会社員
- 民間企業に勤める従業員。給与所得者として民間企業に所属する働き方の代表例として対比される。
国家公務員の共起語
- 国家公務員法
- 国家公務員の身分・権利・義務を規定する基本的な法律。
- 公務員試験
- 国家公務員になるための試験全般。筆記・適性検査・面接などを含む選考プロセス。
- 国家公務員試験
- 国家公務員になるための試験(公務員試験と同義語として使われることが多い)。
- 採用試験
- 公務員に限らず、採用を目的とした試験全般のこと。
- 総合職
- 国家公務員の中で、将来の管理職を想定するキャリア区分。
- 一般職
- 国家公務員の一般的な職員区分。初級から中堅クラスの採用に用いられることが多い。
- 事務系
- 行政事務・庶務など、事務的業務を指す職務区分。
- 技術系
- 技術職・IT職・研究開発など、技術的専門性を要する職務区分。
- 専門職
- 特定の専門領域に特化した職務区分。
- 大卒程度
- 大卒程度の学歴が応募条件・資格条件として挙げられることが多い。
- 学歴
- 採用条件・採用後の昇任などと関連して語られる要素。
- 人事院
- 国家公務員の任用・給与・昇任等を管轄する機関。
- 人事院規則
- 人事院が定める規則。採用・給与・人事管理の基準を規定。
- 省庁
- 国家公務を担う各省庁の総称。公務の現場が所属する組織体。
- 総務省
- 行政・自治・情報通信・選挙行政などを担当する省庁の一つ。
- 財務省
- 財政・税制・国の財政運営を担当する省庁。
- 法務省
- 法務・司法・在留資格管理などを担当する省庁。
- 外務省
- 外交・国際関係を担当する省庁。
- 文部科学省
- 教育・科学技術・文化財保護を担当する省庁。
- 経済産業省
- 産業政策・貿易・エネルギー等を担当する省庁。
- 厚生労働省
- 社会保障・労働・衛生・福祉を担当する省庁。
- 内閣府
- 内閣の政策総合・調整を担う機関。公務員の配置・政策運用にも関与。
- 省庁勤務
- 国家公務員として省庁に勤務することを指す表現。
- 給与
- 給与制度・支給額・手当など、給与関連の話題で共起。
- 年収
- 給与の総額としての年間収入の目安。
- 福利厚生
- 休暇制度・各種手当・健康保険など、福利厚生全般。
- 昇給
- 年次ごとに給与が増える制度的要素。
- 昇格
- 役職・階級の昇進・キャリアの進展を指す。
- 研修
- 新任研修・階層別研修など、職務能力を高める教育プログラム。
- 退職金
- 退職時に支給される一時金・年金的給付の総称。
- 年金
- 公務員の老後を支える年金制度。
- 転勤
- 勤務地の異動・転勤が発生する勤務形態。
- 異動
- 人事異動。配属先の変更を含む広い概念。
- 守秘義務
- 公務で知り得た情報の秘密を守る義務。
- 公務員倫理
- 公務員として守るべき倫理規範・品位の保持。
- 情報公開
- 行政情報の公開・透明性を確保する制度・概念。
- 政策立案
- 国の政策を立案・検討する職務。
- 行政
- 政府の実務・行政運営全般を指す広い概念。
- 配属
- 所属部署・部局への配置のこと。
- 勤務地
- 実際に勤務する場所(省庁所在地・都道府県庁など)。
- 休日
- 法定休日・休暇日程などの休暇制度。
- 休暇
- 年次有給休暇を含む各種休暇の総称。
- 雇用安定
- 公務員特有の安定した雇用環境という特徴。
- キャリアパス
- 公務員としての昇進・異動・専門職などの道筋。
- 記述試験
- 記述式問題による試験。専門知識の深さを問う形式。
- 筆記試験
- 択一・記述・作文などを含む筆記形式の試験。
- 面接
- 個別面接・集団面接など、口頭試問を用いる選考プロセス。
- 適性検査
- 性格・適性を測る検査。適性を重視する配属決定にも影響。
国家公務員の関連用語
- 国家公務員
- 日本の中央政府機関で働く公務員の総称。政策の企画・立案・実施、行政運営の中核を担います。
- 国家公務員法
- 国家公務員の身分・任用・服務・給与・倫理などを定める基本法です。
- 人事院
- 国家公務員の人事を統括する機関。任用・給与・人事制度の企画・運用を行います。
- 人事院規則
- 人事院が定める職員の任用・給与・勤務条件などの細則です。
- 国家公務員採用試験
- 国家公務員になるための公的な試験制度。I種・II種・技術系などの区分があります。
- I種(総合職)
- 高度な大学卒業者を対象とする採用区分。政策形成・企画・マネジメント業務を担います。
- II種(一般職)
- 大学卒業者・短大・専門卒程度を対象とする採用区分。庶務・行政事務の職務が中心です。
- 技術系採用
- 理系・技術系の専門職として設計・開発・分析などの技術業務を担当します。
- 総合職
- 高度な企画・政策形成・組織運営を担う職種群。長期的なキャリアを想定して採用されます。
- 一般職
- 日常的な行政事務を幅広く担当する職種群です。
- 行政職
- 行政の実務・企画・運用を担う職種の総称です。
- 事務系
- 文書管理・データ入力・庶務など、事務処理を中心に担当します。
- 技術職
- 技術・科学系の専門知識を活かして技術的業務を担います。
- 採用区分
- 国家公務員採用の区分全般を指す総称。I種・II種・技術系などを含みます。
- 任用
- 採用後の正式な職務配置と身分付与の手続きです。
- 昇任
- 職位・階級の昇進を指します。長期的なキャリア形成の一部です。
- 昇格
- 給与・階級の見直しを通じた職務能力の評価に基づく昇進を指します。
- 俸給
- 基本給与のこと。階級・職種・年齢に応じて決定されます。
- 俸給表
- 年齢・階級・職種別に定められた給与の基準表です。
- 給与制度
- 公務員の給与水準・支給方法・改定ルールを総称します。
- 懲戒処分
- 規律違反に対して科される処分。訓告・減給・免職などがあります。
- 天下り
- 退職後に政府機関や関連団体へ再就職すること。公務員倫理上の問題として規制・指導対象です。
- 退職後再就職規制
- 公務員の退職後の再就職先や期間制限などを定める規定です。
- 公務員倫理
- 公務員としての倫理基準。利害の衝突回避・機密保持・公正な職務執行を求めます。
- 研修制度
- 新任研修・階層別研修・職務別研修など、職員の能力開発を目的とした教育制度です。
- 福利厚生
- 健康保険・年金・休暇制度・各種福利厚生サービスなど、公務員の生活を支える制度です。
- 霞が関
- 東京都千代田区に所在する主要な中央省庁が集まる通称エリア。
- 内部/大臣官房
- 省庁内の政策調整・企画・庶務を担当する部局で、政策決定を支えます。
- 地方公務員
- 都道府県・市区町村など地方自治体で働く公務員。給与・制度は地方ごとに異なります。
- 配置換え・異動
- 人事異動や部署間の配置換えなど、組織運営のための人事措置です。
- 人事評価制度
- 職員の業績・能力・行動を評価し、昇任・育成・配置に反映させる制度です.



















