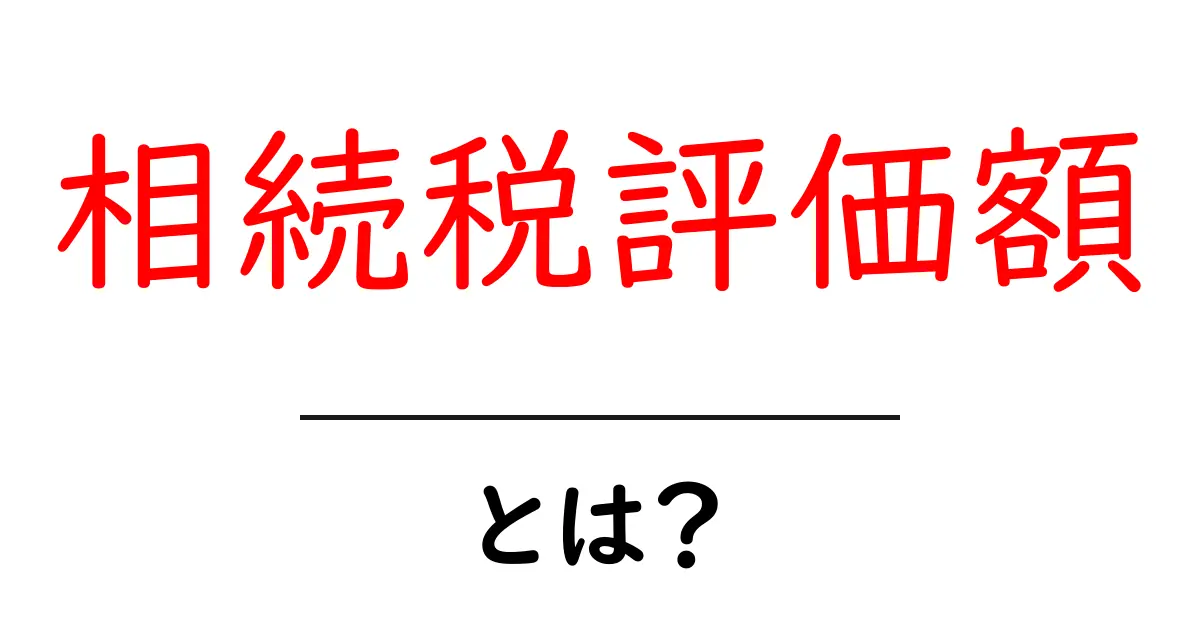

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続が発生した時点で相続財産を課税の対象としてどう価値づけるかを決める「評価額」のことです。相続税評価額は遺産の総額を計算するうえでの基準となり、実際にかかる相続税の額を決める重要な数字です。現金や預貯金はそのままの金額を評価しますが、不動産や有価証券など资产の性質によって評価方法が異なります。市場での売却価格と相続税評価額が必ずしも同じになるとは限らず、税務のルールに沿って別の値が使われることがあります。
この評価額は相続税を計算する際の「ベース」となるため、家族の財産をどう分配するかを考えるときにも大切です。理解しやすいように後の章で具体的な資産ごとの評価方法を詳しく紹介します。
資産ごとの評価方法の基本
相続財産にはさまざまな種類がありますが、それぞれどの指標を使って評価するかは資産の性質によって決まります。以下では代表的な資産の評価の考え方を簡潔に説明します。
現金・預貯金はそのままの金額を評価します。例えば預金口座にあるお金や現金は、死去時点の額をそのまま相続税評価額として扱います。
不動産は路線価や固定資産税評価額といった指標を使って評価します。路線価は道路に面した土地の評価額の基準となるもので、実際の売却価格と異なることがあります。概して路線価や固定資産税評価額のほうが市場価格を反映しつつも税務上の評価基準として使われます。
有価証券は市場価格を基準に評価します。株式や公社債などの評価は死去日前日または直近の取引日を基準として決定されます。市場が開いていない日が死亡日と近い場合には特別な取り扱いがあることもあります。
その他の資産には保険金や動産、仏壇・美術品などの文化財的価値を持つ品もあります。これらは個別の評価ルールがあり、専門家の判断を仰ぐことが多いです。
実際の計算の流れとポイント
相続税評価額を用いた計算は、まず財産を一覧化して評価額を算出することから始まります。その後、負債や葬式費用などの控除、相続税の基礎控除といった控除を適用して最終的な課税価格を決定します。基礎控除は一般的に「基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人の数×600万円」で計算されます。これは相続税がかかる人の数が増えるほど控除額も大きくなる仕組みです。
計算の実務では、各資産の評価額を正確に算出することが非常に大切です。特に不動産は路線価だけでなく実勢価値も影響するため、実務では複数の評価を比較検討する場合があります。財産の内訳によっては、相続税評価額と市場での実売価格が乖離することがある点にも注意が必要です。
具体的な計算の流れ(簡易例)
例として現金500万円、不動産3000万円、株式200万円の計算を考えます。現金はそのまま500万円、株式は市場価格で200万円、不動産は路線価や固定資産税評価額を用いて評価します。仮に不動産の評価額を2500万円とします。これらを合計して相続財産の総額を算出します。そこから負債や葬儀費用を控除し、基礎控除を適用して課税価格を導き出します。ケースによっては保険金の扱いが変わることもあるため、個別の状況に応じて税理士へ相談するのが安心です。
表で見る資産別の評価の目安
よくある誤解と実務のポイント
よくある誤解のひとつは「相続税評価額がそのまま税額になる」と思い込むことです。実際には評価額は課税価格を決めるための基準のひとつであり、基礎控除や債務控除、特例の適用などにより実際の税額は変わります。もうひとつの誤解は市場価格と評価額が同じだと考えることです。特に不動産は路線価と市場価格の差が生じやすく、相続税評価額の算出には専門知識が必要になる場面が多いです。困ったときには税理士や税務署、国税庁の情報を活用し正しい情報を得ることが大切です。
どこで確認するか理解しておくと安心
相続税評価額を正確に把握するには、財産の一覧を作成し専門家に相談するのが近道です。自分で概算を出すことは可能ですが、複雑な相続になるほど専門家の助けが重要になります。税理士は資産ごとの評価方法や控除の適用、申告書の作成まで一連のサポートを提供してくれます。税務署の窓口や国税庁の公式サイトにも評価方法の解説が載っているので、まずは基本的な考え方をつかむところから始めましょう。
まとめ
相続税評価額とは相続財産を課税するための基準となる評価額のことです。現金はそのまま、不動産は路線価や固定資産税評価額を使い、有価証券は市場価格を基準にします。実際の計算では評価額のほか控除や特例が影響します。正確な計算と適切な申告のためには専門家の助けを借りるのが安心です。相続税は複雑なので、事前に情報を集め、早めに準備を始めることをおすすめします。
相続税評価額の同意語
- 課税価格
- 相続税を計算する基礎となる財産の評価額。非課税財産や債務の控除後、税の対象となる価値の目安です。
- 相続税課税価格
- 相続税の課税対象となる財産の評価額。課税価格と同義の表現として使われることが多いです。
- 相続財産の評価額
- 相続財産を金額に換算した評価額。相続税計算の前提となる基礎値です。
- 遺産の評価額
- 遺産として遺される財産の総額を評価した金額。相続税の算定根拠になることが多いです。
- 遺産評価額
- 遺産の価値を評価した額。一般的に「遺産の評価額」と同義で使われます。
- 財産評価額
- 相続財産全体の評価額。相続税の算定基準として使われる金額です。
- 相続財産の課税評価額
- 相続財産のうち、課税対象として評価された額。
- 課税対象財産の評価額
- 課税対象となる財産の評価額。相続税の基礎となる価値です。
- 課税対象遺産の評価額
- 課税対象となる遺産の評価額。遺産の中で課税対象となる部分の評価額を指します。
- 税務上の評価額
- 税務処理上用いられる評価額。相続税評価額と同義で使われることがあります。
- 基礎評価額(相続税用途)
- 相続税の計算の基礎として用いられる評価額。
- 遺産総額
- 遺産全体の金額の総称。相続税の算定基礎となる場合があります。
- 相続税評価基準額
- 相続税計算の基準となる評価額のこと。
相続税評価額の対義語・反対語
- 時価
- 相続税評価額が税務目的で用いられる評価対比、時価は現在の市場で成立する実勢価格。税務評価額と比較して“市場での実際の値段”を指す概念です。
- 公正市場価値
- 市場で取引される公正で公平な価格。税務の公式な評価基準とは異なり、実勢の価格を反映することが多い概念です。
- 実市場価値
- 市場で実際に成立する価値。相続税評価額が税務上の算定基準であるのに対し、実市場価値は現場の取引に基づく価値です。
- 市場価値
- 市場での取引価格に近い価値。相続税評価額とは別の評価指標として用いられることがあります。
- 現実の価値
- 現在の実態に基づく価値。税務評価額の理論的算定と対比して、現実的な価値観を示す表現です。
- 実額
- 資産の実際の金額。評価の仮定を排し、現時点の現実的な額を示します。
- 正味価値
- 負債を控除した後の純粋な資産価値。相続税評価額が資産全体の評価を指すのに対し、正味価値は負債を考慮した“純粋な価値”を示します。
- 純資産価値
- 資産総額から負債を引いた純粋な資産価値。税務評価額の対比として用いられることがあります。
相続税評価額の共起語
- 路線価
- 道路に面する宅地の標準的な1平方メートルあたりの公的価格。相続税評価額を算定する際の土地評価の基礎となる。
- 公示地価
- 市場の目安となる公的な地価。相続税評価額の直接基準では路線価が中心だが参考として用いられることがある。
- 固定資産税評価額
- 固定資産税の課税標準となる評価額。土地・建物の評価の参考になる場合がある。
- 評価時点
- 相続税評価額を算出する時点のこと。評価日や基準日とセットで使われる。
- 相続開始日
- 相続が法的に開始した日。評価の基準日として用いられることが多い。
- 課税価格
- 相続税の課税対象となる財産の総額。控除後の金額が用いられることが多い。
- 基礎控除
- 一定額を相続税の課税対象から差し引く控除。例: 3,000万円+法定相続人×600万円。
- 配偶者控除
- 配偶者が相続する財産に対して適用される控除。一定の条件下で税額を軽減。
- 小規模宅地等の特例
- 相続税評価額の算定時、一定の宅地を大幅に減額する特例。住宅用地の評価を軽減。
- 遺産分割
- 遺産を誰がどの財産を取得するかを決める分割行為。
- 遺産分割協議
- 相続人同士が遺産の分割案について合意する話し合い。
- 相続税申告
- 相続税を申告する手続きそのもの。
- 申告期限
- 相続税申告を提出すべき期限。通常は相続開始日から10か月以内。
- 相続税申告書
- 申告の際に提出する正式な書類。
- 税務署
- 申告先の国税庁の機関。所轄の税務署に提出する。
- 税額
- 支払うべき相続税の金額。
- 税率
- 相続税を算出する際の税率。法定の税率表に基づいて決定。
- 評価方法
- 資産ごとに適用する評価の手順・方法。土地・建物・有価証券で異なる。
- 評価額
- 評価された資産の価値(税務上の評価額)。
- 不動産
- 建物や土地などの不動産資産全般。
- 土地
- 不動産のうち土地の資産部分。路線価などで評価される。
- 建物
- 不動産のうち建物の資産部分。固定資産税評価額などが使われることがある。
- 現金・預貯金
- 現金や預貯金などの流動資産の評価対象。
- 有価証券
- 株式や債券などの金融資産の総称。
- 株式評価額
- 株式の時価・評価額。相続税評価での株式の評価に使われる。
- 代償財産
- 相続人間で代わりに受け渡される財産。遺産分割の際に問題になることがある。
相続税評価額の関連用語
- 相続税評価額
- 相続税を計算するために財産を評価した金額。現金・預貯金はそのままの額、土地は路線価・倍率・面積、建物は固定資産税評価額を基準に算定します。評価日としては通常、相続開始日を基準とすることが多いです。
- 路線価
- 国税庁が公表する路線価は、宅地の評価の基礎となる1平方メートルあたりの課税標準額です。路線価と面積を組み合わせて土地の評価額を算定します。
- 公示地価
- 公的機関が公表する地価の標準値で、路線価と併せて土地評価の参考値として用いられることがあります。
- 評価倍率
- 路線価を実勢の地価へ換算する際に使われる補正倍率。土地の評価額を決定する際の重要な要素です。
- 土地の評価額
- 土地の相続税評価額の総称。路線価・倍率・面積を組み合わせて算定し、特例適用で修正される場合があります。
- 建物の評価額
- 建物の相続税評価額。通常は固定資産税評価額を基準に、築年数などの要因を考慮して算定します。
- 現金・預貯金評価額
- 現金・預金などの金融資産の評価額。名義や残高をそのまま評価額として計上します。
- 有価証券評価額
- 株式・債券など有価証券の評価額。市場価値(時価)を基準に算定します。
- 上場株式の評価額
- 上場株式の相続税評価額は原則時価で算定します。株価の変動がそのまま評価額に反映します。
- 非上場株式の評価額
- 非上場株式の評価は、純資産価値や評価方法(類似企業比準、純資産価値など)を用いて算定します。
- みなし相続財産
- 死亡保険金・退職金・一部の年金等、相続税の課税対象として扱われる財産です。実際の財産と異なる扱いになるケースがあります。
- みなし相続財産の非課税枠
- みなし相続財産に対して適用される非課税の枠。適用要件を満たす場合、超過分が課税対象となります。
- 配偶者控除
- 配偶者が相続する財産に対して税額を軽減する特例。一定条件を満たす場合、相続税が大幅に軽減されることがあります。
- 小規模宅地等の評価額の特例
- 自宅敷地などの評価額を大幅に引き下げる特例。一定の要件を満たす場合に適用され、相続税評価額を大きく減らすことがあります。
- 基礎控除
- 相続税の計算で最初に控除される基礎控除額。法定相続人の数と相続財産の総額に応じて決まります。
- 課税価格
- 評価額から各種控除を差し引いた後の、相続税の課税対象となる財産の総額です。
- 評価日
- 財産を評価する日。多くの場合、相続開始日や申告時点を基準日として用います。
- 相続開始日
- 故人が死亡した日。相続税評価の基準日として非常に重要な日付です。
- 相続人
- 法定相続人または実際の相続人。誰が財産を受け取る権利を持つかを決定する主体です。
- 遺産分割
- 相続財産を誰がどの部分を受け取るかを決める手続き。遺産分割の内容は申告額や実際の分割に影響します。
- 遺産分割協議
- 相続人同士が遺産の分割方法を話し合い、合意すること。合意内容は後の申告書作成にも反映されます。
- 相続税申告
- 相続税を申告・納付する手続きのこと。原則として相続開始日から10か月以内が期限です。
- 申告期限
- 相続税の申告・納付を行う期限。基本は相続開始日から10か月以内です。
- 税率
- 相続税の累進税率。財産の総額に応じて10%〜55%の段階的な税率が適用されます。
相続税評価額のおすすめ参考サイト
- 【自分で確認できる】不動産の相続税評価方法の基本 - 大堀会計事務所
- 相続税評価額とは何か - 相続トータルサポート@京都
- 土地・建物の相続税評価額と計算方法とは? - マルイシ税理士法人
- 相続税における財産評価額とは? 評価の基本と計算方法



















