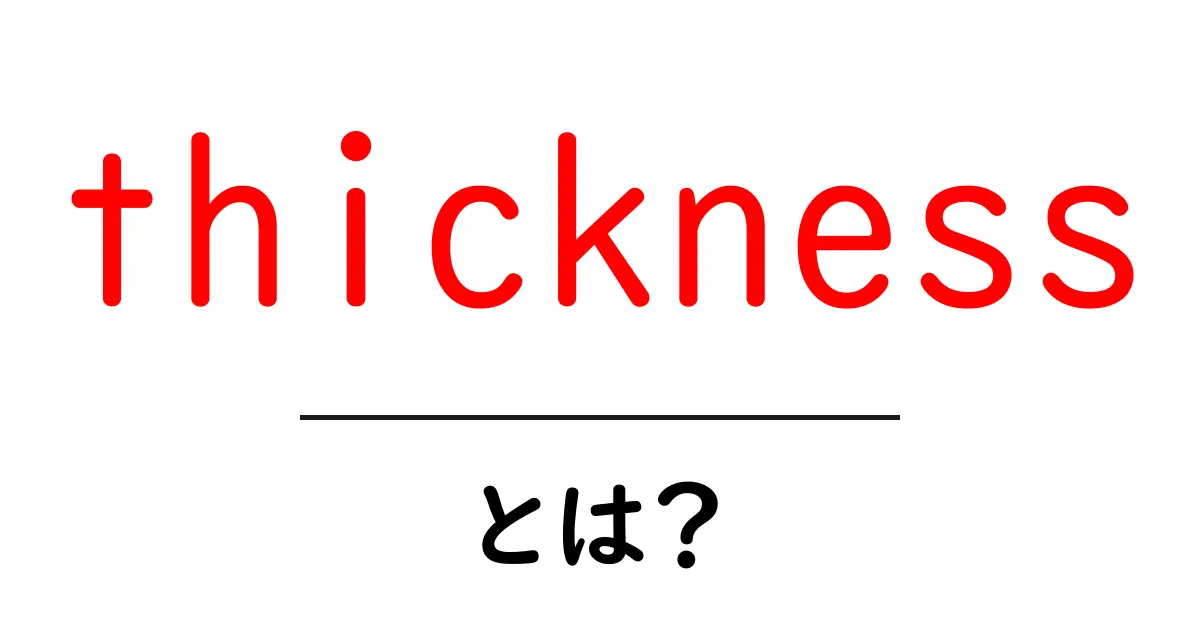

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
thicknessとは何か
thickness は英語で「厚さ」を意味します。物の表面から反対側までの距離のことを指します。日常生活から科学・工学まで幅広い場面で使われます。例えば紙の thickness は薄く、鉄の板の thickness は厚いといったように context によって意味が少しずつ変わります。
ここでは基礎的な考え方と、測り方・単位・注意点を中学生にも分かるように順に解説します。
thickness の基本的な意味
厚さ とは物体の前後方向の距離のことを指します。平たい物の表面から裏面までの距離を測るのが thickness です。厚さは材料の強度、柔らかさ、遮音性、断熱性など多くの性質に影響します。
単位と表現
厚さを表す単位は国や分野で異なります。一般的にはミリメートル mm や マイクロメートル μm などが使われます。たとえば紙は薄く 0.05 mm 程度、プラスチック板は 2 mm から 5 mm 程度、鉄板は 1 mm から 5 mm 程度が普通です。長さの単位と同じように 1 mm は 0.001 m に相当します。
測り方の基本
thickness を測る道具にはいくつかの種類があります。最も身近なのは定規やメジャーでざっくり測る方法です。もっと正確に測りたい場合は
ノギス や マイクロメータ といった専用の測定工具を使います。ノギスは物の外側の厚さを、マイクロメータは誤差が少なく厚さを測ることができます。測定する際には物体を安定させ、平らな面に置くこと、測定位置を一定にすることがポイントです。
日常生活での thickness の例
紙の厚さを気にする場面、衣服の生地の厚み、スマートフォンの画面保護フィルムの厚さなど、厚さは使い心地に直結します。薄さを追求するデザインと耐久性を保つ設計はトレードオフになることが多いです。
厚さと品質管理の関係
製造業では厚さのばらつきが品質のばらつきにつながるため、公差という決まりを設けます。公差は「ある範囲内で厚さが変動しても機能を満たす」という意味です。部品どうしを組み合わせる場合、厚さが極端に異なると組み立てに問題が出ます。だからこそ検査や測定は大切です。
厚さの計算と比較のコツ
厚さをうまく伝えるには、具体的な数値と単位を併記するのがコツです。たとえば
| Context | Thickness の説明 | 代表的な単位と例 |
|---|---|---|
| 紙 | 非常に薄い | 0.05 mm 程度 |
| 金属板 | 適度に厚い | 1 mm 〜 5 mm |
| 絶縁材 | 柔らかい | 2 mm 〜 10 mm |
このように Context と thickness の感覚を分けて覚えると、説明しやすくなります。もし比較するときは、同じ単位で並べるとわかりやすいです。
よくある誤解と正しい理解として、厚さと幅や高さを混同するケースがあります。厚さは物体の前後方向の距離を指し、幅は左右方向、高さは上下方向を指します。特に薄い布や薄い板を扱うときは、厚さと他の寸法を区別して伝えることが重要です。測定する前に「どの方向の厚さか」を自分で確認しておくとミスを減らせます。
厚さと伝わるニュアンス
thickness という語は英語圏のさまざまな文脈で使われ、話すときのニュアンスが少し変わることがあります。科学の授業では材料の厚さを表す専門用語として、日常会話では衣料や紙の薄さを指す柔らかい意味として使われることが多いです。英語の表現を身につけるには、身近な物の厚さを測って、日本語の「厚さ」と英語の thickness の両方を意識することがコツです。
まとめ
thickness は「厚さ」を指す基本的な概念です。単位は mm や μm などが使われ、測定にはノギスやマイクロメータが便利です。日常での用法と工学的な用法の違いを理解することが、正確に伝えるコツです。厚さを測る機会を増やすと、部品設計や製品の品質管理の考え方が自然に身についていきます。
thicknessの関連サジェスト解説
- bond line thickness とは
- bond line thickness とは、二つの材料を接着するときに間にはさまる接着剤の層の厚さのことです。英語では bond line という言葉が使われ、その厚さを測ることが大事になります。身近な例えとして、木材を接着剤でつないだとき、木の間に見えない薄い液状の層ができます。この層の厚さを bond line thickness と呼びます。厚さは用途によって大きく異なり、ミクロン(μm)単位の薄さから、場合によってはミリメートル単位の厚さになることもあります。特に電子部品を接着する場合や高強度を求める場合には、非常に薄い層を正確に作る必要があります。なぜなら、厚さが変わると接着の強さ、熱伝導、応力の分布、湿気や油分の影響を受けやすさに影響するからです。測定方法としては断面を作って顕微鏡で見る方法や、専用の膜厚測定機を使う方法があります。現場では薄さを一定に保つため、接着剤の粘度を選んだり、部品を加圧する時間や温度・乾燥条件をそろえたりします。さらに、設計段階で必要な bond line thickness を決め、それに合わせたスペーサーやダイスを用意して作業します。ボンドラインが薄すぎると十分に広がらず隙間が残ることがあり、厚すぎると内部に欠陥が生じたり、熱が伝わりにくくなったりします。日常での例えとして、適切な厚みの接着層を作ることが、強く長持ちする接合を作るコツです。結論として、bond line thickness は接着の品質を左右する大切な設計要素であり、測定・管理を通して適切な厚さを維持することが重要です。
- substance painter thickness とは
- substance painter thickness とは、3Dモデリングのテクスチャ作成で使われる“厚さ”を表す概念です。厚さマップ(Thickness map)と呼ばれるグレースケール画像を用い、物体の各点がどれくらい厚いかを shader に伝え、陰影の出方やサブサーフェイススキャタリング(SSS)などの見え方をコントロールします。白に近い値は厚みがある、黒に近い値は薄いと解釈されることが多く、中間のグレーは部分的な厚みを示します。使い方の基本は3つです。1) 厚さマップを用意する(自作のグレースケール画像を描く、写真をグレースケール化して使うなど)、2) Substance Painter のマテリアルにそのマップを接続する、3) マテリアルの厚さ関連パラメータを調整して見え方を確認する。マップはペイントツールで直接描くこともできますし、写真素材を白黒化して使うことも可能です。実務的な使い方の例としては、肌の内部光を少しだけ見せるためのサブサーフェイスの効果を強める、木製の板の薄い部分と厚い縁の陰影を強調する、金属表面のエッジにほんのりした透過感を与える、などが挙げられます。厚さマップを用いると、見た目のリアリティを効率よく向上させやすく、UVの分布やカラーと組み合わせると表現の幅が広がります。初心者への注意点として、厚さマップはジオメトリの実際の厚さを変えるものではなく、マテリアルの見え方を調整する情報源です。スケールやライティングの影響を受けやすいので、他のマップ(カラー、ノーマル、AO など)とのバランスをとりながら使いましょう。はじめは白黒だけで練習し、徐々にグレーの細かな段階を追加するのがおすすめです。
- wall thickness とは
- wall thickness とは、物体の“壁”の厚さを示す基本的な用語です。建物の壁、パイプの肉厚、容器の内壁など、さまざまな場所で使われます。厚さがどれだけあるかによって、強さや断熱性、圧力に対する耐性などの性能が変わります。測定は、対象の表面から反対側の表面までの距離を直線で測るのが基本です。一般的にはミリメートル(mm)やインチ(in)で表します。部品ごとに測定点を決め、平坦な面だけでなく曲面でも適切な測定方法を選びます。日常の例としては、壁厚が薄いと寒さが伝わりやすく、厚ければ保温性が高まります。パイプの場合、厚さが薄いと水圧で傷みやすく、厚いと耐圧性が上がります。設計や製造では公差と呼ばれる許容範囲を設定し、品質管理で測定結果を記録します。注意すべき点は、壁厚と外径・内径・全体の直径を混同しないことです。つまり wall thickness は「壁の厚さそのもの」を指す用語であり、寸法の別の要素とは区別して考える必要があります。
- material thickness とは
- material thickness とは、物の表面どうしの距離、つまり厚さを指す言葉です。身の回りのものを例にすると、木の板の厚さ、金属板の厚さ、プラスチックの薄いフィルムなどが挙げられます。厚さはデザインや機械の組み立て、重量の計算などに直結します。日常生活では、木の板の厚さが3ミリ、12ミリ、または18ミリといった具合に選ばれます。単位は主にミリメートル(mm)ですが、英語圏の製品ではインチ(1インチ = 25.4mm)で表示されることもあります。厚さを正しく測るには、ノギス(デジタルノギスでもOK)やマイクロメータが便利です。測定のコツは、物を平らな場所に置き、測定部をしっかり挟んで0点を合わせることです。厚さは均一であることが望ましいですが、現実には端と中央でわずかな違いが出ることがあります。そんなときは複数箇所を測って平均を取ると良いです。厚さが影響するポイントとして、強さ・曲がりやすさ・重量・熱伝導などがあります。薄い板は軽くて柔らかい反面、曲げやすく破れやすいことがあります。厚さが厚ければ強度は増しますが、重くなりコストも上がります。製作や設計では公差(厚さの許容範囲)を考えることが大切です。公差が小さすぎると部品がぴったり入らなくなることがあり、逆に大きすぎるとガタつきます。したがって、 thickness を規格値に合わせ、測定結果を確認して品質を管理します。このように material thickness とは“厚さ”のことで、物を選ぶとき、設計するとき、そして製品を組み立てるときに基本となる大切な数値です。
- gear thickness とは
- gear thickness とは、歯車の軸方向の厚み、つまり歯車の前面と背面の間の距離のことです。円筒状の歯車は軸を回すことで連動しますが、この厚みは機械の収まる空間や隣接部品との隙間に大きく影響します。厚さが薄すぎると材料が弱くなり割れや変形の原因になり、厚すぎるとケースに入らなくなるなどの問題が起こります。そのため設計時には歯数・モジュール・歯厚とともにこの軸方向の厚みをバランス良く決定することが大切です。なお、歯厚という言葉は歯の幅を指す別の寸法で、gear thickness とは別物です。測定にはノギスや深さゲージを使い、図面に書かれた公差を守って正確に測定します。実務ではケースの内寸と歯車の厚さの関係(クリアランス)を必ず確認します。例えばケースの内寸が20 mmで歯車の厚さが18 mmなら、約2 mmのクリアランスを確保できます。
- dry film thickness とは
- dry film thickness とは、塗膜が乾燥した後の膜の厚さを表す、塗装やコーティングの品質を評価する基本的な指標です。塗料は塗るときの厚さ(Wet Film Thickness: WFT)と、乾燥させた後の厚さ(Dry Film Thickness: DFT)が異なります。乾燥過程で溶剤や水分が飛ぶため、最終的な膜厚はWFTよりも小さくなることが一般的です。DFTはミクロン(μm)で表されることが多く、用途や基材によって適正範囲が決まっています。例えば建物の外壁用の塗膜は数十μm程度、車のボディは数十μm程度になることが多いです。DFTが適切でないと、腐食を防ぐ役割が弱くなったり、過剰な厚みがひび割れや剥離の原因になったりします。DFTを測定する方法にはいくつかあります。非破壊式の磁気式ゲージや渦電流式ゲージは、基材の材質に応じて使い分け、現場で手早く厚みを測るのに便利です。別の方法として、塗膜を少量切断して断面を顕微鏡で観察する破壊的な方法もあり、正確さは高い一方でサンプルを失うデメリットがあります。さらに、専用の校正済み機器を使い、測定点ごとに読み値を記録して平均を出す方法も一般的です。読み方のポイントは、機器の校正を事前に行い、基材の性質に合わせた設定を使うことです。現場では、同じ部位を複数回測定してばらつきを把握し、図表として管理する習慣が品質管理につながります。DFTの理解は、塗装計画の作成、塗膜の耐久性評価、コスト管理にも役立ちます。適正なDFTを保つことで、保護機能を長く発揮し、再塗装の頻度を適切に抑えることができます。初心者の方はまず「乾燥後の厚さがどれくらい必要か」を知り、現場の標準値を覚えることから始めてみましょう。
- equivalent oxide thickness とは
- equivalent oxide thickness とは、ゲート絶縁体の性質を、二酸化ケイ素(SiO2)の厚さだけで比べられるように換算した値のことです。MOSFETなどの半導体デバイスでは、ゲートとチャネルを分ける絶縁層の厚さと材料が電気的な「しきい値」やゲート電流の大きさに直結します。違う材料は同じ厚さでも電気的な絶縁力が異なるため、単純に厚さだけで比較できません。そこで使われる指標が「equivalent oxide thickness(EOT)」です。EOTは、実際の絶縁層の組み合わせを、SiO2層だけの厚さt_eqに換算して、同じ電荷容量を得るように定義します。結論として、EOTが小さいほどゲートが強く働く(ゲート制御性が高い)ことを意味しますが、薄くしすぎると漏れ電流が増えやすくなるため設計はバランスが大切です。計算の基本は次の公式です。単一の酸化物を想定したときには、EOT = t_i × (k_SiO2 / k_i) となります。ここで t_iは各絶縁層の厚さ、k_iはその層の誘電定数、k_SiO2はSiO2の誘電定数で約3.9です。多層の場合は各層の寄与を足し合わせて EOT を求めます。つまり EOT = Σ_i (t_i × (k_SiO2 / k_i)) です。実例として、SiO2と高k材料を組み合わせた場合を考えましょう。例えば、HfO2の厚さが2 nmでk_HfO2が約25、SiO2の界面層が0.5 nmでk_SiO2=3.9とすると、EOTの寄与は 2 × (3.9/25) ≈ 0.312 nm、0.5 nmのSiO2は 0.5 × (3.9/3.9) = 0.5 nm、合計で約0.812 nmとなります。これを「SiO2厚さ0.8 nm程度と同じ電気的厚さ」として捉え、デバイス設計の比較指標にします。このようにEOTは実際の材料や層構成を数値で比較するのに役立つ指標です。C-V特性の測定や材料データから推定され、設計上の最適化や性能評価に使われます。初心者の方はまず「EOTはSiO2と同等の電気的厚さ」を意味する点を抑え、次に層の材料と厚さ、誘電定数を使ってEOTを計算してみると理解が深まります。
- lv wall thickness とは
- lv wall thickness とは、左心室の壁の厚さを指す専門用語です。LVはLeft Ventricleの略で、心臓の左側の部屋です。心臓は血液を全身へ送るポンプ役で、左心室の壁の厚さがどれくらいかを測ることで心臓の状態を判断します。測定には心エコー検査と呼ばれる超音波検査が使われ、拡張末期と呼ばれる心臓が最も広がっている時期の内壁の厚さをミリメートルで表示します。部位ごとに前壁、後壁、IVS(間隔中隔)などの厚さを測り、平均値や個別の部位の値をとることが多いです。正常値は性別や体格で多少変わりますが、一般に6ミリから11ミリ程度が目安とされます。12ミリを超える場合は左室肥厚のサインとされることが多く、高血圧や心臓病の影響を示唆します。一方、病気が進むと壁が薄くなることもあります。測定値は年齢や体格、測定部位によって差が出るため、単一の数字だけで判断せず、医師が全体の結果を総合して解釈します。日常生活では高血圧を予防し、適度な運動、バランスの良い食事、喫煙の回避などが大切です。lv wall thickness を知ることは心臓の健康状態を理解する第一歩になり、検査結果に不安がある場合は必ず医師に相談しましょう。
- local thickness とは
- local thickness とは、画像や材料の形の厚さを、点ごとに測る方法のことです。例えば、写真に写っている穴や部材の厚さを“場所ごとに”知りたいときに役立ちます。local thickness は、その場所にある“最大の円”の直径を使って厚さを表します。具体的には、ある点を中心として、形の内部に完全に収まる最も大きな円を想像します。その円が形の内部に収まるときの直径が、その点の local thickness です。改めて言うと、点から形の境界までの距離の中で、最も近い境界までの距離を2倍した値が local thickness になります。距離が大きいほど厚い場所、距離が小さいほど薄い場所というイメージです。計算の仕組みは少しだけ想像力を使います。多くの画像処理ソフトやプログラミングのライブラリには distance transform(距離変換)という機能があり、物体の内部の各点について、その点から最も近い境界までの距離を求めます。求めた距離に2を掛ければ、local thickness の値が出ます。2次元の図形なら円の直径、3次元の立体なら球の直径として解釈できます。なぜこの考え方が useful なのか、いくつかの身近な例を挙げてみます。画像処理では、薄い壁や細い管、穴の大きさの分布を調べるのに使われます。材料科学では、孔径分布を把握し、材料の強度や通気性を予測するのに役立ちます。生物学的な画像でも、組織の厚さの違いを比較することで特徴を見つけやすくなります。使い方のコツとしては、まず正確な領域分割(物体と背景の区別)が前提になる点です。分割が不正確だと、境界までの距離も誤ってしまいます。また、解像度が低いと細かな厚さの違いが見えにくくなるので、データの品質にも注意しましょう。要点まとめとしては、local thickness は点ごとの厚さを示す局所指標で、最大内包円の直径として直感的に理解できます。距離変換で簡単に求められ、形状の特徴を抽出する際の基本的な道具となります。
thicknessの同意語
- 厚さ
- 物体の表面から反対側の表面までの距離。日常的に最も基本的な同義語。
- 厚み
- 厚さの別表現。口語的にもよく使われ、同義語として頻繁に用いられる。
- 厚度
- 技術・工学・科学的文脈で使われる語。寸法を数値で表す場面に適する。
- 太さ
- 円形の断面をもつ物の厚みを表す語。金属線や糸の太さのような場合にぴったり。
- 壁厚
- 壁としての厚さ。配管・構造体の壁の厚さを指す専門用語。
- 肉厚
- 物体本体の厚みを強調する語。比喩的にも用いられることがある。
- 粘度
- 液体の“厚さ”という性質を物理量として表す語。高い粘度は“厚い”流れと感じる。
- 濃さ
- 色や液体の濃度・粘性の感覚を表す語。濃い色・濃い液体の厚みを表現する際に使われる。
- 密度
- 密度は厳密には厚さの同義語ではないが、詰まり具合・濃さのニュアンスで使われることがある(文脈次第)。
- 深み
- 比喩的に物事の厚み・奥行きを指す語。作品・議論などの“厚み”を表す際に使われる。
- 奥行き
- 比喩的にも実務的にも、厚さの代用として使われることがある。物事の奥行き・広がりを表現する語。
thicknessの対義語・反対語
- 薄さ
- 厚さ(物の厚み)の反対語として使われる名詞。物が薄い、厚みが少ない状態を指す。紙の薄さや板の薄さなど、厚みが小さいことを示すときに使います。
- 細さ
- 太さの反対語として使われる名詞。直径・幅・厚みが細い状態を表す。細い線や細い棒、細さのニュアンスを説明するときに便利です。
- 薄手
- 布地や紙などが薄く軽い状態を指す名詞。素材が厚くないことを伝えるときに使われます。薄手のシャツ・薄手のノートといった具合です。
- 淡さ
- 色・味・光の強さが控えめで薄いことを表す名詞。濃さ・厚みの対極として使われ、色の淡さや味の薄さを説明するときに使います。
- 希薄さ
- 密度や濃度が低い・薄い状態を表す名詞。情報量・味・色・富みの薄さを指す際に使われます。
thicknessの共起語
- 厚さ
- 物体の表面から反対面までの距離、厚みの基本概念。単位はミリメートルなど。
- 厚み
- 厚さの別表現。日常語・技術語の双方で使われる。
- 壁の厚さ
- 建造物・機械の壁の内外の距離。耐久性・断熱性の評価指標。
- 壁厚
- 壁の厚さを示す略語・技術用語。設計図や仕様書でよく使われる。
- 板の厚さ
- 板状材料(板・シート)の厚み。
- 板厚
- 板の厚さを表す技術用語の略語。
- 材料の厚さ
- 材料全体の厚みを指す総称的表現。
- ガラスの厚さ
- ガラス材料の厚み。強度・断熱性・遮音性の評価に影響。
- レンズの厚さ
- 光学レンズの厚み。設計や携帯性・重量に関係。
- パイプの厚さ
- パイプの厚み。耐圧・強度設計の指標。
- パイプの壁厚
- パイプの内壁と外壁の厚み。
- 線の太さ
- 図表・デザインで線の厚さを表す。単位はピクセル・ポイントなど。
- ラインの太さ
- ラインの厚さを指す語。デザイン・グラフィックで頻出。
- 線幅
- 線の幅を表す表現。印刷・デザインの語彙。
- フォントの太さ
- フォントのウェイト、文字の視認性を左右する厚み。
- 文字の太さ
- 文字の描画厚み。見やすさ・雰囲気を決定。
- 皮膚の厚さ
- 皮膚の厚み。解剖学・医学・健康関連で用いられる。
- 肌の厚さ
- 肌の厚み。生体・美容・健康分野で使われる。
- 脂肪の厚さ
- 脂肪層の厚み。生体計測・健康評価で用いられる。
- 地層の厚さ
- 地層の縦方向の厚み。地質調査で基本指標。
- 地殻の厚さ
- 地球の地殻の厚み。地質構造の理解に必要。
- 厚さ公差
- 寸法公差のうち、厚さの許容範囲を示す工学用語。
- 厚さ測定
- 厚さを測る行為・測定プロセス。ゲージ・計測機器を使う場面で使われる。
- 試料の厚さ
- 試料サンプルの厚さを表す表現。研究・分析で用いられる。
- 膜厚
- 膜状材料の厚み。薄膜・コーティング・半導体分野で頻出。
- 粘度
- 液体の厚み・流れにくさを表す物理量。thicknessの比喩的な文脈で使われることも。
- とろみ
- 液体の厚み・粘度の口当たりを表す語。料理・飲料・化粧品で使われる。
thicknessの関連用語
- 厚さ
- 物体の厚み、つまり前後の距離を表す基本的な長さの概念。膜の厚さや板の厚さを表す一般的な用語です。
- 厚み
- 厚さの別表現。3次元の厚みを指す場面などで使われ、ニュアンスは厚さとほぼ同義です。
- 肉厚
- 厚さが特に大きい、厚みのある状態を指します。金属の壁厚が厚い、肉厚な材料などの表現に使われます。
- 膜厚
- 薄膜や膜の厚さのこと。コーティングや膜構造の厚みを表すときに用いられます。
- 層厚
- 材料を構成する層ごとの厚さ。多層構造の設計・品質管理で重要です。
- 板厚
- 板状材料(鉄板・アルミ板・プラスチック板など)の厚さを表します。
- 壁厚
- 容器・パイプ・壁の厚さ。強度設計・耐圧設計で重要な指標です。
- 紙厚
- 紙の厚さのこと。印刷・製本・紙選びの基礎となる数値です。
- コーティング厚さ
- 塗装・コーティングの被覆の厚さ。均一性や耐久性に直結します。
- 膜厚計
- 膜厚を測るための測定機の総称。非破壊検査で使われます。
- 厚さ計
- 厚さを測る道具の総称。マイクロメータやセンサ系を含みます。
- 超音波厚さ計
- 超音波を使って対象の厚さを測定する計測機。内部構造の厚み評価にも使われます。
- 磁気厚さ計
- 磁力を用いてコーティングや薄膜の厚さを測る測定器。主に鉄系基材を対象にします。
- 光学式厚さ計
- 光の反射・干渉などを利用して厚さを測る測定機。非接触測定に適しています。
- X線厚さ計
- X線を用いて素材の厚さを測る測定器。内部構造の厚さ検査にも使われます。
- 非接触式厚さ計
- 対象に触れずに厚さを測定するタイプの測定器。温度や形状を崩さず測れます。
- 厚さ公差
- 製造時に許容される厚さのばらつきの範囲。図面や規格で定めます。
- 有効厚さ
- 表面粗さや凹凸を考慮せず、機能的に実質的に使える厚さを指す概念です。
- シェル厚
- 3DプリントやCAD設計での外郭の厚さ。部品の強度・重量設計に影響します。
- 層間厚
- 層と層の間の厚さ。接着・多層構造の密着性や機械特性に関わります。



















