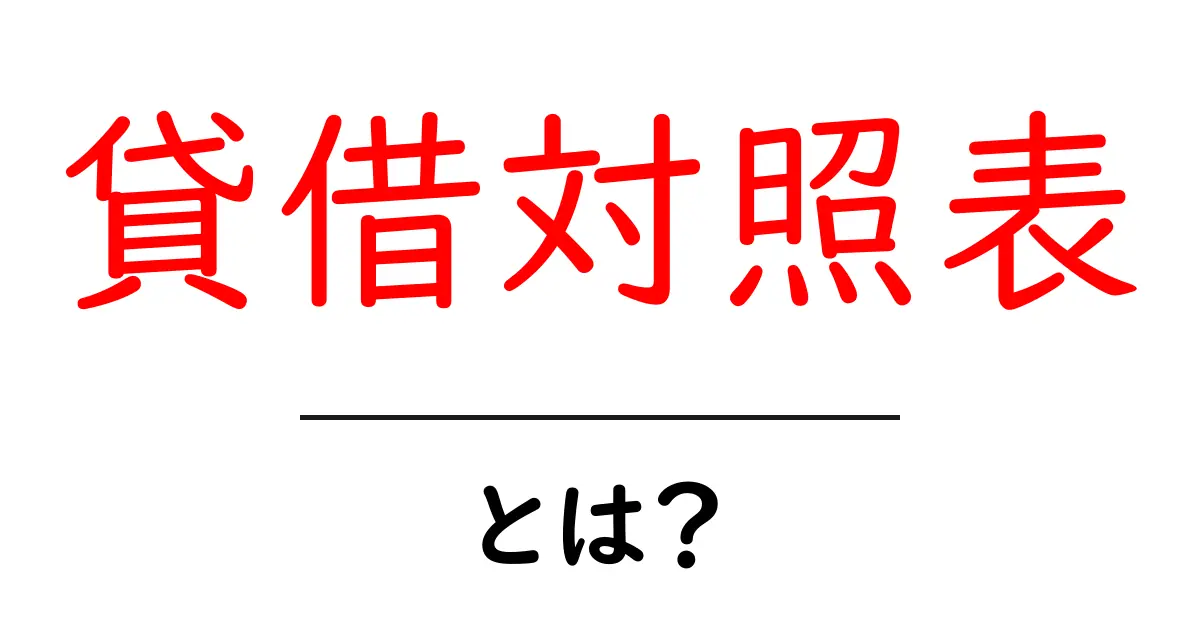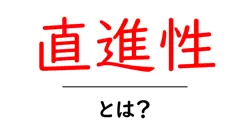この記事を書いた人
岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ)
ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」
年齢:28歳
性別:男性
職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動)
居住地:東京都(都心のワンルームマンション)
出身地:千葉県船橋市
身長:175cm
血液型:O型
誕生日:1997年4月3日
趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集
性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。
1日(平日)のタイムスケジュール
7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。
7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。
8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。
9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。
12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。
14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。
16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。
19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。
21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。
22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。
24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
貸借対照表とは何か
貸借対照表とは 企業がある時点で持っている財産と、それをどうやって手に入れたのかを示す表のことです。日常生活で例えるなら自分の持ち物の“総合計”と、それを誰から借りてきたのかあるいは自分の資金で賄ったのかを明らかにするノートのようなものです。結論として 貸借対照表は資産と負債および純資産の三つの柱で構成され、資産の合計は負債の合計と純資産の合計を足したものと同じになります。これを表す基本の式は 資産合計 = 負債合計 + 純資産合計 です。
この表は特定の時点を切り取って作られるため、常に最新の情報へ更新することが大切です。企業の健康状態を知りたいときには、現金や預金などの流動性が高い資産が十分か、借金の返済に充てられる資金がどれくらいあるか、そして株主に帰属する資本がどのくらいあるかを確認します。中学生でも理解できるように言い換えると、財産と借りているお金のバランスを示す“家計の現状報告書”のような役割を持っています。
三つの部と基本原理
貸借対照表は大きく三つの部に分かれます。第一は資産の部、次に負債の部、最後に純資産の部です。資産の部には現金や預金、売掛金、在庫、固定資産など企業が所有する価値が並びます。負債の部には買掛金や借入金など、企業が返さなければならないお金が入ります。純資産の部には資本金や利益剰余金など、株主や企業自身が蓄えた資本が含まれます。重要な点は資産合計が常に 負債合計 + 純資産合計 に等しくなることです。これを崩さずに表を作ることが、財務の基本となります。
資産の部の説明
資産の部にはすぐ現金化できるものと時間がかかるものの二つのタイプがあります。すぐ現金化できるものには現金預金があり、売掛金は商品を売ってまだ回収していないお金、棚卸資産は在庫のことです。固定資産には建物や機械設備など長く使えるものが該当します。これらを総合して資産合計を作ります。資産は企業が「何を持っているか」を示し、企業の活動を支える土台になります。
負債の部と純資産の部
負債の部には現在支払うべき金額が含まれます。買掛金は仕入れ先にまだ支払っていないお金、短期借入金はすぐ返す必要がある借入金です。純資産の部は株主からの出資と、企業が蓄積してきた利益の合計を表します。企業が自分の力で蓄えた資本が多いほど安定していると判断されます。
具体例で理解する
次の例は簡略化した貸借対照表の一部です。現金及び預金 500、売掛金 800、棚卸資産 1200、固定資産 500 などを資産として持ちます。資産合計は 3000 です。負債には買掛金 600、短期借入金 300 を含め負債合計は 900。純資産には資本金 1000 と利益剰余金 1100 を含め純資産合計は 2100。最終的に負債と純資産の合計は 3000 となり資産合計と一致します。以下の表はその具体的な内訳を示しています。able> | 科目 | 内訳 | 金額 |
|---|
| 資産 | 現金及び預金 | 500 |
| 売掛金 | 800 |
| 棚卸資産 | 1200 |
| 固定資産 | 500 |
| 資産合計 | | 3000 |
| 負債 | 買掛金 | 600 |
| 短期借入金 | 300 |
| 負債合計 | | 900 |
| 純資産 | 資本金 | 1000 |
| 利益剰余金 | 1100 |
| 純資産合計 | | 2100 |
| 負債と純資産合計 | | 3000 |
ble>読み方のコツ
貸借対照表を読むときはまず資産の総額と負債純資産の総額が同じかどうかを確認します。次に資産の中でどのくらい流動性が高いかを見て現金化のタイミングを推測します。株主にとっては自社の資本がどれくらい厚いかが重要な指標になります。初心者のうちは、表の見出しと数字のやり取りをゆっくり練習するだけで十分です。
まとめ
貸借対照表は企業の財政状態を一目で把握する基本的な資料です。資産の部 負債の部 純資産の部の三つの柱と、資産合計が負債合計と純資産合計の和に等しいという原理を覚えることが理解の第一歩です。実際の数字を使って練習すると、財務状況の読み方が自然と身についていきます。
貸借対照表の関連サジェスト解説
- 貸借対照表 とは わかりやすく
- 貸借対照表 とは わかりやすく解説します。中学生にもわかるよう、難しい専門用語を避け、日常の例も使いながら丁寧に説明します。まず、貸借対照表とは会社のお金の「現在地」を一枚の紙にまとめたものです。お店や個人の家計と似ていますが、ビジネスでは資産・負債・純資産の三つの柱で成り立っています。英語では Balance Sheet といいます。次に、左右の役割を見てみましょう。左側には“資産”と呼ばれる、お金や物、価値のあるものが並びます。右側には“負債と純資産”と呼ばれる、借りているお金と自分のかけたお金が並びます。大事なポイントは、左側の合計と右側の合計がいつも同じになることです。これを“貸借一致”といいます。資産には現金、預金、売掛金(商品を売ってまだもらっていないお金)、在庫などが含まれます。一方、負債には借入金、買掛金(仕入れ代金をまだ支払っていない分)など、純資産には自分の資本金や利益の蓄え(利益を会社に留めておいた分)などが入ります。実務では、決算期ごとに貸借対照表を作成して、会社の健康度をチェックします。例えば「現金が足りるか」「借金の返済は計画通りか」「利益がどれくらい会社に残っているか」を見ます。規模の大きい会社ほど詳細な内訳があり、資産の質(現金化しやすい資産かどうか)もチェックされます。最後に覚えておきたい点です。貸借対照表は「資産=負債+純資産」という式で成り立っています。この式を通して、会社がどれだけの資産をどれだけの借金と自分のお金で賄っているかを把握できます。資産が大きくても借金が多ければ危険信号、逆に資産がしっかりと純資産に支えられていると安定していると判断できます。
- 貸借対照表 元入金 とは
- 貸借対照表は、ある時点での“持っているもの(資産)”と“返さなければならないもの(負債)”と“資本・蓄え(純資産)”を表す表です。ここで出てくる元入金とは、事業主が自分のお金を事業に投入した額を指します。簡単にいうと「最初に入れた資金」や「追加で入れた資金」のことです。元入金は純資産の一部として表示され、資本の部に含まれます。資金を新たに投入すれば元入金は増え、事業を続ける中で資金を取り出したり見直したりすると元入金が減ることもあります。元入金は売上や利益とは別物で、事業の財政状態を示す資本の一つの指標です。中小企業や個人事業主の決算書では、元入金がどれだけあるかを確認することで「事業主がどれだけ資金を投入しているか」が分かります。資本金との違いも覚えておくと読みやすく、法人と個人の違いを理解する手助けになります。実務では、開業時の資金投入額や追加投入額を記録して、元入金の推移を追います。読者の方は、貸借対照表の資本の部で「元入金」という項目があるかを探してみると、事業主の資金投入の程度が把握しやすくなります。
- 貸借対照表 未払金 とは
- 貸借対照表 未払金 とは、まだ支払っていないお金のことを表す会計の言葉です。貸借対照表は会社の資産・負債・資本を一つの表にまとめた財務の地図です。未払金はその中の負債の一つで、まだ現金を支払っていない支払義務を指します。たとえば、商品を仕入れて代金をまだ払っていない場合や、電気代・水道代などの費用が発生していて未払いの状態がある場合に未払金として計上します。未払金は通常、1年以内に現金を支払うべき短期の負債(流動負債)として表示されます。貸借対照表の右側に「負債」の項目があり、その中の「未払金」欄に金額が並びます。未払金と似た言葉に買掛金があります。買掛金は主に仕入代金の未払を指すことが多く、未払金はもっと広い意味での未払いの義務を含むことがあります。日常の会計処理としては、未払金が生じたときに費用を計上し、同時に負債を増やします。実際に現金を支払うと、未払金を減らし現金を減らします。初心者には、未払金が増えると会社の現金がすぐに減らないように見えるかもしれませんが、最終的には現金の動きと連動して減少していきます。この考え方を知っておくと、貸借対照表を読んで、会社が今どれくらいの支払い義務を抱えているかが分かるようになります。この記事では、未払金の意味、表示場所、日常の取引での扱いを、難しくなく分かるように解説しました。
- 貸借対照表 その他の預金 とは
- 貸借対照表 その他の預金 とは、企業の財政状態を示す貸借対照表の現金及び預金の区分の一つです。まず、貸借対照表とはなにかを簡単に言うと、ある時点の資産と負債、資本の状態を表す表のことです。現金や預金、さらに現金同等物などを合わせて資産と見なします。その資産の中の現金及び預金には普通預金や定期預金といったよく使われる種類の預金が含まれますが、それ以外にも扱いが分かれやすい預金があり、それがその他の預金です。その他の預金は普通預金や定期預金のような日常的な現金の出入りには該当せず、特定の目的や条件のもとに保有されている預金をまとめて表示するための項目です。具体的には外国通貨建ての預金、特定の目的のために保有する預金、信託口座にある預金、あるいは決算上の処理の都合で分けて表示される預金などがこれに含まれることがあります。なお、その他の預金の意味は企業の会計方針や利用する会計基準により多少異なることがあります。つまり、同じ言葉でも会社ごとに内訳の内容が変わる可能性があるのです。実務ではこの項目を読むとき、どのような預金が含まれているのか、注記の説明もあわせて確認します。流動性に関する理解の観点からは、その他の預金は普通預金より流動性が低い場合が多く、現金化までに時間がかかる可能性があります。したがって財務状況を判断する際には、その金額だけでなく、内訳や連結の状況、注記に書かれた条件を読み解くことが重要です。初めて見る人にとっては、その他の預金の詳しい意味を理解するには、まず現金及び預金の基本を押さえ、次に各項目がどのような取引で生じるのかを具体例で想像すると理解が深まります。最後に覚えておくべきポイントは、その他の預金は企業の現金の補完的な形であり、すぐに使える現金ではないこと、しかし資産としては保証金や預金の形で存在し、企業の資金運用の一部として機能している場合があるという点です。
- 確定申告 貸借対照表 とは
- 確定申告とは、1年に稼いだお金を税務署に申告して税金を決めてもらう手続きのことです。会社に勤めている人は給与所得だけで済むことが多いですが、自分で事業をしている人や副業(関連記事:在宅で副業!おすすめ3選!【初心者向け】)がある人は確定申告が必要になります。青色申告や白色申告といった方法があり、会計の基礎が求められる場合があります。確定申告の書類の中に“貸借対照表”と“損益計算書”という2つの帳票が出てくることがあります。ここで、貸借対照表が何を表すのかを見ていきましょう。貸借対照表とは、ある日を基準に、どんなものを持っているか(資産)と、どんな借りているお金があるか(負債)、そして自分の資本や蓄え(純資産)を並べて示した表です。左側に資産、右側に負債と純資産を記入します。資産の総額は、負債の総額と純資産の総額の和と同じになるのが原則です。これが基本の「資産=負債+純資産」という方程式です。なぜ確定申告で貸借対照表が必要なのかというと、事業の財産状態をはっきり示すことで、税金の計算に正確さを持たせるためです。青色申告を選ぶ人は、税務上の有利な点を受けられる代わりに、貸借対照表と損益計算書を提出することが求められる場合があります。作り方のコツは、次の4つです。1) 事業で使っている現金・預金・売掛金・在庫などの資産を洗い出す。2) 買掛金・未払金・借入金などの負債を整理する。3) 自分の資本や過去の利益の蓄え(純資産)を計上する。4) 資産の合計と負債+純資産の合計が同じになるように金額をそろえる。実務的には帳簿(取引の記録)と照合しながら作成します。小さな例を挙げると、資産として現金100,000円、預金50,000円、機械200,000円、売掛金30,000円の計380,000円。負債として借入金150,000円、未払金20,000円の計170,000円とします。純資産は資産−負債で210,000円となります(この場合、右側は負債170,000円+純資産210,000円で合計380,000円と等しくなります)。このように、資産と負債+純資産の合計をそろえるのが貸借対照表の役割です。初心者には、まず自分が「何を持っているか(資産)」と「何を払わなければならないか(負債)」を分けて考える練習をおすすめします。青色申告で正式に提出する場合は、損益計算書と一緒に貸借対照表の作成が求められることがあります。とはいえ、難しく考えず、日付を決めて「この日点」での財産の状態を整理する作業だと理解すると取り組みやすいでしょう。
- 簿記 貸借対照表 とは
- 簿記の世界でよく出てくる用語に『貸借対照表』があります。この記事では「簿記 貸借対照表 とは」を初心者の目線で分かりやすく解説します。貸借対照表とは、特定の“ある時点”における会社の財産の状態を表した表です。会社がどれくらいの資産を持っているか、そしてその資産をどのように調達したかを一目で見ることができます。大事なポイントは、資産と資金の出所を同じ土台で並べて、常に「資産の総額と資金の出所の合計が等しくなる」ことです。これを簿記では「資産=負債+純資産」の形で表します。資産は現金、預金、売掛金、在庫、設備など、企業が ownershipしている価値のあるものを指します。負債は借入金や買掛金、未払いの費用など、企業が他人に返さなければならない義務を示します。純資産は資本金や利益の累積額など、株主やオーナーが会社に対して持つ権利の部分です。貸借対照表の読み方のコツは、まず総資産と総資本の金額を確認することです。次に資産の中でどれが大きくなっているか、流動性が高い資産(現金・現金同等物)と長期の資産を区別します。負債については、短期の支払義務(1年以内に返すべきもの)と長期の義務に分けて見ると、返済の見通しがつきやすくなります。純資産は会社の“自己資本”の大きさを示し、安定性の目安にもなります。実務での活用として、小さなビジネスの開業時には資金繰りの状態をチェックする目的で作成します。期末に資産がどう動いたかを把握することで、現金が足りなくなるリスクを早く察知できます。最後に、貸借対照表は損益計算書とセットで見ると、期間の結果と現在の財政状態がわかり、経営判断に役立ちます。例として、カフェAの貸借対照表の簡単な例を挙げます。資産: 現金 80,000円、売掛金 20,000円、在庫 30,000円、設備 70,000円 計 200,000円負債: 買掛金 40,000円、借入金 60,000円 計 100,000円純資産: 資本金 100,000円、利益剰余金 0円 計 100,000円総資産 200,000円 = 負債 100,000円 + 純資産 100,000円
- 損益計算書 貸借対照表 とは
- この記事では、損益計算書 貸借対照表 とは何かを、初心者にも分かるように丁寧に紹介します。まず、損益計算書とは、一定の期間(例:1年間)に会社がどれだけ儲けたのかを示す、売上や費用の一覧です。対して貸借対照表は、ある時点の会社の財政状態を表す表で、資産・負債・純資産の3つに分かれます。両者の違いは、期間か瞬間か、という点です。損益計算書は期間の成果を示し、貸借対照表はその時点の資産と負債の関係を示します。損益計算書の主な項目には、売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益などがあります。難しく感じるかもしれませんが、要は「どれだけ稼いだか」「どれだけ使ったか」「実際に手元に残った利益はどれか」を見るための道具です。小さな商店を例にすると、売上高100,000円、売上原価40,000円なら売上総利益は60,000円です。そこから販売費や人件費などを引いて、最終的な当期純利益がいくらかがわかります。貸借対照表の基本は、資産と負債と純資産の3つ。資産には現金、売掛金、在庫などがあり、負債には借入金や買掛金など、純資産には資本金や繰越利益などが入ります。ある時点の例として、現金20,000円、売掛金15,000円、在庫10,000円の資産合計45,000円、負債が借入金10,000円と買掛金5,000円で合計15,000円、純資産が資本金20,000円と利益余剰金10,000円で合計30,000円とすると、資産と負債+純資産は等しく45,000円になります。これが貸借対照表の基本的な成り立ちです。この2つの表を組み合わせて見ると、会社がどれくらい儲かったかだけでなく、今どのくらいお金を持っていて、いくら返さなければならないか、将来に向けてどうお金を回していくのかを読み解く手がかりになります。初心者の練習としては、実際の決算書を見つけて、数字がどの項目に対応するかを自分で追ってみると良いでしょう。
- 自己資本 とは 貸借対照表
- この記事では「自己資本 とは 貸借対照表」というキーワードを使い、初心者にもわかりやすく解説します。まず、貸借対照表とは企業の財政状態をある時点で示す表のことです。ここには資産、負債、そして自己資本の三つの大きな区分があります。自己資本とは、企業が外部の人に借りているお金ではなく、オーナーや株主が企業に出資した資本金や、事業を続ける中で蓄えられた利益(利益剰余金)など、企業自身の資本的な部分を指します。資産から負債を引いた残りが自己資本になる――これが基本的な考え方です。例を挙げると、資産が100、負債が60の会社は自己資本が40です。これは、借金を除いた会社の“持ち分”を意味します。自己資本が多いほど、外部の困難に強く、将来の投資余力が高いとされます。さらに、資本の内訳として“資本金”や“資本剰余金”“利益剰余金”などがあり、利益が蓄えられると自己資本が増えます。一方、赤字や新たな負債が増えると自己資本は減少します。会計を学ぶ上で、自己資本 とは 貸借対照表の重要な要素であり、企業の安全性や成長性を判断する手がかりになります。初心者向けには、まず資産と負債の関係を押さえ、次に自己資本がどうして生まれるのか、どのように変動するのかを日常の数字でイメージすると理解が進みやすいはずです。
- 総資本 とは 貸借対照表
- 総資本 とは 貸借対照表を学ぶときによく出てくる用語ですが、正式な会計科目としては使われないことが多い表現です。日常の財務の話では、「資金の総量」や「資金の出どころと使い道の総括」といった意味で使われることがあります。貸借対照表は、ある時点の財政状態を表す表で、資産・負債・純資産の3つの柱から成り立っています。基本の公式は資産=負債+純資産です。これを理解すると、企業がどのような資金で資産を賄っているかが分かります。総資本の考え方は、この式を使って資金の総量をひとまとめに見る視点です。つまり総資本=負債+純資産と考えると、企業が資産を買うためにどれだけのお金を“外部からの借入”と“株主からの資金”で賄っているかが見えてきます。負債が多いと財務上のリスクが高まる一方で、資金調達の自由度が増えることもあります。純資産が多い場合は、企業に自己資本の余裕ができ、安定性が高まる傾向があります。なお、貸借対照表には「総資本」という名前の列はありません。資産・負債・純資産の関係を頭の中で結びつける考え方として覚えておくと役に立ちます。実務的には、資産の内訳を見て何にお金を使っているか、負債と純資産のバランスを見て資金の源泉が安定しているかを判断します。総資本のイメージを用いれば、財務リスクと成長の余地を一度に捉えやすくなります。具体例として、資産が1億円、負債が5千万円、純資産が5千万円の会社を考えると、資産=負債+純資産が成り立っており、総資本は負債+純資産の合計で1億円となります。
貸借対照表の同意語
- バランスシート
- 英語の Balance Sheet を日本語で表現した言い方。資産・負債・純資産を特定の日点で整理して、企業の財務状況を一目で示す財務諸表のこと。
- 資産負債対照表
- 資産と負債・純資産を対照して表示する表のことで、貸借対照表とほぼ同義で使われる表現です。
- 資産負債表
- 資産と負債を列挙して表示する表。正式名称の代替表現として口語的に使われることがありますが、基本的には『貸借対照表』の同義語として理解されます。
- B/S
- Balance Sheet の略称。財務資料や社内資料で頻繁に見かける短縮形。
- Balance Sheet
- 英語表記そのもの。海外の会計資料や英語の説明文で使われる名称で、日本語解説では『貸借対照表(Balance Sheet)』と併記されることが多いです。
- 貸借対照表
- この語自体が正式名称。資産・負債・純資産を特定の日付における状態として列挙する財務諸表のこと。
貸借対照表の対義語・反対語
- 損益計算書
- 一定期間の売上高・費用・利益を記録する財務諸表。貸借対照表が「この時点での財政状態」を示すのに対し、損益計算書は期間内の成果を示し、収益性を評価する対になる情報です。
- キャッシュフロー計算書
- 一定期間の現金の流入と流出を示す財務諸表。貸借対照表が資産・負債の残高を示す“静的”な状態を表すのに対し、キャッシュフロー計算書は現金の動きを追い、資金の健全性を評価する対となる情報です。
- 資本変動計算書
- 株主資本の増減を示す財務諸表。利益剰余金の蓄積、配当、株式の発行・消却などを通じて資本がどう変動したかを示し、貸借対照表の静的な資本残高と対比される動的情報です。
- 予算対比表
- 予算と実績の差を示す表。経営計画と実際の財務実績を比較して、対外的な財務状態ではなく、将来の意思決定の材料として使われます。貸借対照表が現在の状態を示すのに対して、予算対比表は差異を明らかにします。
- 現金ベースの財務報告
- 現金ベースでの取引を重視する報告形式。発生主義に基づく貸借対照表・損益計算書とは異なり、現金の入出金に焦点を当てて資金繰りを把握します。
貸借対照表の共起語
- 資産
- 企業が所有する経済的価値。現金・預金・売掛金・棚卸資産・固定資産などを含み、貸借対照表の左側(資産の部)に表示される。
- 負債
- 企業が負う返済義務。短期・長期に分かれ、貸借対照表の右側(負債の部)に表示される。
- 純資産
- 資産から負債を差し引いた残り。株主資本や内部留保を含み、貸借対照表の右側(純資産の部)に表示される。
- 流動資産
- 1年以内に現金化・利用が見込まれる資産。現金・預金、売掛金、棚卸資産などが含まれる。
- 固定資産
- 1年以上使用する資産。設備・建物・車両・長期投資などが含まれる。
- 流動負債
- 1年以内に支払予定の負債。買掛金、短期借入金、未払い費用などが含まれる。
- 固定負債
- 返済期限が1年を超える負債。長期借入金、社債などが含まれる。
- 現金及び預金
- 現金と金融機関の預金。現金性の高い資産として資産の部に表示される。
- 売掛金
- 顧客が商品・サービスの代金を支払うべき金額。回収見込みの資産。
- 買掛金
- 仕入先へ支払うべき未払い金。短期性の負債として計上される。
- 棚卸資産
- 販売目的の在庫品。原材料・仕掛品・商品などを含む。
- 受取手形
- 約束手形として受け取る支払債権。現金化が見込まれる資産。
- 支払手形
- 約束手形として支払う義務。将来の現金支出を伴う負債。
- 未収金
- 売上未回収の金額など、回収見込みの資産。
- 未払金
- 支払いが未了の費用・経費。短期性の負債として計上される。
- 有価証券
- 株式・債券などの金融商品。短期・長期の投資資産として分類される。
- 固定資産の減価償却累計額
- 固定資産の減価償却の蓄積額。資産の簿価を示す際の控除項目。
- 資本金
- 株主からの出資元本。資本の基本的な部分。
- 資本剰余金
- 資本取引により生じた剰余金。株主資本に含まれる。
- 利益剰余金
- 過去の利益を内部留保した資金。株主資本の一部として計上される。
- 株主資本等
- 株主資本と資本剰余金などをまとめた区分。
- 退職給付引当金
- 将来の退職給付に備えて積み立てた引当金。
- 資産評価差額
- 資産の公正価値と簿価の差額。評価換算の結果として表示される場合がある。
- 負債評価差額
- 負債の評価差額。評価方法の差異が生じた場合に表示。
- 決算日
- 貸借対照表の対象となる会計期間の末日。
- 会計基準
- 財務諸表の作成ルール。日本基準・IFRSなどがあり、適用ルールが統一される。
- 財務諸表
- 企業の財政状態と業績を示す報告書の総称。貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などを含む。
- 損益計算書
- 一定期間の収益と費用の結果を示す財務諸表の一つ。利益の有無を示す。
- キャッシュフロー計算書
- 現金の流れを示す財務諸表の一つ。営業・投資・財務活動別に区分される。
- 総勘定元帳
- すべての勘定科目の取引を集計して記録する元帳。仕訳の帳簿的基礎となる。
貸借対照表の関連用語
- 貸借対照表
- 企業のある時点の財政状態を示す財務諸表で、資産・負債・純資産の3部から構成されます。
- 資産
- 企業が保有する価値あるもの。現金・預金・売掛金・棚卸資産・固定資産などが含まれます。
- 流動資産
- 1年以内に現金化・消費される資産。現金及び預金、売掛金、受取手形、棚卸資産など。
- 現金及び預金
- すぐに利用可能な現金と銀行口座の預金の総称。
- 受取手形
- 他者への金銭回収を約束する短期の証券。
- 売掛金
- 商品・サービスを提供したにもかかわらず、まだ回収していない金額の権利。
- 棚卸資産
- 販売目的・製造用に保有する在庫。原材料・仕掛品・商品など。
- 固定資産
- 1年以上使用する資産。有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産など。
- 有形固定資産
- 形のある長期資産。建物・構築物・土地・機械設備など。
- 土地
- 企業が保有する不動産としての地権資産。
- 建物及び構築物
- 有形固定資産の一部。建物・構築物の価値。
- 機械設備
- 生産用の機械・設備などの有形固定資産。
- 減価償却
- 固定資産の価値を使用期間で費用として配分する会計処理。
- 減価償却累計額
- これまでに計上した減価償却費の累計額。
- 無形固定資産
- 形のない資産。特許権・商標権・ソフトウェア等。
- のれん
- 企業買収時に支払った対価が簿価を超える場合、その超過分を資産として計上するもの。
- ソフトウェア
- 無形固定資産として計上されるコンピュータソフトウェア。
- 投資その他の資産
- 長期間保有する資産。投資用の証券や長期保有資産など。
- 投資有価証券
- 株式・公社債などの長期的投資用証券。
- 持分法投資資産
- 関係会社・関連会社への投資で、投資先の利益・損失の影響を反映する資産。
- 負債
- 企業が返済すべき義務。資金調達の源泉。
- 流動負債
- 1年以内に支払予定の負債。買掛金・短期借入金・未払費用・未払税金等。
- 買掛金
- 商品・サービスの購入に対する未払い金。
- 短期借入金
- 返済期限が1年以内の借入金。
- 未払費用
- まだ支払っていない費用。例:未払給与・未払水道光熱費など。
- 未払法人税等
- 法人税等の未払い額。
- 固定負債
- 返済期間が1年以上の負債。
- 長期借入金
- 返済期限が1年超の借入金。
- 社債
- 企業が発行する長期の債券。
- 退職給付引当金
- 退職給付の支払いに備えるための引当金。
- 純資産
- 資産総額から負債総額を差し引いた残額。株主資本を含みます。
- 株主資本
- 株主に帰属する資本。資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式の控除などを含む。
- 資本金
- 株式の発行によって企業が受け取った資金のうち資本として計上される部分。
- 資本剰余金
- 資本金以外の出資や資本取引から生じた剰余金。
- 資本準備金
- 資本関連の特定目的で計上される準備金。
- 利益剰余金
- 過去の利益の蓄積で、内部留保として純資産に計上される金額。
- 自己株式
- 企業が自己の株式を保有している状態。純資産を減少させる要因となることがある。
- 新株予約権
- 将来の株式購入権。株式報酬や資本政策で用いられる。
- 評価換算差額等
- 有価証券評価差額・為替換算差額など、純資産の評価変動を示す項目。
- その他の純資産項目
- 特定の状況で計上される追加の資本項目。
- 連結財務諸表
- 企業グループ全体の財務状態を示す財務諸表(親会社と子会社を含む統合財務諸表)。
- 単独財務諸表
- 個別企業だけの財務諸表(連結対象外の財務情報)。
- 決算日
- 貸借対照表を作成する日付。会計年度の期末日など。
- 流動比率
- 流動資産÷流動負債で算出される短期支払能力の指標。
- 当座比率
- 現金及び現金同等物・受取手形など、すぐに現金化できる資産を用いた指標。
- 自己資本比率
- 純資産÷総資産の比率。財務健全性の目安。
- ROE
- Return on Equity。当期純利益÷株主資本で算出される株主資本利益率。
- ROA
- Return on Assets。当期純利益÷総資産で算出される総資産利益率。
貸借対照表のおすすめ参考サイト
ビジネスの人気記事

352viws

209viws

185viws

155viws

153viws

148viws

144viws

127viws

121viws

113viws

111viws

108viws

103viws

102viws

98viws

92viws

92viws

88viws
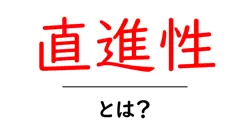
82viws

80viws
新着記事
ビジネスの関連記事