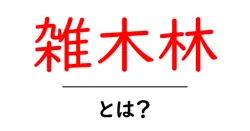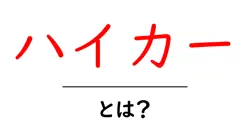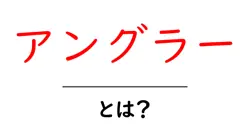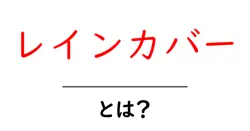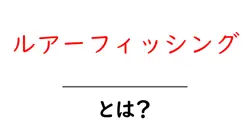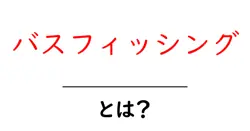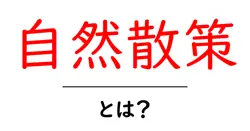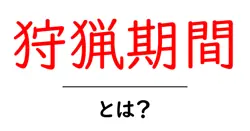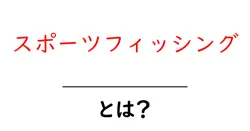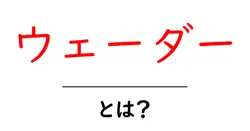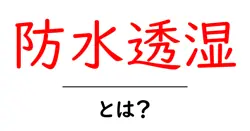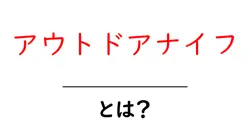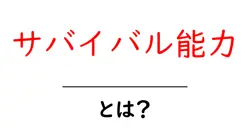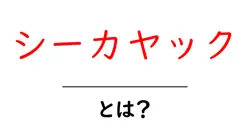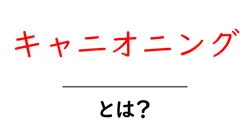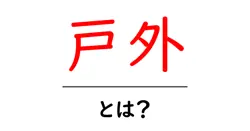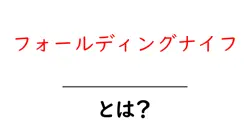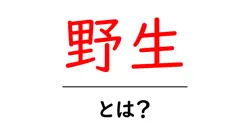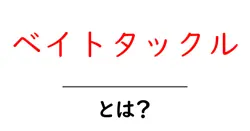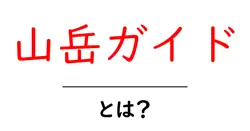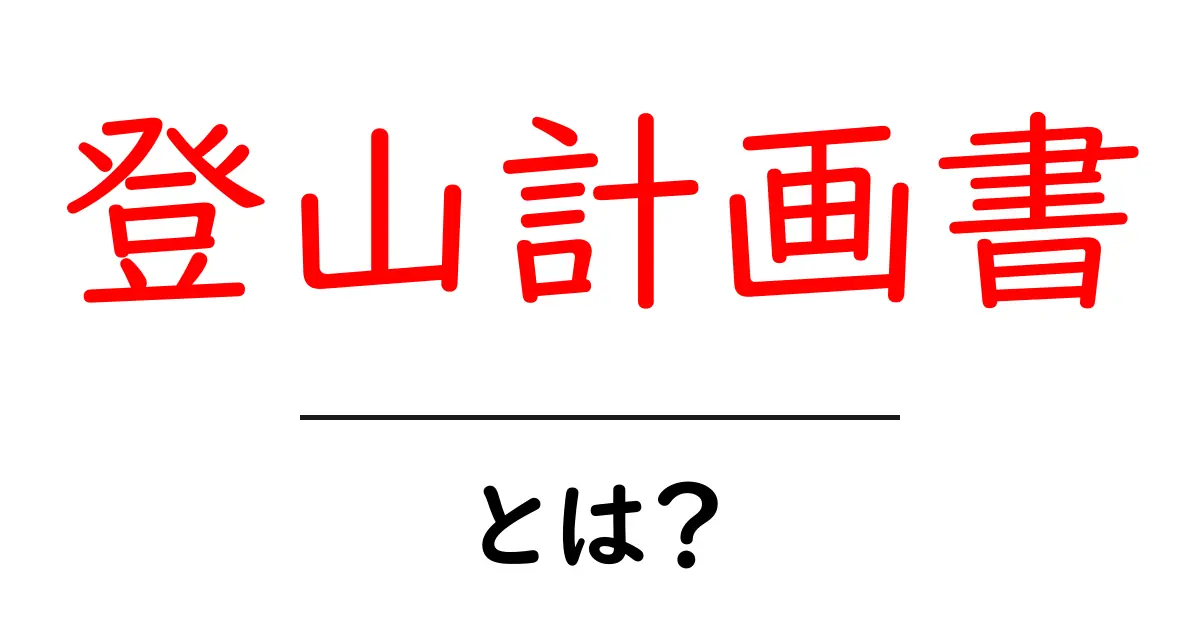

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
登山計画書とは?
登山計画書は、山に入る前に自分の行動を整理するための文書です。安全を最優先に考えるための道具として、登山者・家族・仲間・登山口の管理者などが情報を共有する役割を持ちます。初心者にとっても、経験者にとっても、天候の急変や道の難所に備えることができます。
登山計画書に含める基本情報は、次のような項目です。
この情報は具体的な数値で書くと伝わりやすくなります。例えば「出発7:30、下山17:00、余裕をもって計画する」などです。
書き方のコツと基本の手順
手順は次のとおりです。以下の順で作成すると、抜け漏れが少なくなります。
また、安全第一の原則を忘れずに、計画を組み立てましょう。計画書は自分だけのものではなく、同行者や家族にも共有することで、万一のときの協力を得やすくなります。
例: 初心者向けの山行計画の一例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 山田 太郎 |
| 日付 | 2025年10月12日 |
| 山域 | 高尾山 |
| ルート | 表参道コース、往復 |
| 出発 | 7:30 |
| 下山 | 12:00 |
| 持ち物 | 水2L、軽食、雨具、地図、携帯 |
| 緊急連絡 | 家族 090-xxxx-xxxx |
| 天候 | 晴れのち曇り、気温15度 |
このような例を自分の状況に合わせて作成することで、安全に山を楽しむための準備が整います。最後に、山を楽しむと同時に、無理をしない判断と仲間との連携を重視してください。
登山計画書の同意語
- 登山計画書
- 登山を実施する際に作成する正式な文書。行程・日程・装備・連絡先・緊急時の対応などをまとめたもの。提出先がある場合には受理される前提で作成されることが多い。
- 登山計画
- 登山の具体的な予定そのもの。日付・ルート・難易度・休憩地点・連絡方法などを簡潔に整理した概要版。
- 山行計画書
- 山行(山へ出かける計画)を文書にした正式な記録。行程・装備・緊急連絡先・避難場所などを含めるのが一般的。
- 山行計画
- 山への行動計画の総称。ルート・日程・装備・現地の連絡体制を整理したもの。
- 山岳計画書
- 山岳エリアを前提とした活動計画を文書化したもの。天候判断・ルート情報・安全対策を盛り込むことが多い。
- 山岳計画
- 山岳地帯での行動計画。難易度・標高差・日数・装備などを含む計画の総称。
- 登山計画案
- 正式版の前段階として作成する草案。内容を検討・修正して最終版へと仕上げるための案。
- 山行計画案
- 山行計画の草案版。現地の天候やルート情報を踏まえ、修正が前提の案。
- 山岳計画案
- 山岳活動の計画案。ルート・日程・装備・安全対策を提案する草案。
- 登山日程表
- 登山の実行日程を一覧化した文書。日付・出発時刻・ルート・宿泊地などを示す表形式の資料。
登山計画書の対義語・反対語
- 無計画
- 登山において事前の計画・準備をほとんど行わず、登山計画書の作成やルート・装備の整理を欠いた状態。
- 計画なし
- 出発前に計画を立てず、どのルートでどの時間に何をするかといった計画書自体が存在しない状態。
- 即興登山
- 現地の状況を見てその場で判断・行動を決める登山。事前のルート決定やリスク評価が不足しがちで、安全性が低くなることが多い。
- 現地判断のみ
- 現地での判断に依存し、事前にルート・天候・装備などを決定しない状態。
- 登山中止
- 予定していた登山を取りやめること。計画書を作成していても実行に移さない状況を指す場合がある。
- ルート未定
- 出発前にルートを決定せず、計画書が未作成または不完全な状態。
- 計画破棄
- 既存の登山計画を正式に破棄して実施を取り止めること。
- 無計画性
- 計画を立てる習慣や能力が欠如している状態。計画書を作る意欲・能力が低いことを表す。
登山計画書の共起語
- 登山届
- 山域へ出発する際、自治体や警察に提出して行程を知らせるための書類。
- 登山届け提出先
- 提出先(警察署・自治体・山岳協会など)を指す。
- 行動計画
- 日程・ルート・休憩・想定時間をまとめた行動の計画。
- 出発日
- 山行の開始日。
- 出発時刻
- 出発予定の時刻。
- 下山予定時刻
- 下山する見込みの時刻。
- 到着予定時刻
- 山行の到着見込み時刻。
- ルート
- 選ぶ登山道の進行経路。
- コース
- ルートの別表現。
- 山域
- 登山するエリア名。
- 難易度
- 難しさの指標(初級〜上級)。
- 標高差
- 最高地点と出発地点の標高差。
- 距離
- 全体の歩行距離。
- 総所要時間
- 出発から下山までの総時間(休憩含む)。
- 天気予報
- 出発前の天候予測。
- 気象情報
- 現地の風・雨・雷・雪などの情報。
- 装備リスト
- 必須・推奨の装備の一覧。
- 持ち物
- 個々人が携帯する物の一覧(個人装備)
- 食料
- 行動中の食事やカロリー計画。
- 水
- 飲料水の量と補給計画。
- 防寒具
- 防寒の衣類・小物。
- ヘッドランプ
- 夜間歩行用の照明器具。
- 地図
- 地形図や地図の情報。
- コンパス
- 方位を測る道具。
- GPS
- 位置確認・ナビゲーション用の端末。
- 通信手段
- 連絡方法(携帯・衛星電話・無線など)。
- 緊急連絡先
- 事故や遭難時の連絡先(家族・知人・同行者)。
- 緊急信号
- 遭難時の合図や緊急信号の方法。
- 医療情報
- 薬・既往・アレルギーなどの医療情報。
- アレルギー
- 食物・薬などのアレルギー情報。
- 体調
- 直近の体調状態・疲労感。
- 体力
- 全体的な体力レベル。
- 山岳保険
- 加入している保険と補償内容。
- 安全対策
- 安全を確保するための方針・行動ルール。
- 危険箇所
- 崩落地・渡渉・急斜面などの危険箇所。
- リスク管理
- リスクの特定と対処計画。
- 提出方法
- 登山計画書の提出手順・窓口。
- 署名捺印
- 正式な提出のための署名・捺印。
- 合流場所
- グループの合流・待ち合わせ場所。
- ソロ登山
- 一人で行く場合の計画情報。
- 登山計画書の書き方
- 書式・記載項目・ポイント。
- 山岳警察
- 遭難時の連絡先、山岳警察・警備隊の連絡先。
- 山小屋情報
- 山小屋の予約・位置・連絡先。
登山計画書の関連用語
- 登山計画書
- 山行の安全を確保するために、出発前に自分の行動計画・装備・連絡先などを文書化したものです。天候・ルート・所要時間・避難計画・緊急時の対応を記載します。
- 登山届
- 登山計画を公的に周知する書類で、地域の警察署や山岳団体に提出します。遭難時の捜索・救助を円滑にする情報を伝えます。
- 行動計画
- 日ごとの行動予定を時刻・場所・休憩地点まで含めてまとめた計画。現地での判断材料にもなります。
- ルート情報
- 選択した登山ルートの名称・分岐・難所・所要時間・距離などを記録します。
- 起点・終点
- 出発点(登山口やベースキャンプ)と到着点(山頂・山小屋・下山口)を明記します。
- 天候情報
- 出発前と途中で確認する天候の情報。急変することがあるため定期的にチェックします。
- 気象情報
- 気象庁や民間の天気予報など、最新の気象データ。風、降水、視界の情報を含めます。
- 危険箇所
- 崩落・落石・凍結・暴風など、特に危険と判断した場所の情報です。
- 難所
- 鎖場・岩場・急斜面など技術が必要な区間の情報。事前準備の目安になります。
- ルート難易度
- 初級・中級・上級など、ルートの難易度を表します。
- 標高差
- 起点と終点の標高差、累積の上り下りの目安です。
- 装備リスト
- 防寒具・防水具・登山靴・ヘッドランプ・救急用品など、持参する装備の一覧です。
- 食料計画
- 1日分の食料の種類と量。行動時間に応じて調整します。
- 水分計画
- 1日あたりの水分量の目安と給水ポイント。脱水を防ぐ計画です。
- 装備重量
- 全体の装備の総重量の目安。持ち運びの負荷を把握します。
- 服装・レイヤリング
- 天候に合わせた重ね着(レイヤリング)計画。保温と透湿を両立させます。
- 地図
- 紙地図・電子地図など、現在地を把握するための地図情報です。
- コンパス
- 方位を測る基本的な道具。ナビゲーションの基本要素です。
- GPS
- 現在地・ルートの追跡に使う電子機器。バックアップとしても有用です。
- 緊急連絡先
- 家族・友人・山岳仲間の連絡先を記載します。非常時の第一連絡先です。
- 緊急時の対応
- 遭難・事故時にとるべき初動対応と連絡手順をまとめます。
- コミュニケーション手段
- 携帯電話・無線・衛星電話など、連絡方法を明記します。
- 提出先
- 登山計画書の提出先は地域により異なり、警察署・山岳会・自治体などがあります。
- 山岳保険
- 山での事故・救助費用を補償する保険。加入を推奨します。
- 登山保険
- 山岳保険と同義で用いられる場合の表現。加入が安心です。
- 救助費用
- 遭難時の救助費用が発生することがあるため、事前に確認しておきます。
- 自己負担
- 救助費用の自己負担の可能性を事前に理解しておくことが大切です。
- 野営計画
- 野営地の選択・設営計画・安全確認を含む野営計画です。
- 夜間行動
- 夜間や悪天候時の移動・活動方針と安全対策を定めます。
- 現地情報の更新
- 現地の天候・道の状況の変化を反映して計画を更新します。
- 計画変更届
- 計画を変更する場合の届出手続き。提出先や様式は地域で異なります。
- 健康状態
- 出発前・行程中の体調・健康状態の自己チェックを行います。
- 薬・健康管理
- 持病の薬、応急薬の管理と携行方法を記載します。
- 体力・技量
- 自分の体力・技術レベルの自己評価と、それに合わせた計画づくり。
- 出発前チェックリスト
- 出発前に必ず確認する項目のチェックリストです。
- 安全対策
- 転倒防止・低体温対策・雨天対策など、具体的な安全行動を明記します。
- リスクマネジメント
- リスクを特定・評価・対策を講じる計画の考え方です。
- 遭難時の情報提供
- 救助隊に渡すべき情報(場所・状況・人数)を整理します。
- 位置情報の共有
- 仲間と現在地を共有する方法(アプリ・SNS・通信機器など)を決めます。
- 登山規範・マナー
- 山岳での基本的なマナーとルールを守ることを重視します。
- 関連団体
- 山岳会・山岳連盟・自治体の登山団体など、情報源としての団体を挙げます。
- 緊急連絡の手順
- 事故・遭難時にとる最初の連絡手順と必要な情報の準備を記します。
- ルート変更時の連絡
- ルートを変更した場合の報告先・報告方法を決めておきます。
- 高所病対策
- 高度順応を促す行動・休憩・水分・適切な標高上昇ペースなど、高地環境での健康を守る工夫を記します。
- 山岳警察
- 遭難時の捜索窓口として機能する警察の山岳関連部門を指します。
- 警察への連絡
- 登山届・遭難時に連絡する主要窓口。電話番号や方法を確認しておきます。