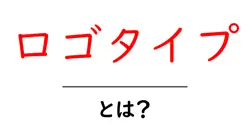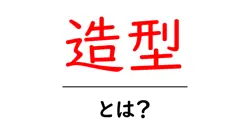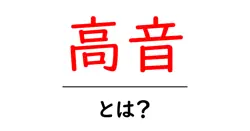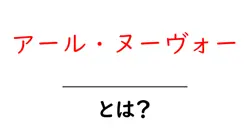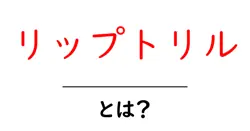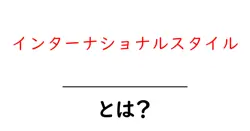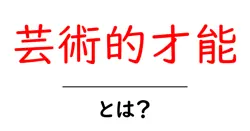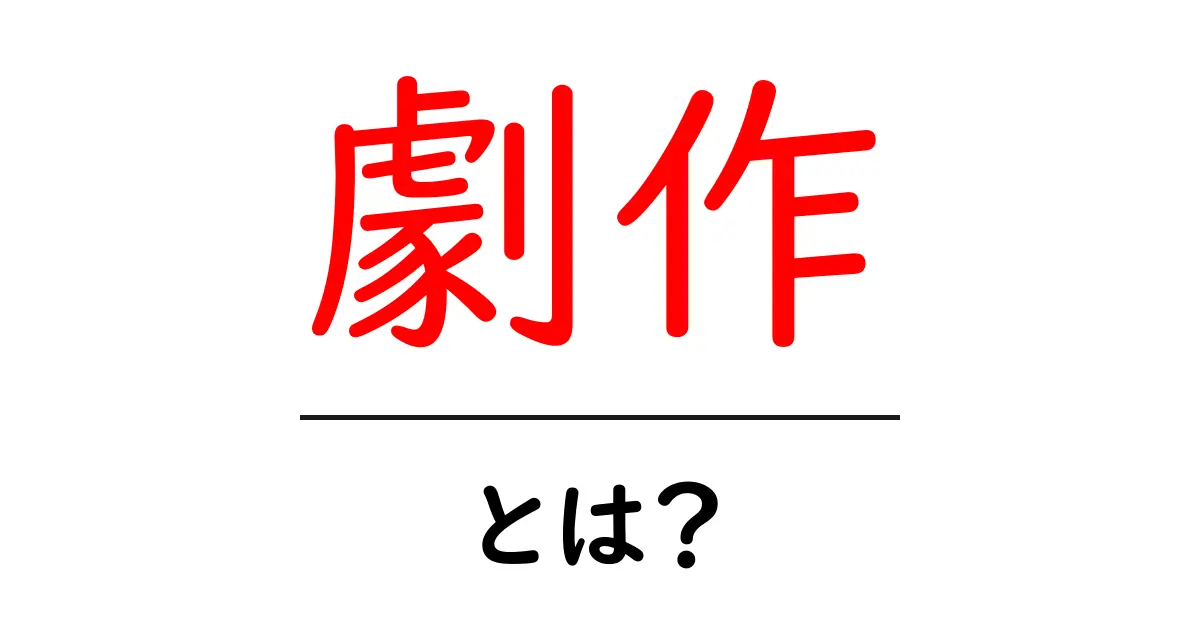

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
劇作・とは?
劇作とは、舞台やテレビ・映画のための脚本を書くこと、またはその技術自体を指します。簡単に言えば「劇を作る作業」です。作品の構成・登場人物・セリフ・舞台設定などを物語として組み立てるのが役割です。
劇作には大きく分けて2つの役割があります。1つは「新しい物語を創る創作」、もう1つは「既存の物語を上演用に整える編集作業」です。実際の舞台では監督・演出家と共に、役者へ伝わる言葉やリズム、間の取り方を決めていきます。
劇作の基本的な要素
登場人物は物語の視点と感情を動かす核です。舞台設定は場所・時代・雰囲気を決め、観客に物語の世界を伝えます。セリフは登場人物の心の声を言葉にします。構成は起承転結のように話の流れを作ります。これらをバランス良く組み合わせることが、観客に伝わる劇作になるコツです。
初心者が押さえる練習法
初めて劇作に触れる人は、短い題材から始めましょう。1日1ページ程度の台本を書いてみて、登場人物の動機や対立を意識します。次に、完成した台詞を声に出して読んでみると、リズムや言い回しの自然さが分かります。友達や先生に読んでもらい、フィードバックを受け取ることも大切です。
練習のコツは次の3つです。
- 1. 短い題材から始める 登場人物を2人程度に絞ると練習しやすい。
- 2. セリフのリズムを意識 口語が自然かどうか、長台詞を避けて短いセリフを重ねる。
- 3. フィードバックを活用 他者の視点で弱点を直す。
最後に、劇作は「想像力を形にする作業」です。自分の感情や観客の感情を結ぶ橋づくりと考えると楽しくなります。
劇作と他の分野の関係
劇作は演出、演技と協力して初めて完成します。演出家は舞台の空間演出・演技の指示を出し、演技は台詞を生きた言葉にします。劇作家はあくまで台本の設計者です。
よくある誤解
台本=完結 という理解は多いですが、現場では解釈の余地が多く、リハーサルを重ねながら修正されます。
このように、劇作は創造と協働の作業です。新しい物語を作る喜びをまずは小さな作品から味わってみましょう。
劇作の同意語
- 戯曲作成
- 劇作の作成。新しい戯曲を生み出す作業です。
- 戯曲執筆
- 戯曲を文字として書き上げる作業。セリフや場面描写を整えます。
- 戯曲創作
- 戯曲を生み出す創作活動全般。アイデア出しから完成までを含みます。
- 脚本作成
- 舞台・映画・テレビなどの脚本を作ること。台本を形にする作業です。
- 脚本執筆
- 脚本を書き上げる行為。セリフと構成を整える作業です。
- 台本作成
- 舞台用の台本を作ること。演出指示やセリフを整えます。
- 台本執筆
- 台本を執筆すること。完成版の台本へと仕上げます。
- 演劇創作
- 演劇全般の創作活動。物語・台本・演出の基盤を作ることです。
- 劇作活動
- 劇作を行う活動全般。新作を生み出す取り組みを含みます。
- 劇作家
- 劇作を行う人。作品の著者として活躍します。
- 戯曲家
- 戯曲を書く作家。劇作家と同義で使われることがあります。
劇作の対義語・反対語
- 観劇
- 劇作の対義語として、脚本を創作する行為ではなく、完成した作品を観賞する行為。
- 上演
- 書かれた脚本を舞台で実際に公演・演じる行為。創作活動の対極として、作品を“見せる”側の活動。
- 演出
- 脚本を舞台化する際の方針・表現づくりの作業。劇作(脚本執筆)とは別の創作分野の対義概念。
- 鑑賞
- 作品を味わい・評価する行為。創作を生み出す行為(劇作)とは受動・評価寄りの対立概念。
- 批評
- 作品を分析・評価・解説する行為。創作側の行為である劇作とは異なる解説・評価の役割。
- 観客
- 舞台を観る側の立場の人。作品を作る側(劇作)との役割の対照概念。
劇作の共起語
- 戯曲
- 舞台で上演される劇の原作。台本の別名として使われることが多い。
- 脚本
- 舞台・映画などの台詞と演出指示をまとめた文書。劇作の中心的成果物。
- 台本
- セリフと演出指示を整理した上演用の文書。脚本と同義として使われることが多い。
- 劇作家
- 戯曲を創作する人。劇作の作者。
- 戯曲家
- 戯曲を書く人。劇作家の同義語として使われることがある。
- 演劇
- 舞台上で上演される芸術表現の領域・作品群の総称。
- 演出
- 舞台表現を指揮・演出する作業。俳優の動きや舞台美術を決定する。
- 登場人物
- 劇の世界に登場するキャラクター。物語の主体となる人物群。
- セリフ
- 登場人物が話す台詞。ストーリーの動きを担う中心的要素。
- 筋
- 物語の展開の大筋。起承転結の流れ。
- プロット
- 物語の設計図。出来事の順序と結末を決める構造。
- 構成
- 作品全体の組み立て方。場面配置や話の進行の設計。
- 場面設定
- 舞台上の場所・時代・雰囲気の設定。
- 場面転換
- 場面と場面の切り替え。演出の技法の一つ。
- モノローグ
- 一人語りのセリフ。独白形式の表現。
- 対話
- 登場人物同士の会話。物語を進める基本手段。
- 台詞回し
- セリフの言い回し・リズム・語感の工夫。
- 登場人物設定
- キャラクターの性格・背景・動機を設定する作業。
- 筋書き
- 物語の概要や設計。企画段階で用いられることが多い。
- テーマ
- 作品の中心となる主題・伝えたいメッセージ。
- 批評
- 戯曲・演劇についての評価・評論。
- 劇作理論
- 劇作に関する理論・研究。構造・表現の考察。
- 劇作法
- 戯曲を書く技法・実践的方法。
- 登場人物デザイン
- キャラクターの設計要素。性格・外見・関係性の決定。
- 舞台
- 公演が行われる場所。舞台演出の対象となる空間。
- 上演
- 作品を舞台で公演すること。実際の公演行為。
- 脚色
- 元作品を新しい形に翻案・再構成すること。
劇作の関連用語
- 脚本
- 演劇の原稿で、セリフと演出指示を含む基本的な文書。
- 台本
- 脚本と同義。上演を前提とした正式な文書で、場面やセリフが整理されている。
- 劇作家 / 脚本家
- 戯曲を創作する作家。物語・登場人物・台詞を設計する人。
- 台詞
- 登場人物が話す言葉。感情や意図を伝える主要な要素。
- 登場人物 / キャラクター
- 物語に登場する人物や存在。性格・動機・関係性を設定する対象。
- キャラクター設定
- 人物像の詳細を決める作業。名前・年齢・性格・背景・目的などを整理する。
- 幕
- 物語を区切る大きな区分。第一幕・第二幕など、上演の構造を作る。
- 幕間
- 公演の中休み。観客が席を外したり休憩を取る時間。
- シーン / 場面
- 舞台上の具体的な状況や場所・時間のまとまり。
- 第一幕
- 物語の導入部分を担う幕。登場人物や状況を紹介する。
- 第二幕
- 対立や緊張が高まる幕。
- 第三幕
- 解決へ向かう幕(三幕構成の場合)
- 四幕構成
- 四つの幕で展開する構成法。
- 五幕構成
- 五つの幕で展開する構成法。古典劇で用いられることがある。
- 三幕構成
- 物語を三つの幕に分ける基本的な構成法。導入・対立・解決の流れ。
- プロット / 筋
- 物語の大筋と出来事の順序。動機と結果の連鎖を設計する。
- テーマ / 主題
- 作品全体を貫く中心の問いやメッセージ。
- モチーフ
- 作品の中で繰り返し現れる象徴的な要素。
- 起承転結
- 物語の基本的な展開順序。導入・展開・転換・結末を示す。
- 伏線
- 後の展開で意味を持つ仕掛け。観客の期待をつくる。
- 独白 / モノローグ
- 登場人物が自分の心情を長く語る場面。
- 会話
- 登場人物同士の対話。物語を前へ進める主要な手段。
- 台詞回し
- 言葉のリズムや抑揚、話し方の工夫を指す表現技法。
- 演出
- 舞台の表現方針を決め、上演を統括する作業。
- 演出家
- 演出の責任者。全体の演出方針と舞台表現を指揮する職種。
- 演出指示 / 舞台指示
- 照明・音響・演技の具体的指示を記した部分。
- 舞台美術 / 美術
- 舞台の背景・セット・色彩など、視覚的要素を設計・制作する分野。
- 舞台装置 / 小道具
- 舞台で使用する道具と装置の総称。
- 照明 / 照明効果
- 場面の雰囲気・時間帯を光で表現する設計。
- 音響効果
- 効果音や音楽を使って場面の感情を高める要素。
- ジャンル
- 作品の種類。悲劇・喜劇・現代劇・歴史劇・ミュージカルなど。
- 書式 / 脚本形式
- 台本の体裁。セリフの配置、段組み、見出しなどの規約。
- 上演台本
- 公演時に用いられる正式な脚本。演出指示を含むことが多い。
- 翻案 / アダプテーション
- 既存作品を新しい形で上演するための改編。
- 原作
- 元となる創作物。
劇作のおすすめ参考サイト
- 劇作(ゲキサク)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 劇作(ゲキサク)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 軋轢(アツレキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 劇作術(げきさくじゅつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク