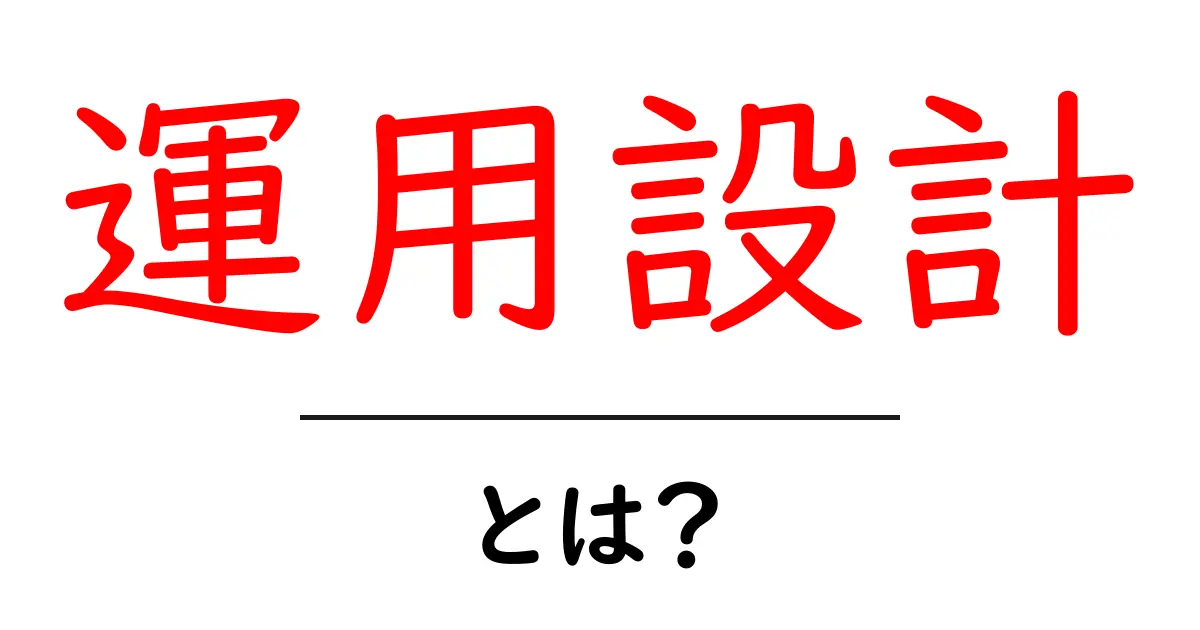

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
運用設計とは、ITシステムやサービスを安定して動かすための「設計作業」です。新しく作るだけでなく、既存の運用を改善するための仕組みを整えることを含みます。運用設計の目的は、障害を減らし、作業のムラをなくし、関係者の役割をはっきりさせることです。
運用設計にはいくつかの基本要素があります。まずは「目的と範囲」です。何を運用の対象とし、どの程度の品質を目指すのかを決めます。次に「運用体制と役割」です。誰が何を担当するのか、連絡の仕組みや責任の所在を決めます。
主な要素の紹介
手順とSOP (標準作業手順) を文書化します。これにより、担当者が変わっても作業内容を再現でき、品質を安定させます。
監視とアラート です。システムの状態を常時監視し、異常を早期に知らせる仕組みを設計します。どの指標を見て、どの閾値で通知するかを決めておくことが重要です。
変更管理 です。変更を計画、承認、実施、検証、記録する流れを決め、予期せぬ影響を減らします。
他にも「バックアップと復旧」、「セキュリティとアクセス管理」、「教育と運用の継続的改善(PDCAサイクル)」などが含まれます。
運用設計の実践フロー
実際の運用設計は、現状の把握から始めます。現場の作業工程を観察し、ボトルネックやムリ・ムダを洗い出します。次に、設計・標準化を進め、文書化されたSOPを作成します。その後、実装と移行を行い、運用開始後は監視と改善を続けます。
この流れを守ることで、障害対応が速くなり、運用コストを抑え、メンバーの負担を減らせます。
運用設計の具体例
ウェブサイト運用の例を挙げてみましょう。監視対象はサーバーのCPU・メモリ、アプリの応答時間、エラーログなどです。SOPには、障害発生時の連絡先、復旧手順、影響範囲の確認方法、再発防止の対策が含まれます。定期的なバックアップ検証や、変更リスク評価も忘れずに行います。
最後に、学ぶべきポイントは「小さく始めて改善を積み重ねる」ことです。最初から完璧を求めるのではなく、現場の声を反映させながらSOPを更新していくことが大切です。
運用設計の同意語
- 運用計画
- 運用を実施するための全体の計画。人員・スケジュール・資源配分・作業のタイムラインを決め、実行に向けた道筋を作る設計。
- オペレーション設計
- 日常の運用作業をどう回すかを決めるための設計。作業の順序・責任者・依存関係を整理する。
- 運用プロセス設計
- サービスやシステムの運用を構成する一連のプロセスを設計すること。各プロセスの目的・入力・出力・担当を定義。
- 運用フロー設計
- 運用の流れ(ワークフロー)を可視化し、手順の順序や分岐を定義する設計。
- 運用手順設計
- 具体的な作業手順を体系化する設計。誰が、いつ、どの手順で作業するかを明確にする。
- IT運用設計
- ITシステムの運用を前提にした設計。監視・障害対応・バックアップ・変更管理などを組み立てる設計。
- サービス運用設計
- 提供サービスの運用を設計すること。サービスレベル、運用体制、監視・通知ルールを決める設計。
- 運用管理設計
- 運用の管理観点を取り入れた設計。KPI・レポート・改善サイクル・資源の最適化を含む。
- 運用方針設計
- 運用の基本方針やルールを定める設計。適用範囲、セキュリティ・品質方針を明確化。
- 運用ガバナンス設計
- 組織としての運用を適切に統制・監督する枠組みを設計すること。権限・責任・監査の体制を定義。
- オペレーション計画
- 英語由来の表現で、運用を実行するための計画。実務の実行順序や期日を整理。
- 運用手順マニュアル設計
- 現場で使う手順書を設計・整備すること。手順の分かりやすさと実用性を重視。
運用設計の対義語・反対語
- 開発設計
- 運用設計が日常的な運用・保守の手順や体制を設計するのに対し、機能開発・実装の設計を重視する視点。実装・機能の仕様・構成を中心に据え、運用の細かな手順は後回し・別枠になることが多い。
- 事前設計
- 導入前・実装前の段階で設計を行う考え方。運用設計が運用時の手順や体制を整えることを目的とするのに対して、事前設計は運用を前提とせず、実装前の仕様・構成を固めることを重視します。
- 高レベル設計
- 全体の構成や方針といった抽象度の高い設計。運用の細かな運用手順よりも、システム全体のアーキテクチャやデータフローを設計する視点が中心です。
- 戦略設計
- 日常の運用の実務ではなく、組織の長期的な方針・目標を決める戦略レベルの設計。運用設計が現場運用に焦点を置くのに対して、戦略設計は方向性を定めます。
- 自動化設計
- 手作業の運用を前提とせず、業務の自動化や自動処理の前提で設計を進める考え方。運用の自動化を促進する観点が中心になります。
- 運用前提なしの設計
- 運用の実務・運用フローを設計対象としない、機能・技術要件を重視する設計。運用の観点を排除・分離する表現として使われることがあります。
- 開発寄り設計
- 設計の焦点を開発・実装の観点に置くスタンス。運用の実務的な手順より、機能実装の仕様・技術選択を優先します。
運用設計の共起語
- 運用フロー
- 日常の運用作業がどの順序で実施されるかの流れ。開始点と完了点を明確にする設計。
- 監視体制
- システムの稼働状況を監視する責任者・役割分担と連携の仕組み。
- 監視設計
- 監視する指標、閾値、通知ルールをあらかじめ決める設計。
- アラート設計
- 障害を知らせる通知の条件・宛先・連絡方法を定義する設計。
- 監視ツール
- 監視を実現するためのソフトウェアやサービス。
- ログ管理
- イベントの記録を保管・整理・分析して障害原因の特定や改善に活用する作業。
- 手順書
- 作業のやり方を具体的に記した文書。誰が読んでも同じ手順で実施できるようにします。
- SOP
- Standard Operating Procedure の略。標準作業手順書として運用の統一を図る文書。
- 要件定義
- 運用で満たすべき機能・条件を整理して明確にする初期設計。
- 仕様化
- 要件を具体的な仕様やルールに落とし込む作業。
- 変更管理
- 変更を計画・承認・実施・影響評価する組織的な枠組み。
- チェンジマネジメント
- 組織全体で変更を効果的に管理する考え方と実務。
- バージョン管理
- コードや設定の履歴を追えるように管理するしくみ。
- データ運用
- データの作成・整備・保守・活用を日常的に管理する取り組み。
- データガバナンス
- データの品質・利用・責任を統一的に管理する枠組み。
- バックアップ
- データのコピーを作成して、災害時や障害時に復元できるようにしておく作業。
- 災害復旧
- 災害時の復旧計画と手順を実行する活動。
- 障害対応
- 障害が発生した際の初動対応と解決までの作業。
- 障害復旧
- 障害後の復旧作業と検証を行う工程。
- 依存関係管理
- 他のシステムやサービスとの依存関係を把握して管理すること。
- 変更影響分析
- 変更が他の機能や部品へ与える影響を事前に評価する分析。
- ルール整備
- 運用ルールを整備し、組織で遵守されるようにすること。
- 標準化
- 作業手順を統一して再現性と品質を高めること。
- ガイドライン
- 推奨される運用方針を示す文書・指針。
- 体制構築
- 運用を担う組織体制と役割分担を整えること。
- 人員配置
- 運用を担当する人員を適切に配置すること。
- 役割分担
- 誰が何を担当するかの責任と権限を決めること。
- 連携設計
- 複数部門やツール間の連携方法を設計すること。
- 連絡体制
- 緊急時の連絡経路と連絡先・手順を定めること。
- エスカレーション
- 問題を適切に上位へ引き上げる通知・対応の流れ。
- PDCA
- Plan-Do-Check-Act の循環で継続的に改善する考え方。
- 継続的改善
- 小さな改善を継続的に積み重ねる文化・取り組み。
- KPI
- 重要業績評価指標。成果を測る定量的な指標。
- KPI設計
- 達成すべき指標と評価方法を設計する作業。
- 指標設計
- 測定する指標の種類と定義・計算方法を決める作業。
- SLA
- Service Level Agreement。提供するサービスの品質基準を契約・合意で定めること。
- SLA設定
- SLAに含める指標と閾値・対象範囲を決める作業。
- 目標設定
- 運用の改善目標を具体的な数値で決めること。
- コスト管理
- 運用コストを見積もり・配分・最適化する活動。
- 予算管理
- 運用の予算を計画・執行・管理すること。
- 品質管理
- 作業の品質を保つための基準・検査・改善を行うこと。
- 品質保証
- 品質を保証するための予防的な取り組みやプロセス。
- リスク管理
- 運用上のリスクを特定・評価・対策すること。
- セキュリティ
- 情報資産を守るための対策・方針・教育を含む領域。
- ITIL
- ITサービスマネジメントのベストプラクティスの集まり。
- SRE
- Site Reliability Engineering。サービスの可用性とパフォーマンスを高める技術・運用アプローチ。
- 自動化
- 繰り返し発生する作業を自動的に実行すること。
- 自動化ツール
- 運用の自動化を実現するツール群。
- RPA
- Robotic Process Automation。定型業務を自動化する技術。
- デプロイ運用
- リリース後の運用を含めたデプロイ手順と監視設計。
- テスト運用
- 本番環境へ移行する前に運用を模擬して検証する作業。
- ダッシュボード
- 運用状況を一目で確認できる可視化画面。
- レポーティング
- 定期的に運用の結果を報告する作業・資料作成。
- 監査
- 運用が規定や法令に沿っているかを独立して検証する活動。
- 環境設定
- 運用環境の構成情報を適切に設定・管理すること。
- 冗長化
- 故障時にもサービスが止まらないように構成を複数持つこと。
- アーキテクチャ設計
- システム全体の構造を設計すること。
- 手順化
- 作業を具体的な手順として文書化すること。
運用設計の関連用語
- 運用設計
- ITサービスの運用を安定・効率的に行うための設計。役割分担、手順、ツール、データ、監視、改善の仕組みを整えます。
- サービスレベル管理
- 提供するサービスの品質を測定・管理する枠組み。SLAの達成状況を監視・報告し、改善を促します。
- SLA(サービスレベルアグリーメント)
- サービス提供条件を明示した契約文書。可用性、応答時間、処理能力などの目標値を定義します。
- SLA管理
- SLAの適用・遵守状況を継続的に管理する活動。
- 変更管理
- 変更を計画・承認・実施・検証するプロセス。リスクを抑え、安定運用を保ちます。
- 構成管理
- 資産と構成の関係を整理・記録する活動。CI(構成アイテム)を管理します。
- CMDB
- 構成アイテムとその関係性を格納するデータベース。変更影響分析や故障時の原因特定に役立ちます。
- 監視設計
- 障害を早期に検知するための監視項目・閾値・通知ルールを設計する作業。
- 可用性設計
- サービスの継続提供を前提に、冗長性・フェイルオーバー・バックアップ・復旧手順などを設計。
- 可観測性
- ログ・メトリクス・トレースを組み合わせ、システムの状態を把握する能力の設計・実装。
- ログ管理
- イベント情報を収集・保管・検索・分析する運用。
- メトリクス設計
- パフォーマンス・利用状況を示す指標(メトリクス)を選び、収集・監視する設計。
- アラート設計
- 異常を知らせる閾値・通知先・通知頻度を決める設計。
- バックアップ設計
- データの定期バックアップと復旧条件を設計する。
- 災害復旧計画 / DRP
- 大規模障害時の復旧手順・優先順位・役割を定める計画。
- 事業継続計画 / BCP
- 事業の継続を確保するための方針・手順・資源確保計画。
- リリース管理
- 新機能・修正を安定的に提供するための計画・承認・デプロイ・評価の流れ。
- デプロイ管理
- ソフトウェアを本番環境へ安全に導入するプロセスと手順。
- 変更影響評価
- 変更が他の機能・サービスへ及ぼす影響を事前に評価する作業。
- インシデント管理
- 障害の受付・分類・暫定対応・恒復・復旧を管理するプロセス。
- 問題管理
- 根本原因を特定し、再発防止策を講じる取り組み。
- ジョブ管理
- 定期的な処理の計画・実行・監視を行う管理。
- バッチ運用
- 夜間処理など大量データ処理を安定させる運用。
- 運用ドキュメント / ランブック
- 運用手順・対応手順を記したドキュメント。再現性を高める。
- セキュリティ運用
- 情報資産を守るための運用ルール・監視・対策・教育。
- キャパシティプランニング
- 将来の需要を見越して適切なリソースを確保する計画。
- リスク管理
- 運用上のリスクを洗い出し、評価・対策を講じる活動。
- サービスカタログ
- 提供サービスの一覧と仕様を公開する文書・データベース。
- サービスデスク
- 利用者の問い合わせを受け付け、一次対応を行う窓口。
- 品質管理
- 運用の品質を測定・改善する仕組みと活動。
- 継続的サービス改善 / CSI
- サービス運用を継続的に改善する取り組み。
- 自動化 / 運用自動化
- 繰り返し作業を自動化して効率・正確性を高める。
- 運用オーケストレーション
- 複数の自動化タスクを連携させ、運用全体の流れを最適化する仕組み。
- RPA
- ロボティック・プロセス・オートメーション。定型業務を自動化するツール。
- データ保全と回復テスト
- データの整合性を保ち、復旧手順が機能することを検証するテスト。
- 監査対応
- 法令・規格・内部監査の要件に沿って記録・証跡を整えること。
- コンプライアンス
- 法令・規格・社内ルールの順守を確保する活動。
- ITIL / ITサービスマネジメント
- ITサービスの設計・提供・改善を体系化するベストプラクティス。
運用設計のおすすめ参考サイト
- 運用設計とは?行うメリットや検討すべき項目を解説
- 運用設計とは?メリットや流れ、運用管理の方法を解説
- 運用設計とは?必要項目や設計の流れ・ポイントをイチから解説!
- 基本設計と運用設計の違いとは?|システム運用のポイント
- システムの運用設計とは?種類やメリット
- 運用設計とは?必要項目や設計の流れ・ポイントをイチから解説!
- システム開発後の「運用設計」とは? 重要性や進め方を解説



















