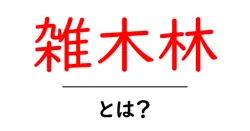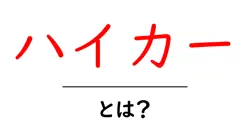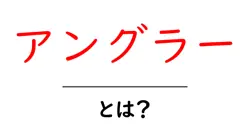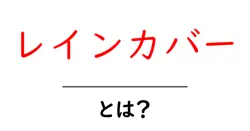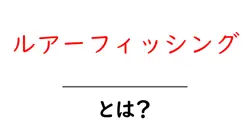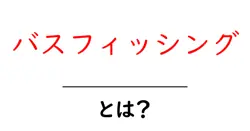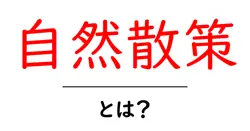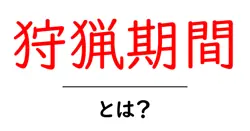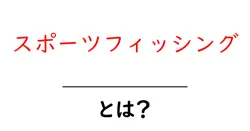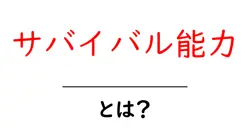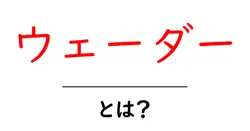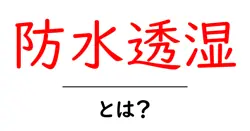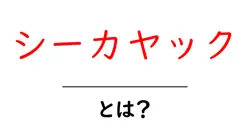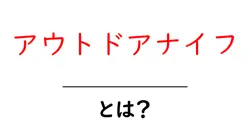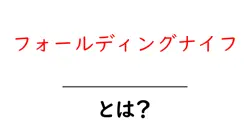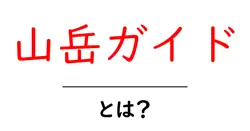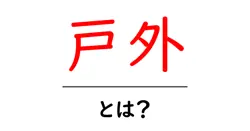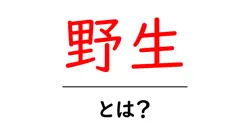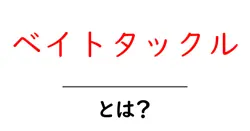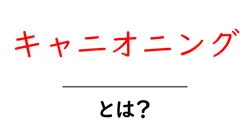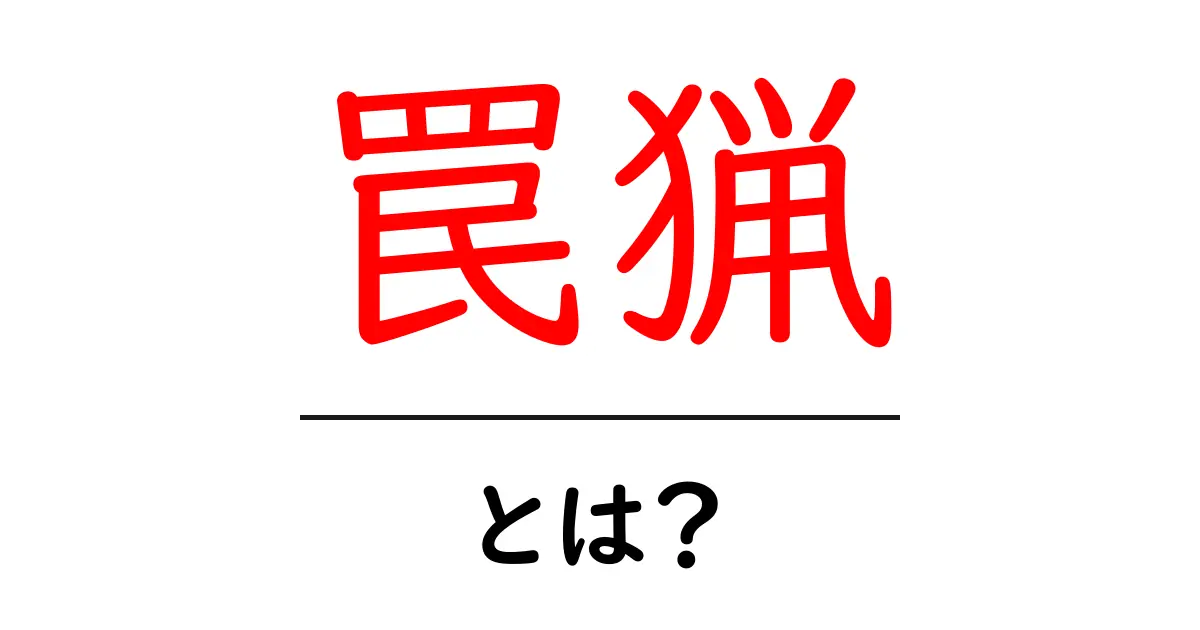

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
罠猟・とは?初心者が知っておく基本と注意点
罠猟とは動物を罠で捕獲する狩猟の一形態です。歴史的には狩りの技術として長く用いられてきましたが、現代では安全性、倫理性、法的規制がとても重要になっています。
罠猟を始める前に知っておくべき3つのポイントは法的要件、安全と倫理、学び方です。これらを理解することで、自然への負荷を減らし、事故やトラブルを防ぐことができます。
法的要件と地域差
日本を含む多くの国では罠猟を行うには免許や講習、猟期などの規定があります。地域ごとに条例が異なるため、まずは自治体の窓口で自分の地域のルールを確認してください。 無許可の設置や違法な捕獲は罰則の対象になり得ます。
安全と倫理の重要性
安全第一を徹底し、道具の取り扱いだけでなく周囲の人やペット、非標的動物への影響を最小限に抑えることが求められます。倫理的には、動物福祉を考え、過度な苦痛を与えないよう努めることが大切です。
学び方と実践の道
罠猟を学ぶには地元の猟友会や自治体の講習を受けるのが基本です。専門の指導のもと、合法的で安全な範囲で知識を深めてください。初学者は地域の先輩に同行して現場を観察する方法が有効です。
罠の種類と扱いの注意
罠には歴史的にいくつかのタイプがあると紹介されることがありますが、ここでは具体的な作り方には踏み込みません。名称のみの説明にとどめ、実際の設置方法は専門家の指導を受けてください。 一般的には捕獲対象に合わせた設計思想があり、誤食防止や非標的動物の被害を考慮する必要があります。
参考となるポイントの表
最後に
罠猟は自然と人との距離を考える難しい分野です。適切な知識と法令順守を前提に、地域の専門家の指導を仰ぎながら学ぶことが大切です。もし興味がある場合は、まず情報を集め、体験談や講習情報を調べてみましょう。
罠猟の同意語
- 罠狩猟
- 罠を使って獲物を捕らえる狩猟のこと。罠を設置・使用して狩猟を行う狩猟法の総称。
- トラップ猟
- 罠猟のカタカナ表記。罠を用いる狩猟の同義語。
- 置き罠猟
- あらかじめ場所に罠を設置して行う狩猟。捕獲を狙う罠の利用法。
- 罠を用いた狩猟
- 罠を用いて獲物を捕らえる狩猟全般を指す表現。
- 罠猟法
- 罠を用いる狩猟の具体的な方法や手順を指す語。
- 罠猟技術
- 罠の設置・誘引・回収など、罠猟に必要な技術のこと。
- 捕獲猟(罠を使った猟)
- 罠を用いて獲物を捕獲することを主目的とする猟の一形態。
罠猟の対義語・反対語
- 銃猟
- 銃を使って獲物を狩る狩猟方法。罠を使わず、距離を取って獲物を狙い撃つのが特徴です。
- 網猟
- 網を使って獲物を捕らえる狩猟方法。罠とは異なる装置で捕獲する点が対になる概念です。
- 手猟
- 素手、あるいは最低限の道具だけで狩る方法。罠を使わない直接的な捕獲手段として挙げられます。
- 非罠猟
- 罠を使用しない猟法の総称。罠猟の対極として、銃猟や網猟、手猟などと比較される表現です。
罠猟の共起語
- 罠
- 捕獲を目的とした器具・装置の総称。動物を罠で捕らえるための仕掛け。
- 猟
- 野生動物を狩る行為。自然環境の中で動物を追い、捕らえる活動の総称。
- 捕獲
- 罠や道具を使って動物を捕らえること。
- 捕獲猟
- 捕獲を目的として行われる猟の一種。罠を主に使って動物を捕らえることが多い。
- 狩猟免許
- 合法的に狩猟を行うために必要な許可。地域によって取得条件が異なる。
- 鳥獣保護法
- 鳥獣の保護と乱獲の禁止を定めた日本の主要な法制度。違法な捕獲を禁じる。
- 猟期
- 狩猟が許可されている期間。季節ごとに種別に定められている。
- 猟法
- 狩猟の方法や規制を定めた法令・規則を指す言葉。
- 狩猟
- 野生動物を狩る行為全般。自然環境と人との関わりを含む広い概念。
- 動物保護
- 動物の生命と福祉を守る取り組みや理念。
- 動物福祉
- 動物が不必要な苦痛を受けずに生きられるよう配慮する考え方。
- 環境保護
- 自然環境と生態系を守る活動の総称。
- 生態系
- 生物とその環境が互いに影響しあう、自然界のつながりの総称。
- 罠の種類
- 罠には様々な形状やしくみがあり、それぞれ対象に適したタイプがあるという分類。
- セット方法
- 罠を設置する前の計画や準備を表す一般用語。具体的手順の詳細は省くことが多い。
- 法規制
- 狩猟・罠の使用に関する法律的決まりごとの総称。
- 野生動物管理
- 野生動物の個体数と生息域を管理・保全する考え方。
- 狩猟文化
- 地域社会における狩猟の伝統・習慣・価値観を指す言葉。
- 狩猟倫理
- 狩猟における倫理観・持続可能性を重視する考え方。
罠猟の関連用語
- 罠猟
- 罠を用いて野生動物を捕獲する狩猟の一手法。日本では地域ごとに法規制があり、猟期の指定や免許の取得が必要になる場合が多い。
- 罠
- 野生動物を捕らえるための器具・仕掛けの総称。形態は多様で、捕獲を目的として設置される。
- くくり罠
- 動物の脚などを拘束して捕獲する固定式の罠の一種。法規制の対象となる場合があるため適正な取り扱いが求められる。
- 掛け罠
- 枝やロープなどを用いて動物を掛けて捕る罠の総称。設置目的や対象に応じて使われる。
- 落とし穴
- 地面に開けた穴に動物を落とさせて捕獲する罠の一種。安全性と法令遵守が重要。
- 罠設置
- 罠を適切な場所に設置する作業。周囲への影響・安全性・法令遵守を考慮して行う。
- 餌付け
- 捕獲対象を引き寄せる餌を設置する行為。法規制によって禁止・制限される場合がある。
- 誘引物
- 餌以外の香り・匂い・視覚的刺激など、動物を近づける要素全般。
- 捕獲
- 罠で動物を捕らえる行為。獲得・捕獲の総称として用いられる。
- 放獲
- 捕獲した動物を自然環境へ放つこと。適切な時期・場所・手順が求められる。
- 猟具
- 狩猟に使う道具の総称。罠以外にも銃・網・ロープなどを含む。
- 狩猟免許
- 狩猟を行うために必要な公的資格。講習受講や登録が要件となることが多い。
- 鳥獣保護法
- 野生動物の捕獲・保護を規定する日本の法律。対象となる動物、捕獲期間、猟具の使用などを定める。
- 狩猟区/猟区
- 狩猟を許可された区域。許可の範囲内で活動する必要がある。
- 狩猟期間/猟期
- 狩猟が認められている期間。季節ごとに定められている。
- 都道府県条例
- 各自治体が定める狩猟に関する追加規制。場所によって異なることがある。
- 安全管理
- 罠の設置・使用・撤去時の安全確保に関する管理事項。
- 倫理的狩猟
- 動物に対する苦痛を最小限にし、法令と倫理基準に沿って行う狩猟の考え方。
- 生態系保護
- 捕獲の影響が生態系に及ばないよう配慮する視点。
- 法規制・罰則
- 狩猟に関する法令と違反時の罰則を指す総称。
- 捕獲後の処理
- 捕獲した動物の取り扱い・搬送・処分に関する手続き。
- 罠の点検・撤去
- 罠の状態を定期的に点検し、不要な罠を適切に撤去する管理作業。