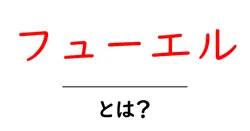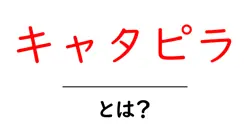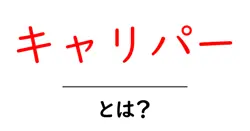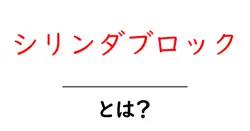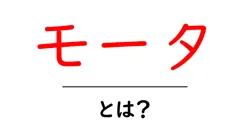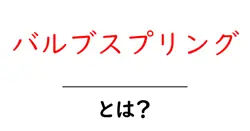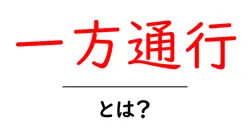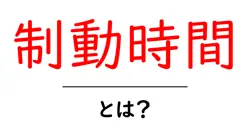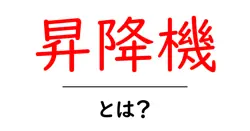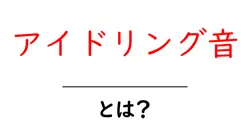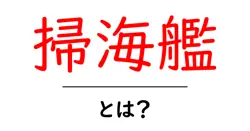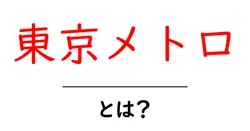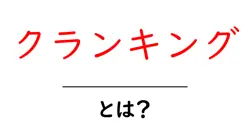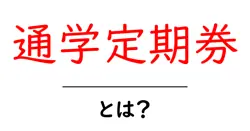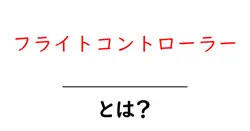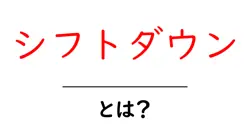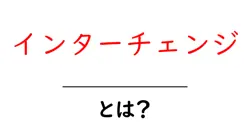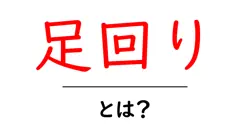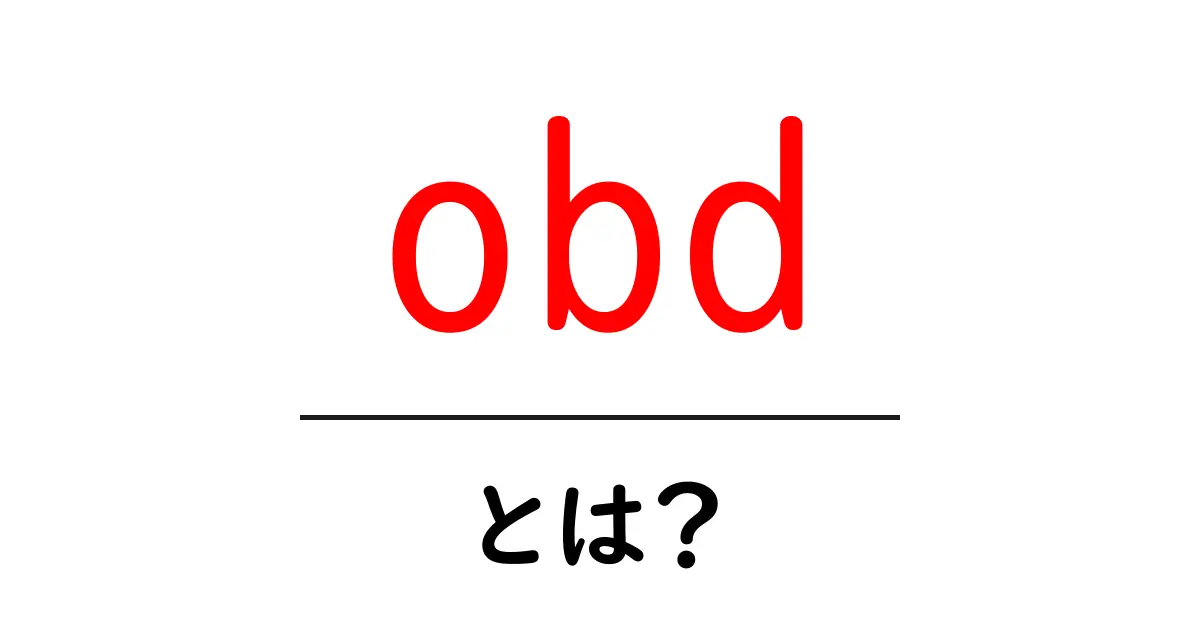

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
obdとは?基礎をつかもう
obdは車の「自己診断システム」(On-Board Diagnostics)の略です。車が普段から自分の状態を点検し、故障の可能性があるときに「診断コード」を表示します。こうしたコードを読み解くことで、何が悪いのかを知る手がかりになります。obdは自動車の健康状態を教えてくれる基本ツールです。
OBD-IとOBD-IIの違い
OBD-Iは車メーカーごとに規格が異なり、読み方も車によって違います。そのため、一般の人が使うには難しいことがありました。OBD-IIは1990年代後半に世界で標準化され、読み方が統一され、多くの車で同じコードが使われます。接続口は通常12〜16ピンの標準ポートになりました。
OBDポートを使って診断する仕組み
車のダッシュボードの下あたりにOBD-IIポートがあります。エンジンをONにして診断機を接続し、車が出すコードを読み取ります。コードは「PXXXX」の形が多く、PはPowertrain(エンジンと動力系)を意味します。コードの意味は辞典のように公開されており、オンラインで調べられます。
代表的なコードと意味の例
以下の表は、よく見かけるコードの例です。実車では正確な意味を公式な資料で確認してください。
上記は代表的な例です。車種や年式によって意味は少し異なります。正確な意味は車の取扱説明書や整備士の資料で確認してください。
OBDを使うときのポイント
安全第一。車を走らせたままコードを読むと危険な場合があります。必ず安全な場所に停車してから作業してください。
使い方の手順は以下のとおりです。
1) 車のエンジンをOFFにしてOBD-IIポートを探します。
2) 12〜16ピンの診断アダプターを接続します。
3) エンジンをONにして診断機を起動します。
4) 診断機でコードを読み取り、意味を確認します。
5) 必要に応じて整備士に相談します。
よくある質問
- Q: obdを使えばすぐ治りますか?
A: いいえ。OBDのコードは故障の原因のヒントに過ぎず、実際の修理には追加の点検が必要です。 - Q: 自分で修理はできるの?
A: 一部の基本的な点検は自分でやることもできますが、複雑な修理は専門家に任せるのが安全です。
まとめ
Obdは車の自己診断の仕組みを理解する第一歩です。OBD-IIの普及により、コードの意味を学び、車の状態を早く把握できるようになりました。正しく使えば、故障の予兆を早期に発見でき、修理費を抑える助けにもなります。
obdの関連サジェスト解説
- obd とは 車
- OBD とは On-Board Diagnostics の略で、車のコンピューターがエンジンや排出ガスなどの状態を監視する仕組みです。車のECU(エンジンコントロールユニット)がセンサーの数値を常に読み取り、規定の範囲から外れると警告灯を点灯させ、必要に応じて燃料の量や点火のタイミングを調整します。OBD は車の健康診断のようなもので、故障の兆候を早めに見つける手助けをします。
- obd とは何の略
- obd とは何の略?という質問は、車を学ぶ第一歩としてとても大切です。OBDはOn-Board Diagnosticsの略で、日本語では車載診断システムと呼ばれます。車のエンジンや排ガスの状態を車自体が常に監視し、異常を検知すると故障診断コード(DTC)を記録します。これにより、故障箇所を特定しやすく、修理の手掛かりになります。OBDには大きく分けてOBD-IとOBD-IIがあります。OBD-Iは昔の車でメーカーごとに仕様が違い、読み取りも難しいことが多かったです。一方OBD-IIは1990年代後半以降の多くの車に搭載され、標準化された規格です。診断コネクターは車内のダッシュボードの下あたりにある16ピンのDLC(データリンク)で、ここを使って診断機を接続します。OBD-IIの大きな特徴は、コードだけでなくリアルタイムのデータも見ることができる点です。例えばエンジン回転数、車速、空燃比、酸素センサーの値などが表示され、何が原因なのかを想像する手掛かりになります。実際にどう使うのかというと、家庭用のOBD-IIスキャナーやBluetooth接続のアダプターとスマホアプリを用意します。車の電源を入れ(多くの場合エンジンをかけなくても準備状態にしますが、指示に従ってください)、OBDポートにスキャナーを挿してコードを読み込みます。表示されるDTCには、Pコードといった分類があり、例えばP0300はエンジンの点火系の乱れを示すことがあります。コードの意味は車種や機器によって多少異なるため、車の取扱説明書やインターネットのリファレンスを参照しましょう。ポイントとして、コードを読むだけでは修理を直すことはできません。故障箇所を特定する手掛かりとして使い、専門の整備士に相談するのが安全です。また、OBDは排気ガスの規制や車の燃費改善にも役立つため、定期点検の一部として活用すると良いです。初心者にもおすすめの使い方は、普段のメンテナンスの記録を取ることです。エンジンのデータを長期間追うと、いつどんな状態から問題が起きやすいかが分かり、予防的な整備につながります。
- obd 検査 とは
- obd 検査 とは、車の車載診断システムを使って排出ガスの状態や部品の健康状態を検査するしくみのことです。車にはエンジンの動作を見守る小さなコンピューター(ECU)があり、センサーから集めた情報をもとに問題があると故障コードという番号を記録します。OBD は On-Board Diagnostics の略で、車が自分で自分の状態を知らせる仕組みです。現在は OBD-II という共通の規格が多くの車で使われており、コードは P、C、B、U の4つのカテゴリに分かれます。検査の流れはだいたい次のとおりです。1) 診断機という専用の機器を車のOBDポートに接続します。2) ECUの情報を読み取り、排出ガスのデータやセンサーの異常を確認します。3) データの記録と、必要に応じて実走行テストを行います。4) 問題が見つかれば修理が必要になります。修理後は再検査を受けることがあります。この検査の目的は、地球温暖化を防ぐための排出ガスを抑え、車の安全性を保つことです。最近の車は排出ガスを減らす技術が進んでおり、OBD検査によって故障の早期発見にも役立ちます。日常のポイントとして、チェックエンジンランプが点灯したら放置せずに点検を受けること、燃費が急に悪くなったり排気の匂いが変わったりしたら早めに整備工場へ相談することをおすすめします。
- obd コネクタ とは
- obd コネクタ とは、車の診断機能と外部のスキャナーをつなぐ接続口のことです。車の走行状態やエンジンのデータを記録・表示するECU(車両のコンピューター)と、整備士や自分で診断する人が情報をやり取りするための窓口です。現在多くの車にはOBD-II規格のコネクタが搭載されており、オーソドックスな形状は16ピンのD字型のコネクタです。OBD-II規格は1996年頃以降の新車にほぼ標準化されており、車種を超えて同じ規格の機器を使える利点があります。場所は運転席の足元やダッシュボードの下、時にはグローブボックスの裏などにあることが多いです。診断機をコネクタに挿し、イグニッションをONにすると車のECUがデータを外部に送り出します。得られる情報は故障コードだけでなく、エンジン回転数、車速、冷却水温、酸素センサの状態、排出ガス関連のデータなど多岐にわたります。初めて使う人は、まずは故障コードを読み取る練習から始めましょう。コードはP0〜P8などのアルファベットと数字の組み合わせで表され、意味をインターネットで調べると大まかな原因をつかめます。なお、コネクタを抜き差しする際は車の安全と法規を意識し、バッテリーのショートや配線の損傷を避けるためエンジンを切った状態で作業することが推奨されます。実際の修理は自分で行う場合とプロに任せる場合があり、それぞれの判断基準を知っておくと安心です。
- obd on uds とは
- obd on uds とは、車の診断に関する考え方のひとつです。OBDはOn-Board Diagnosticsの略で、車のエンジンや排出ガスの状態を常に監視し、異常があれば故障コードとして教えてくれる仕組みです。現在ではOBD-IIと呼ばれる規格が広く使われ、スマホやパソコンにつなぐとデータを読むことができます。一方、UDSはUnified Diagnostic Servicesの略で、車のECUと診断機の間でデータをやり取りする新しい通信手段です。UDSはCANや他のネットワーク上で複数のサービスを使い、データの読み取りや設定変更を行えるのが特徴です。
- 自動車 obd とは
- 自動車 obd とは、車の故障を知らせる情報を車のコンピューターから取り出す仕組みのことです。OBDはOn-Board Diagnosisの略で、日本語では車載診断といいます。現代の車はエンジンや排出ガスを管理する多くの部品を電子制御しており、状態を常に監視しています。故障の兆候を早く見つけ、適切な修理を行うために、車には診断用のポートがついています。これがOBDポートです。日本ではOBD-IIという規格が一般的で、1990年代後半以降に新車の標準になりました。OBD-IIポートは車のダッシュボードの下の近く、運転席の足元やセンターコンソールのそばにあることが多く、接続するケーブルや専用の機械OBDスキャナーを使って車のECUと通信します。OBDが出す情報の多くはDTC Diagnostic Trouble Codesと呼ばれる故障コードです。コードにはPコード、Bコード、Cコード、Uコードなどがあり、Pコードはエンジン系の故障を表すことが多いです。OBD-IIを使うと、車が現在どう動作しているかリアルタイムデータや過去に記録された故障コードを読み取ることができます。読んだコードを解釈することで、燃費の悪化、触媒の劣化、排出ガスの問題、センサーの故障など、どの部品が原因かを推測する手助けになります。実際の使い方はとても簡単です。車を止めた状態でOBDスキャナーの端子をOBDポートに差し込み、機械の指示に従ってコードを読み取り、表示させるといった操作をします。表示されたコードをインターネットで検索したり、整備士に伝えたりすることで、修理の見積もりや作業の計画が立てやすくなります。ただし、OBDはあくまで故障の原因を特定する手掛かりであり、部品の交換や修理自体を代行するものではありません。場合によっては関連する部品を同時に点検したり、排出ガスの検査やセーフティ点検を組み合わせて判断する必要があります。OBDは素人でも活用しやすいツールのひとつです。安全に使うコツとして、車の取扱説明書を確認し、車種ごとのOBD規格の違いにも気をつけましょう。特に年式の古い車ではOBD-Iという規格だったり、OBD-IIでも機能が限定されている場合があります。初心者はまずOBD-II対応のスキャナーを用意し、現在のコードとリアルタイムデータをチェックするところから始めると良いでしょう。
- 車検 obd とは
- 車検 obd とは何かを、初心者にも分かりやすく解説します。OBDはOn-Board Diagnosticsの略で、車のエンジンや排気ガスの状態を車載の診断機で監視する仕組みです。車検のときには、このOBDが正常に作動しているか、過去に出たエラーコードが残っていないかを確認することが重要です。最新の車はOBD-IIという規格に対応しており、エンジンのセンサー情報や排出ガスのデータを読み取り、問題があればコードとして記録します。車検ではこのコードを読み取り、未解決の不具合がないか、排ガスが基準を満たしているかをチェックします。オーナーとして知っておくと役立つのは、OBDスキャナーを使って自宅で事前チェックをする方法と、検査場で求められる情報の準備です。具体的には、車台番号や登録情報、最近の故障歴、警告ランプが点灯していないか、排気ガスが適正かをすべて確認しておくと安心です。自動車整備工場やカー用品店ではOBD読み取りサービスを利用でき、エンジンの不具合コードを確認して修理が必要かどうかを判断できます。車検時にはCO/HC/NOxなど排ガスの基準値をクリアすることが求められ、それにOBD情報が関わる場合があります。OBDとは何かを理解することは、車の健康を保つ第一歩であり、無駄なトラブルや不合格を避ける助けになります。
- 歯車 obd とは
- 歯車とOBDは、車の仕組みを理解するうえで基礎となる用語です。歯車とは車の変速機の中で噛み合う歯のついた部品で、エンジンの力を車の速度や走り方に合わせて伝える役割を持っています。一方、OBDはOn-Board Diagnosticsの略で、車の状態を車載のコンピュータが診断して外部へ情報を出す仕組みです。現在の多くの車はOBD-IIという方式を採用しており、エンジンの不調、排出ガスの不適合、変速機のトラブルなどを故障コードとして読み取れるようになっています。OBDポートは通常、運転席の下あたりやダッシュボードの近くにあり、スマホのOBDスキャナーや専用機器を接続してコードを読み取ります。コードはP、C、B、Uなどの文字と数字で表され、どの部位に異常があるのかを示します。ここで覚えておきたいのは、歯車そのものを直接動かすのはOBDではなく、変速機の制御系(TCMやECU)です。つまりOBDは「今、車がどういう状態か」を知らせてくれる道具であり、歯車を操作する道具ではありません。これにより、車の状態を的確に把握し、適切な整備や点検を行う手がかりを得られます。
- 車の obd とは
- 車の obd とは、車に搭載されている診断システムのことです。OBDはOn-Board Diagnosticsの略で、エンジンの状態や排出ガスの状況を監視し、異常があれば車のコンピューターに情報を記録します。特に現在の車はOBD-IIという規格が主流で、1996年ごろ以降の多くの車に搭載されています。OBD-IIの大きな特徴は、車内の診断ポート(OBDポート)につなぐだけで、エンジンの故障コードやリアルタイムのデータを読み取れる点です。故障コードはP系・C系・B系・U系のように分類され、P系がエンジンや排出ガスの問題を表すことが多いです。たとえばP0300は不定期な点火異常、P0400は排気ガス再循環系の問題など、コードの意味は専門的な用語を少しずつ覚えると理解が深まります。実際の使い方は次のとおりです。OBD-IIポートは車の運転席の下付近やセンターコンソールの下あたりにあることが多く、車種により位置は異なります。スマホやタブレットとOBD-II対応のスキャナーをBluetoothやWi‑Fiで接続し、専用アプリを起動してコードを読み取ります。コードだけを見るのではなく、リアルタイムのデータ(エンジン回転数 RPM、車速、水温、排気温度など)も確認すると、故障の原因を絞りやすくなります。これを日常の点検に活かせば、急な故障を未然に防ぐきっかけになります。注意点として、自己診断結果で過度に確信しないこと、分からない場合は整備士に相談することが大切です。OBDは車の状態を手軽に知るための有力な道具ですが、正しく使うことが重要です。
obdの同意語
- OBD
- 車両の故障診断機能を指す略称で、車載診断システム全体の総称として使われます。ECUからデータを取得し、故障コードを読み取るための仕組みです。
- On-Board Diagnostics
- OBDの英語名称。車載の診断機能を指す同義語として使われます。
- OBD-II
- OBDの第二世代規格。排出ガス規制への対応とデータ項目の標準化により、現在の車の多くで採用されています。
- OBD-II規格
- OBD-IIという規格自体を指す表現。車両間でデータ形式が統一された規格のこと。
- 車載診断
- 日本語での呼称。車両に搭載された故障診断機能の総称。OBDとほぼ同義で使われます。
- 車載診断システム
- 車両本体に組み込まれた診断機能の集合体。故障コードの生成・表示・記録を担います。
- OBDポート
- OBD用の接続端子。診断機器(スキャナー)を車に接続してデータを取得する場所です。
- 診断ポート
- 車両の診断用ポートの総称。OBDポートと同義に使われることもありますが、別の規格のポートを指す場合もあります。
- オンボード診断
- カタカナ表記の日本語表現。OBDの同義語として用いられることがあります。
obdの対義語・反対語
- オフボード診断
- 車の外部機器を使って診断を行う方法。OBDは車載システムを用いる診断の対極として位置づけられることが多いです。
- 外部診断
- 車両の外部ツールやサービスを使って行う診断。車内に依存しない診断のジャンルを指します。
- 手動診断
- 人が直接、観察・点検・測定を行う診断方法。OBDは自動でデータを取得するのに対し、手動診断は人の作業が中心です。
- 非OBD診断
- OBD規格に必ずしも準拠しない診断方法・デバイス。OBDの範囲外でデータを取得する場合に用いられます。
- オフライン診断
- インターネット接続なしで完結する診断。オンライン診断と対比して使われることがあります。
- 車外測定
- 車の外部で計測・診断を行う方法。特定の診断機器を車体の外に置いてデータを取得します。
- 非自動診断
- 自動化されず、人の手で完結する診断。自動診断(OBD)と対照的です。
- 従来型診断
- 昔ながらの整備方法に基づく診断。OBDの高度なデジタルデータ分析と対比されることがあります。
obdの共起語
- OBD
- 車載診断の総称。車両の状態を検知・記録し、故障の有無や排出ガス関連の情報を提供する機能全体を指します。
- OBD-II
- 第二世代のOBD規格。1996年以降の乗用車で標準化され、故障コード(DTC)の読み取り、ライブデータの取得、準備状況モニターの確認などをサポートします。
- OBD-I
- 第一世代のOBD規格。地域や車種で仕様が異なり、普及度は低めです。
- OBDポート
- 車両のOBD診断機器を接続する入口となる16ピンのコネクタ。
- OBD-IIポート
- OBD-II規格に対応した車両の診断ポート。診断機器が接続してデータを読み出します。
- OBDスキャナー
- 故障コードの読み取りとデータ表示を行う診断ツール。初心者にも使いやすい機種が多いです。
- OBDアダプター
- OBDポートとスマホやPCを接続するアダプター。Bluetooth・USB・Wi‑Fiタイプが主流です。
- ELM327
- 人気のOBDアダプターの型番。Bluetooth/USBで接続し、複数のアプリと連携します。
- コードリーダー
- DTCを読み取る基本的な診断機器。初心者向けの入門ツールとして利用されます。
- DTC
- Diagnostic Trouble Codeの略。車両の故障原因をコードとして表します。
- Pコード
- パワートレイン関連の故障コード。エンジン・排気・変速機の異常を示すことが多いです。
- MIL
- Malfunction Indicator Lampの略。チェックエンジンランプとして知られ、故障ありを示します。
- チェックエンジンランプ
- 別名MIL。車両のエンジン系に異常がある場合に点灯する警告灯です。
- ECU
- Engine Control Unitの略。エンジンや車両の多くの機能を制御する車載コンピューターです。
- ECM
- Engine Control Moduleの略。ECUと同義で使われることが多い車載コンピューターの一種。
- CANバス
- Controller Area Networkの略。車両内のECU同士がデータをやり取りする通信バスです。
- CAN
- CANバスの略。車両内の通信規格のことを指します。
- J1979
- OBD-IIの代表的な通信規格。一部の機器がこの規格でデータを取得します。
- ISO 9141
- 古いOBD接続規格。初期の車両で使われていた通信規格のひとつです。
- ISO 14230 / KWP2000
- OBDの別規格。KWP2000は読み取り方式のひとつとして用いられます。
- PID
- Parameter IDの略。車両センサーの値を取得する際の指標となる項目です。
- ライブデータ
- リアルタイムで車両のセンサーデータを取得して表示します。
- データストリーム
- 車両から連続的に送られるデータの流れ。ライブデータと同義に使われます。
- フリーズフレーム
- 故障発生時の車両状態を保存した静止データ。原因を特定するのに役立ちます。
- レディネスモニター
- 排出ガス関連のモニターが準備完了しているかを示す指標。検査に影響します。
- 排出ガス検査
- OBDデータを用いて排出ガスの規制適合性を確認する検査です。
- 16ピンコネクタ
- OBD-II車両で使われる標準の16ピンコネクタ。診断機器を接続します。
- eOBD
- 欧州向けのOBD-II仕様の別名。欧州車で広く使われます。
- OBDアプリ
- スマホやタブレットでOBDデータを表示・解析するアプリケーションです。
- DIY診断
- 自分で車の診断・整備を行うこと。学習や節約に役立ちます。
obdの関連用語
- OBD
- On-Board Diagnostics(車両の自己診断機能の総称)。エンジンや排出ガス系の状態を常時監視し、異常を検知すると警告灯を点灯させます。
- OBD-II
- 第二世代のOBD規格。1990年代後半以降の車両に標準採用され、16ピンコネクタ、統一された診断コード(DTC)とデータ項目(PID)、複数の通信プロトコルを含みます。
- OBD-I
- 第一世代のOBD規格。メーカーごとに仕様が異なり、標準化が不十分でした。
- OBDポート
- 車両の診断機器を接続する入口。OBD-II車はダッシュボード下などにある16ピンのコネクタを使用します。
- OBD-IIコネクタ (J1962準拠)
- OBD-II規格の16ピンコネクタで、車両と診断機器を物理的に接続する部品です。
- DTC / 診断トラブルコード
- 故障の原因を示すコード。P、B、C、Uの4つのカテゴリに分かれ、故障箇所を特定します。
- Pコード / パワートレイン系コード
- 動力系の問題を示すDTCのカテゴリ。エンジンや排気系の異常を表します。
- Bコード / ボディ系コード
- 車体部品の故障を示すカテゴリのDTCです。
- Cコード / シャシ系コード
- 車両の機械部品(サスペンション、ブレーキ等)の故障を示します。
- Uコード / ネットワーク系コード
- 車載ネットワークの通信不良を示すDTCです。
- MIL / チェックエンジンライト
- 故障があると点灯する警告灯。ダッシュボードに表示されます。
- フリーズフレームデータ
- 故障発生時のセンサー値などを時系列で記録した静止データ。診断時の参考になります。
- 準備状態モニター
- 排出ガス関連の監視機能が準備完了かを示す指標。走行後の再学習で変化します。
- 排出ガス関連モニター
- 触媒、EVAP、O2センサーなど、排出基準適合の監視項目です。
- パラメータID (PID)
- OBD-IIで読み取れるデータ項目の識別子。センサー値やエンジン状態を表します。
- Mode 01 / 現在値取得モード
- 現在の車両データを取得するモード。PIDを指定して読み出します。
- モード(01-09, 0A など)
- OBD-IIのコマンドセット。現在値取得、診断結果取得、データクリアなどを指示します。
- CANバス / CANプロトコル
- 車両内部の高速通信路で、OBD-IIの主要なデータ伝送手段です。
- ISO 15765-4 CAN / CAN-OBD-II
- CANベースのOBD-II通信規格。広く採用されています。
- ISO 9141-2
- 古いOBD-IIプロトコルの一つ。低速通信に用いられます。
- ISO 14230-4 (KWP2000)
- Keyword Protocol 2000。低速・高速度の通信モードを提供する規格です。
- SAE J1850 PWM / VPW
- 古い車両で使われるOBD-IIの通信規格。PWMとVPWの2系統があります。
- SAE J1979
- OBD-IIデータの標準仕様。PIDの定義やモードの仕様を提供します。
- OBDアダプター / OBDスキャナー
- 車両の診断データを取得するための工具。USB/Bluetooth/Wi-Fi接続があります。
- ELM327
- OBD-IIアダプターの代表的なチップ/製品名。スマホやPCと接続してデータを読み取ります。
- ECU / エンジンコントロールユニット
- 車両の各センサーとアクチュエータを統括して制御する主要な電子制御ユニットです。
obdのおすすめ参考サイト
- OBD検査とは?(ユーザー向け) - 物流・自動車 - 国土交通省
- OBD点検とは?具体的な内容や料金・OBD車検との違いについて解説
- OBDコネクターとは何か? 5分で完全理解! - Carly
- OBD検査とは?(ユーザー向け) - 物流・自動車 - 国土交通省