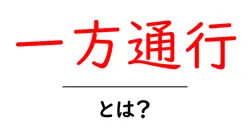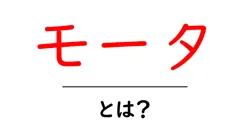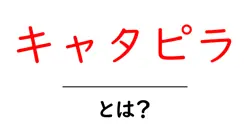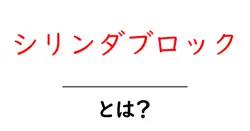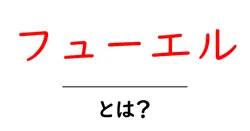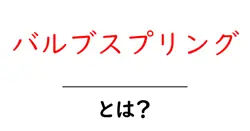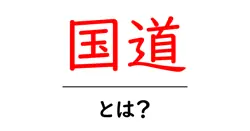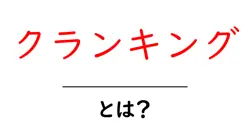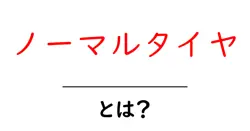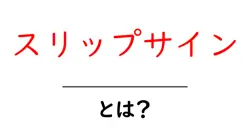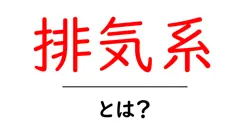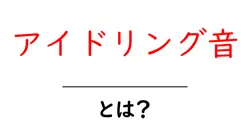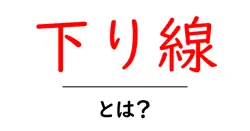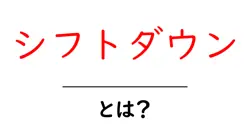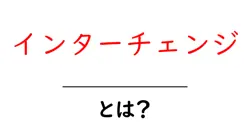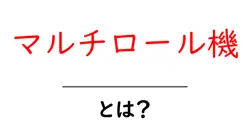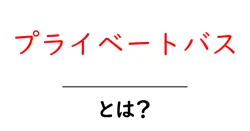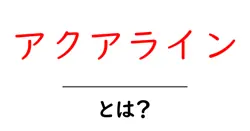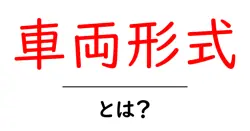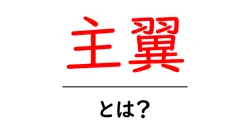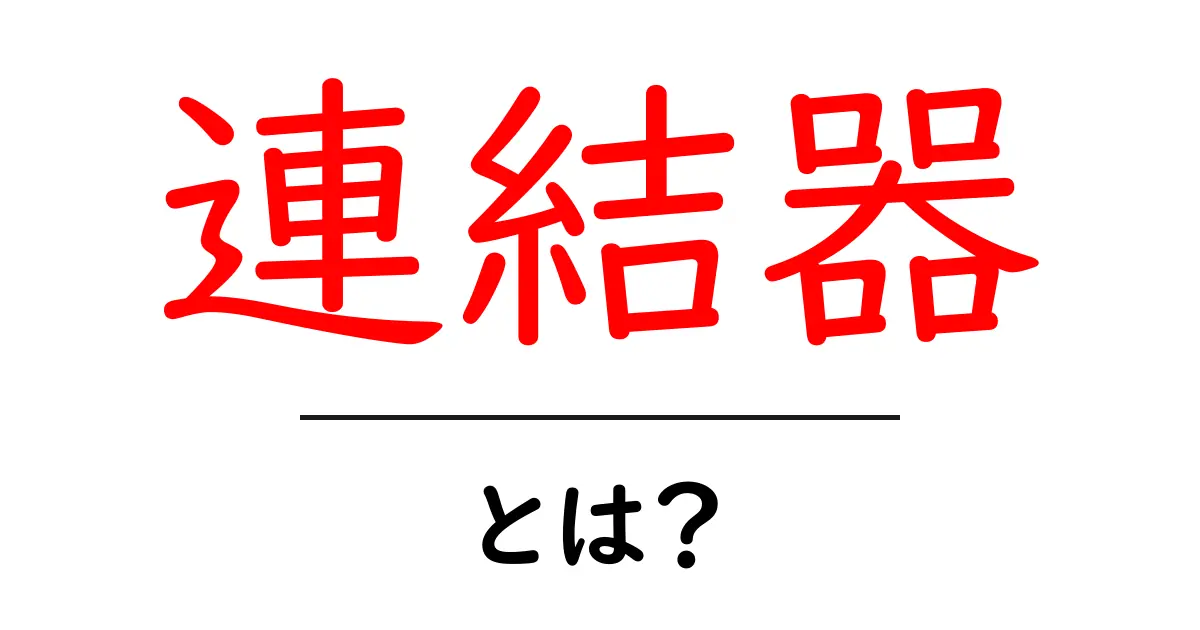

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
連結器とは何かを知ろう
連結器は列車の車両と車両をつなぐ装置です。貨物列車や旅客列車の長い列を滑らかにつなぎ、安全に走らせるための重要な部品です。連結器がしっかりはまっていれば、走行中に車両がぶつかったり外れたりするリスクを減らすことができます。
自動連結器とねじ連結の違い
現在日本の多くの鉄道で使われているのは 自動連結器 です。自動連結器 は車両同士が近づくと自動的に接続され、ブレーキ管 や 空気管 などの管路も同時につながります。これによりブレーキの効きや列車の連結機能がそろい、安全に運転できます。ねじを使って手作業で結ぶ ねじ連結 は古い車両や特別な場合に見られる方式です。
仕組みと役割
連結器の基本的な役割は 車両同士の連結 を成立させ、走行時の衝撃を吸収することです。衝撃緩和装置 が内部にあり、列車が進むときの振動を減らします。自動連結器では接続時に ブレーキ管 や 空気管 が同時に連結されるため、ブレーキの連携が途切れません。
実際の運用と安全
連結作業を行うときは、車両の状態や天候を確認してから行います。作業員は指示に従い、接続後に安全を再確認します。安全第一を守ることが大切です。
歴史と背景
以前は ねじ連結 が主流で、車両間の連結は危険を伴い作業も大変でした。 自動連結器 が普及することで、列車の接続作業は軽減され、効率も向上しました。日本の新幹線では高い安全性と衝撃緩和性を実現するために特別な仕様が使われています。
表で見る連結器の種類
| 種類 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| 自動連結器 | 自動で接続。ブレーキ管空気管も同時接続 | 現代の鉄道の標準形式 |
| ねじ連結 | 手作業でねじを回して接続 | 古い車両や特殊車両 |
まとめ
結局のところ 連結器 は列車を動かすうえで欠かせない部品です。日常では気にする機会が少ないですが、安全でスムーズな運転のためにしっかり機能しています。
連結器の同意語
- カプラー
- 列車の車両を連結するための装置。鉄道分野で最も一般的な同義語。
- 自動連結器
- 車両同士を自動的に結合する連結装置。手作業を必要とせず接続できるタイプを指す。
- 密着連結器
- Knuckle couplingの日本語表現。車両の前部を高い精度で密着させて連結する方式の器具。
- 密着式連結器
- 密着連結器の別表現。車両間の密接な接続を担う器具。
- 連結装置
- 複数の部品をつないで機能を作り出す装置の総称。鉄道以外の機械分野でも使われる。
- 連結機
- 連結を行う機械・装置の意味で使われる語。鉄道・機械業界で用いられることがある。
- 結合器
- 物と物を結合するための器具・部品。連結の意味を表す別表現。
- 結合具
- 結合するための部品・器具。連結の意味合いを含む語。
- 連結具
- 連結を目的とした部品・器具の総称。適用範囲が広い表現。
- コネクタ
- 電気・信号の接続部品。電子機器の連結を表すときの語。
- コネクター
- コネクタの別表現。電気的接続部品を指す語として用いられる。
- 接続部
- 機械・電子の接続部位を指す総称。連結の機能を表す言い回しとして使われる。
- 連結部品
- 連結を担う部品の総称。構成要素としての意味を明示する語。
連結器の対義語・反対語
- 分離器
- 連結器の機能である“結合する”行為の反対、すなわち二つの部品を分離・離れるようにする装置・仕組み。主な用途は、車両間の連結を解いて独立させること。
- 解結器
- 連結を解除するための装置。結びつきを解く機能を持ち、連結器の反対動作を担う器具や機構。
- 切断装置
- 連結を物理的に断ち切る装置。接続状態を強制的に分断することを目的とする機械。
- 離脱機
- 連結された部品・車両を分離させるための機構。結合を解放し、離脱を容易にする役割を持つ。
- 非連結状態
- 連結されていない状態を指す概念。連結器の反対の状態として用いられる表現。
連結器の共起語
- 自動連結器
- 車両同士を自動で結合できる装置。走行中の衝撃を伝え、車両間の連結を自動で行います。
- 密着連結器
- 車両同士の距離をできるだけ詰めて連結するタイプの連結器。安定性を高め、空気圧系の作動範囲を短くします。
- 手動連結
- 人の手で接続・切断を行う連結方法。自動連結が使えない場合に用いられます。
- カプラー
- 英語の coupler の日本語表記。機械・車両の連結部品を総称して指すことが多い語です。
- カプラー方式
- 連結器の設計・取り付け方の呼称。車両間の結合の仕方の違いを表します。
- 連結部
- 車両同士をつなぐ部位の総称。連結器が取り付く場所を指します。
- 連結機構
- 連結を実現する仕組み全体。リンクやジョイント、クランクなどを含みます。
- ジョイント
- 部品同士をつなぐ可動部。関節の意味で、力を伝える役割を持ちます。
- リンク機構
- 連結を実現する部品の集合。リンクとジョイントで動作を伝えます。
- 連結棒
- 連結のための棒状部品。長さや強度が設計上重要です。
- 連結金具
- 金属製の連結用部品。ネジやピンで固定して結合します。
- 車両連結
- 鉄道車両同士をつなぐ行為・部品群。安全性と運行性に直結します。
- 貨車連結
- 貨車同士を結ぶ連結装置の総称。
- 機関車連結
- 機関車と客車・貨車をつなぐ連結装置。
- 列車連結
- 列車を連続して連結するための結合作業・部品群。
- 連結器整備
- 連結器の点検・整備作業。適切な機能を維持するための保守活動です。
- 連結器交換
- 故障や経年劣化により連結器を新しいものに交換すること。安全性のためのメンテナンス作業です。
- 自動密着連結
- 自動連結器の一種で、車両間の距離を詰めて結合する方式です。
- 連結器本体
- 連結器の中心となる主要部品。車両を強く結合させる役割があります。
- 連結受け
- 連結器を受け止める車体側の部品。連結時の位置決めを担います。
連結器の関連用語
- 連結器
- 2つ以上の車体や部品を機械的につなぎ合わせ、動力・荷重・情報の伝達を可能にする部品。鉄道車両では車両間の連結を担い、安全に走行・分離を実現します。
- 自動連結器
- 車両を接触させると自動で嵌合・解放される機構。人手を介さず連結できるため安全性と作業の効率が向上します。
- 半自動連結器
- 自動である程度嵌合しますが、最終的な固定には作業者の操作が必要となる連結方式。安全性と作業性のバランスを取ります。
- 手動連結器
- 作業者が物理的に連結・分離を行う伝統的な連結方式。現在は限定的な用途で用いられることが多いです。
- ねじ式連結器
- ねじを回して接続する昔の連結方式。現在は主流ではなく、歴史的・教育目的で言及されることが多いです。
- 密着式連結器
- 車両間の間隙を極力減らす設計の連結方式で、緩衝器と組み合わせて衝撃を吸収し安定した連結を実現します。
- 電気連結器
- 車両間で電気信号や電力を伝えるコネクタ。照明・ブレーキ系・通信などの配線を車両間で共通化します。
- 緩衝器
- 連結器と組み合わせて使用され、車両間の衝撃を吸収する部品。連結の安全性を高めます。
- 連結作業
- 連結・解結の作業全般を指す用語。半自動・手動連結器では作業員が実際の連結作業を行う場面があります。
- 連結器点検・保守
- 連結器の機能と安全性を維持するための定期点検・整備・部品交換。兆候の早期発見が重要です。
- 規格・仕様
- 地域や車両種別で異なる連結器の規格・仕様。適合・置換の際には規格の違いを確認します。