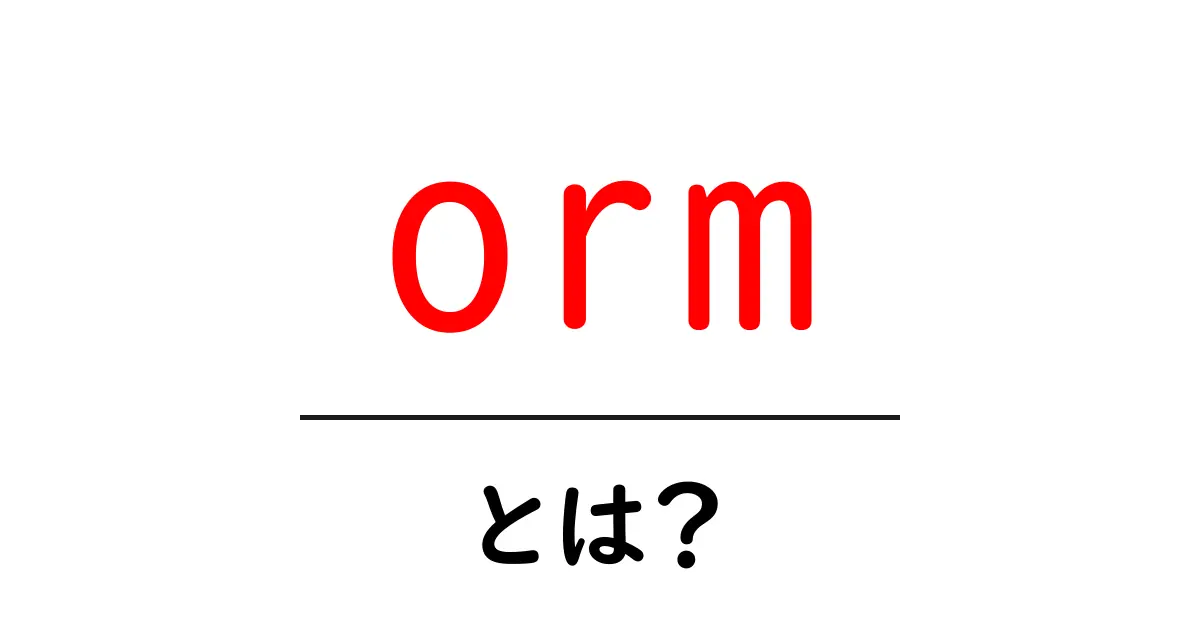

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
orm・とは?
ORM とは、オブジェクト指向プログラミングの『オブジェクト』と、データベースの『テーブル』を結びつけるしくみです。データ操作をコードのオブジェクトとして扱えるようにすることで、SQLを直接書かずともデータを扱えるようになります。
どうして必要なのか
多くのアプリはデータベースを使います。SQL言語で直接データを操作すると、プログラムの処理とデータの整合性を保つための boilerplate が増え、コードが長く複雑になります。ORMを使うと、オブジェクトの操作がそのままデータベース操作に変換され、コードが読みやすく、保守が楽になります。
仕組みの基本
ORMは「エンティティ」と「テーブル」の対応関係を作り、エンティティの属性がテーブルのカラムに対応します。データの取得は「クエリ」を作成して行い、ORMが内部でSQLを組み立ててデータベースに送ります。結果の行はエンティティのオブジェクトとして返されます。
よく使われる用語
エンティティ(Entity):プログラム内のオブジェクト。データベースのテーブルに対応します。
テーブル/カラム:データベース側の構造。エンティティの属性はカラムに対応します。
セッション/コンテキスト:データベースとのやり取りをまとめて管理する仕組みです。
遅延読み込み(Lazy loading)と先読み(Eager loading):データの読み込みタイミングの違い。適切な使い分けがパフォーマンスに影響します。
実践的な使い方のイメージ
ここでは言語を限定せず、 ORM の基本的な考え方をイメージで理解します。実際には Python、Ruby、Java など言語ごとに異なるフレームワークを使います。
例のイメージ
class User(Base):
__tablename__ = 'users'
id = Column(Integer, primary_key=True)
name = Column(String)
age = Column(Integer)
session.add(User(name='太郎', age=20))
session.commit()
このように書くと、データベースには直接 SQL を書かなくても新しいレコードが追加されます。
メリットと注意点
ORMを使うと、日常的なデータ操作が直感的なコードで書け、保守性が高まります。開発速度の向上や、データベース操作の再利用性が高まる点が大きなメリットです。
一方で注意点もあります。複雑なクエリや大量データの処理では、ORMが生成するSQLが最適でない場合があります。N+1問題と呼ばれる過剰なデンマーク読み込みのリスクや、抽象化のレベルが高すぎてデバッグが難しくなることもあります。パフォーマンスを保つためには、適切な設計と、場合によっては生のSQLを併用する判断が必要です。
まとめ
ormはプログラムとデータベースの橋渡し役として強力なツールです。初心者はまずエンティティとテーブルの対応、セッション管理、基本的なCRUD操作を理解しましょう。慣れてきたら遅延読み込みと先読みの使い分け、複雑なクエリの最適化、最終的にはパフォーマンスの監視とチューニングへと進むと良いでしょう。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| エンティティ | プログラム内のオブジェクトとデータベースのテーブルの対応 |
| テーブル/カラム | データベース側の構造。エンティティの属性はカラムに対応します。 |
| セッション | データベースとのやり取りを管理する窓口 |
| 遅延読み込み | 必要になったときにデータを取得する方法 |
| 先読み | あらかじめデータを取得しておく方法 |
ormの関連サジェスト解説
- orm とは sql
- orm とは sql の仕組みを学ぶ最初の一歩として覚えると良いキーワードです。ORM はオブジェクト・リレーショナル・マッピングの略で、プログラムの世界のオブジェクトと、データベースの表を結びつけてくれる仕組みです。SQL はデータベースに指示を出す言語で、データの検索・追加・更新・削除を行います。ORM はこれらの作業を、あなたが書くクラスやメソッドの形に置き換え、直接 SQL を書かなくてもデータを扱えるようにしてくれます。例えば、User というクラスを作り、ユーザーを追加したいときに user = User(name='たろう')、user.save() と書くと、背後で ORM が INSERT 文を作ってデータベースに入れてくれます。ユーザーを探すときは User.find(id) のような命令で、ORM が SELECT を実行します。こうした仕組みのおかげで、開発者はデータの操作を直感的に書ける一方、複雑な SQL の細かい部分を毎回覚える必要が減ります。メリットは、学習コストが低く、コードが読みやすく、データベースを変えるときの移植性が高いことです。データの型や関係をクラスで表現できるため、設計が分かりやすくなります。一方のデメリットとしては、ORM が生成する SQL が必ずしも最適にならないことがあり、思ったより遅いと感じる場合もあります。特に大きなデータ量を扱うときや複雑な結合をするときは、手動で書く SQL の方が速い場合があります。さらに N+1 問題と呼ばれる、関連データを何度も別々の検索で取りに行ってしまう現象が起きることがあり、パフォーマンスの落とし穴になります。これを防ぐには、必要な時だけ eager loading に切り替え、生成される SQL をこまめに確認して最適化する練習が必要です。結論として、初心者には ORM から始めるのがおすすめですが、本当に難しい局面では SQL の手動書きも学んでおくと安心です。目的に合わせて ORM と SQL の使い分けを覚えることが、良いデータベース活用のコツです。
- orm マッパー とは
- orm マッパー とは、データベースの表とプログラミングのクラスをつなぐ仕組みのことです。ORM は Object-Relational Mapping の頭文字をとった言葉で、データベースの「テーブル」と、プログラムの「オブジェクト」を対応づけてくれます。つまり、テーブルの行をそのままプログラムの道具となる「オブジェクト」として扱え、データを読み書きするときに SQL を自分で書く必要がなくなります。典型的な使い方は、まずテーブルに対応する「モデル」や「エンティティ」と呼ばれるクラスを作ります。クラスの属性がテーブルのカラムに対応し、レコードはそのクラスのインスタンスとして表れます。新しいデータを作るときはオブジェクトを作り、保存メソッドを呼ぶとデータベースに挿入されます。データを取り出すときは、条件を指定してオブジェクトを検索するメソッドを使います。複雑な結合や関係も、 ORM が面倒な SQL を隠してくれるので、初心者でもコードを読みやすく保てます。関係の例として、ある人が複数の住所を持つ「一対多」、ある本が複数の著者と関係する「多対多」などがあります。これらの関係は、 ORM が適切なテーブル設計を振り分け、必要な SQL を自動で作ってくれます。注意点として、 ORM は便利ですが、時には生成される SQL が最適でないこともあります。パフォーマンスを意識する場面では、時々自分で SQL を書いたり、 ORM の設定を調整したりする必要があります。学習を進めると Laravel の Eloquent、Python の SQLAlchemy や Django ORM、Java の Hibernate、Node.js の Sequelize など、さまざまな ORM があることがわかります。これらを使うと、データベースの操作が「コードの一部」として自然に感じられ、開発の効率が高まります。
- prisma orm とは
- prisma orm とは、データベースとプログラムをつなぐ道具の一つです。ORM とは Object-Relational Mapping の略で、プログラムの中のオブジェクトとデータベースの表を対応させて操作するしくみのことです。Prisma は Node.js や TypeScript との相性が良い人気のツールで、Prisma を使うとデータベースの操作が直感的で安全になります。Prisma には主に三つの要素があります。Prisma Client はデータベースを操作するための API で、findMany や create、update、delete などのメソッドを型付きで提供します。Prisma Migrate はデータベースの設計をコードとして管理する機能で、 schema.prisma という設計図を作成・変更してデータベースの構造を同期します。Prisma Studio はデータをブラウザの画面で見たり編集したりできるツールです。使い方の流れは次のとおりです。まず npm i prisma @prisma/client を実行してツールを導入します。次に npx prisma init で設定ファイルの雛形を作成し、schema.prisma にデータベースの種類と接続先 URL、そしてモデルを定義します。たとえば User というモデルを作る場合、名前やメールアドレスの列を定義します。続いて npx prisma migrate dev でデータベースに実際の表を作り、npx prisma generate で Prisma Client を生成します。これでコードの中から prisma を用いてデータを読み書きできるようになります。具体的には prisma.user.findMany() で全員を取得したり、prisma.user.create({ data: { name: 'たろう', email: 'taro@example.com' } }) のように新しいレコードを作成したり、条件を指定して更新や削除を行うことができます。初心者にとってのメリットは、SQL をそのまま書く代わりに安全で型付きの操作ができ、データベースの変更をツールで管理できる点です。ただし、学習の初期コストや小さなプロジェクトでは ORM が過剰になる場合もある点に留意しましょう。
- eloquent orm とは
- eloquent orm とは、PHP の人気フレームワーク Laravel とセットで使われるデータベース操作の仕組みです。ORM は Object-Relational Mapping の略で、データベースのテーブルとプログラムのクラスを対応づけ、SQL を直接書かなくてもデータの取得・更新ができるようにします。Eloquent ではモデルと呼ばれるクラスを中心に動き、たとえば users テーブルに対応する User クラスを作ると、User::all() で全データを取り出したり、$user->name のようにカラムを参照したりできます。さらに hasMany、belongsTo、hasOne などのリレーションを使うと、関連するデータを結びつけて簡単に取得できます。例えば Article と Author の関係を定義しておけば、Article::find(1)->author で著者情報を確認できます。この仕組みの良さは、複雑な SQL を覚えなくても直感的なメソッド名でデータ操作ができる点です。初心者でも読みやすいコードになり、データの挿入・更新・削除が自然に行えるため、データベースの学習を始めやすいでしょう。もちろん注意点もあります。ORM は便利ですが、非常に複雑な集計や最適化が必要な場面では、生の SQL を直接書くほうが速いことがあります。その場合は ORM の力を活かしつつ、必要な部分だけ SQL を使う使い分けが大切です。また Laravel のエコシステムと相性が良いので、学んでおくと今後の開発に役立ちます。このように eloquent orm とは、データベース操作を簡単にしてくれるツールで、モデルとリレーションを使って直感的なコードを書くことを目指しています。初めて触れる人でも基本のモデル作成とリレーション定義を覚えれば、CRUD やデータの結合処理をすぐに試すことができます。
- django orm とは
- django orm とは、データベースとPythonのオブジェクトをつなぐ仕組みのことです。DjangoのORMは、モデルと呼ばれるPythonクラスをテーブルに対応づけ、データの取得・保存・更新・削除を Python の記述だけで行えるようにします。初心者向けにいうと、テーブルの形をモデルで表現し、SQLを直接書かずにデータを操作できる道具です。最初はモデルを作成し、makemigrationsとmigrateを使ってデータベースの準備をします。次にArticleなどのモデルを使って、articles = Article.objects.all() と書けば全件を取り出せ、 Article.objects.filter(title__contains='Django') のように条件をつけて絞り込むこともできます。新しいデータを作るには article = Article(title='サンプル', content='Django ORMの説明') を作って save() を呼ぶだけです。既存のデータは article.title = '新しいタイトル' のように変更して save()、削除は article.delete() で行えます。 ORMは複数のテーブルを結合して取り出すクエリもサポートしており、リレーションを表すForeignKeyやManyToManyFieldを使ってデータ同士を結びつけられます。強みはSQLを書く手間を減らし、データベースを変えても影響を受けにくい点、そしてSQLインジェクションの心配を減らす安全なクエリの生成です。ただしORMは万能ではなく、複雑な集計や性能を極限まで求める場合は時に生SQLや追加のメソッドを使う必要があります。学習のコツは、モデル設計を最初によく考え、 migrations の流れを理解し、日常のデータ操作は ORM で完結させる練習を繰り返すことです。
- laravel orm とは
- laravel orm とは、データベースを操作する時に、テーブルの行をそのままデータのまとまりとして扱える仕組みのことです。ORMは、オブジェクトとデータベースの表をつなぐ橋の役割をします。Laravel には Eloquent という ORM があり、モデルと呼ばれるクラスを作ると、対応するデータベースのテーブルとやり取りしやすくなります。例えば User クラスを作ると、users テーブルの行を User オブジェクトとして操作できます。基本的な使い方はとてもシンプルです。すべてを取得するには User::all()、特定の人を探すには User::find(1) や User::where('email', 'a@example.com')->first()、新しく追加するには $user = new User(); $user->name = たろう; $user->save(); のように書きます。データの挿入・更新・削除も、これらのメソッドで自然な英語風の記述に近づけられます。Eloquent ではテーブル名がクラス名の単数形・小文字から推測され、複数形の名前が使われます。リレーション機能を使えば、1人のユーザーが複数の記事を持つ hasMany、記事が1人のユーザーに属する belongsTo など、関連データの取得も直感的にできます。ORM を使う利点は、SQL を毎回書く必要が少なく、コードの見通しがよく、バリデーションやセキュリティのベストプラクティスを守りやすい点です。一方で過度に抽象化されると思い通りに動かないこともあるので、基本を覚えつつ必要なときだけ使うと良いでしょう。
- drizzle orm とは
- drizzle orm とは、データベースを使うときの操作を、SQLを直接書く代わりにプログラミングの型安全な方法で行える道具です。主に TypeScript/JavaScript の環境で使われ、PostgreSQL・MySQL・SQLite などのデータベースと連携します。 ORM(Object-Relational Mapping)という考え方は、データベースの表(テーブル)を「オブジェクト」の形で扱えるようにすること。Drizzle はこの考え方を、軽量で速く、開発者が間違いを起こしにくいように設計されています。特徴として、まず型安全性が高い点が挙げられます。テーブルの定義を TypeScript の型としてデプロイでき、クエリの結果の型も自動で推論されます。これにより、コードを書くときにコンパイル時にエラーを見つけやすく、データの型の間違いを減らせます。次に、クエリの構文はドラッグ&ドロップのように直感的に書け、SQL を直接組むよりも読みやすくなります。もちろん最終的にデータベースへ送られるのは SQL ですので、高速でデータの絞り込み・結合・集計が可能です。使い方の基本は以下の通りです。1) npm で drizzle-orm をインストール。2) テーブルを定義するスキーマを作成。3) モデルを使ってデータの読み書きを行う。4) マイグレーションでデータベースの構造を管理。初めての人でも、公式の例を見ながら進められます。設定ファイルや接続の準備が必要ですが、チュートリアルで順を追って進めると理解しやすくなります。
- python orm とは
- Python orm とは、Python のプログラムとデータベースのテーブルをつなぐ仕組みです。ORM は英語の Object-Relational Mapping の略で、日本語では「オブジェクト関係マッピング」と呼ばれます。難しく聞こえるかもしれませんが、要は「データを Python のオブジェクトのように扱えるようにする仕組み」です。データベースには表と呼ばれる行の集まりがあり、各行はデータを持っています。ORM を使うと、テーブルの行をそのまま Python のオブジェクトとして扱え、データの追加・取り出し・更新・削除をコードで直感的に行えます。これにより SQL を直接書く必要が減り、プログラム全体の読みやすさと保守性が高まります。モデルと呼ばれる設計を作ると、テーブルの構造を Python のクラスとして定義できます。クラスの属性がテーブルのカラムに対応し、データを保存するときは新しいオブジェクトを作って保存します。検索は条件を絞って行い、結果は再びオブジェクトの集合として返されることが多いです。こうした仕組みのおかげで、SQL をぜんぶ覚えなくてもデータ操作が直感的になります。使い方の流れはだいたい次のとおりです。まずデータベースを決め、ORM のライブラリをインストールします。次にモデルを定義し、データベースとつながる設定をします。あとはオブジェクトを作って保存したり、条件を指定して取り出したり、更新したり、削除したりします。Python の文法に慣れていれば、データ操作の基本を学びやすく、SQL の知識が少なくても扱えるようになります。代表的な例として Django の ORM、SQLAlchemy、Peewee などがあります。用途や好みによって選ぶとよいです。
- hibernate orm とは
- hibernate orm とは、データベースの仕組みとプログラムの世界をつなぐしくみです。ORMはObject-Relational Mappingの略で、プログラミングのオブジェクトとデータベースの表を結びつける考え方を指します。HibernateはそのORMを実現する有名なライブラリのひとつで、Javaのクラスをデータベースのテーブルに自動的に対応づけてくれます。これを使うと、SQL文を自分で全部書く必要が少なくなり、データの保存・検索・更新・削除といった基本操作が直感的になります。以下が基本のポイントです。エンティティはデータベースの行に対応するJavaのクラスです。クラスには@Entityや@Table、@Id、@Columnといった注釈を付けて、どのテーブルに対応するか、どの列が主キーかを示します。次にセッション(Session)とセッションファクトリ(SessionFactory)、トランザクション(Transaction)があります。セッションはデータベースとの窓口、トランザクションはデータの変更をまとめて扱う仕組みです。設定はhb.xmlのようなファイルやJPA形式、またはSpringなどのフレームワークと組み合わせて行います。使い方の流れは、まずエンティティを作って設定を整え、SessionFactoryを作成します。実行時にはSessionを開いてトランザクションを開始します。エンティティを保存する場合は保存、取得する場合は検索、更新や削除もそれぞれの操作を使います。Hibernateは遅延読み込みやキャッシュといった機能も持ち、データの取り扱いを効率化してくれます。ただし学習コストがあり、複雑なクエリのパフォーマンス管理には注意が必要です。初心者が押さえるべきポイントは、どのテーブルとクラスが対応するかの理解、保存・取得など基本操作の流れ、設定の仕組みをつかむことです。
ormの同意語
- オブジェクトリレーショナルマッピング
- データベースのテーブルとプログラムのオブジェクトを対応づけ、SQLを直接書かずにオブジェクト指向の操作でデータベースを扱えるようにする設計パターン。
- オブジェクト関係マッピング
- オブジェクトとリレーショナルデータベースの間の対応づけを行う技術。テーブルの行をオブジェクトに、列を属性に自動で割り当てる仕組み。
- オブジェクトリレーショナル・データマッピング
- オブジェクトとデータベース上のデータを結びつけるデータマッピングの一種。ORMの別表現として使われることがある。
- リレーショナルオブジェクトマッピング
- リレーショナルデータベースとオブジェクト指向データの間を結びつける設計概念。
- オブジェクト-リレーショナル・マッピング
- 同義のハイフン付き表現。オブジェクトとリレーショナルデータベース間の対応づけを指す。
- RDBオブジェクトマッピング
- リレーショナルデータベース(RDB)とオブジェクトを結びつける技術。SQLを直接書く代わりにオブジェクト操作でデータを扱えるようにする。
- データベースオブジェクトマッピング
- データベースのテーブルとプログラムのオブジェクトを対応づける技術。
ormの対義語・反対語
- 生SQL(直接SQLでのデータ操作)
- ORMを介さず、SQLを直接書いてデータベースとやり取りする方法。抽象化が少なく、クエリの挙動を開発者が直接管理します。
- 手動マッピング(オブジェクトとテーブルの手動対応)
- オブジェクトとデータベースのレコードの対応づけを自動化せず、手作業で変換を行う方法。
- SQL中心のデータアクセス設計
- データ操作をSQLクエリの作成と実行を最優先に置く設計思想。 ORMの抽象化を使わないアプローチです。
- 低レベルデータベース操作
- ORMの提供する抽象化を捨て、低レベルAPIを使って直接データベースを操作する方法。
- オブジェクト-テーブル自動マッピングを使わない設計
- 自動マッピング機能を使わず、全て手動でマッピングを実装する構成。
- 自動化機能の欠如
- クエリ生成・クラス定義の自動化、スキーマ同期などの自動機能がない状態。
- SQL文をコード内に直書きする設計
- SQLをソースコード内に文字列として直書きし、動的な生成をほとんど使わない設計。
ormの共起語
- Object-Relational Mapping
- オブジェクト指向の世界とリレーショナルデータベースの世界をつなぐ設計パターン。クラスとテーブル、オブジェクトの属性とカラムを対応づけ、SQLを直接書かずにデータを扱えるようにします。
- Code-first
- コードからモデル(エンティティ)を定義し、ORMがそれに合わせてデータベースのスキーマを作成・更新するアプローチ。
- Database-first
- 既存のデータベースを元にORMのモデルを生成・同期させるアプローチ。
- データベース
- データを長期的に保存・管理するシステム。ORMはここに対してオブジェクトを介して操作します。
- テーブル
- データを格納する基本単位。ORMではエンティティとテーブルを対応づけます。
- カラム
- テーブルの列。ORMでは属性とカラムを対応づけます。
- 主キー
- 各レコードを一意に識別する列。ORMはエンティティのIDとして扱います。
- 外部キー
- 他のテーブルの主キーを参照する列。ORMのリレーション設定で使われます。
- インデックス
- 検索を速くするための仕組み。ORMのクエリのパフォーマンスに影響します。
- エンティティ
- データベースのテーブルに対応するクラス/オブジェクト。ORMの中心です。
- エンティティリレーション
- エンティティ間の関連(1対1、1対多、N対N)を表現します。
- マッピング
- クラスとテーブル、属性とカラムを結びつける設定のこと。
- アノテーション
- クラスや属性に付ける注釈。ORMではマッピング情報を表す場合があります。
- XMLマッピング
- XMLファイルでマッピング情報を記述する方式。
- YAMLマッピング
- YAML形式でマッピング情報を記述する方式。
- データマッピング
- オブジェクトとデータベースのデータを結びつける役割を指します。
- Data Mapper
- データベースとオブジェクトの間の橋渡しを担当する設計パターン。
- Active Record
- オブジェクト自身がデータベース操作を担うパターン。ORMの実装形式の一つ。
- リポジトリ
- データアクセスを抽象化する層。ORMでよく用いられます。
- ユニットオブワーク
- 複数の操作を一つの単位としてまとめ、トランザクションを運用する考え方。
- マイグレーション
- データベースのスキーマ変更を追跡・適用する仕組み。
- スキーマ
- データベースの構造定義。ORMはこの構造とマッピングを保ちます。
- トランザクション
- データの整合性を保つための処理単位。原子性を保証します。
- N+1問題
- ORMを使うと起きやすい、データ取得時に過剰なクエリが発生する問題。
- 遅延ロード
- 関連データを必要になった時点で読み込む戦略。
- 遅延読み込み
- 遅延ロードと同義。必要な時にだけデータを取得します。
- イーガーロード
- 関連データを事前に取得して、クエリ回数を減らす戦略。
- フェッチ
- データを取得する操作全般。ORMではフェッチ戦略を設定します。
- クエリビルダー
- SQL文を組み立てるツール。ORMの内部機構として使われることがあります。
- SQL生成
- ORMが内部的にSQLを自動生成して実行します。
- SQL
- 関係データベースに対してデータ操作を行う言語。ORMは内部でSQLを発行します。
- SQLログ
- 発行されたSQLを記録する機能。デバッグ・パフォーマンス分析に役立ちます。
- ロギング
- クエリや操作の履歴を記録する機能。
- パフォーマンス
- ORM導入時の速度・資源の最適化に関する話題。
- キャッシュ
- 取得済みデータを再利用することで読み込みを速くする仕組み。
- Hibernate
- Java向けの代表的なORMライブラリ。
- SQLAlchemy
- Python向けの高度なORM兼データベースツール。
- Entity Framework
- .NET向けの主要ORMライブラリ。
- Django ORM
- PythonのDjangoフレームワークに組み込まれたORM。
- Sequelize
- Node.js向けの人気ORM。
- TypeORM
- TypeScript向けのORM。
- Doctrine
- PHP向けのORMライブラリ。
- GORM
- Go言語向けのORMライブラリ。
- Codeファースト
- コード(エンティティ)側から先にモデルを作り、それに合わせてデータベースを作るアプローチ。
- Databaseファースト
- 既存のデータベースを前提に、ORMのモデルを生成・適合させるアプローチ。
ormの関連用語
- ORM
- オブジェクトリレーショナルマッピングの略。プログラムのクラスとデータベースのテーブルを対応づけ、SQLを直接書かずにデータ操作を行えるようにする仕組み/ライブラリ。
- オブジェクトリレーショナルマッピング
- 同義語。データベースとオブジェクトを橋渡しする技術で、エンティティとテーブルを対応づける。
- エンティティ
- ORMで扱うデータの基本単位。現実世界の概念を表すオブジェクトで、テーブルの行に対応する。
- エンティティクラス
- エンティティをコード上で表すクラス。テーブルの列を属性として持つことが多い。
- テーブル
- データを行と列で組織するデータベースの基本構造。ORMではエンティティと対応づけられる。
- カラム
- テーブルの列。エンティティの属性に対応する。
- 主キー
- テーブルの各行を一意に識別する列。一般的にはIDなどの値が使われる。
- 外部キー
- 別のテーブルの主キーを参照する列。テーブル間のリレーションを作る。
- レコード
- テーブルの1行。エンティティのデータ1つに対応する。
- データベース
- データを長期的に保存する仕組み。ORMはデータベースとアプリの間をつなぐ。
- マッピング
- オブジェクトとデータベースの構造を対応づけること。
- Data Mapperパターン
- データアクセスを専用のマッパーが担い、エンティティは純粋なオブジェクトのまま保つ設計パターン。
- Active Recordパターン
- エンティティ自体がデータベース操作を担う設計パターン。Railsの実装が代表例。
- リポジトリパターン
- データアクセスの抽象化を提供する設計パターン。データ取得の実装を隠蔽する。
- DAO
- データアクセスオブジェクト。データベース操作(取得・保存・更新・削除)を1つのオブジェクトに集約。
- クエリビルダ
- プログラムでクエリを組み立てるためのDSL。SQLを直接書かずにデータを取得できる。
- SQL
- データベースと対話する標準的な言語。SELECT、INSERTなどの命令を使う。
- 遅延読み込み
- 関連データを実際に必要になるまで取得を遅らせる手法。
- 即時読み込み(エager loading)
- 関連データを初回のクエリと同時に取得する手法。N+1問題を避けるのに有効。
- N+1問題
- あるデータを取得するたびに関連データを別クエリで取得してしまい、パフォーマンスが低下する現象。
- プリフェッチ/プリロード
- 関連データを先に取得しておく戦略。遅延を抑える。
- Join
- 複数のテーブルを結合してデータを一度に取得するSQLの機能。ORMでも内部的に活用される。
- 1対多 (One-to-Many)
- 一方のエンティティが複数の関連エンティティを持つ関係。
- 多対多 (Many-to-Many)
- 二つのエンティティが多くの関連を持つ関係。中間テーブルで実装することが多い。
- 1対1 (One-to-One)
- 二つのエンティティが一対一で対応する関係。
- ユニットオブワーク(Unit of Work)
- 複数の変更を1つの単位としてまとめ、コミット時にデータベースへ適用する設計パターン。
- セッション
- ORMでのデータの追跡・整合性を保つ作業単位。トラッキングとキャッシュの役割もある。
- マイグレーション
- データベーススキーマの変更をコードとして扱い、履歴管理と自動適用を行う仕組み。
- Code-first
- エンティティ定義からデータベーススキーマを生成するアプローチ。
- Database-first
- 既存データベースからエンティティを生成するアプローチ。
- アノテーション/属性
- クラスやフィールドにマッピング情報を付与する注釈。設定をコード上で宣言する。
- Fluent API
- メソッドチェーンでマッピングやクエリを記述する設定方法。
- Hibernate
- Java向けの代表的なORM。Data Mapperパターンを採用。
- Entity Framework
- .NET向けのORM。Code-first/Database-firstをサポート。
- SQLAlchemy
- Python向けのORM。Data Mapperパターンを実装。
- Django ORM
- PythonのDjangoフレームワークに組み込まれたORM。
- Eloquent
- PHPのLaravel向け ORM。Active Record風のAPI。
- Doctrine
- PHP向けの ORM。Data Mapperパターンを採用。
- Rails ActiveRecord
- Ruby on RailsのデフォルトORM。Active Recordパターンを実装。
ormのおすすめ参考サイト
- SQLAlchemyの基本的な使い方 #Python - Qiita
- ORMとは?|SQLAlchemy 概要と基本の使い方 - Zenn
- ORMとは #初学者向け - Qiita
- ORMとは?仕組みやメリットなどをわかりやすく解説 - IT用語一覧
- ORMとは?初心者でもわかるオブジェクト関係マッピングの基礎知識



















