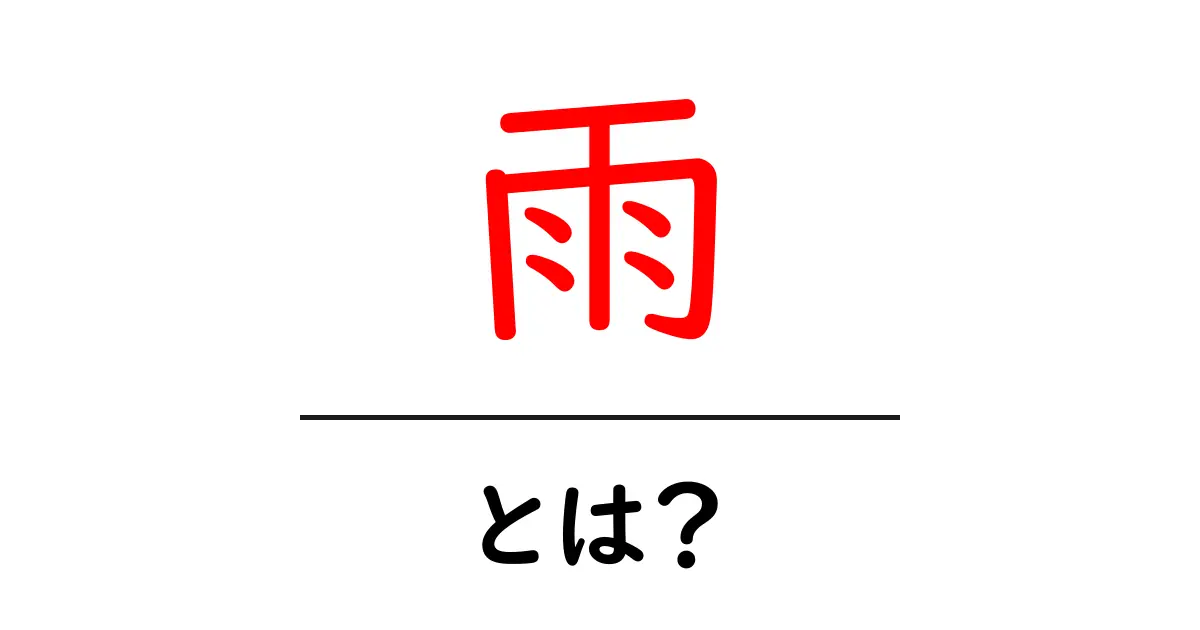

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
雨は私たちが普段からよく目にする現象ですが、実はとても大切な自然のサイクルの一部です。この記事では「雨とは何か」について、やさしく丁寧に説明します。中学生でもわかる自然な日本語で、雨のしくみや種類、生活への影響、雨を楽しむヒントまで紹介します。
雨とは何か
雨とは地球の大気中で水蒸気が冷えて水滴になり、それが雲の中で大きくなって落ちてくる現象です。水は蒸発して上昇し、雲の中で水滴が結びついて重くなると、地表へと降り出します。この流れを「水循環」といい、地球の水が絶えず動く仕組みです。雨は私たちの生活に欠かせない水の供給です。水循環の中で雨は地球を潤し、作物を育て、川を作ります。
雨の発生のしくみ
空は温かい空気が上がる「上昇気流」と冷たい空気が降りる「下降気流」が繰り返されます。上昇する空気は冷えて、水蒸気が水滴に変わります。水滴が雲の中で結びつき、一定の大きさになると重さに耐えきれず降りてきます。このとき地上に落ちる水滴の大きさや速さによって、雨の強さは変わります。降水の量や降り方を見れば、天気をある程度予測することができます。
雨の種類と特徴
実は雨にもいろいろな「種類」があります。代表的なものを挙げると、小雨、霧雨、雨、大雨、雷雨などです。以下の表は、それぞれの特徴をまとめたものです。
雨と生活
雨は私たちの生活にも大きな影響を与えます。雨の日は傘やレインコートが必要で、道路は濡れて滑りやすくなります。一方で雨は水を地面へ染み込ませ、川や井戸を満たします。長い期間降り続く雨は農作物を育て、森の生態系を支えます。雨を理解することは、天気予報を読んだり、災害に備えたりする力にもつながります。
雨を観察するコツ
雨を観察するには、まず天気予報をチェックします。降水量の単位はミリメートル(mm)で表され、1時間あたりの降水量が多いほど強い雨といえます。空の様子を観察することも大切です。雲が低く垂れこめていたら、突然強い雨が降ることがあります。地面が濡れ始めるのを見ると、今雨が降っているサインを確認できます。雨音を聞くのも雨を感じる良い方法です。
まとめ
雨とは水蒸気が冷えて水滴となり、雲の中で大きくなって落ちてくる自然現象です。水循環の一部として地球を潤し、私たちの生活や作物を支えます。雨には「小雨」「霧雨」「雨」「大雨」「雷雨」などさまざまな種類があり、それぞれ降り方や影響が違います。生活の中では、雨具を用意し、天気予報をチェックして安全に過ごすことが大切です。自然を知るための一歩として、雨のしくみや観察のコツを押さえておくと、天気の変化にも強くなれます。
雨の関連サジェスト解説
- 飴 とは
- 飴とは、砂糖を主な材料にして作るお菓子の一種です。硬い飴、柔らかい飴、のど飴など形や用途はさまざまですが、どれも糖を中心にした甘い食べ物です。飴は水、砂糖、糖液、時には麦芽糖やコーンシロップを加え、煮詰めてから冷まして固めます。温度が高いほど硬く、低いと柔らかくなる性質があり、180℃前後の温度管理が作る際のポイントです。日本では「飴」という言葉がキャンディの代わりとして使われ、昔から駄菓子屋やお祭りで親しまれてきました。次に、作り方の基本を説明します: 鍋に砂糖と水を入れて中火で温め、溶けた砂糖をさらに煮詰めて糖度を高めます。温度計があると便利で、硬い飴なら約150~160℃、カラメル状なら130℃前後が目安です。柔らかい飴やのど飴は糖度を低めにして作られます。仕上がりを良くするためには火を止める前に少し冷まし、香りづけや色づけのための食用色素や香料を加えることもあります。種類の話も大切です。硬い「硬飴」は長く口の中で味わえるタイプ、棒状のものや丸い玉状のもの、形も様々です。喉の痛みを和らげる効果をうたった「のど飴」も多く、薬局やドラッグストアで見かけます。味は果実味、ミント、ミルク、キャラメル風など多様です。注意点としては、糖分が多いので虫歯になりやすいこと、小さなお子さんには誤嚥の危険があることです。保存は湿気を避け、涼しく乾燥した場所で密閉容器に入れておくと良いです。最後に、飴は歴史的には中国や東南アジアなどから伝わり、日本でも独自の菓子文化として発展しました。現代では家庭で手作りする人もいますが、市販の飴は原材料と製法が多様で、選び方次第で健康にも味にも影響します。以上が「飴 とは」の基本です。
- ame とは
- ame とは、ひとつの日本語の読み方であり、文脈によって意味が変わる言葉です。この記事では、中学生にも分かるように、代表的な意味と使い方を分かりやすく紹介します。まず大切な点は、ame には主に二つの漢字の意味があることです。雨と飴です。漢字が違えば全く別の意味になりますが、読み方は同じで、漢字が違うだけです。1. 雨(あめ)という意味: 天気の話をするときに使います。例: 今日は雨が降っています。傘を持っていこう。雨という漢字は雨粒や空模様、天気予報とよく登場します。雨は自然現象の名前なので、日常会話やニュース、学校の授業でも頻繁に出てきます。2. 飴(あめ)という意味: 甘いお菓子のことです。飴を舐める、飴玉などと言います。言い換えればスイーツの一つで、子どもにも人気があります。飴は食べ物のカテゴリで、味・結晶性・包装などの話題にも登場します。3. どう使い分けるか: 文脈が重要です。天気や空の話なら漢字が雨、傘や雷、湿度の話題なら雨の意味と判断します。お菓子や甘味の話題なら飴の意味です。会話だけでなく、文章を書くときは漢字を使い分けると伝わりやすくなります。4. 読み方のコツ: 同じ読み方でも漢字が違うだけで意味が変わることを覚えましょう。学校の宿題で雨と飴の違いを練習すると、自然と使い分けが身につきます。初めて ame とは を調べる人は、文脈を先にチェックし、必要に応じて漢字の意味を確認すると良いです。結論: ame とは、場面に応じて雨または飴を意味する、読み方が同じだけの日本語の単語です。読み方・意味・使い分けを理解すると、自然な日本語表現が身につきます。
- 亜目 とは
- 亜目 とは、生物分類を細かく分けるときに用いられる階級のひとつです。大きな「目(オーダー)」の下に存在し、同じ目の中の生物を、進化の近さや共通の特徴でさらにまとめる役割を持ちます。つまり、亜目は目の中で「どのグループが似ているか」を示すための中間的な区分です。亜目を用いるかどうかは分類群ごとの慣例に依存しており、すべての生物群で使われているわけではありません。実際の分類では、亜目は複数の科を含むことが多く、同じ亜目に属する生物は形態や生態の点で似ていることがしばしば観察されます。ただし、現代の分類学は遺伝子データの影響を受けて見直されることが増え、あるグループでは亜目の境界が変わったり、亜目自体が使われなくなったりすることもあります。学習のコツとしては、最初に「目の名前」+「亜目」という形の語を探して覚えると、辞書や図鑑で該当箇所を見つけやすくなります。生物の世界にはさまざまな階層があり、亜目の理解は分類のしくみを理解する第一歩になります。
- アメ とは
- アメ とは、文脈によって意味が変わる日本語の言葉です。代表的には次の三つの意味があります。まず飴(あめ)です。飴は砂糖を固めて作るお菓子のことで、学校の行事やお祭り、友だちとのおやつとしてよく登場します。飴は色や形がさまざまで、棒付きの棒飴や粒状の飴、ミント味や果物味など多様です。次に雨です。雨は空から落ちてくる水滴のことを指します。日常会話では「雨が降るね」と言います。漢字の『雨』を使うのが一般的で、読み方は「あめ」です。カタカナの「アメ」が使われる場面は漫画的表現や強調のとき、または略されて文書内で見かけることがありますが、正式にはかな表現の「雨」または漢字の「雨」を使います。最後にアメリカの略称として使われることもあります。ニュースや会話の中で「アメ」と短く言われる場合、アメリカを指していることがありますが、正式な場では「アメリカ」と書くのが基本です。これら三つの意味を混同しないよう、文脈をよく読むことが大切です。初心者が覚えるコツは、前後の言葉から意味を推測することと、漢字の有無で意味を分けることです。例えば『飴を買う』ならお菓子の意味、『雨が降る』なら天気の意味、『アメリカの経済』なら国名の略称です。
- 1mm の 雨 とは
- 1mm の雨 とは、雨が地表に蓄えられる水の深さが1ミリメートルになることを指します。雨量は深さとして表され、降った雨の総量を測る指標です。1平方メートルの地面に均等に雨が降ると、約1リットルの水が集まります。この関係は雨量計でも使われます。雨量計は降った雨を集めて筒の深さをミリメートル単位で読み取ります。これが私たちが天気予報で見る「〇mmの雨」につながっています。1mm の雨はとても小さく感じるかもしれませんが、植物には十分な水分を与えることがあります。乾燥した日には地表を湿らせ、地温を下げる効果もあります。雨の強さや降る時間と組み合わせると、実際の影響は大きく変わります。例えば、1時間に1mm程度の雨なら歩道は湿る程度ですが、短時間に強く降れば水たまりができることもあります。つまり、1mmは“少ない”と感じるかもしれませんが、状況次第で意味が変わります。天気予報では日ごとの降水量をmmで表します。出かけるときには、雨量を見て傘の要・不要を判断します。初心者の方は雨量計の読み方を覚えると、1mm の意味が理解しやすくなります。雨が続くときは地面の排水性や植物の水やりの目安にも役立ちます。
- 洗車 雨 とは
- 洗車 雨 とは、雨の日に車を洗うことや、雨が洗車の効果にどう影響するのかを指す言葉です。多くの人は「雨が降っているときに洗えばきれいになるのでは」と考えがちですが、現実にはそう簡単ではありません。雨水はきれいではなく、空気中のほこりや花粉、酸性の成分などを少しだけ車体に運んできます。さらに雨が乾くと、水滴に含まれたミネラル分が白い水あか(ウォータースポット)になって残ることが多いです。そのため、雨の日に洗車をしても、仕上がりが雨の日より悪く感じることがあります。こうした点を踏まえ、雨の日の洗車は「待つ」か「短時間の軽い洗浄」にとどめ、完全な洗車は晴れた日を選ぶのが基本です。雨の強さにもよりますが、雨水は表面の大きな汚れを落としてくれることもある一方、虫・油分・頑固な汚れは水だけでは落ちません。車用の洗剤と柔らかいスポンジ、そして二度洗いの方法を使うと、雨に左右されずにきれいを保ちやすくなります。洗車をするときは日陰を選び、直射日光を避け、洗車後はマイクロファイバータオルで丁寧に拭き上げ、水分を残さないことが大切です。結局のところ、洗車 雨 とは「雨を使って洗う可能性がある行為の一部」であり、基本的には晴れた日が安全で確実な選択です。急な雨の日には短時間のすすぎだけにして、汚れの再付着を防ぐコーティング効果を高めるための下地づくりを心がけましょう。
- 3mm の 雨 とは
- 3mm の 雨 とは、雨が地面に落ちて集まった水の深さを表す単位です。雨量は通常、1平方メートルの面積に落ちた水の深さをミリメートル(mm)で測ります。つまり、3mmの雨とは1平方メートルあたり地面に3ミリメートルの水がたまることを意味します。1 mmは1リットル、1平方メートルあたりの深さが1 mmなら1リットルの水がたまる計算です。したがって3mmなら1平方メートルあたり3リットル、水が広がる量がよくわかります。雨を測る道具には家庭用の雨量計や気象台の機器があります。雨水の深さを読み取ってmmで表す仕組みです。雨の降り方は「総量」と「時間あたりの強さ」に分けて考えることもあります。3mmが1日を通じて降ったのか、1時間に降ったのかで印象が変わります。日常生活では、3mmの雨は薄い小雨に近く、傘を使えば体がほとんど濡れずに過ごせることも多いです。道路が濡れる程度なら家の周りの地面だけがぬれて、蒸し暑い日には蒸気のように見えることもあります。もし3mmの雨が1時間続くと、水は1平方メートルあたり3リットル集まります。広い場所では大量の水には見えませんが、長く降り続くと地面がぬれたり、水たまりができたりします。雨量は天気予報にも使われ、傘を持つべきかどうかの判断材料になります。測定には風の影響や、雨量計の設置位置の影響など、誤差を生む要因もあるため、正確さには注意が必要です。このように「3mm の 雨 とは」は、雨の深さを示す基本的な単位であり、天気の様子を理解するための第一歩です。
- 100mm の 雨 とは
- このページでは「100mm の 雨 とは」というキーワードについて、雨の量の意味をやさしく解説します。まず、雨の量は「ミリメートル(mm)」で測られ、1mmの降水量は地面の上に置くと1平方メートルあたり約1リットルの水が降ったのと同じ量になります。つまり100mmの雨は、1平方メートルあたり約100リットルの水が積もった状態を指します。実はこの数字は、降った水の総量を示し、降った場所の面積に対しての量を表します。雨量は気象庁の観測点で測定され、雨量計に水がたまる量を読み取ります。100mmの雨が降ると川の水位が上がったり道路が冠水したりすることがあります。降水の強さは「1時間あたり何ミリか」も重要で、例えば1時間に20mm以上なら激しい雨と呼ばれます。さらに、同じ100mmでも短時間に降るか長時間にわたって降るかで影響は大きく変わります。計画や備えを考えるとき、総降水量だけでなく降水の速さ(降り方)も大切です。最後に、雨の日の生活では、傘やカッパの用意だけでなく、排水溝のつまりや道路の状況にも注意しましょう。初心者にも理解しやすいように、数字の意味と生活への影響を結びつけて説明しました。
- しぐれ 雨 とは
- しぐれ 雨 とは、短い時間で終わる細かな雨のことを指す日本語の表現です。時雨と書くこともあり、秋や初冬に多く見られ、俳句や小説で季節の移ろいを表すときに使われます。雨粒は小さく、空気がひんやりしているときに降りやすく、地面に落ちてもすぐには濡れず、しっとりとした湿り気が残るのが特徴です。降り方は場所によって違い、静かに降ることもあれば、ぱっと降ってすぐ止むこともあります。雨雲が通り過ぎると日が差すことが多く、秋の涼しい風とともに風景に情緒を添えます。しぐれ 雨 とは季節の表現で、夏の雨とは違い蒸し暑さは少ないのが普通です。霧雨よりはっきりした降り方をすることが多く、雨粒の動きを感じられることもありますが、空は曇りがちで心地よい陰影を作ります。日常生活では急な傘の出番になることは少ないものの、外出時には空模様を見て降りそうなら傘を持つと安心です。文学や詩の中では、しぐれ 雨 は季節の情感を伝える象徴として使われ、しとしと降る雨音や風の匂いを想像させます。
雨の同意語
- 降雨
- 雨が降る現象。気象用語としての正式な表現です。
- 降水
- 大気中の水分が地表へ落ちる現象の総称。雨だけでなく雪や霰なども含むことがあります。
- 雨天
- 雨が降っている天候の状態。日常会話では“雨の日”とほぼ同じ意味で使われます。
- 霧雨
- 細かな雨粒が霧のように降る状態。英語の drizzle に近いニュアンスです。
- 小雨
- 降水量が比較的軽い雨。空を薄く濡らす程度の雨を指します。
- 中雨
- 降水量が中程度の雨。通勤・通学時の天気の中間カテゴリです。
- 大雨
- 非常に強い降水。道路が濡れ、視界が悪くなることがあります。
- 土砂降り
- 激しく降る大雨。短時間で大量の雨が降る状態を指します。
- にわか雨
- 突然降り出し、短時間で止む雨。天気の急変を表す言い方です。
- 天気雨
- 晴れている時に降る雨のこと。現象として珍しいケースです。
- 豪雨
- 大量の降水。広い範囲で強い雨が降る状態を指します。
- 驟雨
- 急に降り出す激しい雨。勢いが特徴の表現です。
- 霪雨
- 長時間にわたる雨の詩的・古風な表現。現代語ではやや文語的です。
- 雨滴
- 空から落ちてくる水滴のこと。具体的な描写に使われます。
- 雨水
- 雨として降って地表に溜まる水。資源や排水の話題で使われることがあります。
- 長雨
- 雨が長く降り続く状態。梅雨時や長雨シーズンの表現として使われます。
雨の対義語・反対語
- 晴れ
- 雨が降っていない状態で、空が明るく晴れ渡っている状態のこと。日差しがあり、空が青く見えることが多い。
- 快晴
- 雲がほとんどなく、日差しが強い最高レベルの晴れの状態。天気予報で“最高に良い晴れ”と表現されることが多い。
- 晴天
- 雨が降らず、日が照っている晴れの日の一般的な表現。穏やかな晴れの状態を指す。
- 日照り
- 長期間にわたり降雨がなく、地面や作物が乾燥している状態。雨の反対の天気・気象現象として使われる表現。
- 乾燥
- 湿度が低く、空気や地面が乾燥している状態。雨不足や乾燥した季節を示すこともある。
- 降水なし
- 一定期間において降水(雨・雪など)が発生しない状態。
- 雲のない空
- 空に雲がほとんどない、すっきりとした晴れ模様を表す表現。
- 青空
- 雲が少なく、太陽が輝く明るい空の象徴的な表現。晴れのイメージを端的に伝える言い方。
- 日光が強い
- 日差しが強く降り注ぐ晴天の状態。外出時の暑さ・日差しの強さを表すときに使われる言葉。
- 太陽が出る
- 空に太陽が現れ、雨が降っていない状態を示す表現。晴れへ転じる直感的な表現として使われる。
雨の共起語
- 傘
- 雨を避ける基本の道具。折りたたみ傘や長傘など、雨の日の必須アイテム。
- 雨具
- 雨をしのぐための道具の総称。傘・レインコート・長靴などを含む。
- レインコート
- 雨を防ぐための防水性の上着。体を濡らさずに移動できる。
- 合羽
- 雨天時に体を濡らさないための長めの防水衣。昔ながらの呼称。
- 長靴
- 雨の日に水たまりでも靴の中へ水が入りにくい靴。防水性が高い。
- レインブーツ
- 長靴の別称。雨天の足元を守る靴。
- 雨天
- 雨が降っている天気の状態。日常の天気表現として頻出。
- 梅雨
- 日本特有の長期間続く雨の季節。湿度と降水量が増える時期。
- 雨雲
- 雨を降らせる雲のこと。天気の判断材料になる語。
- 霧雨
- 細かな雨粒が空気中で揺れる、さわやかな雨の表現。降水量は少なめ。
- にわか雨
- 突然降り出す短時間の雨。急な降雨対策が必要。
- 土砂降り
- 非常に激しく降る雨。視界が悪くなることも多い。
- 大雨
- 大量の雨が降る状態。洪水や浸水のリスクと関連。
- 雷雨
- 雷を伴う雨天。雷鳴と光がセットで語られることが多い。
- 雷
- 空で起こる放電現象。雷鳴を伴うことが一般的。
- 豪雨
- 降水量が非常に多い雨。災害級の降水量を指す。
- 降水量
- 一定期間に降った雨の総量を表す指標。統計や予報で使用。
- 降水確率
- 天気予報で降水がある確率の表現。予報の精度と関連。
- 雨音
- 雨が屋根や窓に当たる音のこと。聴覚的なイメージ素材。
- 水滴
- 雨が落ちるときの小さな水の粒。写真や表現で頻出。
- 雨滴
- 雨の滴の粒を指す語。水滴とほぼ同義で使用される場面が多い。
- 雨水
- 降った雨の水。生活や環境の話題にも登場。
- 水たまり
- 地面にできる小さな水の集まり。子どもの遊び場や避難経路の話題にも。
- 濡れる
- 雨で衣服や髪が湿ってしまう状態。動詞として頻繁に使われる。
- 濡らす
- 物を雨で湿らせる動作。対象物を水分で包む意味。
- 雨宿り
- 雨を避けるために屋根の下などで過ごすこと。場所の紹介にも使われる。
- 雨ざらし
- 外にさらされて濡れ続ける状態。耐水性の話題で登場。
- 雨具店
- 雨具を専門に扱う店。商品選びの場面でよく出てくる語。
- 傘立て
- 玄関や施設にある、傘を収納する場所。日常会話や店舗案内で使われる。
- 雨量計
- 降水量を測る計器。気象や防災の話題で登場。
- 低気圧
- 低気圧が近づくと雨が降りやすくなる天気要因。気象用語としてよく使われる。
- 天気予報
- 明日や今後の降水を知らせる情報。SEOでもよく使われる語。
- 洗濯物
- 雨の日は乾きにくいため部屋干しなどの工夫が話題になる。
雨の関連用語
- 降水量
- 一定期間に地表へ降った降水の量。単位は mm。
- 降水確率
- 一定時間内に降水がある見込みの割合。予報の指標として使われます。
- 雨量計
- 降水量を測る測定機器。地上に設置して降水の量を記録します。
- 小雨
- 弱い降水。地表が軽く濡れる程度の雨。
- 霧雨
- 非常に細かな雨粒が連続して降る降水の形。
- 中雨
- 降水の強さが中くらいの降雨。
- 大雨
- 比較的強い降雨。視界が悪化しやすい程度。
- 豪雨
- 非常に強い降雨。短時間で大量の雨量になることが多い。
- にわか雨
- 突然降り出す短時間の雨。
- 夕立
- 夏に多い雷雨。急に強い雨と雷を伴うことが多い。
- 雷雨
- 雷を伴う強い雨。局地的に発生することが多い。
- 雨雲
- 降水を生み出す雲の総称。
- 積乱雲
- 雷を伴い強い雨を降らせる発達した雲。
- 層状降水帯
- 広い範囲にわたり長時間降水をもたらす帯状の降水域。
- 梅雨
- 日本の春~初夏に長く続く雨の季節。
- 雨季
- 地域ごとに雨が多い季節の総称。
- 秋雨
- 秋に長く降り続く雨のこと。
- 傘
- 雨を防ぐ道具。日常で最も一般的な雨対策のひとつ。
- レインコート
- 防水性の長い上着。雨から身を守る衣類。
- 長靴
- 雨天時の水たまりやぬかるみを避ける防水靴。
- 雨具
- 雨の日に使う衣類・小物の総称。傘・レインウェア・長靴などを含みます。
- 雨水利用
- 降った雨水を貯めて生活用水や庭水として使うこと。
- 雨漏り
- 屋根などから雨水が室内へ染み込む現象。
- 水害
- 大雨による被害全般の総称。
- 洪水
- 河川の氾濫や浸水による被害。
- 台風
- 熱帯低気圧が接近して大量の雨を降らせることがある現象。
- アメダス
- 気象庁の自動降水・降水量観測網。
- 雨男/雨女
- 雨が降る日と縁があるとされる人の俗称。
- 雨雲レーダー
- 降水の動きをリアルタイムで表示する観測技術・サービス。
- 雨の音
- 雨が屋根や窓を打つ音。情緒表現やリラックス要素として使われます。
- 雨粒径
- 降る雨粒の大きさの目安。
- 露点
- 空気が飽和して水蒸気が水滴に変わるときの温度。
- 相対湿度
- 空気中の水蒸気量を、同温度で最大湿度に対する割合で示す指標。
- 前線
- 暖かい空気と冷たい空気の境界で降水をもたらす区域。
- 低気圧
- 低気圧の中心部で上昇気流が生じ、降水を伴う天気系。



















