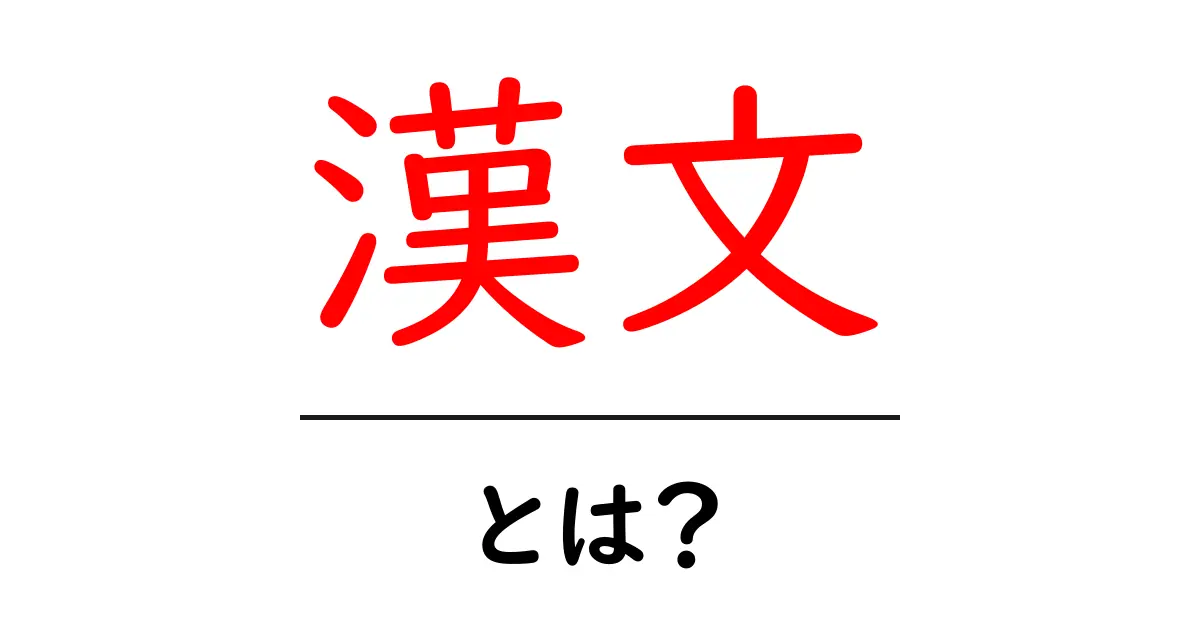

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
漢文・とは?初心者向けの解説
漢文とは、中国の古典文学を、日本語の語順で読み下す技法を指します。現代日本語の語順とは異なり、漢字そのものの意味だけでなく、返読点や訓点と呼ばれる読み方の工夫を使って解釈します。漢文は「中国の古典を日本語で読解する技法」という点が大きな特徴です。
漢文は、紀元前の中国の歴史書・儒教の経典・詩など、長い間日本の読み書き文化と深く結びついてきました。日本で学ぶときは、まず「漢字の意味」を追うよりも「どう読んで、日本語として意味を作るか」を意識します。
ここでは、初心者が押さえるべきポイントを紹介します。2つの基本を覚えると、漢文の読み方の全体像がつかめます。
漢文の基本的な特徴
・漢文は中国語の語順を基盤にしているため、日本語の語順とは異なる順序で文章が並ぶことがあります。実際には漢字の並びを日本語として理解する訓読の力が求められます。
・日本語の読み方として「訓点」や「返読」を使い、漢字の並びを日本語として理解します。訓点は昔の読みのヒントです。
訓読と返読の仕組み
訓読は、日本語の語順に合わせて漢字の意味を読み下す方法です。特に訓点がない古い漢文では、読み手が頭の中で日本語の語順に並べ替えます。
返読とは、漢文の語順を逆向きに読み換えて日本語の意味を取り出す技法です。例えば、漢文の語順「天地不仁、以萬物為芻狗」を日本語に読むとき、私たちは主語・動詞・目的語の関係を再構成します。
実践のコツ
初めて読む場合は、長い文を一気に読もうとせず、短い句から練習します。漢文の読み方を練習するときは、分かりやすい現代語訳と照らし合わせると理解が深まります。
学習の具体的ステップ
1) 基本用語を覚える。漢文・訓点・返読・注釈とは何かを把握する。
2) 短い例文を選んで、漢字の意味と読みを対応させる。
3) 訓点付きの原文と現代語訳を並べて読む。
4) 自分で短い文の読み下しを作成して、誰かに説明してみる。
例文と読み下しの演習
例文として有名な一句を使い、読み下しの練習をします。例: 「天行健、君子以自強不息」この句を日本語で読み下すと、「天は健に行き、君子は自らを強くし、息を絶えず」という意味になります。ここでは、主語・述語・補足語の順序を日本語として整理します。
学習リソースの活用
・辞書や解説書を活用する。漢文辞書は漢字ごとの意味だけでなく、訓読の読み方も併記しています。
・オンラインの練習問題や例文を繰り返し解く。
・学校の授業ノートや先生の解説を見直して、読み方のパターンを覚える。
おさえておきたい用語集
- 訓読 - 漢文の語順を日本語の語順に読み替える方法。
- 返読 - 漢文の語順を逆向きにして日本語の意味を取り出す読み方。
- 訓点 - 日本語の語順を示す補助記号。
まとめ
漢文は難しそうに見えますが、基本を押さえ、短い文から慎重に練習を積むことで徐々に読み方のコツがつかめてきます。訓読と返読の考え方を理解し、日本語として意味を組み立てる練習を続けてください。
最後に、漢文・とは?という問いに対して答えは「漢文は中国の古典を日本語で読むための伝統的な読み方と技法」です。学習を始めるなら、まず短い文から丁寧に扱い、意味の取り方と読み方の両方を同時に身につけましょう。
漢文の関連サジェスト解説
- 漢文 とは 意味
- 漢文とは、中国の古典文学を漢字だけで書いた文章のことです。日本ではこの漢文を「日本語で読むための古典」として学ぶことが多く、訓読という読み方の工夫を使って日本語に直して理解します。漢文は現代の日本語とは語順や文法が異なるため、ただ字面を読んでも意味が取りにくいことがあります。中国語の語順はおおむね中国語のままですが、日本語へ直すときは語の順序を日本語の自然な順序に並べ替え、意味を補う言葉を付け足すことが必要です。歴史的には、奈良・平安時代に中国の書物が日本にもたらされ、学問を身につけるための教材として漢文が広く用いられました。江戸時代には、儒学を中心に漢文の授業が盛んでした。現在も高校・大学の古典講義で扱われ、文学作品や歴史書の知識を深める手段として活用されています。読み方のコツとして、まず漢字の意味を辞書で確認し、文の意味を日本語の語順に整えることが基本です。現代語訳がついた教材を使って訓読を練習し、徐々に返り点や注釈付きの漢文にも挑戦していくとよいでしょう。初めは難しく感じても大丈夫。短い文章から始め、語順の違いと意味の取り方を丁寧に練習してください。
- 漢文 とは限らない
- 漢文 とは限らないという話は、漢字を使う文章を見たときによく出てくる誤解です。漢文は中国の古典文学を指す言葉で、日本では“漢文訓読”と呼ばれる読み方のルールを使って読むことが多いです。しかし、漢字を含む文章なら必ず漢文というわけではありません。現代の日本語の文章でも漢字が多く使われていますし、教科書に出てくる漢文風の表現は、実際には現代日本語で書かれていることもあります。漢文には通常、返り点と呼ばれる読み順を示す符号や注釈がつくことが多いですが、そうした特徴がない文章は漢文とは呼び難いです。漢文の基本は、中国語の語順を日本語の語順に合わせて読めるようにする工夫です。漢文訓読では、漢字の意味だけでなく、文の意味を日本語として自然にとらえるための読み方のルールを学びます。とはいえ、日本語で書かれたテキストの中にも漢文風の文章はありますが、それらが必ずしも漢文訓読の対象とは限りません。このキーワードを見かける場面としては、授業の説明中に“漢文 とは限らない”という注意が出ることがあります。つまり、漢字があるからといって中国の古い文だけを読んでいるわけではなく、日本語として読む工夫が必要だという意味です。学習のコツは、まずその文章が漢文訓読の対象かどうかを判断することです。次に、返り点や注釈があるかをチェックし、なぜその文が日本語として読めるのかを考える習慣をつけましょう。さらに、現代日本語の文章と漢文訓読の違いを比べると理解が深まります。最後に、“漢文 とは限らない”という視点を持つと、古典文学だけでなく現代の日本語の読み方も広がり、文章を読む力がつきます。
- 漢文 訓点 とは
- 漢文とは中国の古典文を日本で読むときの読み方の一つで、通常は漢字の並びがそのまま中国語の語順になるため、日本語として理解しにくいことがあります。そこで現れるのが訓点です。訓点とは、漢文の文章に添える記号や仮名のことで、日本語の語順や文法を読み手にわかりやすく示す役割を果たします。漢文は古代中国の文法を使っており、日本語とは語順が異なることが多いので、訓点を使って日本語での読み順を表現します。代表的な点には返り点と呼ばれる読み順の表示があり、文のどの語を先に読んで説明するかを示します。返り点以外にも、仮名を使って語尾の読みを補うことや、助詞や動詞の結びを示す補助的な記号が使われます。訓点を学ぶと、漢文をただ字面を追うのではなく、日本語として意味がすぐ結びつく読み方が身につきます。読み方の練習としては、短い文を選んで訓点を追い、日本語訳を作ってみるのが王道です。最初は難しく感じるかもしれませんが、版ごとに表記が異なることもある点を理解すれば混乱を避けられます。学校の授業だけでなく、漢詩や中国古典文学の入門書にも訓点の解説は多く、初心者にも取り組みやすい教材が増えています。地道に練習を重ねれば、漢文と日本語の両方の意味を結びつけられる読解力が育ちます。
- 漢文 書き下し文 とは
- 漢文 書き下し文 とは、漢文を日本語の語順に直して読みやすくした表現方法のことです。漢文は古代中国の文章で、主語や動詞の位置が現代日本語と異なることが多く、文法も日本語とは違います。そこで日本の学習者向けに、漢文の意味をとらえやすくするため『書き下し文』という読み方が生まれました。書き下し文では、漢文の語順を日本語の語順に合わせ、助詞や動詞の形を補って、意味を自然に理解できる文章にします。よく使われるポイントとして、返り点と呼ばれる読み順を示す記号、そして送り仮名や助動詞を補うことが挙げられます。書き下し文を作るときの流れはおおむね次の通りです。原文の漢字をそのまま並べる。日本語として自然な語順になるよう再配置する。助詞を補い、動詞を日本語の形に変える。返り点などの符号を添えて、元の漢文の読む順序を示す。現代語訳に近い日本語訳を併記する。教育現場では古典の授業、漢文の教材作成、受験対策などで活用され、原文と書き下し文を並べて比較する練習が効果的です。初めは短い文から始め、徐々に複雑な文へと進めると読み方のコツが身につきます。自分で短い原文を選んで書き下し文を作る演習もおすすめです。短い例として、漢文原文『君子不器』は書き下し文で『君子は器にあらず』となります。この例では不器の意味が日本語の助動詞と述語に置き換えられ、語順も日本語として自然になります。別の例として、簡単な文を自分で探して原文と書き下し文を比較すると、語順の違いを体感できます。書き下し文を練習するコツは、原文の意味をまず把握し、主語と述語がどの順序で来ているかをイメージすることです。そして日本語として読みやすい順序に並べ替え、必要に応じて助詞を補いましょう。最後に、現代語訳と照らし合わせて理解を深めると、漢文の理解がぐんと進みます。
- 漢文 句法 とは
- 漢文 句法 とは、漢文の文の作り方・組み立て方のことを指します。漢文は日本語とは異なる語順や助詞の働きがあり、意味を理解するには句の区切りと助詞の役割を押さえることが大切です。まず、漢文には原文での句読点が少なく、読み手が意味を取るために文をいくつかの「句」に分けて読み進めます。句法の基本は「主語と謂語(動詞)」を中心に、必要に応じて「賓語(目的語)」や補語が添えられる点です。現代日本語の語尾変化で文法を示す日本語と違い、漢文は語の並びと助詞で意味を決めます。よく出てくる助詞には「之」(代名詞・動作の対象を示す)、 「於」(場所・対象を示す前置詞)、 「乎」「也」「矣」などがあり、これらが文の意味合いを大きく左右します。例として「子曰、學而時習之,不亦說乎?」という文を挙げます。現代語訳は「孔子がおっしゃいました。学んで、時々それを練習するのは、喜びではないでしょうか。」のようになります。読解のコツは、まず句を4字・5字などのまとまりに区切り、主語・謂語を探し、場合によって省略されている語を補って現代語訳を作ることです。初学者には、辞典で漢字の意味と訓読・注釈を確認し、短い例文から徐々に練習を重ねるのがおすすめです。好きな教科書の「訓読」版を使うと、読み方と意味がつかみやすくなります。
- 漢文 句形 とは
- 漢文 句形 とは、漢文の文の“形”や組み立て方のことを指します。漢文は中国の古典文を漢字だけで表し、日本語へ読み下すときには文章の意味のまとまり方を意識する必要があります。句形をつかむと、主語はどこにあるのか、動詞はどの語で表されているのか、前後の語がどうつながっているのかが見えやすくなります。漢文には語尾変化が少ないため、意味をつかむコツは句の並び方や修飾の位置を把握することです。読み下す際には、返り点と呼ばれる読み順の印を使って、日本語の自然な語順に並べ直す作業が重要になります。実際の句形の捉え方を理解するには、短い例文を読み解く練習が効果的です。代表的な句形の一つとして、論語の一節「子曰、学而時習之、不亦說乎」を挙げられます。ここでは「子曰」が主語と述語の役割を示し、続く「学而時習之」が動作のまとまりを作り、「不亦說乎」が感嘆と疑問を同時に表現します。このように、漢文の句形は意味のまとまり(句)をいくつか作って、それらを順序よく結びつけることで文全体の意味を作り出します。初心者の読み方のコツとしては、まず全体の意味をざっくりつかむこと、次に句の切れ目や接続の順番に注意することです。漢文は日本語と語順が異なるため、初めは難しく感じますが、例文を繰り返し読むことで徐々に慣れていきます。句形を意識して読む練習を重ねると、漢文の「なぜそうなるのか」を直感的に理解できるようになります。要は、漢文 句形 とは、漢文の文を読み解くための“形”のことです。主語・述語の関係、句のつながり方、修飾語と被修飾語の位置などを意識すると理解が進みます。読み下しの練習や、実際の句の例を多く読むこと、そして自分の言葉で要点を説明してみることが、初心者にとって効果的な学習法です。
- 漢文 白文 とは
- 漢文とは、中国の古典的な文章で、長い歴史の中で作られた文学・思想・史料を指します。日本でも昔から重要な学問であり、現代でも漢文の理解は日本語の歴史や文学を読む力につながります。漢文を学ぶとき、まず耳にするのが「白文」という言葉です。白文とは、漢文の原文そのもの、読み方の手がかりや注釈・読み仮名が付いていない、文字だけの状態を指します。これに対して漢文訓読を用いて日本語として読むときには、返り点や注釈が追加され、意味を読み取りやすくします。つまり、白文は原典の文字だけ、漢文訓読は日本語として読み下す方法のことです。漢文には中国語の語順と日本語の語順の違い、文法の違いなどがあり、現代の日本語とは異なる点が多くあります。漢文を正しく読むには、まず語彙を覚えること、文の構造を見極めることが大切です。白文を読んだあと、返り点の位置を確認し、順序を補う註点を使って日本語の読み方に変換します。初学者には短い文から練習を始め、辞書で漢字の意味を確かめ、全体の意味を理解する練習を繰り返すとよいでしょう。学習のコツとしては、原文と和訳を対照しながら読むこと、漢字の成り立ちや語源を理解すること、そして日常生活で似た文の例を探して意味を結びつけることです。白文と漢文訓読の違いを意識して練習することで、漢文の面白さと奥深さが少しずつ見えてきます。
- 訓読 漢文 とは
- 訓読 漢文 とは、漢文を日本語として読み解くための読み下しの技法です。漢文は中国の古典文で、語順が日本語と違うことが多いので、そのまま読むと意味が取りづらくなることがあります。そこで日本語の語順に合わせて漢文を読み解くための方法として“訓読”が使われます。訓読では、漢文の語句を日本語の文法に近づけるため、訓点と呼ばれる読み順の目印や送り仮名を用いて、原文の意味を読み取りやすくします。漢文自体は中国の文法に基づく文章ですが、日本語として自然に読めるようにするのが訓読の役目です。訓読と漢文の違いを整理すると、漢文は内容そのものを指す「原文」です。一方で訓読はその原文を日本語として理解するための読み方・解釈の方法です。訓読を使うと、語順が日本語の「主語-動詞-目的語」などの順序に近づくよう、漢字の並びを日本語の語順に合わせて読み替えます。さらに、古典の理解を助けるための道具として訓点(漢字の横や上に添える点・符号)や送り仮名、句読点のような表示が用いられます。これらの符号は、読み進める順番を示す手がかりで、実際には複雑なこともありますが、初心者は簡単な例から練習を始めると良いです。初心者向けの練習法としては、まず短い文から始め、原文と訓読の読み方を並べて比較します。次に、漢文の語順を日本語の語順に直す練習をします。辞書を使って難しい語の意味を確認し、文法の基本(助詞の働きや動詞の活用)を覚えると、理解が進みます。さらに、現代語訳がついた教材を併用すると、意味のつながりをつかみやすくなります。例として「君子以自強也」という文を見てみましょう。訓読では「君子は以って自らを強くするなり」と読み、日本語としての意味は「君子は自分を強くするべきだ」という理解になります。漢文の訓読は、一度に完璧を目指すよりも、少しずつ読み方の感覚を身につけることが大事です。現代の教材では、原文と現代語訳、訓読の読み順を同時に示してくれるものが多く、初学者には特に有用です。慣れてきたら、より長い文や、難解な語を含む文にも挑戦していくと良いでしょう。
- 古文 漢文 とは
- この記事では、古文と漢文の違いと意味を、初心者の中学生でも分かるように丁寧に解説します。まず古文とは、日本語の昔の文体の総称です。古文は奈良時代から平安時代に盛んで、源氏物語や枕草子などの作品が代表です。古文の特徴は、使われる語彙が現代の日本語とは違い、動詞の活用や助詞の使い方が現在と異なる点です。そのため、読み解くには文法の知識と、当時の言い回しを覚えることが必要です。読み方のコツは、文章をそのまま頭から読むのではなく、語尾の動詞や名詞の形を手掛かりに、全体の意味をつかむことです。次に漢文とは、中国の古典中国語で書かれた文章を指します。漢文は元々日本語ではなく、中国の歴史・思想・詩文が中心です。日本では漢文を日本語に読む訓読(くんどく)という読み方を使います。訓読では、漢字の意味はそのままに、日本語の語順に並べ替える読み方の補助符号や句読点が付けられます。読み方の基本は、まず漢字の意味を理解し、次に日本語の語順に直して意味を考えることです。漢文の特徴として、文の主語や動詞が省略されがちで、暗記だけで意味が取りづらい部分もありますが、訓点を覚えると読みやすくなります。古文と漢文は、日本の教科書で一緒に学ぶことが多く、日本の歴史や古典の理解に役立ちます。初めは難しく感じるかもしれませんが、少しずつ語彙や文法のパターンを積み重ねれば読めるようになります。
漢文の同意語
- 漢文
- 中国の古典中国語で書かれた文学・文献の総称。漢代からの文献を中心とする、漢字を用いた書き言葉の文学様式を指します。
- 文言文
- 漢文とほぼ同義の語。中国の古典的な書き言葉・文体を指し、日本語では『漢文』と同じ意味で使われることが多い。
- 古典漢語
- 漢文で用いられる古典的な中国語の語彙・文法・表現。学術的には漢文と同義または非常に近い概念として扱われます。
- 漢籍
- 漢字で書かれた中国の古典文学・文献の総称。漢文が書かれている文章群をまとめて指すときに使われる語。
- 中国古典文学
- 中国で成立した古典的な文学作品の総称。漢文の文本を含む広い範囲を指す言葉として使われることが多い。
漢文の対義語・反対語
- 和文
- 日本語で書かれた文体。漢文が古典中国語の文体であるのに対し、和文は日本語の語順・助詞・仮名遣いを活かした表現になります。
- 現代文
- 現代の日本語で書かれた文体。漢文の古典的な文体と比べ、現代語の語彙・表現が使われます。
- 口語体日本語
- 話し言葉に近いカジュアルな文体。漢文の硬い格式とは異なり、より自然な日常語の表現です。
- 和語中心の文体
- 日本語固有の語彙(和語)を中心に用いる文体。漢文で多く使われる漢語由来の語彙とは異なる。
- 洋文
- 西洋の言語(英語・フランス語など)で書かれた文体。漢文は中国語系の古典文体であるのに対し、洋文は欧米言語の文体を指します。
- 現代中国語
- 現代の中国語で書かれた文体。漢文は主に古典中国語を指すことが多く、現代中国語とは別の文体です。
- 漢字仮名交じり文
- 現代日本語の標準的な文体で、漢字と仮名を混ぜて書く形式。漢文の中国語的文体とは異なり、日本語の自然な語順と仮名遣いを使います。
- ひらがな文
- ひらがなのみで書かれた文。漢文の漢字中心の文体とは大きく異なり、読みやすさや口語的印象が強いです。
漢文の共起語
- 訓読
- 漢文を日本語の語順で読み解く方法。日本語の語彙順に合わせて漢字の意味を解釈する読み方の総称。
- 訓点
- 漢文を訓読する際に添える記号。語順を示したり読みを補助します。
- 返り点
- 漢文の読みに使う点の一種。どの語を先に読むかを示す指示記号です。
- 書き下し文
- 漢文を日本語の語順に直して書いた文。読みやすくするための日本語表現です。
- 注釈
- 原文の意味や背景を詳しく解説する補足情報。
- 対訳
- 漢文の日本語訳。原文の意味を日本語で表現します。
- 和訳
- 対訳と同等に、漢文の日本語訳を指す表現。自然な日本語訳を提供します。
- 漢文訓読
- 漢文を訓読する技法や学習分野。学習者向けの読み方を指します。
- 四書五経
- 中国古典の中心となる経典群。漢文教材の代表格です。
- 論語
- 孔子の言行を集めた漢文の古典。教育・道徳の要素が多く含まれます。
- 孟子
- 孟子の著作。儒学の古典の一つで漢文として学習対象です。
- 詩経
- 中国最古の詩集。漢文の読み下し練習にも登場します。
- 典故
- 古典文学の引用・由来の話。漢文の意味理解を深める要素です。
- 倒置
- 漢文独特の語順の入れ替え。意味を取りにくくするポイントで、読み解きのコツが必要です。
- 注解書
- 漢文の語句や文意を解説した書物。難解な語句の意味が詳しく分かります。
- 国学
- 日本独自の古典学問の一分野。漢文の読み・解釈を含むことが多いです。
漢文の関連用語
- 漢文
- 中国の古代の文語体で書かれた文章・文学を指します。日本で学習対象として扱われることが多いです。
- 文語
- 現代語ではなく、古代・中世に使われた書物の文体・語彙のこと。
- 文言文
- 中国古典の統一的な文語体の呼称。日本語では漢文の代表的な表記形式として扱われます。
- 漢文訓読
- 漢文を日本語の語順・意味で読み下す方法。読み下しの技術の一つです。
- 訓読
- 漢文以外にも外国語の文を日本語の語順で読み下すこと。一般的な和読の総称。
- 返読
- 漢文を日本語の語順で再読して意味を取りやすくする読み方。
- 訓点
- 訓読を補助する符号・点。読み方のヒントを示します。
- 返り点
- 漢文を読む際に使う返読の記号。語順を指示します。
- 章句
- 漢文の文節・章・句の区切り。原文の読み解きを助けます。
- 注釈
- 原文の意味・語彙を補足する説明。
- 訳注
- 現代語訳とともに、訳文の補足説明をつけた注釈。
- 現代語訳
- 漢文の意味を現代日本語に訳したもの。
- 漢籍
- 中国の古典籍・文献の総称。
- 漢文学
- 漢文を題材とした文学・研究分野。
- 論語
- 孔子の言行を集めた古典。漢文の代表的テキスト。
- 孟子
- 孟子の著作。倫理・政治思想の古典。
- 詩経
- 中国最古の詩歌集。漢文の教材としても用いられます。
- 易経
- 易学の古典。哲学的・占い的要素を含む経典。
- 史記
- 司馬遷の歴史書。古代中国の歴史を記した漢文の代表作。
- 注解書
- 原文の意味を詳しく解説した書物。
- 典故
- 古典に登場する故事・引用元。
- 白話文
- 口語・現代語に近い表現の文体。漢文と対比して語られます。
- 漢詩
- 漢字で書かれた詩。漢文の詩文を指すことが多いです。
- 読み下し
- 漢文を日本語の語順で読み下すこと。
- 訓読体
- 訓読で表された日本語の文体。
- 竹簡
- 竹に書かれた古代中国の書物。
- 木簡
- 木板に書かれた古代中国の書物。
- 漢文検定
- 漢文の読解力を測る検定試験。
- 語法
- 漢文の語順・文法の特徴。
- 対句
- 二つの句を対比させる修辞技法。詩文に多く用いられます。
- 典拠引用
- 文献の出典元を明示して引用すること。
漢文のおすすめ参考サイト
- 漢文とは何? 日本漢文の世界 kambun.jp
- 漢文とは何? 日本漢文の世界 kambun.jp
- 漢文とは?古文との違いや勉強する意味について簡単解説! - 四季の美
- 漢文(カンブン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
- 漢文とは−大学受験の漢文勉強法① - アクシブアカデミー



















