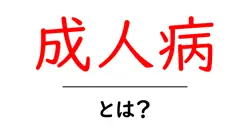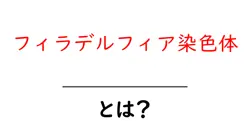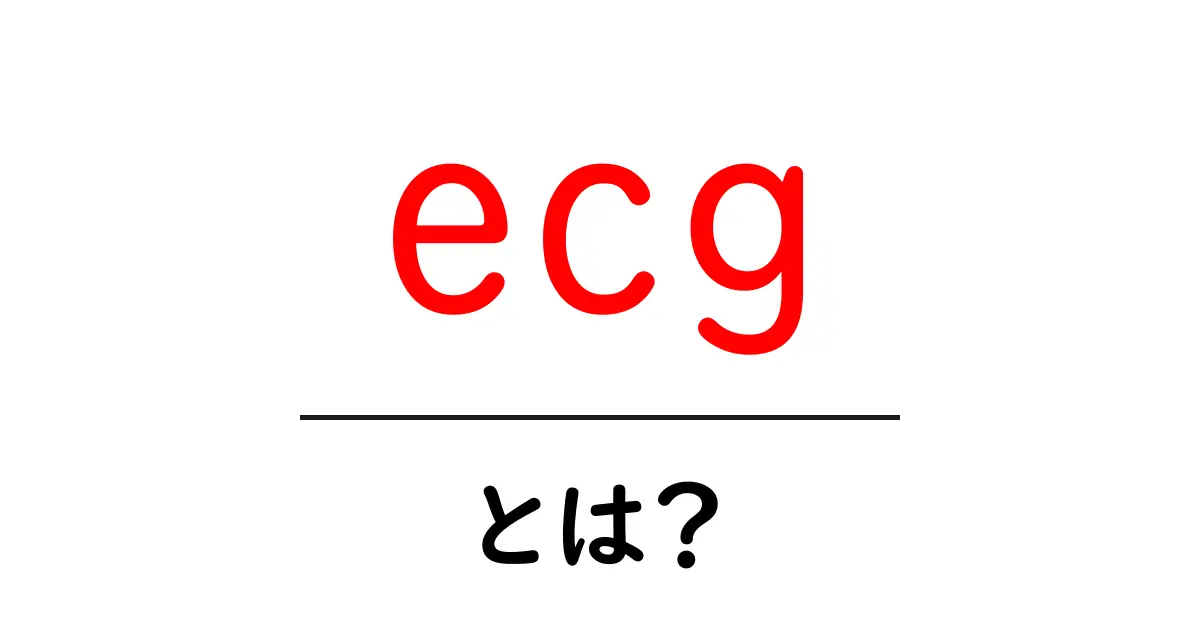

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
ecg(electrocardiogram、心電図)は、心臓の電気活動を記録する検査です。心臓は拍動を起こすときに微かな電気信号を発します。この信号の流れを体の外から測定して、心臓が正しく動いているかどうかを判断します。
検査は皮膚の上に小さな電極を貼り、専用の機械に信号を送って波形を描きます。波形は「P波」「QRS波」「T波」と呼ばれる特徴的な形をとります。これらの波形は心房が興奮してから心室が興奮し、最後に回復するまでの流れを示します。
ECGは痛くも危険でもなく、ほとんどの人が数分で検査を受けられます。体の中の電気信号を外から測るだけなので、放射線は使いません。検査の結果を医師が読んで、心臓のリズム(規則正しいかどうか)、伝導の乱れ、心臓の筋肉の状態などを確認します。
ecg・とEKGはほぼ同じ意味です。英語表記のECGは international 標準、EKGはドイツ語由来の略語として使われることが多いだけで、実際の検査内容には違いはありません。
読み方と基本の波形の意味
波形の各部分には意味があります。P波は「心房の活動」、QRS複合波は「心室の活動」、T波は「心室の回復」を表します。波形の長さや間隔が通常と異なると、心臓のリズムが乱れている可能性を示します。
日常生活の中でのECGは、体調が急に悪くなったときに病院で行われることが多いですが、健康診断やスポーツ前のチェックにも使われます。検査の結果だけで病名が決まるわけではなく、他の検査と合わせて判断します。
もし自分や家族が「心臓の痛みがある」「息切れが続く」「動悸が激しい」などの症状を感じたら、すぐに医療機関を受診してください。ECGはその場の状況を知る手がかりになる大切な検査です。
ecgの関連サジェスト解説
- ecg とは何ですか
- ecg とは、心臓の電気の動きを体の表面に記録する検査のことです。心臓は一定のリズムで拍動しますが、その動きは電気信号で作られています。ECGはこの電気信号を、胸や手足に貼る小さな電極を使って読み取り、波形として見える形にします。病院やクリニックで、心臓のリズムが乱れていないか、心臓の病気の有無を調べるために使われます。ECGは痛みを伴わず、短時間で終わります。検査中は腕や胸、足の皮膚に電極を貼り付けるだけで、普通は体を動かしても大丈夫です。ECGで得られる波形にはP波、QRS複合波(QとRとSの山と谷)、T波などの基本パターンがあり、医師はこれを見て心臓の興奮の流れを判断します。P波は心房の動き、QRSは心室の動き、T波は心室の回復を示します。標準的な心拍数は1分間に60〜100回程度ですが、年齢や体調により変わります。正常なECGでも少しの差はあり、専門家が総合的に判断します。なお、ECGとEKGという表記の違いは地域や病院による呼び方の違いだけで、同じ検査を意味します。ECGのデータは治療の計画を立てる手がかりになり、薬の調整やペースメーカーの評価にも役立つことがあります。
- ecg とは何
- ecg とは何かを理解する第一歩は、ECGが心臓の電気の動きを記録する検査だという点です。ECGはelectrocardiogramの略で、日本語では心電図と呼ばれます。検査の目的は、心臓の電気的な活動を波形として記録し、規則正しいリズムかどうかや、異常な信号がないかを調べることです。検査は痛みがなく、皮膚に貼る小さな電極を数個使い、ベッドに横になって行います。電極は胸や手足の皮膚に貼ります。機械が心臓が発している電気信号を取り込み、紙の記録やモニター画面に波形を表示します。波形にはP波、QRS波、T波という特徴的な部分があり、それぞれ心房が動くとき、心室が動くとき、回復のときを表しています。ECGは心臓の機械的な動きそのものを映すわけではなく、心臓が電気的にどう動いているかを知る道具です。これにより、不整脈や心筋梗塞の疑い、心肥大、電気伝導の異常など、病気の手がかりを見つけやすくなります。日常的には健康診断のときに胸の痛みや息切れ、動悸を感じるときに、さらには手術の前後のチェックなど、さまざまな場面で使われます。ECGは痛みを伴わず、撮影時間も短く、機械の扱い方さえ分かれば誰でも受けられる検査です。ECGとEKGという呼び方は同じ検査を指しますが、表記の違いだけです。心電図は医療者が読み取り、異常があれば追加の検査や治療につながります。心臓の電気的な様子を知るための第一歩として、私たちの健康管理に役立つ重要な道具です。
- ecg とは何か
- ecg とは何かを中学生にもわかるように詳しく解説します。ECGは心臓の電気信号を測る検査の名前です。心臓は血液を体中へ送るために規則正しいリズムで拍動しますが、その拍動は微小な電気の流れで生まれます。ECGは体の表面に貼る電極と呼ばれる小さなパッドを使い、体の外からこの電気信号を拾って機械に記録します。記録された波形にはP波、QRS波、T波といった特徴が現れ、それぞれ心房が収縮する部分、心室が収縮する部分、心室が回復する部分を示します。これを読むと心臓のリズムが速すぎるか遅すぎるか、不整脈があるか、心筋の痛みがあるかどうかの手掛かりを得られます。検査の方法はとてもシンプルです。胸や手首、足首などに粘着性の電極を貼り、機械につなぐだけで痛みはありません。安静にしている安静ECGのほか、運動をしながら心臓の反応を見るストレス検査、24時間以上つけて日常生活を記録するホルター心電図などのタイプがあります。ECGは心臓病の有無を判断する重要な道具ですが、万能ではありません。瞬間的な記録なので、長期間の動悸や息切れをすべて説明できるわけではありません。医師は症状や他の検査結果と組み合わせて判断します。なお、ECGとEKGは同じ意味で、呼び方の違いだけです。初心者が覚えるときは“心臓の電気信号を記録する検査”と覚えると理解が進みやすいでしょう。
- 医療用語 ecg とは
- 医療用語 ecg とは、電気的な心臓の活動を記録する検査のことです。ECGは英語でelectrocardiogramの略称で、日本語では心電図と呼ばれることが多いです。検査の目的は、心臓のリズム(鼓動の規則性)や伝導の異常、心臓の筋肉の活動を確認することです。検査を受けると、胸や腕、足に小さな粘着性の電極を貼りつけ、数十秒から数分間、体を動かさずに測定します。機械が心臓の電気信号を波形として記録し、波形にはP波、QRS波、T波といった特徴が現れます。P波は心房の興奮、QRS波は心室の興奮、T波は再分極の状態を表します。波形の大きさや長さ、波と波の間隔(例:PR間隔、QT間隔)を見て、規則正しいか、異常があるかを判断します。ECGにはいくつかの種類があり、日常的に使われる12誘導ECGは胸と四肢の複数の電極で心臓の状態を多方向からとらえます。急いで状況を確認する場合には1つのリードだけの簡易ECGも使われます。病院では連続で記録するホルター心電図(24時間以上)や長期間のイベントモニターなどがあり、発作性の不整脈をとらえるのに役立つことがあります。検査の前提や限界も知っておくことが大切です。胸痛や息切れ、動悸があるとき、手術前の健康チェック、薬の影響を確認するためにECGが行われることがあります。検査自体は痛くなく安全ですが、皮膚の貼り付け部にかぶれが出ることがあります。ECGの結果は医師が解釈します。ECGだけで病名が決まるわけではなく、必要に応じて血液検査、心臓超音波検査、ストレス検査などと合わせて判断します。日常の医療現場では、心臓の状態を知るための基本的な検査として広く使われており、救急外来やクリニック、病院のさまざまな場面で活躍しています。自分の体の状態を理解する一助として、ECGの目的や流れを知ると安心感が得られます。もし医療スタッフからECGについて説明を受けたら、波形の意味や検査の目的を質問してみるとよいでしょう。
- atypical ecg とは
- atypical ecg とは心臓の電気活動を記録する心電図であり normal なパターンから外れた特徴を指す言葉です 基礎的には心電図は心臓の拍動に伴う電気の流れを線で描いた図です 正常な場合には規則的な波形が現れますが atypical という表現はその形が普通と違うことを意味します 例えばQRSの形やT波の方向が通常と異なることがあります ただし atypical が必ず病気を意味するわけではなく生理的な要因や機械の設定 体の位置や呼吸の影響などで変化することもあります 運動の後やスポーツ選手など体格によっては非典型的に見えることがありこれは珍しいことではありません 一方で胸の痛み息切れめまいなどの症状と一緒に atypical な心電図が出た場合は医師が詳しく検査を進めることが多いです 医師は血液検査や超音波検査など他の情報も合わせて総合的に判断します 自己判断は避け専門家の説明を受けることが大切です 心電図の読み方は難しいところも多いですが基本は波形の形の変化を見つけることです この用語を知っておくと医師の説明を聞くときに理解が進みやすくなります 最終的には個人の健康状態に応じた適切な対応が必要です
- normal ecg とは
- normal ecg とは心電図のことで、心臓が発生させる微かな電気の動きを体の外側に貼った電極で測って記録したものです。心臓は拍動するたびに電気信号を出し、それが波の形となって画面に現れます。ECG を見ると、心臓がきちんと働いているかを判断する手掛かりが得られます。特に normal ecg とは、そんな波形が“ふつう”の状態で現れていることを指します。
- triplicate ecgとは
- triplicate ecgとは、心臓の電気的活動を測る検査であるECGの一つのやり方です。通常のECGが1枚の波形を取るのに対し、triplicate ecgでは同じ条件で3回連続して記録します。目的は、測定に影響するノイズや動きの影響を減らし、心臓の状態をより正確に判断することです。例えば心拍が不規則だったり、微妙な間隔の違いを見たいときに役立ちます。実際のやり方は次のとおりです。まず皮膚とセンサーを清潔にして、胸部・腕に電極を正しく配置します。最初の tracings を確保します。次に同じ条件で2回目、3回目を撮影します。三つの波形を並べて比較し、必要に応じて平均値を取るケースもあります。撮影中は体を動かさないようにし、会話や笑いなどの動作を控えるよう指示されることが多いです。読み方のポイントとしては、三つの波形を横に並べて、心拍のリズムが安定しているか、PR間隔・QRS幅・QT間隔に大きなズレがないか、アーチファクト(ノイズ)が入り込んでいないかを確認します。もし三回の記録で差が大きい場合は、原因を探るために再度撮影したり、別の条件で再測定を行うこともあります。使われる場面としては、病院の診察時や術前の健康評価、薬の影響を詳しく知りたいときなど、心電図の信頼性を高めたい場面で用いられます。なお、自己判断のために使うものではなく、症状があるときは必ず医療機関を受診しましょう。病院での丁寧な説明と適切な測定条件の下で、triplicate ecgは心臓の状態をより確実に把握する手助けになります。
- resting ecg とは
- resting ecg とは、心臓の電気信号を体が安静な状態のときに記録する検査です。心臓は拍動時に微妙な電気信号を出しており、それを皮膚に貼った小さなセンサー(リード)で測定します。検査は痛みがなく、機械の前に横になるだけ。多くの場合、胸や腕、脚に粘着パッドを貼って、数分間静かにしています。12誘導と呼ばれる多方向の波形をとる機器が使われることが多く、心拍数やリズム、電気の伝わり方を調べます。波形にはP波・QRS複合体・T波などの特徴的な形があり、医師はこれらを見て「洞調律か」「心臓の一部で伝わりにくいところがないか」「過去の心筋梗塞の跡があるか」などを判断します。resting ecg は、日常の健康診断や手術前の準備、胸痛の診断時などに用いられます。測定結果だけで心臓の病気を確定することはできず、他の検査と組み合わせて総合的に判断します。例えば心筋梗塞の可能性を示す目安となるST段差の変化や、心房細動のような不整脈の痕跡を見つけ出すことがあります。ただし正常な結果でも病気がないとは限らず、運動時の反応を見るストレス心電図など、追加の検査が必要になることもあります。準備としては、検査前にシャワーを浴びて皮膚を清潔にしておくと粘着がよく付きます。胸元の金属アクセサリーは外し、保湿剤は避けます。検査中はなるべくリラックスし、指示があれば深呼吸を控えめにします。結果の読み方は専門の医師が行い、気になる点があれば詳しく説明してくれます。
- eeg ecg とは
- このページでは eeg ecg とは何かを、初めて学ぶ人にも分かるようにやさしく解説します。まず eeg は脳波を測る検査で、頭皮に小さな電極をつけて脳の神経細胞が発する微弱な電気信号を記録します。測定中は眠くなることもありますが、基本的には体を動かさずに静かにしておく必要があります。 EEG のデータは波形として表示され、アルファ波やベータ波、デルタ波などと呼ばれる周波数帯の違いから脳の状態を判断します。子どもから大人まで安全に受けられる非侵襲的な検査で、てんかんの診断や睡眠障害の研究、脳の機能評価などに使われます。次に ECG(心電図)は、胸や手足の皮膚に貼る電極を使い、心臓の電気的な活動を記録します。P波、QRS波、T波といった波形が現れ、心拍のリズムや伝導の異常、心筋の状態を知る手がかりになります。ECG は胸痛や動悸などの症状があるときに病院でよく用いられ、心臓発作の兆候を早く見つけるのに役立ちます。 EEG と ECG はともに身体の内部を直接傷つけずに情報を得る非侵襲的な検査ですが、測定する場所・目的・読み方が大きく異なります。両方を理解することで、医療現場での判断の仕組みを身近に感じられるでしょう。
ecgの同意語
- ECG
- electrocardiogram の略称。心臓の電気活動を記録して心電図を得る検査の英語表現の一つ。
- EKG
- electrocardiogram の別表記。英語圏で同じ意味の略語。
- electrocardiogram
- 心電図そのものを指す正式名称。心臓の電気活動を記録した波形を表す。
- electrocardiography
- 心電図を記録・解釈する医学的手法・分野。検査自体やその技術を指すこともある。
- 心電図
- 日本語表現。心臓の電気活動を記録する検査を指す言葉。
- 心電図検査
- 心電図を取得する目的で行う検査のこと。
ecgの対義語・反対語
- 非心電図
- ECG(心電図)以外の検査を指す言葉。電気的心臓活動を直接記録しない検査全般を意味します。
- 心電図以外の検査
- ECGの対義的な意味で、心電図を使わない検査の総称。聴診や画像診断、血圧測定などを含みます。
- 心音聴診
- 聴診器で心臓の音を聞く検査。電気信号を記録するECGとは異なる情報を得ます。
- 脈拍測定
- 手首や首などで脈拍を触れて測る方法。心臓の機械的リズムを評価しますが、ECGの電気信号は捕らえません。
- 血圧測定
- 血圧を測る検査。心臓の血圧指標を得るもので、ECGの電気活動とは別の情報源です。
- 呼吸数観察
- 呼吸の回数・パターンを視覚的・触覚的に観察する評価。ECGの電気信号とは無関係です。
- バイタルサイン総称
- 体温・脈拍・呼吸・血圧など、基本的な生体指標の総称。ECGと同じく医療現場で用いられるが、電気信号は含みません。
- 画像診断(MRI/CTなど)
- 体の内部を画像として可視化する検査。ECGのような電気信号測定とは別カテゴリの検査です。
- 自覚的評価のみ
- 患者本人の主観的症状に基づく評価。ECGの客観的電気信号とは異なる情報源です。
- 非電気的モニタリング
- 心臓の電気活動を記録しないモニタリング。血圧・呼吸・脈拍などの非電気的指標を継続観察します。
- 心臓電気活動以外のデータ
- ECG以外のデータ(聴診結果、画像診断、バイタルサインなど)を指す表現。
ecgの共起語
- 心電図
- ECGの日本語名称。心臓の電気活動を記録して波形として表す検査のこと。
- 12誘導心電図
- 標準的な12誘導で心臓の電気活動を評価する検査形式。多くの病変を検出しやすい。
- 心電計
- 心電図を測定・記録する機器。携帯型もあり、病院・クリニックで使用される。
- EKG
- 英語表記のElectrocardiogramの略。日本でも用いられることがある。
- ECG
- Electrocardiogramの略。心臓の電気活動を記録する検査全般を指す総称。
- デジタル心電図
- デジタル形式で記録・解析されるECG。データとして保存・比較が容易。
- 心拍数
- 1分間の心臓の拍動数。ECGで基本的に測定・監視される指標。
- 心拍リズム
- 心臓の拍動の規則性。正常は洞調律。異常は不整脈の可能性を示す。
- P波
- 心房の脱分極を示す波形。ECG波形の一部。
- QRS波
- 心室の脱分極を示す、ECG波形の中心的・最も高い部分。
- T波
- 心室の再分極を示す波形。ECG波形の一部。
- PR間隔
- P波の始まりからQRSの始まりまでの伝導時間。心臓伝導の指標。
- QT間隔
- 心室の脱分極と再分極が完了するまでの総時間。薬物・病態で変化する。
- 誘導
- ECGを記録するためのリード(例:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6)。
- 12誘導
- 12個の導出を使い心臓全体の電気活動を評価するECG形式。
- 心電図波形
- P・QRS・TなどECGで描かれる波形の総称。
- 自動解析
- ECG機器が波形を自動で解析し、初期判断を支援する機能。
- 安静時心電図
- 安静時に記録するECG。基礎的な波形の評価に用いる。
- ストレス心電図
- 運動負荷をかけながら心電図を記録する検査。心機能の評価に用いられる。
- 運動負荷心電図
- ストレス検査と同義。運動時のECG変化を評価する検査。
- 心電図読み方
- ECGの読み方・解釈の基本を解説する表現・教材名として使われる。
- 心電図読影
- ECG波形を読み解く技術・プロセスの呼称。
- 不整脈
- 心臓のリズムが異常になる状態。ECGでよく検出される所見。
- 心筋梗塞
- 冠動脈の閉塞で心筋が障害される状態。ECGで疑われる典型的な所見が現れることが多い。
- 冠動脈疾患
- 冠状動脈の病気全般。ECGは診断補助として用いられる。
- 心電図検査
- ECGを実施する医療検査の総称。
- 心電図機器
- ECGを測定・記録する機器・装置の総称。
- ベースライン
- ECG測定時の基準波形。ノイズ除去や比較の基準として用いる。
ecgの関連用語
- ECG
- electrocardiogramの略。心臓の電気的活動を記録してリズムや伝導、虚血を評価する検査です。
- EKG
- ECGの同義語。呼び方の違いのみで同じ検査を指します。
- 心電図
- 日本語の名称。胸部と四肢の電極から心臓の電気活動を記録する検査の総称です。
- 12誘導心電図
- 12個の誘導(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6)を用いて心臓の電気活動を総合的に評価する検査形式。
- リード
- 心臓の電気活動を別々の角度から記録する電極の組み合わせ。主要なリードにはI, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6があります。
- 標準肢誘導
- I, II, IIIの3つの肢誘導。正面視で心臓の水平・垂直方向の活動を捉えます。
- 拡張肢誘導
- aVR, aVL, aVFの3つの誘導。心臓の他の角度からの情報を補完します。
- 胸部誘導
- V1–V6の胸部誘導。心臓の前面からの電気活動を詳しく評価します。
- P波
- 心房の興奮を表す波。P波の形と持続時間で洞調律や前駆房室結節の活動を推察します。
- PR間隔
- P波の開始点からQRS開始点までの時間。正常は約120–200ms。房室伝導の指標です。
- QRS波
- 心室の興奮を表す鋭い波群。通常幅は80–120ms未満。
- ST段階
- QRS終末とT波開始の間の区間。ST上昇やST低下は虚血・心筋障害を示唆します。
- ST上昇
- ST segmentが基線より上昇。心筋梗塞(特にSTEMI)のサインの一つです。
- ST低下
- ST segmentが基線より低下。虚血やサブエンドイベントを示すことがあります。
- Q波
- 心室の興奮の後に現れる大きな負の波。病的Q波は過去の心筋梗塞の痕跡を示すことがあります。
- QT間隔
- QRS開始からT波終点までの時間。QTcで補正して評価します。
- QTc
- 補正QT間隔。心拍数の影響を除去して正常範囲を判断します。
- P波幅
- P波の持続時間。長い場合は心房伝導異常を示唆します。
- QRS幅
- QRS波の持続時間。伝導障害の有効な指標です。
- T波
- 心室の再分極を示す波。形状異常は高K血症・低K血症・ST変化と関連します。
- 房室ブロック
- 房室伝導が一部または完全に遅延・遮断される状態。Ⅰ度・II度・III度などの分類があります。
- 一度ブロック
- PR間隔が正常より長くなる。通常は処置を要しませんが、他の信号と評価します。
- Mobitz I
- 第II度AVブロックの一種で徐々にPR間隔が延長してQRSが落とされるパターン。
- Mobitz II
- 第II度AVブロックの別型。PR間隔は一定、突然QRSが落ちる。
- 高度AVブロック
- 3度ブロック。心臓の上位と下位の伝導が完全に分断されます。
- 洞調律
- 主な心拍リズム。洞結節からの規則的な興奮で発生します。
- 洞性頻拍
- 洞結節由来の心拍数が速くなる状態(通常>100bpm)。
- 洞性徐脈
- 洞結節由来の心拍数が遅くなる状態(通常<60bpm)。
- 心房期外収縮
- PAC。心房の早期収縮でP波が形を変えることがあります。
- 心室期外収縮
- PVC。心室の早期収縮で広いQRSを伴います。
- 心室頻拍
- VT。連続した広い正弦波のようなQRSが続く危険なリズム。
- 心室細動
- VF。心臓が細かく震えるような致死的リズムで直ちの早急な対応が必要。
- 心電図のノイズ
- 動作・筋電・電極接触不良などによる偽の波形。Artifactとも呼ばれます。
- 基線動揺
- 基線が揺れる現象。リード保持の問題や呼吸、動作が原因です。
- 移動アーチファクト
- 体動によるノイズの一種。心電図の読み取りを難しくします。
- キャリブレーション
- 機器を正確な基準に合わせる作業。通常は0.0mVを基準とします。
- 紙速度
- 心電図の紙の進み方。一般は25mm/秒(標準)、50mm/秒は細かい波形観察に使います。
- ゲイン
- 振幅の拡大倍率。波形の大きさを見やすくする設定です。
- 電極貼付
- 電極を適切な部位に貼る作業。正確な配置が読み取りに直結します。
- 標準肢誘導の数
- I, II, IIIの3つの肢誘導。心臓の電気活動を横から見ます。
- 前胸部誘導
- V1–V6の胸部誘導。前方からの心電活動を観察します。
- Holter心電図
- 24時間以上の長時間モニタリング。日常生活の心電活動を記録します。
- イベントモニター
- 症状発生時にデータを記録する長時間モニタリング機器。
- 心電図解釈のステップ
- 通常はリズム→波形の特徴→間隔・軸→ ST/T/異常の順で評価します。
- 軸
- 心電図の電気軸。正常は約-30°〜+90°程度、偏位があると病態の手掛かりになります。
- 左軸偏位
- 心電軸が左方向にずれる状態。虚血、左心室肥大などで起こることがあります。
- 右軸偏位
- 心電軸が右方向にずれる状態。右室肥大、肺疾患などの影響を受けます。
- 補正Q波
- 病的Q波の有無を判断する指標。大きさ・深さ・持続時間で評価します。
- 心筋虚血のサイン
- ST段階の変化、T波の反転、Q波などから虚血・心筋障害を推測します。
- 心筋梗塞のサイン
- ST上昇/ST低下・新規Q波・T波の変化が手掛かりです。緊急対応が必要です。
- オンラインモニタリング
- 病院内の連携モニタリング。患者の心電図をリアルタイムで監視します。
- 常用の用語の総称
- 12誘導心電図、低侵襲の心臓検査として広く使われます。