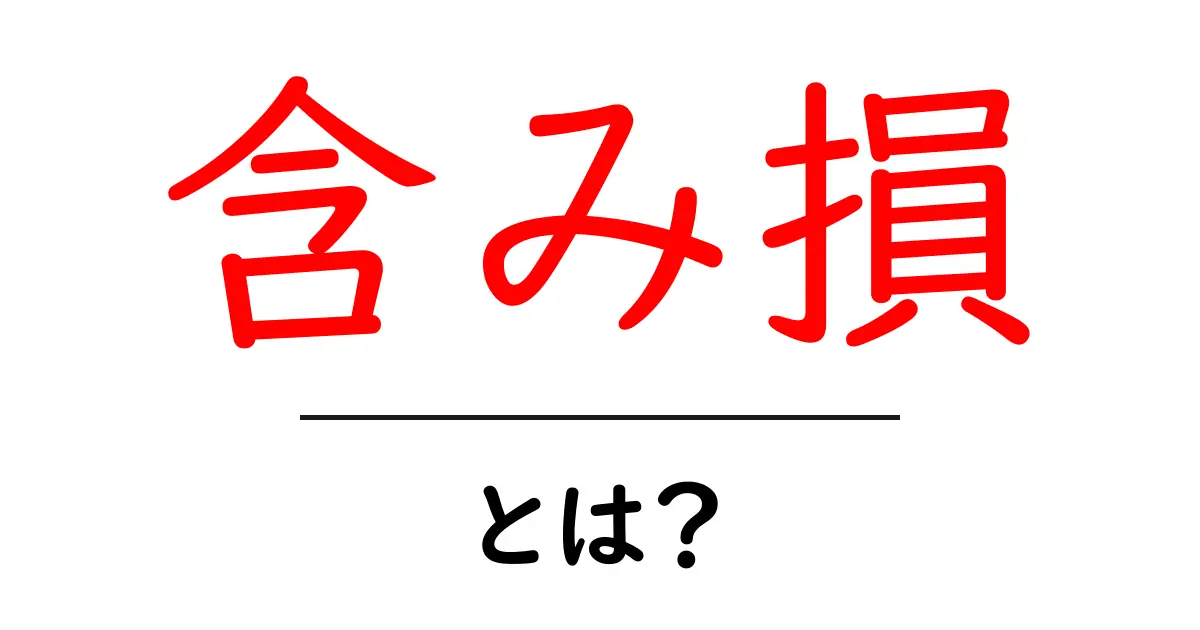

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
含み損・とは?基礎知識
この記事では、含み損・とは?の基本から実践的な対処法までを、初心者にも分かるように丁寧に解説します。株式だけでなく投資信託やFX、暗号資産など、値動きのある資産を保有している人に役立つ情報です。
含み損の定義
含み損とは、現在の市場価格とあなたが購入した価格の差がマイナスになっている状態のことです。まだ売却していないため「確定していない損失」という意味になります。
なぜ含み損が生まれるのか
市場は常に動いています。買った値段より現在の価格が下がれば、含み損が発生します。その状態は紙の上の損失であり、実際のお金はまだ動いていません。人は焦って売ってしまいがちですが、根拠がないと判断を早まることもあります。
含み損の計算と具体例
基本的な計算式は次のとおりです。
含み損 = (現在価格 - 取得価格) × 数量
例を見てみましょう。
上の表は、含み損だけでなく含み益の様子も示しています。含み損・とは?の理解を深めるには「現在価格と取得価格の差」が鍵です。なお、含み損は未確定の損失であり、実際のお金が動くのは売却したときです。
よくある誤解と現実
誤解1 含み損があるとすぐに損失を確定させるべきだ。現実 では、損失を確定するかどうかは戦略次第です。市場が回復する可能性もあるため、安易な売却は避けるべきです。
誤解2 含み損は必ず悪いことだ。現実 には、長期投資の局面では含み損を抱えつつ耐えることが有利な場合もあります。
含み損をどう扱う?実践のポイント
1. 自分の投資目的を見直す。資産形成のゴールが長期か短期かで、含み損の捉え方は変わります。
2. 損切りのルールを決める。損失が一定の割合を超えたら売る、といったルールを決めておくと感情に流されにくくなります。
3. 分散投資とリスク管理を徹底する。特定の資産だけに偏らないようにして、含み損の影響を小さくします。
このような対処は、冷静な判断と長期的な視点を持つときにこそ有効です。含み損を「損を確定させる機会」ではなく「ポートフォリオを整えるきっかけ」として捉える考え方が重要です。
まとめと次の一歩
含み損は、投資の世界では避けられない現象の一つです。未確定の値下がりを意味する現象として理解し、危険信号として過度な売却を避ける判断と、適切なルール作りを心がけましょう。実際に損切りをするか、保有を続けて市場の回復を待つかは、あなたのリスク許容度と目的次第です。
追加情報と次のステップ
実際の取引画面では、含み損の状態をモニタリングするためのツールがあります。通知機能を活用して、あらかじめ決めた閾値を超えたらアラートが届くように設定しておくと、焦って判断することを防げます。投資は長期的な視点で見守ることが重要です。
含み損の関連サジェスト解説
- 含み損 とは わかりやすく
- 含み損 とは わかりやすく、初心者向けの解説記事です。まず、含み損とは保有している金融商品の現在の評価額が取得時の価格より低くなっている状態のことを指します。実際に現金を動かしていない“紙の損”なので、まだ確定した損失ではありません。たとえば1000円で買った株が現在700円なら、含み損は300円です。この数字は市場の動きで日々変わります。この含み損があるからといって必ず損を確定するわけではなく、株価が回復すれば損は消え、売却しなければ実際には損にはなりません。含み損の状態を怖がりすぎず、現在の資産全体のバランスと自分の投資計画と照らして考えることが大切です。なぜ大事かというと、含み損は感情に影響を与えやすく、安易に売ってしまう“衝動売り”につながることがあるからです。落ち着いて判断するためには、以下のポイントを押さえましょう。①自分の投資目的と期限を確認する②リスク分散を意識する③長期の視点で市場全体の推移を見る。実際には、含み損は現金の減少ではなく紙の損にすぎず、税金も「実際に売却して利益が確定したとき」に発生します。必要以上に焦らず、計画的に対処することが大切です。もし含み損が気になる場合は、専門家に相談するのも良い方法です。
- 株 含み損 とは
- 株を買うとき、含み損という言葉を耳にします。含み損とは、今の市場価格と自分が買ったときの価格の差のうち、まだ売っていない損のことを指します。つまり現在の価格が安くなっていても、実際にお金を失っているわけではありません。株を売らない限り、損は“紙の上の評価”にとどまります。例えば、1000円で3株を買ったとします。現在の株価が800円なら、1株あたり200円の含み損となり、3株なら600円の含み損です。これが「含み損」です。反対に、現在の価格が1200円なら、含み損は“含み益”に変わり、実際にはまだ手元のお金は動いていません。株の世界には、含み損だけでなく含み益もあります。実際の利益や損失は、株を売ってお金を受け取ったときに確定します。これを“実現損益”と呼びます。売却せずに価格が戻れば、含み損は解消されて損失がなくなることもありますし、さらに下がれば損失が拡大します。つまり、含み損は市場の動きに左右される“未確定の評価額”です。投資の判断に使うときは、含み損の金額だけに焦って売買を決めないことが大切です。以下のポイントを押さえておきましょう。- 分散投資でリスクを分ける- 長期的な視点を持つ- 事前に売るライン(損切り)を決めておく- 無理に追いかけず、価格の上下に振り回されないこれらを意識すると、含み損の状態でも落ち着いて判断できます。株式投資は元本が減る可能性もある反面、長い目で見ると回復することもあります。焦らず、学びながら少しずつ理解を深めていきましょう。なお、含み損は税金の計算には使われません。税金は実際に売って利益が出た場合に課税対象となるのが基本です。別のケースでは損失を繰り越して将来の利益と相殺できる制度もあるため、状況に応じて確認しましょう。
- 債券 含み損 とは
- 債券というのは国や企業が資金を集めるために発行する借金の証書です。購入すると一定の利息が支払われ、満期が来ると元本が返されます。市場では金利の動きに合わせて債券の価格が上下します。この価格の上下を含み損・含み益と呼びます。含み損とは“まだ売っていないのに価値が下がっている損のこと”を指します。つまり、今の市場価格が自分が買った時の価格より低い場合に生じます。たとえば100,000円で買った債券が、市場の金利上昇で95,000円の値段になったとします。これが含み損5,000円です。まだこの債券を売っていなければ損は確定していません。売れば5,000円の損失が確定します。逆に市場価格が110,000円になれば含み益10,000円となります。なぜそんなことが起きるのでしょうか。債券の価値は金利と反対方向に動くことが多いです。新しく発行される債券はより高い利率になることが多いため、古い債券の魅力が下がり、価格が下がるのです。金利が下がれば逆に古い債券の価格が上がり、含み益が増えます。含み損は実際に売らない限り確定しません。損益は売却のタイミングで決まります。投資の方針によっては、含み損を抱えたまま長く持つ場合もあれば、一定のルールで売却する場合もあります。注意点として、元本が必ず戻ってくるとは限りません。債券には信用リスクがあり、発行体が倒産すれば元本が全額戻らないこともあります。特に個別銘柄や高利回り債はリスクが高くなります。初心者は、含み損・含み益を恐れすぎず、金利動向や自分の投資目的・持つ期限を考えながら判断することが大切です。
- 国債 含み損 とは
- 国債 含み損 とは、現在の市場価格が購入時より低い状態を指し、売却して実際の損害が確定する前の未確定の損失です。国債は利子を定期的に受け取り、満期まで保有すると元本が戻りますが、市場で売却する時点の価格が購入時より低い場合には、保有者は含み損を抱えることになります。含み損は、今すぐ現金化しなくても起こりうるもので、投資の成果は実現時点で確定します。価格は金利の動きに大きく左右され、既発行の国債は新しい国債の利回りが上がると価値が下がり、逆に利回りが下がれば価値は上がります。たとえば額面1000円の国債を1100円で買った場合、金利が上昇して市場価格が950円に下落すると、現在の含み損は150円となります。含み損は売る時点で初めて損失として確定しますが、満期まで保有する前提なら元本が回収されるケースもあり、一度発生した含み損が必ずしも損失として確定するわけではありません。実務では、保有方針(短期保有か長期保有か)、税金や取引コスト、ポートフォリオ全体のリスクバランスを考えながら判断します。なお、国債は信用リスクが低いとされますが、金利変動リスクは避けられません。初心者が理解しておくべきポイントは、含み損は現状の評価に過ぎず、売却時の選択肢や今後の金利動向で変わるという点です。
- 外国 債券 含み損 とは
- 外国債券を持つと、よく耳にする“含み損”という言葉があります。含み損とは、今の評価額が買ったときの値段より低くなっている状態で、まだ売っていないので損益を確定していないことを指します。外国債券の場合、評価額は「円換算」で動きます。債券自体の値段が下がるだけでなく、為替レートの変動により円に直したときの金額も変わります。例えば、外国債券を100円で買い、現在の市場価格が95円相当になっていたとしても、円に換算した価値は為替の影響でさらに変わることがあります。含み損の計算の基本は「現在の時価(円換算) minus 取得価額」です。ここで重要なのは、クーポン収入があっても、それだけで損益が確定するわけではない点です。売却して初めて損益は確定します。含み損がある場合でも、長期では回復することや為替が有利に動くと損失が小さくなることもあります。税金の扱いは、実際に売却して損益を確定した時に変わります。日常の評価額はあくまで“現在の評価値”です。外国債券には為替リスクと信用リスクがあるので、分散投資や長期の視点での運用が大切です。初心者の方は、円換算の仕組みと含み損の意味を理解し、ニュースや金利・為替の動きを見る習慣をつけましょう。
含み損の同意語
- 未実現損失
- 現在保有している資産の評価額が取得時より下がっているが、売却していないため損失が確定していない状態のこと。いわば“まだ確定していない損”です。
- 評価損
- 資産の時価が簿価を下回ることで会計上計上される損失のこと。売却済みかどうかにかかわらず、評価額の下落を意味します。
- 紙上損失
- 実際には現金の動きが発生していないにも関わらず、資産の評価額の下落を“紙の損”として表す表現です。
- 時価評価損
- 資産を時価で評価した結果として生じる損。株式や債券などの市場価格変動が原因となることが多い表現。
- 含み赤字
- 企業や口座内で、まだ確定していない赤字の状態を指します。将来的に損失として確定する可能性がある含みの赤字。
- 評価差損
- 評価額と簿価の差が生じて損失になる状態。未実現の段階で現れることが多い用語です。
含み損の対義語・反対語
- 含み益
- 未確定の利益。保有ポジションの評価額が上昇している状態だが、まだ売却していないため実現していない利益。
- 評価益
- 時価評価などによって生じる利益。市場価格の変動に基づく未確定の利益として使われることが多い。
- 実現益
- ポジションを売却・決済して確定した利益。現金として手元に入る利益。
- 確定益
- 実現済みの利益の別称。実現益とほぼ同義で使われることがある表現。
- 実現損
- ポジションを売却・決済して確定した損失。現金として実際に出る損失。
- 確定損
- 実現済みの損失の別称。実現損とほぼ同義で使われることがある表現。
含み損の共起語
- 未実現損
- まだ確定していない損失。現在の含み損の状態を指す。
- 未実現損益
- 未確定の損益の総称。含み損と含み益を合わせた概念。
- 含み益
- 株価上昇などにより未確定の利益。決済前の利益状態。
- 評価損
- 会計上の評価額が下落して生じる損失。実現していない損失も含むことがある。
- 評価額
- 現在の市場価値での資産の評価額。
- 元本割れ
- 投資の元本を下回る評価・損失状態。
- 実現損益
- 取引を決済して確定した損益。税務上も実現利益・損失として扱われる。
- ロスカット
- 証拠金維持率が一定以下になると自動的に決済される仕組み。
- 損切り
- 含み損を確定させるための売買。リスク管理の基本手段。
- 証拠金維持率
- 取引を維持するのに必要な証拠金の割合。低下すると追証やロスカットの可能性。
- 追加証拠金
- 証拠金不足分を追加で入金すること。維持を図るために必要。
- 追証
- 追加の証拠金の入金を求められる状態。
- 建玉
- 未決済のポジション。開いた取引の数量と方向。
- ポジション
- 現在保有している買い/売りの取引状況。
- 平均取得価格
- 取得した株式・資産の平均的な取得価格。
- コスト平均法
- 一定額を定期的に投資して取得コストを平均化する手法。
- 株価下落
- 株価が下がる現象。
- 時価評価
- 現在の市場価格で資産を評価する方法。
- 損益
- 総合的な利益と損失のこと。含み損・確定損益を含む広い概念。
- リスク管理
- リスクを抑え、損失を最小化するための方針・手法。
- 分散投資
- 資産を複数の銘柄・資産クラスに分散してリスクを軽減する方法。
- 損切りライン
- 損切りを実行するべき水準を示す目標値。
- 長期投資
- 長い期間で資産を運用する投資スタイル。
- 短期投資
- 短期間での売買を繰り返す投資スタイル。
- 元本
- 投資の元になる資金。
含み損の関連用語
- 含み損
- 未実現の損失。現在の時価が取得価格より下がっている状態で、まだ売却して損益を確定していないポジションの評価額の差額。
- 含み益
- 未実現の利益。現在の時価が取得価格を上回っている状態で、まだ売却して利益を確定していない状態。
- 実現損益
- ポジションを売買などの取引で確定した損益のこと。売却時点で初めて利益または損失が確定する。
- 評価損
- 時価評価の差額として認識される損。資産の現在価値が簿価を下回る場合に計上されることが多い。
- 評価益
- 時価評価の差額として認識される利益。資産の現在価値が簿価を上回る場合に計上される。
- 時価評価
- 資産を現在の市場価格で評価する方法。含み損・含み益の算定に用いられる。
- 公正価値
- 取引における公正な市場価格、時価に近い価値。評価の基準として用いられる概念。
- 取得原価
- 資産を取得した際の原価。評価差額の比較対象として用いられる基準値。
- 減損
- 資産の回収可能額が簿価を下回る場合に、簿価を下げて価値を正しく反映する会計処理。
- 減損処理
- 減損を認識して会計帳簿上の価値を減額する手続き。
- 損切り
- 含み損が拡大する前に損失を限定するため、早めにポジションを決済する行動。
- ロスカット
- 証拠金維持率の低下等により、証券会社が強制的にポジションを決済する状態。
- 追証
- 追加の証拠金を請求される状態。含み損の拡大や証拠金不足が原因で発生。
- キャピタルロス
- 資産を売却した際に発生する実現損失。株式や投資信託の売却損。
- キャピタルゲイン
- 資産を売却して得られる利益。売却益のこと。
- 損失繰越
- 税務上、発生した損失を翌年度以降に繰り越して所得から控除できる制度(国や制度によって適用範囲が異なる)。
- 期末評価差額
- 期末時点の時価と簿価の差額。財務諸表の評価額に影響する差額。
- 有価証券評価差額
- 有価証券の時価評価差によって生じる資本項目の差額。株主資本の変動要因となることがある。



















