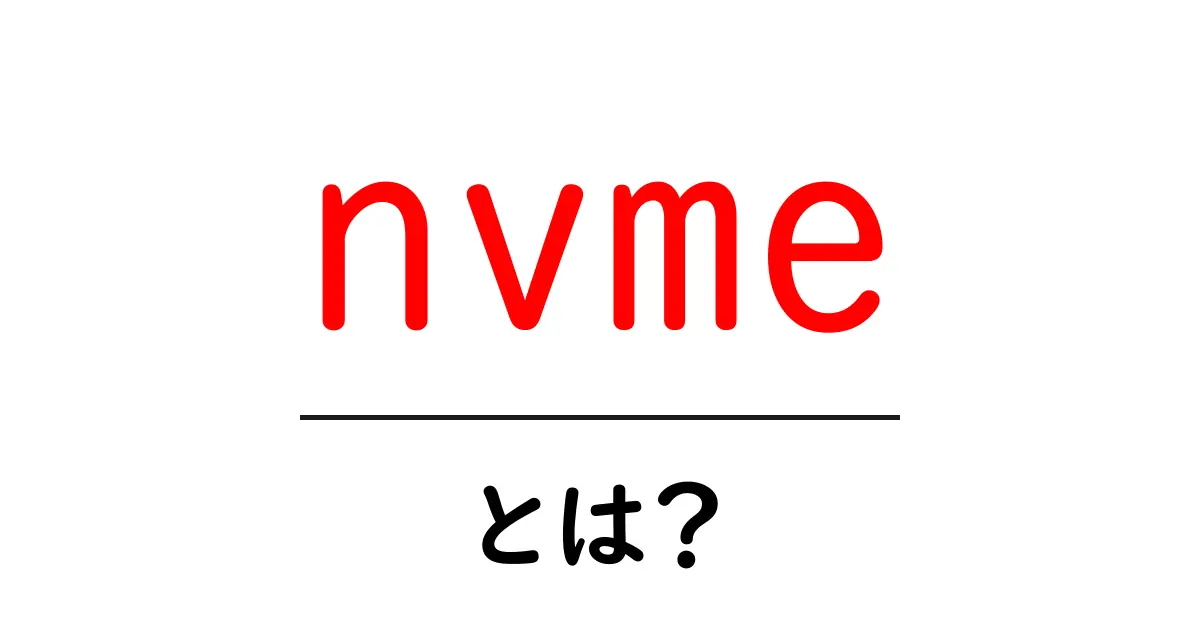

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
nvmeとは何か
nvmeは「NVM Express(NVM Express)」の略で、SSDとPCの間の通信規格のことです。従来のSSDやHDDには
NVMeとSATAの違い
NVMeとSATAの大きな違いは「どのくらい速く、どれだけ同時に処理できるか」です。SATAは昔からある規格で、SSDでも帯域に制限があります。一方、NVMeはPCIeの複数のレーンを使って、同時に多くの命令を処理できる設計になっています。これにより、OSの起動・アプリの立ち上がり・大容量データの転送などが格段に速くなります。
仕組みとメリット
NVMeの肝は「キュー」と「並列性」です。従来のデータストレージは1つの命令列を順番に処理していましたが、NVMeは巨大なキューを持ち、同時に多くの命令を処理できます。その結果、待ち時間が短く、複数の処理を同時にこなせるため、パソコンの体感速度がアップします。実際、OSの起動時間が短縮されたり、動画編集や大きな画像ファイルの読み込みが速くなったりします。
速度の目安と世代
速度は世代と製品によって変わります。Gen3(PCIe 3.0)のNVMeは、実測で数百MB/sから1~2GB/s程度の連続読み書きが目安です。Gen4(PCIe 4.0)では2~7GB/s程度、Gen5(PCIe 5.0)ではさらに高い速度が期待できます。実際には容量、ブランド、データの種類によって差があります。新しい世代のほうが速いのは間違いありません。
実際の選び方のコツ
NVMe SSDを選ぶときのポイントは次の通りです。フォーマット(主に M.2 か PCIeカード)PCIe世代(Gen3/Gen4/Gen5)、容量、耐久性(TBW/保守期間)、予算と互換性です。M.2スロットを持つマザーボードを使っている場合、M.2 の鍵の種類(例: Mキーが多い)にも注意しましょう。OS起動用のNVMeを選ぶ場合は、容量と耐久性を重視すると長く使えます。
導入時の注意点
導入する際の基本は以下の通りです。マザーボードの対応状況を確認すること、PCIe×4対応か、M.2スロットの規格・鍵の種類を確認すること、BIOS/UEFIの設定が正しくNVMeを認識しているかを確認することです。OSのインストール先としてNVMeを選ぶ場合、ドライバの準備やTRIM設定の有効化を忘れずに。さらに、熱管理にも注意しましょう。高速なSSDは発熱が大きくなることがあるため、冷却やケース空間の確保が有効です。
NVMeと他のストレージの使い分けの例
OS起動用にはNVMeを選び、データ用には容量重視のSATA SSDやHDDを使うと、コストを抑えつつ快適さを両立できます。ゲーム用のストレージにもNVMeは向いていますが、容量あたりの単価を考慮して用途に応じて選ぶとよいでしょう。
表で見るNVMeの基本比較
まとめ
nvmeはNVM Expressの略で、PCIe接続で高速にデータをやり取りするSSDの規格です。従来のSATAと比べて圧倒的に速く、OSの起動やアプリの起動が快適になります。世代が新しいほど速くなる傾向があるため、購入時には世代・フォーマット・容量・耐久性・互換性をチェックして選ぶと失敗が少なくなります。
nvmeの関連サジェスト解説
- nvme とは わかりやすく
- nvme とは わかりやすく解説します。まずNVMeとは何かを知ることから始めましょう。NVMeはNon-Volatile Memory Expressの略で、従来のAHCIという規格より新しく、SSDがCPUと直接高速でやりとりできるように作られた規格です。従来のSATA接続のSSDは最大約550MB/s程度ですが、NVMeはPCIeという高速な通信路を使うため、数千MB/sの超高速が狙えます。特にGen3やGen4のPCIe規格を使うと、読み書きの速度が大きく伸び、OSの起動やアプリの起動、ファイルの転送が体感で軽快になります。M.2やU.2といった形状の製品があり、必ずしもSSDの全てがNVMe対応というわけではありません。M.2スロットにはNVMe対応とSATA対応の両方があるので、買う前に“NVMe (PCIe)対応”と書かれているかを確認しましょう。実際の速度は製品の世代(Gen3, Gen4, Gen5)と搭載しているPCIeレーン数、そして冷却性能に左右されます。例えばGen3 x4のNVMeなら読み書きともに数千MB/s、Gen4以上ならさらに速くなる場合が多いです。ただし、すべての用途でNVMeが必要というわけではありません。日常のウェブ閲覧やオフィス作業ならSATA SSDでも十分速く感じますが、OSの起動や大容量ファイルの処理、ゲームのロード時間を短縮したい人にはNVMeが強い味方です。購入時には容量、耐久性(TBW)、保証、冷却性にも注意しましょう。取り付けは、まず外部でM.2スロットがNVMeに対応しているかを確認します。BIOSでNVMeを優先起動に設定することもあるので、必要に応じて設定を見直してください。初めての人でも、現状のPCやノートPCの仕様表を確認すれば、NVMe対応かどうかは調べやすいです。
- nvme とは ssd
- nvme とは ssd というキーワードは、現代のストレージを理解するうえでとても重要です。NVMeはNon-Volatile Memory Expressの略で、SSDがデータをやり取りする“約束ごと”のような規格です。従来のSATA接続よりも高速にデータをやり取りできるよう設計されており、PCの起動やゲームのロード時間を大幅に短縮します。NVMeは必ずしもSSDを意味するものではなく、NVMeという規格を使っているSSDをNVMe SSDと呼ぶのが一般的です。一方でSATA SSDは、SATAという古いインターフェースを使い、速度はNVMe SSDに比べて遅くなります。形状の主流はM.2という細長いカード形で、マザーボードのM.2スロットやPCIeスロットに装着します。NVMeはPCIeという高速な通信路を使うため、データのやり取りが速く、ファイルのコピーやOS起動、アプリの起動が体感で速くなります。また、SATA SSDとNVMe SSDは共にSSDですが、速度差が大きい点を理解しておくと選びやすくなります。選び方のポイントはシンプルです。まずNVMe対応かどうかを確認します。次にフォームファクター(多くはM.2、一部はPCIeカード)を選び、次にPCIeの世代とレーン数を確認します。Gen3 x4が一般的ですが、予算が許せばGen4やGen5に対応する製品を選ぶとさらに速くなります。容量と価格のバランスを考えましょう。すでにSATA SSDを使っていて体感の速度向上を狙うならNVMe SSDへの交換を検討しても良いです。新しいPCを作る場合はNVMe対応のマザーボードを選ぶと快適さが最大化します。最後に覚えておくべきは、nvme とは ssdは“規格名とデバイスの組み合わせ”を指す言葉であるということです。
- nvme raid mode とは
- nvme raid mode とは、複数のNVMe SSDを1つの大きな容量として使えるようにする設定のことです。NVMeは現在のPCで最も速いSSD形式で、データはPCIeという高速な路を通ってやり取りします。RAIDは複数のディスクを組み合わせ、速度を上げたりデータを守ったりする仕組みです。nvme raid modeを有効にすると、マザーボードのRAIDコントローラがNVMeドライブをまとめ、OSからは個別デバイス名ではなく、1つの論理ドライブとして表示されます。OSのインストール時にはRAID用のドライバを読み込む必要がある場合があり、適切なドライバの準備が大切です。用途としては、高速性を求める用途(ゲームの読み込み、写真・動画の編集、仮想環境の起動など)で2台以上のNVMeを使い、RAID 0で速度を引き上げることが多いです。一方、冗長性を重視する場合はRAID 1やRAID 10などの設定を選ぶと良いですが、RAID 0は容量と速度を最大化する反面、1台でも故障すると全データが失われる点に注意が必要です。NVMeのRAIDは機種やBIOSの世代でサポートされる機能が異なり、すべての構成が可能というわけではありません。有効手順は以下のようになります。まずマザーボードがNVMe RAIDモードをサポートしているか確認します。次にバックアップを取ります。BIOS/UEFIで「RAIDモード」または「NVMe RAID」と表示される設定を有効にします。OSを新規に入れる場合は、RAIDドライバ(例:Intel RST)の用意と、OSインストール時のドライバ読み込みが必要です。すでにOSが入っている場合は、データを保護するためバックアップを取り、RAIDアレイを作成してからデータを移行します。作成したRAIDボリュームはOS上で1つのドライブとして現れ、通常のディスク管理ツールで個別ディスクとして扱うことはできません。注意点として、TRIMやSMARTの扱い、ファームウェアの互換性、ブートドライブとしての設定手順、DRAMキャッシュの影響などがあります。初心者は最初からRAIDを使うより、バックアップ重視のRAID 1などから試すと安全です。また、RAIDをセットアップする前に現状のデータを必ずバックアップすることが重要です。
- nvme gen4 とは
- nvme gen4 とは、SSDの新しい高速規格のことです。NVMe は Non-Volatile Memory Express の略で、SSDとパソコンのCPUがデータをやり取りする仕組みを速くする設計の名前です。従来のSATA接続のSSDよりも読み書きが速く、パソコンの動作がすっきり軽く感じられることが多いです。gen4 はこの NVMe の“世代”の名前で、PCIe の第4世代を使います。PCIe 4.0 は前の世代 3.0 に比べて伝送速度が約2倍近く速く、通常は同じ x4 レーンで最大の性能を発揮します。結果として、ファイル転送やOS起動、ゲームの読み込みなど、日常の操作が体感的に速くなります。ただし現実には実測値は機種や使い方で変わります。熱に弱い場合もあり、長時間の連続使用で速度が落ちることがあります。購入時は、マザーボードが PCIe 4.0 に対応しているか、CPU や BIOS が Gen4 をサポートしているかを確認しましょう。さらに SSD 自体が PCIe 4.0 対応(NVMe 対応)であることを確認して選ぶと良いです。Gen3 環境でも使えますが、Gen4 の真の速さを引き出すには PCIe 4.0 対応環境が必要です。実用的には、OS の起動時間やアプリの読み込み、ゲームの読み込み、動画編集などの作業がスムーズになり、日常の使い勝手が向上します。
- nvme tcp とは
- nvme tcp とは、NVMe over Fabrics の一形態で、ストレージデバイスとホストコンピュータの間で高速なデータ伝送をTCP/IPの上で実現する仕組みです。NVMeはもともとPC内部のSSD用の高速プロトコルで、PCIeに直結して超高速な入出力を可能にします。しかし、現場では複数のサーバーが同じSSDをネットワーク経由で使いたい場面があり、NoF(NVMe over Fabrics)が登場しました。NoFはNVMeコマンドをファブリックと呼ばれるネットワーク経路で運ぶ仕組みで、TCPを運搬手段として使うのがNVMe/TCPです。TCPは私たちが普段使うインターネットの基本プロトコルなので、特別な専用線がなくても導入しやすいのが特徴です。使い方は、サーバー側にNVMe/TCP対応のストレージアレイ(ターゲット)を用意し、クライアント側にNVMe/TCPドライバを組み込んだOSを配置します。両者はTCPのポートを通じて通信し、NVMeコマンドとデータをネットワーク越しにやり取りします。これにより、データセンターの量販型のハードウェアを使いながら、複数のホストから高速アクセスが可能になります。利点は、既存のEthernet設備を活用できる点と、コストを抑えやすい点、設定が RDMA系よりも直感的で学習コストが低い点です。一方で、TCPのオーバーヘッドやネットワークの混雑、遅延の影響を受けやすく、RDMA系と比較すると最小のレイテンシは低くなる傾向があるため、用途に応じて選ぶ必要があります。導入の際は、ネットワークのMTU設定(ジャムフレームの導入)、ファブリックの信頼性、セキュリティ対策、ストレージの冗長性、バックアップ計画などを確認します。実運用では、LinuxなどのOSでNVMe/TCPのドライバを有効化し、対象のストレージをボリュームとしてマウントします。まとめとして、nvme tcp とは、コストを抑えつつ高速なストレージアクセスをネットワーク越しに実現する現代的な技術であり、データセンターの拡張性を高める選択肢として注目されています。
- nvme namespace とは
- nvme namespace とは、NVMeと呼ばれる高速なSSDの世界で使われる“仮想のディスク”のことです。NVMeはPCIeという高速な接続を使ってSSDとやり取りします。従来のハードディスクよりも速く、遅延が少ないのが特徴です。名前空間(namespace)は、このNVMeデバイスの中に作られる“ディスクの区分”のようなものです。1つのコントローラ(NVMeデバイスの頭脳)に対して、複数の名前空間を作ることができ、それぞれ独立した容量や識別子を持ちます。OSは名前空間を個別のブロックデバイスとして認識し、/dev/nvme0n1 や /dev/nvme0n2 のように見えることが多いです。名前空間同士は同じ物理デバイスを共有しますが、データは別々に管理されます。実際の使い方としては、OSの起動用とデータ用を分けたい場合や、仮想化環境で複数の仮想ディスクを準備したい場合などに名前空間を活用します。消費者向けのSSDでは通常1つの名前空間しか提供されないことが多いですが、企業向けのSSDや特定の設定では複数の名前空間を作って運用することがあります。注意点として、名前空間を作成・削除するとデータが消える可能性があるため、作業は慎重に行う必要があります。名前空間の確認や管理は、Linuxのnvmeコマンド群やブロックデバイスの知識があると便利です。
- nvme-cli とは
- nvme-cli とは Linux 上で NVMe SSD を操作・情報取得するためのコマンドラインツールです。NVMe は PCIe 接続の高速なストレージ規格で、従来のSATAよりも高速な読み書きが可能です。nvme-cli を使うと、接続されている NVMe デバイスの識別や、コントローラの基本情報、名前空間の状態、SMART データ、ファームウェアのログなどをコマンド一つで確認できます。導入にはディストリビューションごとにコマンドが異なることがあります。例えば Debian 系なら sudo apt-get install nvme-cli、Red Hat 系なら sudo dnf install nvme-cli といった手順です。実際の使い方の例を挙げます。- デバイスの一覧を表示する: sudo nvme list- コントローラ情報を取得する: sudo nvme id-ctrl /dev/nvme0- 名前空間の情報を確認する: sudo nvme ns-list /dev/nvme0- SMART情報を確認する: sudo nvme smart-log /dev/nvme0- ファームウェアのログを確認する: sudo nvme fw-log /dev/nvme0 これらのコマンドは root 権限を要することが多いので、前に sudo を付けて実行します。日々の運用やトラブル対応、ハードウェアの状態チェックに役立つ便利なツールです。初めて使う人は公式ドキュメントを読んで安全に操作できる範囲を理解してから試してみてください。
- ストレージ nvme とは
- NVMeとはNon-Volatile Memory Expressの略です。NVMeはSSDをPCやノートPCのCPUと高速に接続するための通信規格で、従来のSATAより大きな帯域と多くの同時要求を処理できます。SATA接続のSSDは最大約500~550 MB/s程度の実測速度が出るのに対し、NVMe SSDはPCIeバスを使い、世代とレーン数によって大きく速度が変わります。例えばPCIe 3.0 x4の環境なら数千MB/s、PCIe 4.0 x4なら5000~7000MB/s級も現実的です。もちろん実測値は機器や設定次第ですが、日常の起動やゲームのロード、ファイルのコピーといった場面で体感できる差が大きくなります。形状は主にM.2とPCIeカード型の2種類があり、M.2は小さな板状の形でノートPCにもよく使われます。導入のポイントは、マザーボードの対応(NVMeとM.2スロットの有無、PCIeの世代)、冷却対策(高性能モデルは熱で速度が落ちることがあるためヒートシンクを使うと安定します)、容量と予算です。デスクトップなら複数のNVMeドライブを組み合わせてストレージとOS起動を分ける構成も人気です。OSの起動ディスクとして使う場合は、バックアップとクローン作成の手順を事前に確認しましょう。NVMeを選ぶときは、用途(起動・ゲーム・動画編集・大容量データの扱い)と予算を軸に、読み出し・書き込み速度の公称値と実測値を比較します。最新世代ほど速度は高いですが、コストも上がるため、自分の用途と予算のバランスを意識してください。
- ahci/nvme とは
- この記事では、ahci/nvme とは何かを、初心者にも分かる言葉で解説します。まず AHCI は Advanced Host Controller Interface の略で、SATA という古くから使われている接続規格を動かすためのルールです。HDD や SATA SSD でよく使われ、機器同士のやりとりを決める「話し方」が AHCI です。次に NVMe は Non-Volatile Memory Express の略で、PCIe という高速な道を使って SSD と CPU がデータをやりとりします。NVMe は並列性を活かせるため、同時に多くの処理をこなせます。結果として、OS の起動、アプリの起動、ファイルのコピーなどが速く感じられます。実際の違いは、接続の仕方と伝送速度の差です。SATA 接続の HDD/SSD は最大帯域が限られており、現代のNVMe PCIe に比べて遅くなります。一方、NVMe PCIe の SSD は PCIe の世代とレーン数によって速度が変わり、最新の環境では数倍から十倍程度の差が出ることもあります。パソコンを選ぶときは、OS やアプリを速く動かしたい場合は NVMe の SSD を選ぶと良いでしょう。予算が限られる場合は SATA の SSD でも HDD よりはるかに速く、十分日常用途には快適です。初心者の方には、接続規格の名前とその意味を覚えるよりも「速さが違う」という直感を持つことをおすすめします。
nvmeの同意語
- NVMe
- 非揮発性メモリExpressの略称。現在主流のSSDインターフェース規格で、PCIeを介して高速なデータ転送を実現するプロトコルです。
- NVM Express
- NVMeの正式名称(英語表記の規格名)。NVMはNon-Volatile Memory、Expressは高速な通信規格を示します。
- Non-Volatile Memory Express
- NVMeの英語の完全表記。非揮発性メモリを高速に接続するための規格です。
- NVMeプロトコル
- NVMe規格が定めるデータ転送の通信プロトコルのこと。ホストとストレージ間のやり取り方法を規定します。
- NVMe規格
- NVMeの公式な規格全体を指す表現。I/Oキューやコマンドセットなどを含みます。
- NVMeオーバーファブリックス
- NVMe over Fabricsの日本語表現。ネットワーク経由でNVMeストレージを提供・利用する技術です。
- NVMe-oF
- NVMe over Fabricsの略。ファブリックを介してNVMe通信を行うことを指します。
- PCIe NVMe
- PCI Expressバス上で動作するNVMeストレージのこと。最も一般的な実装形態です。
- NVMe SSD
- NVMeを用いたSSD。高速なデータ転送を実現するSSDの代表的なタイプです。
- M.2 NVMe
- M.2フォームファクターでNVMeプロトコルを採用したSSD。
- U.2 NVMe
- エンタープライズ向けのNVMe SSDで、U.2規格(旧SFF-8639)に対応した形式です。
- PCIe SSD(NVMe対応)
- PCIe接続のSSDのうち、NVMe規格に対応して高速転送を実現するものを指します。
nvmeの対義語・反対語
- RAM(揮発性メモリ)
- NVMeは非揮発性の高速ストレージ規格ですが、RAMは電源を落とすとデータが消える揮発性のメモリです。用途や特性が大きく異なる点から、対義語的な位置づけになります。
- HDD(機械式ストレージ)
- NVMeはSSD系の高速ストレージを想定しますが、HDDは回転する機械式ディスクで読み書きが遅く、性能面で対照的です。
- SATA(従来のストレージインターフェース)
- NVMeはPCIe接続の高速インターフェースを使います。一方、SATAは旧来の遅めの接続規格であり、性能の違いから対義的に説明されやすいです。
- IDE/PATA(古いインターフェース)
- IDE/PATAはさらに古い接続規格で、NVMeの現代的で高速な特徴と比べて対照的です。
- SATA SSD(SATA接続のSSD)
- SSDですが、NVMeのPCIe接続と比べるとSATA接続のSSDは遅いことが多く、速度の面での対比になります。
- USBフラッシュドライブ(外部ストレージ)
- USB経由の外部ストレージは、内蔵NVMeのSSDと比べて遅い場合が多く、古典的な対比として挙げられます。
- SAS(Serial Attached SCSI)
- SASはエンタープライズ向けのストレージ規格で、設計思想や性能特性がNVMeとは異なります。対義語的な比較として使われることがあります。
nvmeの共起語
- SSD
- 固体ドライブ。NANDフラッシュを用いた高速なストレージデバイスで、NVMeはこのSSDへアクセスするための高速通信規格です。
- PCIe
- PCI Expressの略。NVMeデバイスが接続される高速インターフェースで、世代ごとに帯域が変化します。
- M.2
- 小型フォームファクターのSSD。NVMeはM.2規格のデバイスにも搭載されます(SATA版もあり)。
- U.2
- サーバー向けの2.5インチ形状のNVMeストレージ。SFF-8639などのコネクタを使うことが多い。
- SFF-8639
- U.2のコネクタ仕様。NVMeデバイスの接続に用いられる規格の一つ。
- SATA
- 従来のストレージインタフェース。NVMeと比較すると遅いことが多く、代替としてSATA SSDもあります。
- AHCI
- 従来のSSD/HDD向けのストレージプロトコル。NVMeはこれを使わず、NVM Expressを採用します。
- NVMe
- Non-Volatile Memory Expressの略。SSDを高速に動作させる通信規格。
- NVMe-oF
- NVMe over Fabricsの略。ネットワーク越しにNVMeデバイスへアクセスする技術。
- PCIe Gen3
- PCIeの第3世代。帯域が増え、NVMeの性能を引き出します。
- PCIe Gen4
- PCIeの第4世代。第3世代より帯域が大幅に向上し、NVMeの最大性能を引き出します。
- PCIe Gen5
- PCIeの第5世代。最新の帯域を提供して、さらに高速化します。
- M.2 2280
- M.2フォーマットの代表的なサイズ。22mm×80mmの形状規格。
- 2.5インチ
- SSDの一般的な形状の一つ。従来のSATA・NVMeともに使われます。
- Form factor
- SSDの形状・サイズの総称。M.2、2.5インチ、U.2などを含みます。
- TBW
- Total Bytes Writtenの略。耐久性の指標として、総書き込み容量を示します。
- DWPD
- Drive Writes Per Dayの略。1日あたりの書き込み耐久を示す指標です。
- IOPS
- Input/Output Operations Per Second。1秒あたりの入出力回数で性能を表します。
- Latency
- 処理の遅延時間。NVMeは低遅延が特徴です。
- Throughput
- データ転送速度の総称。シーケンシャル転送の帯域を表します。
- QD
- Queue Depthの略。I/O待ちの深さ。NVMeは高いQDでの性能が強いです。
- Namespace
- NVMeの論理的ストレージ領域。複数の名前空間を作成して分割利用できます。
- DRAM cache
- DRAMによるキャッシュ。読み書きを高速化し、性能を安定化させます。
- NAND
- NANDフラッシュ。SSDの主な記憶媒体で、NANDタイプによって耐久性が変わります。
- TLC
- Triple-Level Cell。1セルあたり3ビット格納。容量は大きいが耐久性は低めです。
- SLC
- Single-Level Cell。1セル1ビット。耐久性・速度が高いが容量は小さいです。
- MLC
- Multi-Level Cell。セルあたり複数ビット。中間的な特性です。
- Endurance
- 耐久性の総称。TBWやDWPDなどで表現します。
- TRIM
- TRIMコマンド。OSとSSDが空きブロックを管理して、長期的な性能を保つ仕組みです。
- Garbage collection
- 不要データを整理して空きブロックを確保する内部機構。性能維持に役立ちます。
- Firmware
- SSD内部のファームウェア。性能・安定性・機能を決定づけます。
- Controller
- SSDの制御部。データの読み書きを実際に制御する頭脳です。
- NVMe 1.3/1.4/2.0
- NVMe規格の主なバージョン。機能と性能の差を決めます。
- Thermal throttling
- 発熱により自動的に性能を抑制する仕組み。過熱対策が重要です。
- Power consumption
- 電力消費量。高性能モデルは消費電力も大きくなりがちです。
- Heat dissipation
- 熱を逃がす設計・対策。適切な冷却が安定運用に不可欠です。
- Encryption
- データ暗号化機能。ハードウェア暗号化で守ることができます。
- OPAL
- TCG OPAL規格による暗号化対応のSSD機能。セキュリティ要件に対応します。
nvmeの関連用語
- NVMe
- NVM Expressの略。PCIe上で非揮発性メモリ(NVM)へ高速にアクセスするためのストレージプロトコル。
- NVMe over Fabrics
- NVMeコマンドをネットワーク越しに利用する技術。RDMAやFCなどのネットワークを使ってデータセンター内で高速に共有する。
- PCIe
- Peripheral Component Interconnect Expressの略。SSDを含む拡張カードを接続する高速インターフェース。
- PCIe Gen3
- PCIeの第3世代。1本あたりの転送速度が向上し、NVMeの性能を引き出す基盤。
- PCIe Gen4
- PCIeの第4世代。Gen3より約2倍の帯域を提供し、NVMeの最大性能を更に引き出す。
- PCIe Gen5
- PCIeの第5世代。さらに高速化され、最新のNVMeで最高峰の性能を狙える規格。
- M.2
- 形状規格のひとつ。薄い基板にSSDを搭載する小型フォームファクター。
- U.2
- 企業向けのNVMe形状規格。主に高性能サーバで使われ、SFF-8639コネクタを使用することが多い。
- M.2 2280
- M.2の代表的なサイズ。幅22mm、長さ80mmの規格。
- NVMeドライバー
- OSがNVMeデバイスと通信するためのソフトウェア。WindowsやLinuxで提供される。
- AHCI
- 従来のSATA向けホストコントローラ仕様。NVMeでは使われず、古い規格の代替としては非推奨。
- SATA
- 従来のストレージ接続規格。NVMeに比べて速度が劣るが互換性が高い。
- 3D NAND
- NANDフラッシュの3次元積層構造。容量が大きく、耐久性とコストのバランスが良い。
- NAND
- 不揮発性メモリの総称。SSDの基本データ保存媒体。
- MLC
- Multi-Level Cellの略。1セルに複数のビットを格納するNAND。耐久性とコストのバランスが良い。
- TLC
- Triple-Level Cellの略。1セルに3ビット格納。容量は大きいが耐久性・寿命は低め。
- QLC
- Quad-Level Cellの略。1セルに4ビット格納。容量最大だが耐久性は最も低い。
- SLC
- Single-Level Cellの略。1セルに1ビット格納。耐久性と速度が最も優秀だがコスト高。
- TBW
- Total Bytes Writtenの略。総書き込み容量で見る耐久性の目安。
- DWPD
- Drive Writes Per Dayの略。日あたりの書き込み耐久性を指標化したもの。
- IOPS
- Input/Output Operations Per Secondの略。1秒あたりのI/O回数の指標。
- Throughput
- 転送速度の指標。MB/sやGB/sで表されるデータ転送量。
- Latency
- 遅延。要求から応答までの時間。低いほど高速。
- Queue Depth (QD)
- 同時に処理できるI/Oの数。大きいほど並列処理が進む。
- Namespace
- NVMeデバイスを区切って使える仮想領域。複数の空間を作って割り当てる概念。
- Controller
- SSD内部のコントローラ。データの処理・エラー処理・通信を統括する工学部品。
- Firmware
- SSD内部のファームウェア。性能・安定性・新機能を決定づけるソフトウェア。
- TRIM
- OSから未使用ブロックを通知してガベージコレクションを促すコマンド。
- S.M.A.R.T.
- Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technologyの略。ドライブの健康状態を監視する機能。
- Wear Leveling
- 書き込みをセルに均等に分散して寿命を延ばす技術。
- DRAM Cache
- SSD内部に搭載するDRAMをデータのキャッシュとして使用する仕組み。
- DRAMless
- DRAMキャッシュを搭載していない設計。ホストメモリや他の手法でキャッシュを補う。
- HMB (Host Memory Buffer)
- ホスト側のメモリをキャッシュとして使用する機能。
- Pseudo-SLC cache
- 偽SLCキャッシュとも。実質SLCで書込みを一時的に高速化する領域。
- Power Loss Protection (PLP)
- 停電時のデータ喪失を防ぐ保護機構。
- 4Kn
- 4Kネイティブセクタ。1セクタあたり4096バイト。
- 512e
- 512バイトセクタを4K物理セクタでエミュレートする規格。
- 4Kn-512e
- 物理は4Knだが、一部OSで512eとして扱われる中間的な設定。
- Hot Plug
- 稼働中の機器を電源を落とさずに挿抜できる機能。
- Thermal Throttling
- 温度が上がりすぎたときに自動で速度を落として温度を下げる機能。
- Form Factor
- SSDの形状・サイズの総称。例: M.2、2.5インチ、U.2 など。
nvmeのおすすめ参考サイト
- NVMeとは? M.2 SSDを知るうえで欠かせない用語の基礎知識
- NVMeとは | 用語集 | HPE 日本
- 【かんたん解説】M.2 SSDとは?NVMeとは? - バッファロー
- NVMeとは - IBM
- M.2 SSDで見かける「NVMe」とは?SSD選びに役立つ用語の基礎知識
- メモリ基本講座「NVMe とは何ぞや」|TECHブログ
- NVMeとは | 用語集 | HPE 日本
- NVMeとは- NVMe SSDのメリットとユースケース | NetApp



















