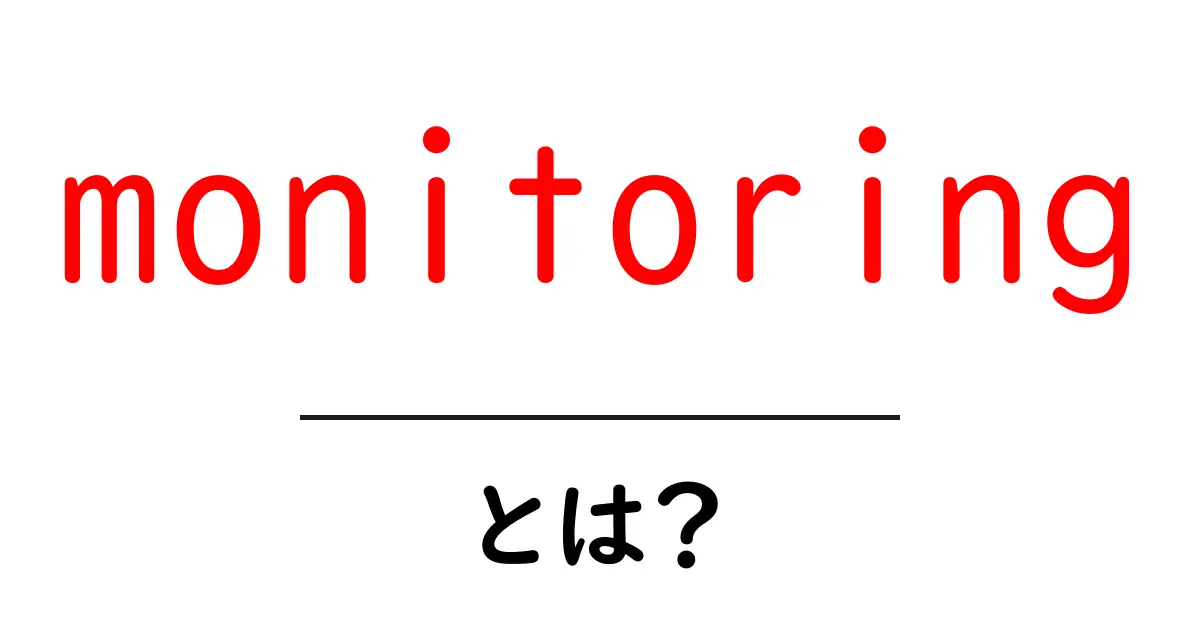

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
monitoringとは何かを、初心者にも理解できるように解説します。
monitoringとは?
monitoringは、物事を継続的に観察して、状態を把握し、問題が起きたときに知らせる仕組みです。
日常の例としては、天気予報の観測、スマートフォンのバッテリーレベルの監視、家のセキュリティカメラの稼働状況などがあります。ITの世界でも同じ考え方を使います。
ITのmonitoringの基本
ITのmonitoringは、サーバやネットワーク、アプリケーションの動作を継続的に監視して、正常かどうかを判断します。
つまり、「何が起きているのか」を知ることと、「異常を早く知らせる」ことが目的です。
よく使われる用語の例をいくつか挙げます。
- 監視項目: CPU使用率、メモリ使用量、ディスクの空き容量、レスポンスタイム、エラーレートなど
- 閾値: 一定の値を超えたときにアラートを出す基準
- アラート: 異常を通知する仕組み、メールやチャット、ダッシュボードで表示
monitoringの種類
以下のようなタイプがあります。
実務で使われるツールの例もご紹介します。
monitoringは単なる「監視」ではなく、データを集めて分析し、意思決定を支えるプロセスです。良いmonitoringを作ると、問題が大きくなる前に対応でき、サービスの信頼性を高めることができます。
良いmonitoringを作るコツ
一度に多くの指標を追いかけると混乱します。最初は以下の3つを押さえましょう。
- 第一のコツ: 重要な指標を絞る、何がビジネスに直結しているかを選ぶ
- 第二のコツ: 閾値は現実的に設定、頻繁にアラートが出ると無視されがち
- 第三のコツ: 可視化を工夫、ダッシュボードをわかりやすく整える
最後に、monitoringを学ぶときのポイントをまとめます。
- 目的: 状態を把握して早期対策をすること
- 対象: サーバー、ネットワーク、アプリ、サービス全般
生活の中のmonitoringの活用例
家庭にもmonitoringの考え方は広がっています。スマートメーターで電力消費を把握したり、ペット用のカメラで留守中の様子を確認したり、子どものスマホの利用状況を見守るアプリを使うことも、monitoringの応用です。
また、風邪を引かないように体温を記録する、運動のペースを測るといった健康管理の監視も、広い意味でのmonitoringです。
学習と仕事での取り入れ方
初心者がmonitoringを学ぶときは、いきなり難しいツールに手を出さず、身の回りのデータから始めるのがコツです。まずは自分のパソコンやスマートフォンの動作状態を観察して、どのデータが「遅い」「重い」「エラーが出る」といった現象に結びつくかを考えましょう。
次に、少数の指標に絞って記録する習慣をつけます。たとえば「CPUの使用率」「ネットワークの応答時間」「アプリのエラーレート」の3つだけを日々ノートに書く、という方法です。これだけでも、問題が発生したときに原因を追いやすくなります。
まとめ
monitoringは、物事を“ただ見る”のではなく、状態を理解し、異常を早く知らせ、対策を取るための仕組みです。インターネットの世界だけでなく、生活の場面にも広がっており、データを正しく集め、整理して活用する力が求められます。
monitoringの関連サジェスト解説
- synthetic monitoring とは
- synthetic monitoring とは、実際の訪問者がサイトを使うのを待つのではなく、事前に用意した操作手順を自動で再現して、ウェブサイトやアプリの応答性・可用性を測定する監視手法です。これはリアルユーザーモニタリング(RUM)と対なる考え方で、RUMが実際の利用者のデータをそのまま観測するのに対し、synthetic monitoring は“予定した動作”を一定の間隔で繰り返します。\n\n仕組み:\n- モニターの種類として HTTP チェック、ブラウザベースのトランザクション(Selenium やヘッドレスブラウザ)、API 呼び出しの検証などがあり、世界各地のサーバーやクラウドから同じ手順を実行します。得られる指標は、応答時間、アップタイム、エラー率、ページの読み込み完了までの時間(TTFB など)です。\n\n用途とメリット:\n- リアルなアクセスが少ない時間帯でも常に監視でき、ダウンを未然に発見しやすい。\n- 地理的な分布がある場合でも各拠点の性能を比較できる。\n- 観測データの再現性が高く、変更前後の影響を検証しやすい。\n\n注意点と限界:\n- 実際のユーザーが遭遇するレイテンシの幅や、動的な個別の行動を必ずしも再現できない。\n- 外部依存(広告ネットワーク、CDN、決済ゲートウェイ)の挙動は同時に測定できない場合がある。\n- コストがかかる場合がある。\n\n導入の流れ:\n- 1) 監視対象となる“重要な業務トランザクション”を洗い出す\n- 2) ツールを選定し、シナリオを作成する\n- 3) 世界各地のモニタリング地点を設定する\n- 4) アラート閾値を決め、通知ルールを作る\n- 5) ダッシュボードで結果を可視化し、問題が起きたら自動で対応する仕組みを組み込む\n\n実務のヒント:\n- シナリオは現実的な操作を想定し、入力データはダミーを使う。\n- 頻度は24時間運用を前提に段階的に増やす。\n- 変更ごとにテストを回して影響を確認する。\n\nまとめ:\n- synthetic monitoring とは、予定した操作を自動で実行してウェブやアプリの性能を定期的に検証する方法です。RUMと組み合わせると、実際の利用と潜在的な問題の両方を把握でき、信頼性の高いサイト運用に役立ちます。
- mic monitoring とは
- mic monitoring とは、マイクに入る声をそのまま自分の耳で聴ける機能のことです。配信や録音をする人にとって自分の声の大きさやマイクとの距離を実感しやすく、聞き手にとって伝わりやすい音づくりができます。主に二つの方法があります。直接モニタリング direct monitoring は マイクの信号がパソコンや機材を通らずにそのままヘッドホンへ届く仕組みです。遅延がほぼなく、歌やスピーチのタイミングが取りやすいのが利点です。もう一つはソフトウェアモニタリング software monitoring で、録音ソフトを通して音を聴く方法です。パソコンの処理遅延により少し遅れて聴こえることがあり、細かなタイミングが難しく感じることがあります。設定のしかたは機材によって少し違います。多くのマイクは直接モニター用のスイッチやつまみがついています。音の出力先をヘッドホンにして direct monitor を ON にするだけの機材もあれば、DAW のトラックモニター機能をオンにして音を聴く方法もあります。Windows や Mac で音を聴く場合は音量のバランスを整えることが大切です。初めての人は耳を痛めない程度の音量から始め、マイクとの距離は約5センチから15センチを目安に保つと声のノイズやポップを減らせます。モニターを使うときの注意点としては自分の声だけを聴くようにし、部屋の反響にも気をつけましょう。まとめとして mic monitoring とはマイクの入力音を自分の耳で聴く機能のことであり、直接モニターとソフトウェアモニターの二つの方法があります。録音配信を快適にする基本的な道具です。初級者は適切な設定から始め、練習を重ねて音質を高めていきましょう。
- cloud monitoring とは
- cloud monitoring とは、クラウド上のサービスやアプリケーションの動作を継続的に監視して、問題が起きる前に気づき、対応できるようにすることです。クラウドではサーバーやストレージ、ネットワーク、データベースなどが分散して動くため、徹底的な監視が不可欠です。主な目的は可用性の確保、遅さの原因の特定、コストの最適化です。監視は通常、メトリクス(CPU使用率・メモリ・ネットワーク通信量・ディスク容量など)、ログ、トレースの3つのデータを集めて分析します。メトリクスは数値で、グラフとして表しやすく、閾値を設けてアラートを出します。ログは出来事の記録で、いつ、誰が、何をしたかを詳しく追えます。トレースは分散した処理の流れを追跡します。これらを組み合わせると、何が原因で遅くなっているのか、どのサービスが落ちているのかを見つけやすくなります。クラウド監視と観測性の違いも覚えておくとよいです。監視は「現在の状態を知らせる」ことに近いのに対して、観測性は「なぜそうなったかを理解する手がかりを提供する」ことを指します。設定次第で、予兆を発見したり、問題再発を防いだりする力が強くなります。どう導入するかの実践例として、重要なサービスのリストを作り、影響範囲を決めることから始めます。次に基準となるメトリクスを選び、現状のベースラインを作ります。アラートの閾値は過度に鳴らさないように、まずは低頻度の通知から始めます。ダッシュボードを作り、関係者がすぐに現状を把握できるようにします。必要に応じて自動通知や自動対応(自動スケーリング、再起動の自動実行など)を設定します。クラウドサービスごとに基本的な監視機能が用意されているので、まずはそれを有効にしましょう。コストにも注意し、過剰な監視で課金が増えすぎないようにします。実践のコツとしては、小さく始めて徐々に拡張するのが良いです。セキュリティの観点からはIAMポリシーを適切に設定すること、監視データの保存期間を必要最低限にすることも忘れずに。
- configuring-enhanced-monitoring とは
- configuring-enhanced-monitoring とは、サービスの監視機能を通常の監視より詳しく設定し、OSレベルのデータを含む詳細なメトリクスを取得できるようにすることを指します。多くのクラウドサービスでは、通常の監視だけではCPU全体の割合やメモリの実利用量、ディスクI/Oの細かな状況、プロセスの動作状態などを把握しにくいことがあります。enhanced monitoring を有効にすると、CPUコア別の使用率やメモリの実利用量、ディスクI/O、ネットワーク帯域、時にはプロセス一覧やシステムコールの統計といった情報がリアルタイム近くの頻度で取得でき、トラブルの原因を絞り込みやすくなります。設定の流れは大きく次のようになります。まず対象サービスが enhanced monitoring を公式にサポートしているかを確認します。次に、データをどのくらい細かく取得するか、粒度(例:1秒、5秒、60秒など)を決めます。粒度を細かくするとデータ量が増え、コストや管理負荷も増えるため、実務では目的に合わせて最適値を選ぶことが大切です。次に、監視データを保存・表示する先を決め、必要な権限(監視データの書き込みやダッシュボードの閲覧に必要な IAM ロールなど)を用意します。設定を有効化する段階では、管理画面、コマンドライン、または API のいずれかを使います。必要に応じて監視ロールを割り当て、データが CloudWatch などのサービスへ適切に送られることを確認します。最後に、ダッシュボードの作成やアラートの閾値設定を行い、実際にデータが表示・通知されるかをテストします。初めのうちは小さな粒度で始め、少しずつ範囲を広げていくと理解しやすいです。この設定を適切に行えば、CPUのコア別使用率、メモリの実利用量、ディスクI/O、ネットワークの帯域、場合によってはプロセスの挙動まで、通常の監視より詳しい情報を得られ、問題解決のスピードが上がります。一方でデータ量が増えるため、費用が増えることやダッシュボードが煩雑になること、誤検知を増やさないように適切な閾値設定が必要になる点に注意してください。
- risk based monitoring とは
- risk based monitoring とは、臨床試験の監視をすべて同じように見るのではなく、リスクが高い場所にだけ重点を置いて監視する考え方です。従来の監視は現場を何度も訪問して紙の記録を確認する作業が多く、時間と費用が大きくかかります。リスクベース監視では、研究の初めにどこに問題が起きやすいかを分析し、リスクの高い施設やデータの項目を特定します。次に、どのデータが正しく入力されているか、患者が安全に治療を受けているかをチェックします。データは電子的に集約され、異常があればすぐ通知される仕組みを使うことが多いです。こうして監視のリソースを重要な場所に集中させ、時間と費用を節約しつつ品質を保ちます。ただしリスクが低くても、規制の要件や記録の正確さを守ることは変わりません。専門家と研究チームが協力して、データの正確さと患者の安全を守るための計画を常に見直します。初心者にも理解できる基本は、監視は数ではなく質を大事にする考え方と、データの信頼性を高めるための継続的な評価と改善です。
- file integrity monitoring とは
- file integrity monitoring とは、サーバーや端末にある重要なファイルが、誰かに勝手に変更されたり削除されたりしていないかを自動で見張るしくみです。日常的な運用の中で、設定ファイルや実行ファイルなど重要なファイルが不正に改ざんされると、セキュリティが崩れ、サービス停止や個人情報漏えいの原因になりえます。file integrity monitoring を使うと、基準となる“ベースライン”を作り、以後の変更を自動的に検知します。変更があればアラートを出したり、記録を残したり、場合によっては自動的に元に戻す対応を促すこともできます。主な仕組みとしてはファイルの内容をハッシュ値で表す方法や、ファイル属性の差分を追跡する方法があります。監視対象はウェブサーバーの設定ファイルやデータベースの構成ファイル、 Windows のレジストリのキーなど、組織の重要資産に及びます。実装の流れは大まかに次の通りです。まず監視対象となる重要ファイルを選び、監視ツールを選定します。次に基準となるベースラインを作成し、検知ルールを設定します。エージェントをデバイスに導入し、初期ベースラインを取り、日常の変更を監視します。変更時には通知を受け取り、適切な対応を行います。導入のポイントとしては監視の範囲を適切に設定し、誤検知を減らす工夫や、パフォーマンスへの影響を最小限に抑える設定が挙げられます。注意点としてはノイズが多くなることを避けるために対象を絞ること、変更の正当性を確認する手順を整えること、そして長期的な運用で証跡を蓄積することが挙げられます。ファイル改ざんの早期発見はセキュリティの第一歩。日頃の監視と適切な対応を組み合わせることで、組織の信頼性を高めることができます。
- therapeutic drug monitoring とは
- therapeutic drug monitoring とは、体の中に入れた薬の濃度を血液で測り、薬がちょうどよい量で働くように管理する方法のことです。薬には「効く範囲」と「副作用が出やすい範囲」があり、それを超えると効かなくなったり副作用が出たりします。人によって体の大きさや腎臓の働き、他の薬との付き合い方が違うので、同じ薬でも濃度はみんな違います。そこでTDMを使い、定期的に血液を検査して薬の濃度を測ります。測定値が安全で効く範囲に入るように、医師が薬の量や回数を調整します。これにより、薬の効果を高めつつ副作用を減らせます。TDMはすべての薬で必要なわけではなく、特定の薬や病気で役立つことが多いです。検査の結果だけでなく、腎機能の状態や他の薬との付き合い方も考えて、個人に合わせた治療を進めていきます。
- abuse monitoring とは
- abuse monitoring とは、オンラインサービスで利用者に対する暴言・脅迫・嫌がらせ・なりすまし・詐欺・スパムといった abuse に該当する行為を検知し、対処する仕組みのことです。実際には、投稿やメッセージ、アカウントの行動を監視し、事前に決められたルールや機械学習の判断基準に沿って警告・ブロック・通報の流れを作ります。例として、チャットでの暴言や脅迫、なりすまし、スパムの大量投稿、連続的な嫌がらせなどが対象になります。運営者はプライバシーを守りつつ、適正な基準で対応する必要があり、透明性のあるポリシーと利用者への通知が重要です。検知の方法は大きく分けてルールベースと機械学習ベースの二つです。ルールベースは特定のキーワードやパターンを事前に設定し、判断を補助します。機械学習ベースでは大量のデータを学習させ、文脈を理解して誤検知を減らす工夫をします。実際の運用では、システムがアラートを出した後に人間が最終確認を行い、必要に応じてアカウントの制限や投稿の削除、アカウント停止などの対応を進めます。これによって利用者の安全が高まり、コミュニティの信頼性が保たれます。なお、過剰な監視や個人情報の取り扱いには注意が必要で、法令遵守と倫理的配慮が欠かせません。導入時には目的を明確にし、どういう行為を許すのか・許さないのかをポリシーとして公開し、利用者に分かりやすく説明することが大切です。最後に、中小規模のサービスでも基本は同じで、適用範囲を広げすぎず、コストと効果のバランスを見ながら徐々に強化していくのがおすすめです。
- guardduty runtime monitoring とは
- guardduty runtime monitoring とは、AWSのセキュリティサービスである GuardDuty を使って、実行中の環境で起こる不審な動作を継続的に検知し、通知や対処を支援する仕組みのことです。GuardDuty は専用のエージェントを各サーバーに入れる必要がなく、マネージドサービスとして動作します。実際には、CloudTrail の API 呼び出しログ、VPC Flow Logs、DNS ログなどを分析して、通常の振る舞いと異なるパターンをファインディングとして提示します。ここでいう“実行時の監視”は、デプロイ後も日常の運用中に常に監視を続けるという意味です。例えば、普段は発生しない大量の新規アクセス、普段使わないリージョンからの通信、正規のキーが急に変更された場合などを検知します。検知はリアルタイム性が高く、通知先を設定すれば即座に担当者が対応できます。設定の流れは次の三つです。1) GuardDuty を有効化し、対象リージョンとデータソースを選ぶ。2) Findings(検知結果)を確認し、どのファインディングが緊急度の高い脅威かを判断する。3) EventBridge/CloudWatch Events などと連携して、SNSやSlack、PagerDuty などへ通知を出し、自動化された対処手順(例えばセキュリティグループの変更、鍵のローテーション、インスタンスの隔離)を実行する。導入時のコツは、最初は小さな環境で試すこと、ベースラインの振る舞いを理解すること、誤検知を減らすためにファインディングの詳細を読み解く訓練をすることです。運用が進むと、インシデント対応のプレイブックを作成し、検知後の手順を自動化して人手を減らせます。初心者には、まず GuardDuty を有効化して「ファインディングを観察する」段階から始め、徐々に通知と対処の自動化を追加していくのがおすすめです。
monitoringの同意語
- 監視
- 対象を継続的に監督・観察する行為。ITや運用ではシステムの健全性や安全性を保つ基本語として使われます。
- 観察
- 対象を注意深く見ること。監視の一部として使われることが多いが、継続性の前提がない場面にも使われます。
- モニタリング
- 英語 monitor の和製語。システムの状態をリアルタイムで監視し、異常を検知・通知する作業を指します。
- 追跡
- データの変化を時間軸で追い、動向を分析すること。監視の一部として用いられることがあります。
- 見守り
- 人・資産の安全をそばで見守ること。ITでは比喩的に監視を指す場合もあります。
- 監察
- 公式・正式な監視・検査。公的機関の監視・調査的文脈で使われる語です。
- 稼働監視
- サーバーやサービスの稼働状態を常時監視し、停止や劣化を早期に検知します。
- 状態監視
- システムの状態情報(正常・異常・負荷など)を継続的に監視すること。
- パフォーマンス監視
- 処理速度・応答時間・資源使用量を監視して、パフォーマンスを評価・最適化します。
- ログ監視
- ログデータを収集・分析して異常や問題を検知する方法です。
- データ監視
- データの品質・整合性・完全性を監視して、信頼性を保つ作業です。
- ネットワーク監視
- ネットワークの可用性・遅延・トラフィックを監視すること。
- アプリケーション監視
- アプリの動作・エラー・性能を監視し、問題を早期発見します。
- セキュリティ監視
- 不正アクセス・脅威・異常を検知・対応する監視です。
- リアルタイム監視
- データをほぼ同時に監視する手法。遅延を抑え、即時の対応を可能にします。
monitoringの対義語・反対語
- 未監視
- 監視が全く行われていない状態。継続的な監視が欠如していることを意味します。
- 非監視
- 監視機能が有効でない、あるいは設定上監視が行われていない状態。
- 無監視
- 監視が一切行われていない完全な状態。
- 放置
- 問題や変化をそのまま放置しておく状態。監視と対応が欠けていることを示します。
- 放任
- 監視や管理を任せきりにして、問題を放置する状態。
- 見逃し
- 監視があっても重要な事象を見逃してしまうこと。
- 見落とし
- データやサインを十分に確認せずに見落とすこと。
- 無視
- 監視情報を受け取らず対応しないこと。積極的な対応を避ける態度。
- 介入不足
- 状況を把握しても、適切な介入が不足している状態。
- 観察不足
- データの観察・分析が不足している状態。
- 監視停止
- 現在の監視機能が停止している状態。
- 非監視体制
- 監視を前提としない運用・体制の状態。
monitoringの共起語
- モニタリング
- monitoring の日本語表現。システムやサービスの状態を継続的に監視し、異常を検知して対処する一連の活動。リアルタイムデータの収集と可視化を含むことが多い。
- 監視
- 対象の状態を継続的にチェックする行為。ログ・メトリクス・イベントを活用して問題を早期に発見する。
- 観測性
- システムの内部状態を外部から推測しやすい性質のこと。観測データ(メトリクス・ログ・トレース)を揃えることが重要。
- 可観測性
- 観測性と同義だが、特に外部から状態を見える化して分析する能力を指す。
- 指標
- システムの状態を数値で表すデータ。例: CPU使用率、レスポンスタイム、エラーレート。
- メトリクス
- 指標の総称。連続的な数値データを指すことが多い。
- ログ
- アプリやサーバーの動作記録。後から原因を追跡するのに役立つ。
- ロギング
- ログを収集・保存・管理する作業。
- テレメトリ
- 外部へ送信される監視データの総称。メトリクス・イベント・ログを含む。
- アラート
- 閾値を超えた場合に通知される警告。迅速な対応を促す。
- 警告
- アラートと同義の通知表現。
- 通知
- アラートを届ける手段(メール・Slackなど)。
- アラートルール
- アラートが発生する条件の設定。
- ダッシュボード
- 監視データを視覚的に表示する画面。傾向や閾値を把握しやすい。
- 可視化
- データをグラフや表で表示すること。
- イベント
- 監視対象で発生する出来事。正常・異常を含むログ要素の総称。
- インシデント
- 重大な障害やサービス停止を扱う対応単位。
- 障害
- サービスが正常に動作しない状態。
- 故障
- 機器やソフトの物理的・論理的故障。
- パフォーマンス
- 処理速度・応答性などの性能を指す指標。
- 可用性
- サービスが利用可能な時間の割合。
- SLA
- サービスレベルアグリーメント。契約上の合意された性能指標。
- アプリケーション監視
- アプリの性能・エラー・依存関係を監視。
- サーバー監視
- サーバーのCPU・メモリ・ディスクなどの状態を監視。
- ネットワーク監視
- ネットワーク機器・トラフィックの状態を監視。
- セキュリティ監視
- 不正侵入や脅威を検知する監視。
- 監視ツール
- 監視機能を提供するツール群(例: Prometheus, Zabbix など)。
- 監視基盤
- 監視を支えるインフラと設計思想。
- 監視データ
- 収集されたメトリクス・ログ・イベントなどの総称。
- データ収集
- 監視データを集めるプロセス。
- メトリクス収集
- 指標データを自動的に収集する作業。
- 監視計画
- 監視を設計・計画する文書・プロセス。
- 監視ポリシー
- 監視の運用方針。
- 監視対象
- 監視の対象となるサービスやシステム。
- リアルタイム監視
- 遅延を最小化して即時にデータを取得・表示する監視形態。
- リアルタイム
- データ処理の遅延を最小化して即時性を重視する概念。
- 予知保全
- 過去データから未来の故障を予測して対処する運用手法。
- AIOps
- AIを活用したIT運用・監視の総称。
- 分散トレーシング
- 分散システムのリクエスト経路を追跡する技術。
- トレーシング
- リクエストの経路を追跡すること。
- 閾値
- アラート発生の基準となる閾値。
- 閾値管理
- 閾値の設定・見直しを行う運用。
- アラート通知
- アラートを通知して対応を促す仕組み。
- イベントストリーム
- イベントデータを連続して処理・分析する手法。
- 監視自動化
- 監視と連携した自動化された対応を実装すること。
monitoringの関連用語
- 監視
- システムの状態をリアルタイムで監視し、異常を検知して通知する作業の総称です。指標の収集、閾値の設定、アラートの発行などを含みます。
- 可観測性
- システムの挙動を深く理解できる性質。メトリクス、ログ、トレースなどを組み合わせ、原因を特定しやすくします。
- メトリクス
- CPU使用率や応答時間など、時系列で数値化した測定値のこと。定常的に計測・保管します。
- ログ
- イベントや出来事を記録したデータ。後から原因を追跡するのに役立ちます。
- トレース
- 分散トレースともいい、1つのリクエストがサービス間をどのように辿るかを追うデータ。遅延の原因特定に有効です。
- テレメトリ
- 監視対象から収集する観測データ全般のこと。メトリクス・ログ・イベントなどを含みます。
- アラート
- 閾値を超えたときに運用担当へ通知する仕組み。迅速な対応の要です。
- ダッシュボード
- 指標をグラフや表で可視化する画面のこと。状況把握を容易にします。
- アプリケーションパフォーマンス監視 (APM)
- アプリの応答時間やエラー率など、アプリ寄りの指標を総合的に監視する手法・ツール群。
- SRE(サイト信頼性エンジニアリング)
- 信頼性を高めるための運用思想。監視・自動化・インシデント対応を組み合わせます。
- SLA / SLO / SLI
- SLAはサービス提供条件、SLOは達成目標、SLIはその指標のこと。信頼性の基準を具体化します。
- 根本原因分析 (RCA)
- インシデントの原因を深掘りし、再発防止策を決定する分析プロセス。
- 事象管理
- インシデントの検知・対応・解決・報告までの一連の運用プロセス。
- 監視ツール
- データ収集・アラート・ダッシュボードを提供するソフトウェア群。例としてPrometheusやDatadogなど。
- Prometheus
- 時系列データベースとモニタリングツール。メトリクス収集とクエリが得意です。
- Grafana
- データを美しく可視化するダッシュボード作成ツール。Prometheusなどと組み合わせて使われます。
- Datadog
- クラウドベースの統合監視プラットフォーム。メトリクス・ログ・トレースを1つの場所で管理します。
- New Relic
- アプリのパフォーマンスを総合的に監視するAPMツール。ダッシュボードも提供します。
- Nagios
- 古典的な監視ツールで、サービスの稼働状況を定期的にチェックします。
- Zabbix
- オープンソースの監視ソリューション。幅広い監視対象とアラート機能を備えています。
- NOC(ネットワーク運用センター)
- 企業やサービスの監視を24時間体制で行う拠点・役割。
- ネットワーク監視
- ルーター・スイッチ・通信トラフィックなどネットワークの健全性を監視します。
- インフラ監視
- サーバーや仮想マシン、クラウド資源など基盤の健全性を監視します。
- アプリケーション監視
- アプリケーションの機能性やパフォーマンスを中心に監視します。
- セキュリティ監視
- 不正アクセスや脅威を検知するための監視。SIEM等と連携します。
- レイテンシ
- リクエストが完了するまでの遅延時間。性能評価の基本指標です。
- スループット
- 一定時間あたりに処理できる仕事量。性能のもう一つの指標です。
- エラーレート
- 処理のうちエラーとなる割合。高いと利用体験が低下します。
- アラートポリシー
- どの条件で誰に通知するかを定義した方針。通知のルールを統一します。
- 監視戦略
- 何を監視するのか、どのツールを使うのか、閾値と対応手順を決める計画。
- 監視設計
- 監視の仕組みを設計する工程。データの収集、保管、可視化、保守方針を決めます。
- 可観測性の三大要素
- メトリクス・ログ・トレースの3つを組み合わせて、原因追跡を容易にする考え方。
monitoringのおすすめ参考サイト
- モニタリングとは | クラウド・データセンター用語集
- モニタリングとは?意味を分かりやすく解説 - IT用語辞典 e-Words
- モニタリングとは? 意味や使い方 - コトバンク
- モニタリングとは? わかりやすく10分で解説 - ネットアテスト



















