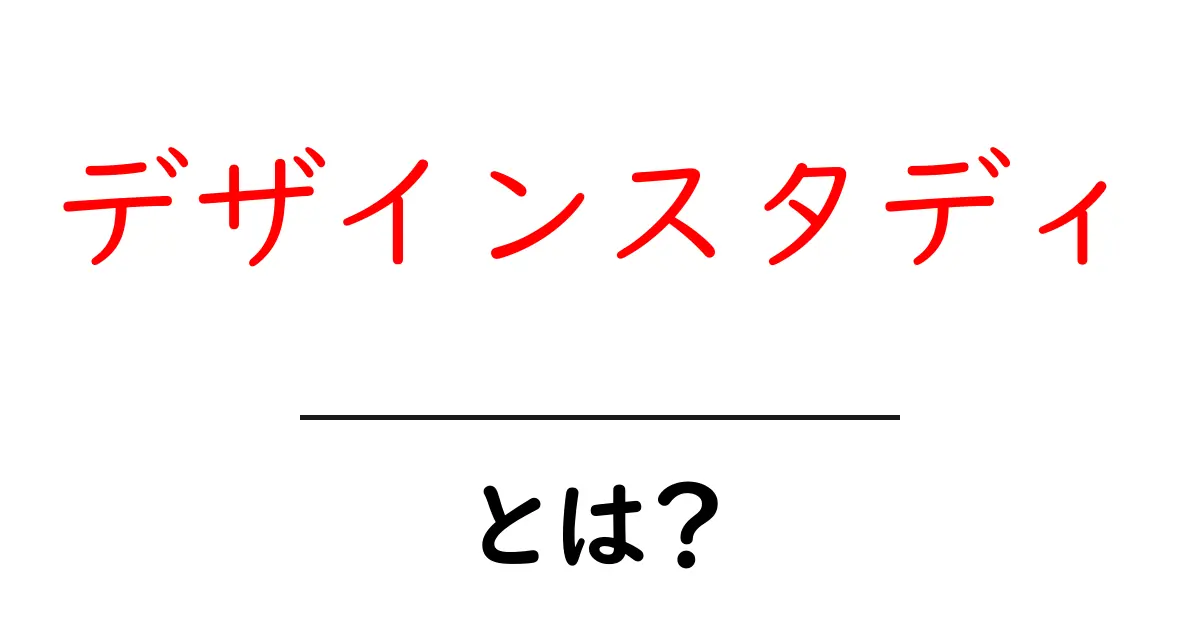

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
デザインスタディとは何か
デザインスタディとは、デザインの考え方や作法を「研究すること」です。デザインは見た目の美しさだけではなく、使いやすさと目的の達成を両立させる技術です。デザインスタディは、観察・分析・仮説・検証という科学的なやり方を取り入れ、作品や製品のよさを探します。初心者の方は、身の回りのデザインを観察して、何が使いにくいか、何が伝わりにくいかを考えるところから始めましょう。
ポイント1: 観察の方法を学ぶ。どこを見て、誰に向けて作られているかを意識します。
ポイント2: 仮説を立てる。例えば「このボタンの色が目立たないのでクリック率が低いのではないか」と仮説を作ります。
ポイント3: 検証する。実際にデザインを変えて、結果を数値や感想で比較します。
デザインスタディの実践ステップ
実践は3つのステップに分けられます。
ステップA: 目的とターゲットを決める。誰に何を伝えたいのかをはっきりさせます。
ステップB: 既存のデザインを分析する。なぜそのデザインが効くのか、どんな課題があるのかを整理します。
ステップC: 改善案を作って検証する。小さな変更からテストを行います。
デザインスタディの実践例
例を一つ挙げましょう。ニュースレターの登録ボタンを考えるとき、色と形を変えた2案を同時に表示して、どちらがクリックされるかを観察します。数日間のデータを集め、クリック率の差を比較します。結果が出たら、より効果の高い案を正式なデザインとして採用します。こうした過程を記録することで、同じ課題に直面したときにも再現性のある判断ができるようになります。
表で見るデザインスタディの要点
| 要点 | 観察・仮説・検証の循環を回すこと |
|---|---|
| 学ぶべき視点 | 使いやすさ・伝わりやすさ・目的適合性 |
| よくある誤解 | 美しさだけがデザインではないこと |
デザインスタディを日常に活かすコツ
日常のデザインはアプリの画面やパンフレット、教科書のレイアウトなど多くの場面に現れます。観察を習慣化し、小さな改善を繰り返すことが上達の近道です。
デザインスタディとデザイン思考の違い
デザイン思考は課題解決の連続的なプロセスであり、共感・定義・ ideation・プロトタイピング・検証を重視します。デザインスタディはこのプロセスを「研究として組み立てる」点が特徴です。目的は結果の再現性と説明力を高めることです。
デザインスタディの学習リソース
本やオンライン講座、データの読み方、比較分析の方法など、学習には順序があります。まずは観察力を鍛え、次にデータの読み方、最後に簡易な実験を自分で設計します。
デザインスタディの同意語
- デザイン研究
- デザインの理論や実践を体系的に探究する研究活動。新しい知見の創出や設計手法の検証を目的とします。
- デザイン調査
- デザインに関する現状・課題・ニーズを把握するための情報収集・分析作業です。
- 設計研究
- 設計分野の原理・方法を探究する研究。建築・プロダクト設計など広い領域で用いられます。
- デザイン分析
- デザインの要素・機能・美学・使い勝手などを分解して理解する分析作業です。
- デザイン探索
- 新しいデザイン案を生み出し、試作・評価を繰り返す探索的なプロセスです。
- ケーススタディ(デザイン領域)
- 実際のデザイン事例を詳しく分析・検討する手法で、実務の学習に用いられます。
- デザインリサーチ
- デザインに関する知見を得るための総称的な研究アプローチで、理論と実践を結ぶことを目的とします。
- デザイン検討
- 複数案を比較・評価し、最適解を決定するための検討プロセスです。
- デザイン比較研究
- 複数デザイン案の差異を比較し、優劣や適用性を検証する研究方法です。
- デザイン実証研究
- デザインの有効性・影響を実データや実験的手法で検証する研究です。
- デザイン思考研究
- デザイン思考のプロセスや効果を検証・評価する研究領域です。
- ユーザー中心デザイン研究
- ユーザーの視点を核にしたデザイン手法の適用・効果を探究する研究です。
デザインスタディの対義語・反対語
- デザイン実践
- 設計理論を学ぶスタディと対比して、実際のプロジェクトでデザインを適用・実行すること。理論を超えて現場での成果を重視する概念。
- デザイン実務
- 現場の業務としてデザインを担当し、実務上の課題解決を優先する状態・動き。
- 現場適用
- デザインのアイデアを現場の条件や制約に合わせて適用すること。研究的な検討より実装を重視する方針。
- 現場設計
- 設計の段階を現場での運用・適用に近い形で進めること。実務寄りの設計活動。
- 実務デザイン
- 実務上のデザイン作業・成果を指す語。研究・分析より作業の完成度・納品を重視する。
- 実務設計
- 実務を前提とした設計作業。理論より成果物の実用性・納期・コストを優先する設計アプローチ。
- 実践志向のデザイン
- デザインを学ぶだけでなく、現場での実践を重視する姿勢。
デザインスタディの共起語
- デザイン研究
- デザイン分野の理論・方法・実践を学術的に探究する活動。新しいデザイン知識を生み出す研究領域。
- デザイン思考
- 人間中心の問題解決アプローチ。共感・定義・アイデア出し・試作・検証の段階から成る思考法。
- デザインプロセス
- デザインの一連の流れ。調査・アイデア創出・設計・検証・実装の段階を通して成果を作る手順。
- デザイン手法
- デザインを進めるための具体的な方法や技法。スケッチ、モックアップ、ペルソナ作成など。
- ケーススタディ
- 具体的な事例を取り上げて、デザインの課題・解決策・成果を分析する手法。
- ユーザーリサーチ
- ユーザーのニーズ・行動を調べる調査活動。観察・インタビュー・アンケートなどを用いる。
- ユーザーインタビュー
- ユーザーと直接対話して情報を得る調査手法。ニーズ・動機・痛点を深掘りする。
- ユーザビリティ
- 使いやすさ・使い心地の良さを評価・改善する設計指向。
- UXデザイン
- ユーザー体験を総合的に設計するデザイン分野。使いやすさ・満足感・価値の提供を重視。
- ユーザー体験
- ユーザーが製品・サービスと関わる全体的な体験。感情・認知・行動の総和。
- 情報設計
- 情報を分かりやすく整理・構造化する設計。目的・伝えるべき情報を適切に配置する。
- 情報アーキテクチャ
- 情報の構造・ラベリング・ナビゲーションを設計する学問・技術。
- インタラクションデザイン
- ユーザーとシステムのやり取りを設計する分野。操作の流れ・反応を設計。
- デザイン教育
- デザインの学習・指導に関する教育活動。カリキュラム・教材の開発。
- デザイン史
- デザインの歴史的発展を研究する分野。時代ごとの特徴や影響を学ぶ。
- デザイン理論
- デザインの原理・美学・機能性などを理論的に解説する分野。
- デザインガイドライン
- デザインの統一性・品質を保つために用意された指針集。
- デザイン原則
- 良いデザインを作るための基本的なルール・基準。
- 色彩設計
- 色の組み合わせ・配色ルールを設計する作業。視認性・美しさ・ブランド性に影響。
- レイアウト
- 情報や要素を配置する設計。読みやすさ・視覚的バランスを重視。
- タイポグラフィ
- 文字の選択・配置・組版の技術。可読性とデザインの表現を左右する。
- 視覚デザイン
- 色・形・タイポグラフィ・写真など視覚的要素でデザインを構築する分野。
- プロトタイピング
- 実体の代替物・モデルを作って検証する過程。早期の学習と評価に用いる。
- ワイヤーフレーム
- 情報構造とレイアウトの骨組みを示す初期設計図。
- コンセプトデザイン
- 製品・サービスの基本的なアイデアと方向性を設計する作業。
- プロダクトデザイン
- 物理的・デジタル製品の形・機能をデザインする分野。
- サステナブルデザイン
- 環境・社会・経済の持続可能性を考慮したデザイン。
- デザイン倫理
- デザイン活動における倫理的配慮。著作権・プライバシー・公平性など。
- デザイン評価
- デザインの有効性・使いやすさ・美観などを評価するプロセス。
- 学術論文
- デザイン研究の学術的な論文・論考。研究成果を整理・発表する文献。
- 学術研究
- 学術的な目的で行われる組織的な研究活動。
- 研究デザイン
- 研究の計画・設計の総称。目的・対象・方法・分析の設計。
- 研究方法
- データ収集・分析の具体的な手法。定量・定性・混合研究法など。
デザインスタディの関連用語
- デザインスタディ
- デザインの課題を把握するための、観察と分析を組み合わせた初期研究のプロセス。ユーザーや状況を理解して設計方針の仮説を立てます。
- デザインリサーチ
- デザインに関わる問題を解決するための調査全般。ユーザー・市場・技術・競合などの情報を集め、設計の意思決定を支える活動です。
- ユーザーリサーチ
- 利用者のニーズ・行動・課題を理解するための定性・定量調査の総称。複数の手法を組み合わせて実データを得ます。
- ユーザーインタビュー
- 利用者と直接対話して動機・課題・期待を深掘りする定性調査です。
- エスノグラフィー
- 現地での長期観察や文化的文脈を把握する定性的手法。深い洞察が得られます。
- 日誌調査
- 利用者が日常で体験を記録するデータを分析する方法。長期的な行動傾向を拾えます。
- 現地調査
- 利用場所や実環境での観察・インタビューを行い、現場の実態を把握する手法です。
- 定性調査
- 言葉や観察で得られる深い洞察を重視する調査手法。
- 定量調査
- アンケートや行動データなど、数値で結果を測定する調査手法。
- 観察法
- 利用者の行動を直接観察してデータを得る基本的な研究手法です。
- ペルソナ
- 典型的な利用者像を具現化した架空の人物。設計の判断材料として使います。
- カスタマージャーニー
- 利用者がサービスを知ってから完了するまでの体験を時系列で整理したものです。
- カスタマージャーニーマップ
- ジャーニーを図として可視化し、接点・感情・課題・機会を一目で把握します。
- ストーリーマッピング
- 機能をユーザーの物語として整理し、実装の優先順位を決める手法です。
- カードソート
- 情報の分類をユーザーに試してもらい、IA設計の指針を得る参加型手法です。
- アフィニティダイアグラム
- 大量のデータを関連性でグループ化して要点を抽出する整理法です。
- タスク分析
- ユーザーが達成したい作業を細分化して設計要件を明確にする分析です。
- 情報設計
- 情報の分類・階層・導線を設計し、使いやすさの基盤を作る作業です。
- 情報アーキテクチャ
- ウェブ・アプリの情報構造を体系化する設計枠組みです。
- サイトマップ
- ウェブサイトのページ構成と階層を視覚化した図です。
- グリッドシステム
- レイアウトを整える格子状の設計枠組み。要素を均等に配置します。
- レイアウト
- 画面上の要素の配置と設計ルールを決める基本要素です。
- ワイヤーフレーム
- ページの骨組みを線画で示した設計図。機能とレイアウトの検証に使います。
- ペーパープロトタイピング
- 紙の設計を使ってインタラクションを検証する、初期段階のプロトタイピング手法です。
- プロトタイピング
- 実際の動作に近いモデルを作って検証する設計過程です。
- モックアップ
- 視覚的に完成度の高いデザイン案。見た目の検証に適します。
- デザインスプリント
- 短期間で問題を特定・解決する集中ワークショップ形式。通常5日程度で実施されます。
- デザイン思考
- 共感・定義・アイデア創出・試作・検証を循環させる、人間中心の問題解決アプローチです。
- デザインシステム
- カラー・タイポグラフィ・部品・ルールを統一して再利用可能にする設計基盤です。
- スタイルガイド
- ブランドやUIの一貫性を保つためのビジュアル規約。色・書体・アイコンなどを定義します。
- デザインブリーフ
- デザイン課題の目的・要件・制約を整理した設計指針文書。デザイナーへ共有します。
- MVP
- 最小限の実用的製品。市場での学習を促す最小構成で検証を行います。
- A/Bテスト
- 2案を同時に比較して、どちらが効果的かを検証する方法です。
- SUS
- System Usability Scale。使いやすさを定量的に評価する11問程度の質問紙です。
- NPS
- ネット・プロモータースコア。顧客の推奨意欲を測る指標で、ブランドの評価を把握します。
- ユーザビリティテスト
- 実際の利用者に使ってもらい、操作性・理解のしやすさの課題を検出する検証法です。
- ヒューリスティック評価
- 専門家が使い勝手の原則(ヒューリスティック)に照らして問題点を洗い出す評価法です。
- ヒューリスティック
- 使いやすさを導く基本原則や経験則のことです。
- 使いやすさ評価
- 使い勝手を複数の指標で総合的に評価・比較するプロセスです。
- アクセシビリティ
- 障害のある人を含むすべての人が利用できるよう設計・実装する考え方です。
- WCAG
- Web Content Accessibility Guidelines。ウェブのアクセシビリティ基準です。
- インクルーシブデザイン
- 誰も取り残さない設計。年齢・能力・環境の違いを超えて使えるようにします。
- デザイン倫理
- 社会的影響・プライバシー・公正さを考慮してデザイン判断を行う姿勢です。
- ステークホルダー分析
- 関係者のニーズ・影響・優先順位を整理して設計方針を決める作業です。
- タッチポイント
- ユーザーとサービスが接触する瞬間・場所のこと。体験を最適化するための重点点です。
- UIデザイン
- 画面上の表示と操作性を具体的に設計する分野です。
- UXデザイン
- ユーザー体験全体を設計・最適化する分野です。
- サービスデザイン
- サービス全体の体験と提供プロセスを統合的に設計するアプローチです。
- カラー理論
- 色の組み合わせ・意味・心理効果を理解して、見やすく美しいデザインを作る知識です。
- タイポグラフィ
- 文字組みの設計。フォント選定・字間・行間などを整えます。
- レスポンシブデザイン
- デバイスの画面サイズに合わせてレイアウトを自動調整する設計手法です。
- UI/UXデザイン
- UIデザインとUXデザインを総称して指すこともありますが、個別にはUIとUXを分けて設計します。
- カラー設計
- 配色のルールや組み合わせを決め、全体の色感を統一します。
デザインスタディのおすすめ参考サイト
- 「スタディ・デザイン」とは?|まなびナビ公式note
- デザインスタディモデル(でざいんすたでぃもでる)とは - 中古車
- デザインスタディモデル(でざいんすたでぃもでる)とは - 中古車
- 「スタディ・デザイン」とは?|まなびナビ公式note



















