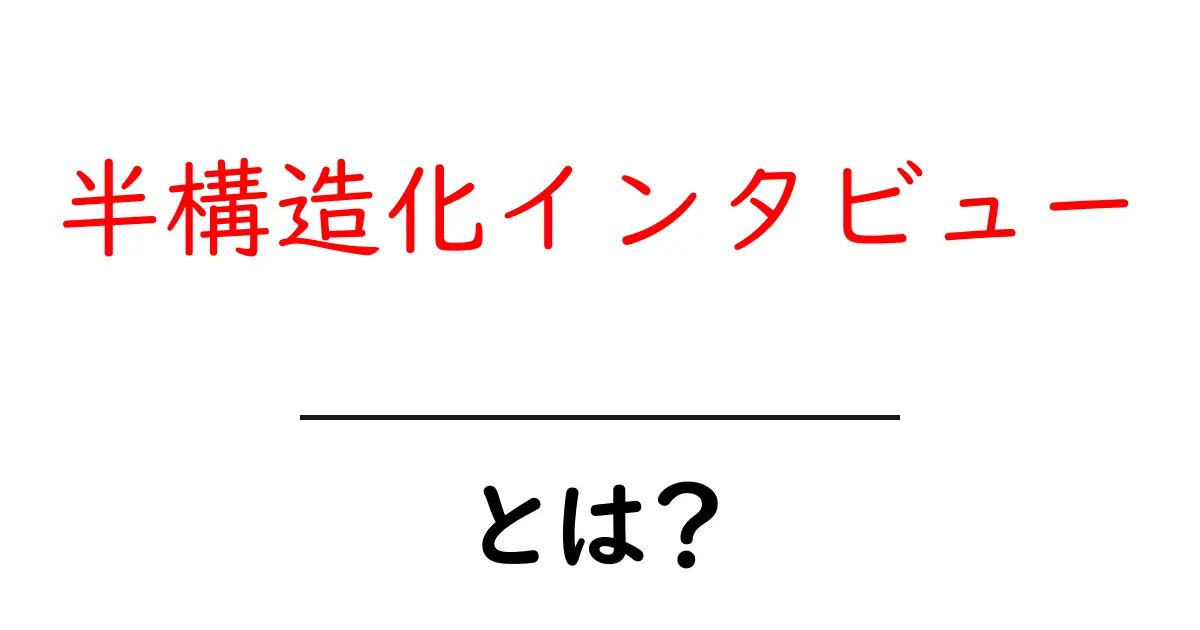

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
半構造化インタビューとは?初心者向けに解説
半構造化インタビューとは 定型の質問を使いながら自由に深掘りするインタビューの方法です この手法は研究や市場調査 ユーザー体験設計など幅広い場面で使われます
特徴と他のインタビューとの違い
この手法の特徴は 中心となる質問を数点準備することと 回答者の話を自由に広げられる追問の余地を残す点です その結果 記録された情報は詳しく多面的になります 一方で非構造化インタビューよりも整理と分析がしやすくなります
構造化インタビューとの違いは 質問の数と順序の自由度にあります 構造化では全員に同じ質問を同じ順序で投げますが 半構造化では話の流れに合わせて順番を変えたり 新しい質問を挿入したりすることが可能です
なぜ半構造化インタビューが選ばれるのか
人の考え方や感じ方を詳しく知りたい時に向いています 複数の視点を比べることができるのが大きな利点です 事前に得たい情報を明確にしつつ 現場の気づきを拾い上げるのに適しています
実践のステップ
- 目的と質問の整理 調査の目的を3つ程度に絞り 基本質問を用意します
- 倫理と同意の確認 録音許可を得る 目的とデータの取り扱いを説明します
- 現場での進め方 導入で信頼関係を作り 本題へ移り 深掘りの追問を行います
- 記録と分析 録音とメモを取り 後で重要なポイントを整理します
質問の例
以下は実務で使える基本例です
まとめ
半構造化インタビューは 設問の枠組みと 自由度のバランスが魅力の手法です しっかり準備をしておくと 言葉の奥にある意味を引き出しやすくなります また 記録と分析のプロセスを整えることで 大量の情報を整理しやすくなります
半構造化インタビューの同意語
- 半構造化インタビュー
- 質問リストをある程度用意しつつ、回答を深掘るために追問を自由に追加できる調査手法。初心者にも使いやすく、定型質問と自由回答の両方を活かす。
- 半構造的インタビュー
- 半構造化インタビューと同義の表現。枠組みは決まっているが、回答に応じて質問を柔軟に展開する方式。
- 半構成的インタビュー
- 半分は構造化されているが、回答に合わせて追加質問を行えるインタビューの呼び方。初心者にも理解しやすい表現。
- 半構造化面接
- インタビューの別表現。研究や人材調査で使われ、準備した質問と自由な追問を組み合わせる形式。
- 半構造的面接
- 半構造化面接と同義の表現。枠組みがある一方で、回答の展開に合わせて深掘りを行う。
- 準構造化インタビュー
- 構造化された部分と柔軟性を両立させたインタビュー。事前に用意した質問を軸にしつつ、回答に応じて追加質問を展開する。
- 準構造化面接
- 準構造化インタビューの面接版表現。主要質問を軸に、追問で洞察を深める手法。
半構造化インタビューの対義語・反対語
- 構造化インタビュー
- 質問と回答の形式が厳密に決められており、同じ質問リストと評価基準で実施される。再現性・比較性が高いが、深掘りの自由度は低い。
- 非構造化インタビュー
- 事前に固定した質問を設けず、インタビュアーが話を引き出しながら対話を深める柔軟な形式。新しい情報を引き出しやすいが、比較が難しくなることもある。
- 無構造化インタビュー
- 非構造化とほぼ同義で、進行の自由度が非常に高く、話題や順序は自由に決められるインタビュー。
- 固定質問インタビュー
- 事前に固定された質問セットを用い、質問の順序や回答形式を厳守するインタビュー。半構造化より制約が強い。
- 完全構造化インタビュー
- 質問と回答形式を完全に事前設計した最も厳密な構造化インタビュー。統制と比較可能性は高いが、柔軟性はほぼゼロ。
半構造化インタビューの共起語
- インタビュー
- 半構造化インタビューの場となる対話形式で、参加者の経験や意見を自由に話してもらい、研究テーマに沿って深掘りします。
- インタビューガイド
- 事前に構成する質問の流れと順番をまとめた指針で、話が逸れても軸を保つ役割をします。
- 質問設計
- 伝えたい情報を引き出すための質問をどう組み立てるかを考える作業。開放的な質問とフォローアップを組み合わせます。
- オープンエンド質問
- 答えが自由に展開できる質問形式で、詳細や背景を引き出すのに適します。
- 導入質問
- 参加者がリラックスできるようにするための軽い話題から始める質問です。
- フォローアップ質問
- 回答の追加情報を得るために使う追加の質問。
- プローブ
- 回答を深掘りする短い質問や促し。
- クローズド質問
- はい/いいえなど限られた選択肢で答える質問。半構造化では補助的に使います。
- 録音
- 音声を記録して後から正確に文字起こしできるようにする作業。
- ノートテイキング
- 現場での観察メモや補足情報を取る行為。
- 転写
- 音声録音を文字起こししてデータ化する作業。
- コード化
- テキストデータを意味のあるカテゴリやコードに分類する作業。
- テーマ分析
- 談話から共通のテーマや洞察を抽出する分析手法。
- 内容分析
- テキストの出現頻度や意味内容を整理する分析法。
- グラウンデッド・セオリー
- データから理論を生成する質的分析法の一つ。
- 飽和点
- 新しい質問をしても新規情報が得られなくなる点。
- サンプルサイズ
- 研究で扱う参加者の数の目安。
- 参加者募集
- 調査に協力してくれる人を集める活動。
- 同意書
- 参加者の同意を得る書類。
- インフォームドコンセント
- 目的やデータの取り扱いを理解してもらい同意を得るプロセス。
- 研究倫理
- 研究を行う際の倫理基準。
- 匿名化
- 個人を特定できる情報を取り除く処理。
- データ保護
- 個人情報を適切に管理する対策。
- 音声録音
- インタビューを音声として記録する方法。
- ビデオ録画
- 映像付きで記録する場合の録画。
- メモ作成
- 現場での気づきを短くメモする行為。
- ファシリテーション
- インタビューを円滑に進行させる進行役の役割。
- ファシリテーター
- インタビューを進行する担当者。
- 対面インタビュー
- 直接会って行うインタビュー形態。
- リモートインタビュー
- オンライン等遠隔地で行うインタビュー形態。
- UXリサーチ
- ユーザー体験を理解するための調査活動に半構造化インタビューを使うこと。
- ユーザーインタビュー
- 実際のユーザーを対象にしたインタビュー。
- ユーザーリサーチ
- 製品やサービスの設計に役立つユーザーの行動・感情を探る調査全般。
- ビアス
- 質問の作り方や状況で結果に影響する偏り。
- バイアス
- 回答や解釈に影響を及ぼす認知的・方法論的な偏り。
- 信頼性
- データが安定して再現可能である程度の信憑性を示す指標。
- 妥当性
- 収集データが研究の目的に対して適切に情報を反映している度合い。
- 信憑性
- 結論の信用性や信頼度。
- トライアングレーション
- 複数のデータ源・手法で結論を検証し信頼性を高める手法。
- パイロットインタビュー
- 本調査前に小規模で実施して設計を検証する予備インタビュー。
- 調査設計
- 研究の全体計画を立てる段階で、目的・方法・分析方針を決める作業。
- 対象選定
- 参加者を適切に選ぶ基準と方法。
- メモ
- 分析に役立つ追加の気づきを短く記録する補助的なノート。
半構造化インタビューの関連用語
- 半構造化インタビュー
- 事前に作成したインタビューガイドを軸にしつつ、回答者の自由度を残して追加の質問を挟む質的調査の手法。
- 構造化インタビュー
- 全て決まった質問と順序で行う厳格なインタビュー形式で、比較や集計を意図しやすい。
- 無構造化インタビュー
- 話者が自由に話を展開できる形式のインタビューで、質問は最小限の導入だけに留める。
- インタビューガイド
- 半構造化インタビューの枠組みとなる主要トピックと質問を整理した文書。
- インタビュー質問票
- インタビューで使用する質問のリスト。質問の順序や表現を事前に整える。
- 質問票
- インタビューで尋ねる項目を整理した文書全般(質問票と同義的に使用されることがある)。
- オープンエンド質問
- 回答者が自由に表現できる質問形式で、単純なYes/Noを避ける。
- プローブ(追問・掘り下げ質問)
- 回答を深掘りする追加の質問。例: 具体的には、どのような状況でしたか?
- ディープインタビュー
- 対象の深い洞察を得るために時間をかけて行う長めの対話形式のインタビュー。
- 逐語起こし
- 録音をそのまま文字に起こす作業。沈黙や話し方のニュアンスも再現することが目的。
- 文字起こし
- 録音内容を文章として起こす全般の作業。
- 録音・録画
- インタビューを音声や映像として記録する方法。後の検証と分析に役立つ。
- 同意書・倫理
- 研究参加にあたり参加者の同意を得て、倫理基準を守ること。匿名性や自由退出の配慮を含む。
- 個人情報保護・プライバシー
- 参加者の情報を保護するための取り組み。名前・連絡先などの取り扱いを慎重に管理。
- データ保護・保管
- 取得データを安全に保存し、アクセスを制限する管理。
- 信頼性・妥当性
- 質的データの信用性を高める努力。信頼性は再現性、妥当性は解釈の適切さを指す概念。
- 三角測量
- 複数のデータ源・手法を組み合わせて結果の検証・補完を行う手法。
- 理論的サンプリング
- 理論的な説明に必要なケースをあえて選ぶサンプリング法。データの理論的飽和を目指す。
- 目的サンプリング
- 研究目的に適合する情報を持つ事例を意図的に選ぶ手法。
- スノーボールサンプリング
- 初期の参加者から連絡を広げてもらい、連鎖的に参加者を増やす方法。
- オープンコーディング
- データを自由にコード化して初期のテーマを抽出する分析過程。
- 軸心コード化
- オープンコーディングで出たコードを関連づけて主要なカテゴリ(軸心)へ統合する段階。
- 選択的コード化
- 軸心コードを中心にデータを絞り込み、理論的な構造を完成させる段階。
- テーマ分析
- データから共通のテーマ(主題)を抽出して整理する分析手法。
- 内容分析
- テキストデータを分類・量的・質的に整理して特徴を抽出する分析法。
- コードブック
- コードとその定義、適用範囲・例を整理した辞書のような資料。
- 二重コーディング
- 複数の研究者が同じデータにコード付けを行い、一致度を確認する品質管理手法。
- ラポール形成
- 参加者が話しやすい雰囲気を作り、信頼関係を築く対話技術。
- アクティブリスニング
- 相手の話を積極的に聴き、理解を確認しながら要点を整理して伝える聴取技法。
- 反省的実践・自己省察
- 研究者自身のバイアスを自覚し、分析に反映させる内省の実践。
- インタビューの実施手順
- 準備・実施・録音・転写・分析の一連の流れとポイント。
- バイアス回避
- 質問設計や対話で先入観や誘導を避け、偏りを最小化する工夫。
- 設計・準備
- 研究目的に合わせた計画作成、サンプリング、倫理配慮、機材準備などの準備段階。
- 実施後の報告・分析報告書作成
- インタビュー結果を整理し、分析結果と解釈を文書化して共有する作業。
半構造化インタビューのおすすめ参考サイト
- 半構造化インタビューとは?メリットや実施時の注意点を解説
- 半構造化インタビューとは?メリットや実施時の注意点を解説
- 半構造化インタビューとは何か?その基本概念と重要性を解説
- 半構造化データとは?構造化データや非構造化データとの違いやメリット
- 半構造化インタビューとは何か?その基本概念と重要性を解説



















