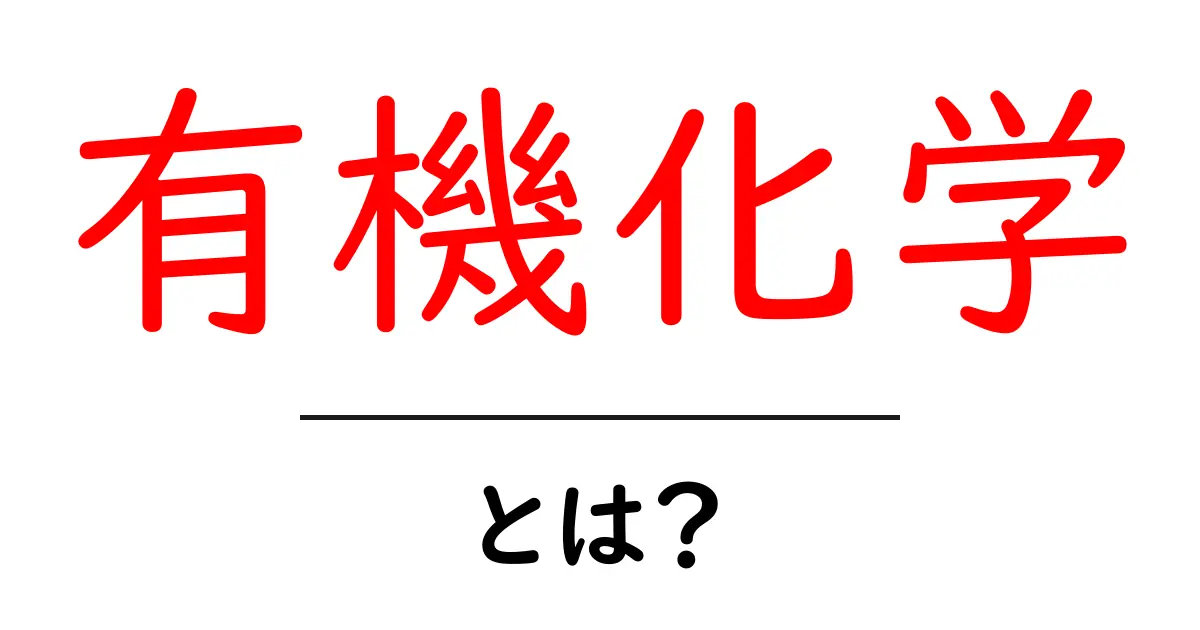

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
有機化学とは何か
有機化学とは、主に炭素を中心に考え、分子の作り方や反応のしくみを研究する科学の分野です。「有機」という言葉はもともと「生物由来の」という意味を含みますが、現代の有機化学は生体由来かどうかを問わず、炭素を含むあらゆる化合物を扱います。私たちの身の回りには有機化学が関わるものがたくさんあり、薬、プラスチック、香料、食品成分などが例です。
有機化学の魅力は、小さな分子がどうつながって大きなものになるのかという「設計の楽しさ」です。分子の形や結合の仕方が、性質や反応の起こりやすさを決めます。例えば、炭素-炭素結合の種類や官能基の有無が、色や臭い、薬の効き目、溶けやすさを左右します。
官能基と命名の基本
官能基とは、分子の反応性を決める「反応の入口」のことです。最も基本的な官能基にはヒドロキシ基(-OH)、カルボニル基(C=O)、ニトロ基(-NO2)などがあります。これらが分子にあると、反応のしかたが決まりやすくなります。覚えるポイントは、官能基があると反応の可能性が増えるという点です。
命名の基本は、IUPAC命名法の考え方を押さえることです。分子の主鎖となる炭素の連なりを数え、官能基の位置を番号で示します。難しく見えるかもしれませんが、まずは数をそろえ、最後に官能基の名称をつけるという順番を覚えると、名前と構造の対応が取りやすくなります。
有機反応の基本タイプ
有機化学でよく出てくる反応には、置換反応・付加反応・脱離反応などがあります。置換反応は、分子内の一部を別の原子や原子団に置き換える反応です。付加反応は、二重結合や三重結合のある分子が別の分子を加える反応のことです。脱離反応は、分子から原子団を取り除く反応です。これらの基本パターンを知っておくと、複雑な反応の流れが見えやすくなります。
実際には、分子がどのように動くかを考えるとき、電子の動き(反応機構)を描くことが役立ちます。図を描く習慣を持つと、反応の「矢印」で電子の動きを表す練習がしやすくなります。反応機構を理解することが、有機化学の理解を深める鍵です。
身近な例と応用
身の回りの多くのものは、有機化学の知識と結びついています。薬の設計では、分子の形を変えると薬の効果が変わります。香料は分子構造の違いで香りが変わり、食品の加工にも有機化学の知識が使われます。プラスチックや合成繊維も有機分子の連なりでできており、私たちの生活を支えています。
日常の例として、台所のアルコール消毒薬はエタノールという有機分子です。酸と塩基の反応を通じて、別の物質に変化することもあり、これも有機化学の基本原理とつながっています。
学習のコツと練習方法
有機化学を身につけるコツは、小さな知識を順番に積み重ね、図で視覚化することです。分子の図を描き、結合の種類と官能基を整理します。次に、代表的な反応をいくつか選んで、反応条件(温度、触媒、溶媒)と生成物をセットで覚えます。
また、英語の用語が多く使われることもあるので、用語を日本語と英語で対応づけて覚えると、辞書を引く手間が減ります。練習として、日常の化学ニュースや教科書の例題を読み、わからない点をノートにまとめ、友人や先生に説明してみるのが効果的です。
有機化学の基礎を支える図表
まとめ
有機化学は初めは難しく感じるかもしれませんが、基本的な概念と反応のパターンを一つずつ理解していくことで、分子どうしのつながり方が見えるようになります。日常生活の中の例を結び付けて考えると、学習が楽しくなり、知識が自然と身についていきます。
有機化学の関連サジェスト解説
- 有機化学 r とは
- R は具体的な分子の名前を固定せず、パターンを示すために使われる点が重要です。学習のコツとしては、まず R を CH3・CH2CH3・C6H5 などの代表的なグループに置き換えて、実際の分子を頭の中に描いてみることです。例えば R-OH を CH3-OH(メタノール)や CH3CH2-OH(エタノール)に置き換えて考えると、アルコールの違いが見えてきます。R-COOH では R=CH3 のとき酢酸、R=C2H5 のときはエチル酢酸のように習得できます。文法的には R と R' を組み合わせてケトンやエステルの構図を理解する練習をすると、反応の仕組みも見えやすくなります。最後に、R は「置換基の集合体」という発想を身につけ、個々の分子の名前を覚える前に、パターンを覚えることが有効です。これを繰り返すと、有機化学の全体像をつかみやすくなります。
- 有機化学 イソ とは
- 有機化学は、炭素を中心にさまざまな分子の作り方や性質を学ぶ分野です。その中でよく目にするのが「イソ」という接頭辞です。イソは、名前の中に現れ、直鎖の炭素骨格に対して1本または複数の分岐(枝分かれ)がある分子を指す古くから使われてきた記号です。つまり、同じ炭素数をもつ別の形(異性体)で、形が異なることを伝える役割を果たします。具体的な例を挙げると、イソブタンは有名な4個の炭素からなる直鎖ブタンに対して中央付近にメチル基が分岐している形です。分子式はC4H10で、日常名としては“イソブタン”と呼ばれます。IUPAC名は 2-メチルプロパン です。もう一つの例としてイソペンタン(2-メチルブタン)があります。これは5つの炭素を持つ直鎖のブタンにメチル基が1つついた形で、こちらも一般名としてイソペンタンと呼ばれます。また、イソは置換基の名前にも現れ、イソプロパン(一般に isopropyl )のような表現が使われます。イソプロパンはプロパン分子の2位の炭素に分岐が生じた置換基で、構造としては CH3-CH(CH3)2 となります。現代の公式名では、置換基としては プロパン-2-yl などの表現が用いられることが多く、学術的には 2-プロパノール(= isopropanol)など別名も知っておくと便利です。このように「イソ」は、直鎖の形に対して分岐した形を示す古くからの命名の一部として使われます。現代の学術的には、より正確な IUPAC 名(例:2-メチルプロパン、2-メチルブタン)と、伝統的な日常名(例:イソブタン、イソペンタン)が併用されることが多いです。名前に “iso” が含まれていれば、分岐していることを示す手がかりになる一方で、すべての分岐が必ず iso というわけではなく、他の命名規則も併用される点には注意しましょう。この知識は、有機化学の命名ルールを理解する際の基礎になります。新しい化合物の名前を聞いたとき、iso の有無を一つの手がかりとして Structure を想像する癖をつけると、学習がスムーズになります。
- 有機化学 d とは
- この記事では、有機化学 d とは何かを、初心者にも分かりやすく解説します。有機化学は、私たちの体や身の回りの物質を作る仕組みを学ぶ学問です。その中で現れる d という記号には、いくつかの意味が存在します。まず最初に覚えておきたいのは、d が光学活性を表す場合です。物質が「右に回転する」性質を dextrorotatory(英語で dextrorotatory の略)と呼び、昔は d- や (+) と書かれることがありました。これに対して左回りに回転する場合は l- や (-) と表されます。次に、d が同位体を示すこともあります。化学実験では水素の代わりに重い同位体デュテリウムを使い、これを示すときに前に小文字の d をつけて表すことがあります。例として、d-標識の分子は反応経路を追跡するのに役立ちます。さらに、D/L や R/S などの立体化学表記と混同しないことが大切です。D/L はグリセリアルデヒドと比較して立体配置を表す古い記法で、必ずしも光学活性と一致するわけではありません。一方、d/l は光学活性の向きを指すことが多いのです。日常の学習では、文脈をよく読み、前後の説明を確認することが意味を取り違えないコツです。以上の点を押さえておけば、有機化学における d という記号の使われ方を理解しやすくなります。なお、初学者は同じ記号でも意味が違う場合があることを意識し、教科書や講義ノートの定義を参照する習慣をつけましょう。最後に、 d の意味を一つに絞らず、文脈から判断する練習を重ねると、化学の用語に対する理解が深まります。
- 有機化学 me とは
- この記事では、検索キーワード『有機化学 me とは』をきっかけに、有機化学の基本を中学生でも理解できるように解説します。まず、有機化学とは何かを簡単に説明します。有機化学は、炭素を中心にした分子の作り方や反応のルールを学ぶ科学です。私たちの体の構成成分や、薬、プラスチック、香りのもとなど、身の回りの多くのものが有機化学と関係しています。次に、主なポイントをいくつか挙げます。1) 炭素の結びつき=炭素骨格。炭素は4つの結合を作る性質があり、長い鎖や環の形、枝分かれした分子を作ることができます。2) 官能基とは?有機化学で大事な機能を持つ原子のグループのことです。例として、アルコールの–OH、アルデヒドの=O、カルボン酸の–COOH、アミンの–NH2などがあります。3) 反応の基本イメージ。有機反応は「反応条件(温度・溶媒・触媒)」と「反応の目的」によって進み方が変わります。反応式を読めるようになると、途中で何が起きているのか想像しやすくなります。実験を通じて観察→仮説→検証という流れを身につけると理解が深まります。4) 学習のコツ。有機化学は覚える用語が多いですが、まずは身の回りの例を結びつけて覚えるのが近道です。6つの基本的な官能基を覚え、名前と役割をセットで覚えると、複雑な分子にも対応しやすくなります。最後に、難しく感じるときは、先生や友達に質問する、動画や図解を活用する、用語カードを作るなどの方法を取り入れてみましょう。
- 有機化学 tert とは
- 有機化学には、分子の置換基や結合の仕方を表すさまざまな用語があります。その中でも「tert」はとてもよく使われる重要語です。tert は英語の tertiary の略で、日本語では「三級・三重置換に関係する」という意味合いに近い記号として使われます。具体的には、置換基がどれだけ分岐しているかを表すときに登場します。1°(一次)、2°(二次)に対して3つ以上の炭素と結合しているような特定の炭素を指すことが多いです。最も代表的な例が tert-butyl(tert-ブチル)基です。これは (CH3)3C– の形をしており、中心の炭素が三つのメチル基と結合して、全体として非常に分岐しています。日常の化学式や反応式では「t‑Bu」と略されることも多いです。tert の性質が重要になる理由は、置換基が大きくて立体的に邪魔になる(立体選択性を左右する)性質を持つからです。つまり、反応がどの部位に進むかを難しくしたり、速度を遅くしたりする効果(立体障害と呼ばれる効果)を与えることがあります。tert-ブチル基を含む化合物は、近くの部位が反応しにくくなるため、別の反応を選ぶようになったり、反応の分岐比が変わったりします。名称の使い方について補足すると、「tert」は古くから日常的に使われてきた呼び方です。現代の正式な命名(IUPAC 名)では、tert-を使わず、具体的な分岐構造を表す名前に言い換えることもあります。例としては、tert-butanol は IUPAC 名で 2-methylpropan-2-ol、tert-butyl chloride は 2-methylpropane-2-yl chloride などになります。しかし教材や実験ノートでは、今でも「tert-」という呼び名が多く使われ続けています。要は、tert とは「分岐構造を持つ大きめの置換基」を指す有機化学の用語で、分子の反応性や性質を理解する手がかりになる、ということです。
- 有機化学 cat とは
- 有機化学 cat とは、反応を速くするが自分自身は反応で消費されない 触媒 のことを示す略記です。化学式の反応式では、反応物の上や下に cat. と書かれ、実験では適切な触媒を用いて反応を進行させます。たとえば不飽和結合の水素化にはパラジウム触媒の Pd/C が使われ、関与する有機分子の結合の切り替えを効果的に行います。窒素を含む有機合成の成分を作る場合にも酸化還元酵素のような触媒や金属触媒が活躍します。触媒の役割は、反応の活性化エネルギーを下げて、反応が起こる道のりを短くすることです。これにより反応は速く進み、必要なエネルギーを少なくして副反応を減らすことができます。覚えておきたいのは、 cat は反応物や生成物の一部ではなく、反応を手伝う道具だという点です。置換基の影響や温度、溶媒の性質、pH などの条件によって、どの触媒を用いるべきかが決まります。実験ノートには cat. 触媒名 と書かれることが多く、どの触媒を使ったかを記録しておくと再現性が高まります。家庭の現象に置き換えると、触媒は反応を助ける 手伝い役 で、消費されない点が分かりやすい例です。要するに 有機化学 での cat とは、反応を速くするための助っ人のような存在で、正しい条件下で選択的に使うことで目的の化合物を効率よく作る手助けをしてくれるのです。
- 有機化学 キラル とは
- 有機化学 キラル とは、鏡像を重ねられない性質を持つ分子のことです。キラルという語は、手のような左右非対称さを表す言葉で、古代ギリシャ語の由来があります。分子がキラルかどうかを判定するポイントは、炭素原子の周りに四つの異なる原子団が結合している“不斉中心”があるかどうかです。不斉中心を持つ分子は鏡像異性体、すなわちエナンチオマーの対を生み出します。エナンチオマーは外から見た形は同じでも、鏡像を重ねてみると別の物質になります。日常生活での例としては、乳酸のLとDの形、あるいは柑橘系の香りを作る limonene のエナンチオマーが互いに異なる匂いを放つことなどがあります。生体内では特定のエナンチオマーだけが活性を示すことがあり、薬の設計でもこの点が重要です。つまりキラルとは、分子の“左右の handedness”を指す基本概念で、分子の性質や生物学的作用に深く関係しています。初歩としては、4つの異なる結合を持つ不斉中心、鏡像異性体、エナンチオマーという用語を覚えることから始めると理解が進みます。
- 無機化学 有機化学 とは
- 無機化学とは、金属や岩石、塩、酸、塩基、酸化物、セラミックスなど、炭素を中心とした有機化合物以外を対象に、その性質や反応を研究する化学の分野です。日常生活でも見かける材料や物質の成り立ちを理解するのに役立ちます。例えば水にはH2Oがあり、食塩はNaCl、太陽光発電の部材や建築材料にも無機化学の知識が活かされています。対して有機化学は、炭素を中心とした有機化合物の性質と反応を扱う分野です。炭素と水素を基本とした分子が多く、油、プラスチック、薬、香料、食品添加物など、私たちの生活に深く関わる製品の多くが有機化合物です。これら二つの分野は、扱う物質の違いと結合の特徴が大きな違いになります。無機化学ではイオン結合・金属結合・配位結合といった結合の種類が見られる一方で、有機化学は主に共有結合を中心とした反応が多いのが特徴です。学習のコツとしては、周期表の元素の性質を覚え、酸化数の考え方を身につけること、そして有機化学では機能基と呼ばれる特定の原子団がどんな取り扱いをされるかを覚えることです。生活の中の例としては、歯磨き粉や衣類用洗剤の成分に含まれる無機塩・界面活性剤、有機化合物としての油脂・糖類・薬品・プラスチックなどがあります。二つの分野は互いに補完し合い、材料開発・医薬品・環境技術・エネルギーなど、現代社会のさまざまな課題を解く手がかりを提供してくれます。初心者のうちは、「無機化学は無機物、有機化学は炭素を中心とした物質」と覚えると入りやすく、身近な製品の成分を例に分野を結びつけて考えると理解が深まります。
- ラジカル とは 有機化学
- ラジカルとは有機化学の世界で、原子や分子の中に不対電子を1つだけ持つ状態のことを指します。不対電子はペアになっていないため非常に反応しやすく、他の分子と素早く結合を作っていきます。代表的な例としてメチルラジカルCH3•や塩素ラジカルCl•などがあります。こうしたラジカルは分子の最も外側の電子の状態を変えることで、他の分子に付加したり、分子を分解したりします。ラジカルは通常、イオンとは違い電荷を帯びていませんが、反応の進み方は大きく異なります。イオンは電子を獲得したり失ったりして帯電していますが、ラジカルは中性で不安定な状態のため、反応の起点として働くことが多いです。有機化学ではラジカル反応を使って長い鎖状分子を作ることがあります。開始は光や熱、あるいは分解反応でラジカルを作る段階です。次に進行として、ラジカルが別の分子と反応して新しいラジカルを作り、別の反応へとつなげていきます。最後には終結として、二つのラジカルが結合して安定な分子になることがあります。安定性の差は、共鳴や置換の効果で変わります。温度、光、溶媒の性質によって反応の速さや可能性が変わるため、実験では条件を適切に選ぶことが大切です。身の回りで完全に無縁というわけではありませんが、日常生活で直接扱うことはほとんどなく、学習用の教材や授業の教材を通じて学ぶのが一般的です。
有機化学の同意語
- オーガニックケミストリー
- 英語の Organic Chemistry の日本語表記の一つ。学術・教育文献で広く使われる語で、意味は有機化学と同じです。
- オーガニック化学
- 有機化学の別表記。カタカナ表記で書かれることが多く、同義語として使われます。
- 有機反応化学
- 有機化学の中で、特に有機分子の反応と反応機構を扱う分野を指す語。総称としては有機化学と同義で使われることも多いです。
- 有機合成化学
- 有機化学の中でも有機分子の合成法を研究する領域を指します。広義の有機化学と重なる部分が多いが、専門的には合成に焦点を当てた表現です。
- 有機系化学
- 化学の分類の一つとして有機の分野を指す語。無機化学と対比して使われることが多いです。
- 有機物化学
- 有機化合物を対象とする化学のことを指す表現。日常会話では有機化学とほぼ同義で使われることがあります。
- 有機化学分野
- 化学の中で有機化学全体を指す言い回し。学習・研究のトピックとしてよく使われます。
- 有機化学科
- 大学の学部・学科名や研究分野の一つとして使われる表現。実務的には研究領域を指します。
有機化学の対義語・反対語
- 無機化学
- 有機化学の対となる分野。炭素を含まない物質の性質・反応・合成を扱う学問領域。
- 無機化合物
- 炭素を含まない、または極めて少ない物質の総称。無機化学の研究対象となる物質群で、金属元素や無機結晶などを含む。
- 無機的
- 有機的な特徴(生体由来・炭素-水素結合の多様性など)を持たない性質・性格を指す形容詞。対義語として使われることがある。
- 非有機化学
- 有機化学以外の化学分野を指す表現。実務的には無機化学を含む広い意味で使われることが多い。
- 無機物質
- 炭素を含まない、または極めて少ない物質を指す総称。日常的には無機化学の対象となる物質群を示すことが多い。
有機化学の共起語
- 有機化合物
- 炭素と水素を中心に結合した化学物質の総称。酸素・窒素・硫黄などを含む多様な分子があり、医薬品・香料・材料など、身の回りの多くの分野と関わる。
- 官能基
- 分子の性質や反応の決まりを決める特定の原子団。例: -OH(アルコール), -COOH(カルボン酸), -C=O(カルボニル基) など。
- 炭素骨格
- 分子の枠組みとなる炭素の結合の連なり。炭素骨格の違いで性質や反応の傾向が変わる。
- 命名法
- 有機化合物の名前を体系的につけるルール。分子構造が分かるように正しく表現するための基本。
- IUPAC命名法
- 国際的な統一命名法。主鎖・官能基の優先順位を決めて名前を決める。
- 反応機構
- 反応がどのように進むかを、電子の動きや中間体を用いて説明する考え方。
- 置換反応
- 分子の特定の原子が別の原子・基に置き換わる反応。
- 求核置換
- 求核剤が正電荷の中心へ攻撃して置換を起こす代表的な反応。SN1/SN2 など。
- 付加反応
- 不飽和結合(例えば二重結合)に新しい原子が加わる反応。
- 脱離反応
- 分子から小さな分子が離れて、別の結合が現れる反応。
- 縮合反応
- 二つの分子が結合して小さな分子を取り除くような反応(例: 水の脱離)。
- 酸化
- 電子を失う、または酸化数が上がる反応。
- 還元
- 電子を得る、酸化数が下がる反応。
- 酸化還元
- 酸化と還元の両方を含む反応の総称。
- 触媒
- 反応を早めるが自体は消費されず元の状態に戻る物質・物質群。
- 酸・塩基
- 酸はH+を手放し、塩基はH+を受け取る性質を持つ物質。
- pH
- 水溶液の酸性・アルカリ性の度合いを示す指標。
- 溶媒
- 反応の場になる液体。反応の速さ・選択性などを左右する。
- 溶媒効果
- 溶媒の性質が反応の進み方に影響を与える現象。
- 反応速度
- 反応がどのくらいの速さで進むか。温度・触媒・溶媒などで変化。
- 収率
- 望んだ生成物の実際の量が理論量に対してどれくらいか。高いほど効率的。
- 遷移状態
- 反応過程で最もエネルギーが高い瞬間の分子構造。
- 活性化エネルギー
- 反応を開始するために越えるべきエネルギーの壁。
- 有機実験
- 教科書の手順を実験室で実践する実践活動。
- 実験手順
- 実験を進めるための具体的な作業順序。
- 安全
- 有機化学実験での危険性を避けるための対策全般。
- 分離・精製
- 混合物から目的物を分離し、純度を高める作業。
- クロマトグラフィー
- 混合物を成分ごとに分離する技術全般。
- 薄層クロマトグラフィー
- 薄い板を使って成分を分離・確認する基本手法。
- ガスクロマトグラフィー
- 気体・揮発性分子を分離して分析する方法。
- 液体クロマトグラフィー
- 液体移動相を使って成分を分離する技術(HPLC等)。
- カラムクロマトグラフィー
- 固定相を柱に詰めて分離する技術。
- 再結晶
- 不純物を取り除くために純度を高める結晶化法。
- 結晶化
- 分子が整然と並んで結晶を作る現象。
- 芳香族
- ベンゼン環を含む安定した有機化合物の総称。
- ベンゼン
- 六員環の芳香族化合物の代表的な基礎構造。
- アルコール
- -OH基を持つ有機化合物。
- アルデヒド
- アルデヒド基を持つ有機化合物(R-CHO)。
- ケトン
- カルボニル基を持つ有機化合物(R-CO-R')。
- カルボン酸
- -COOH 基を持つ酸性官能基の有機化合物。
- エステル
- カルボン酸とアルコールが縮合してできる官能物。香りにも関与することが多い。
- アミン
- 窒素を含む有機化合物の官能基。塩基性を示すことが多い。
- アミド化
- カルボン酸とアミンが反応してアミドを作る反応。
- アシル化
- カルボニル基を含む官能基を導入する反応。
- 有機合成
- 目的の分子を作るための計画・実践的な反応設計の総称。
- 薬学
- 薬の開発・評価・使用法を扱う学問分野。
- 医薬品
- 治療に用いられる薬剤の総称。
- 有機材料
- 有機分子を材料として用いる分野(半導体・有機膜など)。
- ポリマー
- モノマーが繰り返し結合してできる高分子。
- 天然物化学
- 自然界にある生体由来の化合物を研究・合成する分野。
- 光化学
- 光をエネルギーとして反応を起こす現象を扱う分野。
- NMR
- 核磁気共鳴スペクトルを用いて分子構造・環境を知る分析法。
- 1H-NMR
- 水素原子の周囲の化学環境を読み解くNMR の一種。
- 13C-NMR
- 炭素原子の環境情報を得るためのNMR。
- IRスペクトル
- 赤外線を使って分子内の官能基を特定する分光法。
- 紫外可視スペクトル
- UV-Visスペクトル、電子遷移を通じて情報を得る分光法。
- 質量分析
- 分子の量(分子量)と構造の手掛かりを得る分析法。
有機化学の関連用語
- 有機化合物
- 炭素を中心に水素や他の原子と結合してできる化合物の総称。生体物質やプラスチック、医薬品など、身の回りの多くを占める。
- 官能基
- 反応性を決定づける特定の原子団。反応のタイプや性質を大きく左右する。例:-OH、-C=O、-C≡N など。
- アルキル基
- 炭素と水素だけで構成される置換基(R-)。様々な有機分子の骨格を作る基本単位。
- アルケン
- 二重結合を持つ炭化水素(C=C)。反応性が高く、付加反応が起きやすい。
- アルカン
- 全て単結合の炭化水素(飽和炭化水素)。安定で反応性は比較的低い。
- アルキン
- 三重結合を持つ炭化水素(C≡C)。高い反応性を示す。
- アリール基
- 芳香族環を含む置換基。例:フェニル基(C6H5-)。
- 芳香族化合物
- ベンゼン環を基本単位とする安定した環状化合物。特有の反応性を示す。
- アルコール
- -OH基を持つ有機化合物。種類により「一次・二次・三次」などと呼ばれる。
- アルデヒド
- カルボニル基を1つだけ持つ有機化合物。酸化の指標となることが多い。
- ケトン
- カルボニル基を1つ持つ有機化合物。中核となるカルボニル化合物の一種。
- アミン
- 窒素原子を含む官能基。塩基性を示し、求核剤としても働くことがある。
- カルボン酸
- -COOH基を持つ有機酸。酸性を示し、エステル化などの反応の出発点になる。
- エステル
- カルボン酸の酸素と有機基が結合した化合物。香りや香料、溶媒などに多い。
- アミド
- カルボン酸のOHがアミノ基に置換された化合物。タンパク質の主成分にも関わる。
- ハロゲン化有機物
- C–X結合をもつ有機化合物(X は F, Cl, Br, I)。置換反応などで反応性を変える。
- 酸化剤
- 他の分子を酸化させる試薬。反応中に電子を奪う側。例:過マンガン酸カリウム、 PCC など。
- 還元剤
- 他の分子を還元させる試薬。電子を与える側。例:水素、ナトリウム水素化金属など。
- 付加反応
- 分子が二重結合・三重結合などの部位に新しい原子団を付加する反応。
- 縮合反応
- 2分子が結合して水などを放出し、より大きな分子を作る反応。
- 置換反応
- 分子内のある原子基を別の原子基に置き換える反応。
- 脱離反応
- 分子から小さな分子を切り離して新しい結合を作る反応。
- 環化反応
- 直線状の分子が閉じた環を形成する反応。
- 反応機構
- 反応がどの順序と経路で進むかを説明する具体的な手順。
- 触媒
- 反応を速めるが自身は消費されにくい物質。活性化エネルギーを下げる役割。
- ルイス酸/ルイス塩基
- 電子対の受け渡しで反応を促進する概念。酸は電子対を受け取る側、塩基は渡す側。
- 保護基
- 反応の干渉を避けるため、特定の部位を一時的に反応性から守る基。
- 脱保護
- 保護基を取り除き、元の部位を再び反応させる過程。
- レトロ合成
- 複雑な分子を、より簡単な出発物質へさかのぼって設計する戦略。
- 合成経路
- 目的物を作るための具体的な手順の全体像。
- 立体化学
- 分子の3次元的な配置と、鏡像異性体などの性質を扱う分野。
- 手性中心
- 鏡像を作り出す炭素原子など、立体異性体の起点となる中心。
- ジアステレオマー
- 同じ分子式・同じ手性中心を持つが、他の立体配置が異なる異性体。
- エナンチオマー
- 鏡像異性体のうち、光学活性を持つ対の片方。
- 光学活性
- 手性分子が偏光された光を回転させる現象。
- 共鳴
- 電子の分布が複数の構造式で部分的に分布して、安定性を高める現象。
- π結合
- 二重結合など、π軌道による結合。反応性の指標にもなる。
- σ結合
- 単結合を形成する、軸に沿って電子を共有する結合。
- 共役系
- π結合が連続して広がる分子の構造。安定性・発色性に影響。
- 芳香性
- 特定の環状π系が特別に安定な性質。反応性や吸収スペクトルに影響。
- NMR(核磁気共鳴)
- 分子の構造を調べる主要な分光法。原子の周囲の環境を反映。
- IRスペクトル
- 赤外分光法。官能基の振動を観察して同定に役立つ。
- 質量分析
- 分子量や構造情報を得る分析法。断片イオンなどから推定する。
- クロマトグラフィー
- 混合物を成分ごとに分離する分離技術。状態・溶媒により多様な手法がある。
- 再結晶
- 純度を高める結晶化手法。高純度の結晶を得る基礎手法。
- 蒸留
- 混合物を揮発性の差で分離する熱力学的分離法。
- 溶媒
- 反応・溶解に用いる液体。極性・非極性など性質に応じて選ぶ。
- 有機溶媒
- 有機溶媒としてよく使われる物質群。例:エタノール、エーテル、クロロホルムなど。
- 溶媒の極性
- 極性の高低に応じて反応性・溶解性が変わる。反応選択性にも影響。
有機化学のおすすめ参考サイト
- 有機化学とは?簡単に他の化学との違いや内容を解説!
- 有機合成とは|研究用語辞典 - WDB
- 有機化学とは? | 大分市 数学 化学 物理専門 |大分理系専門塾WINROAD
- II. 化学物質とは - 図書館員のための薬学事始め



















