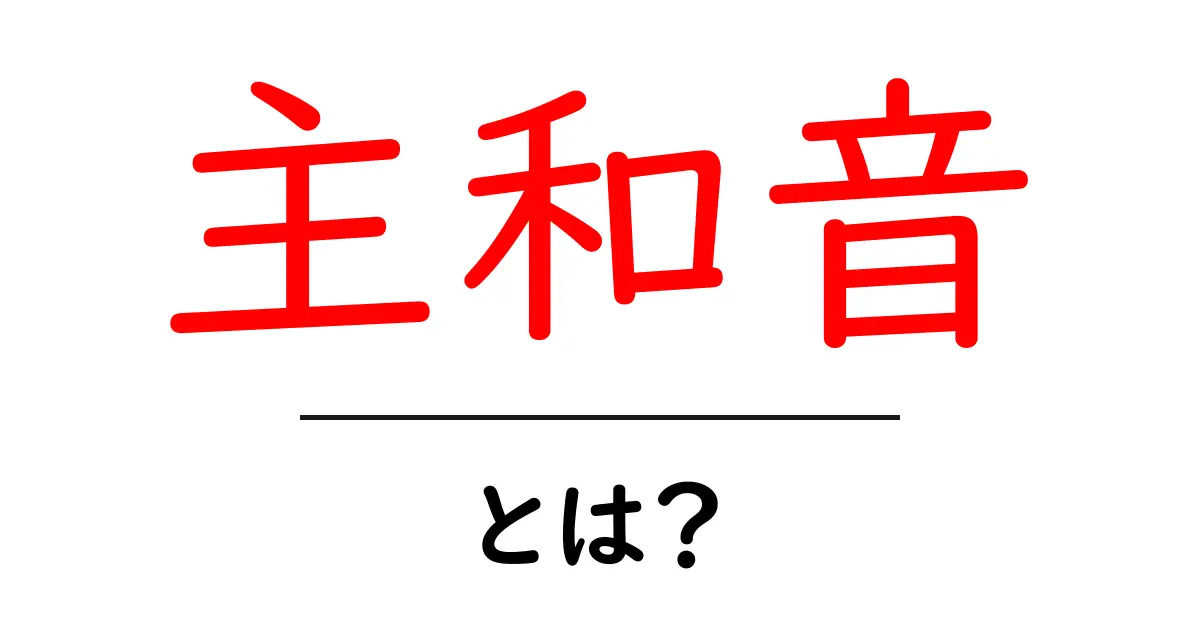

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
主和音・とは?
音楽理論を学ぶときによく出てくる言葉が主和音です。主和音は曲の中で「家のような安定感をくれる和音」であり、調性を決める大事な役割を果たします。調が C メジャーなら主和音は C E G の三和音です。この和音が曲の基点となり、ほかの和音がこの基点から動いていくと聴き手は安心感を得ます。
主和音の英語表現は chord の中の triad でありだいたい Iコードと呼ばれます。Iコードはその調の最初の音を根とする三音からなる和音で、"I" というローマ数字で表されるのが一般的です。
主和音の構成と役割
主和音は三つの音からなります。基音となる音を1度、和音の第3音、五度音を合わせて和音を作ります。主和音の構成音はスケールの1,3,5音です。例えば Cメジャーのスケールは C D E F G A B ですが、そこから Iコードは C E G の三音で作られます。
調がマイナー系になると主和音は少し変わることもありますが、基本的なアイデアは変わりません。自然短音階なら Iコードは小三和音、長調では Iコードは大三和音として響きます。大事なのは「家に帰る感覚」を作る音であるという点です。
実際の音と例
具体的な例を見てみましょう。Cメジャーの主和音は C E G です。これを弾くと、曲の安定した入口が生まれます。Aマイナーの主和音は A C E で、これはマイナーな響きになります。Gメジャーの主和音は G B D です。どれも 1 度の音から始まり、3 度と5 度が重なって三和音になります。
聴き分けのコツとしては、主和音は「安定感」が強く、次の和音へと滑らかに進むための橋渡し役になっている点です。曲が進むとき Iコードはよく Vコードへと進み、最後に Iコードへ戻る「I-V-I」や「I-vi-IV-V」などの進行がよく使われます。I-V-Iは特に安心感のある基本進行として覚えておくとよいです。
表で整理してみよう
この表を見れば、主和音の構成音がどの音から作られるかがすぐに分かります。自分の好きな曲を例に取って、調性に合わせて主和音を探してみると理解が深まります。
練習のコツとまとめ
練習のコツとしては、まずは自分の好きな曲のキーを決め、そのキーの主和音を弾いて聴いてみることです。次に Iコードを基準にして、Vコードへと流れる progress の練習をします。初めは I - IV - V - I の順番から始め、慣れてきたら I - VI - IV - V など少し複雑な進行にも挑戦してみましょう。
最後に覚えておくべきポイントは、主和音は曲の“帰る場所”であり、聴き手に安心感を与える音という点です。音楽理論の学習は難しく感じることもありますが、少しずつ身近な曲から着実に理解を広げていくと楽しくなります。
主和音の同意語
- トニック和音
- キーの基音を根音とする和音で、安定感の源となる基本の和音。大調では長三和音、自然短調では短三和音になることが多い。
- トニック三和音
- 主和音の三和音(3つの音だけからなる和音)で、根音をキーの第一音に置く和音。I和音として機能します。
- I和音
- ローマ数字表記で表される和音で、キーの第一度に対応する和音。主和音の代表的表現の一つ。
- Iコード
- I和音を指す呼び方の別表記。音楽理論やコード進行の表記で使われます。
- 第一和音
- 第一度を根音とする和音。一般に主和音と同義で使われることが多い表現です。
- 第一度和音
- 第一度を根音とする和音。主和音として機能する和音の伝統的名称の一つ。
- トニックコード
- トニックを含むコード全般の呼称。I和音と同義で用いられることが多く、日常的な表現です。
主和音の対義語・反対語
- 属和音(V和音)
- 主和音の対になる和音。機能的には緊張を生み、解決先として主和音へ落ち着くことが多い。
- 下属和音(IV和音)
- 主和音の前後関係を作る和音。緊張は強くなく、安定感や広がりを提供する。
- 代用属和音
- 本来の属和音の代わりとして使われる和音。機能は属和音に近いが、響きは異なるため代用として使われる場面がある。
- 非機能和音
- 機能的なドミナント-トニックの関係に縛られず、局所的な響きを作る和音。主和音と直接的な対比を作る際に挙げられることがある。
- 無調性の和音
- 特定の調に縛られず、無調性の文脈で使われる和音。主和音の機能を前提としない対比として考えられる。
主和音の共起語
- 和音
- 同時に鳴る複数の音の組み合わせ。和音は和声の基本単位で、主和音をはじめとする多様な和音が組み合わさります。
- 三和音
- 三つの音から成る和音。主和音は三和音の一種で、最も基本的な響きを作ります。
- コード
- 和音を指す現代的な呼び方。コードという言い方はポップスやジャズなどでよく使われます。
- コード進行
- 複数の和音が順番に鳴る連なり。曲の流れを作り、主和音へと解決することが多いです。
- 和声
- 和音の組み合わせとそれらの動きを指す総称。
- 和声理論
- 和声のルールや法則を体系化した学問。初心者には基本的な進行の理解に役立ちます。
- 音階
- 音の高さの並び。曲の調を決め、主和音はこの音階の第一音を基準に作られます。
- 調性
- 曲全体の調の性質。主和音はその調の中心となります。
- 調
- 曲が属するキーのこと。長調か短調かによって響きが変わります。
- トニック
- 主音。曲の安定感の中心となる音や和音です。
- 主音
- スケールの第一音。和声的には曲の“拠り所”となる音です。
- 根音
- 和音の基礎となる音。和音の土台になる音です。
- Iコード
- 調の主和音を指す略称。I度の和音として機能し、安定した響きを作ります。
- Vコード
- 属和音。解決を促し、終止感を生む和音です。
- IVコード
- 下属和音。調の中で主和音の下に位置する和音。
- 下属和音
- IVコードの別称。主和音へ向かう準備の役割を果たします。
- 属和音
- Vコードの別称。緊張感を作り出し、Iへ解決させる力を持ちます。
- 終止
- 楽曲の区切りを作る和声の形。完結感のある終わりへと導きます。
- カデンツ
- 終止を作る定型的な和声パターン。楽曲のまとまりを生み出します。
- 代位和音
- 主和音以外の機能を持つ和音の総称。二次的な和声進行を作ります(例: V/V など)。
- 機能和声
- 和声が持つ機能(トニック機能、ドミナント機能、サブドミナント機能)を指します。
- ルート音
- 和音の根音。和音の安定の軸となる音です。
- 音程
- 二つの音の高さの差。和音を構成する基本的な要素です。
- 転調
- 曲の調を別の調へ移すこと。場面の変化を作る手法です。
- コードネーム
- コードの名称(例: C、Am、F など)。楽譜や楽曲解説で使われます。
主和音の関連用語
- 主和音(I和音)
- キーの基盤となる和音で、音階の1度を根音とする。曲全体に安定感を与える最も重要な和音。長調では長三和音、短調では短三和音になることがある。
- トニック
- 和声の安定の中心となる機能を指す言葉。曲の“家”のように戻ってくるべき音や和音のこと。
- I和音
- 英語表記の I chord。日本語では主和音と同義。映画や楽譜の表記では I の和音として現れる。
- 三和音
- 三つの音から成る和音の総称。最も基本的な和音の形で、和声の基礎となる。
- 和音
- 同時に鳴らされる二つ以上の音の組み合わせ。メロディと対照的に、音を同時発生させる音の集合。
- 構成音
- 和音を作る個々の音名。例えば I和音なら1度・3度・5度の音で構成される。
- 根音
- 和音の基礎となる音。転位した場合は下に来る音が根音でなくなることもあるが、和音の“元の音”として扱われる。
- 導音
- トニックへ解決する音階の7音。主和音への導きを担い、響きを引き締める役割。
- 機能和声
- 和音の役割分担の考え方。主和音(I)、属和音(V)、下属和音(IV)の三つの機能を使って進行を設計する。
- 属和音(V和音)
- 緊張感を生み出す和音。主和音へ強く解決させる性質があり、和声の推進力となる。
- 下属和音(IV和音)
- 安定感を生み出す和音で、しばしば属和音へと流れる前触れとして機能する。
- 完全終止
- VからIへ解決して聴感上最も安定とされる終止形の和声進行。
- 半終止
- 文の終わりを示すが、強い解決感はなくVで終わる進行形。
- 終止形
- 楽曲の終結を区切る和音の配置の総称。
- I度三和音の構成音
- I和音を構成する1度・3度・5度の音。例:C–E–G(Cメジャーの場合)。
- 第1転位
- I和音の第一転位。3度と5度と根音の順で鳴る配置(例:3–5–1)。
- 第2転位
- I和音の第二転位。5度・1度・3度の順で鳴る配置(例:5–1–3)。
- 転回形
- 同じ和音でも音を入れ替えて響きを変える形。第1転位・第2転位などがある。
- 長調/短調
- 主和音の性質と響きが異なる二つの調性。長調は明るく、短調はやや暗めの響きになりやすい。
- 調性
- 曲全体の基本的なキーや音階の枠組み。
- 和声進行
- 和音が連なっていく順序のこと。代表例には I–IV–V–I などがある。
- 基本進行(I–IV–V–I)
- 最も典型的な和声進行のひとつ。主和音を中心にIVとVを経てIへ解決する流れ。



















