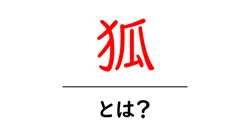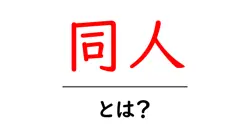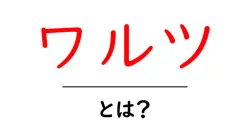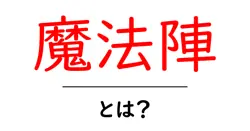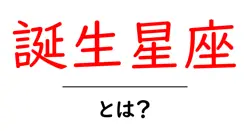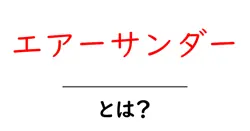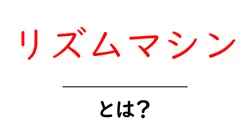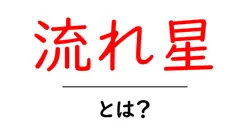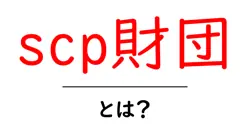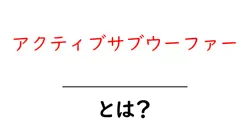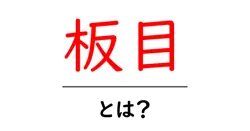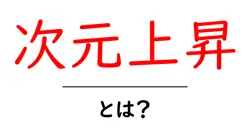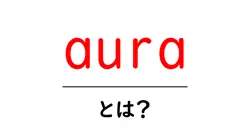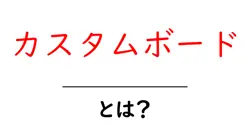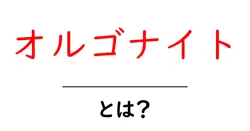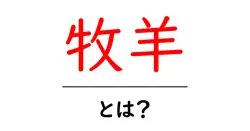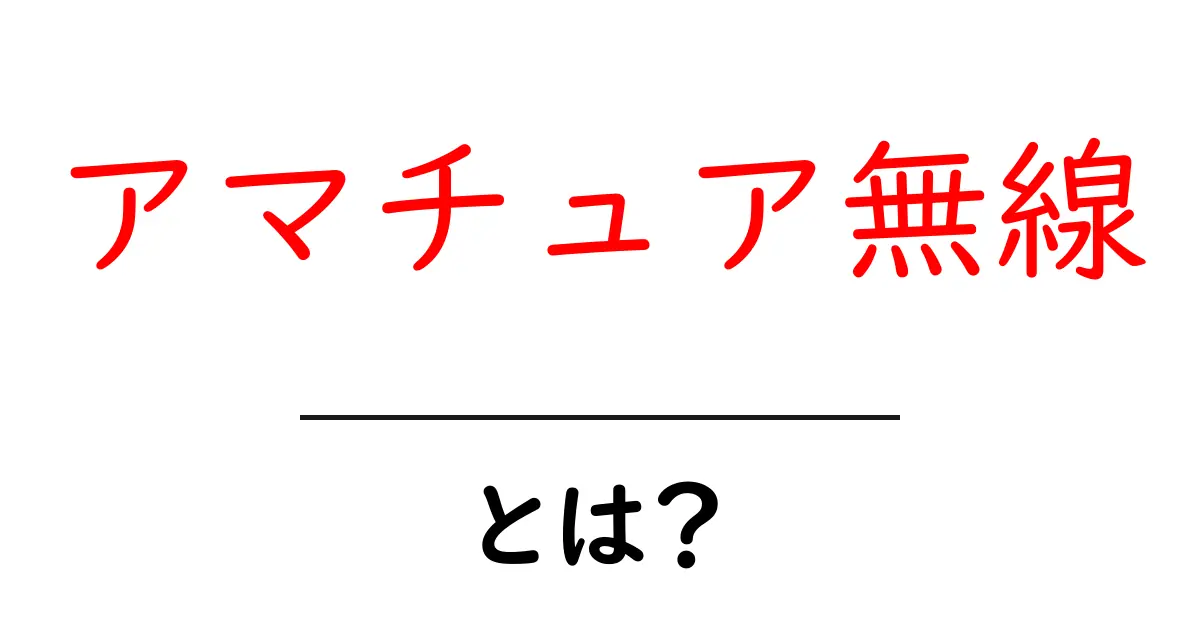

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
アマチュア無線は、個人が無線通信を使って仲間と話したり、さまざまな情報を交換したりする趣味です。初めて耳にする人にも分かりやすいように、基本の考え方と、始める手順をやさしく紹介します。
アマチュア無線とは?
アマチュア無線とは、無線局を自分で開設し、法令で決められた周波数帯で通信を楽しむ活動のことです。実際には、世界中の人と会話を楽しんだり、機材の仕組みを学んだり、天気や自然現象を観察したりする目的で行われます。大切なポイントは、無線局を開設するには適切な免許と設備、そして法令遵守が必要であることです。
基本のしくみ
無線は空気中を伝わる電波を使います。無線機は送信機と受信機、アンテナ、電源から成り立ちます。これらを組み合わせて、決められた帯域と出力を守りながら通信します。初心者のうちは、機器の動かし方や周波数の読み方を学ぶことから始めましょう。
免許とルール
日本でアマチュア無線を始めるには、総務省の免許が必要です。免許の取得には、基礎的な無線工学・法令の知識を問う試験が伴います。さらに、電波法に従い、周波数帯と出力の制限を守ることが求められます。違反した場合には免許の取消や罰則の対象になることもあるため、最初は講習会や専門書で基礎を学ぶと安心です。
始める前に知っておきたいこと
無線は安全で楽しい趣味ですが、機材の組み立てや設置には専門知識が必要な場合があります。地域の無線クラブやオンライン講座に参加して、経験者の話を聞くとよいでしょう。実際に話してみると、機械の中身が見えてきて学ぶ楽しさが増します。
用語と基本の用語表
初心者向けの主要用語を、分かりやすく表にまとめました。
どう始めるの?
初心者が無線を始める基本的な流れは次のとおりです。学習を最初にしっかり行い、次に機材を選び、最後に開局手続きをします。
1) 学ぶ: 基礎的な知識と法令を学習します。入門書、動画、講習会が役に立ちます。
2) 機材を選ぶ: 初心者向けのセットや中古機器を選ぶとコストを抑えられます。アンテナ選びも重要です。
3) 申請と開局: 総務省の手続きに従い開局します。開局後は周波数帯のルールと安全を守って運用します。
ここで大切なのは、安全第一・法令遵守・学習を続けることです。最初は難しく感じるかもしれませんが、仲間のサポートがあり、徐々に理解が深まります。
まとめ
アマチュア無線は、世界中の人とつながる楽しさを体験できる趣味です。正しい知識と手続き、適切な機材の準備をすれば、誰でも始められます。もし興味があるなら、地域の無線クラブに参加して経験者の話を聞いてみてください。新しい友だちや技術の学びが待っています。
アマチュア無線の関連サジェスト解説
- アマチュア無線 ft8 とは
- 実際の使い方は次のようになります。まず、無線機とパソコンを接続し、WSJT-Xというソフトを使ってFT8モードを選択します。次に、周波数をFT8用の帯域に合わせ、画面の表示を見ながら相手を待ちます。誰かが呼び出しを送ると、こちらのパソコンがその信号を解析して返答します。送信は音声ではなくデータとして行われるため、ボイスモードより静かな音にも対応できます。FT8は運用ルールを守ることが前提ですので、ライセンスの有無や地域の法令を確認し、適切に運用してください。機材は無線機、パソコン、サウンドカードやインターフェース、ケーブルなどが基本です。初めは身近な人と安全・マナーを守って練習するとよいでしょう。FT8は世界中の人と交流できる一方で、すぐに返事が来るわけではないこともあります。根気よく待つ忍耐力や、信号の届きやすさを学ぶ良い機会になります。
- アマチュア無線 コンテスト とは
- アマチュア無線 コンテスト とは、世界中のアマチュア無線局が決められた時間内にできるだけ多くのQSOを作り、得点を競うイベントです。QSOは1回の交信のことを指し、交信にはコールサイン(相手局の識別)、相手の場所、使われたバンドとモード、信号レポートなどをログに残します。信号レポートはRS(T)と呼ばれ、Rは読みやすさ、Sは信号の強さ、Tはトーンを表します。コンテストにはいくつかの運用スタイルがあり、ランモード(自分から呼びかけて多数の局と交信を狙う)と、 CQを出して他局が呼んでくるのを待つ形などがあります。難しそうに見えますが、初心者でも参加できるルールが用意されており、公式の解説やクラブのサポートを受ければ始めやすいです。コツとしては、まず自分の機材と周波数帯を整理し、ログをきちんと残すこと、ルールを事前に確認することです。多くの大会ではバンドやモードごとにポイントが決まり、獲得したQSO数に加え、地域や国の数といったマルチプライヤーを掛け合わせてスコアを作ります。日本国内では日本アマチュア無線連盟(JARL)などが主催する大会があり、初心者向けのイベントも開かれています。さらに、実際に参加するにはライセンスを持っていることが基本条件です。クラブ活動に参加したり、経験者の仲間と一緒に練習したりするのも良い方法です。練習としては、身近な仲間と短時間の小規模イベントから始め、徐々に長い時間や複数のバンドへ挑戦すると良いでしょう。これらを通じて、無線の楽しさだけでなく、機材の扱い方や周囲の安全にも配慮する力が身につきます。
- アマチュア無線 コールサイン とは
- アマチュア無線 コールサイン とは、無線を楽しむ人に与えられる“名前”のようなものです。無線局を識別するための固有の識別子で、世界中の相手にも自分が誰なのかを伝える役割を持っています。コールサインは国や地域を示す先頭の部分、地域を表す数字、そして個人を識別するアルファベットの組み合わせでできています。日本の場合は、例として JA1AAA のような形がよく使われます。ここで JA は日本を示すプレフィックス、1 は地域ブロックを示す数字、AAA は個人を特定するアルファベットの組み合わせです。コールサインは総務省の所管である日本の電波法のもとで運用され、取得にはアマチュア無線のライセンスが必要です。ライセンスを取得するには、無線法規や電波の安全な使い方を学ぶ講習を受け、試験に合格する必要があります。合格後は自分のコールサインが割り当てられ、無線機に表示して運用を始めます。運用時には、最初に相手にコールサインと呼出符を合わせて交信を始めるのが基本です。挨拶の後、相手のコールサインを確認し、会話を進めます。コールサインには運用上のルールがあり、例えば同じチャンネルで多くの人が同時に交信しないよう、呼出符の使い方や敬称の使い方、交信の順序などが決められています。初心者は、はじめは挨拶と自己紹介、そして相手のコールサインを正しく聞き取る練習から始めると良いでしょう。練習には短波帯だけでなく、地域のクラブやオンラインのシミュレーションも役立ちます。コールサインを正しく使えるようになると、世界中の人と友達になれる楽しさを味わえます。
- アマチュア無線 pota とは
- アマチュア無線 pota とは Parks on the Air の略で、世界中の公園を使って無線の交信を楽しむイベントです。公園を拠点に無線を運用するアクティベーターと、その公園を探して交信するハンターが協力して、多くの局とつながることを目指します。POTAでは公園ごとにIDがあり、交信のたびにコールサインや周波数、時刻などの記録が公式サイトのログに残ります。一定条件を満たすと表彰や新しい公園を開拓したときの達成感を味わえます。魅力は屋外での無線体験と世界中の仲間とつながる楽しさです。装備は初めはハンディ機と折りたたみ式アンテナ、軽いバッテリ程度で十分な場合が多く、準備を工夫すれば費用を抑えられます。ただし野外運用には日差しや水分、虫よけ、交通規制など安全面にも気をつけましょう。
- アマチュア無線 リニアアンプ とは
- この記事では、アマチュア無線の世界にはさまざまな機材がありますが、その中でも「リニアアンプ」とは何かを初心者にも分かりやすく解説します。リニアアンプとは、入力されたRF信号をできるだけ波形を崩さず大きな出力に増幅する装置のことです。簡単に言えば、小さな信号を遠くへ強く届けるための機械ですが、内部にはいくつかの重要な部品が組み合わさっています。基本的な仕組みは、入力段、ドライブ段、最終段、マッチング回路、電源、そして冷却系です。入力段で信号を受け取り、ドライブ段で少し増幅します。最終段が主にパワーを生み出し、マッチング回路が出力をアンテナに合わせます。冷却は高出力になるほど重要で、過熱を防ぐためにファンやヒートシンクが使われます。リニアという名前の意味は、信号の波形をできるだけそのまま保つことです。歪みが少なければ音声やデータがきれいに伝わり、受信側で誤解が生じにくくなります。一方、リニアアンプは効率がいいとは限らず、熱を多く出すこともあるため、適切な設計と運用が必要です。用途と注意点として、アマチュア無線では出力を法令に従って設定します。高出力ほど電力消費や熱、そしてスペクトラム上の副次的な信号(ハーモニクスやサイドピーク)に注意が必要です。市販品を使う場合は、取扱説明書をよく読み、適切な帯域と出力で運用しましょう。初心者がリニアアンプを選ぶときは、帯域(どの周波数で使いたいか)、最大出力、冷却方法、機体の大きさと価格、信頼性などを確認します。初めは低出力の機器から始め、徐々に知識と経験を積んでいくのがおすすめです。
- アマチュア無線 ストローク とは
- 結論から言うと、アマチュア無線の分野で「ストローク」という用語は、一般的な専門用語としてはあまり使われません。実際のところ、ストロークは医療用語や日常語として使われることが多く、無線技術の公式な説明には現れにくいです。そのため、インターネットの記事やSNSで「ストローク」という語を見かけても、文脈次第で意味がすぐには分からないことが多いでしょう。それでは、なぜこの言葉が出てくるのかを考えてみましょう。可能性としては、英語の stroke の和訳がそのまま使われているケース、機器の取扱説明書や古い文献で別の意味が混ざって訳されているケース、あるいはCW(モールス符号)やキーイングに関連する古い表現が日本語に混じっているケースなどが考えられます。ここからは、ストロークが無線用語として現れたときに考えるべきポイントと、用語を正しく理解するためのコツを紹介します。1) 文脈を最優先で確認する どの機器・どの操作・どの資料の中で出てくるのかを見てください。説明の前後に何が書かれているか、関連する図や用語と一緒に読むと意味が見つかりやすいです。2) 信頼できる情報源を使う 公式のマニュアル、メーカーのサイト、ARRL や JARL の資料など、公的・専門的な情報源を優先しましょう。ウェブ記事だけで判断せず、同じ語が他の資料でどう説明されているかを比べると誤解を避けられます。3) 類似する用語と混同する可能性を考える 英語の stroke が、医療用語・機械の動作を指す語・古い無線文献の表現として使われることがあります。日本語訳がそのまま残ると、意味が変わって見えることがあります。4) もし意味が不明なら質問する 無線クラブやフォーラムで『ストローク』がどう使われているか尋ねると、経験者の具体例を教えてもらえることが多いです。5) 無線の基礎語の理解を深める QSO、QSL、CW、SSB、FM、アンテナ、送信機、受信機などの基本用語を先に押さえておくと、いざ新しい語に出会っても文脈から意味を推察しやすくなります。このように、ストロークという語が無線の正式な用語として頻繁に使われるわけではありません。もし特定の資料や文章でこの語を見かけたら、その文脈を一度手掛かりとして解読を試み、分からなければ信頼できる情報源で再確認するとよいでしょう。最後に、無線の学習は公式用語を一つずつ覚えるより、文脈と実例を多く読むことが理解を深める近道です。
- アマチュア無線 免許 とは
- この記事では、アマチュア無線 免許 とは何かを、初心者にも分かりやすく解説します。アマチュア無線とは、趣味として無線機を使い、世界中の人と会話したり情報を交換したりする人のための無線活動のことです。日本ではこの活動を行うために、総務省が免許を発行します。免許を取得すると、決められた周波数帯と出力で送信できる権利が与えられ、個人にはコールサインと呼ばれる自分の呼び名が割り当てられます。免許には等級や条件があり、どの周波数帯で、どれくらいの出力で送信できるかが決まっています。具体的には、無線の基礎知識、電波法・安全のルール、機器の使い方や運用上のマナーなどを学ぶ試験に合格する必要があります。合格後、申請をして免許を取得します。取得後は、通常は法令を守って運用する責任があり、他の局への干渉を避ける配慮が求められます。自分の呼出符号を使って通信する場面では、敬語やルールを守ることが大切です。学習には日本アマチュア無線連盟(JARL)などの講習会や地域の教室を活用すると良いでしょう。免許を持つと、災害時の緊急通信支援や、趣味仲間との情報共有など、社会的にも役立つ経験が積めます。
- アマチュア無線 識別信号 とは
- アマチュア無線の世界でよく出てくる『識別信号』という言葉は、通信をしている局を特定するための合図のことを指します。特に初心者にとっては、会話を始める前に自分の局を相手に知らせる“自己紹介”の役割だと覚えると分かりやすいです。識別信号の中心になるのは『呼出符号(呼出し符号)』と呼ばれるもので、免許を受けた運用者に日本をはじめとした各国の無線規則に沿って割り当てられます。呼出符号は国ごとに決まりがあり、日本ではJAやJHなどの形で始まることが多いですが、地域によってさまざまです。使い方は、送信を開始する時、会話の区切りごと、そして会話が終わるときに必ず相手に局を識別して伝えることです。識別は自局の呼出符号をそのまま声で読み上げる方法が基本ですが、モールス符号(CW)やデジタルモードでは符号を使って送信することもあります。どのくらいの頻度で識別するかは地域のルールによりますが、一般には『10分ごとに1回以上』『送信の終了時にも必ず1回』といった規定が多いです。長時間の交信では、途中で自局をはっきり知らせることが大切です。識別信号を正しく送る目的は、混信の防止、誰が話しているのかを相手に知らせる、非常時の連絡をとりやすくする、そして無線の健全な運用のためです。初心者は最初は“呼出符号を読み上げる練習”から始め、会話が続く間にも適切なタイミングで挿入する練習をしましょう。実践のヒントとしては、家族や友人と模擬交信を作って、開始時と中間と終わりに自分の呼出符号を伝える練習をすると良いです。さらに、無線クラブやオンライン講座でルールを確認し、地域の管轄局のサイトにあるガイドを見て、実際の運用に必要な知識を身につけてください。なお、識別信号の扱いは地域によって細かい規定が異なります。日本や他の国で取得した免許の有効性や呼出符号の形式も異なることがあるため、必ず自分の地域の総務省・規制機関やJARLの情報で最新のルールを確認しましょう。
- アマチュア無線 pk とは
- アマチュア無線 pk とは、英語の Packet の略で、パケット通信というデジタル方式を指す言葉です。アマチュア無線の世界では、音声だけでなくデータを送る通信も行われます。パケット通信では、情報を小さなデータのかたまり(パケット)に分けて、相手の無線機へ順番に送ります。受信側ではパケットを組み立て直して元の情報を再現します。具体的には、AX.25 というデータの枠組みが使われ、送信元と宛先のコールサイン、データ本体、誤り検出の情報などがパケットの中に入ります。
アマチュア無線の同意語
- アマチュア無線
- 無線を趣味として運用・学習する人々の活動全体を指す一般的な語。免許を取得し、無線局を運用することが前提となる日本での正式な名称。
- アマチュア無線通信
- アマチュア無線を用いた通信そのものを指す語。音声、データ、モールスなどを用いて情報をやり取りする行為を含む。
- アマチュア無線局
- 免許を受けて運用される無線局を指す語。個人・クラブ・学校などが所有・運用する局を含む表現。
- ハムラジオ
- アマチュア無線を日常会話で指す俗称。一般的に“ハム”と略されることが多い。
- ハム
- アマチュア無線の愛好者・利用者を指す呼称。本人を指す場合もある。
- アマ無線
- アマチュア無線の略称。カジュアルな表現として記事や会話で頻繁に使われる。
- 無線趣味
- 無線を趣味として楽しむことを表す語。特にアマチュア無線の趣味性を強調する際に用いられる。
- 無線愛好者
- 無線通信を趣味として愛好する人のこと。アマチュア無線の愛好家を指す一般的な表現。
- アマチュア無線技術者
- アマチュア無線に関する技術を学び、実践している人を指す言い方。
アマチュア無線の対義語・反対語
- 商用無線
- 企業や団体の業務用途で使われる無線。営利活動の連絡・サービス提供を目的とし、周波数帯・出力・運用ルールはアマチュア無線とは異なる。
- 業務用無線
- 現場の業務連絡を目的とした無線。工場・建設現場・物流などで使われ、個人の趣味利用ではなく業務遂行が中心。
- 公的無線
- 政府機関・自治体・警察・消防など公的機関が災害対応・行政運用のために使う無線。
- 産業用無線
- 産業分野で使われる無線。製造・倉庫・資材管理など、現場の効率化を目的とした運用。
- 放送無線
- テレビ・ラジオ放送など広く聴取者へ情報を届ける無線。用途・発信対象がアマチュア無線とは大きく異なる。
- プロフェッショナル無線
- 専門職として無線を運用・監督する通信。高度な信頼性・規制遵守が求められる場面が多い。
- 公衆安全無線
- 警察・消防・救急など公衆安全分野で使われる専用無線。緊急時の連携を支える役割を持つ。
- 民間企業向け無線
- 民間企業が自社の業務連絡・現場運用のために利用する無線。商用性が高く、アマチュア無線とは別カテゴリ。
- 放送局系無線
- 放送局と連携した無線系の運用。大量の受信者を前提にした情報伝達が中心で、趣味用途のアマチュア無線とは異なる。
アマチュア無線の共起語
- アマチュア無線技士
- アマチュア無線を合法的に運用する資格を持つ人のこと。第一級・第二級・第三級などの区分があり、免許取得が前提です。
- コールサイン
- 呼出符号。あなたの局を識別する固有の符号で、免許に基づき割り当てられ、交信時に相手へ通知します。
- QSLカード
- 交信の成立を証明するカード。相手局へ送って交信報告を確認・記録するための伝統的な手段です。
- QSO
- 無線での交信そのものを指す用語。1対1の会話や情報交換を意味します。
- 無線局
- 免許を受けて運用される無線機器とアンテナを含む局全体を指します。
- 免許
- 無線機器を運用するための国家資格。取得後に適用範囲が定められます。
- 免許状
- 免許の正式な証明書。免許の内容や有効期間を示します。
- 電波法
- 無線の運用ルールを定める日本の法律。周波数の割り当て・出力制限などを規定します。
- 総務省
- 日本の電波を管轄する行政機関。無線規制や周波数管理を担当します。
- 日本アマチュア無線連盟
- JARL。国内のアマチュア無線を支援・情報提供する主要団体。
- バンドプラン
- 周波数の用途を割り当てる運用指針。混信防止や法令順守のために存在します。
- 周波数帯
- 無線で使われる周波数の大きな区分。例としてHF(短波)、VHF、UHF など。
- モード
- 通信の方式のこと。音声・データ・符号伝送など、送受信の形式を指します。
- CW
- モールス符号で送受信する伝統的モード。
- SSB
- Single Side Band の略。HF帯の音声モードの一つです。
- FM
- Frequency Modulation の略。音声を搬送波の周波数で変調する方式で、主にVHF/UHFで使われます。
- デジタルモード
- デジタル信号を用いて交信するモード群の総称。PSK31、RTTY、JT65、FT8 などを含みます。
- FT8
- 現在最も普及する低信号伝搬向けデジタルモードの一つ。短時間で交信を成立させやすい特徴があります。
- JT65
- デジタルモードの一つ。長距離伝搬時に安定して交信可能です。
- QRP
- 低出力運用のこと。一般的には5W以下など、出力を抑えて運用します。
- アンテナ
- 電波を送受信するための導体。性能は設計・設置場所で大きく左右されます。
- トランシーバー/リグ
- 送受信機の総称。局の中核機材として用いられます。
- 自作
- 機材を自作したり改造したりする趣味。コスト削減や学習目的で行われます。
- ハンディ機
- 携帯型の無線機。屋外運用や非常時の携帯性に優れています。
- コンテスト
- 多くの局と短時間で交信数を競うイベント。運用技術と機材の両方を試されます。
- ハムフェア
- 日本で開催される大規模な無線機イベント。製品展示や講演などが行われます。
- アマチュア無線クラブ
- 地域の無線愛好家が集まる会。情報交換や技術講習、イベントの場になります。
- 災害時/緊急通信
- 災害発生時における通信支援の役割。非常時のバックアップ通信として活用されます。
- 国内局
- 日本国内の無線局との交信。
- 海外局
- 海外の無線局との交信。
アマチュア無線の関連用語
- アマチュア無線
- 趣味として無線を使い、世界中の人と交信を楽しむ活動です。法令を守り、免許を取得したうえで運用します。
- コールサイン
- 無線局を識別する固有の呼名で、免許取得後に割り当てられます。例: JA1XYZ、JF7ABC など。
- 無線局
- 送信と受信を行う設備と場所の総称。基地局、移動局、常設局などの区分があります。
- アマチュア無線技士
- アマチュア無線を運用するための国家資格。三級・二級・一級などの階級があります。
- 第一級アマチュア無線技士
- より広い周波数帯域と運用権限を持つ上位クラスです。
- 第二級アマチュア無線技士
- 中位クラスで、より多くの帯域・運用が可能です。
- 第三級アマチュア無線技士
- 入門レベルのクラスで、基本的な運用が可能です。
- 基地局
- 自宅や専用施設に設置される固定局で、長時間の運用に向います。
- 移動局
- 車載・携帯など、場所を変えて運用する局です。
- QSLカード
- 交信を証明する受領カード。QSOの記録として保管します。
- ログブック
- 交信の記録を整理する日誌。紙・デジタルの形式があります。
- モード
- 通信の方式のこと。例: FM、SSB、CW、AM、デジタルモードなど。
- モールス信号(CW)
- モールス符号を用いる伝統的な通信方式です。
- FM
- 周波数変調を使う音声通信のモードで、日常的に多用されます。
- SSB
- 単側波帯のモード。HF帯で長距離通信に向きます。
- AM
- 振幅変調の通信モード。現在は主流ではない場面もあります。
- デジタルモード
- デジタル信号を用いる通信モード群の総称。RTTY、PSK31、FT8/FT4 などを含みます。
- RTTY
- ラジオテキストを送受信する古典的なデジタルモード。
- PSK31
- 低速デジタルモードで、短いメッセージをやり取りします。
- JT65/JT9/JS8Call
- 弱い信号でも交信できるデジタルモード群。
- FT8/FT4
- 低出力・短時間交信を得意とする現代的デジタルモードです。
- アマチュア衛星通信(OSCAR)
- 人工衛星を使って地上局と交信する活動。OSCARと呼ばれます。
- DX/遠距離運用
- 遠方の局と交信すること。世界中の同好者とつながる楽しみです。
- 出力/電力制限
- 送信出力の上限は帯域や免許クラスによって決まります。省電力運用(QRP)も人気です。
- アンテナ/無線設備
- ダイポール、モービルアンテナ、ビームアンテナなど、電波を送受信するための機材全般です。
- リグ/トランシーバー
- 送受信を行う実機(ラジオ本体)を指します。
- DIY/自作
- 自作のアンテナや自作機、改造を楽しむ活動。技術の向上につながります。
- JARL/日本アマチュア無線連盟
- 国内のアマチュア無線家が所属する団体。免許情報の提供やイベント、QSL窓口などを行います。
- 電波法/法規
- 無線を扱う際の法律・規則。免許、出力、周波数の使用制限などを定めています。
- 天体通信/アマチュア衛星
- 衛星を介した交信を楽しむ分野で、OSCARという枠組みで呼ばれます。
- バンドプラン/周波数帯の使い方
- 各帯域の利用の目安や混信を避けるルール。運用のマナーにも関係します。
アマチュア無線のおすすめ参考サイト
- アマチュア無線とはAbout Amateur Radio - JARD
- アマチュア無線とは - 山梨大学
- アマチュア無線とはAbout Amateur Radio - JARD
- アマチュア無線とは?楽しみ方となぜ人気なのかを5分で解説