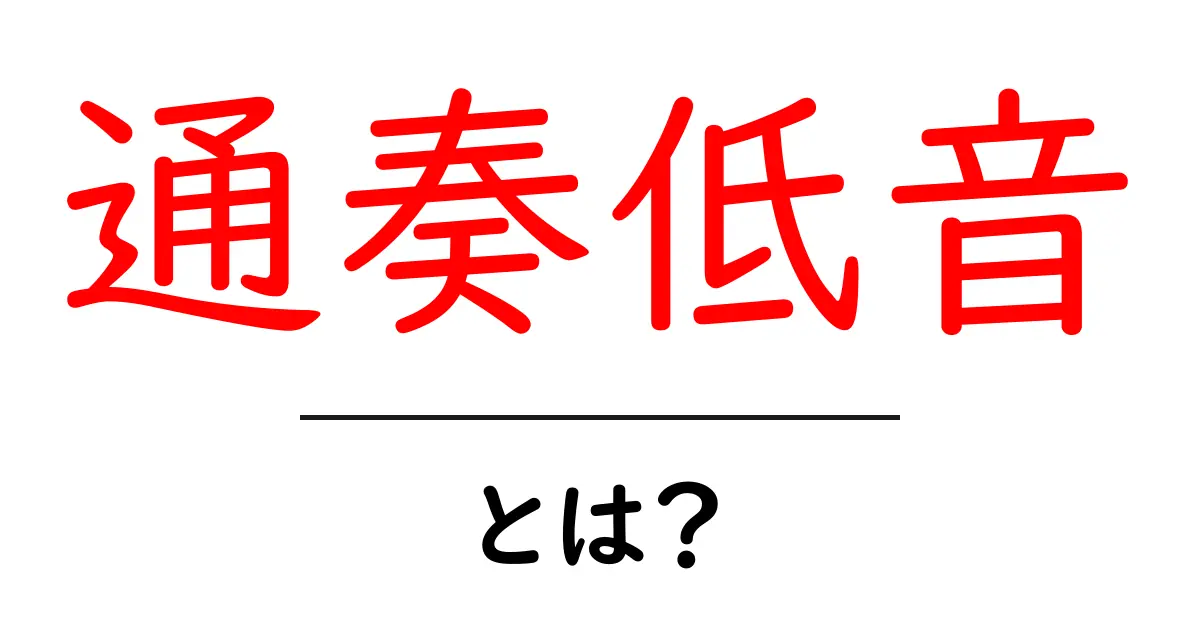

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
通奏低音とは?基本をわかりやすく解説
こんにちは。この記事では、通奏低音という音楽の技法について、初めてでも分かるようにやさしく説明します。
通奏低音とは、低い音を長く支える役割の音楽の仕組みです。曲の「土台」となる部分の基音を、チェンバロやオルガンなどの鍵盤楽器と、チェロやコントラバスのような低音楽器が一緒に演奏します。こうして低音が安定すると、他の楽器がその上に和音をのせて豊かな響きを作り出すことができます。
歴史と目的
この技法は、バロック時代に特に重要になりました。作曲家は和声の構造を意識して書き、演奏者は低音のラインを演奏することで音楽の方向性を決めました。
どんな楽器が使われるの?
典型的な組み合わせは、チェンバロやオルガンと、チェロやヴィオラ・ダ・ガンバ、コントラバスなどの低音楽器です。鍵盤楽器が和音の“指針”を示し、他の楽器がその指針に従って和音を組み立てます。
現代の解釈と学び方
現在でも、通奏低音は歴史的演奏の基本概念として研究・演奏されています。現代の演奏では、鍵盤楽器1台または2台に、低音を担当する楽器を組み合わせる形が多いです。初心者が学ぶ場合は、まず和音の基本形と低音のつながりを理解すると良いでしょう。
- 要点: 通奏低音は低音と和声を同時に支える仕組みです。
- 覚え方: 低音を安定させること、和声を聞くことを意識する。
身近な例として、ピアノの左手で低い音を安定させ、右手で旋律を演奏する場面を想像してください。これが通奏低音の考え方の基本です。音楽を聴くときには、低音が曲の土台を作っていることに気づくと、メロディと和音の関係がよりよく理解できます。
通奏低音の練習方法としては、まず「和声音程の感覚」を養い、次にfigured bassの読み方を学ぶと良いです。現代の教育では、鍵盤楽器の演奏と低音楽器の聴き分けを同時に進めることが多く、聴覚的に和声の流れを追う練習が推奨されます。
通奏低音の同意語
- バッソ・コンティヌオ
- バロック期の音楽で用いられる、低音部を担当する楽器群(例:チェロ、コントラバス)と、それを元に和声を実現するキーボード楽器(チェンバロ、オルガン、リュート)を組み合わせて和声の基盤を持続させる演奏形式。
- コンティヌオ
- バッソ・コンティヌオの略称で、低音と和声の実現を担うこの仕組みを指す短い呼称。
- 持続低音
- 低音が絶えず持続して和声を支える特徴を表す語で、通奏低音の核心的性質を言い換える表現。
- 継続低音
- 低音が継続して鳴り続く点を強調する表現で、通奏低音の意味を説明する際に使われることがある。
- 連続低音
- 低音が連続して鳴ることを表す語で、通奏低音の要素の一つを指す言い回し。
- 低音オスティナート
- 低音部にオスティナート(繰り返し模様)がある場合の表現で、通奏低音の一形態を示す。
- オスティナート低音
- 低音の反復模様を特徴とする表現。通奏低音の説明に使われることがある。
- 和声基盤低音
- 和声音の基盤を形成する低音を指す言い換えで、通奏低音の役割を説明する際に用いられる。
通奏低音の対義語・反対語
- 無伴奏
- 伴奏がない状態。歌や楽器がソロで演奏することで、通奏低音のような低音付きの和声を伴わない演奏形態を指す。
- 独奏
- 一人の演奏者だけで演奏する形。複数の楽器・声の伴奏や和声がない場面で用いられる。
- モノフォニー
- 一つの旋律線だけが鳴る編成。和声の同時進行がない状態。
- 和声なし
- 和音・和声の進行がない状態。旋律中心の演奏に近い形を指す。
- アカペラ
- 楽器伴奏を使わずに歌うこと。無伴奏とほぼ同義だが、歌唱を指す語として使われることが多い。
- 旋律中心
- 和声よりも旋律を主役とする演奏形態。和声の補助となる bass の役割が薄い場合を指すことがある。
- 低音なし
- 低音部を省略した編成。通奏低音の役割がなく、響きが薄くなる状態。
- ソロ演奏
- 一人で行う演奏。特定の楽器や声が一人で完結する演奏形態を指す。
通奏低音の共起語
- オスティナート
- 一定のリズム・モチーフが低音部で繰り返される技法。通奏低音の背景を作る役割。
- 低音
- 楽曲の最も低い音部。通奏低音の基盤となる音域。
- 数字譜
- 通奏低音の和声を数字で指示する記譜法(figured bass)。
- 和声
- 音を同時に鳴らす構成。通奏低音は和声の骨格を支える。
- ハーモニー
- 和音の組み合わせと響き。通奏低音が背景で和声を整える。
- 調性
- 曲の調・キーの性質。通奏低音は調性に基づく和声進行を前提とする。
- バロック音楽
- 17〜18世紀の音楽様式。通奏低音の発展と深く結びつく時代。
- チェンバロ
- 鍵盤楽器の一つ。通奏低音の基本的な実演楽器。
- チェロ
- 低音部を担う弦楽器。通奏低音の典型的な担当楽器の一つ。
- コントラバス
- 低音楽器の総称。通奏低音の低音ラインを支える役割。
- バッソ・コンティヌオ
- イタリア語で“通奏低音”;低音と和声の土台を指す。
- 対位法
- 複数の旋律が相互に関係して進む技法。通奏低音は和声基盤を提供する。
- 和声進行
- 和音がどの順序で進むかの流れ。通奏低音はこの進行を支える裏方。
- 音楽理論
- 音楽のしくみを学ぶ理論。通奏低音の理解には基礎理論が役立つ。
- 演奏法
- 実際の演奏での表現・実現の方法。通奏低音の具体的な演奏手法を含む。
通奏低音の関連用語
- 通奏低音
- バロック音楽で使われる基本の伴奏法。低音のラインを基準に、和音を現実化して演奏します。チェンバロやオルガンなどの鍵盤楽器と、チェロやガンバ、テオルボなどの低音楽器の組み合わせが一般的です。
- バッソ・コントゥーネ
- 通奏低音の別称。イタリア語表記で同じ意味です。
- フィギュアド・ベース(figured bass)
- 楽譜の低音に対して数字を添えて和音の構成を指示する記譜法。演奏者はその指示をもとに和音を現実化します。
- 和声の実現
- 低音の指示に従い、和音の構成を具体的な音として弾く技法。主に鍵盤楽器で即興的に行われます。
- チェンバロ
- 鍵盤楽器の一種で、通奏低音の実現で最も一般的に用いられます。低音を支え、和声を響かせます。
- オルガン
- 教会音楽で頻繁に用いられる鍵盤楽器。持続する低音と和声の補助を担います。
- チェロ
- 低音部を担当する弦楽器。通奏低音の低音線を演奏する重要な楽器です。
- ヴィオラ・ダ・ガンバ
- 低音部を担当する弦楽器の一つ。温かい音色で和声を支えます。
- リュート
- 指弾きの弦楽器。通奏低音の補助として使われることがあります。
- テオルボ
- 長尺のリュートに近い弦楽器。低音の強化と響きを提供します。
- グラウンドベース(ground bass)
- 楽曲全体を通して繰り返される低音動機。通奏低音の基盤となることが多い。
- オスティナート
- 反復するベースラインやリズムの動機。通奏低音の構造を作る基本要素です。
- 即興
- 通奏低音の実現は多くの場合、書かれた指示だけでなく、演奏者が即興で和音を補うことを含みます。
- バロック音楽
- 通奏低音が特に発達・普及した時代の西洋音楽。



















