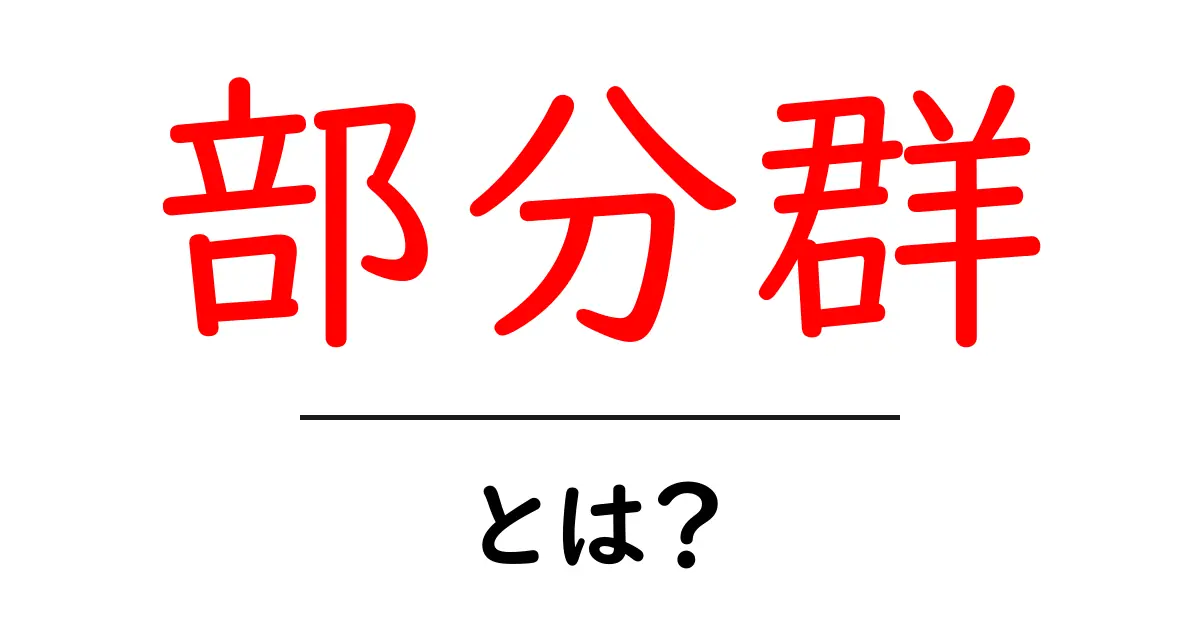

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
部分群とは何か
部分群は、数学の大きな枠組みである群の中の小さな集まりを指す言葉です。ここでは 部分群 という言葉の意味を、初心者にも分かるように丁寧に解説します。
まず覚えておきたいのは、群とは集合とその上で定義された演算の組み合わせが、次のような性質を満たすものだということです。演算は結合的であり、適切な単位元が存在し、全ての元には逆元が存在します。これらの性質を満たす集合と演算の組を群と呼びます。例を挙げると、整数の集合と加法の組み合わせは群の一例です。
このような群の中で、いま挙げた群の一部を取り出しても、その取り出し方によっては再び群として成り立つことがあります。これを部分群と呼びます。要するに、元の群の性質を壊さずに取り出した“小さな群”のことです。
部分群になるためには、単に元を集めるだけでは不十分です。次の3つの条件をすべて満たす必要があります。1) 閉包性、2) 単位元の包含、3) 逆元の包含です。これらを順番に見ていきましょう。
まず 閉包性 とは、集合内の任意の2つの元を演算して得られる結果が、同じ集まりの中に必ず含まれているという性質です。次に 単位元の包含 とは、取り出した集合の中に元として0や1など、元の演算において“そのままの効果”を持つ元が含まれていることを意味します。最後に 逆元の包含 とは、集合の中の任意の元に対して、その元と演算をすると単位元になるもう一つの元が、必ずその集合の中に存在することを指します。これら3つを満たして初めて、その集合は部分群となります。
ここで具体的な例を見てみましょう。例1として、全ての整数の集合 Z に加法を考えるとします。このとき 集合 2Z = {…, -4, -2, 0, 2, 4, …} は部分群になります。なぜなら、2Z の任意の二つの元を足しても、必ず再び 2Z に入るからです。加法の単位元は 0 であり、0 は 2Z に含まれています。また、任意の元 a ∈ 2Z に対して -a も 2Z に含まれ、逆元の条件も満たします。
例2として、有限群の一つであるモジュロ演算を考えます。G = Z4 に加法を適用するとします。G の部分群として {0}、{0, 2}、そして {0, 1, 2, 3} の全てが挙げられます。これらはすべて部分群の条件を満たします。特に丸め込みの演算において、{0, 2} は 4 の約数 2 に対応するようなサブグループとして振る舞います。このように部分群は、もとの群の構造を保ちながら、サイズや性質の異なる小さな構成を作る役割を果たします。
実際に自分で確認してみる手順を簡単にまとめます。まず元を集めて候補を作る、次にその集合が演算に対して閉じているかを確かめる、単位元と全ての元の逆元が含まれているかを確認する。この3つをクリアすれば、その集合は部分群です。反対に、これらのどれか一つでも欠けていれば、それは部分群ではありません。初心者のうちは、まず簡単な例から練習して、感覚をつかむとよいでしょう。
部分群を理解するためのコツ
最初は「どんなときに部分群になるのか」を直感的に考えると良いです。例えば「全体をそのままの形で演算していくとき、ある元の集まりだけを取り出しても同じ演算で計算が完結するか」を想像してみてください。もし内側で計算が閉じ、逆元が存在するなら、それは<部分群の候補です。
さらに、表現の練習として小さな表を作ると理解が深まります。以下の表は、G = Z4 に加法を適用したときの代表的な部分群の例と、それが部分群である理由をまとめたものです。
よくある誤解と注意点
「任意の非空な subset が部分群になる」わけではありません。閉包性と逆元の包含、単位元の包含を満たさない場合は、部分群にはならないのです。とくに無条件に「演算が結合的だから大丈夫」と思いがちですが、集合に対しては徹底的に確認する必要があります。
部分群の考え方は、後で学ぶやや高度なトピックにも深く関わります。例えば対称性の考え方や、群論の定理の多くは部分群を前提として考えられることが多いです。最初は身近な例から練習し、慣れてきたら自分で新しい集合を作って部分群かどうかを検証してみてください。
要点のまとめ
部分群とは、もともとの群の性質を保ったまま、集合を小さく切り取った“群の一部”を指します。判断のコツは、閉包性、単位元の包含、逆元の包含の3条件をすべて満たすかどうかを順番に確かめることです。具体例として Z の加法や Z4 の加法のような、身近な演算を使って練習すると理解が深まります。
この考え方を押さえておくと、後で出てくる群の定理や応用にもスムーズに入っていけます。部分群は数学の中で「どうやって大きな仕組みを小さな部品で理解するか」という大切な考え方を教えてくれる基礎的な道具です。
部分群の同意語
- 子群
- 群 G の部分集合 H が、H に対しても同じ演算を適用したとき、H 自身が群の公理を満たすとき、H は G の子群(部分群)と呼ばれる。つまり、H は G の演算に対して閉じており、単位元と逆元を含み、結合法則が成り立つ集合。
- サブグループ
- 英語 subgroup の日本語表記。群 G の部分集合で、群演算を閉じ、G の群構造を保持する集合。日常的には「子群」と同義で使われることが多い。
- サブ群
- 群 G の部分集合で、演算を G に対して閉じ、群の公理を満たす集合。学術的には「サブグループ」と同義に使われる略称。
部分群の対義語・反対語
- 全体群
- 部分群の対義語として使われることがある。HがGの部分群である場合、G自体を指すときには全体群と呼ぶことがある(H = Gを含む場合もあるが、文脈により解釈が変わる)。
- 母群
- Hを含む大きな群。文脈によって母群という言い方をすることがあり、対義語的な概念として扱われることがある。
- スーパーグループ
- Hを含むより大きな群。HがGの部分群であるとき、GはHのスーパーグループになるという関係を表す。
- 上位群
- Hを包含する、より大きい群という意味。対義語的な使われ方をすることがある。
- 非部分群
- ある集合が群の公理を満たさず、部分群ではない状態を指す。部分群の対極的な性質を示す語として挙げられる。
部分群の共起語
- 群
- 集合と演算の組み合わせで、結合法則・単位元・各元の逆元が存在する代数系。部分群はこの群の性質を満たす『部分集合』です。
- 部分集合
- 群の元の中から条件を満たす一部の集合。部分群はこのうち、閉性・単位元・逆元の条件を満たします。
- 演算
- 群の元同士を結ぶ二項演算。部分群も同じ演算で構成されます。
- 閉性
- 部分集合が演算に対して閉じている性質。つまり、元どうしを演算しても結果がその部分集合に含まれること。
- 単位元
- 群の演算の中性元。部分群にもこの元が含まれます。
- 逆元
- 各元の逆元が存在する性質。部分群の任意の元には逆元が含まれます。
- 正規部分群
- すべての群元で共役を取っても、部分群の中にとどまる部分群。商群を作る際に重要です。
- 商群
- 正規部分群を法として、群の元を「割る」ことで作る新しい群。
- 生成集合
- 部分群を生成する元の集合。生成元の集合が分かれば部分群を作れます。
- 部分群の階数
- 部分群に含まれる元の個数。群の階数に対しての比率を測る目安になります。
- 有限群
- 元の数が有限な群。多くの定理は有限群での性質を扱います。
- Lagrangeの定理
- 有限群の部分群の階数は全体の階数の約数になるという重要な性質。
- 同型定理
- 2つの群が構造的に同じ形をしていることを示す定理。部分群の性質理解に役立ちます。
- 最小部分群
- 性質を満たす部分群の中で最小のもの。単位元だけを含むことが典型的な例です。
- 最大部分群
- ある部分群の上位にあって、他の含まれる部分群を含まない『最大』な部分群。
部分群の関連用語
- 群
- 二項演算を持つ集合の集合で、結合律、単位元、逆元を満たす代数系のこと。例として整数の加法群 (Z, +) などがある。
- 部分群
- G の部分集合 H が、G の演算で閉じ、単位元と各元の逆元を H に含むとき、H は G の部分群と呼ぶ。
- 自明な部分群
- 自明な部分群は {e}(単位元のみからなる集合)と、全体群 G 自身のこと。
- 全体群
- 群 G における元すべてを集めた集合で、H が G の部分群である場合も指すことがある。
- 正規部分群
- すべての元 g ∈ G に対して gHg^{-1} = H が成り立つ部分群のこと。正規部分群を用いて商群が作られる。
- 商群
- H が正規部分群のとき、G/H を定義できる。元は左陪集合の集合で、積は (aH)(bH) = (ab)H のように定義される。
- 同型写像
- 二つの群の構造が同じになるよう、操作を保存する写像。群の同型は「等しい構造」を意味する概念。
- 同型
- 二つの群が同じ構造をもつ場合、同型であると呼ぶ。対応する全単射同型写像が存在する。
- 第一同型定理
- 群同型 φ: G → K に対し、G/ker φ ≅ Im φ が成り立つ。ホモモルフィズムの核と像の関係を表す基本定理。
- 核
- ホモモルフィズム φ に対して φ(x) = e となる元 x の集合。ker φ は正規部分群になる。
- 像
- ホモモルフィズム φ が写す元の像の集合。常に部分群になる。
- ホモモルフィズム
- 群の演算を保存する写像。x, y に対して φ(xy) = φ(x)φ(y) が成り立つ。
- 単射
- 1対1の写像。異なる元が異なる像をもつ。
- 全射
- 像がすべての対象を覆う写像。すべての元が像として現れる。
- 左陪群
- ある部分群 H × G に対して、aH = {ah | h ∈ H} の形の集合。左コサートとも呼ぶ。
- 右陪群
- ある部分群 H × G に対して、Ha = {ha | h ∈ H} の形の集合。右コサートとも呼ぶ。
- 指標(Index)
- 部分群 H に対して [G : H] と書き、G を H の陪集合に分割する個数のこと。
- ラグランジュの定理
- 有限群 G に対し、任意の部分群 H の階数 |H| は |G| の約数になる。
- 生成集合
- H を生成する元の集合 S のこと。H = ⟨S⟩ と表す。S の元から H が作られる。
- 生成元
- 部分群を生成する元の集合の各元。例えば H を生成する個々の元のこと。
- 部分群の生成
- 特定の集合 S から、その元だけで作られる最小の部分群 ⟨S⟩ を構成する操作のこと。
- 共役部分群
- gHg^{-1} が H と等しい、あるいは gHg^{-1} が H の部分群として含まれる場合のこと。共役関係は正規性と深く関係する。
- アーベル群
- 全ての元が可換で、ab = ba が成り立つ群。最も基本的な例のひとつ。
- 群作用
- 群が集合に対して、群の元で集合の要素を動かす「作用」を持つ概念。軌道や安定化子などを扱う。
- 軌道と安定化子
- 軌道はある元が群作用で到達できるすべての元の集合、安定化子はその元を動かさない群の元の集合。
- 部分群の積
- H K = {hk | h ∈ H, k ∈ K}。一部の場合のみ部分群になる。正規性があるときに特に安定する。
- 部分群の交差
- H ∩ K は常に部分群になる。
- サブグループの格子
- 部分群同士の包含関係を図式化した格子構造のこと。部分群の階層を表す。
- 有限群
- 有限個の元からなる群。
- 無限群
- 無限個の元からなる群。
- 部分群判定
- H が G の部分群であるかを判定する基礎的な条件や手順のこと。通常は e ∈ H、閉包、逆元の存在を確認する。



















