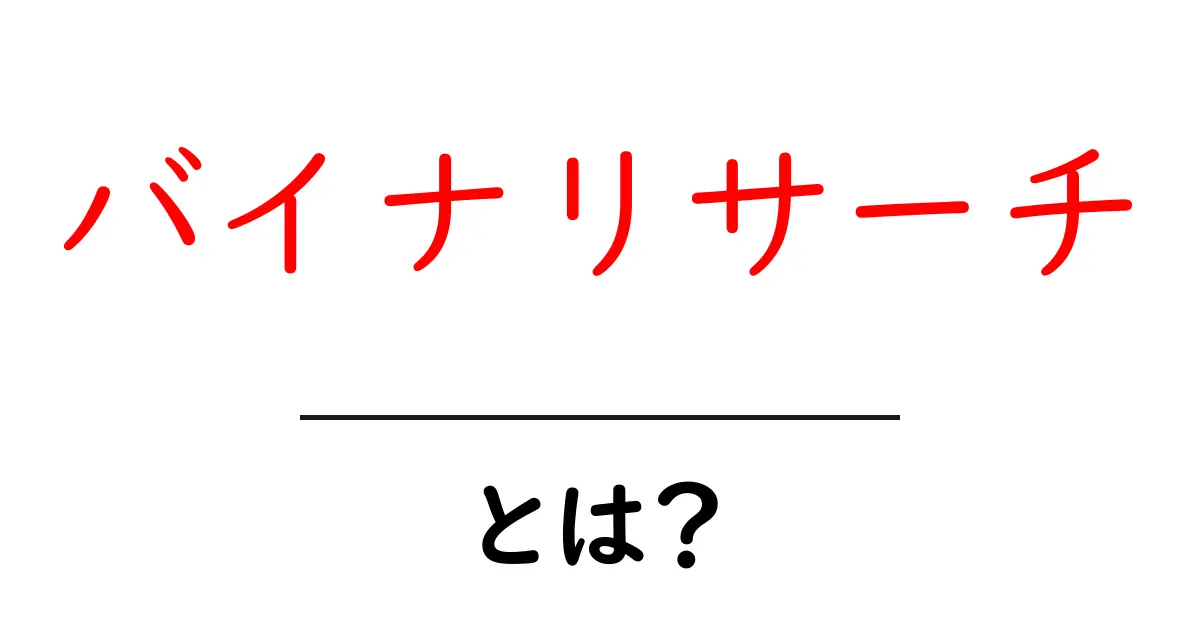

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
「バイナリサーチ」は英語で Binary Search と呼ばれるアルゴリズムの日本語名です。この方法は、データが昇順に並んでいることを前提に、範囲をどんどん半分に絞っていく点が特徴です。結果として、探す回数はデータの個数 n に対して O(log n) の回数で済み、 n が大きくなっても時間が急には増えません。
このガイドでは、初心者のひとにも分かるように、原理、手順、具体例、線形探索との違い、注意点を順番に解説します。
バイナリサーチの基本
前提条件として、配列やリストが 昇順に並んでいる 必要があります。降順でも扱いは変わりますが、通常は昇順で使います。比較可能なデータであることも大事な条件です。
基本的な考え方はとてもシンプルです。データの中央をまず見ます。そして、中央の値と探している値を比べ、左側か右側の半分だけを次の探索対象にします。これを、範囲がなくなるまで繰り返します。
使い方の流れ
1) 検索範囲を左端 l と右端 r で表します。初期値は l = 0, r = n - 1。
2) 中央の要素 m = floor((l + r) / 2) を見る。
3) data[m] が探している値 target と同じなら見つかりました。
4) data[m] < target なら、右側を捜索範囲にします。l = m + 1、それ以外は r = m - 1。
5) 探索範囲がなくなるまで 2) 〜 4) を繰り返します。見つからなければ「見つかりません」と終わります。
具体的な例
昇順に並んだ配列 [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13] の中から 9 を探す場合を考えます。
最初の中央は 5、9 は右側にあるので左端を l = 3 にします。
次の中央は 7、9 は右側にあるので左端を l = 4 にします。
次の中央は 9、一致します。これで見つかりました。
比較のポイント
線形探索(全体を順番に見る方法)と比べると、バイナリサーチは回数が大幅に減ります。特にデータの数が増えるほど差が大きく現れます。
よくある注意点
注意1: データが昇順でないときは別の方法を使います。昇順が条件を満たさない場合、バイナリサーチは正しく動作しません。
注意2: 重複する値がある場合、見つかる場所が複数あります。最初に見つかった位置を返す仕様にするか、全ての出現箇所を探す工夫が必要です。
まとめ
バイナリサーチは、データが並んでいるときに効率よく探せる基本的なアルゴリズムです。前提条件を守ること、中央を基準に範囲を半分ずつ絞ることがポイントです。これを理解すると、検索だけでなくソート後の様々なアルゴリズムにも応用が利きます。
バイナリサーチの同意語
- 二分探索
- 整列済みのデータ列から中央の要素と比較して、探索範囲を半分ずつ絞り込みながら目的の値を見つけ出すアルゴリズム。計算量は O(log n)。
- 二分探索法
- 二分探索を実現する具体的なアルゴリズムのこと。英語の Binary Search Algorithm の日本語訳で、基本的な手順を指す表現。
- 二分探査
- 二分探索と同じ意味の表現。日本語では文脈によっては『探査』を用いることがあるが、意味は同義。
- バイナリ探索
- 英語表現のカタカナ表記。日本語話者にも広く使われる同義語。
- バイナリ検索
- 英語の binary search の別表記。検索処理を指す同義語として使われることがある。
バイナリサーチの対義語・反対語
- 線形探索
- データを先頭から1件ずつ順番に調べる基本的な探索法。データが整列されている必要はなく、最悪の計算量は O(n) 。バイナリサーチの半分絞り込みと異なり、並び順の仮定に依存しません。
- 線形走査
- 線形探索と同義。データを一つずつ順に走査して条件に合う要素を探す方法。
- 逐次探索
- データを逐次的に調べる探索。未整列データにも適用でき、一般に線形探索とほぼ同義として用いられます。
- シーケンシャルサーチ
- Sequential Search の和製表現。左から右へ順に要素を検索する方法で、データが整列されていなくても機能します。
- 全探索
- 候補となる全ての要素を試して探す探索。データ数 n に対して最悪 O(n) の時間がかかり、バイナリサーチの半分絞り込みとは異なるアプローチです。
- 全件走査
- データベースやデータ集合の全レコードを1件ずつ走査して条件に合うものを探す方法。全探索と同義として使われることが多いです。
- 単純探索
- ナイーブで平易な探索方法。実装は簡単ですが、大規模データには不向きで、線形探索とほぼ同義として扱われます。
- リニアサーチ
- Linear Search のカタカナ表記。線形探索と同義です。
バイナリサーチの共起語
- 二分探索
- データ集合を中央で分割して半分ずつ範囲を絞り、目的の値を探すアルゴリズム。
- 二分法
- 半分に分割して探索を進める考え方。二分探索と同義語として使われることが多い。
- 検索アルゴリズム
- データの中から特定の要素を見つけ出す手法の総称。
- 探索アルゴリズム
- データの中から目的の要素を探し出す手法の総称。
- ソート済みデータ
- バイナリサーチを正しく動かすにはデータが昇順または降順に並んでいる必要がある状態。
- 配列
- 要素が連続して並んだデータ構造。バイナリサーチでよく利用される基本形。
- データ構造
- データを整理・格納する枠組み。バイナリサーチは特定のデータ構造と組み合わせて使われることが多い。
- 計算量
- アルゴリズムの処理時間や資源の指標。バイナリサーチでは主に時間計算量を語る。
- O(log n)
- データ量 n に対して処理時間が対数時間になることを表す表現。
- 対数時間
- データ量の増加に伴う処理時間が対数的に増える性質。
- 最悪時計算量
- 最悪の条件で求められる計算量の指標。
- 中点
- 探索範囲の中央のインデックス。
- 探索範囲
- 現在絞り込んでいるデータの範囲。
- 左端
- 探索範囲の左側の境界。
- 右端
- 探索範囲の右側の境界。
- low
- 探索範囲の下限を表す変数名としてよく使われる。
- high
- 探索範囲の上限を表す変数名としてよく使われる。
- 再帰
- 自分自身を呼び出して解を求める手法。
- 反復
- ループ処理で解を求める手法。
- 実装例
- 実際のコード例。初心者が理解を深めるための具体的な例。
- 配列検索
- 配列の中から対象の値を探す作業。
- 線形探索
- データを先頭から順に照合していく探索手法。データがソートされていない場合に使われる。
- ソート
- データを特定の順序に整列させる操作。
- 昇順
- 小さい値から大きい値へ並べる並べ方。
- 降順
- 大きい値から小さい値へ並べる並べ方。
- 条件分岐
- 範囲を絞る判断に使う条件分岐(if文など)の要素。
- 境界条件
- 探索の端の条件・境界値。
- 区間
- 絞り込みの対象となる連続範囲。
- 二分木
- データを二分木の形で構造化するデータ構造。バイナリサーチとは別の概念だが関連語として見かけることがある。
- 二分探索木
- データを二分木の形で格納・検索を高速化するデータ構造。バイナリサーチと混同されやすいが別物。
- 目的値の存在確認
- 探している値がデータ集合にあるかを判定することを指す表現。
バイナリサーチの関連用語
- バイナリサーチ
- 整列済みデータに対して、中央の要素と比較して探索範囲を半分ずつ絞り込む探索アルゴリズム。時間計算量は O(log n)。
- 整列済みデータ
- 探索を正しく行うために、データが昇順または降順に並んでいる状態。バイナリサーチはこの前提が必要。
- 左端インデックス
- 現在の探索範囲の下限を指すインデックス(low)。
- 右端インデックス
- 現在の探索範囲の上限を指すインデックス(high)。
- 中間要素
- 現在の探索範囲の中央に位置する要素。ターゲット値と比較して進む方向を決める。
- 探索範囲
- 現在検討しているデータの区間。通常は low から high までのインデックスで表す。
- 比較操作
- ターゲット値と中間要素を比較して、左側へ絞るか右側へ絞るかを決定する処理。
- 半分に絞る
- 探索範囲を常に半分に縮小する操作のこと。
- 時間計算量
- アルゴリズムが要する計算時間の目安。バイナリサーチは O(log n)。
- 空間計算量
- 追加のデータ構造に使うメモリ量。反復実装では通常 O(1)、再帰実装では O(log n) などの影響がある。
- 再帰実装
- 自分自身を再帰的に呼び出して探索を進める実装。理解しやすいがオーバーヘッドが増えることがある。
- 反復実装
- ループを使って実装する方法。スタック操作が不要で高速になることが多い。
- 境界条件
- low が high を越えるなど、探索が終了する条件。見つからない場合の処理も含む。
- 二分探索木
- データを二分木の形で格納し、挿入・検索を高速に行うデータ構造。バイナリサーチとは別概念。
- 昇順/降順対応
- データの並び方に応じて、比較の方向を変える必要がある。降順の場合は探索方向の判定を反転。
バイナリサーチのおすすめ参考サイト
- バイナリサーチとは #Java - Qiita
- 二分探索(2分探索 / バイナリサーチ)とは?意味を分かりやすく解説
- 二分探索法(バイナリサーチ)とは? #アルゴリズム - Qiita
- バイナリサーチとは #Java - Qiita
- 二分探索(2分探索 / バイナリサーチ)とは?意味を分かりやすく解説



















