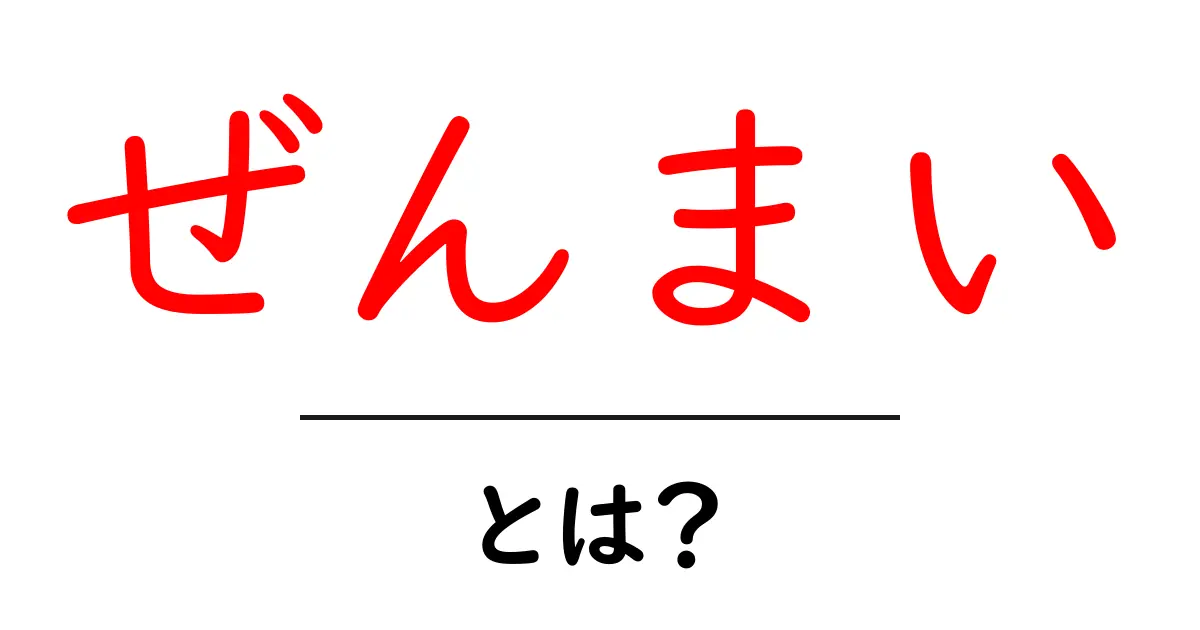

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
ぜんまいとは?機械の心臓と暮らしを動かす秘密を分かりやすく解説
みなさんが日常で耳にするぜんまいという言葉には、実は二つのとても身近な意味があります。ひとつは機械の世界で使われる「ばね」のこと、もうひとつは日本の山野に自生する植物の名前です。この記事では ぜんまい の二つの意味を分かりやすく分解し、どの場面でどの意味になるのか、どうやって動くのかを丁寧に解説します。
ぜんまいには二つの意味
以下の表を見てください。意味が違うと使われる場面も異なります。同じ読み方ですが、文脈で判断することが大切です。
機械のぜんまいのしくみ
機械のぜんまいはねじり力を蓄える「ばね」の一種です。ひねり(ねじり)でエネルギーを貯え、解放されると力が戻ってきます。時計の中には小さな円筒状のねじりばねがあり、巻くと内部の金属がねじれてエネルギーをためます。解放されると、ばねが戻ろうとする力で歯車を少しずつ回し、時計が動きます。仕組みはとても単純ですが、正確に動かすには設計の巧みさが必要です。
風船のような大きなばねではなく、時計のような細かな部品に使われる小さなぜんまいは、素材の硬さ・ばね定数・耐久性のバランスで性能が決まります。摩耗を減らすための潤滑も重要な要素です。
ぜんまいという言葉の語源と意味の変遷
ぜんまいの語源は古く、日本語の「巻く」という意味と関係があるという説があります。巻くことからエネルギーを蓄えるという発想が、機械のばねの名称として定着したと考えられています。一方、山野のぜんまいは別の語源を持つとされ、名前として定着しました。言葉の起源は諸説あり、地域によっても呼び方や使い方に差が出ることがあります。
ぜんまいの見分け方と使い分けのポイント
文脈を見れば、どちらの意味かすぐ分かります。機械のぜんまいが話題のときは、時計・機械・歯車・回転・力の蓄えといった語彙が近くに出てきます。一方、山菜のぜんまいが登場する場合は、食べ物・山野・煮物・山菜の名前といった語が出てくるでしょう。文章の主語を確認するだけでも判断はつきます。
ぜんまいの使い方の例文
・この時計は古いですが、ぜんまいを巻くとまだしっかり動きます。
・夏はぜんまいが日陰で育つ場所が多いので、山歩きの楽しみが増えます。
・煮物には山のぜんまいを使うと、風味と食感がよく出ます。
まとめ
ぜんまいには「機械のばね」と「山菜の名前」という二つの意味があります。意味が異なる二つの使い分けは、文脈を読めばすぐに分かります。機械のぜんまいはエネルギーを蓄えて解放する役割を、山菜のぜんまいは食材としての役割を持ちます。日常生活の中でこの言葉を見かけるときは、前後の語句をよく見て意味を判断しましょう。
この記事を読むことで、ぜんまいの二つの意味とその違いがはっきりわかり、学校の授業や会話の中で使い分けができるようになります。初心者の人でも、文脈を意識すれば自然に正しい意味を選べるようになるでしょう。
ぜんまいの関連サジェスト解説
- ぜんまい とは 機械
- ぜんまい とは 機械の動力源になる“ばね”の一種です。特に時計やおもちゃなど、電気を使わずに動く道具に使われます。主ゼンマイと呼ばれることもあり、現在の機械式時計の核となる部品です。仕組みとして、ぜんまいは薄い金属のリボンを螺旋状に巻いた形をしており、巻くと内部に緊張が生まれてエネルギーが蓄えられます。巻く力を強くすると蓄えられるエネルギーが多くなり、ぜんまいがゆっくり解ける間じゅう力を供給します。解放されると力は歯車列を回す動力となり、回転の速さは歯車の比率で決まります。時計のケースの中には「バレル」と呼ばれる筒があり、その中のぜんまいがゆっくりと回転を伝えながら時刻を刻みます。時計だけでなく、風のおもちゃや古いカメラのシャッター機構にも使われました。材質は主に鉄で作られ、疲労に強いよう設計されています。螺旋状のぜんまいは「主ゼンマイ」と呼ばれることもあり、筒の中の力の出方をコントロールします。長く使うと金属が疲れて弱くなることがあるので、現代の機械では耐久性を高める工夫がされています。ぜんまいのよいところは、電力を使わなくても動く点です。停電を気にせず、静かに動くため、機械式時計をはじめ趣味の道具やおもちゃにも広く利用されています。一方で容量には限界があり、長く動かすには一定の巻き直しが必要です。環境条件や摩耗、過度な巻きすぎにより破損することもあるため、取り扱いには注意が必要です。身近な例としては、腕時計を手首で巻くとぜんまいが巻かれてエネルギーを蓄え、時間が進むにつれ少しずつ力を放出して針を動かします。ぜんまいは機械の“心臓”のような役割を持つ大切な部品です。
- ぜんまい とは時計
- ぜんまい とは時計の内部にある細長い金属のスプリングで、巻くとねじれてエネルギーを蓄えます。主に機械式時計で使われ、手で巻くタイプではぜんまいを自分で巻く作業が必要です。 この蓄えたエネルギーは、ぜんまいがゆっくりほどけるときに放出され、歯車列を回して時刻を動かします。ぜんまいの回転を安定して取り出すために、エスケープメントと呼ばれる仕組みと、小さな振動部品であるバランスホイールが組み合わさり、時計を一定の間隔で進ませます。 巻き方には主に手巻きと自動巻きがあります。手巻き時計は文字どおり手でぜんまいを巻き、時間とともに力を少しずつ蓄えます。自動巻き時計は、身につけて動く人の動きでローターが回ってぜんまいを巻く仕組みです。 また、現代には電池で動くクオーツ式の時計もあり、こちらはぜんまいを使いません。機械式時計は美しい歯車の動きや音、手入れの楽しさが魅力ですが、長持ちさせるには定期的なオイルの注油や専門家による点検が必要です。 つまり、ぜんまい とは時計の動力源であり、蓄えたエネルギーをどう取り出して針を動かすかという“しくみ”が、時計の仕組みを支えています。
- ぜんまい とは 山菜
- ぜんまい とは 山菜 という言葉を見たとき、多くの人が春の山の風景を思い出します。ぜんまいは山で採れる食用の山菜の一種で、正式にはシダの仲間の若い茎を指します。名前のとおり、芽は丸く巻いた状態で現れ、成長すると葉が開いていきます。地方によって呼び方や採取時期に少し差がありますが、春から初夏にかけて山の道端や林のふちで見つけることができます。ぜんまいは栄養価が高く、食物繊維やミネラルが含まれ、体にうれしい成分を少しずつ取り入れることができます。下処理が重要で、アク抜きをしてから調理します。下処理の基本は、まず根元を切り、洗ってから熱湯で2〜3分ほど下茹でし、冷水にさらしてアクを抜きます。茹でた後は水気を絞って食べやすい長さに切ります。保存するときは、冷蔵で2日程度が目安です。調理法としては、煮物はもちろん味噌汁の具、炒め物、天ぷらなど幅広く使えます。だしとしょうゆ、みりん、少しの砂糖で甘めの煮物にしたり、和風の味付けでアクと香りを活かすと美味しいです。初めて挑戦する場合は、スーパーなどで新鮮なぜんまいを選ぶとよいでしょう。また、山で採る場合は、自然環境を守りつつ、過剰採取を避け、同じ場所に戻して後の世代のためにも配慮しましょう。
- ぜんまい ナムル とは
- ぜんまい ナムル とは、山菜のぜんまいを使い、韓国のナムル風に味付けした副菜のことです。ぜんまいは日本の山で春に採れる食材で、歯ごたえが強く香りがよいのが特徴です。ナムルは野菜を茹でて、ごま油・塩・にんにく・しょうゆなどで和える韓国料理の基本的な副菜のことを指します。ぜんまい ナムル では、ぜんまいの食感と香りを生かすシンプルな味付けが基本です。まずぜんまいをよく洗い、食べやすい大きさに切ります。次に茹でて、3分から5分程度で固さを見ながら火を止めます。茹でたらすぐ冷水にさらして色を保ち、水気をしっかり絞ります。その後、ボウルに入れ、しょうゆ、砂糖、酢、にんにくのみじん切り、少量のごま油、塩、好みで唐辛子などを加えて和えます。仕上げに白ごまをふると香りと風味が増します。味付けは好みに合わせて調整しましょう。さらにコクや香りを足したい時はごま油を少し足すと良いです。保存する場合は冷蔵庫で1日〜2日程度が目安ですが、長く置くと風味が落ちやすいので食べきる分だけ作るのがおすすめです。コツはぜんまいを茹ですぎず、歯ごたえを残すことと、ごま油の香りを活かす程度に控えることです。健康面では食物繊維が多く、腸の健康をサポートする可能性があります。家庭で作る際は、辛い味付けが好きならコチュジャンを少し加えるとピリ辛に、定番の和風テイストにしたい場合は少し酢を足してさっぱりにするなど、アレンジの幅も広い一品です。
- ゼンマイ とは
- 「ゼンマイ とは」には2つの意味があります。1つは機械の部品としてのゼンマイ、もう1つは山菜としてのゼンマイです。初心者にも分かりやすいように、順番に説明します。1) 機械のゼンマイゼンマイは金属でできたコイル状のばねです。巻くと内部にエネルギーが蓄えられ、ばねが戻る力で動く仕組みになっています。時計の中に入っているゼンマイはその代表例で、巻くと回転を蓄え、針を動かしたり、歯車の動きを調整したりします。現代のスマホには使われなくなっていますが、古い時計や機械式の玩具には今でも欠かせない部品です。機械の設計では、強さ・柔らかさ・耐久性を合わせて選ぶことが大切です。2) 食用のゼンマイゼンマイは春に山で採れる山菜で、細長い筒のような新芽が特徴です。若いゼンマイは柔らかく、老いると硬くなるので、採ってすぐに食べるのは難しい場合があります。通常はまず水で洗い、アクを抜くために短い時間ゆでます。煮物や和え物、炒め物に使われ、独特の香りとほどよい苦味が春らしさを引き立てます。食べ方は地域や家庭でさまざまです。注意点として、山菜には自然の中で育つ細菌や虫がつくことがあるので、加熱して食べるのが基本です。市場で売られているゼンマイは処理済みのものが多く、家庭での調理も比較的簡単です。3) まとめゼンマイには2つの意味があることを覚えておくと、文章を読んだり会話をするときに混乱しにくくなります。機械のばねとしてはエネルギーを蓄える役割、山菜としては春の味覚として食卓を彩る役割を持っているという点を押さえておくとよいでしょう。
- ゼンマイ とは おもちゃ
- この記事では、ゼンマイ とは おもちゃについて、基本の仕組みから遊び方、安全な使い方までを中学生にも分かる言葉で紹介します。ゼンマイ とは おもちゃについて俯瞰で理解しておくと、見た目の動きだけでなく、なぜ動くのかを想像しやすくなります。まず基本として、ゼンマイとは内部に巻き上げ式のバネを使って動く仕組みのことです。おもちゃのゼンマイは、手でゼンマイを巻くとバネにエネルギーが蓄えられ、その力が歯車を回して動きを生み出します。巻き上げる時間が長いほど長く動くことが多いですが、過度に巻くと壊れやすくなります。仕組みのポイントは、バネ、歯車、リリース機構です。歯車は小さな歯のかみ合わせで力を伝え、リリース機構が手で巻く行為と動きの開始を結びつけます。結果として、車が走る、動物の尾が振れる、鳥が飛ぶように見えるといった簡単な動きを生み出します。楽しみ方のヒントとして、平らで滑りにくい場所を選ぶこと、他のものとぶつからないよう見守ることが大切です。巻き方はほどよく力を入れて、カチッと感触があったら巻くのをやめます。力を込めすぎると部品を傷める原因になります。歴史的には、ゼンマイを使ったおもちゃは長い間子どもたちの遊びの定番でした。蒸気機関車や機械式のロボット、音楽を鳴らす箱など、色々な形に進化してきました。現代でも電池を使わない動力として、小さな部品で動くおもちゃとして人気があります。安全面では、部品が小さいものは誤飲の危険があるため小さなお子さんには向きません。大人と一緒に遊ぶこと、遊ぶ場所を安全に整えることを心がけましょう。最後に、ゼンマイ とは おもちゃを通じて、力の使い方、原因と結果の関係、機械の基本的な仕組みを学ぶことができます。観察力を養い、少しの工夫で同じ動きを工夫する楽しさも味わえるでしょう。
- 薇 とは
- 薇 とは、漢字の一つであり、現代の日本語の日常会話や文章ではあまり見かけません。日常用語としては使われず、教科書にも頻繁には登場しない珍しい字です。日本語で「薇 とは」と調べるときは、主にこの字の成り立ちや、どの場面で使われるのかを知りたい場合が多いです。中国語圏ではこの字を含む語が身近で、例えば蔷薇( qiángwēi)という言葉があります。これは日本語でいう「バラ」を指す語で、薇はその一部として使われます。こうした中国語由来の語を通じて、薇という字の意味を知る手がかりになります。現代日本語での独立した意味ははっきりと定義されていないことが多く、主に人名・地名・漢詩・漢文の引用など、特別な文脈で登場します。植物を連想させる草冠(艹)を持つ漢字であることから、字の印象としては“植物・花”と結びつくことが多いのですが、それが必ずしも現実の意味とつながるわけではありません。読み方については、日本語の辞書で確定した音読み・訓読みが付かないことが多い点も特徴です。薇は中国語の読み方が主として使われることが多く、日本語としての読み方は文脈次第で任意に当てられることがあります。名前や地名、文学作品の中で登場するときには、著者や登場人物が読みを指定している場合もあり、それをそのまま読めば良い場合が多いです。したがって学習の際には、読み方を一つに決めず、文脈を確認して読み方を判断するのがコツです。覚え方のコツとしては、「珍しい漢字だと覚える」「中国語の語彙とセットで覚える」をおすすめします。蔷薇という語に出会ったときに薇がどの字か思い出せると、関連語の意味を結びつけやすくなります。また、薇が出てくる文書を読むときには前後の語が中国語由来か、日本語の難読人名か漢詩かをチェックすると、読み方と意味が見えやすくなります。もし調べる際には「薇 とは」だけでなく「蔷薇」「薇 字 意味」など関連語も併せて調べると、全体像がつかみやすくなります。
- 時計 ゼンマイ とは
- 時計のゼンマイとは、機械式時計の動力源になる部品です。薄い金属の帯を渦巻き状に巻いたバネで、手で巻くか、腕の動きで自動的に巻き上げられてエネルギーを蓄えます。ゼンマイは巻くと張力が蓄えられるエネルギーの貯蔵庫のような役割を果たします。蓄えたエネルギーは、内部の香箱という筒を介して徐々に解放され、歯車を回して針を動かします。鉄や鋼で作られた薄い帯が解放される力に合わせて回転するため、時計の速さは一定ではなく、エスケープメントと呼ばれる仕組みで一定のリズムに整えられます。手巻き時計はリューズを回してゼンマイを巻き上げ、使わないと止まってしまいます。自動巻き時計はローターと呼ばれる半円形の部品が腕の振動を利用してゼンマイを自動的に巻き上げる仕組みです。現代の多くの機械式時計はこの二つの方式を組み合わせた設計もあり、長時間正確に動かすには定期的な巻き直しや着用が必要です。ゼンマイの手入れとしては過度な力をかけたり磁気の近くで長時間置いておくことを避けると良いでしょう。初心者でも分かるように、ゼンマイがどうエネルギーを蓄え、どう歯車を動かして時間を刻むのかを意識すると、機械式時計の仕組みが見えてきます。
- こごみ とは ぜんまい
- 春になると山の木陰でよく見かけるこごみとぜんまい。どちらも山菜として楽しまれていますが、名前が似ていて混同されやすいです。こごみはオーストリッチファーンの若芽と呼ばれる植物の一種で、ぜんまいは別のシダの若芽です。いずれも春が旬で、山歩きの楽しみのひとつとして人気があります。こごみは葉が折りたたまれて筒のようになっており、明るい緑色で、食感はシャキシャキと歯ごたえがあります。ぜんまいは細長い茎と小さな葉が連なっている感じで、口に入れるとやわらかく噛みごたえがあります。見た目だけでは区別が難しいこともあるので、初心者は購入時に店員さんに「こごみとぜんまいを見分けたい」と伝えると教えてくれます。これらを見分けるコツは、形と色と茎の太さ。こごみは葉の皺がはっきり見えることが多く、ぜんまいは細長い茎が目立ち、葉の枚数が多い印象です。味の違いも軽く説明すると、こごみはほろ苦さと香りが強く、歯ごたえがしっかりしています。ぜんまいはややあっさりしていて、煮物や和え物、味噌汁に入れると主張しすぎず、他の具材とよく馴染みます。調理法としては、まずよく洗って根元を少し切り落とします。下茹でを1〜2分程度行い、アクを抜いてから炒め物や和え物、スープに使うと美味しく仕上がります。炒める時はバターや醤油、塩で味を整え、仕上げにごまを振ると香りが広がります。栄養的にはどちらも食物繊維やミネラルが豊富で、春の食卓を彩る優れた山菜です。一方でぜんまいには微量の有害物質が含まれることがあるとされ、過剰摂取は避け、よく加熱して食べるのが推奨されます。安全のためにも新鮮で清潔なものを選び、加熱は十分に行いましょう。春の山の香りを楽しみながら、こごみとぜんまいを組み合わせて調理にチャレンジしてみてください。
ぜんまいの同意語
- 野ぜんまい
- 野生で自生するぜんまい。山野で採られ、煮物や炒め物などの山菜料理に使われることが多い。
- 山ぜんまい
- 山野で採れるぜんまいのこと。野ぜんまいとほぼ同義で、主に山菜として流通・消費される文脈で使われる。
- 主ゼンマイ
- 時計や機械の動力源となる主要な巻きバネのこと。エネルギーを蓄え、機械を回転させる役割を担う。
- 巻きバネ
- ぜんまいの別称として使われることがある、円形に巻かれてエネルギーを蓄えるバネの総称。主に機械・時計の動力源として用いられる。
- 駆動バネ
- 機械を駆動するためのバネ。ぜんまいの一種として使われ、駆動力を生み出す部品としての意味合いが強い。
- バネ
- 一般的な金属製のばねの総称。ぜんまいはこのカテゴリに含まれることが多いが、広義の語である。
ぜんまいの対義語・反対語
- 自動式
- 人の手を介さず自動で動作する機構。ぜんまいを巻いて動かすタイプとは対照的に、電力などの力で自動的に動くことを指します。
- 手動式
- 人の手で巻いたり操作したりする方式。自動式・電動式の対義語として説明されることが多い概念です。
- 電動式
- 電力を動力源として使用する仕組み。ぜんまいなどの機械的巻き上げを使わず、スイッチ一つで動くタイプを意味します。
- ほどく
- 巻かれて張力のあるぜんまいを解く・ほどく動作。『巻く』の反対の意味合いとして使われます。
- 緩む
- 張力や緊張が解けてゆるんだ状態。ぜんまいが張っている状態の対極を表します。
- 元気
- 体力や気力がみなぎっている状態。ぜんまいが切れてしまったときの対義として使われるイメージです。
- 活力
- 心身のエネルギー・勢い。元気と同様、勢いを取り戻す状態を指す語です。
- 疲労
- 体力が消耗し、力が出ない状態。ぜんまいが切れてしまった状態の反対イメージとして使われることがあります。
- 無気力
- やる気や興味を失い、動く意欲がない状態。元気・活力の対義語的なニュアンスとして挙げられます。
ぜんまいの共起語
- ばね
- 金属でできたエネルギーを蓄える部品。ぜんまいはこのばねの一種で、巻くことで力を蓄え、機械を動かします。
- 発条
- ぜんまいの正式名称の一つ。機械の巻き上げばねを指す専門用語です。
- ゼンマイ
- ぜんまいの読み方・表記の一つ。時計や機械の巻き上げ用部品を指します。
- 時計
- 時計の中でぜんまいが巻かれ、歯車を回して時を刻む動力源となる部品です。
- 腕時計
- 腕につけるタイプの時計。機械式の場合、ぜんまいを巻いて動力を蓄えます。
- 懐中時計
- 携帯用の古典的な時計。ぜんまいを巻くことで動作します。
- 柱時計
- 置き時計の代表格。内部にぜんまいが組み込まれ、長時間動作します。
- 自動巻き
- 自動で巻き上げる機構を指します。ローターが動くとぜんまいを巻き上げます。
- 手巻き
- 自分の手でぜんまいを巻くタイプの機械式時計です。
- 巻く
- ぜんまいを巻く動作のこと。動力を蓄える第一歩です。
- 巻き上げ
- ぜんまいを巻くことでエネルギーを蓄える工程のこと。
- 巻き上げ機構
- ぜんまいを巻く仕組みの総称。自動巻きではローターがこれを動かします。
- 歯車
- ぜんまいの力を他の部品へ伝える、機械式の基本部品です。
- ムーブメント
- 時計の内部機械(ムーブメント)全体を指す言葉。ぜんまいはその動力源の一つです。
- 機械式
- 機械の力で動く仕組みを指し、クォーツ式に対して使われます。
- 機械仕掛け
- 機械で作動する仕組み全般のこと。ぜんまいを動力とする装置が多いです。
- 駆動
- 動力を伝えて動作を起こす仕組み。ぜんまいのエネルギーが駆動力になります。
- 動力源
- ぜんまいがエネルギーを蓄え、時計などの動力として使われている源です。
- コイル
- ぜんまいはコイル状のばねで、ねじれや収縮で力を蓄えます。
- 鋼
- ぜんまいは主に鋼製で作られることが多く、耐久性が求められます。
ぜんまいの関連用語
- ぜんまい
- 機械式装置の動力源となる巻き上げばね。時計・オルゴール・機械式玩具などで、エネルギーを蓄えて後の動力として放出します。
- ばね
- 弾性の力を利用して力を蓄えたり反発したりする部品の総称。用途は自動車、家具、家電、時計など多岐にわたります。
- コイルばね
- 円環状のコイルで作られたばね。圧縮・引張・ねじりのタイプがあり、さまざまな機械の力を支える部品です。
- 圧縮ばね
- 圧縮して力を蓄え、元の長さに戻ろうとするばね。荷重を受け止める用途に使われます。
- 引張ばね
- 引っ張ると力を蓄えるばね。部品を近づけたり固定したりする用途に使われます。
- ねじりばね
- ねじって力を蓄えるばね。回転部位のトルク調整や動作の復元力に用いられます。
- 螺旋ばね
- ぜんまいのように螺旋状に巻かれたばね。機械の主動力として使われます。
- ヘアスプリング
- 時計の振動系を制御する細い螺旋ばね。テンプと呼ばれる部品とともに一定周期で振動します。
- 脱進機
- 機械式時計で、ぜんまいのエネルギーを一定の間隔で歯車に解放する機構。安定した時刻表示を支えます。
- テンプ
- 脱進機と連携して一定の周期で振動する部品。時計の心臓部で、時間の精度を左右します。
- ローター
- 自動巻き機構の回転錘。腕の動きに合わせてぜんまいを巻く役割を果たします。
- 自動巻き
- 腕の動きでぜんまいを自動的に巻く機構。日常的にゼンマイを巻く手間を減らします。
- 手巻き
- 手動でぜんまいを巻く方式の機構。長時間使わない場合には手で巻いて動力を回復します。
- 駆動系/歯車列
- ぜんまいのエネルギーを歯車群に伝える機構。時刻表示と指針の動きをつくります。
- 材質(高炭素鋼・合金鋼など)
- ぜんまい・ばねの材質には高炭素鋼や合金鋼、ニッケル系合金などが使われ、強度と耐久性を高めます。
- 時計用潤滑油
- ぜんまいや歯車の摩擦を減らす潤滑剤。長寿命と安定した動作を保つ上で重要です。
- オルゴール用ぜんまい
- オルゴールの演奏を可能にする巻き上げばね。音楽を再生する原動力として使われます。



















