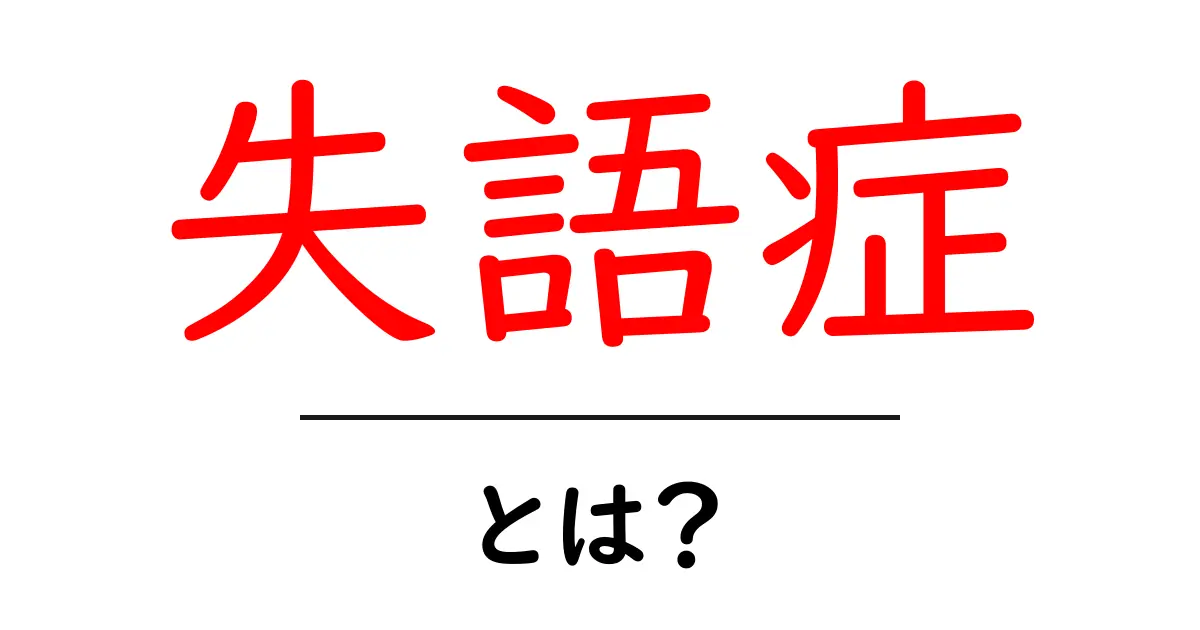

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
失語症とは?
失語症は、脳の言語機能が傷つくことで、話すことや聞くこと、読むこと、書くことのいずれか、または複数の能力がうまく使えなくなる状態です。多くの場合、脳の一部が損傷を受けることが原因です。
主な原因と発生部位
もっとも多い原因は脳卒中です。脳の言語をつかさどる部位が影響を受けると、言葉を作る力や理解する力が低下します。代表的な場所としてはブローカ野(前頭葉の一部)とウェルニッケ野(側頭葉の一部)が挙げられます。
他にも頭部外傷や腫瘍、認知症などが原因になることがあります。損傷の場所と広がりによって、出る症状のタイプが変わります。
どんな症状が出るの?
話す言葉が出にくくなる「話す能力の低下」。意味はわかるのに言葉が出てこない状態、相手の話を正しく理解できないこと、読むことや書くことが難しくなるなど、複数のパターンがあります。症状は人によってさまざまで、日によっても変わることがあります。
診断と治療の基本
診断は、言語聴覚士という専門家が行います。検査では話す、聞く、読む、書くの四つの能力を詳しく調べ、脳画像検査(MRIやCT)で原因の場所を調べます。
治療の中心は「言語療法」です。専門の言語聴覚士による訓練と家庭での練習を組み合わせ、言葉を出しやすくしたり、相手の言葉を理解する力を取り戻す手助けをします。治療は早く始めるほど効果が期待できます。
日常生活でのサポート
話すときはゆっくり、短い文で伝えると相手が理解しやすくなります。視覚的な情報(写真・絵・文字)を使うと伝えやすくなります。家族や友だちの協力が大切で、あきらめずに継続することが回復のカギになります。
簡単な表でまとめると
回復の見通しと注意点
回復の程度は人それぞれです。年齢・原因・損傷の範囲・訓練への参加度が影響します。急いで結論を出さず、長い目で取り組むことが大切です。家族のサポートや専門家の助言を受けながら、日常生活の中でできる練習を少しずつ取り入れていきましょう。
よくある質問と誤解
失語症は「性格が変わった」「頭が悪くなった」という意味ではありません。脳の機能の一部が傷ついた結果であり、適切な訓練と支援で改善が期待できます。
失語症の同意語
- 失語
- 脳の損傷や疾患により、話す・理解する・読む・書くといった言語機能が障害される状態。『失語症』の略称として日常的にも使われることが多い表現です。
- 言語障害
- 言語機能そのものに何らかの障害がある状態を指す総称。失語症はこの大分類の一部で、主に脳の障害によって生じる言語の障害を指すことが多い用語です。
- 語失語
- 語彙の選択・言語の表現・理解といった言語機能が障害される状態を指す表現の一つ。文献や医療現場で『語失語』と呼ばれることがあり、失語症とほぼ同義に使われることがあります。
- 脳性言語障害
- 脳の損傷・機能異常によって生じる言語機能の障害を指す表現。失語症はこの分類の一部として扱われることがあります。
失語症の対義語・反対語
- 言語機能正常
- 意味: 言語の理解や運用などの機能が正常で、失語症の特徴が見られない状態。
- 言語能力正常
- 意味: 語彙・文法・理解・表現など、言語全般の能力が通常の範囲にある状態。
- 言語障害なし
- 意味: 言語に関連する障害が認められない状態。
- 健常な言語機能
- 意味: 言語機能が健全で、日常の会話や理解に問題がない状態。
- 会話能力正常
- 意味: 会話をスムーズに成立させる能力が正常な状態。
- 発話能力正常
- 意味: 発話を構成し声に出して伝える能力が通常通りある状態。
- 発語が可能
- 意味: 発語能力があること、言葉を声にして伝えられる状態。
- 話すことができる状態
- 意味: 人と会話を成立させるための話す能力が備わっている状態。
- 理解・表現が正常
- 意味: 聞解・意味理解・語の選択・表現の機能が正常な状態。
- 言語機能が健全
- 意味: 言語の理解、発話、運用など全般が健全で問題が見られない状態。
失語症の共起語
- アファシア
- 失語症の英語名。脳の損傷により話す・理解する・読む・書くなど言語機能のうちいずれかが著しく障害される状態を指します。
- 言語障害
- 言語の理解・表現・語彙・発音など、言語全般の機能に障害が生じる状態の総称。
- 言語療法
- 失語症の回復・改善を目的とした訓練や治療の総称。
- 言語聴覚士
- 言語療法を担当する専門職。失語症のリハビリを実施します。
- ブローカ野
- 発話をつくる脳の領域で、損傷すると非流暢性の失語が起きやすいとされます。
- ウェルニッケ野
- 言葉の意味を理解する領域で、損傷すると意味の通じにくい失語が生じることがあります。
- 前頭葉
- 脳の前方の部位で、思考・計画・発話などに関与します。
- 側頭葉
- 聴覚処理と意味理解を担う脳の部位です。
- 脳卒中
- 脳の血管が詰まる・破れる病気で、失語症の主な原因のひとつです。
- 脳梗塞
- 脳の血管が詰まり、脳組織が壊死する状態。
- 脳出血
- 脳内の血管が破れて出血する状態。
- 脳血管障害
- 脳への血流が障害される病態の総称です。
- 語彙障害
- 語彙の選択・使用に障害が生じる状態。
- 名詞呼称困難
- 物の名前を思い出して呼ぶのが難しくなる現象。
- 語音障害
- 話す際の音声の生成・出力に関する障害。
- 構音障害
- 正しく音を出して発話する機能の障害。
- 読解障害
- 文章の意味を理解する力が低下する状態。
- 書字障害
- 文字を書く能力が低下する状態。
- 語義理解障害
- 言葉の意味を正しく理解する力の障害。
- 認知機能障害
- 記憶・注意・実行機能など、認知機能全般に影響が生じる場合。
- 画像診断
- 脳の状態を画像で評価する検査領域。
- MRI検査
- 磁気を使って体の内部を詳しく見る画像検査。
- CT検査
- X線を用いて体の断層画像を作る検査。
- 脳画像診断
- MRI/CTなどを用いて脳の状態を診断する方法。
- アファシア検査
- 失語の程度やタイプを評価する検査。
- 西部失語評価尺度
- WAB; 失語のタイプと程度を総合的に評価する代表的な検査。
- ボストン命名テスト
- 名詞名指し・語彙の能力を評価する検査。
- トークンテスト
- 理解・表現・語形成の機能を評価する検査の一つ。
- リハビリテーション
- 機能回復を目指して行う訓練・治療の総称。
- 補助具
- 会話を補助するツールや道具(絵カード、ジェスチャー、デジタル機器など)。
- コミュニケーション支援
- 日常会話を円滑にするための工夫・ツール。
- 家族教育
- 家族が失語症を理解し、適切にサポートできるよう学ぶ教育活動。
- 早期リハビリ
- 発症直後からリハビリを開始する考え方。
- 予後
- 治療後の回復の見通しや今後の経過。
- 生活の質
- 日常生活の満足度や快適さを表す指標。
- 日常生活動作
- 日常生活で必要な基本動作の訓練。
- 代替コミュニケーション手段
- 絵カード・ジェスチャー・デジタル機器など、言葉以外で意思を伝える方法。
- 会話療法
- 対話を通じた言語リハビリのアプローチ。
- 絵カード
- 意味を伝えるための絵が描かれたカード。
- ピクチャーカード
- 絵を用いて意思伝達を補助するカードセット。
失語症の関連用語
- 失語症
- 脳の損傷により言語の理解・表現・運用が障害される状態の総称。主に左半球の言語中枢の損傷が原因となり、話す・理解する・読む・書くなどの言語機能が影響を受けます。
- ブローカ失語
- 話す能力が遅く・不完全になり、文法的には簡潔になるが意味は取りにくいタイプ。ブローカ野の損傷が原因。
- ウェルニッケ失語
- 話は流暢だが意味が通じず、理解が困難になるタイプ。聴覚言語理解をつかさどるウェルニッケ野の損傷が原因。
- 伝導性失語
- 聞いた言葉を正確に繰り返せず、語の選択・文の構成は保たれることが多い。伝導路の損傷による。
- 全失語
- 話す・聴く・読む・書くの全機能が重度に障害される状態。最も重いタイプの失語症です。
- 連合失語(アノミック失語)
- 語名を思い出せない、検索に時間がかかるが、理解と文の構造は比較的保たれることが多い。
- 失読症
- 文字を読んだり理解する力が著しく低下する読書障害で、失語と併発することがあります。
- 書字失語
- 文字を書く能力が障害され、単語・文の表出が難しくなる状態。
- 脳卒中
- 脳の血流が急激に障害される病気。左半球の損傷は失語の最も一般的な原因です。
- 左半球言語中枢
- 言語機能を主に担う脳の部位群。ブローカ野・ウェルニッケ野を含み、損傷で失語が生じます。
- ブローカ野
- 発語の生成を司る前頭葉の領域。損傷すると言葉の出力が難しくなります。
- ウェルニッケ野
- 言語理解を司る側頭葉の領域。損傷すると聞いた言葉の意味を取り違えやすくなります。
- AAC(代替・補助コミュニケーション)
- 言語喪失を補うための絵カード・筆談・音声支援デバイスなど、日常のコミュニケーションを補助する手段です。
- 構音障害
- 発話の運動機能の障害により、話し方が不明瞭になることがある。必ずしも言語理解の障害とは同じではありません。
失語症のおすすめ参考サイト
- 失語症 (しつごしょう)とは | 済生会
- 失語症とは?言語聴覚士が関わる失語症について - 関西福祉科学大学
- 失語症とは?言語聴覚士が関わる失語症について - 関西福祉科学大学
- 失語症とはどんな症状?原因やリハビリ、認知症との違いなどを解説



















