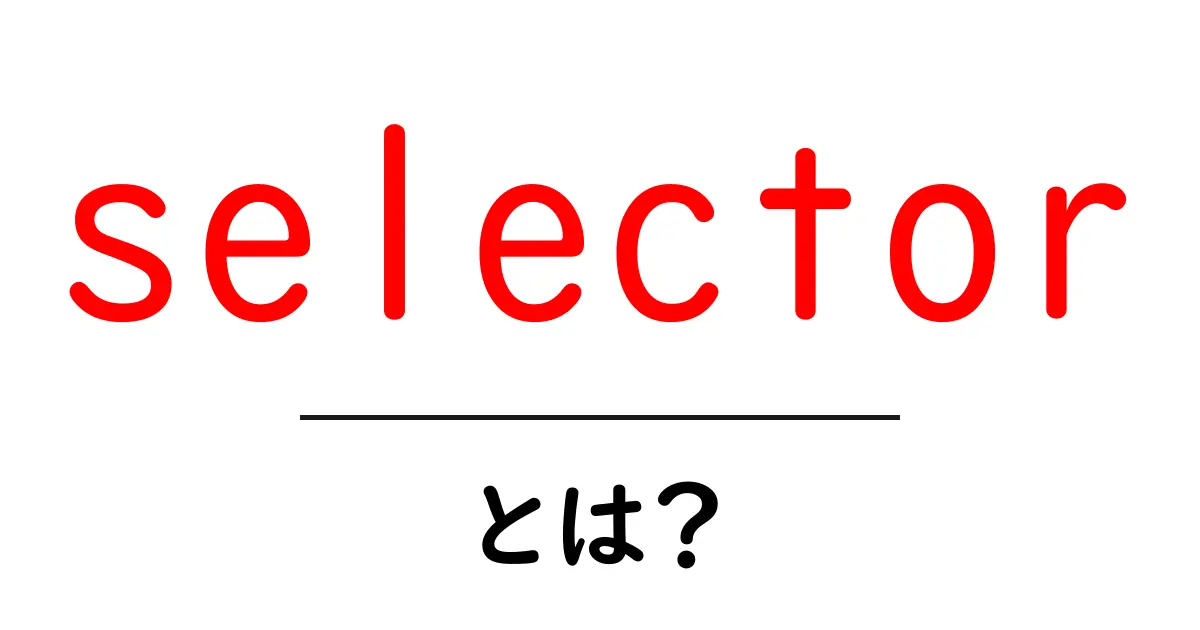

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
selectorとは?基礎のしくみ
selector は HTML の要素を絞り込む「パターン」です。ウェブ制作では CSSのスタイルを誰の要素に適用するかを決める道具として使われます。また JavaScript でも document.querySelector などで要素を見つけるときに使われます。
このページでは、初心者にも分かりやすいように selector の基本をゆっくり解説します。結論から言うと、要素を特定するためのルール集が selector です。複数のセレクタを組み合わせて、特定の条件を満たす要素だけを対象にできます。
代表的なセレクタの種類
要素セレクタはその名のとおり要素名を指定します。例: p { color: red; }
クラスセレクタはクラス名を指定します。例: .note { font-size: 14px; }
IDセレクタは id を指定します。例: #header { background: #f0f0f0; }
属性セレクタは属性と値を指定します。例: input[type=text] { border: 1px solid #ccc; }
階層セレクタは要素の階層構造を使います。例: div .item は div の中の class が item の要素を対象にします。
実践的な例と表
使い分けのコツとして、用途に応じてセレクタの階層を深くしすぎないことと、意味のあるクラス名をつけることが大切です。
以上のセレクタを組み合わせると、特定の条件を満たす要素だけを狙い撃ちできます。注意点は特異性とパフォーマンスです。セレクタが長く複雑になると、ブラウザは要素を探すのに少し時間がかかることがあります。意味のあるクラス名と適切な階層の組み合わせを心がけましょう。
特異性と使い方のコツ
特異性は、同じ要素に複数のセレクタが適用できるとき“どのスタイルが適用されるか”を決めるルールです。IDはクラスよりも強い力を持ち、複数の要素で同じIDを使うのは避けます。できるだけユニークなクラス名を使い、IDはレイアウト用ではなく単一要素の識別に使うのが基本です。
実際に使ってみよう
ブラウザのデベロッパーツールを使うと、どのセレクタがどの要素にマッチしているかを視覚的に確認できます。実験を重ねるほどセレクタの理解が深まります。
JavaScript での選択は document.querySelector で最初にマッチした要素を返します。複数を取るには querySelectorAll を使います。これらも同じセレクタの文法を使います。
まとめ
selector はウェブ開発の基本中の基本です。正しく使えばコードの可読性・保守性・パフォーマンスが向上します。初めは難しく感じても、基本のパターンを覚え、実際の例で手を動かしていくと自然と身につきます。日常的に小さな例を作って練習することが上達の近道です。
selectorの関連サジェスト解説
- search engine selector とは
- search engine selector とは、ウェブツールやコードの中で、どの検索エンジンを使って検索結果を取得するかを選ぶ機能のことです。SEOを学ぶとき、Google や Bing、Yahoo など、検索エンジンごとに順位や表示結果が違います。そこで多くのツールには検索エンジンを選ぶを表すセレクター(ドロップダウンメニューやボタン)が用意されています。たとえば、SERP分析ツールやキーワードツールで、まずどの検索エンジンを基準にするかを選択します。選択すると、そのエンジンのデータだけを表示・比較できます。エンジンごとにランキングやクリック率の指標は異なるため、同じキーワードでも結果が変わることを理解しておくとよいです。実務的な使い方の例として、1) 複数の検索エンジンで自サイトの順位を比較したいとき、2) アフィリエイトや広告の効果をエンジン別に評価したいとき、3) 新しいコンテンツの最適化をする際に、どのエンジンがどのくらいの影響を持つかを確認する、などが挙げられます。地域や端末による差もあるので、同じエンジン内でも地域(国)・デバイス(スマホ/PC)を設定して比較することが重要です。最後に、search engine selector はツールごとに表現が違うことがあるので、英語表記のまま使われていることも多く、使い方ガイドを読んで正しく設定しましょう。
- selector ai とは
- selector ai とは、AI(人工知能)の一種で、複数の選択肢の中から条件に合うものを自動で絞り込んで取り出してくれる機能の総称です。大量のデータや候補がある場面で人が判断するより速く、同じ条件で何度も判断してくれるのが長所です。使い方はシンプルで、目的を決め、どんな結果を欲しいか基準を作り、データをAIに渡すだけ。結果を人が確認して必要に応じて微調整します。たとえばオンラインショップでは、あなたの好みや予算に合う商品をAIが絞り込んで表示します。ニュースサイトでは、あなたが読みたいと思う記事を優先して並べます。SEOの世界では、検索エンジンの意図を満たすキーワードや見出しの案をAIに選ばせ、記事の構成を決める手助けにもなります。仕組みは基本的にデータとルール、そして学びの三つ。AIはまず基準を受け取り、次に大量のデータを読み込み、最後に候補を並べ替えます。機械学習を使えば、過去の結果から“この条件だと良い成果が出やすい”という傾向を学習します。これが selector ai の強みです。使うときのコツは、目的をはっきりさせること、データを整えること、そして基準を具体的に設定することです。出力を鵜呑みにせず、必ず人の目で確認しましょう。偏り(特定の条件だけを重視するような癖)を避けるため、複数の基準を用意するのもおすすめです。実務での注意点として、データの品質とプライバシー、偏りの回避、結果の検証が大切です。
- app selector とは
- app selector とは、アプリの中で“どの機能や画面を使うかを決める仕組み”のことを指します。日常で言えば、複数の選択肢がある中から、今使うべき一つを選ぶ作業そのものです。プログラミングやアプリ設計では、ユーザーの操作や状態に応じて表示する画面や動作を切り替えるためにこの“セレクター”が使われます。例えば、天気アプリを例に取ると、天気データが取得できたときと取得できなかったときで見せる画面を変えるのは“selector”の役目です。データがあるときには最新の天気情報を表示し、データがないときにはエラーメッセージや再試行ボタンを出す、まさに条件を分けて一つを選ぶ仕組みです。使いどころにはいくつかの代表的な場面があります。1つはUIの状態管理で、ボタンの押下や通信の成否などの「状態」に応じて表示を切り替えるケース。2つ目は画面遷移の決定で、どの画面を見せるかを決める判断材料になるケース。3つ目はリソースの選択で、設定や端末の状態に合わせてアイコンや背景を変えるケースです。これらはすべて、条件に対して“今これを表示する”と一択を選ぶための考え方です。使い方のコツは、まず小さな例から始めることです。ボタンを押すと背景色が変わる程度の簡単なケースから練習しましょう。次に条件を増やすときは、 if-else などの分岐を整理し、共通部分をまとめる工夫をします。フレームワークを使うときは公式のドキュメントで“selector”という用語の意味と使い方を確認すると理解が深まります。最後に、複雑さを避けてシンプルに保つことが長く使える設計のコツです。
- app selector とは何
- app selector とは何かを、初心者にも分かる言葉で解説します。まず、app selector は“アプリを選ぶ仕組み”のことを指します。あなたがスマホで何かの作業をするとき、同じ種類の処理を実行できる複数のアプリが候補として現れることがあります。例えば写真を共有するとき、どのアプリで共有するかを選ぶ画面(アプリセレクター)が表示されます。これが app selector の代表的な例です。この仕組みのポイントは三つです。1つ目は、あるアクションに対して複数のハンドラ(処理を担当するアプリ)があるときに、システムがその選択画面を表示すること。2つ目は、ユーザーが好きなアプリを選ぶと、そのアプリへ処理が渡されること。3つ目は、選択後は元のシーンへ戻るか、あるいは結果が返ってくることです。実際のプラットフォームの例としては、Android ではACTION_PICKやACTION_VIEWのようなアクションを呼ぶと、どう扱うかを決めるアプリセレクターのダイアログが出ます。状況によっては「このアクションをこのアプリで常に開く」などのデフォルト設定を促す画面も現れます。iOS では写真やリンクを他のアプリで開くときに、共有シートや Open In などの形で同様の選択肢が表示されます。二つのプラットフォームはいずれも、ユーザーが選択する自由を尊重しつつ、作業をスムーズに進められるよう設計されています。開発者として意識するポイントは、アプリが受け付ける処理の種類を正しく伝えること、選択肢が多すぎて混乱しないようUIをシンプルに保つこと、そして必要に応じてデフォルトを設定するオプションを提供することです。一般ユーザーにとっては、アプリセレクターそのものは普段は気にすることの少ない機能ですが、複数のアプリを使い分ける場面ではとても重要な役割を果たします。このように app selector は、私たちが日常的に使うスマホやPCの体験を支える“選ぶ仕組み”のひとつです。理解しておくと、どのアプリを選ぶべきか判断する基準が持て、より快適にデジタル機能を活用できるようになります。
- css selector とは
- css selector とは、ウェブページのHTML要素を選ぶための「パターン」を言います。CSSはこのパターンに従って、どの要素にスタイルを適用するかを指示します。たとえば、pタグの文字色を赤にしたいときは、p { color: red; } のように書きます。ここでの「p」はセレクタで、実際にはHTMLの要素を指しています。セレクタにはいろいろな種類があります。要素セレクタはタグ名だけで選びます。クラスセレクタは、class属性が特定の値の要素を選びます。書き方は .highlight のように先頭にドットをつけます。IDセレクタは #main のように先頭にハッシュをつけ、IDがこの値の要素を選びます。階層を使うセレクタも覚えましょう。 子孫セレクタはスペースで区切って、親の中の子孫を選びます。例: article p は article の中の p 要素全てを選びます。 子セレクタは > を使います。例: ul > li は ul の直下の li 要素だけを選びます。 隣接兄弟セレクタは +、一般的な兄弟セレクタは ~ です。例えば h1 + p は直後の p を、 h1 ~ p は同じ親を持つすべての p を選びます。属性セレクタには、属性名と値で絞り込みます。例として、リンクの href が https で始まる場合を選ぶには、条件の組み合わせを使います。疑似クラスと疑似要素は、要素の状態や特定の部分を選ぶ仕組みです。たとえば :hover はマウスを乗せたとき、:nth-child(2) は親の中の2番目の子要素、::before は要素の前に挿入した内容を選べます。実務的なポイントとしては、基本の要素・クラス・IDを使い分ける練習から始め、階層セレクタや属性セレクタを必要に応じて追加していくと良いでしょう。また、ブラウザの開発者ツールで選択対象を確認しながら、特異性のルールを理解すると効率的にスタイルを作れます。
- dkim selector とは
- DKIMとは、メールにデジタル署名をつけて、受信側がそのメールが本当に送信者のドメインから来たかを検証できる仕組みです。署名は送信側の秘密鍵で作られ、受信側は公開鍵をDNSの公開鍵レコードから取得して署名を検証します。検証が成功すれば、途中で改ざんされていないことと送信者のドメインの正当性が確認できます。dkim selector とは、DKIM署名の中に含まれる“selector(セレクタ)”という識別子のことです。署名にはs=selectorという情報があり、公開鍵を探すときの手掛かりになります。公開鍵は、DNSに「selector._domainkey.ドメイン」というTXTレコードとして格納します。例えば、ドメイン example.com に対してセレクタを「mail」と決めた場合、公開鍵は mail._domainkey.example.com という名前のTXTレコードに保存され、値は v=DKIM1; k=rsa; p=…(公鍵) の形になります。送信側ではこのセレクタを決め、メール本体やヘッダの一部をハッシュ化して秘密鍵で署名します。受信側はそのセレクタを用いて DNS から公開鍵を取得し、署名を照合します。複数の送信部門やサブドメインがある場合には、異なるセレクタを使い分けると鍵の管理が楽になり、トラブルが起きにくくなります。設定のポイントは、DNSの伝播時間に注意すること、秘密鍵の管理を厳格に行うこと、署名対象を範囲指定することです。DKIMを正しく設定すると、正当なメールの信頼性が高まり、受信者の迷惑メール判定を避けやすくなります。
- credential helper selector とは
- credential helper selector とは、Git が認証情報をどう使うかを決める仕組みのことです。Git には credential.helper という機能があり、パスワードやトークンを保存したり、再利用したりするヘルパーが複数用意されています。たとえば、長期保存に向く store、一定時間だけ記憶してくれる cache、OS の鍵束と連携する manager-core などが代表的です。ところで、同じ環境内でも複数のサービスを使う場合、どのヘルパーを使うべきか迷います。ここで登場するのが「selector」(選択器)です。selector は、ホスト名や URL、プロトコルなどの条件を基に、どの認証ヘルパーを呼び出すかを判断します。つまり、credential helper selector は「どのヘルパーを使うかを自動的に決めてくれる仕組み」と言えます。実務では、セレクターを自作して使うことも多いです。具体的には、まず使いたい条件を決めます。例: github.com には manager-core、社内サーバーには store、テスト環境には cache を使う、など。次に、条件に応じて適切なヘルパーを呼ぶ小さなスクリプトを作成します。最後に git config --global credential.helper '/path/to/selector.sh' のように設定します。この設定を入れると、Git はそのスクリプトを通じてヘルパーを決定し、認証情報を取得・保存します。初心者はまず安全な環境から試し、1サービスずつ動作を確認するとよいでしょう。
- dolby profile selector とは
- dolby profile selector とは、音声の処理設定を切り替える仕組みのことです。Dolby が提供するいくつかの音声処理の「プロファイル」を、利用環境や聴き方に合わせて選べる機能を指します。プロファイルとは、音の強弱や音場感、低音の量、ダイナミックレンジの広さなどを事前に決めた設定のことです。たとえば映画を見るときは大迫力の音場を再現する「Movie」プロファイル、音楽を聴くときには細かな高音もきれいに聴かせる「Music」プロファイル、セリフを明瞭にする「Voice」プロファイルなどがあり、それぞれ聴き心地が変わります。dolby profile selector はこれらのプロファイルを選択する窓口のようなもので、スマホやPC、ホームシアター用のアプリや設定画面に現れることが多いです。使い方は機器やアプリによって異なりますが、基本は Settings や Dolby のアプリを開き、Profile Selector などの項目を探して、聴く用途に合ったプロファイルを選ぶだけです。選んだ後は音楽を再生して聴き比べ、好みの音色を見つけると良いでしょう。もし表示が見つからなかったり、プロフィールが選べない場合は、デバイスの Dolby アプリを最新に更新するか、機器の取扱説明書を確認してください。なお、実際の名称や画面の位置は機器ごとに異なる場合があります。
- traffic selector とは
- traffic selector とは、VPN(仮想私設網)の設定で使われる用語です。具体的には、暗号化して保護する「トラフィックの範囲」を決める条件のことを指します。例えば自宅と会社を結ぶVPNを設定するとします。会社のネットワークは192.168.0.0/24、自宅のネットワークは10.0.0.0/24だとします。この時、どの通信を暗号化して送るかを決めるのが traffic selector です。IPsec では、セキュリティポリシーと Security Association (SA) があり、TS はこのポリシーの一部として、送信元/宛先の IP アドレス、必要に応じてポート番号やプロトコルなどを組み合わせて、マッチするトラフィックを特定します。TS は通常、地元側と相手側の二つのTSで構成され、両方が一致したときだけ、そのトラフィックが暗号化されて送信されます。なお、トラフィックを許可する条件を決める ACL とは別物です。ACL は通過可否を決めますが、TS は「暗号化するべきトラフィック」を決める役割です。実際には SPD(Security Policy Database)で組み合わせて使われることが多いです。設定の手順は機器ごとに違いますが、概略は以下のとおりです。まず自分のネットワーク範囲を決め、次に暗号化したい相手先のネットワークを決め、最後に送信元/宛先の組み合わせをTSとして設定します。トラブルを避けるため、最初は小さな範囲から試すのがコツです。
selectorの同意語
- セレクタ
- HTML要素を絞り込むための書式・式。CSSやJavaScriptで、どの要素を対象に操作するかを決める条件の集合です。
- セレクター
- セレクタの別表記。意味はセレクタとほぼ同じで、文脈に応じて使い分けます。
- CSSセレクタ
- CSSで要素を指定するためのパターン。クラス指定はクラス名、ID指定はID、階層関係は親子や兄弟関係で表します。
- クエリセレクタ
- JavaScriptの API で要素を探す際に使う表現。CSS風のセレクタを書いて要素を取得します。
- 選択子
- 日本語の古い用語で、CSS の要素選択を指す言い方です。現在はセレクタが主流です。
- 選択条件
- 要素を選ぶ基準となる条件のこと。クラス名やID、属性、階層関係などを組み合わせて決めます。
- 要素選択式
- 要素を選ぶための式・表現。セレクタと同義として使われることもあります。
- 絞り込みパターン
- 要素を絞り込むためのパターン。複数の条件を組み合わせて対象を絞り込みます。
- 絞り込み条件
- 要素を狭く絞る基準となる条件。クラスや属性などの条件を指します。
- 要素選択規則
- 要素をどう選ぶかのルール。階層関係や属性、クラスなどの組み合わせで決まります。
- セレクタ表現
- セレクタの書き方・表現のこと。文法に沿って正しく記述するのがコツです。
- 選択表現
- 要素を選ぶ方法を表す言い方。セレクタと大枠として同義に使われます。
- セレクト文法
- セレクタの正しい書き方・構文のこと。スペースや子関係、子孫関係の記号を使います。
selectorの対義語・反対語
- 排除者
- 選択の反対の役割を担うもの。候補を除外・排除する人や物のこと。
- 拒否者
- 提案や候補を拒む人・組織。選択を拒む立場を指す。
- 非選択
- 選択を意図的に行わない状態。候補を選ばず、決定を保留する意味合い。
- 未選択
- まだ選ばれていない状態。決定が保留中の状況を指す。
- 除外
- 候補の中から対象を取り除く行為。選択の対極として、検討対象から外すこと。
- 排除
- 除外とほぼ同義。対象を意図的に外す処理や結果を表す。
- 反選択
- 選択の逆の動作。候補を選ばない、あるいは選択を取り下げること。
- 不採択
- 採択されないこと。選択の対象から外す状態・事象。
- 未決定
- 決定がまだ下されていない状態。候補が未確定のままの状況。
- 非マッチ
- 基準・条件に一致しない状態。選択の対象から外れる要因になる。
- 非適合
- 条件・要件に適合しない状態。選択の観点で外れることを示す。
selectorの共起語
- CSSセレクタ
- HTML/CSSで要素を絞り込むための構文の総称。複数条件を組み合わせて要素を指定する。
- セレクタ
- 対象を選ぶ表現・記法。CSSセレクタ以外にもXPathや自動化ツールのセレクタなどを含む広い概念。
- 要素セレクタ
- タグ名で要素を指定するセレクタ。例: div, p。
- クラスセレクタ
- class属性の値で絞り込むセレクタ。例: .menu
- IDセレクタ
- id属性の値で一意の要素を指定するセレクタ。例: #header
- 属性セレクタ
- 属性と値で絞り込むセレクタ。例: [type='text'], [data-id]
- 擬似クラス
- 要素の状態を表す特定の条件を指定するセレクタ。例: :hover, :focus, :nth-child(2)
- 擬似要素
- 要素の特定の部分を選ぶセレクタ。例: ::before, ::after
- 子孫セレクタ
- 親から下位のすべての要素を辿って絞り込むセレクタ。例: div p
- 直下の子セレクタ
- 直接の子要素だけを選ぶセレクタ。例: ul > li
- 隣接兄弟セレクタ
- 直前の兄弟要素と同じ親を持つ次の要素を選ぶセレクタ。例: h1 + p
- 一般兄弟セレクタ
- 同じ親を持つすべての兄弟要素を選ぶセレクタ。例: h1 ~ p
- グループセレクタ
- 複数のセレクタをカンマで区切って同時に適用する。例: div, span
- ユニバーサルセレクタ
- 文書内の全要素を対象にするセレクタ。例: *
- セレクタ構文
- セレクタの書き方全般。複数条件の組み合わせ方も含む。
- セレクタの特異性
- セレクタの優先度を示す数値。ID > クラス/属性 > 要素の順で決まる。
- セレクタエンジン
- ブラウザがセレクタを解釈して要素を検索する内部機構。
- CSS3セレクタ
- CSS3で追加された新しいセレクタ群。
- セレクタ文字列
- セレクタを表す文字列。例: '.class > #id'
- DOM
- 文書オブジェクトモデル。HTMLの構造をプログラムで操作する根本データ構造。
- HTML
- ウェブページのマークアップ言語。セレクタはHTML要素を対象にする。
- CSS
- スタイルシート言語。セレクタはCSSの要素を指定する機能。
- querySelector
- 文書内の最初のマッチ要素を返すDOM API。セレクタ文字列を使う。
- querySelectorAll
- 文書内のすべてのマッチ要素をNodeListとして取得するDOM API。
- XPathセレクタ
- XML/HTMLでノードを指す階層的表現。自動化ツールで使われることがある。
- Seleniumセレクタ
- Seleniumで要素を特定する表現。CSSセレクタやXPathが使われる。
selectorの関連用語
- セレクタ
- HTML要素を“選ぶ”ための指示子の総称。どの要素に対してスタイルを適用するか、あるいは要素を取得するかを決めます。
- CSSセレクタ
- CSSで使う具体的なセレクタの書き方。要素名、クラス名、ID名、属性、疑似クラスなどを組み合わせて対象を絞ります。例: div, .class, #id, a[href^='https'] など。
- 型セレクタ
- 要素名だけで選ぶ基本的なセレクタ。例: div はすべての div 要素を対象にします。
- ユニバーサルセレクタ
- 全ての要素を対象にするセレクタ。書き方は * 。
- クラスセレクタ
- 特定のクラス名を持つ要素を選びます。例: .btn は class='btn' の要素を対象。
- IDセレクタ
- 特定のID名を持つ要素を厳密に選ぶ。例: #header
- 属性セレクタ
- 属性の値や条件で絞る。例: a[href^='https'], [data-value='1']
- 子孫セレクタ
- 親子関係をまたいで任意の深さの子要素を選ぶ。例: div p は div の中のすべての p。
- 子要素セレクタ
- 直系の子のみを対象。例: ul > li は ul の直接の li。
- 隣接兄弟セレクタ
- 同じ親の直後に現れる兄弟要素を選ぶ。例: h1 + p
- 一般兄弟セレクタ
- 同じ親の後ろの兄弟要素をすべて選ぶ。例: h1 ~ p
- 疑似クラス
- 要素の状態に応じて選ぶ。例: a:hover, input:focus, :nth-child(2)
- 疑似要素
- 要素の特定の部分を対象にする。例: p::before は p の前に内容を挿入
- 複合セレクタ
- 複数のセレクタを組み合わせて絞り込む。例: div.btn.primary は div 要素のうち class が btn かつ primary のもの
- 特異性
- セレクタが持つ優先順位の指標。一般的には ID > クラス/属性/型 > ユニバーサル。数値として計算されます。
- セレクタの最適化・パフォーマンス
- 大量の要素を高速に絞り込むには、シンプルなセレクタを優先し、過度に複雑な連結を避けるのがコツです。
- CSSセレクタAPI
- JavaScript で CSS セレクタを使って要素を取得する API。代表例は document.querySelector と document.querySelectorAll。
- XPathセレクタ
- XML/HTML を XPath 式で選ぶ別の手法。例: //div[@class='content']
selectorのおすすめ参考サイト
- selectorとは・意味・使い方・読み方・例文 - 英ナビ!辞書 英和辞典
- セレクタとは?意味をわかりやすく解説 - trends - コードキャンプ
- セレクタとは?意味をわかりやすく解説 - trends - コードキャンプ
- selectorとは・意味・使い方・読み方・例文 - 英ナビ!辞書 英和辞典
- セレクターとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書



















