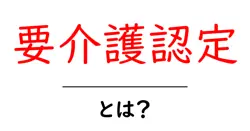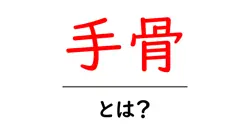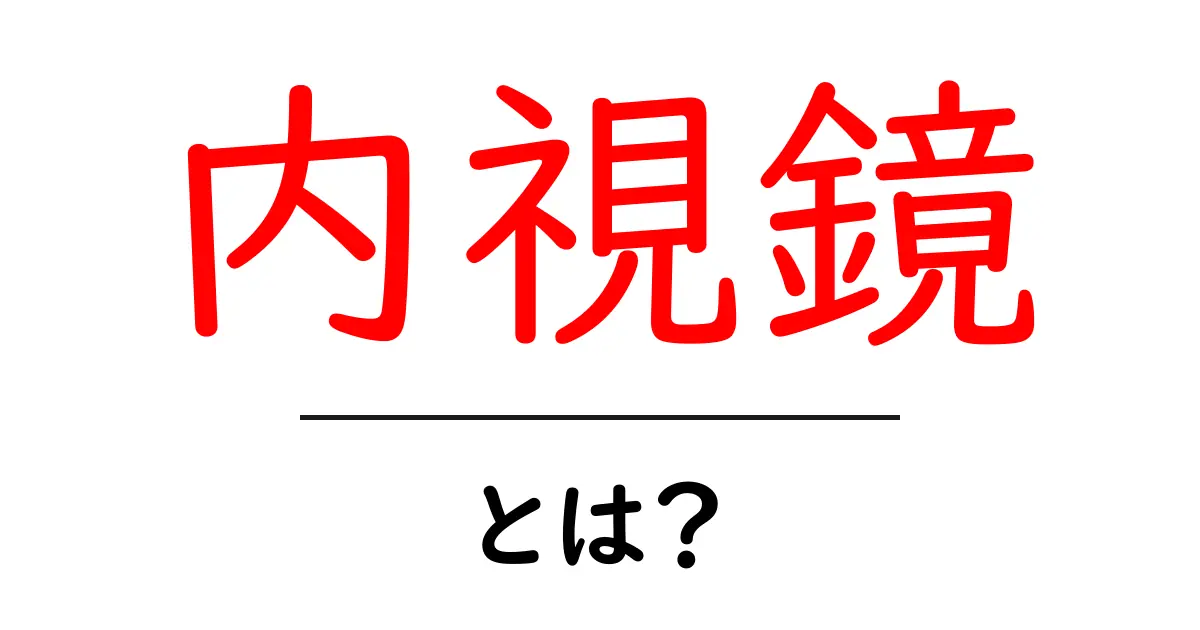

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
内視鏡とは?初心者向けガイド
内視鏡とは、体の内部を観察するための細長い管状の器具です。先端には小さなカメラと光源があり、医師がモニターを見ながら内部を映し出します。痛みを抑える工夫も多く、検査は安全に行われます。
この道具は、体の内部を直接見るだけでなく、必要に応じて組織の一部をとる「生検」も行えるなど、多くの診断に役立ちます。
内視鏡の仕組みと使われ方
内視鏡は本体の柄と、体の内部へと進む細長い挿入部から成り立っています。先端のカメラが映す映像は、医師の手元にあるモニターへ送られ、挿入角度を変えたりカメラを回転させたりして、体の内部を細かく観察します。挿入部は柔らかく、体の中を傷つけにくい設計になっています。
代表的な内視鏡には、胃や腸の内部を観察する胃内視鏡(胃カメラ)、大腸の観察を行う大腸内視鏡、鼻や喉、気道を観察する鼻腔・気道内視鏡、さらに関節腔や胸腔をのぞく特殊なタイプがあります。
検査の目的と検査の種類
日常的に受けることの多い検査は、胃内視鏡と大腸内視鏡です。これらは粘膜の異常を診断するほか、必要に応じて組織をごく小さく採取する「生検」も可能です。生検によって病変の詳しい情報を得られ、早期発見につながることがあります。
鼻腔や喉の痛みの原因を探す検査、呼吸器の状態を確かめる検査、膝や関節の内部を観察する関節鏡など、目的に応じてさまざまなタイプの内視鏡が使われます。
検査の流れと準備
検査は、事前の説明と同意から始まります。検査の目的に応じて、麻酔の有無や鎮痛剤の使用が決まり、前日からの絶食指示が出ることが多いです。検査当日には検査着に着替え、体を安定させて検査を受けます。
挿入されるチューブはとても柔らかく、医師は痛みを感じにくいようにゆっくりと進めます。検査中に不快感が強ければ、遠慮なく伝えましょう。麻酔を使用する場合は、検査後しばらく眠気が残ることがあります。
検査後の過ごし方と注意点
検査後は、麻酔の影響が完全になくなるまで安静に過ごすことが推奨されます。飲酒や重い食事は、医師の指示が出るまで控えるほうが安全です。結果はすぐに説明される場合と、画像や組織検査の結果を待って説明される場合があります。
まれに出血や感染、麻酔に対する反応などのリスクはあります。心配な点がある場合は、検査前に医師へ質問して理解を深めましょう。
内視鏡の安全性とよくある誤解
現在の内視鏡検査は、安全性が高く痛みも軽減されています。昔のイメージとして「痛そう」「怖い」と思われることがありますが、医師は患者さんの不安を和らげる工夫を日々進めています。検査前には、麻酔の有無や痛み止めの使用について、しっかりと説明を受けましょう。
準備とケアの実践チェックリスト
用語解説と基礎知識の glossary
- 内視鏡とは、体の内部を観察するための細長い管状の器具。先端にカメラと光源がある。
- 生検とは、病変の組織を少し採取して検査すること。
- 鎮静剤とは、検査中の不安や痛みを和らげる薬のこと。
まとめ
内視鏡は体の内部を安全に見るための強力な道具です。 現代の技術は痛みを最小限に抑え、検査時間も短くなるよう改良が重ねられています。検査を受ける際は、事前説明をしっかり読み、疑問点を医師に尋ねることが大切です。定期的な検査は病気の早期発見につながり、健康を守る第一歩となります。
よくある質問と注意点
Q. 内視鏡は痛いですか? A. 痛みを感じにくいように工夫されており、麻酔や鎮痛剤が使われる場合もあります。個人差はありますが、医師と相談して最適な方法を選びましょう。
Q. 検査後にすぐ動けますか? A. 多くは問題なく動けますが、麻酔の影響が残る場合は少し安静にすることがあります。医師の指示に従ってください。
内視鏡の関連サジェスト解説
- 内視鏡 手術 とは
- 内視鏡 手術 とは、体の中を直接見ることができる細長い管(内視鏡)を使って、傷を小さく抑えながら病気を治す医療の方法です。内視鏡の先端にはカメラと照明がついており、看護師と一緒にモニターの映像を見ながら、医師が器具を操作して治療します。大きな開腹手術と比べて体への負担が少なく、術後の回復が早いことが多いのが大きなメリットです。内視鏡は口から入れるタイプと、尿道や鼻など体の自然な開口部を通して入れるタイプがあります。胃や腸の中を観察したり、病変を取ったり、細い管で狭くなっている場所を広げたりすることができます。最近は胃や大腸の検査・治療だけでなく、鼻や喉、泌尿器の治療にも使われるようになってきました。)内視鏡手術の代表的な利点は、傷口が小さく済むこと、出血や痛みが少ないこと、回復が早いことです。一方で、全ての病気に適しているわけではなく、リスクもゼロではありません。手術前にはしっかりと検査を行い、体の状態や病気の性質を判断します。麻酔の安全性や感染リスク、合併症の可能性も医師が説明します。患者さんが安心して受けられるよう、術前の準備として絶食や薬の服用制限、体調管理、当日の麻酔計画などが詳しく説明されます。術後はすぐに歩くことが推奨される場合もあり、消化の良い食事や安静を指示されることが多いです。普段と違う体の不調があればすぐに医療機関に連絡することが大切です。内視鏡手術は、病気を早期に治療する選択肢として重要な役割を果たしています。専門の医師と病院で、自分の病気にどの程度適しているかを丁寧に相談して決めることが大切です。
- 内視鏡 emr とは
- 内視鏡 emr とは Endoscopic Mucosal Resection の略で、胃や大腸などの粘膜にできた早期のがんや良性のポリープを、手術をせずに内視鏡だけで取り除く治療法です。日本語では内視鏡的粘膜切除術と呼ばれることが多く、EMR の頭文字をそのまま日本語表現にしたものです。内視鏡は、口や肛門から体の中をのぞいたり病変を治療したりできる細くて柔らかい管です。EMR はこの管の先についた小さな器具(スネア)を使って病変の表面だけを切除する方法です。治療の流れは次の通りです。まず、病変の周りを傷つけないように、病変の下の粘膜に生理食塩水などを注入して持ち上げます。これをリフティングと呼び、病変を見やすく、取りやすくします。次に、内視鏡のスネアを病変の部分に置き、電気の力で軽く焼きながら病変を囲んで切り取ります。切除した組織は病理医が検査し、がんかどうか、どの深さまで病変が及んでいるかを判断します。大きい病変や複数の病変の場合には、病変を分割して取り除く分割EMRを使うこともあります。EMR は、外科的な手術に比べて体に優しく、回復も早い場合が多いです。胃や大腸の浅い病変に対して、同じ日のうちに治療を完了することもあります。ただし、すべての病変に適しているわけではなく、病変の深さや形によってはESD や 外科的治療のほうが適切なこともあります。リスクとしては、出血や穿孔(腸に穴が開くこと)といった合併症の可能性があります。治療後も定期的な経過観察が必要で、再発がないかを確かめるための内視鏡検査が行われます。準備としては、医師の指示に従い、前日から食事制限や薬の調整を行います。鎮静薬を用いることが多く、治療中は眠っている人もいます。回復後はしばらく安静にし、飲食は医師の指示を待つのが安全です。医師と相談して、自分の病変に EMR が適しているかを判断してください。
- 内視鏡 カテーテル とは
- 内視鏡 カテーテル とは、医療現場で使われる二つの道具の役割をつなぐ言葉です。まずはそれぞれの道具について簡単に説明します。内視鏡は体の内側を観察するための細長い管で、先端には小さなカメラと光源がついています。口や喉から胃や腸、あるいは気道などの狭い場所をのぞくことができ、病気の診断や治療の手助けをします。一方、カテーテルは体の中に入れる柔らかい管で、薬を届けたり液体を取り出したり、体の中の圧力を測ったりする働きがあります。長さや細さは目的に合わせてさまざまです。内視鏡 カテーテル とは、これら二つの道具の特徴を組み合わせた道具のことを指すことが多いです。内視鏡の作業チャンネル(管の中を通る小さな道)を使って、カテーテルを体の中へ入れてさまざまな処置を行います。具体例としては、狭くなった道を広げるためのバルーンを入れて膨らませる拡張、薬を局所的に注入する注入、痰や血液などを吸い取るための吸引、あるいは組織を採取するための小さな器具を届けるなどがあります。これらの作業は、内視鏡の視界と手元の器具が連携して初めて安全に行われます。使用時には専門の医師や看護師が手順を確認し、体内には侵入するため、感染対策や麻酔の配慮が必要です。初めて聞く言葉で不安になるかもしれませんが、要点は「見る道具(内視鏡)」と「届ける道具(カテーテル)」を組み合わせて、病気を診断したり治療したりする道具だということです。
- 内視鏡 eus とは
- 内視鏡 eus とは、内視鏡に超音波の機能をつけた検査のことです。EUSはEndoscopic Ultrasoundの略で、胃や腸の内側を観察しながら、周囲にある膵臓・胆道・リンパ節といった臓器の状態を超音波で詳しく調べます。通常の内視鏡検査だけでは見つけにくい病変を、臓器のそばの様子までわかりやすく確認できるのが特徴です。検査の流れは施設ごとに少し違いますが、基本は眠剤や軽い鎮静を使い、口から内視鏡を入れて食道・胃・十二指腸の壁に沿って超音波の探触部を臓器のそばに置きます。探触部には円形(ラジアル)タイプと線形タイプがあり、線形タイプは針を通して組織を採取するFNAと呼ばれる検査を同時に行える点がメリットです。EUSの主な目的は病気の診断と病期の評価です。膵臓がん・胆管がん・胆石・胃がん・食道がんなどの位置や広がりを正確に把握したり、嚢胞性腫瘍の性質を判断したりします。また、膵臓や胆道系の炎症性疾患や腹部の腫瘤の性状を詳しく知るためにも使われます。検査を受ける前には絶食が求められ、血液をサラサラにする薬を飲んでいる人は薬の中止について指示を受けることがあります。検査後には喉の違和感や軽い吐き気が数時間続くことがあり、まれに出血や感染の兆候が見られることもありますが、重い合併症は非常にまれです。EUSは診断の精度を高め、がんや炎症の進行状況を判断して治療方針を決める際に役立ちます。初心者には、内視鏡で喉の奥から観察しつつ、腹部の奥にある臓器を超音波で見るイメージを持つと理解しやすいでしょう。
- 内視鏡 鎮静剤 とは
- 内視鏡とは、体の中を直接見るための細長い管です。喉から胃、腸の中を観察する検査で、病気の早期発見や治療の判断に役立ちます。検査中は緊張したり痛みを感じたりすることがあり、できるだけ楽に受けられるように鎮静剤という薬を使うことがあります。鎮静剤にはいくつかの種類があり、目的に応じて組み合わせて使用します。代表的なものには、心を落ち着かせるベンゾジアゼピン系の薬(例:ミダゾラム)、痛みを和らげる鎮痛薬、そして短時間で眠くなる性質をもつ薬(例:プロポフォール)などがあります。プロポフォールは使い方次第で深い眠りに近い状態を作り出しますが、呼吸や血圧の変化を注意深く監視する必要があり、通常は麻酔科医や熟練したスタッフが安全を見守ります。投与は静脈内投与で行い、検査中は心拍・呼吸・血圧・酸素濃度などを機械でモニターします。これにより薬の量を適切に調整し、体が過度に眠りすぎないようにします。鎮静剤の利点は、不安を減らし体の動きを抑えることで検査をスムーズに進められる点です。一方で眠気が強く残ることがあり、検査後もしばらく頭がふらつくことがあります。気分が悪くなったり呼吸が苦しくなったりした場合はすぐ医療スタッフに知らせてください。鎮静剤は体質や病気、飲んでいる薬によって効き方が異なります。高齢者や呼吸器や心臓の病気、妊娠している方は特に注意が必要です。検査前には飲食や薬の取り扱いについて指示をよく守り、心配であれば同行者を準備しておくと安心です。なお、鎮静を使わない選択肢もあり得ます。検査の性質や患者さんの希望、医師の判断によって、軽い鎮静だけにすることや全身麻酔を選ぶこともあります。内視鏡 鎮静剤 とは、検査を安全で楽に受けられるように工夫された薬の組み合わせのことを指します。医師と看護師が個々の状態を見て最適な方法を提案しますので、わからない点は検査前に遠慮なく質問しましょう。
- 内視鏡 ercp とは
- 内視鏡 ercp とは、内視鏡検査とX線を組み合わせて胆管と膵管の状態を調べ、必要に応じて治療を行う検査です。口から細長い内視鏡を胃と十二指腸へ通し、十二指腸の開口部から胆道へ造影剤を注入してX線で胆管と膵管の様子を写します。胆石が胆管に詰まると黄疸や腹痛が起こることがあり、その原因を取り除いたり通りをよくしたりするためにERCPが使われます。治療としては、胆石を取り出す、狭くなった部分を広げる、通るように管を置くステントを入れるなどがあります。診断と治療の両方が可能な点が特徴です。準備としては前日からの絶食や、薬を飲んでいる場合の一部中止が指示されることがあります。検査中は眠くなる薬や静脈麻酔などを使い、痛みや不安を抑えます。検査後は安静が必要な場合があり、医師の指示に従います。副作用として最も多いのは急性膵炎です。また、感染・出血・穿孔(管が破れること)・アレルギー反応などのリスクがあります。これらのリスクは事前に説明を受け、適切な準備をすることで低くできます。ERCPは非侵襲的な検査ではなく、専門的な設備と訓練を受けた医師が行う検査です。必要性があるかどうかはMRCPなどの他の検査と組み合わせて医師とよく話し合って決めます。
- esd 内視鏡 とは
- esd 内視鏡 とは、消化管の病変を内視鏡を使って切除する医療技術です。ESDは Endoscopic Submucosal Dissection の略で、従来のEMRよりも大きな病変を一塊で取り出せる点が特徴になります。胃・大腸・食道などの早期がんや前がん病変が適用対象です。手術は経験豊富な内視鏡専門医が鎮静下で行い、病変の周りに印をつけ、粘膜下層に薬を注入して病変を浮かせ、細い器具で慎重に切除します。術後の回復は個人差があり、入院期間は病院や病変の大きさによって異なります。メリットはえんぶくろ切除により病理診断が正確になり再発を減らせること、デメリットは出血や穿孔といったリスク、術後の合併症の可能性です。ESDは誰にでも勧められるわけではなく、適否は医師の診断によって決まります。医師とよく相談し、必要ならセカンドオピニオンを活用しましょう。
- apc 内視鏡 とは
- apc 内視鏡 とは、消化器内視鏡の治療の一つです。正式にはアーゴン・プラズマ凝固法(Argon Plasma Coagulation, APC)といいます。これは、体の表面に接触せずに熱を届け、粘膜の血管を焼灼して止血したり、病変の表層を薄く焼くことで治療効果をねらう方法です。仕組みは、ガスとしてアーゴンを流しながら、電気的エネルギーをそのガスのプラズマにのせて体内の組織へ送ることです。プラズマは粘膜表面で拡散して熱を起こすので、探している部位に対して広く、均一にエネルギーを当てることが可能です。 この治療は内視鏡を通じて行われ、皮膚に接触する針のような器具を使わず、非接触でエネルギーを届けます。出血を起こしている胃や腸の粘膜の小さな血管を閉じたり、ポリープの一部や表層病変を焼き尽くしたりする目的で用いられます。血管が多い部位や粘膜が薄い人でも安全に使えることが多く、他の止血法と組み合わせて使われることもあります。実際の選択は病変の場所や性質、患者さんの状態によって決まり、担当の医師が適切なエネルギー量(出力)や照射時間を調整します。一般に痛みは少なく、局所麻酔や鎮静を併用することが多いです。治療後は軽い痛みや熱感、珍しいケースとして一時的な腹部の不快感が起こることがありますが、多くは短時間で治まります。APCは強力な治療法ですが、深い組織まで届くわけではなく、がんの治癒を目的としたすべての場面に適しているわけではありません。適応は医師が判断します。情報だけでなく、実際の治療を受ける場合は、事前に利点とリスクを医師とよく話し合い、術前の検査や術後の経過観察を指示通りに行うことが大切です。
- jed 内視鏡 とは
- jed 内視鏡 とは?という言葉を見たとき、医療で使われる「内視鏡」という器具の説明を想像しますが、実は「jed」という言葉自体が標準的な用語ではなく、機器名やブランド名として使われている場合があります。この記事では、初心者にも分かりやすく内視鏡の基本を解説します。内視鏡とは、先端に小さなカメラと照明がついた細長い管状の医療機器です。体の内部を直接見るため、口や喉から胃や腸、気道、泌尿器などの検査に使われます。検査には柔らかく曲がる flexible 型と、硬めの rigid 型があり、体の形に沿わせやすい柔らかいタイプがよく使われます。映像はモニターに映し出され、医師が診断します。必要に応じて組織の一部を採取する生検も同時に行われます。検査は麻酔や鎮痛薬を使って痛みを抑えることが多く、検査前には食事の制限や腸をきれいにする準備が指示されます。検査後には喉の違和感や軽い不快感が続くことがありますが、ほとんどの場合日常生活へすぐ戻れます。なお「jed 内視鏡 とは」という表現は特定の機器名を指す場合もあるため、実際の意味は医療機関で確認してください。
内視鏡の同意語
- 内視鏡
- 体内の内部を観察するための長い筒状の医療機器。口や喉、鼻から挿入して消化管や気道などを直接見ることができます。
- 胃カメラ
- 胃を観察するための内視鏡の俗称。胃の検査や診断で使われることが多い表現です。
- 胃鏡
- 胃を観察する内視鏡の別名。胃カメラと同義として使われます。
- 胃内視鏡
- 胃を対象とした内視鏡の総称。胃を詳しく観察する機器です。
- 胃内視鏡検査
- 胃を調べるための内視鏡検査のこと。
- 大腸カメラ
- 大腸を観察する内視鏡の俗称。大腸検査で使われます。
- 大腸鏡
- 大腸を観察する内視鏡の別名。大腸カメラと同義です。
- 大腸内視鏡
- 大腸を観察する内視鏡の正式名称。
- 大腸内視鏡検査
- 大腸を検査するための内視鏡検査。
- 経鼻内視鏡
- 鼻腔から挿入して観察するタイプの内視鏡。喉への負担を減らすことが多いです。
- 経口内視鏡
- 口から挿入するタイプの内視鏡。胃や十二指腸などを観察します。
- 経鼻内視鏡検査
- 鼻から挿入する内視鏡を用いた検査のこと。
- 経口内視鏡検査
- 口から挿入する内視鏡を用いた検査のこと。
- 腹腔鏡
- 腹腔を観察・操作するための内視鏡。腹腔鏡手術などで使われる代表的なタイプです。
- 喉頭鏡
- 喉頭を観察するための内視鏡。声帯などを診るときに使われます。
- 鏡視
- 鏡を用いて体内を観察することを指す古い表現で、内視鏡を使う観察・診断の意味で使われることがあります。
- 内視鏡機器
- 内視鏡を構成する機器一式。本体のほかチューブや光源、処置具などを含みます。
- 内視鏡装置
- 内視鏡と関連機器を総称する表現。機器一式を指す言い換えです。
内視鏡の対義語・反対語
- 肉眼
- 器具を使わず、目だけで体の内部を直接観察すること。内視鏡の対義語として、体内を映す装置を使わない観察法の総称。
- 視診
- 医師が肉眼で体表や開口部を直接観察する診察法。内視鏡の代わりに器具を使わず観察する行為。
- 非内視鏡的診断
- 内視鏡を使わずに行う診断。血液検査・画像診断など、体内を直接カメラで見る方法でない検査。
- 画像診断
- X線・CT・MRI・超音波などの画像を用いて体内を評価する診断法。内視鏡とは異なる映像取得手段。
- 非侵襲的検査
- 体内へ器具を挿入せず、体を傷つけずに行う検査の総称。内視鏡検査が挿入を伴うことが多いため、対比として使える。
- 超音波検査
- 体表から超音波を用いて内部の情報を得る非侵襲的な検査。内視鏡を使わない代替検査として挙げられる。
内視鏡の共起語
- 内視鏡検査
- 内視鏡を使って消化管の粘膜を観察する検査の総称。病変の有無を調べ、診断に役立てます。
- 胃カメラ
- 胃の内視鏡検査の俗称。口または鼻から挿入して胃の内部を直接観察します。
- 大腸内視鏡
- 大腸の内側を観察する検査。ポリープの発見や大腸がん検診に用いられます。
- 内視鏡手技
- 内視鏡を用いた治療・処置の総称。ポリープの切除や止血、粘膜下剥離などを含みます。
- 生検
- 組織を少量採取して病理検査を行う検査。内視鏡を介して病変部から組織を採取することが多いです。
- ポリープ
- 粘膜にできる良性の腫瘍や異常。検出されれば切除されることがあります。
- 粘膜
- 消化管の内側を覆う薄い組織。病変の観察対象として重要です。
- 食道観察
- 食道の粘膜を観察すること。炎症や潰瘍、がんなどの診断に役立ちます。
- 胃観察
- 胃の粘膜を観察すること。炎症や腫瘍などの診断に用います。
- 大腸観察
- 大腸の粘膜を観察すること。ポリープやがんの有無を確認します。
- 局所麻酔
- 検査部位の痛みを和らげるため、局所に麻酔薬を注入します。
- 鎮静
- 静脈注射で落ち着かせる薬を使い、検査中の不快感を低減します。
- 全身麻酔
- 眠っている状態で検査を行う麻酔。安全性や快適さのために選択されることがあります。
- ファイバースコープ
- 細く柔軟な内視鏡の一種。現在は電子内視鏡が主流ですが、依然として使われる場面もあります。
- スコープ
- 内視鏡の総称で、検査機器を指す日常語として使われます。
- 光源
- 内視鏡の照明。粘膜を明るく照らして細部を観察します。
- 絶食
- 検査前に食事を控えること。胃や腸を空にして観察を安定させます。
- 事前問診
- 検査前に医師が体調・アレルギー・薬の情報を確認する問診です。
- 合併症
- 内視鏡検査に伴うリスク。出血・穿孔・感染などが起こる可能性があります。
- 出血
- 粘膜の切除や病変周囲で起こる出血。止血処置が行われます。
- 穿孔
- 腸壁や胃壁に穴が開く重い合併症の一つ。緊急対応を要することがあります。
- ESD
- 内視鏡的粘膜下層剥離法。病変を粘膜下層ごと大きく切除する治療法です。
- EMR
- 内視鏡的粘膜切除法。比較的小さめの病変を内視鏡で切除します。
- 内視鏡医
- 内視鏡検査や治療を専門に担当する医師です。
- 胃がん検診
- 胃がんを早期発見するための検査。胃カメラで胃の粘膜を観察します。
- 大腸がん検診
- 大腸がんを早期に発見するための検査。大腸内視鏡を用います。
- 病変
- 粘膜の異常部分。腫瘍・潰瘍・炎症などを指します。
- 画像
- 検査中に撮影される映像・写真。診断の根拠となります。
内視鏡の関連用語
- 内視鏡
- 体内の腔所や臓器の内部を観察・治療する細長い管状の医療機器。先端にはカメラと光源が備わり、挿入部・操作部・洗浄・給水チャンネルなどがある。
- 胃内視鏡
- 胃を直接観察するための内視鏡。喉から挿入して胃内の粘膜を検査・診断する。胃がん・潰瘍の発見に用いられる。
- 大腸内視鏡
- 大腸を観察・治療する内視鏡。大腸がん検診に用いられ、病変部の観察・切除が可能。
- 十二指腸内視鏡
- 十二指腸まで挿入できる内視鏡。ERCPなど胆道・膵管の検査・治療に使われる。
- 内視鏡検査
- 内視鏡を用いて体内の粘膜・臓器を観察する診断手技全体の総称。
- 内視鏡手術
- 内視鏡を使って病変を切除・治療する低侵襲な手術技法の総称。
- 内視鏡的粘膜下剥離術
- 粘膜下層を剥離して大きな病変を取り除く高度な内視鏡治療。
- 内視鏡的粘膜切除術
- 内視鏡で病変を切除する治療。小さめの病変に適用される。
- 内視鏡的逆行性胆管膵管造影法
- 内視鏡を使って胆道・膵管の造影・治療を行う手技。チューブ挿入・ステント留置など。
- 経鼻内視鏡
- 鼻から挿入する細長い内視鏡。喉の反射を抑え、長時間の検査にも適する。
- 内視鏡超音波検査
- 内視鏡先端に超音波プローブを搭載し、臓器の深部構造を評価する検査。穿刺を伴う場合もある。
- 白色光内視鏡
- 標準の白色光を用いた基本的な内視鏡観察。
- 拡大内視鏡
- 病変を高倍率で観察する技術。微細な粘膜構造を評価するのに有用。
- 色素内視鏡
- 染色液を使い、粘膜のパターンを強調して病変を見つけやすくする。
- 狭帯光観察
- 狭帯光内視鏡とも呼ばれ、特定波長の光を使って粘膜表層と血管を強調する画像強調技術。
- 画像強調内視鏡
- I-SCAN / FICE / SPIES など、画像を処理して病変の識別を高める技術群。
- 洗浄・給水チャンネル
- 内視鏡本体に備わる洗浄・給水の機能。視野をクリアに保つために使われる。
- 生検
- 病変部の組織を採取して病理検査を行う診断法。内視鏡検査中に頻繁に行われる。
- ポリープ切除
- 内視鏡でポリープや病変を切除する治療。EMR / ES D などの方法がある。
- 粘膜下層
- 病変が存在する粘膜の下の層。ESD/EMR の適応判断や治療方針に影響する。
- 鎮静下内視鏡検査
- 薬剤で鎮静して行う内視鏡検査。痛みや不安を軽減する。
- 全身麻酔下内視鏡検査
- 全身麻酔の状態で行う内視鏡検査。長時間・高度な処置に適用される。
- 内視鏡滅菌・消毒
- 使用後の洗浄・滅菌・消毒を徹底して感染を防ぐ。