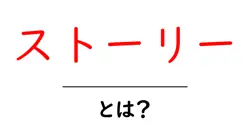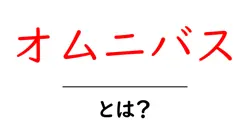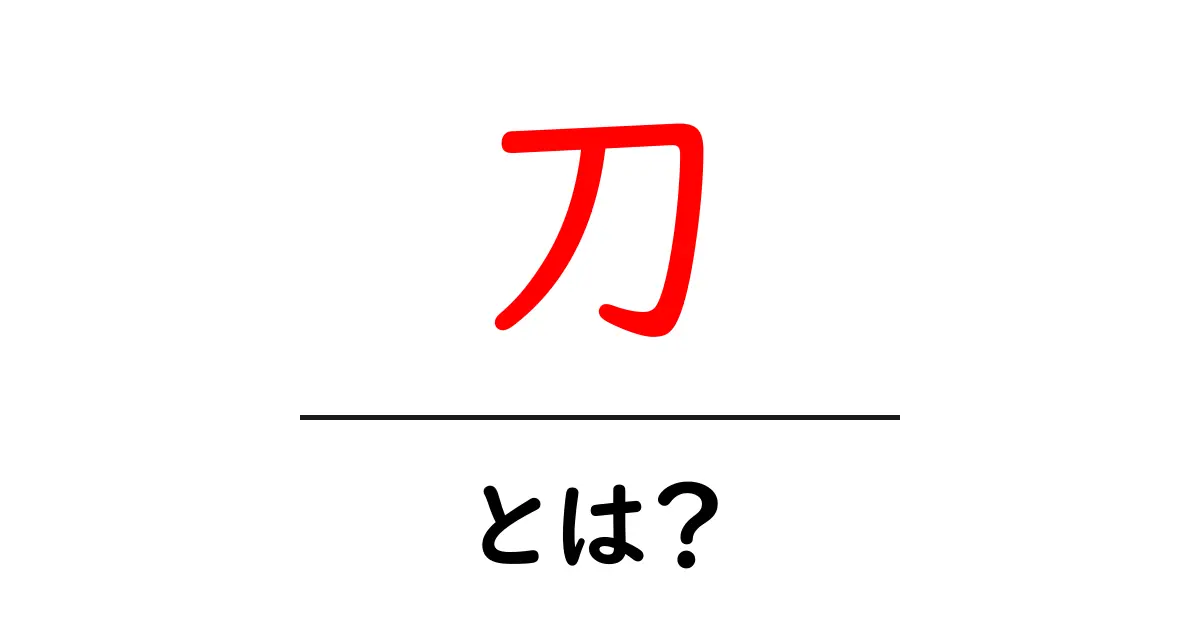

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
刀・とは?基本の意味
「刀」とは、刃を持つ道具の総称です。日常では特定の形を指すことが多く、日本語では特に武器としての日本刀を思い浮かべる人が多いです。刀は切る力と美しい刃の形を両立させる道具として長い歴史を持ちます。現代ではコスプレ・美術品・スポーツ競技の道具など、さまざまな場面で使われる言葉です。
刀の種類と違い
世界には多くの刃物がありますが、刀という言葉自体には様々な意味が含まれます。日本で特に有名なのが「日本刀」で、独特の曲線、片刃、鍛え方が特徴です。一方で西洋の剣は一般に両刃で直線的な刃が多いといった違いがあります。
刀の歴史と役割
日本の歴史の中で、刀は侍の象徴として有名です。しかしただの武器ではなく、鍛冶職人の技術の結晶であり、長い年月をかけて鍛えられた美術品でもあります。時代が変わって武器としての役割は薄くなりましたが、現在では美術館で鑑賞されたり、居合道などの伝統的な武道に深く結びついています。
安全と扱い方
刀は鋭い刃を持つため、取り扱いには必ず大人の監視と安全ルールが必要です。家庭や学校で刀を扱うときは、決められた場所と方法を守り、子どもには触らせないことが基本です。目的以外の使用や、子どもだけでの扱いは避けましょう。
現代の文化と楽しみ方
最近では刀の美術品としての価値が改めて評価されています。美術館での展示や、博物館の企画展、刀剣の研究など、学問的にも興味深い対象です。趣味としては日本刀をテーマにした資料収集や、居合道・剣道といった武道の練習を通じ、刀の歴史を学ぶ人も多いです。正しい知識と敬意を持って見ることが大切です。
まとめと日常のヒント
刀という言葉は、歴史・文化・芸術の広い意味を含みます。基本的な知識を身につけることで、刀を敬いながら理解することができます。美術館で刀を見かけたら、刃の鋭さだけでなく、鍛冶職人の技術と造形美にも注目してみましょう。
刀の製作過程についての注意
刀の製作過程は高度で危険を伴う作業です。実際の制作方法を学ぶ際には必ず専門家の指導のもとで行い、家庭内で真似をすることは避けてください。歴史的・技術的な背景を理解することに focus して学習しましょう。
刀の関連サジェスト解説
- katana とは
- katana とは、日本の武器として世界的に有名な日本刀の一種で、長くて湾曲した刃と美しい鍛え方が特徴です。刃は鋭く、柄と鞘を合わせて使い手が握りやすいように作られています。刀身は玉鋼などの鋼を何層も合わせて作る伝統的な技法で作られ、焼き入れと呼ばれる熱処理で硬さと切れ味を高めます。katana とは、単に長い刀という意味だけでなく、侍の時代に活躍した戦いの道具であり、日本の職人技と歴史を象徴する存在として語られることが多いです。現代では、戦闘用の実用品としてはほとんど作られなくなり、博物館での展示品や映画・アニメの影響で世界中の人に知られるようになりました。現地の文化財としての価値も高く、日本刀は専門家や職人の手によって長い時間をかけて守られてきました。katana の構造は大きく分けて刀身、柄(握る部分)、鞘、鍔からなり、刃の反り方(そり)や刃文と呼ばれる模様が特徴です。安全と敬意をもって扱うべき伝統的な品であり、日本の美意識と歴史を伝える大切な文化財と言えます。
- カタナとは
- カタナとは、日本の伝統的な長い日本刀の一種で、曲線を描く細身の刀身と片刃、そして木の柄を両手で握る長さが特徴です。世界的に有名な「日本刀」の中でも特に代表的な形で、サムライの象徴としてよく知られています。カタナの特徴は、刃が薄く鋭く、反りがあることで切れ味と美しさを両立している点です。刃の表面には模様のような「刃文(はもん)」が現れ、これは鍛え方の違いによって生まれる美しい模様です。伝統的な製法は折り返し鍛錬と呼ばれ、鋼を何度も折り返して組み合わせることで強さと粘りを作り出します。現代では、武道の道具としてだけでなく、美術品や歴史資料としても価値があり、博物館に展示されることも多いです。また、居合道や剣術の演武、刀剣関連の歴史研究の対象としても重要です。カタナとは、単なる武器以上の、日本の技術と文化を長い時間をかけて築いてきたものを示す言葉であり、日本の伝統を理解する手がかりとなる存在です。
- 株式会社 刀 とは
- この記事では「株式会社 刀 とは」というキーワードを初心者にも分かるように解説します。まず、株式会社とは日本で一般的に使われる法人の一つで、会社法のルールのもとで設立される組織です。株主が出資しており、会社は規模に応じて利益を追求します。キーワードの中心である『刀』は、企業名の一部として使われる場合が多い漢字です。刀は歴史上の武器であり、伝統・技術・職人精神の象徴としてのイメージを作ることがあります。つまり『刀』という名前の企業は、実際に刀を扱う事業をしていなくても、その字面から強さや誠実さを連想させる狙いで選ばれることがあります。株式会社を作るには、設立の手続きが必要です。定款の作成、資本金の払い込み、出資者の確定、役員の選任、そして法務局への登記申請が基本です。資本金の最低金額は現在1円から可能ですが、現実的には事業計画に見合う資金を用意するケースが多いです。登記が完了すると、会社は法的に人格を持つ組織となり、契約を結んだり銀行口座を開いたりすることができます。SEOの観点から見た場合、『株式会社 刀 とは』という完全一致の検索は難易度が高いことがあります。そのため、読者のニーズに合わせて『株式会社』『刀』『企業名の意味』『ブランド名の付け方』などの組み合わせ語で説明すると、検索に引っかかりやすくなります。
- ジュラルミン 刀 とは
- ジュラルミンとは、アルミニウム合金の一種で、主にマグネシウムとシリコンを加えて作られる材料です。1900年代初めに開発され、軽さと強さのバランスが特徴です。熱処理を工夫することで強度を高められる点も魅力のひとつで、航空機の部品や自動車の部品、建築材料など、さまざまな用途に使われてきました。では「ジュラルミン 刀 とは」というと、結論からいうと刀として使われることはほとんどありません。刀や刃物には、普通は鉄を主成分とした鋼が使われます。鋼は硬さが高く、切れ味を長く保つ性質があり、日本刀をはじめとする多くの刃物に適しています。一方、ジュラルミンのようなアルミニウム合金は、鋼ほど硬くはなく、曲がりやすい性質があるため、現代の実用的な刃物としては向いていません。そのためジュラルミンを刀の材料として選ぶことは、現代の実用面では一般的ではありません。ただし、現場の安全や展示目的の場では、装飾用の“刃”としてジュラルミンを使うケースもあります。博物館の展示品や劇用の小道具など、見た目の軽さや軽快さを生かす用途です。しかしこれは実際に切る目的の刃物として使われるものではなく、見た目を再現するための素材として用いられます。実刀の代わりにはなりません。歴史的には、ジュラルミンは飛行機の機体材料として広く使われ、軽量化と耐久性の両立を達成した重要な合金でした。現代の刃物設計においては、鋼の優れた性能が依然主役です。ジュラルミンは刃物の材料としての適性よりも、他の機械部品や構造材としての役割のほうが大きいと覚えておくとよいでしょう。初心者の方には、ジュラルミンを刀と結びつけて覚えるより、アルミニウム合金がどんな材料で、どんな特徴を持つのかをセットで覚えると理解しやすいです。安全面にも注意が必要で、刃物の取り扱いは専門家の指導のもとで行い、適切な材料と用途を選ぶことが大切です。
- なかご 刀 とは
- なかご 刀 とは、刀身を支える重要な部位のひとつです。なかごは日本刀の刃の根元が柄の内部に収まる部分で、英語では tang と呼ばれます。刀を柄に固定する基盤となり、刀身と柄を結ぶ役割を果たします。なかごには柄と刀身をつなぐめぐぎ穴という小さな穴がいくつか開いており、これに竹製のめぐりくぎを打ち込むことで刀を丈夫に固定します。穴の数や位置、長さは刀の設計や時代によって違います。また、なかごには銘meiが刻まれていることがあります。銘は刀工の名前や作られた時代を示し、刀の歴史を知る手がかりになります。銘があるかどうか、銘の読み方は専門家でないと難しいことが多く、偽物も存在するため真偽を判断するには専門知識が必要です。なかごの形や長さは刀のバランスにも影響します。長いなかごは重心を後ろに保ち、短いものは手元の操作性に影響します。形状や長さは現代製か古刀かの見分けにも役立つ情報です。安全面にも注意が必要です。なかごを含む部位は鋭く危険なため、素人が扱うと大きな事故につながることがあります。実物を扱う場合は美術刀剣の専門家や博物館の指導のもとで行い、正しい保存方法を学ぶことが大切です。
- 竹光 刀 とは
- 竹光 刀 とは、竹を材料とした訓練用の刀のことです。実際の刀のような鋭い刃はなく、練習中の安全を第一に考えて作られています。多くの場合、刀の形を整えるために竹の芯の周りに布や木の柄が組み合わされ、柄は木でできていることが多いです。刃は竹でできており、鋭さはありませんが、正しい姿勢や動作を練習する道具として十分な重さと手ごたえを感じられるよう設計されています。竹光は木刀(ぼっけん)や竹刀(shinai)とは違い、刃が竹である点が特徴です。用途としては、基本の構え、踏み込み、払い、突きなどの動作を安全に練習することが中心で、特に初心者が刀剣の感覚をつかむ導入道具として適しています。現代の道場では、仲間と安全に技を確認するために竹光を使う場面があり、正式な競技では shinai や木刀が使われることが多いです。歴史的には、日本の武術の練習において、鋭利な刃を避ける目的で竹製や木製の訓練用具が用いられてきました。竹光はその流れの中で現代にも残り、児童や初心者が基本の型を覚えるのにふさわしい道具として重宝されています。購入する際は長さや重さ、竹の太さ、先端の丸さ、柄の握りやすさなどを確認し、場所によっては安全保護具の着用を義務づけていることもあります。使用時には周囲に人がいない場所を選び、保護具を着用し、使用後は乾燥させてカビを防ぎ、刃の節や割れをチェックしてから保管しましょう。
- 打ち粉 刀 とは
- 打ち粉とは、小麦粉などを生地や作業台に薄くふりかけて、生地がくっつくのを防ぐ粉のことです。パン作りやうどん作り、餃子の皮を伸ばすときなど、作業の場所で使います。粉は小麦粉だけでなく米粉や片栗粉、場合によってはでんぷん系の粉を使い分けます。打ち粉は少量で十分で、厚く振りすぎると生地の風味が変わったり、仕上がりが重くなったりするので注意しましょう。 また、キッチン用語として『刀』は刀剣を意味します。料理の現場では通常、『包丁』や『ナイフ』を使います。『刀』という言葉は日常の台所ではあまり使われず、検索時に混乱を招くことがあるため、混同しないようにしましょう。もしレシピに『打ち粉を打つ』と書かれていても、刀で粉を振るわけではなく、作業面の滑り止めとして使う粉を指しています。 打ち粉の使い方のコツは以下の通りです。1) 作業台の表面と生地の表面の両方に薄く打ち粉を振る。2) 伸ばす前に軽く粉を払う程度にする。3) 切ったり成形したりする際、粉が多すぎないようにし、必要に応じてさらに少量追加する。4) 粉を使いすぎると生地の食感が変わるので、目的に応じて調整する。 また、包丁を使うときは安全に注意し、刃を滑らせる方向と手元の指を守る姿勢を心がけましょう。 このように、打ち粉は料理の現場で“くっつき防止”の役割を果たす道具であり、刀(刀剣)とは別物です。
- 大小 刀 とは
- 大小 刀 とは、二つの刀種をまとめて表す中国語の表現です。ここでの「刀」は日本語の刀とは別に、中国語の dao、すなわち“刃の長い武器”を指します。大刀(dàdāo)は長くて厚みのある刃をもつ武器で、隊列戦や広い範囲を切る動作を想定して使われました。小刀(xiǎodāo)は刃が短く、近接戦や護身用として携帯されることが多い小型の武器です。歴史的には、大刀は歩兵の戦闘で、斬る・払いの動作を重視しました。小刀は近づいて攻撃・防御するための武器として役立ちました。現代の解釈では、武術の練習や演舞の場で「大小刀」をセットで練習することがあります。長い刃と短い刃を組み合わせて、動作の幅を広げる訓練として用いられることがあります。ただし、現代日本や他国で扱う場合は、法規制や安全の問題があるため、無闇に携帯したり実戦的な使い方を教える場面は避け、博物館の展示解説や専門家の指導の下で学ぶことが大切です。「大小刀」という語は、武術・歴史・文化の解説でよく使われ、学校の授業や一般向けの解説でも紹介されます。名前の通り「大小」はサイズの違いを指し、「刀」は武器としての刃を意味します。日本語の文章では「大小刀」と表記することもあれば、学術的な場面では「大刀・小刀」と別名で説明されることもあります。
- 拵 刀 とは
- 拵 刀 とは、日本刀の刃身を包み、実際に握る柄(つか)と刃を収める鞘(さや)をセットにした外装の総称です。拵えは刀身と離れず、一体となって刀の重さのバランスや扱いの感触を決めます。歴史的には江戸時代を中心に多くの職人が技を競い、素材や装飾の組み合わせが作り手の技術と時代背景を反映しました。現代でも拵えは美術品として高く評価され、博物館やコレクションで展示されることがあります。主な部品には鞘、柄、鍔、金具類が含まれます。鞘は木で作られ、漆を塗ることで傷に強く、刀身を守ります。鞘にはsageo(下げ緒)を通す穴や紐の結び目を作る装飾が施され、帯に差して携帯する際の安定性を高めます。柄は握りの部分で、皮(鮫革・samegawa)と布・紐で巻かれて手に馴染むよう作られています。柄の内部には目貫と呼ばれる飾り金具が入ることがあり、風合いを引き立てます。柄の先端にはkashira(柄頭)と呼ばれる金具が、柄の付け根にはfuchiと呼ばれる金具が取り付けられ、全体の強さと美しさを支えます。鍔(つば)は刀身と柄の間を覆い、安全性とデザイン性を両立させる役割を担います。さらに、刀身を鞘に固定するhabaki(留め金)や座金(seppa)などの部品も使われ、拵えの締まりを調整します。装飾としては、金属の彫刻や象嵌、能装飾などが施されることがあり、素材には木・漆・金属・宝石などが使われることがあります。
刀の同意語
- 剣
- 日本語で長い刃を持つ武器を指す一般的な語。刀と同義に使われる場面もあるが、剣は双刃の武器を含むことが多い点に注意。
- 日本刀
- 日本で製作・使用された伝統的な刀の総称。刃長や製法の特徴を含む総称で、現代語で“刀”を指す際の具体例として使われることが多い。
- 刀剣
- 刀と剣を総称する語。美術品・博物館・刀剣ファンの話題で、複数の刀をまとめて指す際に使われる。
- 太刀
- 日本の古代〜中世に用いられた長い片刃の刀。現代では刀の一種として扱われるが、形状と携行スタイルに特徴がある点に留意。
- 長剣
- 長さのある剣を指す語。文脈によっては西洋の長剣を指す場合もあるが、日本語では用法が限定されることが多い。
刀の対義語・反対語
- 盾
- 刀は攻撃用の刃物で、敵を切り崩すことを主な目的とします。一方、盾は防御の道具で、刃を使わずに敵の攻撃を受け止める役割を担います。攻撃と防御という対義性を持つイメージとして挙げられます。
- 無刀
- 刀を携帯・使用しない状態のこと。武器を持つこと自体を避ける概念で、“刀を使う”という状況の反対として捉えることができます。
- 素手
- 武器を使わず、手だけで戦う状態のこと。刀を使った戦いに対する非武装の戦い方の対義として理解できます。
- 鈍刀
- 刃が鋭くない刀のこと。鋭い切れ味を持つ刀(鋭利な刀)に対して、攻撃力が落ちたイメージの対義として挙げられます。
- 木刀
- 木製の刀。金属製の刀と比べて切れ味や破損の危険性が低く、現実の戦闘向けではない非致傷性の道具という対比を作ります。
- 槍
- 長柄の武器で、刀とは別の形状と運用を持つ武器。刀と対照的な武器種として挙げられます。
- 銃
- 現代の火器。刀の歴史的・伝統的な武器というイメージに対して、現代的・遠距離の武器という対比として使えます。
- 平和
- 刀が戦いや暴力を連想させる象徴であるのに対し、平和は暴力を避け非暴力を意味する概念として挙げられます。
刀の共起語
- 日本刀
- 日本で作られた刀の総称で、歴史・美術的価値が高い武器として扱われます。
- 太刀
- 刀の一種で、腰帯から抜く長くて湾曲した形状。戦闘時の使い方や時代背景で語られます。
- 薙刀
- 長柄の日本の武器で、刀とは別カテゴリですが刀剣の話題と一緒に出ることがあります。
- 刀剣
- 刀と剣の総称。日本刀を含む武器全般・美術品のカテゴリとして用いられます。
- 刃
- 刀の切れ味を左右する鋭い部分のこと。
- 刃紋
- 刃の表面に現れる模様で、技量の高さや美術的価値を示します。
- 鍛冶
- 刀を作る職人の総称。
- 刀鍛冶
- 刀を専門に鍛える職人。高度な技術を要します。
- 鍛造
- 鉄を打って刃を作る加工工程。
- 研ぐ
- 刃を研ぎ澄まして切れ味を回復させる作業。
- 研ぎ
- 研磨作業の総称。砥石を用いて行います。
- 砥石
- 刃を研ぐ際に使う石。粗砥・中砥・仕上砥などがある。
- 鑑定
- 刀の真偽・価値を専門家が判断・評価すること。
- 銘
- 刀工の署名のこと。銘があると作り手を特定しやすい。
- 鑑定書
- 真偽・価値を示す専門家の証明書。
- 拵え
- 刀の柄・鞘・鍔・覆いなどを含む外装・装い全体のこと。
- 柄
- 握る部分(つか)のこと。長さや形状が握り心地に影響します。
- 鍔
- 刀の鍔は刃と柄の間にある金属製の護置部。
- 鞘
- 刀身を収める鞘。材質や装飾も美観に影響します。
- 刃長
- 刀の刃の全長のこと。区分や用途に関係します。
- 反り
- 刀身の曲がり具合。美観と強度のバランスに影響します。
- 重ね
- 刀身の厚みのこと。強度・耐久性に関係します。
- 産地
- 刀が作られた地域名。流派の特徴を示します。
- 備前
- 有名な刀剣の産地の一つ。多くの名刀を輩出しました。
- 相州
- 相州系の刀工・流派に由来する産地名。
- 美濃
- 美濃国の刀工伝統・流派を指します。
- 越前
- 越前地方の刀工伝統・流派を指します。
- 大和
- 大和地方の刀工伝統・流派を指します。
- 名刀
- 歴史的にも高く評価される刀の総称。
- 重要文化財
- 国が重要な文化財として指定した刀剣類。
- 保存刀剣
- 文化財保護の分類の一つで、現状を維持して保存される刀剣。
- 刀匠
- 刀を作る熟練の職人・匠。
- 歴史
- 刀には長い歴史があり、技術と文化の変遷を伝えます。
- 戦国時代
- 戦乱の時代で刀剣の製法・戦術に影響を与えました。
- 手入れ
- 保管時のさび防止・状態維持のための手入れ作業。
- 文化財
- 美術的・歴史的価値が認められた貴重な遺物として扱われます。
- 刀剣乱舞
- 人気ゲーム・アニメなど、現代文化と結びつく刀剣の話題。
- 鑑定士
- 刀剣鑑定を専門的に行う専門家。
- 銘読み
- 銘の読み方・判別の技術。
- 拵えの美学
- 拵えは刀を美しく見せる外装デザインのこと。
- 手打ち
- 伝統的な手打ち鍛造に基づく作刀技術。
- 刃物
- 刀は刃物の一種として、日常語としても語られることがある。
刀の関連用語
- 日本刀
- 日本刀は、日本で長い歴史の中で作られてきた伝統的な刃物の総称。刃・鞘・拵え・柄・鍔などを含む一連の刀剣を指します。現代でも美術品や武道の対象として重視されます。
- 太刀
- 長い曲刀で、戦国時代以前に広く用いられた種類。抜き方や拵えの形状が特徴的です。
- 打刀
- 現代の日本刀の基本形となる刀の一種。携帯時の構え方が変化し、刃長が比較的短く作られることが多いです。
- 脇差
- 太刀と刀の中間の長さを持つ短い刀。戦国時代以降に携帯され、補助的な役割を担いました。
- 小太刀
- 更に短い刀の総称。補助的な武器として使われることが多いです。
- 刀身
- 刀の刃の本体部分。切れる部分を形成する素材と加工の集約点です。
- 刃
- 刀の鋭い部分全般を指します。切れ味に直結します。
- 刃文
- 刃の焼き入れ後に現れる模様のこと。美術品としても重要です。
- 反り
- 刀の曲がり具合、刃の弯曲の程度を表します。美観と機能のバランスで評価されます。
- 玉鋼
- 玉鋼は伝統的な日本刀用の高品質な鋼材。砂鉄を炉で高温加工して作られます。
- 鍛冶/刀匠
- 刀を作る職人の総称。鍛冶・刀匠は技術と名声が重要視されます。
- 拵え
- 拵え(こしらえ)は、刃を包む鞘・柄・鍔・装身具などの総称。美観と機能を両立します。
- 鞘
- 刀を収める外鞘(さや)のこと。携行時の保護と美観を担います。
- 柄/柄巻
- 刀の握り手となる部分。柄巻は表面を巻いて手触りと装飾を提供します。
- 鍔
- 刀の刃と柄の間にある金属の護具。防護と飾りの役割を持ちます。
- 銘
- 刀身に刻まれた作者名や製作時期を示す銘文のこと。真贋や価値の判断材料になります。
- 砥石/研ぐ
- 砥石は刃を研ぐ道具。研ぐは刃を鋭く整える作業です。
- 刀剣/刀剣美術
- 刀と剣を指す総称。刀剣美術は美術品としての刀剣の研究・鑑賞分野です。
- 古刀/新刀/業物
- 刀の歴史的区分。古刀は江戸以前の作刀、新刀は江戸時代中期以降、業物は切れ味・品質の高さを指す美術用語です。
- 居合刀/居合道
- 居合道で用いられる練習用の刀や、それを行う武道の総称です。
- 包丁
- 家庭用の刃物で、刀と同じく刃物の一種として関連します。
刀のおすすめ参考サイト
- 刀とは/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館
- 刀とは/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館
- 日本刀とはどんな特徴がある物でしょうか? - 名古屋刀剣博物館
- 日本刀とは/ホームメイト - 刀剣ワールド大阪
- 日本刀とはどんな特徴がある物でしょうか? - 名古屋刀剣博物館
- 刀(カタナ)とは? 意味や使い方 - コトバンク