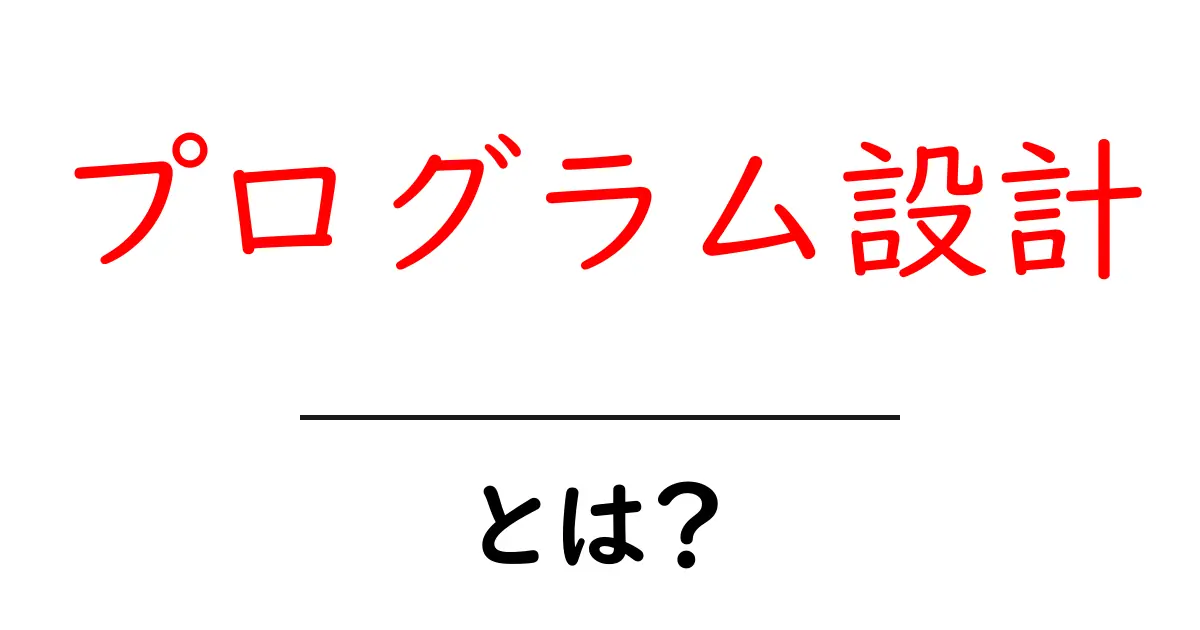

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
「プログラム設計・とは?」は、ソフトウェアを作る前に何を作るか、どう作るかを決める作業のことです。設計をしっかり行うと、最終的なコードが読みやすくなり、バグが減り、作る人が増えても協力しやすくなります。ここでは中学生にも分かる言葉で、設計の基本と実践のコツをやさしく解説します。
設計の目的
設計の主な目的は三つです。何を作るかをはっきり決める、どう動くかを整理する、そして変更に強い仕組みを作ることです。これらを最初に考えることで、後の作業がスムーズになります。
設計の基本ステップ
1. 要件の整理:誰が使うのか、何を実現したいのかをはっきりと書き出します。
2. データと機能の分担:どのデータを扱い、どんな機能が必要かを分けて考えます。
3. アルゴリズムの選択:どの手順で問題を解くかを決めます。難しすぎず、できるだけ簡単な考え方で設計します。
4. 実装計画とテスト設計:実装の順序を決め、どのように動作を確かめるかを決めます。
実践の例:簡単なTODOリストの設計
例として、日常生活でよく使われる「TODOリスト」を考えます。ここでは何を設計するのか、どう動くのかを分かりやすく整理します。
この表のように、データがどのような情報を持ち、どんな操作を受けるかを前もって決めておくと、実装時に迷わなくなります。設計の段階でデータと機能の関係を整理することが大切です。
設計がうまくいくコツ
コツ1: 大きな問題を小さな部品に分けて考える。分割して考えると全体像が見えやすく、実装もしやすくなります。
コツ2: 変更に強い設計を目指す。将来の変更を想定して、部品同士の結びつきを弱くしておくと修正が楽になります。
まとめ
プログラム設計は、何を作るかを決めることと、どう作るかを決めることの二つを丁寧に行う作業です。要件を正しく整理し、データと機能を分け、アルゴリズムを選び、実装計画を立てることで、はじめてのプログラムでも無駄なく作業を進められます。反復練習を重ねるほど、設計力は高まります。
プログラム設計の同意語
- ソフトウェア設計
- ソフトウェア全体の構造・挙動を決定する設計。プログラム設計の最も一般的な同義語です。
- アプリケーション設計
- アプリ(アプリケーション)向けの機能・構造を設計すること。
- 概要設計
- 全体の枠組み・主要機能の配置など、高レベルの設計を指します。
- 詳細設計
- 各機能を具体的にどう実装するかを決める、実装へつなぐ設計段階です。
- 機能設計
- 提供する機能の仕様と実現方法を決定する設計作業。
- アーキテクチャ設計
- ソフトウェアの基本構造(層・部品・相互作用)を決める設計作業。
- ソフトウェアアーキテクチャ設計
- ソフトウェア全体のアーキテクチャを設計すること。
- システム設計
- ソフトウェアを含むシステム全体の構成・動作を設計します。
- モジュール設計
- モジュール単位の構造・インターフェースを決める設計作業。
- 構造設計
- データ構造・クラス・モジュール間の関係など、全体の構造を設計します。
- アルゴリズム設計
- 問題を解くためのアルゴリズムを選択・設計する作業。
- 仕様設計
- 機能・性能・制約などの仕様を定義・落とし込む設計作業。
- 実装設計
- 実装時の方針・コード規約・実装方針を決める設計作業。
プログラム設計の対義語・反対語
- 実装
- 設計で決めた仕様を、動くコードとして実際に作成する作業。プログラム設計の対義語として最も直接的に捉えられる作業です。
- コーディング
- コードを書くこと。設計で決めた構造やアルゴリズムを具体的なプログラムのソースコードへ落とし込む作業。
- デプロイ
- 完成したコードを実運用環境へ配置して動作させる工程。設計・実装の次の段階として位置づけられることが多い作業。
- 実行
- プログラムを実際に動かして結果を得る行為。設計段階の抽象性を離れ、コードの挙動を確認するフェーズ。
- 運用
- システムを日常的に使用・監視し、継続的に維持・改善していく活動。設計・実装の後に来る実務の場面です。
- 保守
- 運用中のシステムを安定させ、障害対応や機能改善を行う活動。完成後の長期的管理に当たるフェーズです。
- テスト
- 実装したプログラムが仕様どおり機能するかを検証する工程。品質保証の一環として、設計と実装を結ぶ役割を担います。
- デバッグ
- 実装コードの不具合を見つけ出して修正する作業。動作検証の過程で頻繁に行われる重要な作業です。
プログラム設計の共起語
- ソフトウェア設計
- ソフトウェア全体の構造・部品の配置を決める設計作業。要件を満たすための機能と非機能を整えます。
- アーキテクチャ設計
- システムの高レベルな構造(層・部品・相互作用)を設計する工程。拡張性・保守性を左右します。
- ソフトウェアアーキテクチャ
- ソフトウェア全体の基本構造や部品の分割単位、相互作用の設計を指します。
- オブジェクト指向設計
- オブジェクトとクラスの責任分担を明確にし、再利用性・拡張性を高める設計手法です。
- クラス設計
- クラスの責任・属性・操作・関係性を決め、他の部品との結合を抑えます。
- モジュール設計
- 機能を独立したモジュールに分割し、結合度を低く保つ設計です。
- デザインパターン
- よくある設計課題に対する再利用可能な解決策の型・テンプレートです。
- 設計パターン
- 設計の定番パターンの総称。デザインパターンと同義で使われます。
- SOLID原則
- ソフトウェア設計の5つの原則の集合。単一責任・開放/閉鎖・リスコフ置換・インターフェース分離・依存性逆転を指します。
- 単一責任原則
- クラスはたった1つの責任だけを持つべきという指針です。
- オープン/クローズド原則
- 拡張には開き、変更には閉じるよう設計する原則です。
- リスコフ置換原則
- 派生クラスは基底クラスの代わりに安全に使えるべきという原則です。
- インターフェース分離原則
- 大きなインターフェースを細分化し、不要な依存を避ける原則です。
- 依存性逆転の原則
- 高水準モジュールは低水準モジュールに依存せず、抽象に依存するべきという原則です。
- 依存性注入
- 依存する部品を外部から提供して結合度を下げる手法です。
- デザイン原則
- 設計の質を高める一般的な指針の総称です。
- 抽象化
- 現実の複雑さを共通点で取り出し、具体性を減らす技法です。
- カプセル化
- データと処理をひとまとめにして内部実装を隠す考え方です。
- ユースケース設計
- 実際の利用場面の流れを基に要件を設計する手法です。
- UML
- Unified Modeling Language の略で、設計を図で表す表現方法です。
- 設計ドキュメント
- 設計内容を文書として記録し、開発者間で共有する資料です。
- テスト駆動開発
- 先にテストを作成し、それを満たす機能を実装していく開発手法です。
- TDD
- テスト駆動開発の略。短く表記されることが多いです。
- リファクタリング
- 既存のコードの挙動を変えずに内部構造を改善する作業です。
- 保守性
- 変更・修正を容易に行える設計の性質を指します。
- 拡張性
- 新機能を追加しやすい設計の性質を指します。
- データ設計
- データの保存・取り扱いを前提に、データ構造・モデルを設計する作業です。
- データベース設計
- データベースのテーブル構成・リレーションを設計します。
- API設計
- 外部システムと通信する際の仕様・使い方を決める設計です。
- インターフェース設計
- モジュール間の接点となる関数・メソッドの仕様を決めます。
- エラーハンドリング設計
- エラーの検出・伝搬・回復の方針を決める設計です。
- セキュリティ設計
- 不正アクセスやデータ漏えいを防ぐ観点を組み込む設計です。
- クリーンアーキテクチャ
- 依存の向きを中心に、保守性とテスト容易性を高める設計方針の一つです。
- レイヤードアーキテクチャ
- 層ごとに責任を分離する構造設計です。
- DDD(ドメイン駆動設計)
- ビジネスドメインの知識を中心に設計・実装を進める方法論です。
- 設計レビュー
- 他の人の目で設計を評価・指摘し改善する評価プロセスです。
プログラム設計の関連用語
- アルゴリズム設計
- 問題を解く手順を決める作業。最適な計算手順(アルゴリズム)を選び、データの流れと処理の順序を設計します。
- データ構造設計
- データをどう入れておくか、どう取り出すかを決める設計。検索・追加・削除などの操作を効率よく行える構造を選びます。
- モジュール設計
- 機能を独立した部品(モジュール)に分け、再利用と保守をしやすくする設計。
- オブジェクト指向設計
- 現実世界のモノをオブジェクトとして捉え、クラスとオブジェクトの関係で設計します。
- クラス設計
- 属性(データ)と振る舞い(メソッド)を1つの設計単位として決め、責任を分離します。
- デザインパターン
- よくある設計課題に対する再利用可能な解決策の集まり。
- API設計
- 外部のプログラムが使う入り口(API)を、使いやすく、拡張しやすいように決めます。
- インターフェース設計
- モジュール同士の接続点をどう定義するかを決める。入力と出力、依存関係を整理します。
- アーキテクチャ設計
- システム全体の構造(どの部品をどう組み合わせるか)を決める大枠の設計です。
- レイヤー設計
- 機能を層に分け、それぞれの層が責務をもち、他の層とどうやり取りするかを決めます。
- 要件定義と仕様設計
- 何を作るかの要件を決め、それをどう実現するかを仕様として具体化します。
- 非機能要件設計
- 性能・セキュリティ・信頼性・保守性など、機能以外の要件を設計します。
- テスト設計
- どんなテストを実施するか計画を立て、品質を担保する設計作業です。
- ユースケース分析
- 利用者の視点で、システムがどう動くべきかを具体的な場面で整理します。
- 拡張性設計
- 将来の機能追加を想定して、変更に強い構造を作る設計。
- 保守性設計
- 長く運用しても修正・追加がしやすいように、コードの読みやすさとモジュール化を重視します。
- パフォーマンス設計
- 処理の速さやリソースの使用量を考えて、無駄を省く設計。
- セキュリティ設計
- 悪意あるアクセスを防ぐための設計。認証・権限・データ保護などを含みます。
プログラム設計のおすすめ参考サイト
- プログラム設計のコツとは? - 株式会社システムインテグレータ
- プログラム設計書とは?役割や書き方を詳しく解説【サンプル付き】
- プログラム設計とは?意味を分かりやすく解説 - IT用語辞典 e-Words
- プログラミングとは? 小学生の子どもに簡単に説明するためには?
- プログラム設計とは?意味を分かりやすく解説 - IT用語辞典 e-Words
- プログラム設計書とは?役割や書き方を詳しく解説【サンプル付き】
- プログラム設計とは?初心者でもわかる5つの基本ステップ
- 設計とはなんだ? #プログラミング初心者 - Qiita
- プログラム設計書とは?必要性や他設計書との違い【2025年最新版】



















