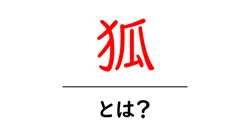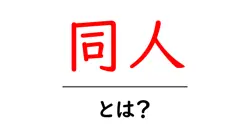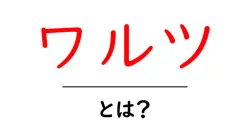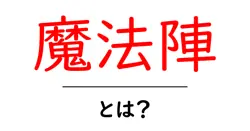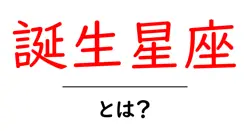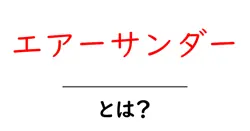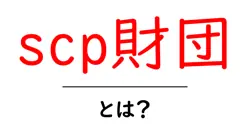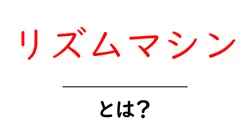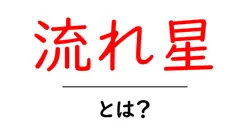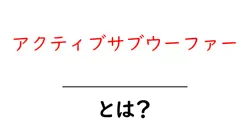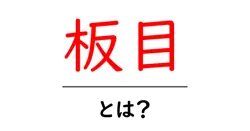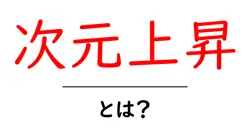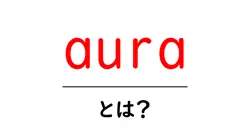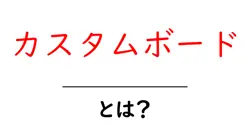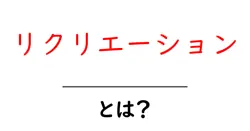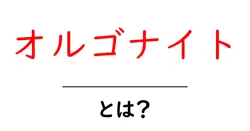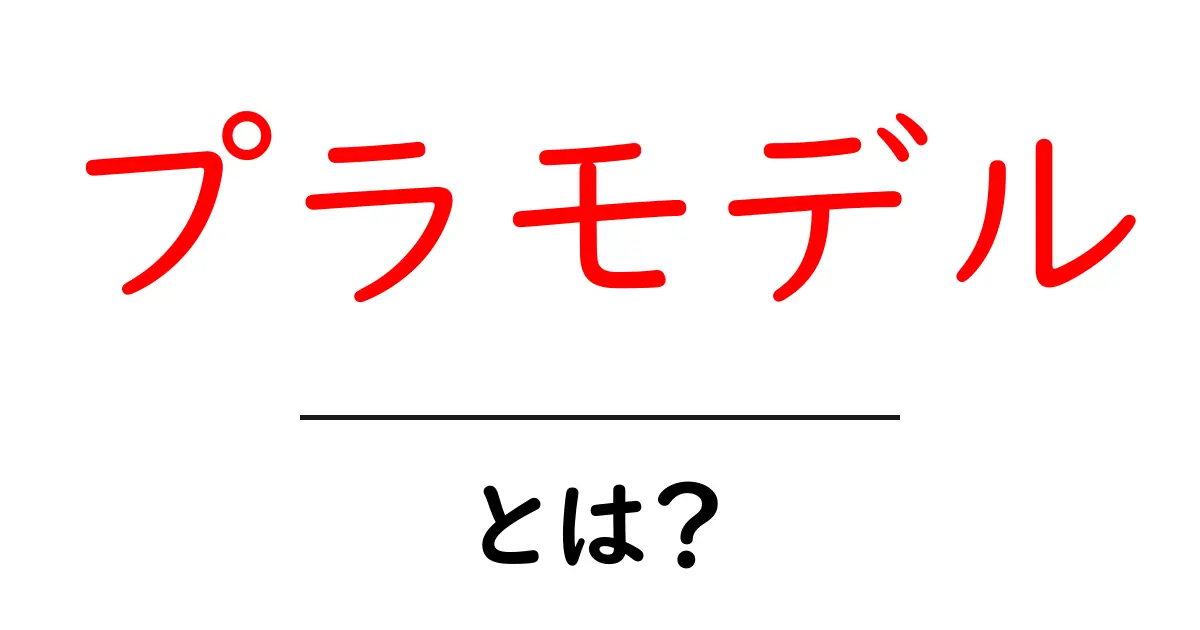

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
はじめに
プラモデルとは、プラスチック製の部品をはめあわせて完成させる模型のことです。正式には「プラスチックモデル」と呼ばれ、模型の世界で長い歴史を持ちます。最近では子どもだけでなく大人にも人気で、趣味として広く楽しまれています。
この記事では、プラモデルとは何か、どんな kit があるのか、初めて作るときのコツ、必要な道具、組み立てと塗装の基本手順を、初心者にもわかりやすい言葉で紹介します。
1. プラモデルの基本用語
スケールとは、実物とモデルの大きさの比のことです。よく使われるのは 1/144、1/72、1/48 など。数字が小さいほど大きく作ることを意味します。
キットは完成品のもとになる部品セットのこと。プラモデルにはいくつかの難易度やジャンルがあり、初心者は入門用の kit から始めると良いです。
2. 初心者が知っておくべき基本道具
基本道具は、ニッパー、小刀、ヤスリ、接着剤、塗料セット、筆、サーフェイサー(下地剤)、トップコートです。これらを揃えると作業がスムーズになります。
道具は高価でなくても大丈夫です。初心者向けのセットも販売されており、まずは最低限のものから揚せると良いです。
3. 作り方の基本ステップ
以下のステップは多くのプラモデルに共通します。
初心者は最初から完璧を目指さず、少しずつ段階を踏むのが大切です。焦らず、部品の位置を確かめながら進めましょう。
4. 安全と楽しさのコツ
作業中は 換気をよくし、 手袋を使う場面もあります。小さなパーツを飲み込まないよう、子どもの手の届かない場所で作業しましょう。
プラモデルの魅力は完成したときの達成感と、部品一つひとつを組み合わせていく創造性にあります。完成した作品は飾ることができますし、友人と作り方を共有する楽しさもあります。
5. まとめ
プラモデルは、部品を切り出し、整形し、接着、塗装、仕上げと段階的に作る模型です。初心者は入門キットから始め、道具を少しずつ揃え、基本ステップを確実にこなすことで、スキルを着実に伸ばせます。
ぜひ自分の好きなジャンルのプラモデルを選んで、楽しく作ってみてください。分からないことがあれば、ショップのスタッフやオンラインの解説記事を参考にすると良いでしょう。
6. 歴史とジャンル
プラモデルは1960年代ごろに普及し始め、日本では初期のブランドとして タミヤ や 童友社 などが知られています。現在では機械や乗り物だけでなく、アニメ作品のキャラクターを再現した キャラクターモデル や、ミリタリーモデル、艦船、航空機など多岐にわたります。
主なジャンルには、車・オートモビル、戦車・軍事、飛行機、艦船、ロボット、キャラクター(アニメ・映画のキャラクター)などが挙げられます。自分の好きなジャンルを見つけて取り組むと、学習意欲が高まります。
7. 練習用のコツと追加 tips
上達のコツは、丁寧に少しずつ進めることと、道具の使い方を覚えることです。初めは部品を丁寧に切り離し、接着後のはみ出しを拭く練習を重ねましょう。塗装は薄く何度も重ね塗りを行います。デカールは水につけて柔らかくしてから、スコッチのような綿棒で優しくなじませます。
安全面では、作業中は換気をよくし、ニッパーやカッターを使うときは手元に気をつけることが大切です。子どもだけでなく大人も無理をせず、休憩を挟みながら進めましょう。
最後に、完成品を写真に撮って友だちと共有することで、モチベーションが上がります。自分の作品を紹介する場所として、オンラインのコミュニティも活用できます。
プラモデルの関連サジェスト解説
- プラモデル ヒケ とは
- プラモデル ヒケ とは、プラモデルの部品表面にできる凹みのことです。ヒケは英語で sink marks と呼ばれ、樹脂が固まるときの冷却・収縮の差によって表面がへこんでしまう現象を指します。特に部品の厚みが厚い部分や複雑な形状の境目、型の取り方の影響を受けやすく、小さな凹みから大きな平滑性を損なう線状の変化まで現れます。部品を塗装する前の段階で光を当てて図ると、ヒケが見つけやすいです。なぜ起こるのかというと、主に厚みの不均一、型の構造的な影響、そして保管・取り扱いによる樹脂の水分や温度変化が原因です。厚い部分は冷却が遅く、周囲の薄い部分との収縮差が大きくなるため凹みができやすくなります。さらに型の設計上の癖や、部品の気泡・薄すぎる肉厚の境界部でもヒケが出やすいです。水分を含んだ樹脂を使うと、乾燥後の収縮でヒケが目立つこともあります。対策としては、実際の作業で厚みを均一にする工夫が大切です。パーツ分割の際に薄い部分を増やす、凸部を埋める、薄い箇所を作るなど設計段階での対策も有効です。組み立て後にヒケが出やすい部分は、プラ用パテや瞬間接着剤パテで埋めて平滑にします。平面を作るためには、サフを吹く前に軽くヤスリがけをして表面を均一に整え、サフを吹いてヒケを再確認します。サフ後に再度パテ処理をして、最後にもう一度ヤスリがけとサフを行うと、目立たなくなります。完成後の塗装を美しく仕上げるには、ヒケを早めに見つけて適切に処理することが大切です。初心者の方は、一度に完璧を狙わず、段階を踏みながら練習するのがおすすめです。
- プラモデル 素組み とは
- プラモデル 素組み とは、塗装やデカール貼りなどの仕上げを一切行わず、パーツを組み立てだけで完成させる作業のことです。素組みは初心者がプラモデルの基本を理解するのに最適で、部品のかたちや接合のしくみを実感できます。作業を始める前に、パーツごとに分ける説明書を手元に置き、順番を確認しましょう。作業の流れはおおむね次のとおりです。1) パーツを説明書どおりに分ける 2) ゲートと呼ばれる余分な部分をニッパーやカッターで丁寧に除去する 3) 表面を軽くヤスリがけして滑らかにする 4) パーツを組み合わせて仮組みをして位置合わせする 5) すぐに固定が必要な箇所は接着剤で接着する 6) 完成後は必要に応じて軽く拭き取り、仕上げの塗装は省くか最小限にする素組みで用意しておきたい道具は、基本のニッパー、カッター、ヤスリまたは紙やすり、ピンセット、接着剤(必要な場合)、説明書を見やすくする透明テープなどです。作業中はパーツを紛失しないように小さなケースに分け、作業ゾーンを整理してから始めましょう。素組みのメリットは、完成までの時間が短く、破損のリスクが比較的低い点です。コストも抑えられ、構造の理解が深まります。一方でデメリットとして、塗装やデカールを使わない分、色味の再現性が低かったり、隙間が目立ちやすい点が挙げられます。初心者がつまずきやすいポイントとコツは、説明書の順番を守ること、部品同士をしっかり合わせること、接着剤は少量をムラなく塗布することです。慣れてきたら少しずつ塗装や仕上げに挑戦して、素組みの上達を楽しみましょう。
- プラモデル 依存症 とは
- プラモデルは小さな部品を組み立てて完成させる趣味です。楽しく取り組む分には良いのですが、作業が長時間に及び日常生活に支障を感じると依存症のような状態に近づくことがあります。ここではプラモデル 依存症 とは何かを中学生にもわかる言葉で解説し、サインの見分け方と健全に楽しむコツを紹介します。まず、依存症の基本は自分の意思だけでは適切に管理できなくなることです。プラモデルの場合は、完成の喜びや収集欲、他の人と作る充実感などが強く働きすぎて、睡眠不足や学業・部活の時間が削られることがあります。具体的なサインとしては、作業を止められず日常の予定を度々変更する、予算を超えて材料を買い続ける、部屋が部品や工具で散らかり整理ができない、友だちとの約束を断ってまで作業を続ける、などが挙げられます。こうした状態が続くとストレスや体調不良、学校の成績や人間関係の悪化につながることもあります。では、どうすれば健全に楽しめるでしょうか。まず自分の時間と予算の上限を決めることが大切です。1週間で使えるお小遣いの範囲や、制作に使う時間をあらかじめ決めておくと良いでしょう。次に、作業と休憩のバランスをとるためのルールを作ること。例えば1日1時間まで、月に1つのキットだけ買うなど現実的で守りやすい決まりを設けます。また、ほかの趣味や運動、友だちとの時間も意識して確保することが大切です。家族や友人にも自分の状況を伝え、困ったときに相談できる体制を作りましょう。もし自分でコントロールできないと感じたら学校の相談員や医療の専門家に相談することも選択肢です。健全に楽しむコツとしては、完成までの道のりを楽しむこと、完成品を人に自慢するより自分の成長を喜ぶこと、部品の保管を整頓することなどを挙げられます。 このような視点を持つことでプラモデルを長く、健康的に楽しむことができます。趣味は心を豊かにしてくれる大切な時間ですから、適切な距離感と計画を持って取り組みましょう。
- プラモデル トップコート とは
- プラモデルの仕上げで重要な役割を果たすのがトップコートです。プラモデル トップコート とは、模型の表面に塗る透明な保護塗膜のことを指します。塗装後の色を長くきれいに保ち、デカールの定着を助け、傷や埃から塗膜を守ります。仕上がりの雰囲気を決める大切な要素でもあり、光沢、半光沢、つや消しの三つのタイプがあります。光沢は色を鮮やかに見せ、写真映えも良くなりますが、指紋や埃が目立ちやすいことがあります。つや消しは落ち着いた印象で、汚し表現にも向いており、戦車や軍用車などに人気です。半光沢は光沢とつや消しの中間で、使い勝手がいいと感じる人が多いです。スプレー式は均一に塗れるのが魅力で、初心者にもおすすめです。筆塗りは細部の周囲や小さな部品に使いやすく、スプレーが苦手な人に向いています。作業前には表面をよく乾燥させ、埃がない状態で塗布を始めましょう。通常は薄く一層塗り、乾燥後に必要であればさらに薄く重ね塗りをします。デカールの上からトップコートを塗ると、デカールの境界が馴染み、剥がれにくくなる効果が期待できます。乾燥時間は温度や湿度によって変わりますが、一般的には室温で数時間程度を目安にします。厚塗りはひび割れや剥がれの原因になりやすいので、薄く重ねる方法を心がけましょう。安全面では換気の良い場所で作業し、マスクを着用することをおすすめします。初めての人は、テスト用の小さな部品で塗り感を確認すると良いでしょう。
- プラモデル 中古 とは
- プラモデル 中古 とは、既に誰かが所有していたプラモデルのことを指します。新品と比べて箱の開封状況、部品の欠品、組み立て済みかどうか、塗装の痕跡などが異なります。中古品には未開封の状態のものもありますが、多くは開封済みや箱が傷んでいるケースが多く、完成品のようにそのまま使えるとは限りません。中古の利点は価格が安い点ですが、デメリットとしてはパーツ欠品や摩耗、デカールの使用不可などが挙げられます。選び方のコツは、まず自分が作ろうとしているキットがどの程度組み立てられる状態かを想定することです。未組立ての中古品なら新品同様の感触を期待できますが、箱や説明書が欠品していることがあります。購入前に写真でランナーやパーツの欠品・破損を確認し、部品番号が揃っているか、説明書が揃っているかをチェックしましょう。特にデカールが付属しているか、箱の状態は湿気や日焼けの痕がないかも大事なポイントです。製造年が古いキットは色味や部品の彫りが現代のモデルと異なることがあり、現代の塗装方法で再現するには追加の作業が必要になる場合があります。価格は新品より安く設定されていることが多いですが、状態が悪い場合はさらに安くなることがあります。購入先としては中古プラモ専門店や模型ショップの中古コーナー、オンラインのフリマやオークション、メルカリやヤフオクなどが利用できます。写真だけで判断せず、可能であれば出品者に状態を詳しく質問し、欠品の有無、箱の状態、デカールの有無、パーツの欠け・破損がないかを確認しましょう。受け取り後のケアとしては、湿気を避け、直射日光を避け、保管は箱やケースに入れるのがおすすめです。中古品をうまく活用すると、コストを抑えつつコレクションを増やせますが、最終的には自分の作るスケール感や完成度に影響する要素もあるため、事前の情報収集と現物確認を徹底しましょう。
- プラモデル デカール とは
- このページでは、プラモデル デカール とは何かを分かりやすく解説します。デカールとは、プラモデルの表面に貼って細かな模様や文字を再現する薄い紙やシートのことです。小さな文字や軍用機の番号、車両の insignia など、塗装だけでは難しい細部をきれいに表現できます。デカールには主に水転写デカールと転写デカール(ドライデカール)の二種類があります。水転写デカールは水に浸して裏紙を剥がし、湿った紙ごと模型の表面へ滑らせて固定します。転写デカールは裏紙を剥がして直接貼り付け、専用の道具でこすって密着させます。
- プラモデル バリ とは
- プラモデル バリ とは、プラモデルの成形品に残る余分な樹脂の突起のことです。金型で作るときの型の縁やゲート付近に薄く尖った部分が生じやすく、それをバリと呼びます。バリは見た目にも触感にも影響し、パーツの組み立てを妨げたり、接着面の隙間を増やしたりする原因になります。塗装前の下処理が不十分だと塗膜がはがれやすくなることもあるため、初心者にも重要なポイントです。バリの多くは触ると引っかかったり、パーツの表面に傷をつけやすいため、慎重な作業が必要です。発生場所はパーツのゲート周りや分割ライン近く、角の尖った部分などで、裏側にも目立つことがあります。対策としてはまずバリの場所を確認し、適切な道具を選ぶことが大切です。基本的な道具にはプラモデル用のニッパー、デザインナイフ、紙ヤスリが挙げられます。バリ取りの手順は、1) バリの位置を確認して傷つける箇所を避けながら、2) ニッパーでバリを根元ごと慎重に切り取る、またはナイフで薄く削って浮きを取る、3) 刃を傷つけないように平行に少しずつ削る、4) 仕上げとして紙ヤスリや細目の耐水ヤスリで表面を滑らかに整える、5) 設置前にパーツを少し触ってバリがないか再確認する、という流れがおすすめです。深いバリや角のバリには小さなやすりや細い棒状ツールを使うと安全で、塗装前には表面の油分を落とす脱脂も忘れずに行いましょう。初めての場合は力を入れすぎず、パーツの強度を守ることが大切です。正しくバリを取り除くことで、組み立てがスムーズになり、後の塗装もきれいに決まりやすくなります。
- ランナー プラモデル とは
- ランナー プラモデル とは何かを、初心者にもわかりやすく解説します。プラモデルは、薄いプラスチックの板に小さな部品がついた“ランナー”と呼ばれる枠から部品を切り離して組み立てる模型です。ランナーは英語で sprue(スプルー)といい、部品はこの枠の上に並んでいます。部品を切り離す際には、切り口にゲートと呼ばれる余分な直線が残ることがあり、これをやすりやナイフで整える作業が必要です。そうすることで、つなぎ目や段差が少なくなり、完成品がきれいになります。作業の流れは大まかに次のとおりです。1) 作るモデルを決める。2) 説明書を読んで必要な部品を把握する。3) ランナーから部品を慎重に切り離す。4) ゲート処理をする。5) パーツを組み立て、接着剤で固定する。6) 細かい仕上げや塗装、デカール貼りなどを行う。ランナーには色が付いている場合が多く、素組み(組み立てだけ)で完成させる人もいます。色分けされた成形色を活かして塗装を最小限にする“ノン塗装”の方法も人気です。初めは簡単なキットから始めると良いでしょう。道具も大切です。おすすめは、部品を傷つけず切り離すためのニッパー、やすり、ピンセット、接着剤、そして必要なら塗装工具です。安全のため、カット時は手を切らないように注意してください。このようにランナー プラモデル とは、部品がランナーに連なっている形の模型を指し、組み立てのプロセスが全体としての体験になります。練習を重ねると、難しいキットにも挑戦できるようになり、完成の達成感を味わえます。
- 30mm プラモデル とは
- 30mm プラモデル とは、小さめのプラスチック製の組み立てキットのことを指します。完成時の身長が約30ミリ程度になることが多く、手のひらサイズのミニチュアとして楽しむ人が多いです。主にテーブルトップのミニチュアゲーム用に使われることが多く、ガンプラのような大きなスケール模型とは別の楽しみ方ができます。部品はスプリットされた小さなパーツの集合で、箱に入っている説明書の順番に沿って組み立てます。最近は素組み(色を塗らずに作る方法)や、カラーキット(最初から色が塗られているキット)など、初心者にも入りやすいタイプが増えています。作業の流れはおおむね次の通りです。箱の中身を確認し、部品のゲート跡をニッパーで切り落としてから、ヤスリや紙やすりで滑らかに整えます。次に説明書の順番に従い、接着剤を使って少しずつ組み立てます。塗装をする場合は、サーフェイサー(下地を整える塗装前の下地剤)を吹いてから、好みの色を塗ります。塗装は筆塗りでもエアブラシでもよく、デカールを使う場合は水転写デカールの扱い方を守りましょう。完成後にはトップコートで仕上げをして、傷や汚れを再現するウェザリングにも挑戦できます。道具の基本は、ニッパー、ヤスリ、筆、塗料、プライマー、トップコート、必要に応じてデカール用のセッティング液などです。最近はスナップフィット型のキットも増えており、接着剤を使わずに組み立てられるものもあります。自分の好きなキャラクターや車両を選ぶと続けやすいです。初心者のコツは、最初は小さめのキットで作業に慣れること、道具をそろえすぎず、手頃なキットから始めることです。小さな部品を扱うので、ピンセットを使いこなすと作業が楽になります。安全面では、小さな部品は誤飲の危険があるため、子どもと作る場合は大人の監督が必要です。作業中は換気を良くし、刃物を使う時は手を切らないように注意しましょう。
プラモデルの同意語
- プラモ
- プラモデルの略称。日常会話で最もよく使われる呼び方で、プラスチック製の模型キットを指します。
- プラスチックモデル
- 材料がプラスチックで作られた模型の総称。組み立て式の模型キットを指す用語として広く使われます。
- プラスチック製模型
- プラスチックで作られた模型のことを表す表現。特にキット化された“プラモデル”を指す場合に用いられます。
- プラスチック模型
- 材料がプラスチックの模型。文脈によってはプラモデル全般を指すことがあります。
- 模型キット
- 完成させるための部品と説明書がセットになった“模型のキット”。プラモデルを指す最も一般的な同義表現のひとつです。
- 組立キット
- 組み立てて完成させるタイプのキット全般を指す語。プラモデルの文脈でも頻繁に使われます。
- 組立式模型
- 組み立てて作るタイプの模型を指す表現。プラモデルの説明文などで見られます。
- モデルキット
- 英語の Model Kit の日本語表現。プラモデルの別称として使われます。
- プラモデルキット
- プラモデルの部品と説明書がセットになったキットのこと。プラモデル特有の呼び名です。
- プラスチックモデルキット
- 材料がプラスチックのモデルキットの正式な表現。商品名やカタログでよく見かけます。
プラモデルの対義語・反対語
- 木製モデル
- 材料が木材の模型のこと。プラモデルの主材料であるプラスチックと対比して使われるイメージです。
- 紙模型
- 紙を主材料とした模型のこと。プラモデル(プラスチック製)に対する別素材の対義語としてよく挙げられます。
- 金属模型
- 金属を主体として作られた模型のこと。素材の違いを意識した対義語です。
- 完成品
- 組み立て済みで完成している模型のこと。キットとしての未組立を反対に捉えた表現です。
- 手作り模型
- キットを使わず自作・自組みで作る模型のこと。既製キット(プラモデル)と対立するニュアンスがあります。
- 布製模型
- 布素材の模型のこと。硬質素材のプラモデルの対義語として挙げられます。
- 段ボール模型
- 段ボールなどの紙を素材にした模型のこと。素材の違いを表す対義語のひとつです。
- 3Dプリント模型
- 3Dプリンタで作られた模型のこと。製作方法がプラモデルと異なる対義語として挙げられます。
プラモデルの共起語
- 組み立て
- 部品を組み合わせて模型を完成させる作業のこと
- 接着剤
- パーツを固定するための糊。瞬間接着剤やエポキシ系などがある
- ニッパー
- ランナーから部品を切り離す専用工具
- デカール
- 車両・キャラクターの細かい模様を貼る薄いシール状の図案
- デカール貼り
- デカールを展開させ、位置決めして定着させる作業
- ゲート処理
- ランナーの薄い溝を切り離す前後の処理全般
- ヤスリ
- パーツのバリ取りや表面を滑らかに整えるための削り道具
- バリ取り
- ゲートや成形後に出る突起を削って整える作業
- サーフェイサー
- 下地を均一に整える塗装前の下地剤
- 下地処理
- 塗装前に表面を整える一連の作業
- 塗装
- 部品に色を塗る作業
- エアブラシ
- 細かな塗装を吹き付ける道具
- 塗料
- 模型用の塗料。アクリル・ラッカー・水性などがある
- 水性塗料
- 水で薄めて使う塗料。初心者にも扱いやすい
- アクリル塗料
- 水性系の塗料の代表。匂いが控えめで扱いやすい
- ラッカー塗料
- 溶剤系の塗料。乾燥が速いが取り扱い注意
- パテ
- 隙間や段差を埋める充填材
- マスキングテープ
- 色を塗り分ける際の保護用テープ
- マスキング
- 塗り分けの工程全般
- トップコート
- 仕上げのコーティング。ツヤの有無を選ぶ
- つや消し
- 光沢を抑えた仕上げ
- 半光沢
- 中間の光沢感
- ツヤあり
- 高い光沢の仕上げ
- スミ入れ
- 凹凸の陰影を強調する塗装技法
- ウェザリング
- 汚れや風化を再現する技法
- 塗装レシピ
- 色の組み合わせや手順のガイド
- パーツ分割
- キット内の部品の分割状態
- ランナー
- 部品が入っている枠。切り離して使う
- 成形色
- 部品に元から塗られている色
- 表面処理
- 表面を整える全般の作業
- 箱絵
- 箱の外箱に描かれた完成予想図
- パッケージ
- キットの外箱・包装
- 完成品
- 組み立て・塗装を終えた最終形
- ディスプレイ
- 展示・見せ方を工夫すること
- ディスプレイケース
- 完成品を飾る専用ケース
- 改造
- 公式キットを自分好みに改変すること
- ガンプラ
- ガンダムのプラモデルを指す総称
- 保管
- 完成品や部品の保存方法
- ピンセット
- 細かな部品を扱う精密工具
- 筆
- 細部を塗る模型用筆
- 接着剤の種類
- 用途に応じて選ぶ接着剤のカテゴリー
プラモデルの関連用語
- プラモデル
- プラスチック素材の組み立て式模型の総称。ランナーと呼ばれる枠にパーツが分割され、切り離して組み立て、塗装やデカールで仕上げる趣味の対象。
- ランナー
- パーツが取り付けられているプラスチックの枠。部品を切り離して使います。
- ゲート
- ランナーとパーツを結ぶ入口の樹脂。切り離した後はヤスリで整えます。
- 合わせ目
- 組み立てたときにできる、パーツとパーツの境目の段差のこと。
- 合わせ目消し
- 接合部の段差をパテや溶着材で埋め、塗装の前に滑らかに整える作業。
- パテ
- 合わせ目や傷を埋める充填材。ポリパテやエポパテなど。
- 接着剤
- パーツを固定するための専用の粘着剤。プラモデル用が一般的。
- 瞬間接着剤
- 速乾性の接着剤。小さな部品の仮止めにも使われます。
- サーフェイサー
- 下地剤。塗装の密着を良くし、表面を均一に整える。
- 下地処理
- 塗装前の前処理全般。表面を平滑にし、塗膜の定着を高める作業。
- 塗装
- 色を塗る作業。筆塗り、エアブラシ、スプレーなどの方法があります。
- エアブラシ
- エアを使って薄く塗装する道具。細かな色分けに向く。
- 筆塗り
- 筆を使って塗装する方法。手軽で初心者にも適していることが多い。
- マスキング
- 塗り分けたい部分を保護する養生作業。マスキングテープやマスキングシートを使います。
- デカール
- 水転写デカールなど。図柄を貼り付けて細かな表現を再現します。
- デカール処理
- デカールを貼った後の段差を整え、定着させ、トップコート前の仕上げを行います。
- トップコート
- 完成後の透明な保護膜。ツヤ有り・半光沢・マットなど、仕上がりの質感を決めます。
- ツヤ有りトップコート
- 透明な保護膜で光沢感を出すトップコート。高光沢の仕上がりになります。
- 半光沢トップコート
- 光沢を抑えたトップコート。落ち着いた質感になります。
- マットトップコート
- 光を抑えたマット仕上げのトップコート。艶を消してリアルな質感にします。
- ウェザリング
- 実車の使用感や汚れ、錆、陰影を表現する技法。
- ウェザリングカラー
- ウェザリング用の塗料。油性・水性・溶剤系などがある。
- スミ入れ
- 陰影を強調するため、溝や彫りに薄い色を流して定着させる技法。
- スミ入れ用塗料
- スミ入れに適した暗い色の塗料。
- 養生シール
- 塗装中に特定の部分を保護するためのシール。
- ゲート処理
- ゲート跡を削り取って、表面を整える作業。
- 1/144
- 小型スケールの代表。主に戦闘機やガンダムのキットで頻出。
- 1/100
- 中型スケール。ガンプラの大型キットにも多い。
- スケール
- 現実の大きさと模型の大きさの比。例: 1/144、1/100、1/48 など。
- タミヤ
- 日本の老舗模型メーカー。プラモデルの定番ブランドを多数展開。
- ハセガワ
- 日本の模型メーカー。高品質でデカールが充実している。
- フジミ
- 日本の模型メーカー。コストパフォーマンスと実用性が特徴。
- エデュアルド
- 海外系のプラモデルメーカー。エッチングパーツやデカールも扱う。
- ミニアート
- 海外の模型メーカー。細密パーツやディテールが特徴。
プラモデルのおすすめ参考サイト
- プラモとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書
- プラモデル (ぷらもでる)とは【ピクシブ百科事典】 - pixiv
- バンダイホビーのプラモデルとは?
- プラモデルとは? 意味や使い方 - コトバンク
- プラモとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書