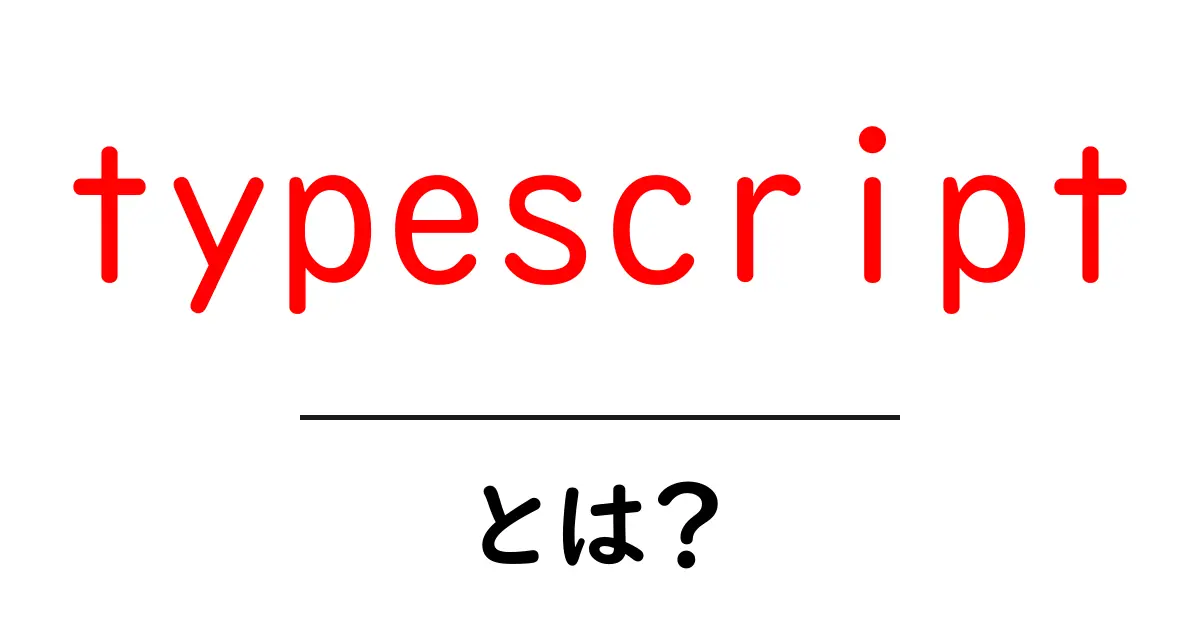

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
typescriptとは?
このページでは typescript とは何か、なぜ使われるのか、初心者が知っておくべき基本を中学生にも分かる言葉で解説します。typescript は javascript の進化版と言われることが多く、厳密には javascript の拡張言語です。つまり javascript の書き方をそのまま活かしつつ、型というルールを追加してくれます。
まず結論から言うと 型を使うことでバグを減らし、コードの意味を自分でも他の人でも理解しやすくします。typescript を使う人は 主に三つのメリットを得られます。第一に 型の安全性が高まり runtime でのエラーを減らせること。第二に エディタの補完機能が賢くなり、どんな値を渡せばよいのかを教えてくれます。第三に チーム開発で共通の約束事を守りやすくなることです。
typescript の基本的な考え方
typescript は javascript のコードをそのまま動かすことができます。もし型を付け忘れていたり不適切な型の値を使おうとすると、コンパイル時に警告やエラーを出してくれます。ここでいうコンパイルとは ts ファイルを実行可能な javascript に変換する作業のことです。変換された javascript はどの環境でも動かせます。
よく使われる型と宣言の仕方
基本的な型には number や string や boolean などがあります。例として次のように書きます。 ここでは説明だけをしていますので実際のコードは覚えておく程度で大丈夫です。 age は number 型で 15 を設定します。 name は string 型で 太郎 という文字列を設定します。
インターフェースと型エイリアス
オブジェクトの形を定義するには interface や type を使います。 interface Person { name: string; age: number; } のように書くと、この Person という型のオブジェクトは name が文字列、 age が数値であるという約束になります。型エイリアスは複雑な型を一つの名前にまとめるのに便利です。
ジェネリクスと型推論
ジェネリクスは型を後から決める仕組みです。関数やクラスで使うと、使う側の型に合わせた型で動きます。型推論は型を明示せずに変数を宣言しても、 TypeScript が自動的に型を決めてくれる機能です。これらはコードを安全に保ちながら書きやすくする大きな助けになります。
コンパイルと設定ファイル
typescript を使うにはまずパソコンに node を入れ、プロジェクトで typescript を開発依存として追加します。次に tsconfig.json という設定ファイルを作ることで、どのファイルを変換するか、どのように変換するかを細かく決められます。設定は初期設定のままでも動きますが、エディタの補完をさらに良くするには適切な設定を追加します。
実務での使い方のヒント
小さなプロジェクトから始め、徐々に型を増やしていくのがコツです。最初は any 型を使っても動きますが、徐々に型を限定していくと安心してコードを読めるようになります。またエディタの提案を活用して型の安全性を高めましょう。
typescript とエディタ
現在の主要なエディタには TypeScript のサポートが組み込まれており、補完機能やエラーチェックが非常に強力です。これにより学習の過程で躓くポイントを早く見つけられます。
比較表: javascript と typescript
まとめ
typescript は javascript の力を借りつつ、より安全で読みやすいコードを書くための道具です。最初は難しく感じるかもしれませんが、基本を知るだけでも日常の開発で役立ちます。学習を続けると、型のおかげでコードの意味がすぐに伝わるようになり、チーム開発でもミスを減らせます。
typescriptの関連サジェスト解説
- typescript とはわかりやすく
- typescript とはわかりやすく解説します。TypeScriptは、JavaScriptの上に作られた言語で、コードに型をつけることができます。型とは、変数にどんなデータが入るかを教えてくれる仕組みです。例えば、年齢は数値、名前は文字列といった具合です。型があると、間違いをコンピュータが事前に教えてくれるので、あとで見つけづらいバグを減らせます。さらに、エディタの補完機能が強くなり、コーディングがスムーズになります。使い方のイメージとしては、JavaScriptのコードを書いて、TypeScriptで型をつけてから、最終的にはJavaScriptに変換します。これを「コンパイル」といいます。実行環境は変わらず、ブラウザやNode.jsで動かせます。なぜ使うのかというと、チームでの開発で型があると他の人の意図が読み取りやすく、共同作業が楽になります。大規模なプロジェクトでは、型宣言があるとリファクタリングも安全になります。基本の使い方は、まず自分のプロジェクトにTypeScriptを導入して、拡張子を .ts にします。簡単な例として、 let name: string = '花子'; function greet(n: string): string { return 'こんにちは ' + n; } というコードを書いて練習します。tsconfig.jsonという設定ファイルで、コンパイラの挙動を調整します。小さなプロジェクトから始め、徐々に設定を覚えるとよいです。
- typescript とは qiita
- この記事のテーマは、typescript とは qiita というキーワードの意味と使い方を、初心者にもわかるように解説することです。まず、TypeScript とは何かをかんたんに説明します。TypeScript は JavaScript の“型が使える版”です。難しく聞こえるかもしれませんが、要は「値の型」を決めておくと、あとで間違いを見つけやすくなり、コードの保守がしやすくなります。TypeScript はコンパイルという作業を通じて、書いたコードを JavaScript に変換します。実行する環境は JavaScript と同じでも、TypeScript の型チェックのおかげでデバッグが楽になります。次に Qiita というサイトについてです。Qiita は日本のエンジニアが知識を共有する場所で、記事、サンプルコード、質問と回答などが集まっています。「typescript とは qiita」というキーワードを使って検索すると、TypeScript の基礎から実践的な使い方まで、さまざまな記事が見つかります。初心者向けの記事を選ぶと、型の組み方、関数の書き方、クラスの使い方などの基礎を丁寧に学べます。最後に、検索のコツです。まず短い説明や用途を知りたいときは、初心者向けの解説を探しましょう。次に実際のコードが載っている例記事を選ぶと手を動かしやすくなります。もし英語記事が混ざっていても、日本語の解説と併せて読むと理解が深まります。この記事のように「typescript とは qiita」というキーワードを使えば、Qiita での学習をスムーズに始められます。
- typescript + swc とは
- typescript + swc とは、TypeScriptのコードを高速にJavaScriptへ変換してくれる組み合わせのことです。TypeScriptはJavaScriptに型を追加した言語で、変数の型を決めることで間違いを減らし、後からコードを読みやすくします。一方、SWCはRustで作られたとても速いコンパイラ/トランスパイラです。JavaScriptやTypeScriptを従来より速く出力できるのが特徴です。つまり、typescript + swc とは、TypeScriptをSWCで変換してビルド時間を短くする方法という意味になります。ビルド速度を速くしたい大規模プロジェクトで特に効果を発揮します。 使い方の基本は次の通りです。まず必要なパッケージを開発依存として追加します(例:@swc/core、@swc/cli、@swc/preset-typescriptなど)。次に.swcrcなどの設定ファイルを用意するか、コマンドラインで設定を渡します。最後にビルドコマンドを実行して、src の.tsや.tsxを dist などの出力先へ出力します。SWCを使うメリットは、ビルドが速い点と設定が比較的シンプルな点です。特に大規模なコードベースや頻繁に変更があるプロジェクトで体感しやすいでしょう。一方で注意点として、SWCはデフォルトで型チェックを行わないため、型の検査を厳密に行いたい場合は別途TypeScriptの型チェック(tsc)を走らせる必要があります。Next.jsなどのモダンなフレームワークは内部でSWCを使っていることが多く、設定を最小限にして速さを体感しやすい点も魅力です。
- typescript promise とは
- typescript promise とは、未来のどこかで結果が返ってくる約束のことです。JavaScript では時間のかかる処理をするときに、待つ間に他のことをできるようにするために Promise を使います。TypeScript はこの Promise に型情報を付けられるので、何が返ってくるのかを事前に決めておくことができます。例えば Promise
は、将来「文字列」が返されることを約束する型です。Promise には三つの状態があります。まだ結果が出ていない pending、結果が出て正しく返る fulfilled、何か問題があって失敗した rejected です。\n\n作り方です。新しい Promise を作るには new Promise((resolve, reject) => { ... }) を使います。例: function fetchData(): Promise { return new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(() => { const ok = true; if (ok) resolve('データです'); else reject(new Error('データ取得失敗')); }, 1000); }); }\n\n使い方は二通りです。then/catch で処理をつなぐ方法と、async/await を使う方法です。例: fetchData().then(data => console.log(data)).catch(err => console.error(err)); あるいは: async function main() { try { const data = await fetchData(); consoleログデータ; } catch (e) { console.error(e); } }\n\nポイントとして、TypeScript で型をつけるとエディタの補完が効きやすく、非同期処理を連続して書くときの可読性が上がります。ネストが深くなる「コールバック地獄」を避けられる点も大きいです。\n\n覚えておくべきことは、Promise は必ず解決か拒否のいずれかで終わるということです。呼び出し元は .then/.catch または await で結果を受け取り、エラーを適切に処理します。 - typescript interface とは
- typescript interface とは、オブジェクトの『形』を決める設計図です。JavaScript だけでは、変数がどんなデータを持つかを厳密に決められません。しかし TypeScript の interface を使うと、名前、型、メソッドの署名などを事前に定義でき、実際の値がその設計図に合っているかをコンパイル時にチェックしてくれます。基本的な書き方は次のとおりです。interface User { name: string; age?: number; }ここで age? はオプションプロパティ。つまり age がなくてもエラーになりません。この interface を使って変数の型を指定すると、間違いを早く見つけられます。例:interface User { name: string; age?: number; sayHi(): void; }const tom: User = { name: 'Tom', sayHi() { console.log('Hi'); } }もしモノが implements でクラスに取り入れられる場合は class が契約を守るかを確認します。class Player implements User { name: string; sayHi() { console.log('Hi ' + this.name); } }インターフェースは拡張もできます。interface Employee extends User { employeeId: number; }このように extends で複数の契約を組み合わせたり、クラス実装したりできます。注意点としては、型エイリアス(type)と混同しないこと。タイプはユニオン型などにも使え、インターフェースはオブジェクトの形を表すのに強い点が特徴です。また、インターフェースは複数回宣言して自動で結合される宣言のマージができる一方、type にはそれがありません。実務では、公開APIや関数の引数・戻り値の型を決めるときに積極的に使うのがオススメです。
- react typescript とは
- この記事では、react typescript とは何かを、中学生にも分かるように丁寧に解説します。まず、ReactはUIを作るための部品(コンポーネント)を組み合わせて画面を作る仕組みのことです。TypeScriptはJavaScriptに型を追加した言語で、データの型を決められるため、あとでエラーを見つけやすくなります。つまり react typescript とは、Reactの部品を作るときに TypeScript の型を使って、安全に開発することを指します。実際には、propsとstateの型を決めたり、関数の引数と戻り値の型を明確にしたりします。たとえば、部品へ渡す名前は string ですという宣言をしておくと、数値を渡してしまうミスを防げます。プロジェクトを始めるには、ファイル拡張子が .tsx となる React コンポーネントを書きます。新しいプロジェクトを作るときは Create React App や Vite などのテンプレートを TypeScript 版で選ぶと、tsconfig.json という設定ファイルが自動で作成され、型チェックの設定まで整います。簡単な例を見てみましょう。type GreetingProps = { name: string };function Greeting(props: GreetingProps) { return Hello, {props.name}!;}このように書くと、Greeting に渡す name は必ず string になることが保証されます。もし number を渡そうとするとエラーになります。React with TypeScript のメリットは、コードの安全性と保守性が高まること、IDEの補完が効いて気づきやすくなることです。デメリットとしては、学習コストが少し増える点や、小さなプロジェクトではオーバーヘッドに感じることもあります。しかし大規模なアプリや長く運用するサイトでは、バグを減らせる大きな味方になります。
- tsc とは typescript
- tsc とは TypeScript のコードを JavaScript に変換する「コンパイラ」のことです。TypeScript は JavaScript に型の仕組みを足した言語で、型を使うことでバグを早く見つけやすくなります。tsc はその TypeScript のコード(拡張子 .ts や .tsx)を、実際に動く JavaScript に変換してくれます。変換後の JavaScript は通常の Web ブラウザや Node.js で動作します。使い方の基本は次の通りです。まず npm を使って TypeScript をインストールします。グローバルにインストールする場合は「npm install -g typescript」、プロジェクト内だけに入れる場合は「npm install --save-dev typescript」を使います。次に tsconfig.json という設定ファイルを作ると、コンパイルの設定をまとめて管理できます。コマンドは「tsc」一発で現在のファイルをコンパイルしますし、ソースコードの変化を自動で監視して再コンパイルする「tsc -w」もよく使われます。新しいプロジェクトでは「tsc --init」で初期設定ファイルを作成すると便利です。実際には TypeScript で型を付けたファイルを作り、エラーを直してから「tsc」でコンパイルします。エラーが出ると、どの行のどの変数が原因かがわかりやすく表示され、バグを未然に防ぐ手助けになります。なぜ TypeScript が選ばれるかというと、大規模なアプリでも保守性が高く、IDE の補完機能やリファクタリングの安全性が向上するからです。学習の初期段階でも、まずは小さな TS ファイルを書いて tsc でコンパイルする手順を体験すると、TypeScript の利点をすぐに実感できます。
typescriptの同意語
- TypeScript
- JavaScript に静的型付けを導入した、Microsoft が開発したプログラミング言語。JavaScript のスーパーセットとして設計され、型チェックと高いツールサポートを提供します。
- TS
- TypeScript の略称。日常のコードや資料ではこの短縮形がよく使われます。
- TypeScript言語
- TypeScript の正式名称を指す表現。言語そのものを意味します。
- 型付きJavaScript
- JavaScript に型情報を追加する機能を持つ言語としての説明。TypeScript の特徴の代表例です。
- 静的型付きJavaScript
- TypeScript の特徴である静的型付けを強調した表現。実行前の型チェックを活かします。
- JavaScriptのスーパーセット
- TypeScript は JavaScript の機能をすべて含む“スーパーセット”として設計され、既存の JS コードと互換性があります。
- JavaScriptに型を追加する言語
- JavaScript に型情報を追加して、型安全性・保守性を高める目的の言語という説明です。
- 型定義付きJavaScript
- TypeScript は型定義ファイルを用いて型情報を提供する点が特徴。型定義付きJavaScriptとも言われます。
- 静的型付けJavaScriptの拡張
- JavaScript に静的型付けを追加する拡張言語として表現するときに使われます。
- TypeScriptの略語としてのTS
- 略称の TS を使って TypeScript のことを指す表現です。
- タイプスクリプト
- 日本語読みの表現の一つ。TypeScript の別表現として用いられることがあります。
- TypeScript(型付きJavaScriptのスーパーセット)
- TypeScript は型付き JavaScript のスーパーセットとして設計され、JavaScript の機能を拡張します。
- Microsoft製の型付きJavaScript拡張言語
- Microsoft が開発した、JavaScript に型を付ける拡張言語という説明です。
typescriptの対義語・反対語
- JavaScript
- TypeScriptの対義語としてよく挙げられる。型定義を前提とせず、動的型付けで動くスクリプト言語である。
- 動的型付け
- 実行時に値の型が決まり、コンパイル時の静的検査がほとんどない。TypeScriptの静的型付けの対義。
- 弱い型付け
- 型の厳密さが低く、型変換が多く起こりやすい。TypeScriptの厳格な型チェックと対照的。
- 未型付け言語
- 型の概念をほとんど持たない、型チェックを行わない言語。TypeScriptの型機能の反対イメージ。
- 型なし言語
- 型を持たない言語の総称。TypeScriptの型付け機能を使わない世界観。
typescriptの共起語
- typescriptとは
- JavaScriptに静的型付けを加えた、型安全と最新機能を提供するオープンソースの言語。
- typescriptの使い方
- 型注釈を付けたソースを TypeScript コンパイラ(tsc)で JavaScript に変換します。設定は tsconfig.json で行います。
- typescript 入門
- 初心者向けの基本概念と設定方法を解説する入門記事・資料の総称。
- typescriptの特徴
- 静的型付け、型推論、最新のJavaScript機能のサポート、エディタ補完の向上など。
- typescriptの型システム
- 型宣言・検査・推論・ジェネリクス・ユニオン型・インターセクション型などを含む総称。
- typescript ジェネリクス
- 汎用的な型を扱う仕組みで、再利用性と型安全性を両立。
- typescript インターフェース
- オブジェクトの形状を宣言する設計図で、クラスの実装との契約を定義します。
- typescript クラス
- オブジェクト指向の基本要素。継承・実装・アクセス修飾子をサポート。
- typescript ユニオン型
- 複数の型のいずれかを許容する型。
- typescript リテラル型
- 特定の値のみを許容する型(文字列・数値リテラル)。
- typescript 型推論
- 明示的な型指定を省略しても、コンパイラが自動で型を推定します。
- typescript 型定義ファイル
- .d.ts ファイルで外部ライブラリの型情報を提供します。
- typescript d.ts
- 型定義ファイルの拡張子および関連概念の略語。
- tsconfig.json
- TypeScriptのコンパイル設定を行う設定ファイル。
- tsc
- TypeScript コンパイラ。ts ファイルを JavaScript に変換する実行コマンド。
- 型チェック
- コード内の型の整合性を検査してエラーを検出します。
- 静的型付け
- 変数の型を コンパイル時に厳密にチェックする仕組み。
- 型安全
- 型の不一致によるエラーを防ぐ性質。
- 型注釈
- 変数・引数・戻り値の型を明示的に記述する構文。
- 型定義ファイル
- 外部ライブラリの型情報を提供するファイル。複数の場所で参照されます。
- any型
- 型チェックを無効化して任意の値を許容する型。
- unknown型
- 不明な型を表し、型ガードを通して安全に取り扱うべき型。
- never型
- 値を返さない関数など、到達不能な型。
- JavaScriptとの互換性
- TypeScriptは JavaScript のスーパーセットで、既存の JavaScript コードと併用できます。
- ReactとTypeScript
- React の開発で型を活用する組み合わせ。Propsの型などを厳密化。
- Node.jsとTypeScript
- サーバーサイド開発で TypeScript を用いるケース。
- Next.jsとTypeScript
- Next.js などのフレームワークで TypeScript を使う場合の設定と実装。
- Visual Studio Code
- TypeScriptの静的検査・補完を強力にサポートする人気エディタ。
typescriptの関連用語
- TypeScript
- JavaScriptを拡張して静的型を使えるようにした言語。型チェックとエディタ支援を強化します。
- JavaScript
- TypeScriptの基盤となる言語。動的型付けで柔軟性が高いが、型エラーは実行時には分かりにくいことがあります。
- 静的型付け
- コードを記述する時点で型を決める仕組み。型エラーを事前に見つけやすくします。
- 動的型付け
- 実行時に型が決まる性質。TypeScriptは静的型付けを追加しています。
- 型
- 値の性質を表す概念。数値、文字列、真偽値など。
- インターフェース
- オブジェクトの形を決める設計図。プロパティ名と型を定義します。
- 型エイリアス
- 型に別名をつける機能。複雑な型を短く表現できます。
- ジェネリクス
- 型を引数として扱い、再利用性の高いコードを作る機能。
- ユニオン型
- 複数の型を許す表現。例: number | string。
- 交差型
- 複数の型を組み合わせて新しい型を作る。例: A & B。
- リテラル型
- 特定の値だけを許す型。例: 'hello' や 42 のような値。
- タプル
- 固定長の配列で、各要素の型が異なる場合に使う。
- 型推論
- 式から型を自動で推測する機能。
- any
- 型を自由に使えるが安全性が低い。必要最低限で使用。
- unknown
- 任意の値を表すが、使う前に型を絞る必要がある安全な型。
- never
- 到達不能な値の型。例外を投げる関数の戻り値など。
- void
- 値を返さないことを示す型。関数の戻り値で使う。
- null
- 値が空であることを示す値。
- undefined
- 未定義の値を示す。
- 識別可能なユニオン型
- 共通の識別子で分岐できるユニオン型。識別子を使って型を絞り込む。
- keyof
- オブジェクト型の全プロパティ名を表す型演算子。
- typeof
- 値の型そのものを表す型演算子。
- 型アサーション
- 値を別の型として扱うための指示。as 句で書く。
- satisfies
- 値が特定の型を満たしているかを型レベルで保証する演算子。
- 宣言ファイル
- 外部ライブラリの型情報を提供するファイル。
- 宣言のマージ
- 同名の宣言を一つに結合する仕組み。
- tsconfig.json
- TypeScriptの動作を細かく設定する設定ファイル。
- tsc
- TypeScript コンパイラ。型チェックと JavaScript への変換を行う。
- トランスパイル
- TypeScriptをJavaScriptへ変換する作業。
- モジュール
- import/export を使ってコードを分割管理する仕組み。
- 名前空間
- 古い形のコードのグルーピング。現在はモジュールが主流。
- JSX/TSX
- TypeScriptとJSXを組み合わせた書き方。React などで使う。
- 標準ライブラリ
- 組み込みの型定義や関数の集合。lib.d.ts など。
- strict
- 厳密な型チェックを一括して有効にする設定群。
- strictNullChecks
- nullとundefinedを別の値として厳密に扱う設定。
- noImplicitAny
- 暗黙の any をエラーにする設定。
- esModuleInterop
- CommonJS と ES モジュールの互換性を向上させる設定。
- module
- 出力されるモジュール形式の設定。例: commonjs や esnext。
- target
- 生成する JavaScript の言語レベルを設定。
- lib
- 利用する標準ライブラリの定義を選ぶ設定。
- incremental
- 増分ビルドを有効にしビルドを速くする設定。
- emitDeclarationOnly
- 宣言ファイルのみを出力する設定。
- sourceMap
- ソースマップを出力しデバッグを助ける設定。
- downlevelIteration
- 低レベル環境での高度なループを有効化。
- types
- グローバル型定義の検索場所を指定する設定。
- @typesパッケージ
- 外部ライブラリの型定義を提供するパッケージ群。
- DefinitelyTyped
- 多くの型定義が集まるリポジトリ名。
- デコレーター
- クラスやメソッドに付与する注釈機能。実験的機能。
- Babel+TypeScript
- Babel で TypeScript をトランスパイルして実行する組み合わせ。
- ts-node
- 実行時に TypeScript を直接実行するツール。
- React+TypeScript
- React を TypeScript で型付き開発する際の組み合わせ。
- Promise
- 非同期処理の結果を表すオブジェクト。
- ReturnType
- 関数の戻り値の型を取得するユーティリティ型。
- Partial
- 全プロパティを任意にするユーティリティ型。
- Pick
- 型から一部のプロパティだけを抽出するユーティリティ型。
- Omit
- 指定したプロパティを除外した型を作るユーティリティ型。
- Readonly
- プロパティを読み取り専用にするユーティリティ型。
- Required
- 全プロパティを必須にするユーティリティ型。
- Exclude
- 型から特定の型を除外するユーティリティ型。
- Extract
- 型の共通部分を抽出するユーティリティ型。
- NonNullable
- null と undefined を除外するユーティリティ型。
- Parameters
- 関数の引数の型を取得するユーティリティ型。
- InstanceType
- クラスのインスタンス型を取得するユーティリティ型。
- Awaited
- Promise の解決後の型を得るユーティリティ型。
typescriptのおすすめ参考サイト
- TypeScriptの特徴とは?JavaScriptとの違いを交えて解説 - 発注ナビ
- TypeScriptの特徴とは?JavaScriptとの違いを交えて解説 - 発注ナビ
- TypeScript/タイプスクリプトとは?特徴やメリット・デメリット
- TypeScriptとは?JavaScriptとの違いや導入のメリット・課題を解説
- TypeScriptとは?どのような言語で何ができるのかをわかりやすく解説
- TypeScriptとは(基本や魅力を包括的に解説) - Kinsta
- TypeScript の基本概念と特徴|Next.js 実践入門 - Zenn
- TypeScriptとは?JavaScriptとの違いなどを解説
- TypeScriptとは?特徴やJavaScriptとの違い、将来性まで解説



















