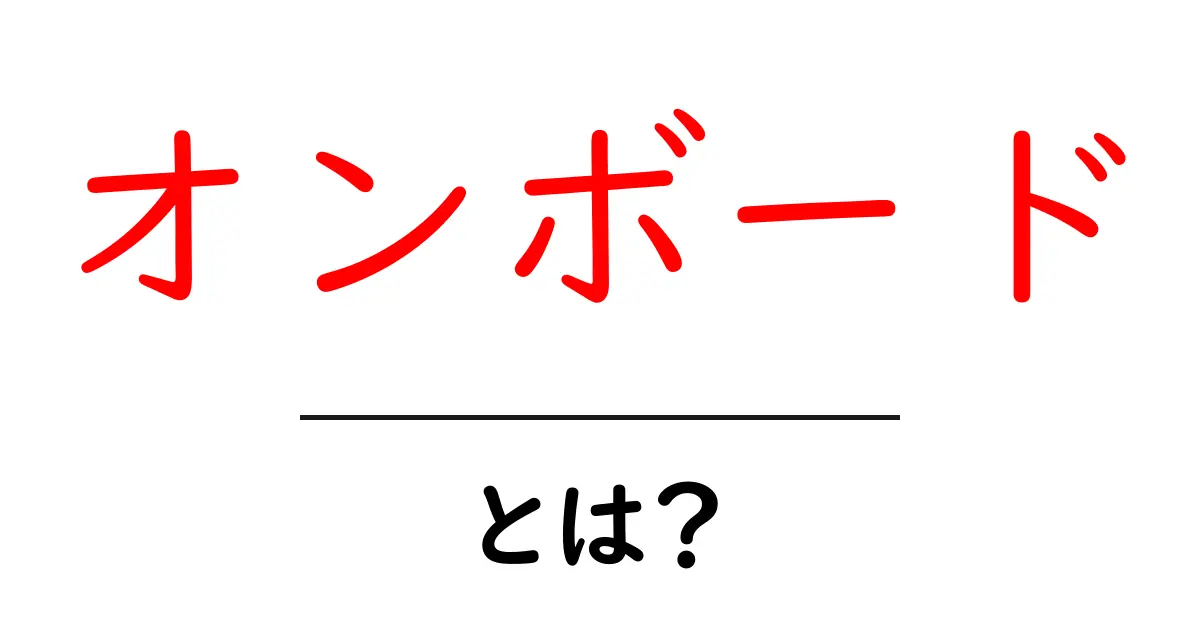

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
オンボード・とは?
オンボードは英語の on-board に由来し、日本語で「機器の内部に搭載されていること」や「内部に組み込まれている部品・機能」を指します。日常の会話ではあまり耳にしない言葉に聞こえるかもしれませんが、ITや電子機器、車載システムなどの分野ではとてもよく使われる用語です。オンボードという語は「外部に接続されているのではなく、内部にある」という性質を強調します。
本記事では、オンボード・とは?という問いに対して、初心者にも分かりやすく、具体例とともに解説します。まずは基本的な意味から、日常生活での代表的な使い方、よく混同される言葉との違い、そして実際の現場での活用ポイントまでを丁寧に見ていきます。
主な意味と使い方
1) 機器の内部に組み込まれていることを表す技術用語。例えば、オンボードCPU、オンボードメモリ、オンボードカメラ、オンボードストレージなどといった言い方が一般的です。これらは機器の内部に搭載されており、外部の部品を追加する必要がない状態を指します。
実際の例としては、スマートフォンの内部に搭載されているチップやカメラ、車のダッシュボードに組み込まれたセンサー類、ゲーム機の内蔵グラフィック機能などが挙げられます。オンボードの部品は通常、安定性や省スペース性、低消費電力などの理由で選ばれることが多いです。
オンボードとオフボードの違い
対義語として「オフボード」があります。オフボードは外部に接続・追加される部品や機能を指すことが多く、例えば外付けのグラフィックカードや外付けストレージなどが該当します。オンボードは内部組み込み、オフボードは外部接続というざっくりとした区別が基本です。
オンボードとオンボーディングの混同を避ける
音は似ていますが意味は全く別です。ビジネスの場面で使われる「オンボーディング」は新入社員の受け入れから教育、定着までの一連のプロセスを指します。ITや機器の話題で出てくる「オンボード」はあくまで機器内部の搭載部分を指す用語です。
使い方のコツ
日常の技術系記事では、名詞や形容詞として使います。例としては次のような文が自然です。「このボードにはオンボードのWi‑Fiモジュールが搭載されている」。文章の中で混乱を避けるためには、「搭載済み」「内部に組み込まれている」という言い換えも有効です。
業界別の実用例
組み込み機器分野では、オンボードCPU・オンボードメモリといった用語が常用され、部品個別の性能や省電力設計が議論の中心になります。車載システムでは、オンボードセンサーやオンボードECUといった表現が使われ、車の内部で完結する処理を意味します。スマート家電では、オンボードチップが中心となり、外部デバイスに頼らず動作を完結させる設計が重要です。
よくある誤解と対処法
よくある誤解は「オンボード=低コスト」や「オンボード=古い技術」というイメージです。実際には、搭載する部品の性能次第で高機能にもなるし、スペースや電力制約の中で最適化を図るために意図的にオンボードを選ぶケースも多いです。適切な用語を使い分けることが、読者に伝える力を高めます。
表で見る用語一覧
まとめ
オンボードとは、機器内部に組み込まれていることを指す技術用語です。IT・電子機器・車載システムなど多くの分野で使われ、外部部品との違いを理解することで、機器の設計や選択を正しく行えます。混同を避けるためにも、「搭載済み」「内部に組み込まれている」という表現を意識して使い分けましょう。
オンボードの関連サジェスト解説
- オンボード とは pc
- この記事ではキーワード「オンボード とは pc」を、初心者にも分かりやすく解説します。オンボードとは、パソコンの部品のうち、マザーボードやCPUに内蔵されている機能のことを指します。代表的な例は、オンボードグラフィックス(統合グラフィックス)、オンボードサウンド、オンボードLANなどです。これらは別売りの拡張カードを購入せずとも、パソコンを動かすための基本的な機能を提供します。利点は、安価で導入しやすい点、スペースを取らない点、組み立ても簡単な点です。一方で欠点は、性能の限界とアップグレードの自由度の低さです。特にオンボードグラフィックスは、専用のグラフィックスカード(ディスクリートGPU)には劣り、最新の3Dゲームや高度な映像処理には不向きです。日常の作業や動画視聴、軽い写真編集なら十分ですが、ゲームやCG作業を本格的にやるならディスクリートGPUを検討しましょう。見分け方と使い分け方はこうです。自分のPCにどんな映像出力があるかをチェックします。マザーボードの背面にHDMIやDisplayPortが直接ある場合、それはオンボードの出力の一つです。またCPUが統合GPUを持っている場合も多く、CPUの仕様書でグラフィックス機能があるか確認します。BIOSやUEFIの設定で「初期ディスプレイアダプター」や「iGPU」を優先にする設定があります。ディスプレイを外部の拡張カードへ切り替えたいときは、ディスプレイをディスクリートGPUの出力に接続し、必要に応じてBIOSでオンボードを無効化します。結論として、オンボードはコスト削減と手軽さを重視する初心者には最適な選択肢です。ただし、将来的に高い性能が必要になった場合は、ディスクリートGPUを追加する計画を立てておくと良いです。
- オンボード とは ビジネス
- オンボード とは ビジネス という言葉は、会社に新しく入る人を迎え入れる準備や、初めて商品やサービスを使い始めるお客様を案内する一連の手続きのことを指します。英語ではオンボーディング(onboarding)と言い、日本語には「新入社員の導入」「顧客の導入支援」などの意味が含まれます。ビジネスで重要なのは、相手が不安を感じずにスムーズに活動を始められる状態を作ることです。まず新入社員のオンボードについてです。入社前の情報共有、初日や初週のオリエンテーション、社内ルールの説明、IT機器の設定、業務マニュアルの提供、先輚社員によるメンターやバディ制度を用意します。これらの工程がしっかりしていると、新人は早く業務の流れを掴み、質問を減らせます。次に顧客向けのオンボードについてです。新しいお客様が product を使いこなせるよう、導入ガイド、アカウント作成、初期設定、使い方動画、FAQ、定期的なフォローアップなどを準備します。顧客が最初の成功を体験できると、解約率が下がり、長期的な信頼につながります。オンボードを成功させるコツは3つです。1つ目は事前準備を徹底すること。必要な資料、設定項目、担当者の割り当てを事前に決めておくと混乱が少なくなります。2つ目は小さな成功体験を積ませること。小さな達成感がモチベーションを高め、継続を後押しします。3つ目は定期的なフィードバックを行うこと。相手の理解度を確認し、改善点を具体的に伝えると効果が上がります。
- メモリ オンボード とは
- メモリ オンボード とは、電子機器の基板上に搭載されたメモリのことを指します。ここでのメモリとは、データを一時的に保存して処理を速くするRAMのことが多いです。オンボードは“その基板にくっついている(取り外せない)”という意味があり、半田づけされたり、SoC(システム・オン・チップ)に組み込まれていたりします。対して、後から追加できるRAMは一般的に“拡張メモリ”やDIMMと呼ばれ、パソコンのようにスロットに挿して増設します。スマホや一部の組み込み機器では、RAMが基板上に直接載っていますので、いわゆるオンボードメモリです。これにより小型化・低コスト・低消費電力が実現します。ただし、容量を後から増やすことは難しく、壊れた場合の交換も困難です。CPUのキャッシュ(L1/L2/L3)やマイクロコントローラ内蔵メモリは、技術的には“オンボード”の性質を強く持っていますが、用途によって呼び方が微妙に変わることがあります。つまり、オンボードとは基板上に固定された記憶装置のこと。外部のメモリカードやRAMを追加で挿すタイプとは区別されます。用途を決めるときは、将来の容量拡張の必要性、価格、サイズ・省スペースを考え、オンボードかどうかを判断することが大切です。
- グラフィック オンボード とは
- グラフィック オンボード とは、CPU やマザーボードに内蔵されたグラフィックス機能のことです。専用のグラフィックスカードを別途用意しなくても、画像の表示や動画の再生が行えます。一般には iGPU(インテグレーテッド・グラフィックス・プロセッシング・ユニット)と呼ばれ、CPU と同じチップセット内に組み込まれていることが多いです。オンボードの特徴は「メモリを共有する」点です。つまりパソコンの RAM の一部をグラフィックス用に使うため、システム全体の使用可能メモリが少し減ります。性能はCPUとセットで決まり、最新の世代のグラフィックスは日常用途には十分ですが、高いグラフィック性能を必要とする最新ゲームや3D編集には向いていません。動画視聴、ネットサーフィン、オフィス作業、軽いゲーム程度なら快適なことが多いです。用途に応じて、将来的により強いグラフィックスを求めるなら、ディスクリートGPU(別売りのグラフィックカード)を追加する選択肢があります。どうやって自分のPCがオンボードかを確認するには、Windows のデバイスマネージャーを使う方法が一般的です。「ディスプレイアダプター」を開くと、Intel や AMD の統合グラフィックス名が表示されます。ノートパソコン(関連記事:ノートパソコンの激安セール情報まとめ)の場合は、メーカーの仕様書やCPU名を調べてもわかります。ドライバーを更新する場合は、CPUメーカーの公式サイト(例:Intel、AMD)、または PC メーカーのサポートページから適切なものを選びます。オンボードの利点はコストが安い、発熱が抑えられる、静音性が高い、電源の消費を抑えやすい点です。一方の欠点は、ゲームのような高度なグラフィック処理には不向きで、VR や4K 動画編集などでは力不足になることです。自分の用途を考え、将来的に快適さを優先するならディスクリートGPU への買い替えを検討しましょう。
- mde オンボード とは
- mde オンボード とは、文脈によって意味が変わる用語ですが、初心者には基本の考え方を知ることが大切です。ここでは、よく使われる意味の一つである「Model-Driven Engineering(モデル駆動開発)」と「オンボード(機器の本体に組み込み、内部で動くこと)」の組み合わせについて解説します。オンボードとは、機器自体に処理能力や機能が内蔵されている状態を指し、外部のサーバーや別の機器に依存せずに動作する利点があります。Model-Driven Engineering は、設計の段階でモデルを作り、それを元にコードや動作を自動生成する方法です。これをオンボード環境で使うと、設計モデルから直接ファームウェアや組み込みソフトを生成し、端末内部で実行できます。実際の使われ方として、埋め込み型システムや IoT デバイス、ロボット分野で見かけることが多いです。オンボードで処理を行うと、ネットワークに頼る場面が減り、処理の速度が安定し、通信量や遅延を抑えることができます。またデータを外部へ送らない選択肢になることがあり、セキュリティの観点でメリットになることもあります。初心者向けのポイントとしては、文書ごとに MDE の意味が微妙に異なることがある点を理解し、公式ドキュメントの定義を必ず確認することです。モデルとコードの関係を理解するには、簡単な図を描くと効果的です。例えば、設計モデルを中心に置き、それを自動生成したファームウェアが機器内部で動く、という流れを思い描くと理解が深まります。初心者向けの例として、スマート家電の設定をモデルで設計してから、それを機器のファームウェアへ変換して内部で動かすような流れを想像すると分かりやすいです。実際の現場では、製品の公式資料や開発ガイドを参照し、どの意味で使われているかを確かめることが重要です。要点をまとめると、mde オンボード とはは文脈次第で意味が変わりますが、機器の本体に設計と自動化機能を組み込んで動かすという考え方を指すことが多いです。初心者はまずオンボードの意味とモデル駆動開発の基本を押さえ、公式資料で具体的な使い方を確認するのが良いでしょう。
- lan オンボード とは
- lan オンボード とは、パソコンのLAN機能がマザーボードに直接組み込まれている状態のことです。通常、コンピューターにはネットワーク接続用のカード(NIC)が必要ですが、オンボードLANの場合はその機能がマザーボード上のチップセットやコントローラーに内蔵されています。背面パネルにはRJ-45と呼ばれるLANポートがあり、ここに有線LANケーブルを差し込むだけでネット接続が始まります。オーディオやグラフィックのように、別売の拡張カードを買わなくても使えるのが特徴です。オンボードLANの良い点は、追加の部品がいらないためコストが抑えられ、消費電力も安定しています。取り付けも簡単で、マザーボードと一体化しているので壊れにくい場合が多いです。一方で注意点もあります。場合によっては、メーカーのBIOS設定で「Onboard LAN」を無効にしている場合があり、ドライバーの更新がうまないこともあります。性能面では、最新の拡張カードやWi-Fiと比べてアップグレードの余地が少なく、接続先を変更したい場合には別のカードを追加する必要が出てくることもあります。家庭用の有線接続なら、オンボードLANで十分なケースが多いですが、ゲーム用の安定性や高い帯域を求める場合はGigabit(1Gbps)やそれ以上に対応したLANカードを検討してもよいでしょう。実際の使い方は簡単で、イーサネットケーブルをRJ-45ポートに挿し、OS側でネットワーク設定を確認するだけです。速度は契約している回線と機器の性能次第ですが、ほとんどの場合は100Mbps以上、最新機器なら1Gbps近い速度が出ます。
- defender オンボード とは
- defender オンボード とは、Windows に標準で搭載されているセキュリティ機能のことです。正式には Microsoft Defender Antivirus などと呼ばれ、パソコンに最初から入っているオンボードの防御ツールです。現在の Windows ではウイルス対策ソフトを別に入れなくても、悪意のあるプログラムからあなたのPCを守る仕組みが用意されています。主な仕事はファイルを調べて悪いソフトを見つけ出すこと、怪しい振る舞いを監視して未然に防ぐこと、そして必要に応じて安全なファイルに分類することです。定期的な定義ファイルの更新、クラウドベースの保護、ファイアウォールとの連携など、複数の機能が組み合わさっています。使い方はとてもシンプルで、設定アプリの Windows セキュリティからウイルスと脅威の保護を開き、リアルタイム保護をオンにするだけです。検査の方法もクイックスキャン、フルスキャン、カスタムスキャンなどから選べ、更新は自動で行われます。とはいえ万能ではありません。家庭での基本的な保護には十分ですが、特別なセキュリティ機能を求める場合は追加のソフトを検討するのがよいでしょう。さらに他のセキュリティソフトを同時に使う場合には相性や設定の衝突に注意してください。
- gpu オンボード とは
- gpu オンボード とは、パソコンのグラフィックス機能が別のグラフィックスカードを追加することなく、CPUやマザーボードに内蔵されている場合を指します。英語では integrated graphics、略して iGPU と呼ばれます。オンボードGPUはCPUと同じチップやチップセットに組み込まれているケースが多く、画面表示の処理を担当します。日常の作業、動画視聴、Webブラウジング、文書作成などは通常これだけで十分です。専用のグラフィックスカードをつけるディスクリートGPUに比べ、処理能力は劣ることが多いですが、コストが安く、電力も少なく、冷却が楽という利点があります。オンボードGPUの仕組みは、グラフィック用の専用VRAMを必ずしも持たず、システムメモリ(RAM)を共有して使うことが多い点です。つまりRAMをグラフィックス用途と共有するため、他の作業と同時に使うとメモリ使用量が増え、性能が影響を受けやすくなります。この特性は予算が限られている人や省電力志向の人にはメリットですが、ゲームや3Dソフト、動画編集のような重い作業には厳しくなります。用途をはっきり決めて選ぶとよいでしょう。もし本格的なゲームや高度な映像編集をしたい場合は、ディスクリートGPUを後から追加するか、最初から高性能な機種を選んでください。実際の確認方法としては、WindowsのデバイスマネージャーやDxDiag、またはGPUベンチマークを使って現在の能力をチェックします。ノートパソコンでは省電力モードと高性能モードの切り替え機能があり、使い方によって動作が変わります。BIOS/UEFIの設定で表示優先を変更することも可能です。初めての人は、画面が正しく表示されるか、解像度が適切か、動画再生時の滑らかさを確認してください。要するに、gpu オンボード とは、コストと省電力を重視する人に向く、CPUに組み込まれたグラフィックス機能のことを指す用語です。
- サウンド オンボード とは
- サウンド オンボード とは、パソコンのマザーボードに内蔵された音声機能のことです。オンボードサウンドとも呼ばれ、別途サウンドカードを挿さなくても音を出すことができます。仕組みは、マザーボード上の音声チップがデジタルデータをアナログ信号に変換する DAC(デジタル-アナログ変換)と、マイク入力をデジタルデータに変換する ADC(アナログ-デジタル変換)を使い、スピーカーやヘッドホンに音を送ります。一般的な出力はステレオや5.1chの端子、最近の機器では HDMI や光デジタル出力にも対応しています。オンボードサウンドの長所はコストが低いこと、別の機器を追加する必要がないこと、ケーススペースをとらないこと、そして日常用途には十分な音質を提供する点です。反対に短所としては、音質の余地が狭い場合があること、低価格帯の製品ではノイズやS/N 比が劣ること、音楽制作や高音質のリスニング、ゲームでの低遅延を強く求める場合には外部のサウンドカードやUSB DACのほうが適していることです。選び方としては、マザーボードの仕様書にオンボードサウンドの有無と出力端子を確認し、用途に応じて DAC の品質やサンプリング周波数のサポート、信号処理の機能を比べてください。実際の使い分けとしては、日常的な動画視聴や通話、ライトなゲーム、普段使いならオンボードで十分の場合が多いです。音質にこだわる人は USB DAC や外付けのサウンドカードを検討するとよいでしょう。
オンボードの同意語
- 内蔵
- 機器の内部に機能や部品が組み込まれており、外部から追加しなくても使える状態を指す。
- 内蔵済み
- すでに機器内部に搭載されている状態。
- 搭載
- 機能や部品を機器に追加して動作させている状態。例: CPUを搭載する。
- 搭載済み
- 機器に部品や機能がすでに搭載されている状態。
- 内蔵型
- 内蔵として設計・搭載された形態のこと。
- 組み込み
- 部品や機能を機器の内部に組み込むこと。
- 組み込み済み
- 部品や機能がすでに機器内部に組み込まれている状態。
- 基板上
- プリント基板(PCB)の上に部品が実装されている状態。
- 基板搭載
- 基板に部品や機能を搭載している状態。
- 基板上の
- 基板の上に配置・実装されていることを表す表現。
- オンボーディング
- 新規の従業員や顧客を組織へ迎え入れる一連の導入プロセスを指す。
- 導入研修
- 新規メンバーを組織にスムーズに統合するための初期教育・手続き。
- 新入社員研修
- 新しく入社した社員を対象に行う教育・習熟を目的とした研修。
- 入社オリエンテーション
- 入社時に行う会社案内や制度説明などの初期オリエンテーション。
- 新人教育
- 新規メンバーの基礎的な教育・習熟を指す。
- 受け入れ手続き
- 新しい人材を組織へ迎える際の各種手続きの総称。
- 受け入れプロセス
- 新規メンバーを組織へ統合する一連の手順や流れ。
オンボードの対義語・反対語
- オフボード
- オンボードの反対語。基板上に搭載されていない、外部の別基板や外部機器に接続されている状態を指す。例:オフボードRAM、オフボードGPU、オフボードセンサーなど。
- アウトボード
- 音響・映像機器などで使われる外部機器を指す語。ボード外の機器という意味で、オンボードの対義語として使われる。例:アウトボードエフェクター、アウトボードサウンドカードなど。
- 外付け
- 外部に接続・取り付けられている状態。機器が内部に搭載されず、外部にあることを示す。例:外付けハードディスク、外付けウェブカメラ。
- 外部搭載
- 本体以外の外部システムを搭載している状態。文脈によってオンボードの対義語として使われる。例:外部搭載センサー。
- 未搭載
- オンボードとして搭載されていない状態。反対語として使われることがあるが、ニュアンスは未搭載=搭載なし。
- オフボーディング
- 人事用語で従業員の退職・離職プロセスを指す。オンボーディング(入社手続き・オンボード)に対する反対語として用いられる。
オンボードの共起語
- オリエンテーション
- 新しいメンバーを組織に慣れさせるための案内・説明の場。仕事内容・ルール・組織文化を伝え、業務開始をスムーズにする一連の初期対応の一部。
- オンボーディング
- 新規採用者が組織に順応し、業務を実際に遂行できる状態になるまでの手続き・教育・支援全般。採用後の定着を目的とする。
- 初期設定
- デバイスやソフトウェアを使える状態にする最初の設定作業。アカウント作成・権限付与・環境整備を含む。
- セットアップ
- システム・端末の基本構成を整え、利用開始に備える作業。
- アカウント作成
- 新規ユーザーのアカウントを作成して権限を割り当てる手続き。
- プロビジョニング
- デバイスやアプリ、アカウントを事前に準備して利用開始できる状態にする作業。
- デプロイ
- 新しいソフトウェアやデバイスを組織内へ配布・導入するプロセス。
- 導入
- 新規システム・機器・ソフトウェアを組織に取り入れること。
- オンボード機能
- 機器に内蔵された機能。外部部品を使わず、内蔵で提供される機能の総称。
- オンボードストレージ
- デバイス内部に搭載された記憶領域。外部ストレージではなく内蔵の記憶領域。
- オンボードCPU
- 機器内部に組み込まれたCPU。外部の別筐体のCPUではなく、内蔵型を指す。
- ネットワーク設定
- 社内ネットワーク接続・VPN・Wi-Fiなど、通信環境を整える設定。
- セキュリティ設定
- アクセス権限・認証、ポリシーの適用など、セキュリティ関連の設定作業。
- 教育
- 業務遂行に必要な知識・技能を身につける学習活動。
- 研修
- 新規メンバーや既存社員の能力向上を目的とした体系的な学習プログラム。
- 新入社員
- 新しく組織に入る社員。オンボーディングの対象となる人材。
- 入社手続き
- 雇用契約関連の手続き。オリエンテーションや研修とセットで案内されることが多い。
- 定着支援
- 新規メンバーが長期的に組織へ馴染み、働き続けられるようにする支援活動。
オンボードの関連用語
- オンボード
- デバイス内部に搭載・内蔵されていること。外付けではなく基板・チップ上に組み込まれている状態を指します。例としてはオンボードLANやオンボードグラフィックスなどがあります。
- 内蔵
- 機器の本体内部に組み込まれている部品・機能のこと。オンボードと意味が近く、同義として使われる場面が多いです。
- 組み込み
- Embeddedの日本語。外部に依存せず機器内部に機能を組み込む設計や、組み込み系の製品・技術を指します。
- オンボーディング
- 新規ユーザー・新規従業員・新規顧客をシステムへ迎え入れる導入プロセスのこと。初期設定・教育・権限付与を含みます。
- ユーザーオンボーディング
- ウェブサービスやアプリの新規ユーザーを効果的に導く一連の体験設計・手続きのこと。
- オンボードグラフィックス
- CPUやマザーボードに内蔵された統合型GPU。外部のグラフィックカードを使わず映像処理を行います。
- オンボードLAN
- マザーボードや本体にあらかじめ搭載された有線LANポートのこと。別途NICを追加する必要がありません。
- オンボードWi-Fi
- 機器本体に内蔵された無線LAN機能。ノートPCなどで無線接続を可能にします。
- オンボードストレージ
- 本体や基板内部に搭載されたストレージ(例:eMMC/SSD)。外付けではなく内部に組み込まれているストレージを指します。
- オンボードセキュリティ
- ハードウェアレベルでのセキュリティ機能。例としてTPMなど、基板上に実装された防御機能を指します。
- オンボードIC
- 基板上に直接搭載された集積回路(IC)のこと。小型機器の内部構成を表します。
- オンボード回路
- 基板上に実装された信号処理用の回路全般のこと。
- オンボードセンサー
- 機器内部に組み込まれた温度・加速度・ジャイロなどのセンサーのこと。外部追加なしでデータを取得できます。
- オンボード管理
- ハードウェアの監視・管理機能を指します。ファームウェアや周辺機器の状態を基板上で管理します。
- HRオンボーディング
- 企業における新規従業員の受け入れ・入社手続き・教育・権限付与などを包含する人事プロセスのこと。
- 外付け
- 本体外部に追加して取り付ける方式。オンボードの逆で、柔軟性は高いが追加部品が必要になります。
- SoC(System on Chip)
- CPU・GPU・メモリ・周辺機能を1つのチップに集約した設計。省スペース・省電力で、オンボード機器にも多く使われます。
- オンボードカメラ
- デバイス本体に内蔵されたカメラ機能。ノートPCやスマートデバイスに標準搭載されるカメラのこと。
- オンボードオーディオ
- 本体に内蔵された音声入出力機能。スピーカーとマイクを統合したオーディオ構成を指します。
オンボードのおすすめ参考サイト
- オンボードとは?意味を分かりやすく解説 - IT用語辞典 e-Words
- オンボーディングとは?目的・導入方法・実施のポイント・事例
- パソコンのグラボ(グラフィックボード)とは?役割などを簡単に解説
- オンボードとは?マザーボードの機能を拡張する技術



















